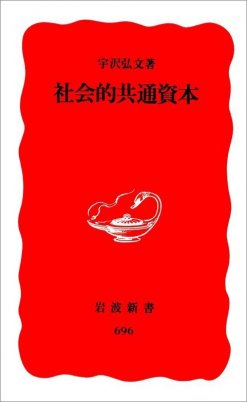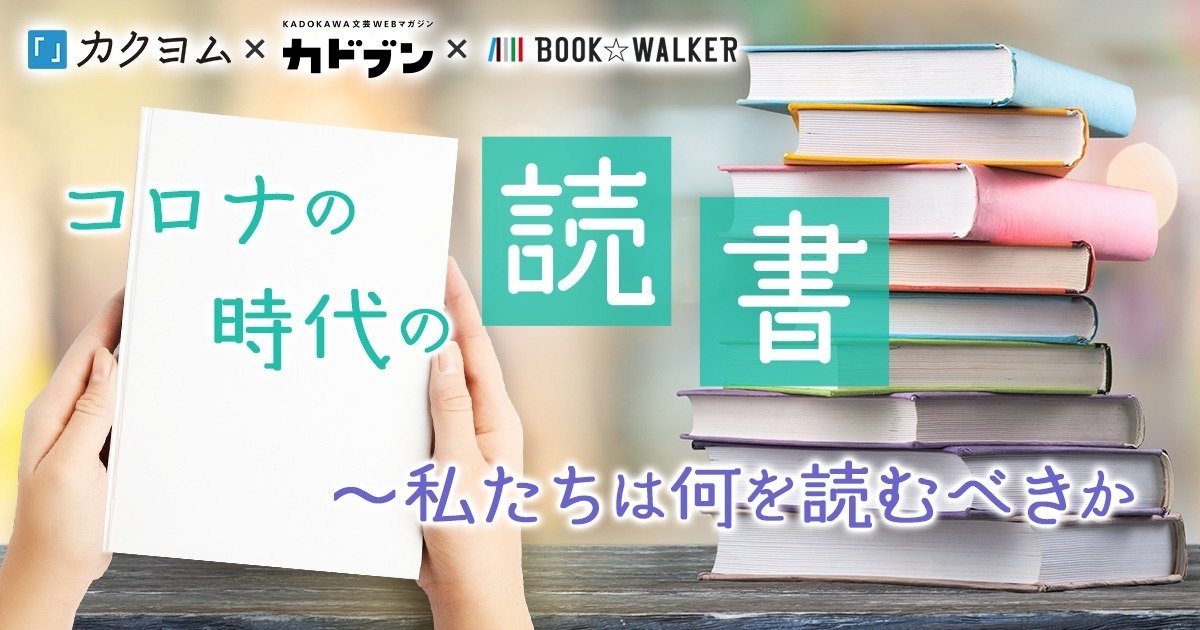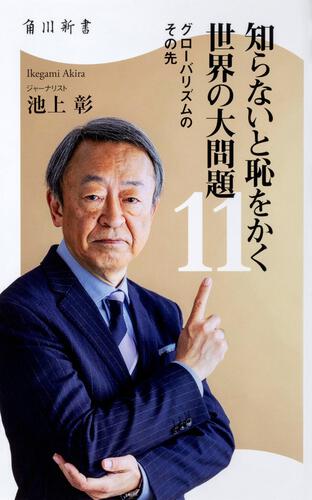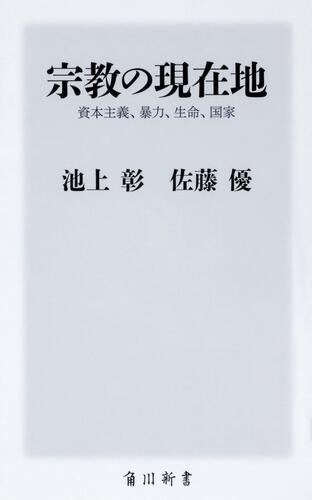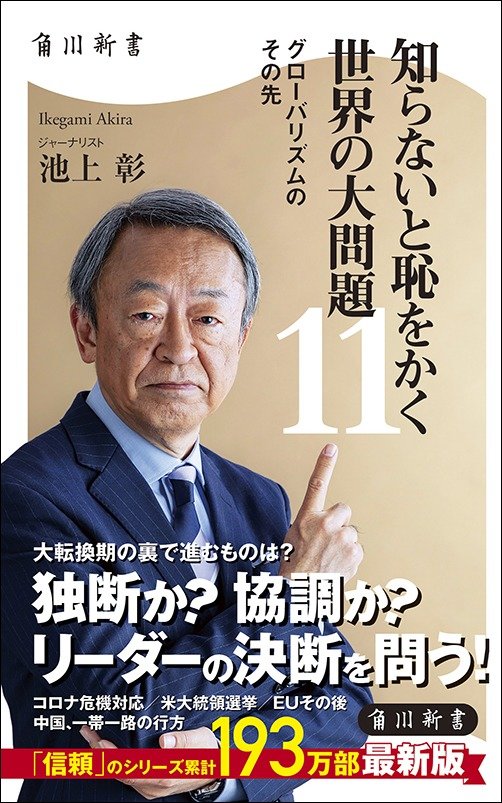新自由主義へのアンチテーゼ――池上彰【コロナの時代の読書】
コロナの時代の読書〜私たちは何を読むべきか
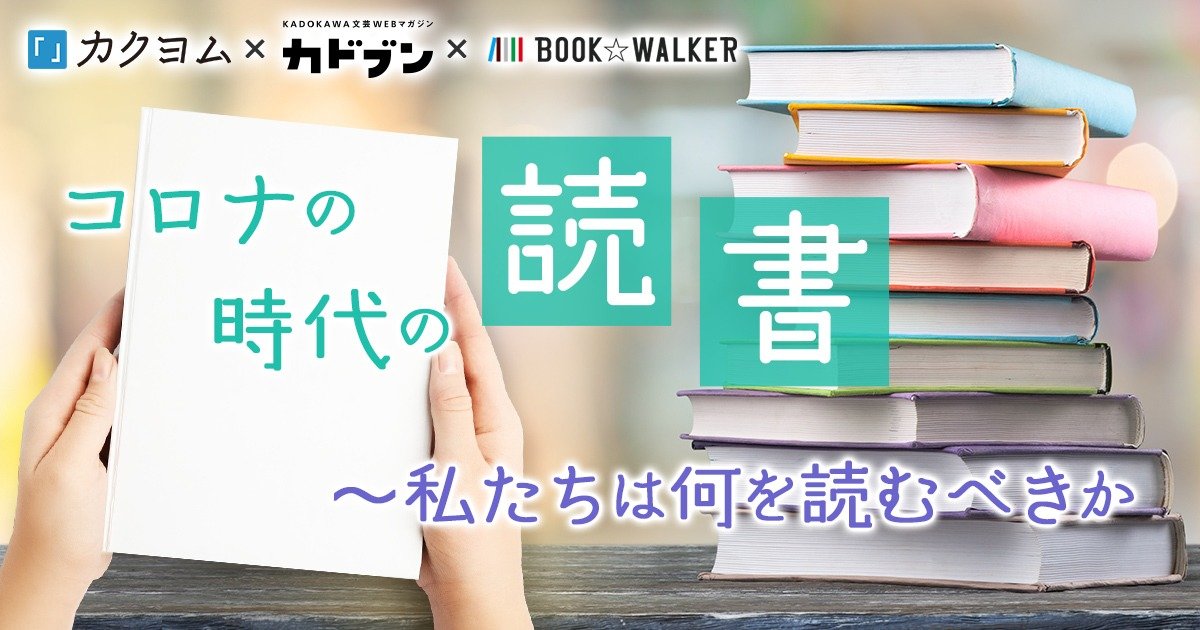
文字と想像力があれば、人はどこにでも行ける。
世界の見え方が変わる一冊、ここにあります。
池上彰さんが選んだ一冊
『社会的共通資本』
宇沢弘文・著/岩波新書
https://bookwalker.jp/de0f2cd9d1-5ad1-4005-9b0c-91bdce8c878a/
新型コロナウイルスの感染者が増加する中、世界で医療崩壊が問題になりました。
財政難から医療機関の効率化を進め、病院の統廃合、病床を削減してきたイタリアは医療崩壊状態となり、多くの死者を出して国民を不安に陥れました。
日本でも現在、公立・公的医療機関の再編統合の検討が進められています。厚生労働省は昨年、経営状態のよくない全国400以上の病院を再編統合の対象としてリストアップしました。
異端の経済学者とも称された故・宇沢弘文氏は、著書『社会的共通資本』のなかで、大気、森林、河川、土壌などの「自然環境」、交通機関、上下水道、電力、ガスなどの「社会的インフラ」、教育、医療、金融などの「制度資本」は社会的共通資本である。とくに教育と医療は人間が人間らしい生活を営むために重要な役割を果たすもので、決して市場的基準によって支配されてはならないと訴えました。
1980年代、ロナルド・レーガン米大統領、マーガレット・サッチャー英首相、そして日本では中曽根康弘首相が、アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンが唱えた「新自由主義」政策を推し進めました(歴史的背景については、拙著『知らないと恥をかく世界の大問題11』に書きました)。フリードマンはすべてを市場に任せよう、極端な言い方をすれば「儲けるためなら何でもあり」と説いたのです。法律や制度が邪魔ならば改革をすればいい――。その結果、今があります。
宇沢氏は、シカゴ大学の同僚だったフリードマンの主張に嫌悪感を覚え、決意を持ってアメリカ生活に別れを告げ、日本に帰国しました。
今こそ、宇沢氏が提起した「社会的共通資本」の考え方が広く知られるべきではないか。宇沢氏の高弟でノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツは「宇沢先生の考え方は、30年後に理解されるようになるだろう」と予言したそうですが、30年を待たずに現在、宇沢経済学が輝きを増しています。
池上彰(ジャーナリスト・名城大学教授)
みなさんもぜひ「コロナの時代に読んで欲しい本」を投稿してください。
ご応募はこちらから→https://kakuyomu.jp/special/entry/readingguide_2020