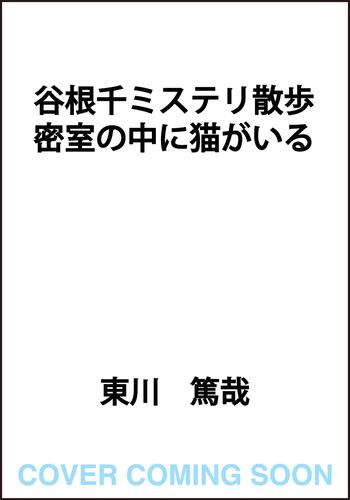谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる

【試し読み】東川篤哉氏が放つ、超人気ユーモア×本格ミステリ最新作!『谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる』冒頭を大ボリューム特別公開!
ゆるすぎる名探偵と、犯人に騙されまくる助手が活躍する本格ミステリシリーズの最新作『谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる』が、7月2日発売になりました。この作品から読んでも楽しめる、下町を歩きながら謎解きする超人気シリーズの冒頭大ボリューム試し読み、ぜひご一読ください。
東川篤哉『谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる』試し読み
第1話 密室の中に猫がいる
1
「ねえ、つみれちゃん、猫もらってくれない?」
「ね、お願い。一匹でいいから、ね?」
――いやいや、一匹ならOKとか、二匹じゃ多いとか、そんなんじゃなくて!
思いがけない提案に戸惑う私は、「えぇー、猫ぉ!?」といって両目をパチパチ。自慢のポニーテールを揺らしながら
私、猫は嫌いじゃないし、ペットを飼いたいという願望も、実は子供のころからずっとある。
けれど、だからといって『わーい、いいの? タダで? だったら、もらうもらう! 猫大好きー、タダ猫サイコー』と
慎重になる私はカウンターの向こう側へと視線を送った。そこに立つのは白い調理服に身を包む兄の姿だ。こちらの視線に気付いた兄は、
『そんなの駄目にきまってんだろ、つみれ』そういうアクションだ。
――やっぱり無理だよねえ。
カウンター席に座る私は、そっと
そう、何を隠そう、ここは清潔感が命の飲食店。場所は下町情緒あふれる街並みが散歩客に人気の
屋号はズバリ『鰯の
私の父、
私とひと回りほど年の離れた兄だが、精神年齢なら私と同じ程度か(もしくは五歳ほど下かも)。そんな兄の名前は、冗談みたいだけれど『なめ
ちなみに、そんな変わり者の父は、娘である私には『つみれ』の名を授けてくれた。『岩篠つみれ』だ。これまた鰯料理っぽいネーミングではあるけれど、まあ、この名前はぎりぎりセーフなんじゃないかしら。少なくとも『お造り』とか『フライ』とか名付けられなくて本当に良かったと、いまの私はそう思っている。
ま、岩篠家と鰯の話は、ともかく――
そんなわけで家業が家業だから、我が家において猫という生き物は常に招かれざる客である。万が一、近所の猫が店内に忍び込んだりしようものなら、なめ郎兄さんは凶暴化したサザエさんのごとき形相でもって、お魚くわえたドラ猫を地の果てまで追い回すに違いない。私は友人の隣で、うなだれるように頭を下げるしかなかった。
「ごめん、雛子ちゃん、うちじゃあ猫は飼えないんだよね」
「そっかー、駄目かー」
と雛子ちゃんは残念そうにいって、皿に載った鰯のつみれ(料理のほう)をパクリ。そしてジョッキのレモンサワーをゴクリ。それから自分以外に客のいない店内を見回すと、ひとり納得した顔で
「いや、余裕があるとかないとかじゃなくてさ」まあ実際、余裕も全然ないんだけどさ。「にしても、急にどうしたの? 雛子ちゃんちで子猫でも産まれたの?」
「ううん、そうじゃないのよ。子猫じゃなくて大人の猫ちゃんなの。実をいうと、死んだおばさんが可愛がっていた猫なんだよねえ」
その発言が飛び出した瞬間、私は思わずハッと息を
――もう、慌てすぎだよ、お兄ちゃん!
居酒屋『吾郎』の店内に微妙な空気が漂う。その沈黙を破って私が口を開いた。
「そういえば、雛子ちゃんの
言葉に迷いながら確認すると、雛子ちゃんは私の目を見詰めて頷いた。
「うん、そう、誰かに殺されたの……だと思う」
前半はキッパリ。だけど後半は自信なげな口調だ。その反応を私は不思議に思った。
「ん、『だと思う』って何? 殺されたかどうか、よく判らないってこと?」
「ううん、たぶん殺されたことは間違いない。だって事故や自殺には見えないから。でも殺されたにしては、現場の状況が変なのよねえ。
「え!? なになに……それって、ひょっとして……」
慎重に言葉を選ぶ私が、どう尋ねていいか迷っていると、まったく言葉を選ばない兄がズバリと人差し指を突き出して叫んだ。
「み、密室だ、密室ッ! そりゃ、まさしく密室殺人だぁーッ!」
あまりの迫力に
「そんなことより、お兄ちゃん、指から血! 血が出てるよッ。――ほら、
おう、気が利くな、つみれ――といいながら、なめ郎兄さんは血まみれの人差し指に絆創膏を巻く。応急処置が済むのを待って、雛子ちゃんがあらためて事件の詳細を語った。
「事件が起きたのは、いまから十日ほど前。現場となったのは、千駄木にあるおばさんの自宅よ。実をいうと事件の夜、私はその家に偶然泊まっていたの……」
2
その夜、森山雛子は父方の祖父の妹にあたる女性、
べつに珍しい話ではない。雛子の家族は昔から春江と深い付き合いで、雛子にとっては実の祖母も同然の関係。しかも春江の住む家は、
その日は所属するゼミの飲み会があり、帰りが遅くなることは事前に判っていた。そこで雛子は前の晩から春江に電話で連絡を取って、この日の夜に彼女の家に泊めてもらう約束を取り付けていたのだ。
阿川春江は今年で七十二歳。かつては一流企業に勤める夫を支える専業主婦だった。その夫は取締役まで登りつめたものの、病気のため数年前に亡くなった。以降、春江は夫の残した団子坂の家で遺産と年金を頼りにしながらのひとり暮らしだ。
悠々自適といえば聞こえはいいが、いわゆる独居老人であることに違いはない。そんな春江の身を案じた雛子が、ときどき様子を見るために自ら孫代わりとなって
千駄木にある阿川邸は和洋折衷の立派な平屋建て。この付近ではひと際目立つ邸宅で、正直、年寄りのひとり暮らしには広すぎる家だ。
いかめしい門をくぐった雛子は、純和風の玄関先へと進み、呼び鈴を鳴らした。すると中から「はーい」と応じたのは、気品を感じさせる女性の声。春江の声に間違いなかった。
間もなくガラリと引き戸が開いて、阿川春江がその姿を現した。
「まあ、よくきたね、雛子ちゃん。ゼミの飲み会は、どうだった?」
「うん、楽しかったよ。だけど、少し飲みすぎたかも。おばあちゃんちに泊めてもらえるって判ってるから、ついつい油断して飲みすぎちゃうんだよねえ」
てへへ、と笑いながら、雛子は玄関の中へと足を踏み入れる。と、そのとき雛子はふと違和感を覚えて、ムッと
「あれ!? おばあちゃん、誰かきてるの!?」
「ああ、そうなんだよ、実は急に
と春江が詳しい説明を加えようとした、そのとき――
「やあ、こりゃ随分と珍しい顔じゃないか」
突然、聞こえてきたのは、どこか聞き覚えのある男性の声。次の瞬間、玄関に姿を現したのは、短い髪を茶色く染めたポロシャツ姿の中年男性だ。
昭和の二枚目俳優を思わせる顔立ち。
雛子はその男性の顔に覚えがあった。
名前は
そんな雅彦は、雛子に向かってニッと白い歯を覗かせると、気安い口調でいった。
「雛子ちゃん、久しぶりだなぁ、見違えたよ。僕のこと、覚えてるかい……?」
「わ、判ったぜ、雛子ちゃん!」居酒屋『吾郎』に唐突に響き渡る叫び声。「その三田雅彦って遊び人が、春江さん殺しの容疑者Aってわけだ。そうだろ、雛子ちゃん!」
カウンターの向こう側にいるなめ郎兄さんが、絆創膏の巻かれた指でもって友人を真っ直ぐ指差す。しかし差された雛子ちゃんは、いったん話を中断して困惑の表情だ。
「え、そんなふうに聞こえちゃいました!?」
べつに、そんなつもりじゃなかったんだけどなぁ、あと『遊び人』だなんて、私ひと言もいっていないんだけどなぁ――と友人は口の中でブツブツ。それから三田雅彦なる人物について、あらためて補足説明を加えた。
「確かに雅彦さんは、快楽主義者で自堕落で『働いたら負け』って本気で思っているような変わり者。春江おばさんから小金をせびり取っては、酒やギャンブルで使っちゃうような困った人で、親戚筋からは自動車の排ガスのように煙たがられています。だけど、まさかそんな……いくらなんでも人殺しとかするようなタイプじゃ……」
「いやいや、雛子ちゃん」私は友人の話を中途で遮って、「その説明だと、もう完全にそういうことやらかすタイプじゃん。完全に容疑者Aだよ。――ね、お兄ちゃん?」
「ああ、『特A』だな。最重要容疑者だぜ」と容赦なく決め付ける兄。
雛子ちゃんは「うーん、そっかー」といって髪の毛を
「ほら、絶対怪しいよ、その人」私は友人の隣で口をへの字にしながら腕組みだ。「で、その雅彦って駄目男は、その夜、春江さんちに泊まったの?」
「うん、泊まった。最初から、そのつもりだったみたい」
だけど私、雅彦さんのこと『駄目男』とはひと言もいってないよ――と、また友人は口の中でブツブツ。そして再び事件の夜の説明に戻った。
「雅彦さんはリビングのソファーでゴロ寝。私はお客さん用の部屋でお布団を敷いて寝かせてもらったの。え、危なくないのかって? まあ、雅彦さんと同じ部屋なら身の危険を感じたかもだけど、部屋は別々だしね。それに、春江おばさんも寝室にいるんだから、その点はあまり気にしていなかった。私は何事もなく平穏な朝がくるものと、そう思い込んでいたの。ところが、その夜に想像もしない一大事が起きて……」
それは森山雛子が寝床について、しばらく経った真夜中のことだ。雛子はTシャツと短パンを寝間着代わりにして布団の上。普段と違う枕の感触に
「きゃああぁーッ」
闇を切り裂くような女性の叫び声が、雛子を眠りの淵から引き戻す。雛子は薄い掛け布団を
雛子は布団の上でキョロキョロとあたりを見回して耳を澄ます。直後に聞こえてきたのは、やはり異常に興奮した女性の声だ。それは切羽詰まったような金切り声だった。
「ちょっと、何するのッ! 誰なの、やめて、こらッ!」
何者かと争うような大声。事ここに至って、これはもう異常事態だと雛子は確信した。いま阿川邸にいる女性といえば、雛子の他には春江だけのはず。ならば、あれは春江の声に違いない。
おばさんの身に何か起こったのだ。――そう思った直後だ。
「ぎゃああぁーッ」
ゾッとするような悲鳴が再び闇に響いた。阿川邸の隅々まで届くほどの絶叫。それに続いて聞こえてきたのは、なにやら人が倒れるようなバタンという大音響だ。雛子は
彼は雛子の姿を認めるなり、暗い廊下を駆け寄ってきた。
「ああ、雛子ちゃん、君も聞いたかい、いまの悲鳴?」
「ええ、それに人が倒れるような音も……おばさんの寝室でしょうか」
「そうだな。とにかく、いってみよう」
二人は雛子の持つ懐中電灯の明かりを頼りに、暗い廊下を進んだ。春江の寝室は、二人がいる廊下の突き当たりから二つ目の部屋だ。たどり着くと、なぜか寝室の扉が半開きになっていた。雛子は部屋の中へと懐中電灯の明かりを差し向ける。だがベッドの上は、もぬけの殻。掛け布団がベッドの端に寄せられている。寝床に入った形跡はあるものの、肝心の春江の姿はどこにも見当たらなかった。
「おばさん、どこにいったのかしら……?」
「うーむ、なんだか訳が判らないな……おや!?」
廊下で首を傾げる雅彦の視線が、ふと隣の部屋へと向けられる。春江の寝室のすぐ隣、廊下の突き当たりに位置する角部屋だ。彼はその入口の前に立つと、扉を指差していった。
「ほら、見てごらん。扉の隙間から明かりが漏れている」
「ホントだ。てことは、中に誰かいるんですね」
「ああ、間違いない」頷くと同時に、雅彦がドアレバーを右手で
「ええッ、なんで鍵なんか……?」
雛子も自らドアレバーに手を掛けてみるが、確かにそれはロックされていてビクとも動かない。仕方なく雛子は扉に顔を寄せながら、「おばあちゃん、いるの? いたら返事して!」
懸命に呼びかけてみるが、中からの応答はない。それを見て、雅彦が聞いてきた。
「雛子ちゃん、鍵の
「あ、それなら私、判るかも!」心当たりのある雛子は、即座に
いうが早いか、雛子は暗い廊下を駆け出した。キッチンに飛び込み、心当たりの引き出しを片っ端から開けていく。すると三つ目の引き出しを開けた瞬間、「――あったぁ!」
雛子の口から
ひと声発して、雛子は再びドアレバーに手を掛ける。扉は音もなくすんなりと開いた。
その瞬間、雛子はギョッと目を見張った。
カーペットを敷いた床の中央付近に、寝間着姿の春江がいた。頭から血を流して、ばったりと床に倒れている。その小柄な身体は微動だにしていない。
あまりの衝撃に堪えきれず、雛子の口から盛大な悲鳴があふれ出した――
「そのとき、すでに春江おばさんは息絶えていたの」当時の感情がぶり返したように、雛子ちゃんは声を震わせた。「警察の調べによると、死因は頭部への打撃による脳
「そうなんだ」私は神妙に頷いた。「で、その現場が密室だったってこと?」
「そう。入口は施錠されていた。角部屋だから窓は二つあったけれど、どっちの窓も中からクレセント錠が掛けられていたの」
「ちょい待ち、雛子ちゃん!」と声をあげたのは、カウンターの向こうにいる兄だ。「そのクレセント錠、部屋に飛び込んだ容疑者A……じゃねえ、誰だっけ、そう、三田だ。三田雅彦、そいつが後からこっそり施錠したんじゃねーか。雛子ちゃんが悲鳴をあげて泣き崩れている隙に、ひとり窓辺に歩み寄って、こっそり中から戸締りを……」
「いいえ、それはありません」雛子ちゃんはキッパリ首を横に振った。「私は確かに悲鳴をあげましたけど、べつに泣き崩れるほど取り乱していませんから。むしろ私のほうから雅彦さんに提案したんです。『窓を確認してみましょう』って」
「そしたらクレセント錠が掛かっていたってわけか。ふーん、なるほど」
なめ郎兄さんは
「実はその部屋の中に、誰かが潜んでいたっていう可能性はないのかな? 例えば、扉の裏側に誰かが隠れていて、隙を見て部屋から出ていった――なんてことはない?」
「それはないよ、つみれちゃん。だって部屋の扉は外開きだから、扉の陰に隠れるなんて無理。それに私、部屋の中に誰かいるかもと思って、かなり警戒しながら扉を開けたの。だから、どさくさ紛れに誰かが部屋から出ていったなんて、あり得ない。おまけに、その部屋って人間が隠れられるような場所がほとんどないのよ。だって猫の部屋だから」
「あ、猫が出てきた……」
唐突に現れた猫に、私はちょっとビックリ。だが考えてみれば、そもそも雛子ちゃんの話は『猫もらってくれない?』のひと言から始まったはず。話の中に猫が登場するのは、至極当然のことではある。「だけど、猫の部屋って何?」
「もともとは亡くなった
「ふーん、それで猫の部屋かぁ」
「そう。猫専用の部屋だから、大きな机とかベッドなんてない。誰かが物陰に隠れて、脱出の機会を
「ふぅん――で、その猫を雛子ちゃんは私に押し付けようとしているってわけだね?」
「べつに押し付けようとはしていないけどね」
ピシャリといって、雛子ちゃんはレモンサワーをゴクリ。私は思わず苦笑いだ。
「ところで、その猫ちゃん、なんて名前なの?」
「コトラよ。キジトラの猫で比較的小さな猫だからコトラって名付けたんだってさ。春江おばさんがそういってた。ちょっと前から庭に姿を見せていた野良猫が、だんだんと春江おばさんになついて、それでとうとう飼うことにしたんだって。しかも専用の部屋まで与えてね」
「てことはよぉ」と、いきなり横から口を挟んできたのは、なめ郎兄さんだ。「春江さんが殺されたとき、犯人のいちばん近くにいたのは、そのコトラって猫なわけだ。だったら、その猫、ひょっとすると犯人の顔を見ているのかもしれねーな」
「そりゃ、そうかもだけど」何いってんの、お兄ちゃん? 私は
「え!? いや……はははッ、そういや、全然無理だな。
自らを笑い飛ばして頭を搔く兄。雛子ちゃんはガックリと肩を落としながら、
「そうなのよねえ。コトラが犯人の顔に引っ搔き傷でも残しておいてくれたなら、それが事件解決の手掛かりに――っていう展開にもなるんだけど」
「さすがに、そんな都合良くはいかないよねえ。ていうか、そもそも犯人がどこにもいないんじゃあ、引っ搔き傷を残すことだってできないじゃない」私はあらためて飼い猫から密室へと話題を戻した。「結局、春江さんを殺した犯人は、どこに消えたわけ? 入口も窓も施錠された部屋の中から、犯人はどうやって逃げ出したの?」
「そうなのよねー」雛子ちゃんは嘆息しながら、ジョッキの底に残ったレモンサワーをぐっと飲み干した。「そこが不思議なのよねえ。なんだか警察も手を焼いているみたい」
「へえ、警察も……あ!」てことは、これはひょっとして、あの人向きの事件かも。だったら、さっそく明日にでも会いにいってみようかしら?
そう思った途端、私は不謹慎ながらも、なんだか久々にワクワクした気分。
でも待って、と私は不安になった。――ちゃんとたどり着けるかなぁ、あの店!
3
あの店というのは、ご利益があるのか否か怪しいような開運グッズを取扱う店。その名も『
路地が入り組んだ場所にあるためか、あるいは古びた店舗そのものに他人を欺く霊的な何かが取り
パッと見た感じでは、商店というよりも古びた民家としか思えない木造建築だ。『怪運堂』と書かれた小さな看板を確認してコクンと頷く私。建て付けの悪い引き戸をガラガラッと開けながら、「ごめんくださーい」と控え目な声で中へと呼びかける。
そんな私を最初に迎えたのは、二体の巨大招き猫だ。まるで神社の
通常サイズの招き猫はもちろん、龍の置物や鯉の掛け軸。七福神のフィギュア。お守りやお札や
そんな中、私は無用なガラクタども(失礼!)には見向きもせず、棚の間をすり抜けるようにして店の奥へと向かう。そこが畳敷きの小上がりになっているのだ。
その人は古いちゃぶ台に向かう
こげ茶色の
ただし、単なる店舗経営者ではない。ここ最近、谷根千界隈で頻発する難事件の数々を、散歩がてら解決に導いてきた謎の知恵者。あるいは判りやすく『名探偵』と呼んでもいいだろう。
そんな竹田津さんは、私の姿を認めるなり、「やあ、なんだ、つみれちゃんか」と片手を挙げて優しい笑顔。「そうか、君か……正座して損したよ」といって足を崩すと、あらためてあぐらを搔きながら、「今日はなんの用だい? なめ郎の奴に何か頼まれたのかな?」
竹田津さんとなめ郎兄さんは、幼少のころからの知り合いだ。兄はそれを
私はポニーテールに結んだ髪の毛をブンブンと左右に振りながら、
「いいえ、なめ郎のやーつに何かいわれたわけではありません。今日は私自身の用があって、この店にきました。けっして損はさせませんよ」
「いらっしゃいませ。何をお探しですか」
瞬時に態度を翻して、正座しなおす竹田津さん。ようやく客扱いする気になったらしい。
しかし私は顔の前で手を振りながら、「いえ、何か買いにきたってわけでもなくて……」
「ちぇ、なんだよ」舌打ちして、また足を崩す竹田津さん。今度は両足を畳の上で真っ直ぐ伸ばしたまま、退屈そうに前屈運動を始めながら、「お客さんッ、じゃないならッ、いったいッ、なんだいッ? ただのッ、冷やかしッ、かいッ?」
――こらこら、ストレッチしながら質問しない! 私のこと、馬鹿にしすぎでしょ!
ムッと眉根を寄せる私は、首を左右に振って低い声でいった。
「いいえ、冷やかしではありません。――密室です」
このパワーワードの効果は絶大だった。「えッ、密ッ、室ッ」とさらに三度、前屈を続けた竹田津さんは、「なに、密室ぅ!」と大きな声を発してストレッチを中断。
「ええ、マジです。マジで密室」
すると彼は伸ばした足を引っ込めて、今度は四つん
「まあまあ、そんなところに突っ立っていないで、上がりなさい。いいから、上がりなさい。せっかくだから、熱いお茶でも
「…………」竹田津優介、やはりこの手の謎には目がないらしい。
ニンマリとした笑みを浮かべる私は、遠慮なく小上がりにお邪魔することにした。
それから、しばらくの後。ちゃぶ台を挟んで竹田津さんと向き合う私は、湯飲みのほうじ茶を
「密室じゃないですか」いったい、なんの文句が? といわんばかりに私はTシャツの胸を張った。「鍵の掛かった部屋で人が殺されたんですよ。間違いなく密室殺人です」
「でも入口の扉は中からカンヌキが掛かっていたとか、そういう話じゃないよね。扉はただ鍵によって施錠されていただけ。だったら犯人は合鍵を持っている人物で、犯行後にその合鍵で扉をロックして逃走した。そういう可能性だって否定できないだろ」
「はぁ!? あり得ませんよ、そんなの」私は即座に反論した。「なんで一刻も早く現場から逃走したい犯人が、わざわざ合鍵を使って扉を施錠するんです? 扉なんか開けっ放しにして、さっさと逃げればいいじゃないですか」
「ふむ、そりゃまあ、そうだ」
「それに、タイミング的にいっても、竹田津さんのいうような可能性はあり得ません」
「ん、タイミング……というと?」
「春江さんが残した最後の絶叫。それこそが、まさしく彼女が致命傷を受けた瞬間だと思われます。つまり犯人が角材か何かで春江さんの頭を殴打したのは、このときでしょう。で、その絶叫を耳にしたほんの数秒後には、もう雛子ちゃんは廊下に飛び出していた。三田雅彦もリビングから廊下へ出てきた。もし、このとき犯人が現場の扉の前で、合鍵を使ってモタモタと扉をロックしていたなら、いったいどうなるか――」
「ふむ、判ったよ。その場合、犯人は雛子ちゃんたちと廊下で鉢合わせしたに違いない」
「そういうことです。だって現場は廊下の突き当たりの部屋なんですからね。きっと雛子ちゃんは犯人の姿を目撃できたはず。でも実際は、彼女は犯人を見ていない。つまり現場の扉は犯人が合鍵を用いて施錠したものではない――と、雛子ちゃんがいっていました」
「なーんだ、いまのは雛子ちゃんの推理か」ホッとしたように竹田津さんは作務衣の胸許を
「ムカッ!」私は判りやすく内心の憤りを
「いや、まさか抜け道なんて、ないとは思うけどね」竹田津さんは腕組みしながら、何事か考える素振り。やがて、ゆっくり顔を上げると、落ち着いた口調でいった。「ひょっとして早業殺人じゃないかな」
「え、早業殺人って……誰の?」
「もちろん容疑者Aの男、三田雅彦だよ。雛子ちゃんが犯人じゃないと信じるなら、残る容疑者は彼しかいないだろ」
「それはそうですけど」なんか安直すぎませんか? 私は首を傾げながら、「でも、どうやるんですか、早業殺人って? 雅彦がどのタイミングで、どんな早業を?」
「タイミングならあったはずだよ」竹田津さんは説明した。「雛子ちゃんと雅彦は、ほぼ同時に廊下に出て現場の前へとたどり着いた。そして入口の扉が施錠されていることを、二人で確認した。問題はその後だ。雛子ちゃんはキッチンに鍵束を取りにいった。このとき現場の扉の前には、雅彦がひとりだけ残った。このタイミングなら雅彦は誰の目も気にすることなく、凶行に及べるってわけだ」
「でも凶行って、どうやって? 扉には鍵が掛かっているんですよ」
「それこそ合鍵を使ったのでは?」竹田津さんはちゃぶ台から身を乗り出すようにして、問い掛けた。「雛子ちゃんが鍵束の在り処を知っていたように、実は雅彦もそれがキッチンの引き出しにあることを知っていたのかもしれない。だとしたら雅彦が前もって合鍵を手に入れていた可能性は充分にあるだろ。彼だって過去に何度も春江さんの家を訪れているんだから」
「なるほど。それは確かに……」
「雅彦は雛子ちゃんが鍵束を取りにキッチンへ向かった直後に、ポケットから合鍵を取り出した。それを使えば扉は難なく開く。雅彦は素早く部屋の中に入って、まだ生きてピンピンしている春江さんを速攻で殴り殺した――」
まるで見てきたように、竹田津さんは雅彦の犯行過程を説明する。私は
「殴り殺すって、どうやって? 凶器は何ですか?」
「え、凶器!?」竹田津さんは虚を
「そんなもの、雅彦はどうやって隠し持っていたんですか」
「えっと、隠し持つのは無理か……じゃあ最初から部屋の中にあったんだろ、角材が」
「じゃあ、犯行後、雅彦はその角材をどうしたんですか。現場からは、角材はもちろん、凶器になりそうな角ばったものなど、いっさい見つかっていないんですよ」
「あれ、そ、そうなんだ……」しどろもどろの状態に陥った竹田津さんは、不満げに唇を尖らせながら、「つみれちゃん、君、さっきの説明の中でそういった? いってないよね?」
「いいました」いや、いわなかったかもだけど、ここは断固として言い張る私。「それに、合鍵を持っていたというなら、雅彦はその合鍵をどう処分したんですか。ポケットに隠していたら警察に身体検査されて終わりでしょうし、かといって現場周辺に捨てれば、やっぱり警察がすぐに見つけたでしょう。でも実際には、そんな合鍵なんて、どこからも発見されていないんですよ」
「ああ、そうかい」とアッサリ折れて、竹田津さんは長い髪を指で搔き上げた。「うーん……てことは、やっぱり早業殺人なんて無理か……」
「そうですよ。そもそも雛子ちゃんは、春江さんの悲鳴や何者かと言い争う声、バタンと人が倒れるような音を聞いてから、現場に駆けつけたんですよ。だったら春江さん殺しは、その時点ですでに終了しているはずじゃないですか」
「でも、その悲鳴や争う声などにも何かトリックがあったなら……いや、まあいい。とにかく早業殺人というアイデアは、ひとまず撤回しよう。となると、いったい何だ? 鍵の掛かった部屋から犯人はどうやって消え去った? どうもよく判らない事件だな……」
最後は独り言のようにいって、竹田津さんは湯飲みのほうじ茶をズズズッと飲み干す。そして丸眼鏡越しの視線を真っ直ぐ私へと向けながらいった。
「その密室となった現場――猫の部屋だっけ――そこを一度、この目で見てみたいな」
「あ、だったら私、雛子ちゃんに電話でお願いしてみましょうか」
「ん、お願いするって、どうやって? まさかと思うけど、『知り合いの三十男が殺人現場を見たがっているのー』って本当のことをいうつもりかい? でも、そんなこと急にいわれたら、雛子ちゃん、『何そいつ、気色悪ッ』ってドン引きしないかな?」
「うーん、それもそっか」――にしても竹田津さん、自分の怪しさをよくお判りで!
確かに雛子ちゃんは竹田津さんと面識がない。彼が名探偵であることなど、まったく知らないのだ。そんな友人の目に『怪運堂』店主の姿は、単なる|《作務衣丸眼鏡男》としか映らないだろう。まあ、実際そういう外見だから仕方ないのだが……と思ったそのとき!
「あッ、そうだ。いいこと思いついたッ」
突然の
4
翌日は快晴の土曜日。私は竹田津優介さんを引き連れて、団子坂にほど近い阿川邸へと向かった。『現場を見てみたい』という名探偵のリクエストに
「あ、こっちですよ、こっちの路地……ほら、見えてきた……わ~い、雛子ちゃ~ん!」
たどり着いた阿川邸の門前では、Tシャツにデニムパンツ姿の友人が、私たちの到着を待ちわびていた。「つみれちゃ~ん、電話ありがとね~」と笑顔で両手を振る雛子ちゃん。そして丸眼鏡の三十男に視線を移すと、彼女はペコリと頭を下げた。
「竹田津さんですね。お話はつみれちゃんから伺っています。さあさあ、遠慮なく……」
雛子ちゃんは私たちを引き連れて門をくぐる。そこにあるのは、古びた日本家屋に最新の洋風建築を付け足したキメラな建物だ。狭い庭には大きなケヤキの木があって、太い枝が屋根まで届いている。玄関の引き戸を開けた雛子ちゃんは、
「さあ、どうぞ中へ」
といって愛想よく私たちを招き入れた。なんの疑いもなく故人の家に通されたことが、逆に不思議だったのだろう。竹田津さんは丸眼鏡の奥から
「いまさら聞くのもナンだけど、君の友人は僕の勝手な申し出をよく許可してくれたね。つみれちゃん、あの
「え!? いえいえ、弱みなんて、まさか……」
慌てて手を振る私は、友人の背中を追うように廊下を進む。竹田津さんは
「ほぉ、つまり犯行現場ってわけだね。――おや!?」竹田津さんは問題の扉を見るなり、不思議そうに声をあげた。「この扉、廊下側にカンヌキがあるね。珍しいな……」
「ホントだ。普通は室内側にあるものですよねえ」
それは金属製の粗末なカンヌキだ。位置的にはドアレバーから十センチほど高いあたり。ホームセンターなどで買った既製品を、後から扉に取り付けたものらしい。
首を
「はい、そうです」雛子ちゃんが頷いた。「猫って意外と賢くて、コトラの場合もドアレバーに飛びついて扉を開け、ひとりで部屋から出ちゃうことが、ときどきあったらしいんです。それで春江おばさんは、こんなふうに廊下側にカンヌキを取り付けたんですね」
「ふむ、いちいち鍵を使って施錠するのは面倒だものね」竹田津さんは納得した顔で頷いた。「ちなみに事件発覚の際には、このカンヌキは掛かっていなかったのかい?」
「ええ、扉は施錠されていましたが、カンヌキは掛かっていませんでした」
「そうか」竹田津さんはカンヌキの滑り具合を確かめると、「中に入ってもいい?」
「もちろんですとも。ちゃんとコトラも連れてきてありますから」
「ほう、猫もか……てことは、つまり事件発覚の際とまったく同じ状況が再現されているってわけだ。それはありがたい……」
独り言のようにいって、竹田津さんはドアレバーを引く。扉を入った雛子ちゃんが、壁のスイッチを押して天井の照明を
なるほど、そこは猫の部屋だった。
広さは四畳半ほど。まず目に飛び込んでくるのは、部屋の片隅に置かれたキャットタワーだ。いわば猫用のジャングルジムみたいなものか。かなり立派なもので人の背丈を超えるほどの高さがある。高いところが大好きな猫たちは、このタワーに上ることで束の間、野生の本能を満たすのだ。それ以外にも、猫用の寝床や砂の入ったトイレ、餌を与える際に使う銀の皿、ボールや猫じゃらしなどの遊び道具がカーペットの床に置いてある。
逆にいうと、それら以外に目立つ家具などはない。なるほど、この空間に何者かが身を潜めるということは、まったく不可能なことだろうと、あらためて私は納得した。
そんな中、ペット用のキャリーケースが入口付近に置いてある。中で窮屈そうに身を丸くしているのはキジトラの猫。これが話題のコトラちゃんらしい。さっそく雛子ちゃんはケースの扉を開けると、大事な猫を室内へと解き放った。晴れて自由の身となった猫は、久々の我が家でテンションが上がった様子。狭い室内を駆け回ると、瞬く間にキャットタワーのてっぺんへと上り詰めた。その姿を指差して、竹田津さんが尋ねた。
「これが犯行現場にいた猫だね。ふむ、なるほど、当然ながら普通の猫だな。――ちなみに、この猫って、いまはどこで暮らしているんだい?」
「いまは、私のアパートで居候中です」
「わあ、雛子ちゃんのアパートってペット飼っていいんだぁ。いい部屋なんだねぇ」
私が無邪気な感想を述べると、なぜか友人は気まずそうな表情。「あ、いや、違うの、つみれちゃん……」といったきり、意味深な無言状態に陥った。「……………………」
「……あ!」駄目なんだ! 本当はペット不可の部屋で、猫、飼ってるんだね、雛子ちゃん!
友人の無言の意味を、私はそう解釈した。「で、でもまあ、事情が事情だから仕方がないよね。一時的にはそういうことだってあるよ。うん、あるあるッ」
けっして友人を
「ほぼ部屋の中央ですよ。頭を壁のほうに向けて
そういって雛子ちゃんが部屋の真ん中あたりを指差す。すると『怪運堂』の物好きな店主は、死んだ人の気分を味わいたいとでも思ったのだろうか、床の上でいきなりゴロンと仰向けに横たわった。「てことは、こんな感じかい? 身体は大の字に? じゃあ、こんな感じかな。――おや、あれは!?」
竹田津さんは真上を向いたまま眼鏡の縁に指を当てて目を凝らす。天井に何か興味深いものを見つけたらしい。何だろう、と思って私も咄嗟に上を向く。なるほど、そこには意外なものがあった。「あれって……天窓ですよね」
ゆるやかな傾斜の付いた天井にガラス窓がひとつあった。不透明なガラス越しに外の光が、部屋の中へと差し込んでいる。竹田津さんは天井を見やったまま上体を起こした。
「ふむ、確かに天窓だな。――つみれちゃんの話の中には出てこなかったよね?」
「そ、それは、雛子ちゃんの話の中に出てこなかったから。――ね、雛子ちゃん?」
「え、だって天窓なんて、どうだっていいでしょ? あれは明かり取りと換気のための窓。ほんの少し斜めに開くようになっているけれど、人間が通れるほどには開かない。つまり犯人が誰にせよ、あの窓から出入りしたなんてことは考えられないってわけ。警察の人たちも、あの窓のことは重要視していなかったみたい。――ていうか、そんなことより!」
ブンと顔を振った雛子ちゃんはキャットタワーに歩み寄って、てっぺんにいる猫を両手で引っ張り下ろす。そして、その猫を竹田津さんの胸許にぐいぐい押し付けながら、
「ねえねえ、どうです、コトラちゃん? かわいい猫でしょう? おとなしくて人懐っこくて、それから……ほら、立派なおヒゲも生えてるんですよぉ。かぁわぁい~ぃ!」
「はぁ?」竹田津さんは無理やり抱っこさせられたトラ猫を見詰めてキョトンだ。「猫なら大抵ヒゲは生えてるんじゃないの……」そういって狭い額を撫でると、すぐさまカーペットの上に猫を下ろしていった。「密室の中には被害者の他に、この猫しかいなかったんだね。で、犯人の姿はどこにもなかった。なおかつ、雛子ちゃんや三田雅彦さんが犯人という可能性も考えられない状況だった」
「ええ、そうです。私は犯人じゃありません。もちろん雅彦さんもです」
「でも、そうだとするなら、これはもう『猫が犯人だ』って話になっちゃうのでは?」
「んな馬鹿な!」雛子ちゃんは顔の前で両手を振りながら、「あり得ませんよ、そんなの! だって、春江おばさんは角材みたいなもので頭を殴られて亡くなったんですよ。猫がどうやって角材を振り回すっていうんですか」
「ふむ、そりゃまあ、そうだ」竹田津さんはいったん頷き、そしてニヤリと愉悦の笑みを浮かべた。「でも判らないよ。コトラちゃんが、実は化け猫ってことかも……」
「そんなわけありません。コトラは
「ふぅん、そうか。だったら化け猫ってことはなさそうだね」
竹田津さんは納得した様子で引き下がる。彼がなぜ納得できたのか、私にはサッパリ理解できない。――化け猫予防の注射があるとでも? 何いってんの、二人とも?
呆れ返る私の隣で、竹田津さんは作務衣の肩をすくめていった。
「まあ、化け猫は冗談だとしても、密室の中に猫一匹というのは、やはり気になるな」
「気になるって、どんなふうにです?」
(気になる続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:谷根千ミステリ散歩 密室の中に猫がいる
著 者:東川 篤哉
発売日:2025年07月02日
最強凸凹コンビ×猫と下町グルメたっぷりの本格ミステリ!
“猫”だけが目撃した密室殺人、大学祭で起きた人間消失事件、お巡りさんとのデート中(?)に遭遇した殺人未遂事件。
下町情緒あふれる谷中にある、鰯専門の居酒屋。看板娘の岩篠つみれのもとには、不可解な事件が次々に持ち込まれる。困ったつみれが怪しい開運グッズ店の店主・竹田津を頼ると、彼は事件現場で猫をかまったり、喫茶店でスイーツを食べたりしながら、衝撃の真相を解き明かしていく! 本作から読んでも楽しめる、超人気コージーミステリ最新刊!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322309001301/
amazonページはこちら
楽天ブックスページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら