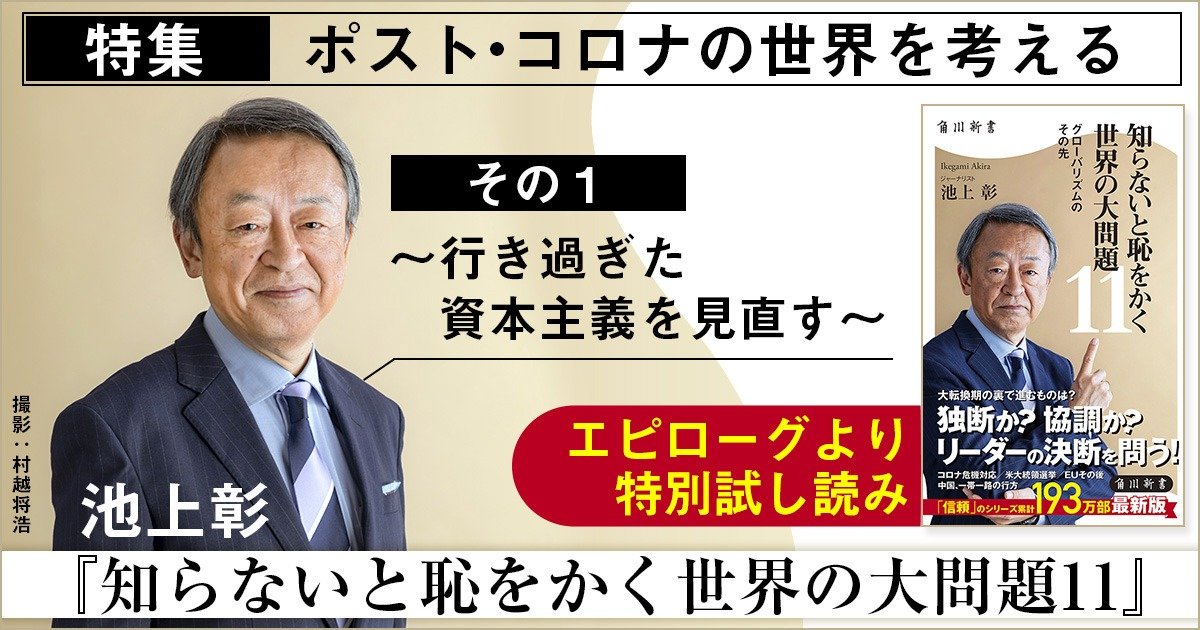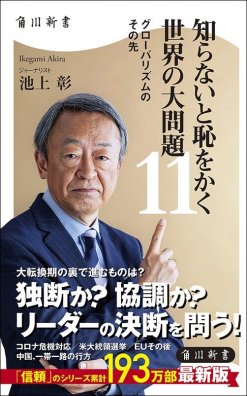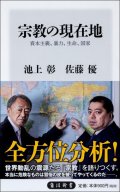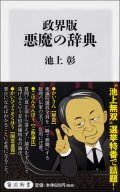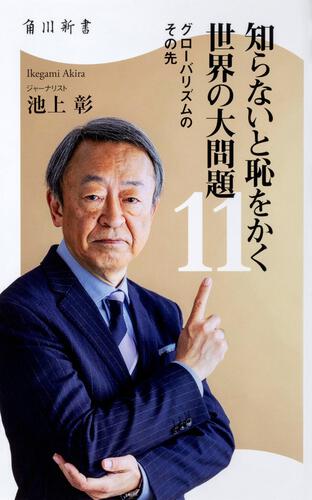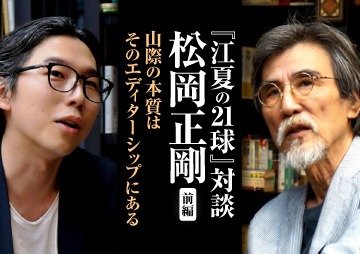池上彰さんによる信頼の「ニュース入門」第11弾、角川新書『知らないと恥をかく世界の大問題11 グローバリズムのその先』が2020年6月10日(水)に発売となりました。シリーズ累計193万部突破、愛称「知ら恥」シリーズの最新刊です。本書では、新型コロナウイルスで大きく変化した世界を見通し、その裏で進むものを解説しています。
そこで、今回は、「ポスト・コロナの世界を考える その1」と題し、本書の中から抜粋します。
■行き過ぎた資本主義を見直す
今回の新型コロナウイルスの感染拡大は、世界経済のグローバル化に伴うものです。人類の歴史の中で過去に何度も感染症が世界に広がりましたが、これほど短期間に拡大したものはありませんでした。グローバル化の影を思い知りました。
中国からの感染拡大で、「世界の工場」である中国に部品の供給を頼っていた各国の企業は、部品の供給ルート、いわゆる「サプライチェーン」が一時的に切断されてしまいました。日本もマスクの製造を中国に頼っていたことが判明。国民の健康や安全に関わる製品の製造を他国に頼っていることの危険性を思い知らされました。
やがてコロナ禍が収束したら、世界中でサプライチェーンの再検討が進むでしょう。と共に、「行き過ぎた資本主義」の見直しも行われるはずです。「行き過ぎた資本主義」とは、効率一点張りの企業活動です。
コロナ禍があっても、世界経済のグローバル化を止めることはないでしょう。しかし、大きな変化が起きることは間違いありません。かつての感染症が世界史を変えてきたように、いままた、新しい歴史が書かれようとしているのです。(「おわりに」より抜粋)
■社会主義の崩壊と資本主義の失敗
2020年も半年近く経ちました。現代社会のキーワードは何か。ひとつは「格差」でしょう。世界がグローバルなマーケットになったことによって、経済格差が生まれ、新たな分断が生まれた。格差の中で自分さえよければという世界の流れが広がっています。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大の様相を見ても、アメリカでは所得の低い人の死亡率が高いのが特徴です。格差は人を殺すのです。
東西冷戦が終わって約30年が経ちました。社会主義が崩壊して、資本主義が勝ったと言われました。東西冷戦が終わったとき、国際政治学者のフランシス・フクヤマは『歴史の終わり』を書きました。「東西冷戦」というイデオロギー対決の歴史は、自由主義、民主主義の勝利によって終わった、と。
資本主義と社会主義のイデオロギー闘争では、資本主義によって格差が広がると労働者の不満が高まり、革命が起きるのではないか。そういう恐怖心があります。そこで資本主義を推進する側も、格差をなるべく減らそうとしてきました。そうしたら社会主義が自滅した。資本主義が勝利した。資本主義の優れたところは自由な市場だ。国家の規制を排除し、自由な経済競争をすることが、豊かな社会を築くことだ。
ここに思い上がりがあったのですね。結果的に「資本主義万歳!」になり、格差是正の取り組みをしなくなったらこんな状態になってしまったのです。資本主義には、貧富の格差を拡大する力が内在しているのです。
歴史は本当に進んでいるのか、疑わしくなります。東西冷戦が終わって、世界はひとつのマーケットになりました。グローバリズムそれ自体はよかったのですが、域内で貧富の差が大きすぎると、かえって世界は混乱してしまうことを痛感しました。
しかし、自国第一主義=アンチ・グローバリズムで世界の問題が解決できるわけではありません。
■ポスト資本主義の時代
2020年1月21日に開幕した世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)は、資本主義の再定義が主題になりました。
ダボス会議とは、毎年1月末にスイスのリゾート地ダボスで開かれる国際会議です。そもそもは経営学を専門とするジュネーブ大学のクラウス・シュワブが、冬のリゾート地で世界の問題をじっくり考えようと呼びかけたのが始まりです。多くの世界的企業の協賛でどんどん規模が大きくなり、いまでは世界中から2500人もの知識人や経営者、政治家があつまるイベントになっています。
ダボス会議は今回で50回目となりますが、ちょうど50年前、アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンが「企業の唯一の目的は株主価値を最大化することだ」と主張しました。株主第一というわけです。当時はこの発言が新鮮な驚きを持って受け止められました。資本主義の本質を衝いた発言だったからです。
でも潮目は変わってきたようです。今年のダボス会議では、格差是正や環境問題と向き合い長期的な成長をめざす「ステークホルダー資本主義」が掲げられました。
資本主義のあり方を変えていかなければいけないということですね。ポスト資本主義の模索が始まっているのです。
近代日本経済の父と呼ばれ、新一万円札の「顔」になる渋沢栄一は『論語と算盤』の中でこう説いています。「利を図るということと、仁義道徳たる所の道理を重んずるということは、並び立って相異ならん程度において、初めて国家は健全に発達し、個人は各々その宜しきを得て、富んで行くというものになるのである。」
経済と道徳、どちらも大事で調和するのが最善というわけです。
■宇沢弘文が提起したもの
ポスト資本主義というと、2014年に亡くなった経済学者・宇沢弘文さんのことを思い出します。近代経済学の世界の頂点に立ちながら、自らの足場を打ち砕くようにその批判に転じ、「社会的共通資本」の理論構築によって新たな経済学を目指された異端の経済学者です。
宇沢さんは鳥取県米子市出身。米子の人たちは、宇沢さんの理想を実現するために「よなご宇沢会」を結成し、勉強会を毎年開いています。私も呼ばれて、「よなご宇沢会」の人たちの前で宇沢さんの功績について話をしました。
そこで私が提起した課題のひとつが、公立病院の再編の話です。厚生労働省は診療実績が乏しい病院の統廃合の検討をすすめています。リストに上がった424の病院はとくに再編統合についての議論が必要だというのです。
病院がすぐ近くにある都会の人はピンとこないかもしれませんが、島根や鳥取など、地方では、県内に数少ない公立病院が減らされてしまうことは、実に深刻な問題です。
今回の新型コロナウイルスの感染拡大で、地域医療の拠点になる病院の存在を多くの人が認識したのではないでしょうか。医療の効率化は必要だとはいえ、人の健康と命が効率化で疎かになってはなりません。
今回の感染で、イタリアは医療崩壊となり、多くの人命が失われました。イタリアは、財政状態が悪化してユーロ危機を招いた経験から、国内の医療機関の効率化を進め、医療従事者が激減していました。効率化は人の命を危うくすることもあるのです。
宇沢さんは「社会的共通資本」というキーワードを残してくれました。非効率な医療が問題だと「資本効率」だけ考えれば統廃合を進めたほうがいいのかもしれないけれど、地域の医療を守るのは社会的共通資本です。効率よりもっと大事なことがあるのではないかということです。
あるいは学力があってお金のある子はみんな私立の学校に行って、公立学校がどんどん荒れてしまったら、ますます格差が広がってしまいます。誰でも無料できちんと教育が受けられるような公立学校を充実させる。これも社会的共通資本ではないか。国を豊かにする、国づくりの根幹は教育です。
■広い視野を持ち、多角的に考えるために
アメリカにしても、「急進左派」とされるエリザベス・ウォーレンが出てきたり、公立大学無償化を掲げるバーニー・サンダースが出てきたりするのも、行き過ぎた資本主義に対するブレーキをかけようという動きです。
国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)が注目されるのも、社会のさまざまな試練に対処するには「節度」が必要だからです。
自国第一主義がはびこる世界、その背景には宇沢さんが危惧していた新自由主義の猛威がありました。新型コロナウイルスの感染拡大に多くの人が不安に思ういまこそ宇沢さんが提起した「社会的共通資本」の観点から、日本と世界を見直してみませんか。
格差の広がり、民族間の対立など人々が分断されています。世界にはさまざまな言語があるように、多くの民族や宗教にあふれています。グローバル社会に生きるには多様性を尊重していかなければなりません。学ぶことによって、あなたが生きている日本や大事にしている価値観とは異なるものがあることを知ってください。学び方を深めるコツの第一歩は、その違いに気づくことだと思います。(以上、「エピローグ」より抜粋)
書誌情報
角川新書『知らないと恥をかく世界の大問題11 グローバリズムのその先』
著者:池上 彰
定価:(本体900円+税)
発売日:2020年06月10日
ISBN:978-4-04-082355-3
頁数:280ページ
発行:株式会社KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000121/
関連書籍(池上彰の好評関連本)
角川新書
『宗教の現在地 資本主義、暴力、生命、国家』
著者:池上彰・佐藤優
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000007/
『知らないと恥をかく東アジアの大問題』
著者:池上彰・山里亮太・MBS報道局
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000122/
『政界版 悪魔の辞典』
著者: 池上彰
https://www.kadokawa.co.jp/product/321712000255/