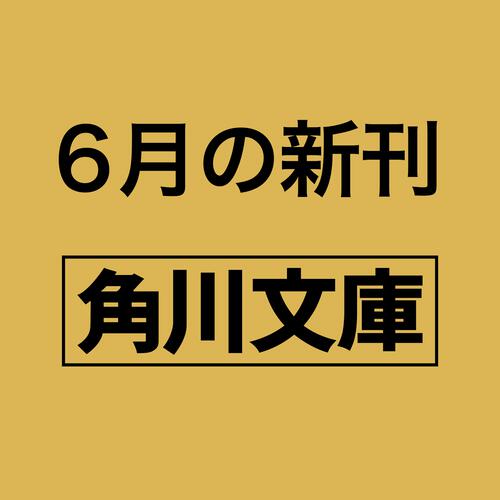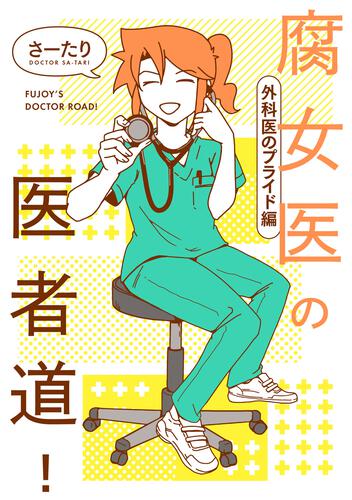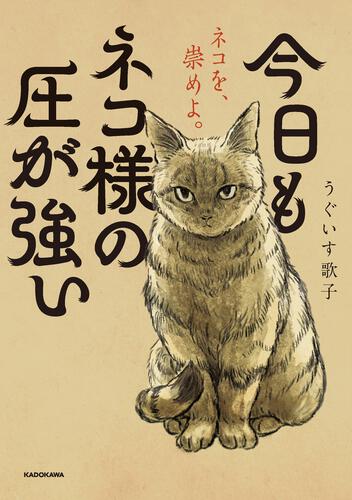宮部みゆき『よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
宮部みゆき『よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続』文庫巻末解説
解説 聞こえない響き
あるとき人は、「生活」の次元と「人生」の次元を明確に感じ分けることになる、と作家の
この小説に限らない。
たとえば、一見しただけでは、何ら特別なことはないかのように見える次の一節もそうだ。
人の年齢は声にも出るが、むしろしゃべるときの調子や言葉の選び方によく表れる。これは一言二言ではなく、しゃべり続けているとよくわかる。(第一話)
語る内容をとりつくろって、自分を偽ることはできる。しかし声や語る調子、そして言葉の選び方すべてを装うのはむずかしい。そこには、人生の軌跡が不可視なかたちで刻まれているからだ、というのだろう。
たしかにそうである。人は生活のありようを覆い隠すことはできても、人生との関係を偽ることはできない。ただ、この物語はそこでは終わらない。読者をもう一段、深い場所へと導こうとする。先の一節の少し前にも声をめぐるこんな言葉が記されている。
「十一のときに、笑い方を忘れました。それっきりいっぺんも笑ったことがねえ。他人 様に愛想を言うこともできやしません。だからこんな顔をしておりますが、勘弁してやっておくんなさい」
声を聞いたら、三 十 路 に届いていないと感じた。もっとずっと若い。もしかしたら富次郎と同じくらい、二十二、三ではないか。(第一話)
十一歳にして、笑いを封印しなくてはならなかった男は、実年齢が刻んだ時間とは別な「時」の世界に生きている。この作品を貫く百物語もまた、「時」の世界を私たちに告げ知らせるものである。
「語る」にせよ「聞く」にせよ「声」から離れることはできない。だが人は、語られた内容はもちろん、声だけを聞いていても真実を見失ってしまう。この小説に登場するある人たちは、話の内容や声だけでなく、「響き」を聞いている。ここでいう「響き」とは、音響のことではない。むしろ、無音の音と言った方がよい何ものかである。
「響く」、あるいは「響き」は、この物語の奥行きを感じ取るための扉になる言葉だ。読者はさほどページをめくらないうちに「響き」の文字を目にする。
「どうにも語ることがむつかしければ、わたしといっとき茶飲み話だけしていただいて、お帰りになってくださってかまいません。この変わり百物語は三島屋の酔狂でございます。ただの酔狂でお客様を苦しめることがあっては、商人 の地獄に落とされてしまいます」
思いつきの台詞 だったが、語り手の耳にはよく響いたらしい。(第一話)
「よく響いた」という表現には、言っていることがよく理解できたという以上の意味が込められている。人が「響き」を感じるのは頭でも心でもなく、魂と呼ぶべき場所だからである。この物語──作者というより作者を超えた物語そのもの──は、読者にも同質の準備を穏やかに求めている。
目で文字を追い、語意によって読み進めるだけでなく、「響き」という生ける意味を魂で感じ取る。そのとき現実界の
良く練られた物語ほど、良く読むことができる。場合によっては早く読むこともできる。こう言ってもよい。読者は熟読するのに必ずしもゆっくりと読む必要はない。そうした小説の
読者は、どんなに読む速さを高めてもよい。ただ、
語りを聴きながら、いつしか、富次郎は両手を強く握りしめていた。
生きている土左衛門。その思いがけぬ強 靱 でしぶとい動き。白濁した眼は、花代の目と似ている。何か関わりがあるのだろうか。先を急いで問いかけてはいけないとわかってはいるが、気が逸 る。こんな話は初めてだ。(第三話)
この作品が、「三島屋変調百物語」を読むはじめての機会だった、という人のなかには
この文章も終わりに近づいてきた。作品のはじめに立ち戻ることにしよう。作者なのか、物語の世界の語り手なのかが、おちかをめぐってこんなふうに語っている。
おちかは暗い影を引きずる孤独な娘だった。ほんの少し浮ついた娘心が災いして許婚者を失い、身近な男を人殺しに堕 してしまったと、我が身を責めていた。しかし変わり百物語の聞き手を務め、この世の数奇で不思議な出来事を耳に入れてゆくうちに、傷ついた心を縫い合わせ、その痕 を抱えながらも立ち上がる強さを持っていた。(序)
この一節をおちかを紹介するものとして読むだけではもったいない。彼女が厳しい経験を生きるちからへと変容できる気丈な女性であるのは確かである。しかし、読者である私たちが見過ごしてはならないのは、「物語」のちからである。おちかが、幾多の試練をいのちの糧に変えることができたのは、物語とともに生きてきたからだった。
事実を告げるだけなら人は、物語のちからを借りなくてもよい。しかし、事実の奥に潜む真実にふれようとするなら、そこに物語があるか否かは大きな問題になる。
物語において語る主体は、人であるとは限らない。「物」が語るから「物語」なのである。
現代ではほとんどの場合物質を意味している「物」という言葉も、この作品の時代では意味がまったく異なっていた。「物になる」、「物にならない」、「物々しい」という場合もある。
「物」は、肉眼を見開いただけでは感じ取ることのできない何ものかである。「物になる」というときの「物」は真実の自己をさえ意味することがある。「物々しい」とは単に物騒だというだけではない。この世界に「存在」するというより、五感を超えたかたちで「実在」しているというべき何かを指している。そうした「物」が、響きを携え、語り始めたとき、真の意味での「物語」が動き出す。
読者は、その瞬間をこの作品のどこかで感じることになるだろう。
作品紹介
書 名:よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続
著 者: 宮部みゆき
発売日:2024年06月13日
この部屋で語られる怪談は、ひとの心を解きほぐす
江戸は神田の袋物屋・三島屋は風変わりな百物語で知られている。語り手一人に聞き手も一人。話はけっして外には漏らさない。聞き手を務める小旦那の富次郎は、従妹であるおちかのお産に備え、百物語をしばらく休むことに決めた。休止前最後に語り手となったのは、不可思議な様子の夫婦。語られたのは、かつて村を食い尽くした〈ひとでなし〉という化け物の話だった。どこから読んでも面白い! 宮部みゆき流の江戸怪談。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000734/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら