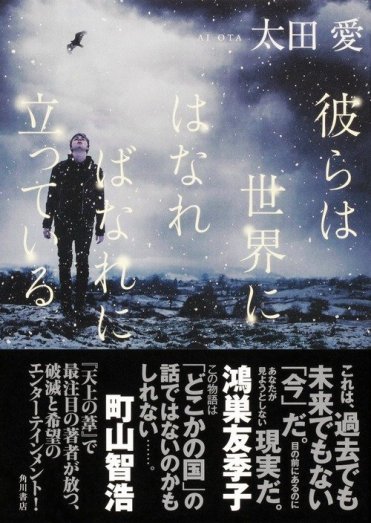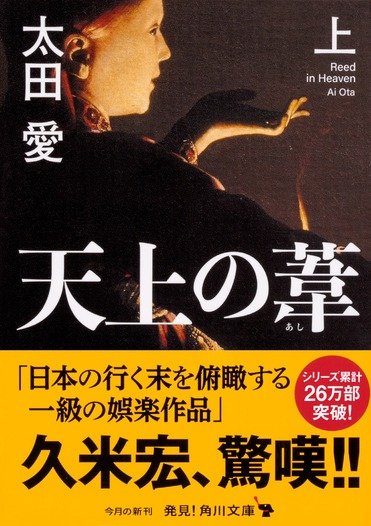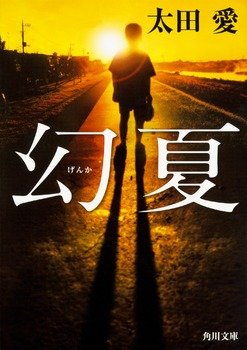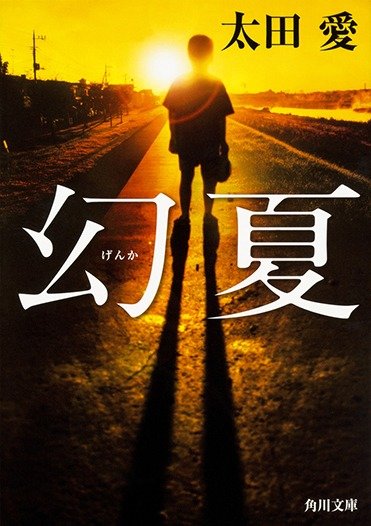彼らは世界にはなればなれに立っている
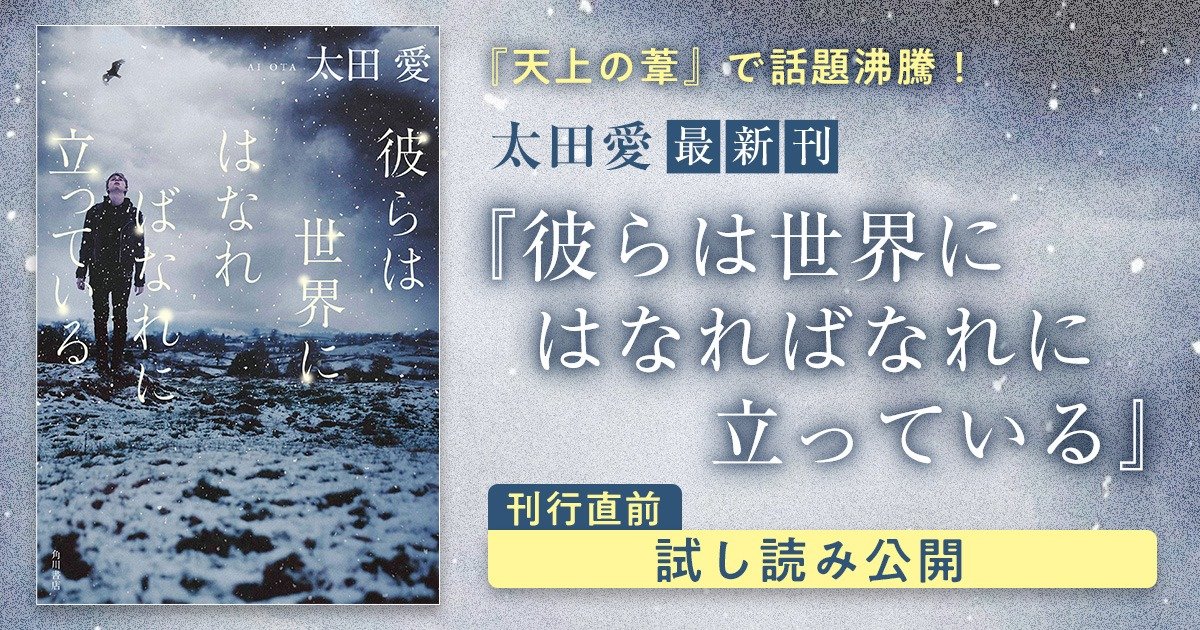
『天上の葦』『幻夏』の著者が放つ、破滅と希望のエンターテインメント! 太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』特別試し読み#1
〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれ、公然と差別される存在だ。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレの一家に浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した――。
最注目の著者による衝撃作、10月30日の刊行を前に特別試し読み!
序章
右の耳に父が言う。
──おまえの体にはこの町の人間の血が流れている。始まりの町に生まれた者の誇り高く勇敢な血だ。
見ろ、と父が北を指さす。
──あの山に眠る光る石と共に、我々の歴史は始まったのだ。
父の目には、山へ向かう大勢の鉱夫たちの姿、その
父が生まれるはるか昔、この塔の地・始まりの町の
しかし、父が指さす山に私が見ているのは、子供部屋から見えるいつもの風景だ。なだらかな
あの山を守るために、と父は私の右の耳に言う、我々の祖先はこの地に塔を築いた。そこから水平線に現れる略奪者の船影を見張り、果敢に迎え撃ち、打ち負かしたのだ。
父は誇らしげに広場の方角に
秋の終わりの庭には、父と私の長い影が伸びている。
私は塔を見上げるふりをして、扉口に
私が六歳の時、初等科に上がった年の記憶だ。この町にとって自分がどのような存在なのか、おぼろげにわかりかけてきた頃だった。
長く故郷を離れ、見知らぬ地を転々としたのち、私はようやく帰郷の機会を得た。それはいわば、大きな航海の前に水夫に与えられる短い休暇のようなものだった。生まれ育った町を目指して夜を日に継いで旅を続けるあいだ、あの晩秋の庭のひとこまが、なぜかしきりと思い出された。
帰り着いたのは明け方だった。うっすらと辺りが白み始めるなか、私は無人の広場に立って街並みを眺めた。
始まりの町はすっかり変わってしまったと聞いていたので、悲しくはあったが驚きはしなかった。そこは一言でいえば、世界中のどこにでもある町のひとつになっていた。かろうじて昔日の面影を残しているのはこの石畳の広場だけだ。
──今さら君が帰ったところで、起こってしまったことは変えられない。
きっとカイならそう言うだろう。
あるいは、マリならこう言うだろう。
──泣いて元に戻るものなんて、この世にありゃしないんだよ。
私は目印のついた一枚の敷石を見つけ出し、それを裏返す。三十センチほどの深さの穴にビスケットの円い缶がしまわれている。大きなリュックサックを背負って町を離れる前夜、私は缶をここに隠したのだ。かつて明るいブルーのティーポットが描かれていた
私は蓋を開いて中のものを取り出した。
薄緑色の小さな
それは港に客船が入った日、この広場で催されたお祭りを写したものだった。
夏の夕暮れ、広場は色とりどりの電球を連ねたイルミネーションで飾られ、塔を背にして仮設舞台が作られている。揚げ菓子や飲み物の屋台が広場を縁取るように建ち並び、ランタンを載せたいくつもの円テーブルでは町の人々や旅行客が
〈週報〉の発行人が試し撮りをしたもので、誰もカメラの方を見ていない。けれども私にとってこれは奇跡のような一枚だった。生涯けっして忘れることのできない人々が偶然にも、ひとり残らずここにおさまっているのだ。彼らは私にとって、始まりの町という星座をかたちづくる恒星だった。
写真の中の私は十三歳で、両親と共にテーブル席に座って白い粉砂糖をまぶした揚げ菓子を頰張っている。父はビールのジョッキを手に母になにか話しかけており、淡い緑色のドレスを着た母はいつもの癖で少し首を傾けるようにして父の方を見ている。
仮設舞台の正面、一番良いテーブルについているのは〈伯爵〉だ。伯爵といっても本物の貴族ではなく、遺伝的に受け継がれるらしい尊大な性格と突発的な大盤振る舞いによってそう呼ばれていた資産家で、このお祭りを思いついて気前よく資金を出したのも伯爵だった。
伯爵は町の銀行、ホテル、映画館、缶詰工場、数隻の客船などを所有しており、さらに町の外にもいくつもの会社や工場を持っていた。そういうわけで、銀行が金で破裂するのを防ぐためだろうと人々は噂していたが、伯爵には数年に一度、長い船旅に出る習慣があった。何ヶ月もかけて海の向こうの地を巡り、そのつど膨大な土産もの──宝石や絵画はもちろん、踊り狂う奇怪な彫像、座ると妙な音をたてる椅子、用途のわからない巨大な牛の鼻輪のようなものまであれこれ持ち帰り、これまた伯爵のものである博物館に並べるのを喜びとしていた。
それらの土産ものの中でも、もっとも華麗で洗練されたもののひとつと
驚いたことに、伯爵は旅の途上で出会った
伯爵たちのそば、舞台の上手脇に控えているのは、長いローブをまとった〈魔術師〉だ。みずから百歳を超えていると豪語していただけあって、
肝心の『魔術』の方はというと、消えたはずの鳩の脚が箱から突き出て
魔術師の反対側、舞台の下手近くにいるのが、〈なまけ者のマリ〉だ。マリはどこにいても目をひいた。この町でただひとり褐色の肌をもっていたからだ。
写真の中のマリは三十歳前後、片手を腰に当てて物憂げに煙草を吸っている。
マリの登場はひとつの事件として町の人々に記憶されていた。
ある冬の早朝、伯爵の料理番が魚を仕入れに出たおりに、海岸公園に倒れている子供を発見した。見たこともない褐色の肌をしたその子供は、
驚いた料理番は魚を積んだ荷馬車に乗せて高台のお屋敷に連れ帰ったのだが、忙しさに取り紛れて子供のことを忘れてしまった。後に経緯を知った町の人々からうっかりにもほどがあるという
そんなわけで数日後に執事が荷台で眠っている子供を見つけて料理番に問いただし、おそらく客船に乗ってきた誰かが町に捨てていったのだろうという結論に至った時分には船はすでにはるか海の向こうの港にあった。頭の傷からある程度予想されていたことだが、問い合わせに対し保護者だと名乗り出る者はいなかった。回復した子供は名前もなにもいっさい答えず、仕方なく執事がマリと名付けた。
当時マリは見たところ七、八歳くらいで、体つきもしっかりしていたので、ホテルの洗濯場の夫婦が下働きとして引き取った。その夫婦が腹にすえかねるほど嫌なやつらだったのか、あるいは頭に負った怪我の後遺症だったのかは定かではないが、最初の一年ほどマリは一言も口をきかなかったらしい。
夫婦が亡くなり、マリが映画館の受付に座るようになったのがパラチフスが大流行した翌年で私が初等科に上がった年だった。だから私の記憶の中にあるのは、この写真のマリともうひとつ、映画館の受付に座っているマリの姿だった。
マリの左側にひとりの老婆が写っている。全身がブレていることから、かなりの速さで舞台と逆方向に歩いているのがわかる。老婆は黄色いパラソルを手にしており、そのパラソルに対する愛着がいささか度を越していたため、町では〈パラソルの婆さん〉と呼ばれていた。
土砂降りの雨の日、パラソルの薄い布を貫通して降り注ぐ雨にずぶ
噂によると、そのパラソルはコンテッサが老婆に与えた護符のようなものらしかった。
ある夏、どこからともなく町に現れた老婆は、突然通りで妄言を
その格好の標的となっていたのが〈怪力〉だった。
呼び名のとおり、怪力は並外れた筋力をそなえていた。町に来た当初は浜で引き網漁の引き子として日雇い仕事をしていたのだが、あるとき道を歩いていて
その日、坂道の下に一台の車が停まっていた。町に二台きりの自家用車はいずれも伯爵が所有していたが、停まっていたのはそのうちの大きな方で、馬車のような箱型の車だった。運転席ではお抱え運転手がなんとかしてエンジンをかけようと奮闘していたが、車は
通りがかった男たちがすぐさま褒美めあてに車を押して動かそうとしたが、
怪力は
伯爵は自分の役に立つことがどれほどの恩恵をもたらすか、機会あるごとに人々に知らしめるのを怠らない性格だった。そこで、高齢で耳が遠くなっていた博物館の警備員を引退させ、新たな警備員として怪力を雇い、さらに家具付きの守衛室を住居として提供したのだ。
以来、怪力は青いサージの制服を着て博物館に座るようになった。口数の少ない控えめな性格だったので、来館者を黙って見ているという仕事は性に合っているようだった。もっとも普段は訪れる者もほとんどなく、やることといえば窓から迷い込んだテントウムシを捕まえて外に逃がしてやるくらいだったけれど。
写真の中の怪力もやはり警備員の制服姿で、パラソルの老婆の襲撃から首をすくめて逃げ出そうとしている。怪力と一緒にいた〈葉巻屋〉が先に気がついたのだろう、おどけた身振りでパラソルの老婆の方を指さしている。
すり切れた鳥打ち帽を
葉巻屋はよく
古い写真には、私と同じように当時まだ家の中の子供だった二人も写っている。
ひとりは赤毛のハットラ。彼女は両親にはさまれて円テーブルに座っている。あの頃、ハットラはたったひとりで広い世界に通じる扉を開けようとしていた。
もうひとりは優等生のカイ。彼は分厚い本を抱え、憂いに沈んだ顔をして、人混みの中に立っている。カイはこの町の暗い秘密を知ってしまったことで苦しんでいた。だが私はそのことに気づかなかった。
伯爵、コンテッサ、魔術師、なまけ者のマリ、パラソルの婆さん、怪力、葉巻屋、赤毛のハットラ、カイ、そして父と母。
私がいま立っている広場に、あの夕暮れ、彼らがいた。
なにをすればあのあとに起こったことを防げたのか、今でもわからない。
写真が撮られてからほんの半年ほどのあいだにいくつかの事件が起こり、このうちの五人が町からいなくなった。それらは互いに響き合うように発生した一連の出来事であり、同時に深部にひとつの根を持つ事件でもあった。けれども、そのことに私が思い至ったのはずっとあとになってからだった。
私は写真を手に、もう一度、変わり果てた町を眺めた。
もしかしたら、いなくなった五人は、私がこのようなかたちで町に帰ってくることをも予期していたのではないか。
初めてそう思った。
最初のひとりがいなくなったのはお祭りの四日後、七月最初の木曜日のことだった。
第1章 始まりの町の少年が語る羽虫の物語
クラスのみんなが帰ったあと、オト先生は僕の机の前に立つと、進路カードの提出期限を忘れていたのかね、と尋ねた。いいえ、と僕は答えた。期限が七月の最初の木曜日、つまり今日だということは覚えていた。明日から夏期休暇が始まるのだから忘れようがない。
僕は初等科の七年生で、進学を希望すれば九月から五年制の中等科へ進むことになる。中等科は校舎の西翼にあるので、実際にはカードの進学の項に印をつけて先生に渡し、教室を移動するだけだ。だが中等科に行ってもクラスの顔ぶれがほとんど変わらないことを考えると、心躍るような五年間が待っているとは到底思えなかったし、町には僕より年下でも働いている子供が大勢いた。そういう子供たちは品物の名前が読めて日当や釣り銭をごまかされずにやっていけるようになれば、初等科の途中であっさり学校に来なくなっていた。つまり僕も進学せずに仕事に就くという選択肢がないわけではない。
僕の考えを見透かすように先生が言った。
「ハットラは中等科で頑張っているよ」
先生の言いたいことはわかった。ハットラが立派にやっているのだから、君にだってできるはずだ、という
たしかにハットラと僕のあいだにはひとつだけ共通点があるが、その一点をのぞけば僕たちはまるで違っていた。まずハットラは女の子で、僕より三学年も上だ。さらに素晴らしい俊足で、秋に行われる中央府の大会に町の代表としてただひとり選抜されている。たまに町の通りで見かけることがあったが、ハットラはいつも脇目も振らずに急ぎ足で歩いていた。固く唇を結び、じっと前方を見つめた目は、トラックのスタートラインに立つ時の張りつめた表情と少しも変わらない。赤い髪を短く切りそろえたハットラは、どこまでも飛び続ける矢のように孤独で真剣だった。
それにひきかえ僕は、絶えず辺りの様子を
オト先生は黙ってうつむいている僕に小さくため息をついた。それから、七月の終わりまでに進路を決めなさいと言った。僕はお辞儀をし、帆布の
すでに正午を過ぎており、古い石造りの校舎は静まりかえっていた。昨晩、一睡もしていないせいだろう、体がだるく
オト先生の言った七月の終わりが、百年も先のように思えた。その頃自分自身がどんなふうになっているのか見当もつかなかった。
僕にとって今日が一日目なのだ。
大きな変化のあとの最初の一日。町の人間はまだ誰も知らない。僕は少しずつ新しい秩序をあみだし、それに自分を慣らしていかなければならない。
まず土曜日までのことを考えろ。僕は自分に言い聞かせた。父さんが帰ってくるのは土曜日だ。それまでになにをしておけばいいのか。
どのように行動すれば人々に不審を抱かれずにすむのか、警察にはどのタイミングで知らせるべきなのか、スベン
だが僕の思考はまるでコマのように同じ場所で無意味に高速回転するばかりで、ひとつの解決策も浮かんでこなかった。
校庭に続く玄関扉を開けると、いきなり人影が近づいてきた。
「君は
僕は無視して歩き出した。
「どうして
カイは図書室の分厚い本を抱えて追ってきた。
「うっかりして書き忘れたんだ」
「いや、わざとだ。零点を取るためにわざと名前を書かなかったんだ。なんでそんなことをしたのか言ってみろ」
カイは僕が意図的に零点を取った理由を勝手に決め込んで憤慨しているのだ。君の考えはまったくの見当違いだとはっきりわからせない限り、どこまでもついてきそうだった。
僕は立ち止まってカイに向き直った。
「僕が名前を書かなかったのは、カイに一番を譲るためじゃない。僕にはそんなことをするいわれはない」
たとえ君が判事の息子であっても。僕は胸の中でそう付け加えた。父親が町の有力者であるという事実が、カイに誤った思い込みを抱かせたのだろうから。
カイの表情にはなんの変化も現れなかった。納得したかどうか定かではなかったけれど、僕はかまわず足早に校門を出た。友達というには僕たちはもうあまりに遠く、互いに理解できない存在になっていた。
カイと話すようになったのは五年生の頃、学校ではなく映画館のロビーでだった。町で一軒の映画館に新しいフィルムが来るのは三ヶ月に一度、長い時は半年に一度なのでいきおい同じ映画を繰り返し観ることになるのだが、受付でスタンプカードに判を押してもらえば二度目は半額、三度目以降は無料になるので、揚げ菓子やレモン水を我慢すれば子供の小遣いでなんとかなる。それでも初等科の生徒で足繁く映画館に通っていたのはカイと僕だけだったから、ロビーで顔を合わせるうち自然と言葉を交わすようになった。
帰りは二人で自転車を押して海岸公園を歩きながらいろんな話をした。映画の話だけでなく、いつもニコリともせずに判を押す受付のマリのことや、死を超える恐怖と噂される青年団の入会儀式に関する推論、明け方に町外れを通る水色の長距離バスはどこから来てどこへ行くのか。話題は尽きず、僕たちはしばしば海岸通りの街灯が
ところが冬休みが終わった頃からカイは突然、映画館に来なくなった。教室でも不機嫌に押し黙っていることが多くなり、ついに新年の祝賀講話で来賓が
カイは
もし以前のままのカイだったら、僕は昨晩自分がしたことを打ち明けただろうか。
そんな思いがふと頭をよぎった。
そうであれば、そうできれば、どんなにいいだろう。
その時、急に後ろから腕を
「僕に一番を譲るのでなければ、ほかにどんな理由がある」
失望と怒りで、昨晩から張りつめていた気持ちが破裂しそうになるのを僕は懸命に
なにか言おうとするカイを、僕は両手で力いっぱい突き飛ばした。カイはすごい勢いで後ろへふっ飛んでひっくり返った。カイの運動靴の裏の白さが目に残り、喉がヒュッと音をたてて息を通した。僕はあとも見ずに駆け出した。
道のところどころで消え残った水たまりが光を乱反射させていた。
斜がけの鞄が跳ねて責めるように背中を打った。
フヨウの生い茂る角を曲がると、うちの庭のフェンスが見える。そこまで来て僕は眼前の光景に棒立ちになった。ペンキの
家に警察が来ている。
鼓動が急激に速まり、なにも考えられぬまま家へ近づくと、朝、僕が
父さんが戻っているのだ。土曜日までは帰ってこないはずなのに。警察を呼んだのは父さんだ。
全身がすっと冷たくなった。
父さんは、地下室のあの大きな衣装箱を開けてしまったのだろうか。だとすれば僕はどうすればいいのか。
家の中から父さんの苛立たしげな声が聞こえた。
「だから買い物なんかじゃないんだよ、マーケット通りにはいなかったんだから。昼飯にはトゥーレが戻るのに、アレンカが家を留守にするはずがないんだ。きっとなにかあったんだよ」
父さんは、母さんがどこかで事故かなにかに遭ったのではないかと考えているのだ。つまり、まだ地下室の衣装箱を開けてはいない。
半信半疑の顔で聞いていたベルさんが扉口の僕を認め、制帽をちょっとあげて、やあ、と微笑んだ。探るような表情を見られたのではないかと頰がこわばるのを感じた。だがそれどころではない様子の父さんがやにわに僕の両肩を摑んだ。
「トゥーレ、おまえ今朝、学校に行く前に母さんを見たか」
考える時間を少しでも稼ぐために僕は、なにかあったの、と尋ねた。父さんは取り乱している自分に気づいたように僕から手を離し、ソファテーブルの上の煙草を取りながら言った。
「母さんがどこにもいないんだよ」
そう聞いて驚いた表情を作るだけの落ち着きは取り戻していた。
それから僕は今日、二度目の噓をついた。
「僕、すごく寝坊したんで大急ぎで家を出たから」
「母さんが家にいたかどうかわからないのか」
僕は黙って
父さんは遠くのいろいろな町にトラックで缶詰を運んでいて、一ヶ月の半分くらいは家にいないのだが、帰ってくる日を母さんが間違えたことは一度もない。日付を
父さんは、積み荷に不良品があるという無線が入って引き返してきたのだと答えたが、力任せに擦ったマッチの軸が折れ、くわえていた煙草を床に投げ捨てた。
次に誰が話しかけても父さんは怒鳴る。僕は慎重に沈黙を守った。
ベルさんが、なにか急用ができたのかもしれないし、となだめるのを父さんは予想以上に激しい勢いで怒鳴りつけた。
「あんただって修繕屋の店が火事で燃えたの覚えてるだろ」
僕は驚いて思わず父さんの顔を見た。父さんがあの火事のことを気にしていたなんて、これまで考えてみたこともなかったからだ。
父さんはひどく深刻な目でベルさんを見据えていた。ベルさんの顔から微笑が消え、困惑したように目をそらせた。
「あれは、ただの煙草の火の不始末じゃないか」
三月の終わり頃、商店街の端に新しくできた修繕屋の店で火事があり、ひどいやけどを負った修繕屋のおじいさんは今も病院に入っている。
そして町では、昔から火事は災厄の前触れといわれていた。
パラチフスが
修繕屋で火事が出た時、僕は夜の
だが僕はずっと、父さんはそんな迷信じみた恐れや不安などとは無縁な人だと思っていた。というのも、父さんは大道芸の蛇使いが客を怖がらせようとして差し出した大蛇を平気で摑んで肩に乗せてみせるような豪胆な人で、驚嘆した見物客が蛇使いにではなく父さんに投げ銭をするあいだも、暴れる蛇の首をねじ上げたままカメラに向かって笑顔でポーズを決め、なおかつ、雰囲気に乗じて浮き浮きと投げ銭を拾っていた僕のうしろ頭をはたくだけの冷静さをも兼ね備えていたからだ。僕が八歳の頃、町に鉄道が走っていた最後の年の出来事だったが、週報に『恐れ知らずの男』というタイトルで掲載された父さんの写真は
けれども目の前で不安げに押し黙った父さんは、ひどく疲れて一度に老け込んでしまったようだった。
僕はいつだったか魔術師から聞いた話を思い出した。魔術師によると、
考えてみれば、父さんもその種の仕事に従事している者のひとりだった。
いくつもの山を越えて遠い地へ行く運転手には、積み荷を狙う盗賊に襲われる危険が常にある。何年か前の冬に運転手たちが出発前に集まる詰め所に連れて行ってもらったのだが、入り口のコート掛けの脇に先代の伯爵が仕留めたという大きな雄鹿の
僕は斜がけにしていた学校の鞄をそっと床に置いた。父さんが投げ捨てた煙草がソファの脇に転がっていた。
母さんの不在という説明不能の事態を、父さんが修繕屋の火事と結びつけて考えるのは自然なことなのかもしれない。
だが、火事と母さんは無関係なのだと僕は知っている。
母さんがあんなことをしたのは、僕が追い込んだせいなのだ。だから昨晩、僕は決めたのだ。せめて最後は母さんの思ったとおりにと。
なにがあっても、父さんにあの大きな衣装箱の中を見せてはいけない。
積み荷の不良で戻ってきたのなら、父さんは数日のうちに荷を積み直して出発しなければならないはずだ。それまで、僕は父さんと同じように振る舞う。母さんの不在に戸惑い、混乱し、町のあちらこちらを捜して回る。父さんが決して地下室に目を向けないように。
「僕、マーケット通りの方を捜してみるよ」
返事を待たずに僕は玄関を飛び出し、納屋から自転車を引っ張り出した。
(つづく)
▼太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000901/(KADOKAWAオフィシャルページ)