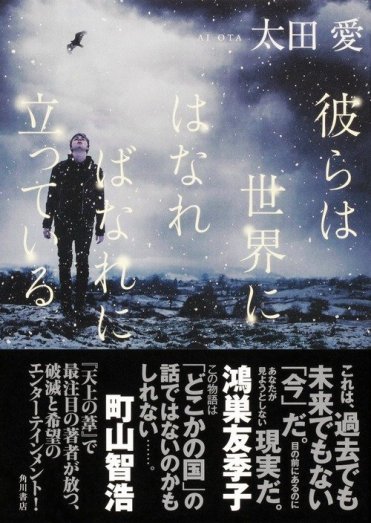彼らは世界にはなればなれに立っている
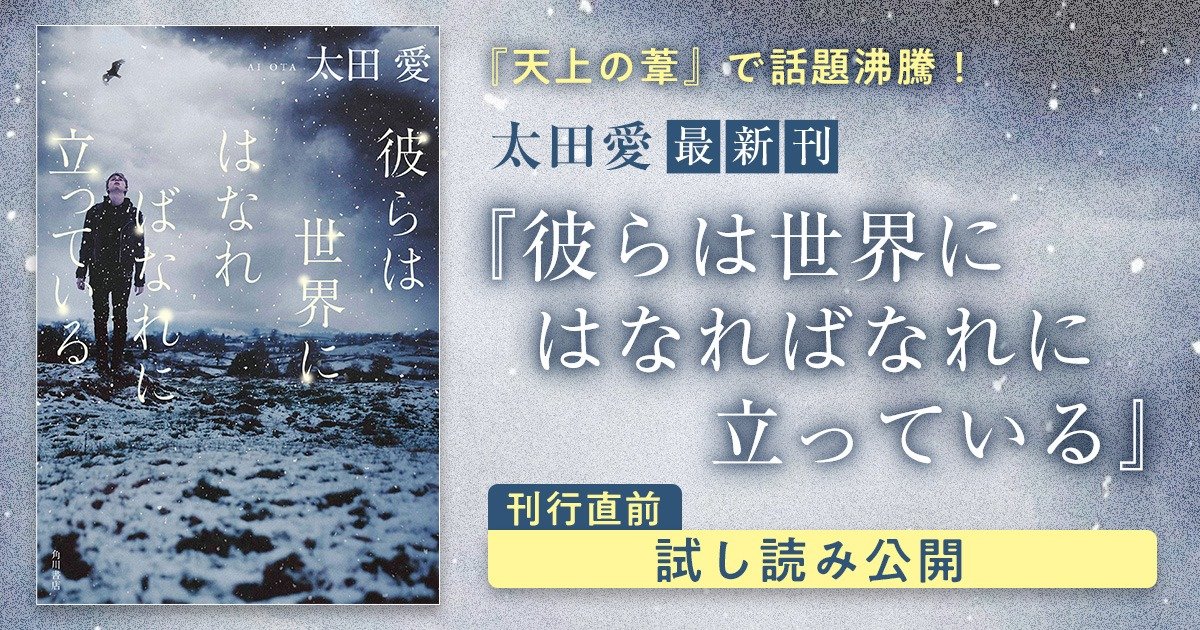
「これは『どこかの国』の話ではないのかもしれない……」町山智浩氏推薦! 太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』特別試し読み#2
〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれ、公然と差別される存在だ。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレの一家に浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した――。
最注目の著者による衝撃作、10月30日の刊行を前に特別試し読み!
>>前話を読む
†
なだらかな下り坂の先、マーケット通りへと曲がる角に先代の伯爵の胸像がある。いかめしい顔のどこかしらに常に鳥の
僕が自転車を停めると、葉巻屋は時刻でも訊くように、お母さん見つかったかい、と尋ねた。
葉巻屋が母さんの件を知っているのには驚かなかった。父さんがベルさんを呼ぶ前にマーケット通りを捜したようだったので、その時にきっと葉巻屋に尋ねているだろうと思っていた。葉巻屋は誰もが認める町一番の情報通だからだ。
「心配しなくても晩飯の支度をする頃には戻ってくるさ」
葉巻屋は僕を元気づけるように
「マーケット通りなら開店休業だぜ。みんな不機嫌の虫にとり
振り返った僕は期待通りの
「あれは客船のせいだ」
葉巻屋が港の方に
今朝まで大きな客船が停まっていた桟橋は空っぽで、遠く水平線が見通せた。
四日前の日曜日、あの港に大きな客船が入港した。歓迎の花火が打ち上げられ、広場ではお祭りが催され、町中が浮き立つようだった。客船が町を訪れるのは実に二十年ぶりのことだった。
葉巻屋の話では、客船のおかげでマーケット通りは連日大勢の客でごった返したらしい。そして店に並べられている品物ならなんでも、それこそ缶詰工場で廃棄された魚の骨を揚げたものから、馬鹿馬鹿しいほどゼロが連なった値札のために長らく鑑賞用となっていた
当然、僕はそんなに儲かったのにどうして不機嫌なのかと尋ねた。
葉巻屋は、オト先生が頭の回転の遅い生徒から愚かな質問を受けた時のように一瞬、宙を見上げた。それから嚙んで含めるように言った。
「いいか、客船は次にいつ来るかわからないんだぞ。来年かもしれないし、また二十年先かもしれない。ひょっとして死ぬまで来ないってこともおおいにありえる。仮に四日間で四年分儲かったとしても、末代まで遊んで暮らせるわけじゃなし。とすれば、この始まりの町でなにをして楽しむんだ」
鉄道が走っていた頃はサーカスや劇団の巡業が来ていたが廃線後はそれもなくなり、港の近くにあった劇場も
葉巻屋は町の人々を
「ここじゃあ休みを取って旅行に出る習慣もないし」
そう言ってから高台のお屋敷の方を指さして付け加えた。
「もちろん、伯爵は例外だけどな」
なににおいても伯爵が例外であることは町の人間すべてが認めるところだった。
「つまりだ、マーケット通りのめんめんは、二十年ぶりに肉にありついた犬みたいな気分だってことだ」
よくわからなかったが、葉巻屋が宙を見るのが嫌だったので黙って続きを待った。
「想像してみろよ、二十年ぶりに脳天で歓喜の鐘が鳴り響くような
葉巻屋は吸い殻を集めた革のショルダーバッグと
「ま、俺の勝手な見立てだけどな」
それから、じゃあな、と言う代わりに鳥打ち帽の縁に軽く手をやると、塔の広場の方へと歩み去った。
葉巻屋の話には盛大に
緩い上り坂の両側に古い商店の建ち並ぶ通りは客の姿もなく、葉巻屋の言っていたとおりショーウインドウが空っぽになっている店が目立った。いくつかは日よけも下ろされておらず、わずかに売れ残った桃や
僕は母さんを捜すふりをしながら店を一軒一軒
レジスター脇に座った店主やその妻は、誰も僕に声をかけなかった。
普段は整然と鉢植えの並んでいる花屋の店先に氷菓子の紙コップが散乱していた。真っ赤な
今日はみんなくたびれているせいだ。こんなのはいっときのことで、すぐに元どおりになる。葉巻屋も、まずい飯でも食わなきゃ死んじまうと言っていた。だが、葉巻屋の見立てが当たっているとしたら、腹の底にたまっていく
落ち着かない気持ちで自転車を押しながら、僕はなじみ深い夕暮れ時の通りを思い出そうとした。小さい頃はよく母さんと一緒に夕飯の買い物をしに来た。魚屋や青物屋の威勢のいい声が飛び交うなか、母さんはセロ編みの買い
果物や野菜を買う時、たいていの人は手に取って熟れ具合や傷の有無を確かめてから購入を決めていたが、母さんは目だけでじっくりと吟味し、必要なものを、それとあれ、というふうに指さして店主に取らせ、自分では決して触れようとしなかったのだ。そのせいでごくたまに食卓に虫食いのマッシュルームなどが出ることがあり、そのたびに父さんがちゃんと確かめて買わないとだめじゃないか、と不平を述べたが、母さんは次からそうするわ、と微笑むだけで買い物の仕方を変えることはなかった。その行為はまるで病原菌に感染するのを恐れるかのように徹底していた。
不意に
マーケット通りの北の端、火事で焼けた修繕屋の店まで来ていた。
屋根も壁もすべて焼け落ち、地面を覆ったオレンジ色のシートのあいだから黒焦げになった柱が突き出している。
このシートは週報で客船が来ると報じられたあとで掛けられたものだ。それまでは
白くて太い
おじいさんは僕が生まれるずっと以前から修理道具を載せた荷車を引いて町の家々を回っていた。とても器用な人で、パンクした自転車はもちろんのこと、閉まりの悪くなった扉から切れにくくなった鋏や縁の欠けた皿まで、その手にかかればたいていのものは息を吹き返した。だが年を取って荷車を引くのがきつくなったらしく、堅パン屋のおばあさんが店じまいするのを機にこの店舗を買い受けた。火事が起きたのは、みずから内装を整えて開店してから一週間と経たない深夜だった。おじいさんはいつも革袋に吸い殻をためて葉巻屋に持ち込んでいたので、その消え残りが出火の原因となったようだった。
母さんも凶事の前触れではないかと不安を感じていたのだろう、火事のあと
もう三ヶ月以上経っているのに、辺りには家財と建物の燃えた臭いが強く残っていた。
僕は自転車にまたがってペダルを踏み込んだ。全身がひりひりと熱く、少しだけどこかで休みたかった。
この近くで安心できる静かな場所はひとつだけだった。
†
大きな
展示品はすべて伯爵が船旅の記念に外の地から持ち帰った土産ものなので、町の人間はここを陰で『伯爵家の物置』と呼んでいた。
警備員の怪力が中央玄関の奥の椅子に座っている。
僕はいつもするように軽く片手をあげて怪力に近づいていった。平素なら怪力は片手をあげて
怪力は眠っていた。
頰に血の気がなく、まるで精も根も尽き果てたというようなひどく疲れた顔をしていた。たぶん鏡を見ずに大急ぎで制服だけ着替えたのだろう、髪の毛や首に乾いた泥がこびりついており、革靴はぬかるみで飛び跳ねたかのように泥だらけだった。
昨晩は真夜中頃から
なにか異様な感じがして僕は声をかけるのを
すると怪力が喉の奥で小さくうめくような声をあげ、ポカリと目を開けた。一瞬、自分がどこにいるのかわからないように怪力は辺りを見回した。それから僕に気づき、さらに僕の視線を追って自分の泥だらけの革靴に目をやった。怪力はひどく動転した様子で口もきけず、気の毒なほどまごついていた。
僕は見ていられず助け船を出した。
「浜へ行ったの?」
「ああ、ああ、そうなんだ」
怪力はにわかに笑顔になって頷いた。
浜の砂なら潮の匂いがするし、乾けばサラサラと落ちる。怪力の靴についているのは砂ではなく泥だとわかっていた。だが今の僕がそうであるように、怪力にも人に知られたくないことがあっても不思議ではない。僕は怪力の答えに納得したふりをして話題を変えた。
「母さんを捜してるんだ」
葉巻屋から聞いていたのだろう、怪力は申し訳なさそうに首を横に振った。ここには来ていない、という意味だ。
「少し休んでいっていい?」
怪力は何度も頷いた。僕は玄関ホールの一隅にあるお気に入りの展示品へ向かった。
展示パネルのタイトルに『空中庭園の
僕は石鉢に横たわって天井を見上げた。陶器のようになめらかでひんやりとした生地が心地よかった。少し体の重心を動かすと石鉢はハンモックのように優しく揺れ始める。
目を閉じるとまるで待っていたように、居間の隅でミシンを踏む母さんの姿が浮かんだ。
†
母さんは、町でただひとつの婦人服店であるネラさんの店から注文をもらってドレスを縫う仕事をしていた。
結婚式やなにかのパーティーに着る特別な晴れ着を作るお客は、割増料金を払ってお針子を指名することができるのだが、僕がものごころついて以来、母さんへの指名が途絶えたことは一度もなかった。仕立ての腕もさることながら、顧客たちがなにより気に入っていたのは、母さんがドレスに施す花々の刺繡だった。それらはどこから見ても生きた花としか思えないできばえで、胸元をラベンダーやジギタリスの刺繡で飾った女たちはドレスの花が強い陽射しで
だが、それだけの労力をかけても、手にする縫い賃は指名のないお針子よりもはるかに少なかった。僕がそのことを知ったのは初等科に上がる少し前、ネラさんの店にあるお針子たちの食堂兼休憩室でだった。
母さんがドレスに使う生地やレースをネラさんからもらってくるまで、僕はたいていそこで待っていることになっていたのだが、昼食時と三時の休憩の時以外は無人のはずの部屋に、その日は階上の裁縫場から三人の年かさのお針子たちがやってきた。暑い日で、僕が椅子ではなく冷たい床に座っていたので気づかなかったのだろう、白い上っ張りを着た女たちは煙草を吸いながら目の疲れと肩こりの話から、顧客がお針子を指名する際の割増金のこと、母さんと自分たちの縫い賃の金額などをべらべらと喋り、ネラさんは母さんにまだ払い過ぎているくらいだという点でおおいに意気投合したあげく、目の疲れのせいなのかどうかわからないが、まったく僕に気づくことなく出ていった。
当時の僕は町の一週間の出来事を報じる週報をすでにひとりで読めるようになっていたし簡単な計算もできたから、女たちの話はしっかりと理解できた。絶えず指名を受けて評判のドレスを作っているにもかかわらず、なぜ母さんの報酬は格段に低いのか。いくら考えてもわからなかった。
夕方、僕は直接、母さんに理由を訊いてみた。夕食の支度をしていた母さんはセージを刻む手をとめることなくこう答えた。
お針子さんたちはみんな決まった時間にネラさんの店の裁縫場に出勤して働いているけれど、母さんは家にいて好きな時間に仕事をさせてもらっているから、そのぶん安くなって当たり前なのよ。
まるで自明のことを説明するかのような母さんの口調に、なるほどそういうことか、と僕の疑問は氷解した。
だがあとから考えれば、雇い主のネラさんは母さんを指名した顧客から割増料金をもらっていたから、家で仕事をすることで母さんの報酬をびっくりするほど安くしなければならないほどの不利益を被っているはずがなかった。セージの匂いのする台所で母さんがやすやすと僕を納得させた説明は、実はまったくのでたらめだったのだ。
母さんは刺繡の腕前と同じように、噓をつくのも巧みだった。
──お母さんは、どこにいても君のことを思っているよ。
身近くで怪力の声がした。
どうしてそんなことを言うのだろう。僕がもう二度と母さんに会えないと知っているかのように。
怪力に尋ねようとしたけれど声が出なかった。
どうやら僕は半分眠ってしまっているらしく、全身に力を込めても口を開くことはおろか
はたして僕を救ったのは自動車の甲高いブレーキ音だった。
石鉢の中で僕は声をあげて目を覚ました。見ると怪力は元どおり椅子に座ったまま通りの方に顔を向けている。
さっきのは夢だったのだろうか。だが怪力の声も抑揚も生々しく耳に残っている。
激しい走行音がして僕は通りに目をやった。
運転席から降り立ったのは、蜂蜜色に輝く豊かな髪を結い上げたコンテッサだった。
いつどこに現れても、彼女の上にだけ天から光が降り注ぐように人々の視線をひきつける。コンテッサを評してそう言ったのは魔術師だったが、まさにそのとおりだと思った。伯爵は逆にそれが心配なのだろう、護衛と称して下僕のドニーノに、養女であり愛人であるコンテッサを常に見張らせている。実際に今もコンバーチブルの助手席に座ったドニーノが、回転扉に向かうコンテッサの背中をじっと睨んでいた。
その時になってコンテッサがここに来るつもりなのだとわかり、僕は急いで石鉢から出ようとした。ところが焦って鎖に足を引っかけてしまい、外に転がり出たものの四角い石鉢はまるで腹を立てた振り子のように大きく揺れ始めた。
うなりをあげて近づいては遠ざかるそれはもはや荒ぶる巨大な凶器で、駆けつけた怪力と共になんとかしがみついたが、コンテッサの軽やかなヒールの音が館内に響き渡った時には僕たちはまだ石鉢と一緒に揺れていた。
コンテッサはドライブ用の白いレースの手袋を外しながら近づいてきた。そして僕たちがどうにか石鉢を落ち着かせ、よろめきながら立ち上がるのを見てわずかに微笑んだ。
「表にトゥーレの自転車があったから」
その言葉は、コンテッサが僕の自転車を認めて車のブレーキを踏み、バックして戻ってきたことを意味していた。僕はわけがわからなかった。
コンテッサは話を続けかけて、怪力の泥だらけの革靴に目を留めた。それからどういうわけかハンドバッグを開けてミント味の板ガムを取り出すと、どうぞ、と僕と怪力に勧めた。面食らいながらも僕たちは礼を言って受け取った。その拍子に怪力の大きな
コンテッサはなぜか納得したようにガムをハンドバッグにしまうと、僕に目を転じて言った。
「お父さんが青年団を呼んで沼の辺りを捜索するそうよ。あなたの家に集まって出発するらしいわ」
家に戻らなければ。
頭に浮かんだのはそれだけだった。
†
フヨウの咲く茂みの角を曲がると、前庭にすでに七、八人の青年団の団員がいるのが見えた。沼の捜索用のゴム長靴や草刈り鎌を地面に置いて、キョウチクトウの木陰で煙草を吸っている。
鍵屋の弟子のサロが、フェンス脇の郵便受けを狙って小石を投げつけていた。山型パンの形をした郵便受けは木の支柱がもともと少し斜めになっていたのだが、小石が支柱に命中するたびにさらにグラリと傾いた。団員たちの注目を集め、サロはふざけたフォームで、だが的を外すことなく石を投げ続ける。
お祭りの日以来おさえつけていた憤りとも嫌悪ともつかない感情が真っ黒い夕立雲のように膨れ上がり、僕はすぐさまUターンしたい衝動にかられた。
だがコンテッサと怪力は僕が母さんの捜索に加わるために急いで家に向かったのを知っている。もしあとになって僕が戻らなかったとわかったら二人は妙に思うに違いない。それが疑いの端緒にならないとも限らない。今はどんな危険も冒せない。
フェンスに自転車を立てかけると、団員たちが一斉にこちらを見た。僕はお辞儀をして玄関に向かおうとした。その時サロが
「左目」
サロは許可を求めるように団長のウルネイを見た。
とめてくれると思った。子供の目を潰すような卑劣な暴力を青年団の団長が許すはずがない。
ウルネイは、大丈夫だ、というふうに僕に微笑んだ。若くして地位のある大人に特有の大胆で清潔な微笑だった。それからサロを振り返ると、同じ顔で黙って頷いた。
自分の見ている光景が信じられなかった。
サロが小石を握り直し、
開いた玄関扉の向こうに父さんとスベン叔父さんの背中が見えた。二人は奥の台所で地図を広げて話し合っている。
サロの腕が弧を描いて振り下ろされる瞬間、僕は鋭い痛みを予感して反射的に両手で顔を覆ってしゃがみこんだ。
鈍い音がした。続いてなにかが体の脇に倒れ込んできた。恐怖で脚が動かず、僕はしりもちをついた。団員たちの失笑が湧くなか、僕は郵便受けが倒れたのだと気づいた。
動物の
「たかが〈羽虫〉のために」
僕はようやく理解して
「どうかしたのか」
玄関先からスベン叔父さんの声がした。
「トゥーレが郵便受けにぶつかって」と、サロが答えた。
僕は立ち上がるだけで精一杯だった。
学校や帰り道で、級友たちに羽虫の子と呼ばれて小突き回される。それが僕の日常だった。しかし、きちんとした立派な大人から直接こんな仕打ちを受けたのは生まれて初めてだった。その事実で頭が
父さんが地図を折り畳みながら玄関ポーチに出てくるのが見えた。
今朝、ひとりであの玄関に鍵をかけて家を出る時、僕は今日が最初の一日なのだと自分に言い聞かせた。母さんのいない日常の一日目だと。
もしかしたら、母さんがいなくなったことでこの世界はおかしくなってしまったのではないか。馬鹿げた考えだとわかっていたが、そう思うと陰鬱な顔をしたマーケット通りの人々も、泥だらけの怪力も、博物館に現れたコンテッサも、今日はなにもかも尋常でない気がした。
「暑いなか悪いな」
父さんが青年団に声をかけた。
「うちのはたぶん染料の草を探しに行って、怪我をしたかなにかで動けなくなってるんだと思うんだ。あのへんにはサソリも多いしな」
すでに長靴に履き替えたウルネイは「なに、きっとすぐに見つかりますよ」と笑顔で請け合うと先に立って歩き出した。
僕は父さんに駆け寄った。
「僕も行く」
僕が父さんのそばにいなければと思った。ウルネイたちは母さんを捜す気などないのだ。
「おまえの心配をしている余裕はないんだ」
父さんは気ぜわしそうに僕を押しのけて青年団に続いた。
スベン叔父さんが軍手をした手で励ますように僕の背中を叩いた。
「トゥーレは家で勉強してろ、九月からは中等科だろ」
誰もいない家はいつもより光が多いように感じられた。
台所のテーブルに父さんとスベン叔父さんがコーヒーを飲んだカップが残されていた。汚れたままのカップが母さんの不在を強く思わせた。僕はそれを丁寧に洗って片付けた。
それから喉が渇いていたのを思い出して蛇口から直接、水を飲んだ。
なにかに体に触れていてほしくて、そのまま僕は流れる水に頭を突っ込んだ。髪の毛や耳や頰を柔らかい水が撫でていった。
僕の母さんは羽虫だった。羽虫は〈遠くから来て町に住みつき、害をなす者〉という意味を込めて、帰るべき故郷を持たない流民を指す
羽虫は、夜明け前に町外れの道路を通る水色の長距離バスでやってくる。そのためバス停付近の荒れ地には羽虫の住むみすぼらしい小屋が建ち並んでいる。彼らは公的には居留民として登録されていて、大人は漁の引き子などの日雇い労働や缶詰工場の工員、子供は農場やホテルの下働きとして働いていた。
この家に住んで晴れ着を縫っていた母さんは、もちろん特殊な羽虫だった。子供の頃に故郷を失って羽虫になり、遠い町の運転手あいての終夜食堂で働いていた時に父さんが見初めたらしい。やがて二人は恋に落ち、母さんは父さんのトラックの助手席に乗ってこの町にやってきたのだ。膝の上に
父さんの妻となった母さんは表向きは町の人間であり、居留民ではなかった。けれども、縫い賃がひどく安いのは母さんの出自のせいだし、母さんが買い物の時に食材に手を触れないのも同じ理由からだった。羽虫の触れた果物や野菜は町の人が嫌がって買わないのだ。安価で手に入る刺繡入りの晴れ着は喜ぶにもかかわらず。
母さんの故郷は洪水でなくなったと聞いているが、その町の名前を僕は知らない。だが僕の半分が町の人間であり、もう半分が羽虫であるのは事実だった。僕の左の耳は羽虫の耳だ。だからどんな汚い言葉を聞かせてもかまわないのだ。
父さんは〈塔の地・始まりの町〉の人間であることを誇りに思っている。塔の地の繁栄の礎を築いた始祖を崇拝し、その勇猛果敢な血脈に
夜遅くになって父さんは帰ってきた。階下から家具にぶつかりながら歩く足音が聞こえていたが、やがて静かになった。
倉庫街にある町で一軒きりの酒場〈踊る雄牛〉に青年団を連れていき、労をねぎらっていたのだろう。明日また自分で捜してみるから気にしなくていいと、なんでもないことのように笑って若者たちのグラスを酒で満たして回った。父さんはそういう人だ。
僕はしばらく寝つかれずにいたが、父さんが居間から上がってくることはなかった。
†
朝、着替えて階下に行くと、父さんが居間のソファで眠っていた。テーブルに落花生の殻が散らばり、床に空っぽになった酒瓶が転がっていた。
僕は戸棚から麻の夏掛けを出して父さんにかけて二人分の簡単な朝食を準備した。母さんのようにはいかないけれど、卵を
ひとりで食べ終わると庭に出た。母さんはいつも如雨露を使って花に水をやっていたけれど、僕はホースの口を指で絞って空に向かって水を放った。丹精された花々の上に細かな雨のように水が降り注ぎ、足下から夕立の匂いが立ちのぼる。キラキラと光る水の粒に斜めに
あれは
僕は誰とも会いたくなくて自転車で港の倉庫街の辺りをぶらついていた。幅広の道は人っ子ひとりおらず、ときおり風に乗ってマーケット通りの方から客船の人々の賑わいが聞こえてくるくらいで、〈踊る雄牛〉も扉を閉めてまだぐっすりと眠っていた。
僕はうわの空で自転車を走らせていたので、建物から人が出てきた時、すぐには母さんだとわからなかった。その人がこちらを見てハッと身を固くして立ち止まったせいでそうと気づいたのだ。母さんは初めて見るようなこわばった顔で立ち尽くしていた。
母さんが出てきたのは、〈三階建て〉と呼ばれているレンガ造りの建物で、かつて〈日報〉を発行していた新聞社だった。僕が学校に通い始める前に閉鎖になったのだが、当時、父さんが新聞には中央府のラジオ放送と同じことしか書かれていないから紙の無駄だと言っていたのを覚えている。
社屋の一階と二階は扉も窓も板で塞がれていたが、扉脇にある内階段の入り口は通りに向かって長方形の暗い口を開けていた。母さんはそこから出てきたのだ。
階段は三階の張り出し窓のある小部屋に通じている。そこは昔、記者と呼ばれた人々が交替で泊まっていた部屋で、今ではひとりの羽虫が住んでいた。町でただひとり濃い褐色の肌を持つ羽虫、映画館の受付に座っているなまけ者のマリだ。
毎週水曜は映画館の休館日だ。母さんがマリを訪ねていたのだと知って僕は正直、驚いていた。二人が親しくしているなんて思ってもみなかったのだ。母さんには映画を観る習慣はないし、家でマリの話をしたこともなかった。僕が覚えている限り、母さんとマリが言葉を交わしたのは一度きりだった。
それは僕の苦い記憶に繫がっていた。
初等科の一年生の時、父さんが遠くの町のデパートで
翌日の午後、僕はサファイア号を抱えて海岸公園の噴水池に向かった。博物館通りから直接海岸公園に抜ける路地は、
僕に目をつけたのは羽虫ではなく、中等科の制服を着た町の子供だった。彼らは物乞いから喜捨の入った空き缶を取り上げ、公園の方へ投げ捨てることで路地から追い出していたが、僕の手のサファイア号を認めると獲物を見つけたようにいかにも
僕はあとにも先にもないほど無我夢中で抵抗した。彼らも予期していなかったらしく、僕が振り回した
彼らはなにか不平を言いながら去っていったが、耳に入らなかった。マストを握りしめた僕の前に船の破片が散らばっていた。悲しくて身の置きどころがなく、僕は生まれて初めて声をあげて泣いた。息の続く限りまさにサイレンのように泣いた。
きっとやかましくて我慢できなくなったのだろう、路地に面した扉が開いて誰か出てきた。
それが僕がマリを見た最初だった。
噂に聞いていたとおりマリは濃い褐色の肌をしていた。そしてやはり噂どおり不機嫌な顔をしていた。大きな胸とお尻を持っていたが腰はおそろしく細く、その奇妙なバランスがなんとなくアシナガ蜂を思わせた。
マリは僕のシャツに残された運動靴の跡と壊れたヨットの玩具を一瞥してなにが起こったか察したらしく、やれやれといった様子でため息をついた。それからほんの少しだけ表情を和らげて僕を見つめた。
「馬鹿だね。泣いて元に戻るものなんて、この世にありゃしないんだよ」
そう言うとマリは壁際のブリキのゴミ箱の
サファイア号が跡形もなく消え去ったことであらためて喪失が実感され、再燃した悲しみでさらに
マリは僕にかまわずシガレットケースから葉巻屋の煙草を取り出して一服し始めた。片手を腰に当て顎を上げ、深々と吸い込んだ煙を斜め上に吐き出す。釣り
一服していてもちっとも
翌週、僕は母さんと一緒に映画館へ行くことになった。それまで僕は一度も映画を観たことがなく、通りから大きな赤い扉を眺めるだけだったので、その日は朝からはやばやとよそゆきを着て待っていた。ところが、行きがけに母さんが仕立てものを届けた酒屋の奥さんのお喋りに捕まってしまい、上映開始時刻に大幅に遅れてしまった。
僕たちが着いた時には、マリは受付の机に上半身を投げ出すようにして突っ伏していた。幕間に客席の掃除をするとき以外はマリはいつもこの姿勢のまま動こうとしない。それがなまけ者のマリと呼ばれるゆえんだった。母さんが申し訳なさそうに小さく声をかけると、マリは死ぬほど面倒くさそうに身を起こし、ミシン目も無視してチケットをもぎった。僕たちはとりつく島もなく、こそこそと客席に入った。
映画は大人の男の人と女の人がなじり合ったり抱き合ったり駅で待ちぼうけをくわされたりする話で、その理由が僕にはよくのみこめなかったので全体的に
上映が終わってロビーに出ると、母さんは僕に自販機の紙コップ入りレモン水を買い与えて、マリが掃除のために起き上がるのを静かに待っていた。上映終了後十分近く経ってようやくマリは身を起こして立ち上がった。母さんは子鹿のように
母さんは、父さんと僕とスベン叔父さん以外の人に自分から話しかけることはほとんどない。それでとても緊張していたのだと思う、普段より早口で高く尖った声になっていた。
マリは最初なんのことかわからない様子で不審そうに母さんを見ていたが、ロビーの隅でレモン水を飲んでいる僕に気づいて、ああ、と思い出したようだった。
「べつに。券があまってたんだよ」
つっけんどんにそう言うと、マリは母さんが話を継ぐ間もなく屋内用の箒とちり取りを手に客席に向かった。
あの時、母さんが僕を振り返って、帰りましょう、と微笑む前、少しのあいだ寂しそうな顔でうつむいていたのを覚えている。だから、〈三階建て〉から出てきたのを見て、母さんはマリといつのまに親しくなったのだろうと
さらに戸惑ったのは、たいていのことには上手に説明をつける母さんが、マリを訪ねたもっともらしい理由を思いつかなかったことだ。倉庫街の一角で黙って自転車にまたがったままの僕に、母さんはただ、買い物をして帰るから先に帰っていなさいと言った。たしかに買い物籠を持ってはいたけれど。
(つづく)
▼太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000901/(KADOKAWAオフィシャルページ)