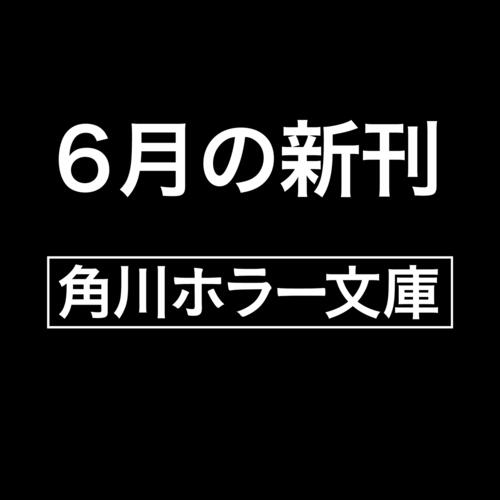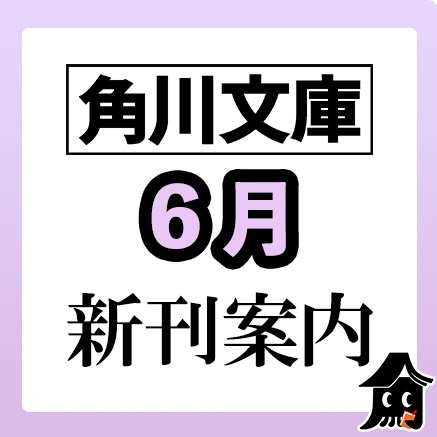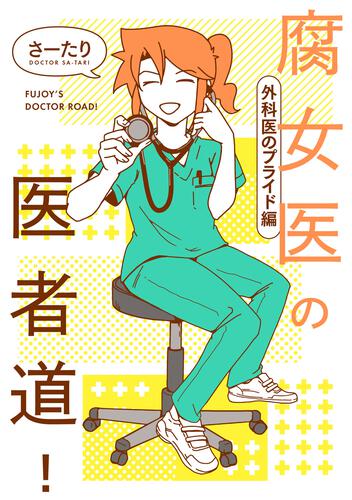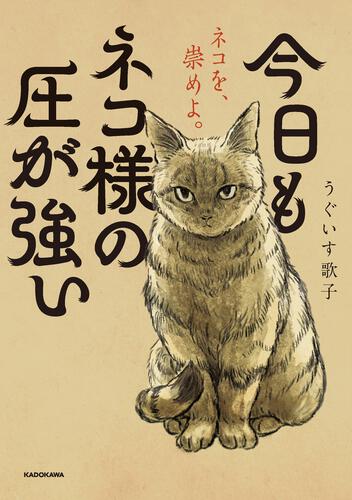大島清昭『最恐の幽霊屋敷』(角川ホラー文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
大島清昭『最恐の幽霊屋敷』文庫巻末解説
解説
今思い返してみても二〇二二年から二三年にかけての約二年間というのは、日本ホラー小説史において特別な時期だった。現代ホラーの年表に大書されるような傑作や重要作が、この二年の間に立て続けに刊行され、ホラーシーンを彩ったのだから。
ざっと具体例をあげるなら、
このほど文庫化された
大島清昭の作品が角川ホラー文庫に入るのは本書が初めてなので、著者のプロフィールを紹介しておこう。
大島は一九八二年、栃木県生まれ。
テーマパーク勤務などを経て、二〇二〇年に短編小説「影踏亭の怪談」で第十七回ミステリーズ!新人賞を受賞して作家デビュー。この際、選考委員を務めたのが
大島は翌二一年、「影踏亭の怪談」に登場した怪談作家・
その後も『赤虫村の怪談』(二二年)、『バラバラ屋敷の怪談』(二四年)と呻木叫子シリーズを書き継ぐかたわら、『地羊鬼の孤独』(二二年)、『一目五先生の孤島』(二四年)と中国の妖怪をモチーフにした長編シリーズも上梓。いずれの作品でも超常現象の存在を前提としたうえで、不可解な事件の合理的な謎解きが進められるという、ホラーとミステリの融合が試みられている。
ミステリーズ!新人賞受賞時のコメントやその後のインタビュー記事によると、大島が作家を志したきっかけは、
一方で(先の経歴からも明らかだが)大の怪談好き、妖怪好きでもあるようで、これまで
本格ミステリ志向と怪談趣味。この二つを混ぜ合わせれば大島清昭のホラーミステリになる、と言ってしまってはあまりにも単純化のきらいがあるが、この二つが大島作品の特色であることもまた事実だろう。そして本格ミステリ志向と怪談趣味が打ち消し合うことなく、それぞれ自己主張しながら危うく共存しているところに、大島作品の面白さがある。
本書『最恐の幽霊屋敷』は大島の四冊目の小説作品で、タイトルから明らかなとおり「幽霊屋敷」をテーマとしたホラーミステリである。
私立探偵の
それにしても“最恐”なんて
騒動の発端は一九九四年夏、この家に住んでいた主婦の朽城キイが、何者かに殺害されたという事件だ。キイは地元では名の知られた拝み屋で、凶器として使用されたのは祭壇に置かれた
幽霊屋敷として恐れられるようになったその家を、
こうして住む人のなくなった家は、現在短期契約者向けの物件として貸しに出されている。そこが幽霊屋敷であると知ってあえて借りる人、たとえば宗教者や霊能者、テレビや雑誌の取材クルーに人気を博しているが、そうなった後も容赦なく人は死に続けている──。
幽霊屋敷をテーマにしたホラー小説は、これまでも数多く書かれてきた。代表的な例をあげるなら、心霊現象が頻発する屋敷に調査チームが滞在するシャーリイ・ジャクスン『丘の屋敷』(一九五九年)、雪で閉ざされた幽霊ホテルを舞台にしたスティーヴン・キング『シャイニング』(七七年)などだ。それらと『最恐の幽霊屋敷』の違いはどこにあるのだろうか。
ひとつには建物自体の造りである。ホラーに登場する幽霊屋敷の多くは、重々しい雰囲気を放つ由緒正しき西洋建築だ。建物自体がまるで登場人物のように振る舞い、物語のトーンを決定づける。一方で、本書の旧朽城家はそんなゴシック趣味とは無縁の、「何の変哲もない木造二階建て」の一戸建て住宅である。どこの町にもありそうな、安っぽい造りの家。そのことが物語に、身近さとリアリティを付与することになった。
もうひとつの注目ポイントは、犠牲者の数の多さである。幽霊屋敷ものの過去の名作をひもといてみても、霊障によって命を奪われる登場人物の数はそれほど多くはない。もちろん作品によるが、せいぜい数人といったところだろう。それどころか幽霊すらはっきりと姿を現さないこともある。古典的な幽霊屋敷小説は、風景描写と心理描写を丹念に積み重ね、じわじわと幻想的なムードを醸成していくのが王道なのだ。
本書はそうした段取りを意図的に省略し、暴力的なまでの霊障をダイレクトにぶつけてくる。読んでいて連想したのは、
さて物語は、旧朽城家に関わった者たちにまつわるエピソードが、複数の視点から描かれていく。婚約者とともに旧朽城家に住み、さまざまな心霊現象に襲われた
同じ家を舞台にした連作であるものの、基本的には一話完結のオムニバスホラーであり、鍋島視点の第二章では怪談ルポ風、温水視点の第五章では幽霊屋敷からやや距離を置いた地点からの事件の考察といった具合に、それぞれ趣向を凝らしたストーリーと恐怖が描かれる。
本書の怪異描写は読むと意外にあっさりしているのだが、独特の力強さと生々しさがあり、少ない言葉で異様な気配を伝えてくる。顔が中心からぐにゃりと
また、序盤で旧朽城家にまつわる悲劇をたっぷりと読まされているだけに、ここでは誰の身に何が起こっても不思議ではないという緊張感が常につきまとう。たとえ視点人物であっても、判断を誤れば死亡する。誰一人安全圏にはいられないというスリルが、作品に強度をもたらしていることも確かだろう。
こうして旧朽城家の過去のエピソードをたどってきた物語は、最終章において現在(二〇一八年)へと時間が戻り、関係者を前にしての獏田による謎解きが描かれる。といっても獏田の推理は、怪異を合理的に解明するのではなく、怪異をもたらしたものの正体を指摘し、事件全体の構図を明らかにするというものだ。
その結果、恐怖は消え去るどころか、事件の異様さがいっそう際立つこととなり、なんともいやな余韻を残して物語は終わる。解決しているようで、肝心なところは何も解決していない。大島作品において、謎解きはホラーに奉仕することが多いのだが、本書は特にその傾向が強いのだ。
本書で大島が目指したこと。それは平凡な田舎町に、他に類を見ないような“最恐の幽霊屋敷”を建設することだったに違いない。そしてその狙いは見事にクリアされている。本書の最終ページを閉じた読者の脳裏には、フラッシュバックしてくる数々の恐怖シーンとともに、禍々しい気配を漂わせて栃木県北部にたたずむ、あの家のシルエットが浮かんでいるはずである。
それともうひとつ指摘しておきたいのは、本書全体を覆う一種独特の幻想的な手触りだ。大島の恐怖描写は実話のテイストを取り入れたものだが、一方で犠牲者の多さに象徴されるような過剰さや、密室からの人の消失に代表されるような人工性・構築性を感じさせる部分もある。それらが
現代日本のホラー小説において、ホラーとミステリの融合はさまざまな作家によって試みられている、ひとつのトレンドである。本格ミステリと怪談を愛する大島が新人賞を受賞してデビューし、その作風が広く受け入れられている背景には、ホラーミステリのこうした隆盛があることは疑いえない。
といっても大島がトレンドに迎合したのではない。大島が長年磨いてきたユニークな感性と、大きな時代の流れが共鳴しているといった方が正確だろう。いずれにせよ大島が現代ホラーシーンを彩る、重要な書き手の一人であることは事実。次はどんな趣向のホラーミステリで私たちを楽しませてくれるのだろうか。今後の活躍にも
作品紹介
書 名:最恐の幽霊屋敷
著 者:大島清昭
発売日:2025年06月17日
転落が止まらない、 ジェットコースター級の事故物件ホラー長篇!
「最恐の幽霊屋敷」という触れ込みで貸し出されている物件がある――。幽霊を信じない探偵・獏田夢久(ばくたゆめひさ)は、屋敷で相次ぐ不審死の調査を頼まれる。さまざまな理由でその家に滞在した者たちは、一様に背筋の凍る怪異に見舞われた上、恐ろしい死に直面する。屋敷における怪異の歴史を綴ったルポ。その中に謎を解く手がかりがあるのだろうか。調査に乗り出す獏田を待ち受ける、意外な真相とは――? 「最恐の幽霊屋敷」はなぜ生まれたのか、そして、何が屋敷を「最恐」にしたのか。恐ろしい真実がいま明かされる。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000644/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら