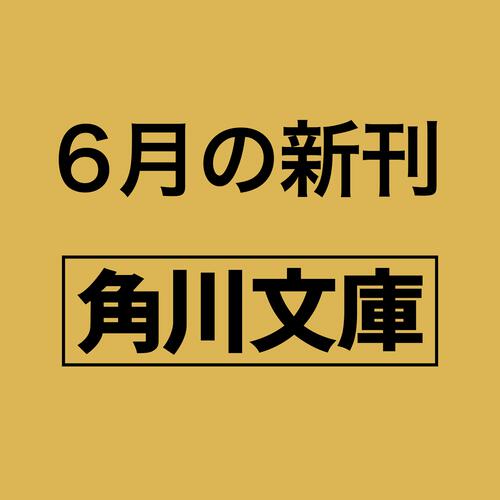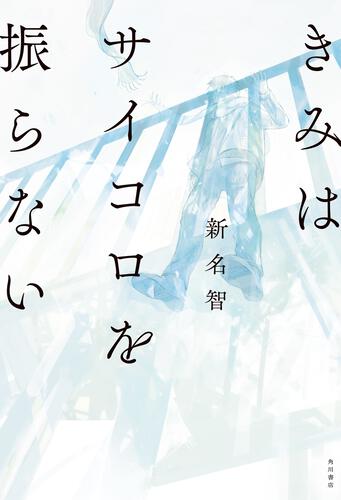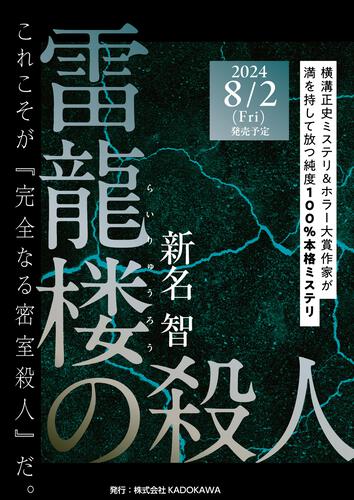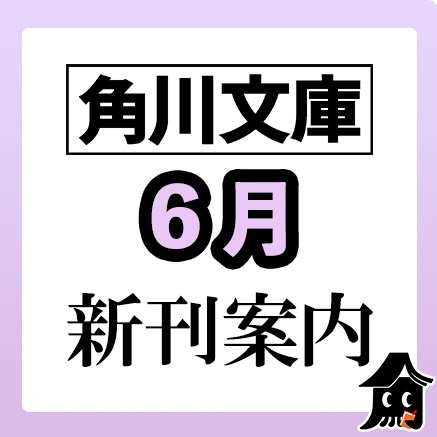新名 智『あさとほ』(角川文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
新名 智『あさとほ』文庫巻末解説
解説
本書は二〇二二年七月にKADOKAWAより刊行された単行本『あさとほ』を、加筆訂正し文庫化したものである。その加筆訂正には「結末の大幅な変更」が含まれる。これにより作品の構造も単行本と大きく変わった。なので各読者の読後感も異なるものになるだろう。が、私が言いたいのはそこではなく、「単行本と文庫で結末が異なること」そのものに、著者である
『あさとほ』は、新名さん自身の言葉で言えば「物語がお化けになって襲ってくる話」だ。雑誌『怪と幽』vol.013(二〇二三年四月発行)で対談した際、私はご本人から直接そう聞いている。では具体的にどういう内容なのか。
語り手「わたし」であるところの
月日が経ち大学生になった夏日は、卒論の指導担当の教授の失踪事件や友人の異変をきっかけに、「あさとほ」という平安時代に存在し、今は失われた物語の存在を知る。それが青葉の「消失」と無関係ではないらしいことも。夏日は自分以外で唯一青葉のことを覚えている
(※以降の文章には本作の終盤の展開や、結末を
構造としてはミステリ的で、題材としては超自然ホラー的で、総体としてはよくある物語の一つに思える。不可解な事件が複数起こり、事件は全て
文庫解説から先に読むタイプの読者諸氏は、ここまで読んでこうお考えかもしれない。じゃあきっと「わたし」が「あさとほ」の謎を解くことは事件の解決とイコールで、きっと終盤に事件は「わたし」の手で解決され、その結果「わたし」の傷は癒え、きっと「わたし」と幼馴染は自分の気持ちに気付き、特別な感情で結ばれるのだろう。そしてめでたしめでたしで終わるのだろう、と。
結論から言うと、本書はあなたが想像したとおりの物語であると言えるし、まるっきり正反対の物語とも言える。
終盤、「わたし」は真相を暴く。
だが「わたし」は暴かれた真相そのものである。
「わたし」の傷は癒える。
だが「わたし」は自分が負ったはずのない傷を負っている。
「わたし」は自分の本当の気持ちに気付く。
だが「わたし」は「わたし」がこれまでの「わたし」ではないことにも気付く。
ぼんやりとしか書けないのがもどかしいが、つまり本作は物語の類型をなぞりながら、同時に反転してみせるのだ。
重要なのはあくまで「反転」であって「否定」ではないこと。「人間は物語というフィルターを通してしか現実を認識できない」という趣旨の冷めたモノローグが繰り返されはするが、だからといって物語であること、娯楽小説であることを手放さない。メタでありながらベタであろうとし、
この分かりにくさは何なのか。言い換えると、新名さんはどうしてこんな分かりにくい小説を書くのか。面白さより分かりやすさが大切、いや分かりやすければつまらなくてもいい、と言わんばかりの「分かりやすさ至上主義」が
ありのままの現実は
デビュー作『虚魚』において、偽りの秩序とは「怪談」だった。第三作『きみはサイコロを振らない』では「ゲーム」だ。第四作『雷龍楼の殺人』では位相こそ異なるが「ミステリ」だろう。本作にはミステリという虚構を現実に
偽りの秩序。言い換えるなら幻想であり、もっと言うと「分かりやすさ」だ。たしかにこうしたものは人間に必要だ。不条理な世界を生き抜くための手掛かりになる。だからといって、新名さんは無邪気に幻想を肯定しない。現実を直視することは怖いが、現実を物語のように消費することも「同じくらい怖い」と、『あさとほ』の登場人物に語らせている。その具体例が後半に登場する「友人の不幸をダシに面接用のドラマチックな自己PRを作成し、それを恥じない就活生」だろう。
また、先述した対談で、新名さんは「いわゆるジャンル小説みたいなものはあまりやりたくない」「チェックシートを埋めただけの小説は嫌」と、類型的な物語を書くことへの抵抗を表明していた。類型的、つまり分かりやすい物語に批判的なのだ。事実、『きみはサイコロを振らない』は特殊設定ミステリなんて書いてやるもんか、と言わんばかりの内容だし、『雷龍楼の殺人』には密室ミステリ好きを後ろから蹴り飛ばすような「密室」が登場する。幻想はしょせん幻想にすぎず、物語もしょせん物語にすぎない。どれほど分かりやすくても、偽りの秩序が真の秩序になることは決してない。作品内容でも、執筆態度でも、新名さんの冷ややかな視線は一貫している。
だが、その冷ややかさは冷酷であることを意味しない。読者の幻想を打ち砕き、突き放すことを狙った物語は無数にあるが(私もしばしば書く)、新名さんはそのような真似はしないのだ。現実を現実のまま受け入れられない人間の弱さを暴きつつ、新名作品はその弱き者たちに寄り添う。或いは幻想に傷付けられた人間に焦点を当てる。そして既存の分かりやすい物語とは異なるアプローチで、読者にカタルシスを与えようとする。
新名作品全般にある「分かりにくさ」の本質はここにある。それを新名さんの「優しさ」と言語化するのは簡単だが、私はそうしたくない。何故なら「作者がこういう性格だからこういう小説を書いたんです」も、一つの分かりやすい物語、偽りの秩序に過ぎないからだ。そもそもを言うなら、この文庫解説という代物もそうだ。
長々と書いてきたが、最後に私が言いたいのは以下のようなことだ。というより『あさとほ』を解説するなら、こういう結びにせざるを得ない。すなわち──
読者諸氏におかれましては、私の書き連ねた解説という名の物語ごときで、新名作品を「分かった」「理解した」つもりにならないでください。誰かに見つけてもらうんじゃない。あなたがあなたの『あさとほ』を見つけるの。
作品紹介
書 名:あさとほ
著 者:新名 智
発売日:2025年06月17日
この物語を追うと、人が消える。横溝ミステリ&ホラー大賞、受賞第一作!
夏日が通う大学で教授が突如失踪し、「事情を探る」と言う同級生も大学に来なくなった。部屋を訪ねると本が山積みになっており、「あさとほ」という無名の古典を執拗に調べていたらしい。そして風呂場には彼女の遺体が……。同じように失踪した人が他にもいると知った夏日は、幼いころ双子の妹が失踪した日の思い出を重ねてしまい、恐る恐る調査に乗り出す。はたして単なる”お話”に、生き死にを左右する力があるだろうか? 人間と物語の本質に迫る、精緻を極めたホラーミステリ。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000692/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら