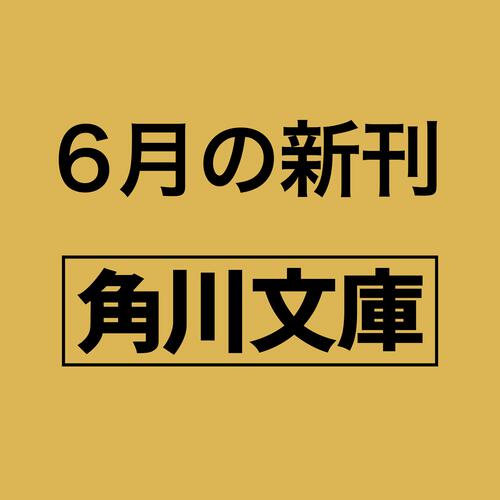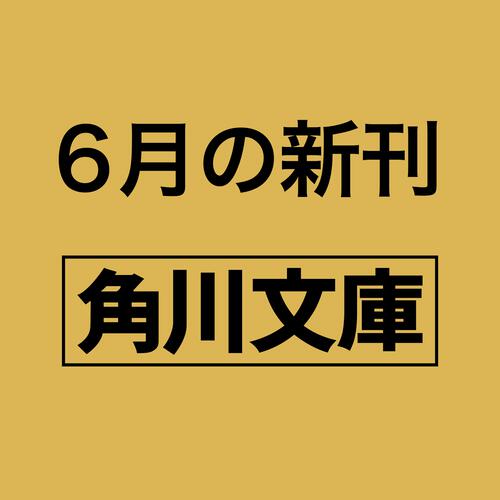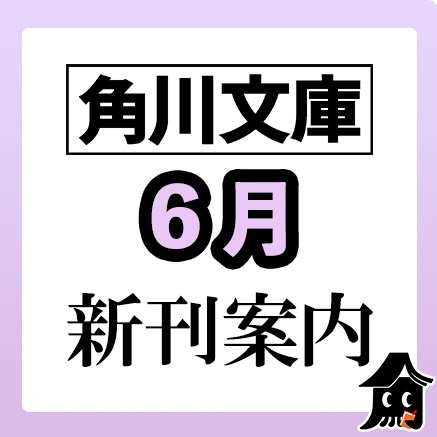辻村深月『この夏の星を見る』上・下(角川文庫)の刊行を記念して、下巻の巻末に収録された「解説」を特別公開!
辻村深月『この夏の星を見る』文庫巻末解説
解説
山崎 直子(宇宙飛行士)
交わるはずのなかった人と人が、ふとしたきっかけで出会う、そんなドキドキするような偶然がこの小説にはあります。けれど読了後には、それが偶然ではなく、必然だったのではと思えるような不思議な感覚が残ります。
目に見えない新型コロナウイルスが蔓延していく中、何気なく過ぎていた日常が制限され、変わってしまうもどかしさと不安。そんな時代を生きた中高生たちが主人公です。皆どこかやるせない想いを抱え、その想いがさまざまな「糸」を手繰り寄せていき、やがて思いもしない点と点がつながれていくのです。必死に「今」をつかもうとし、オンラインツールも駆使しながら、逆に「距離を越えたつながり」が生まれていきます。孤立した自粛生活の中でも世界とつながっていけるんだ、ということに気づいていくのですが、その糸口は、昔のラジオの電話相談での会話だったり、きのこがお互い好きというニッチな趣味の一致だったり、離れていても同じ星を眺めたいという想いだったり。型にハマっていないところが人間らしくて、だから愛おしくなるのです。
最初にこの作品の解説のお話をいただいたとき、正直とても驚きました。というのも、辻村深月さんといえば、ミステリーや心理描写の巧みな小説のイメージを強く持っていたからです。そんな辻村さんが「星」をタイトルに入れた小説を書かれたと聞いて、どんな作品なのだろう? とワクワクした一方で、解説の執筆者として「星」に詳しい人はたくさんいて、もっと適任な方々がいるのではという戸惑いもありました。なぜ、私なのだろう、私でいいのだろうか。そう思いながら、自分なりの答えを探して読み進めていくことは、自分にとってはミステリーの謎解きをしているようでもありました。そして、登場人物たちが現実の影を背負いながら、思いがけない形でつながっていく姿を見ていくにつれ、ふと、自分自身も作品を超えて登場人物たちとつながったような、そんな瞬間が訪れたのです。
作品中の花井うみか宇宙飛行士が語る「『好き』や興味、好奇心は手放さず、それらと一緒に大人になっていってください」という言葉に、私自身がこれまで多くの人に伝えてきた想いが重なったからです。いろいろ悩んだとしても、どの道を行ったとしても、自分の中にある好奇心を大切に持ち続けてほしいと思うのです。きっかけは些細なことでいい。自信なんてなくてもいい。形を変えていってもいい。何となく始めていくうちに、それがだんだんと道につながってくることがあるからです。私自身、子どものころ星を見ることが好きで、そこが原点だったなあと思うと同時に、学校の先生に憧れたり、他国の少女との文通に心躍らせたり、周りの人に圧倒されたり、恐る恐る一歩を踏み出したり、いろいろなことを思い出します。そんな時、それでも、好きだなあ、楽しいなあと内側から湧いてくる気持ちを持つことは、何かに挑戦するときの原動力になるような気がするからです。
この小説は、コロナ禍でさまざまな想いを抱えた中高生に捧げられた作品かもしれませんが、同時に、大人たちにも読んで欲しいと思いました。制限だらけの毎日、余裕のなさの中で、何が正解なのか分からず不安になりながら、それでも子どもたち、生徒たちのことを見守る親や先生の存在もこの小説では丁寧に描かれています。作者の辻村深月さんが教育学を学んでいたことを後から知り、なるほどと思いました。辻村さんの教育への想い、子どもたちへの眼差しが、この作品に込められているように思えたからです。
作品中で、サッカー部に入りたかったのに、サッカー部が存続されず苛立ちと諦めを隠せない真宙が、なりゆきで理科部に入り、顧問の先生に励まされ、そこで出会いを得たように──子どもたちに「こんな道もあるよ」「こんな人もいるよ」と、選択肢の存在をそっと教えること。そして、「大丈夫」と背中を押すこと。選ぶのは本人ですが、寄り添って励ますことはできます。ひとたび自分の興味を見つけた子どもは、自ら歩き出していきます。人間万事塞翁が馬。思いがけない方向に進んだ道が、振り返ると大切な経験になっていたこともあります。それは決して最初から望んでいたことではなかったかもしれないけれど、後から振り返った時に、必要な体験だったと感じることがあります。だからこそ、子どもが自走できるまで見守り後押しする、そんな大人たちの姿から、学ぶことも多かったです。
ところで、星は冬の方がきれいに見えることが多いのに、なぜこの作品は「夏」なのか? もちろん、夏は中高生にとって特別な時間です。夏休みという時間があり、何かに取り組みやすい時期であり、来年度の進路を考えていく時間でもあり、青春の季節かもしれません。それに加えて、夏の夜空の象徴である「夏の大三角形」は、七夕伝説で親しまれていて馴染み深いですが、作品中の五島列島の天文台館長・才津さんのお話によれば、「夏の大三角形の星は、将来の北極星ば見とると思うとまた不思議な感慨がある」のです。つまり、夏の大三角形のうちのはくちょう座のデネブ、そしてこと座のベガが、それぞれ約八千年後、約一万二千年後に「北極星」になるというのです。地球も宇宙の中で動いていて、北が指し示す方向も長い時間をかけて変わっていくのです。きっと、私たちの日常も、この雄大な宇宙の中での出来事で、私たちも宇宙の一部なんだと感じて欲しい、という作者の想いもあったことと思います。それは、私自身、宇宙に行った時に感じたことと全く同じでした。国際宇宙ステーション(ISS)の中で浮かびながら、何だか宇宙が懐かしく感じられたのです。宇宙は遠いところというよりは、故郷のようなところで、自分のルーツを探して訪ねているような感覚になりました。この地球も私たち一人ひとりもみんな宇宙の一部なんだなあと。
ISSからも、月の満ち欠けや、天の川や夏の大三角形を見ることができ、地上の家族や友人も、同じ星空を見ているかもしれないと想像していました。作品中の円華のように私もあまり泣かない方ですが、この本を読んで共感し、久しぶりに涙が出てきました。皆さんもぜひ「#きぼうを見よう」のサイトなどをご参考に、ISSを見てくださったら嬉しいです。
この小説に描かれた“つながり”を、どう受け取るかは、皆さん一人ひとりに委ねられています。きっと、読み終えた後には、ふと星を見上げたくなる、誰かに想いを届けたくなる、そんな物語だと思います。
作品紹介
書 名:この夏の星を見る 上・下
著 者:辻村深月
発売日:2025年06月17日
この物語は、あなたの宝物になる。
亜紗は茨城県立砂浦第三高校の二年生。顧問の綿引先生のもと、天文部で活動している。コロナ禍で部活動が次々と制限され、楽しみにしていた合宿も中止になる中、望遠鏡で星を捉えるスピードを競う「スターキャッチコンテスト」も今年は開催できないだろうと悩んでいた。真宙(まひろ)は渋谷区立ひばり森中学の一年生。27人しかいない新入生のうち、唯一の男子であることにショックを受け、「長引け、コロナ」と日々念じている。円華(まどか)は長崎県五島列島の旅館の娘。高校三年生で、吹奏楽部。旅館に他県からのお客が泊っていることで親友から距離を置かれ、やりきれない思いを抱えている時に、クラスメイトに天文台に誘われる――。
上巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000850/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
下巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000849/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
作品特設サイト
https://kadobun.jp/special/tsujimura-mizuki/kono-hoshi/