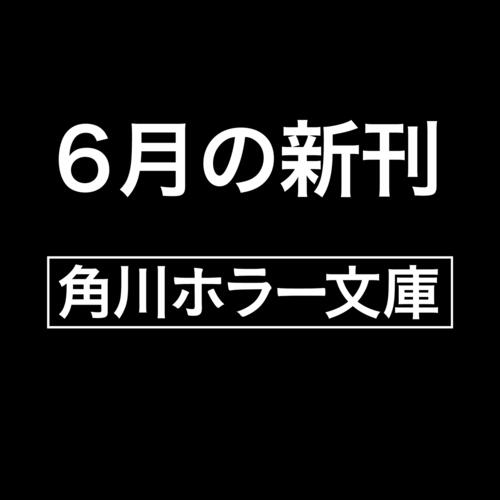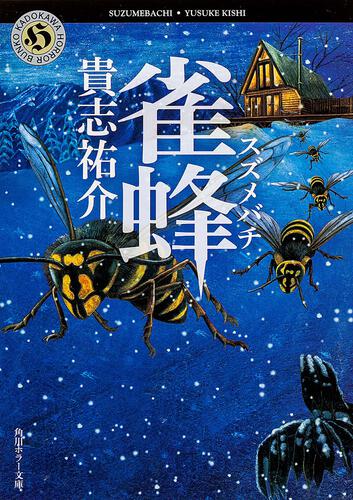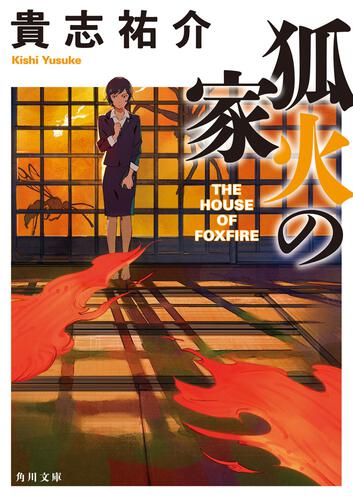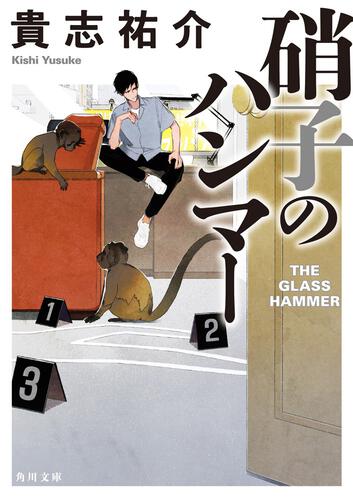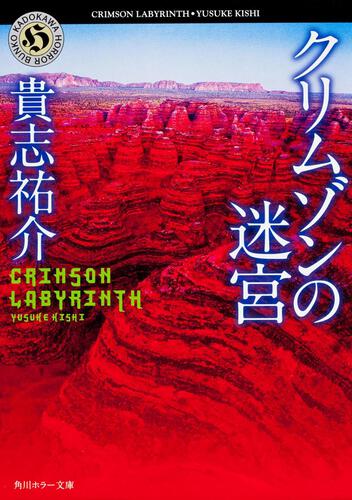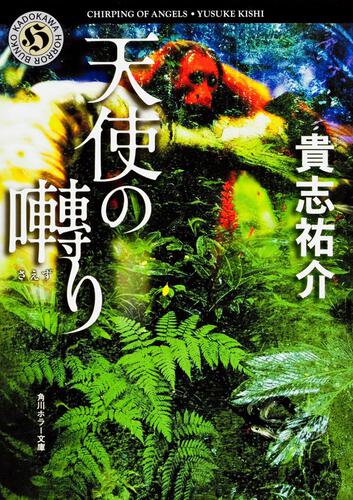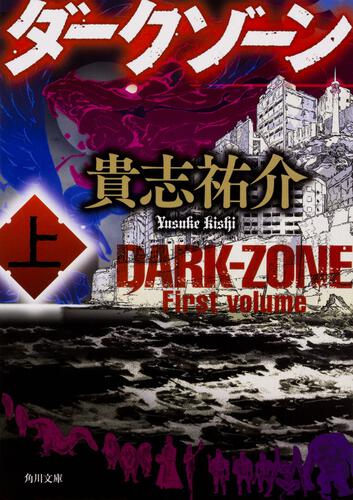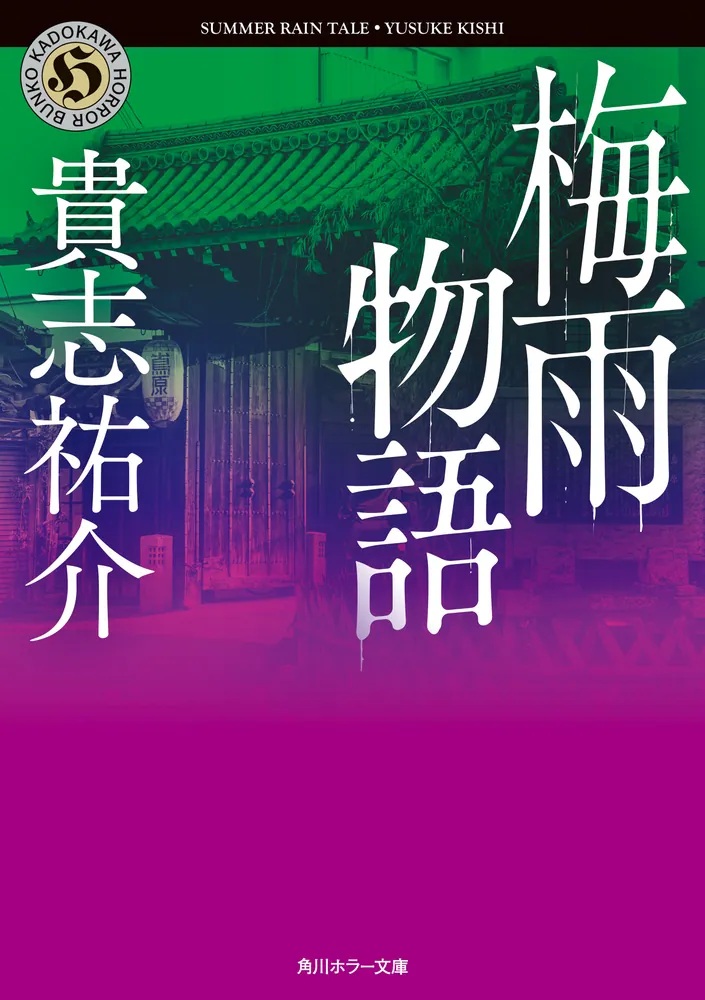貴志祐介『秋雨物語』(角川ホラー文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
貴志祐介『秋雨物語』文庫巻末解説
解説
杉江 松恋
恐怖と畏怖の念を共にこの作家に感じる。
貴志祐介は当代随一の物語作家である。代表作には重厚長大な長篇が挙げられることが多く、短篇作家という印象は薄い。しかし防犯探偵・榎本径を主人公に据えた『狐火の家』(二〇〇八年。現・角川文庫)など、連作として書かれたものは粒揃いであり、決して短篇を苦手とする作家ではないのだ。最も早く世に出た作品も、一九八六年に第十二回ハヤカワ・SFコンテストで佳作を受賞した短篇「凍った嘴」であった。推察するに、一作あたりに駆使する熱量が長篇とそう変わりないため短いものは書きづらいということがあるのではないだろうか。
『秋雨物語』は、その貴志が長篇とは異なる形式、短篇の密度で物語を書くことにもう一度挑戦する、という強い意志の下で執筆された四篇を収めた作品集である。親本である単行本の奥付は、二〇二二年十一月二十九日初版発行となっている。今回が初めての文庫化だ。
一口で言えば、密度が高い。詰まっている物語の質量がただならないのである。そして、これぞ貴志祐介、という作家の精髄を感じさせられる作品集になっている。長篇でしかこの作家を知らない読者も、収録作を読めば納得するのではないだろうか。そうそう、貴志祐介とはこういう作家だった、と。
二番目に収録された「フーグ」は「小説 野性時代」二〇一六年十二月号~二〇一七年三月号に掲載された。視点人物は松浪弘という文芸編集者で、彼が担当する青山黎明という作家が〆切を前に失踪することから話が始まる。作家のパソコンには「フーグ」という作品の書きかけファイルが残されていた。どうやら実体験を元にした物語であるらしく、それを読みながら青山に何が起きたかを松浪は探っていく。
この作品で驚かされるのは想像の多様さである。パソコン内から発見された短篇の中には青山が見たものと思しき悪夢の数々が挿入されているのだが、その一つひとつが鮮やかな情景を備えていること、現実感にあふれており、そのために感情を絶えず刺激されることに驚かされる。作中で描かれる青山の行動は怪談のある定型に則ったものなのだが、恐怖が増幅する地点が途中にあり、そこから見せられる悪夢は背筋が粟立つほどに怖い。この、だんだん加速していく感じは貴志作品の特徴でもある。本書の後に刊行された姉妹作ともいえる短篇集『梅雨物語』(二〇二三年。KADOKAWA)に「ぼくとう奇譚」という作品が収められているが、よく似た構造なので関心ある方は読み比べていただきたい。
本編を最後まで読むと、それまでの感覚が増幅された形で戻ってくる。あれはそういうことだったのか、と伏線に納得させられ、それがまた慄然とする気持ちを誘う。構造はミステリーのそれで、よくできた謎解き小説は真相を知った後にもう一度前に戻り、さりげなく明かされた手がかりの数々を探して楽しむという読み方ができる。話の核になっている着想は、実はミステリーのために貴志が温めていたものであったそうで、それをホラーに転じて書いた作品なのだ。さすが、『硝子のハンマー』(二〇〇四年。現・角川文庫)で第五十八回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門を受賞した実力者と言いたいが、この着想の活かし方はミステリーというよりもSF作家のそれかもしれない。わからないことを科学的に突き詰めていくという合理主義精神が全篇を覆う物語なのである。
収録作中最も長い巻末の「こっくりさん」(『怪と幽』Vol.010 二〇二二年)は、少年期に行われた奇妙なルールの儀式の物語だ。その名もロシアンルーレットこっくりさんである、四人で参加して神のような存在からお告げを受けるのは同じだが、そのうちの一人かそれ以上が生贄になって命を奪われるという代償が伴う。近藤拓矢も小学六年生でこの儀式に加わり、生き残った。それから十八年が経過し、彼は再び忌まわしい行為に手を染めることになる。
貴志作品には独自ルールのゲームが描かれるものがある。たとえば『ダークゾーン』(二〇一一年。現・角川文庫)は将棋やチェスなどの盤面で対戦するゲームを下敷きにしているし、謎のサバイバルゲームに登場人物が巻き込まれる『クリムゾンの迷宮』(一九九九年。角川ホラー文庫)もそうだ。敷衍していえば法廷という特殊な場が主舞台となる『兎は薄氷に駆ける』(二〇二四年。毎日新聞出版)を仲間に加えていいかもしれない。特殊な条件下に置かれた者たちはルールを探りながら必死の努力を重ねる。
その結果が登場人物の思い描いたのとは遠く離れたものになることが多いのが貴志の恐ろしいところで、読者の想像力を常に上回ってくる。宇宙的規模で遠く隔たったところに着地する『我々は、みな孤独である』(二〇二〇年。現・ハルキ文庫)はその代表格である。卑小な人間を遥かに超える巨大なものが存在している、というのが貴志作品の世界観であり、そうした理解があるゆえに登場人物たちはしばしば裏切られることになるのだ。
ある女性の生涯を調べて解き明かしていくという構成になっているのが「白鳥の歌」(「小説 野性時代」二〇一七年十二月号、二〇一八年一月号、三月号~六月号)である。売れない作家の大西令文が、嵯峨平太郎という資産家の老人から、ほとんど録音を残さずに亡くなったミツコ・ジョーンズというソプラノ歌手の評伝を書くように依頼されることから話は始まる。ジョーンズの人生について調べるために嵯峨はアメリカで私立探偵を雇っており、その報告を聞くという形で話は進んでいく。
オーディオに関する蘊蓄を嵯峨が語る場面が導入になっている。その話題が声楽歌手についての読者の関心を高めていくのである。ある題材を掘り下げて語られる蘊蓄が読みどころにもなっているという構造は〈防犯探偵・榎本径〉シリーズなどでも見られるものだ。密室劇の『雀蜂』(二〇一三年。角川ホラー文庫)ではあの獰猛な昆虫に関する知識が登場人物たちの運命を左右することになるし、大長篇『新世界より』(二〇〇八年。現・講談社文庫)では作中で描かれる進化生物の数々が物語の最大の魅力でもあった。
可笑しかったのは、探偵の報告を聞いていた大西が、あるところで唐突にヘヴィー級ボクサーのマイク・タイソンを連想することである。貴志はボクシング愛好者で、隙があればその話題を振ってくるのである。そうした場面は、緊張した物語の中に緩急をつける、コメディ・リリーフの役割を担っている。
コメディタッチで始まり、他の収録作とはかなり風合いが違うのが、巻頭の「餓鬼の田」(「小説すばる」二〇〇九年十一月号)である。本書の収録は雑誌の発表順になっており、この作品だけがかなり早い。餓鬼の田は富山県にある実際の景勝地で、そのパンフレットを貴志が見たことから着想した話であるという。この短篇を手始めに連作を書く構想もあったというが、実現はしなかった。どういう連作であったかは各自の想像にお任せする。
社員旅行の夜が明け、朝の散歩と洒落込んだ谷口美晴は、憎からず思っている同僚の青田好一がやはり一人で外に出ていることに気づき、話しかける。そこで思いがけず、青山が人生に苦しめられていることを知るのである。
最も短い話で、短篇としての切れ味も鮮やかである。谷口のちゃっかりした性格など、作者は明らかに笑いを誘うように書いているのだが、そこは『秋雨物語』というホラー短篇集に収められただけのことはある。ある地点で物語は反転し、運命の惨さが露わになる。「フーグ」についても書いたが本書の収録作は、何もわからないときよりも、すべてが明らかにされた後のほうが怖さがこみ上げてくるという構造になっている。他の三篇とは怖さの質も違うのだが、「餓鬼の田」の結末も十分に恐ろしいものだと私は思う。
わからないから怖いのではなくわかるからこそ怖い。それがSFやミステリーなどの合理的精神を宿した貴志祐介が、ホラーを書く際の最大の特徴である。すべてがわかったときに恐怖は最高潮に達する。初期作品でこの感覚を最初に味わったのは、おぞましい幕切れが待ち構えている『天使の囀り』(一九九八年。現・角川ホラー文庫)だろうか。主人公の推理が悲劇を招き寄せる『青の炎』(一九九九年。現・角川文庫)、世界を理解した瞬間に絶望に包まれる『我々は、みな孤独である』など、合理的思考と恐怖の感覚が貴志作品では根強く結びついている。恐怖、または世界に対する畏怖の念と言ってもいいだろう。自身の存在がいかにちっぽけなものであるかを思い知らされるのである。人間という器の外側に広がっている世界の巨大さを表現しようとして、貴志は物語を綴っているのだ。
『秋雨物語』、翌年の『梅雨物語』という姉妹篇は、原点に立ち返り、自身の出発点であった短・中篇の長さで緊密な物語を綴ろうという作家の目的意識から生まれた。モノノケという言葉があるように、モノとはもともと霊魂を指す言葉でもある。物語るという行為の本質は、人間存在の中核に言葉で接近するということなのだ。万人の、そして自分の中にもあるモノを語るためにはどうすればいいかという試みから本書の物語は生まれた。各話に、登場人物による物語り、という要素が含まれていることにお気づきになった読者も多いだろう。モノ語ること自体を要素として取り込むことにより、小説内に読者の空想に任された余白を確保し、物語を解放されたものにしていくのが狙いである。
本作で貴志が意識しているのが、江戸時代の作家・上田秋成である。初め国学者として出発した上田は、近世における怪異小説の代表作であり近代以降の作家にも大きな影響を与えた『雨月物語』の著書がある。同作の収録作がそれ以前の伝説集と一線を画すのは、物語のバリエーションが多彩であり、意図的にプロットを変えて執筆したとしか思えない語りについての自覚があることだ。また晩年には、歴史上の逸話や伝説が主たる題材となる『春雨物語』も著わしている。語りの自由さを、書き手としての上田は追究し続けた。
近世の作家がそこまで成しえたのであれば、現代に生きる自分は作品にもっと大きな振れ幅を生み出さなければいけないのではないか、という問いかけが本作の根底にはあるのだろう。四篇がまったく違った物語であるのもそれが理由だ。貴志はインタビューなどで、小説の結末の付け方は杉本苑子が理想形だと発言している。未知の場所に読者を誘い、幕を不意に下ろす。読者の空想力を上回ることが重要なのだ。
常に広がり続ける運動体として物語を書く。どこに行き着くかわからない果ての見えなさを示して、世界の広大さを表現する。そうしたものとして『秋雨物語』は書かれている。物語の可能性を信じる作者の世界に身を委ね、その奥行を存分に味わってもらいたい。
作品紹介
書 名: 秋雨物語
著 者: 貴志祐介
発売日:2024年10月25日
最後はすべて絶望。『黒い家』『悪の教典』の著者が紡ぐ4つの地獄譚。
失踪した作家・青山黎明が遺した原稿には、彼が長年悩まされていた謎の転移現象の体験が記されていた。霊能者を招くなど転移が起きないよう試みていた青山だが、更なる悪夢に引きずり込まれていく――(「フーグ」)。前世の報いを背負った青年の生き地獄、この世のものとは思えない絶唱を残したレコード、人生の窮地に立たされた4人が挑む命がけのこっくりさん。秋雨の降るなかで、深い絶望へ誘われる至高のホラー4編を収録。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322401000275/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら