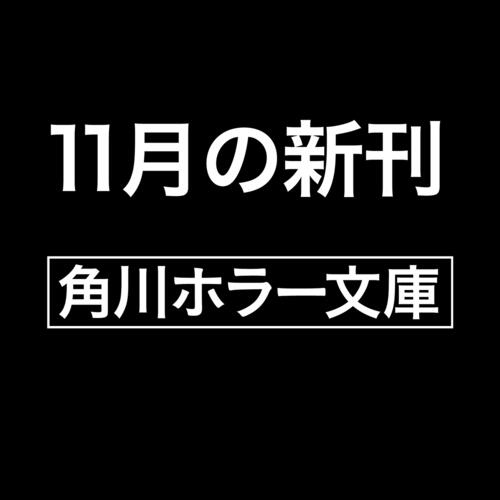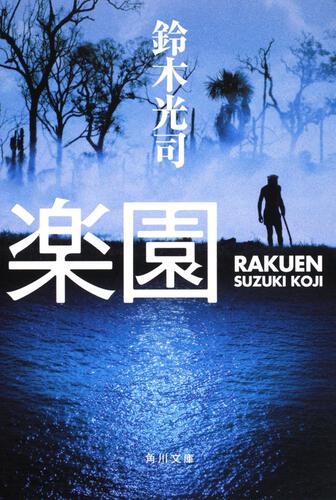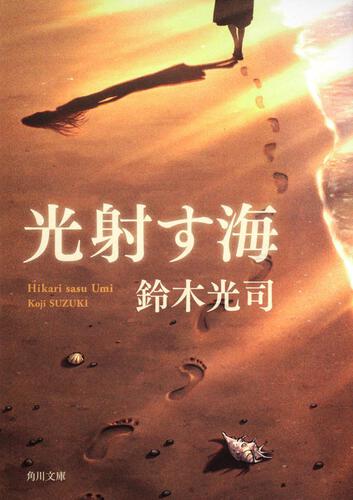鈴木光司『仄暗い水の底から』(角川ホラー文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
鈴木光司『仄暗い水の底から』文庫巻末解説
解説
一九九一年の初夏、小説家としての第一歩を踏み出したばかりの私は、衝撃的な一冊に出会った。
「リング」である。ビテオテープの絵のついた目立たない表紙の本に、なぜ自分が手を伸ばしたのかはわからない。さほど話題になってはいなかったはずだし、「鈴木光司」という作家の名前も知らなかった。ページを開いてみれば、冒頭で、立て続けに登場する人物が変死する。「出だしで死体を転がせ、一体だけでなく、いくつか転がせば、ますますいい」という当時
実際のところ、ただならぬ作品だった。それは
そのテープを作り上げた人物と過去を掘り起こしていく過程、解決……。エピソードのどれ一つ取っても、安易なオカルティズムに流れたり陳腐な動機で語られる部分はない。ホラー小説の金字塔と言われる「リング」の真にホラーな部分というのは、実はテープが人殺しをする、などという超自然性にあるのではない。活字の限界を鮮やかに乗り越えたかのように五官に直接訴えてくるその文章力、
鈴木光司の作品の本質は、「楽園」「光射す海」のような幻想冒険
「仄暗い水の底から」は、東京湾をテーマとする作品集だ。短篇集を編む場合、作品の舞台となる地域でまとめるケースがよくある。たとえば、京都であったり、どこか海外の都市であったりするが、たいていは歴史や特異な精神的風土をもっている地域だ。そこで展開する物語も、それらしい情緒を帯びることになるが、本作品集の場合は、ややニュアンスが違う。東京湾は単なる舞台ではなく、作品内容に深く関わりあう。
東京湾というのは、変わりゆく日本の象徴であり、不安定でアンバランスな東京という都市と、海という異界との境界線でもある。
「都市の感性」という言葉は、バブルの頃、都会的軽薄文化を賛美するときにひんぱんに使われ、擦り切れてしまったフレーズだが、真の意味での「都市の感性」がこの中のいくつかの作品に見いだせるだろう。
「浮遊する水」に登場する母親、「夢の島クルーズ」の日本アムウェイの会員とおぼしき夫婦、「孤島」で登場する新宗教の女性信者。現代都市という特殊空間の生み出したこうした人々と東京湾という水辺との接点に、不気味な物語が生まれる。
湾岸にあるマンションの屋上で、真っ赤な幼児用のバッグを発見するところから「浮遊する水」は始まる。処分されたはずなのに再び同じところに落ちている赤いバッグ、二年前に行方不明になった幼児、棺桶を思わせる高架水槽、屋上へ向かう無人のエレベーター、そして
しかし母親の視線自体は、決して透明なレンズではない。作者は物語を進めながら、母親の
ひずんだ視点の中で結びついていくいくつかの現象と、その結果導きだされる結論は、この母親の内側で膨れ上がり固定化していく妄想と読める。こうした形で行方不明の女の子をめぐる怪奇現象を否定してみると、この母親の病んだ内面と、荒廃したマンションの風景があいまって、今度は幽霊より数段怖い人間の心の闇につきあたる。
本書の中の多くの作品は、丁寧に読めば怪奇現象の存在を前提としていないというのがわかる。
「夢の島クルーズ」は「浮遊する水」とは対照的に、主人公のきわめて健全な視点から描かれる。
彼はマルチまがい商法に洗脳された友人夫婦のクルーザーに乗せられるが、沖まで出たときに、突然船は動かなくなる。陽は落ち、あたりが暗くなる中、友人の夫の方が船底のキールを確認するために海に潜る。そこで彼の見た物というのが、私がこれまで読んだ怪談のうちでも、飛び抜けて不気味で恐ろしい。それだけなら「夢の島クルーズ」は単なる怪異譚だ。しかし怪異は、友人夫婦、特に「どう、すばらしいと思わない」を連発するその妻への
このマルチ商法夫婦は、読者からみても嫌悪感を誘うような、病的な「都市の感性」を持つ人々だ。彼らと行動力にあふれた常識人である主人公との心理的な
しかし物語は、短篇にふさわしい驚きと疑問符をもって幕を閉じる。単なる偶然か、怪異か、それは読み手の解釈にまかされる。因縁話にもならず、合理的解釈もなされないために、独特の不気味な余韻が残るのは、鈴木光司の他のいくつかの作品にも共通した特徴といえる。そこに作品世界の奥深さを見るか、後味の悪さとしてしりぞけるかは、読み手の感性の問題であろう。
「穴ぐら」の主人公は漁師で、その他の作品の主人公といくぶん肌触りを異にする。しかしここで描かれる崩壊した家庭の有様、夫婦、親子関係のとらえ方は、極めて現代的だ。虐待する父親の心理描写の生々しさ、その人物像のリアリティーは驚嘆にあたいする。鈴木光司の描き出す人物は、エンタテイメント小説で「人間が描けている」と誉められる類のキャラクターとは一線を画す。独自の成長史、生活史を持ち、物を食い、
親から虐待を受けて育った主人公が家庭を持ったとき、父親とそっくりのことをしている、というのは、因縁話のように見えるが、実は実子への虐待の一般的なケースである。それをふまえた上で、作者は結末近くで、父親に自分がこの場で死ななければ、息子が自分と同じ運命をたどる、として死を決意させる。
そして意外なラストを迎えるわけだが、不気味と見るか、感動を覚えるかは、読み手により印象の分かれるところだろう。「孤島」とともに、この「穴ぐら」は私がもっとも気にいっている作品である。
「海に沈む森」は、最後まで冷静さを失わず、
舞台は、奥多摩の鍾乳洞。そこに閉じこめられた男の冒険譚であり、幼い息子への思いを極めてストレートに描き出したものである。エッセイや取材で目にする鈴木光司の考え方や行動と重なる部分もあり。これをもって鈴木光司の本質に近い作品、とする見方もあるが、私はそうは思わない。作家の本質はその作品世界を総括するところのもので、エッセイその他で本人が主張するところとは微妙にずれる。彼が作品を通して描き出す父親の概念は、極めて生物学的で壮大なものだということを付け加えておきたい。
なお鈴木光司がめざすところは、一般的なエンタテイメントではない、と言われる。実際に本人から、高橋和巳の「邪宗門」のようなものを書きたい、という話も聞いた。
私はそれを文学への接近とは考えていない。エンタテイメントと文学との境界作品をめざしていると考えるのも誤りだろう。
彼は単に小説を愛し、小説を書いているだけだ。彼の好きな作家、谷崎潤一郎にしろ高橋和巳にしろ書いているのは、ストーリーがあって、次はどうなるかとページをめくらせる「小説」である。江戸川乱歩よりも谷崎潤一郎に
純文学が観念的で一般の人々にとってよくわからないものになってしまった現在、テーマを設定し、ストーリーを動かす、「普通の小説」にエンタテイメントの文字がかぶせられた。
ちょうどクラシックの現代音楽(矛盾した言い方だ)が、なにがなんだかよくわからないものになってしまって、美しい旋律を聴かせたければ、映画音楽その他、ポピュラー音楽のジャンルで活動せざるをえないようなものだ。
「仄暗い水の底から」は、上質で普遍的な魅力をもった「小説」だ。便宜上「ホラー小説」に分類される。
*この解説は、一九九七年九月に小社より刊行した文庫に収録されたものです。
作品紹介
書 名:仄暗い水の底から
著 者:鈴木光司
発売日:2025年11月25日
すべてが最恐、すべてが規格外――日本ホラー界の帝王による伝説的短篇集
夫と離婚し、港区の埋立地に建つマンションに引っ越してきた淑美と5歳の娘・郁子。
ある日2人は、マンションの屋上でおもちゃの詰まった赤いバッグを見つける。
しかし、このマンションに子供は郁子以外いないはず……
その日を境に、不可解な現象が起き始める(「浮遊する水」)。
大ヒットホラー映画原作「浮遊する水」、『ユビキタス』の原型ともいえる「孤島」など、
“水”をモチーフとした7篇を収録。
『リング』著者による至高の恐怖短篇集。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000537/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら