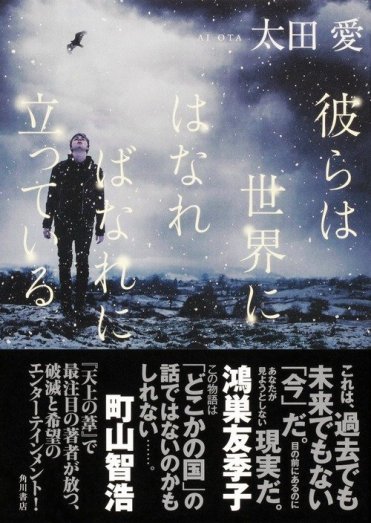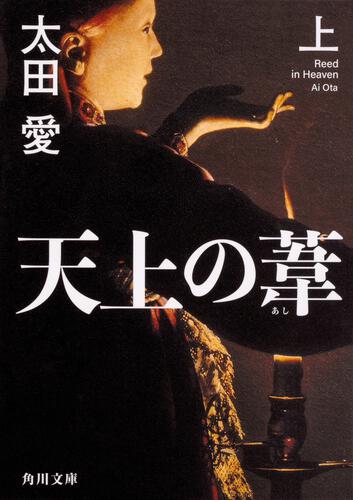彼らは世界にはなればなれに立っている
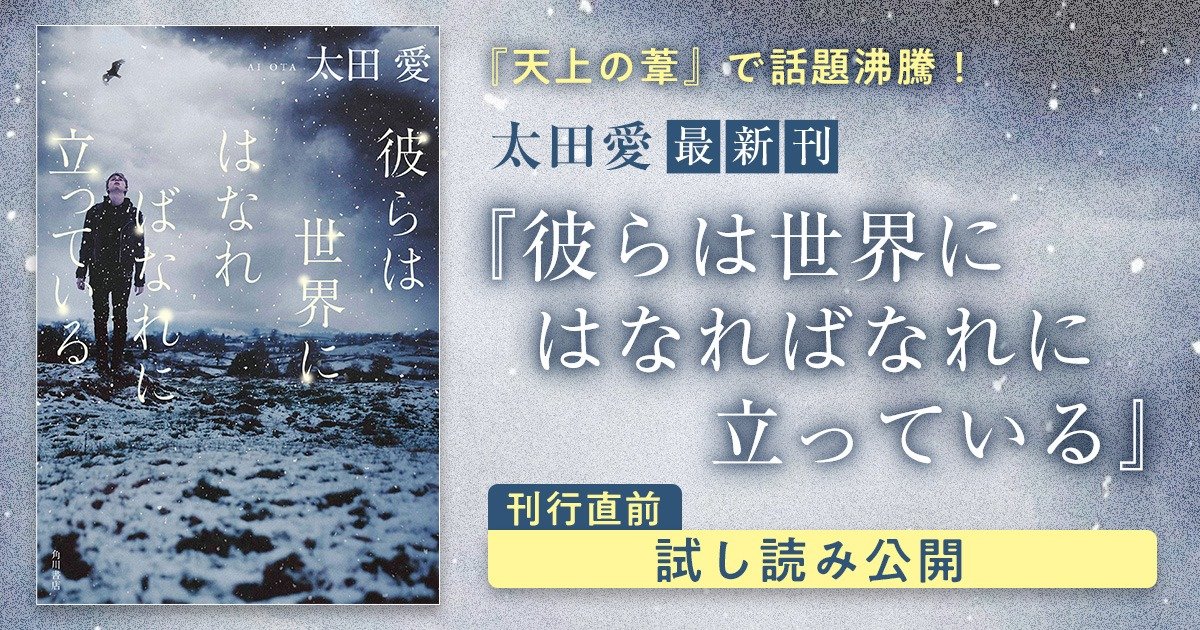
「相棒」の人気脚本家が突きつける、現代の黙示録! 太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』特別試し読み#3
〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれ、公然と差別される存在だ。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレの一家に浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した――。
最注目の著者による衝撃作、10月30日の刊行を前に特別試し読み!
>>前話を読む
†
花の水やりを終えて台所に戻ると、父さんが朝食を食べ終えた皿が流しに置かれていた。居間に父さんの姿はなく、麻の夏掛けが床に落ちていた。
寝室に上がったのかと廊下に出てみると、階上からではなく下から物音がした。地下室へ続く扉が開いていた。
肌が
地下室の薄寒いような空気の中で、父さんが古い物入れを引っかきまわしていた。
「なにしてるの」
鼓動が
「どこかに祖父さんの縄ばしごがあっただろう」
「そんなものなにに使うの」
「
父さんはじれったそうに言った。
「まえに猟に出かけた郵便局員が涸れ井戸に落ちたことがあっただろ。あの時は連れていた犬が騒いだんで仲間が気づいて助かった。でも母さんはひとりなんだ」
父さんは今度は母さんが森に行って誤って涸れ井戸に落ちたのではないかという可能性を思いついたらしい。
「縄ばしごなら、ここじゃなくて納屋だよ」
「そうか」と、父さんは意気込んで階段を駆け上がっていった。僕は力が抜けて綿のはみ出た丸椅子に腰を下ろした。
細長い高窓から斜めに射し込む光の中にまるで記憶の胞子のように無数の銀色の
奥の壁際に、あの大きな衣装箱がある。
赤茶色の木肌にところどころリボンのような縞目が光って見える。僕が生まれる前にお
そのそばに僕が使ったベビーベッドやビニールプール、壊れた旧式のラジオやお祖父さんの肘掛け椅子などが雑然と置かれていた。
不意に涙が頰をつたって落ちた。
一昨日の夜に来た時は気づかなかった。ここにあるのはすべて思い出の品々で、二度と使われることのないものなのだ。
僕はポケットに入れたままだったコンテッサの板ガムを取り出し、包みを剝いて口に入れた。ミントの味が涙と混じって甘く苦く喉を刺した。
テーブルに散らばった落花生の殻をくずかごに落とすと枯れ葉の音がした。僕は固く絞ったふきんで居間のテーブルを丁寧に
父さんは縄ばしごと水筒を持ってひとりで森へ出かけていった。一緒に行くことは許されなかった。母さんについてなにかわかったらベルさんが電話してくれるので、それを待つのが僕に課された役目だった。
けれども母さんのことでベルさんにわかることはなにもない。
だから電話は鳴らない。
ラジオの気象ニュースを聞いてから空の酒瓶を拾い上げ、勝手口の外のブリキのゴミ箱に捨てた。午前中から気温が上がっているようで、キョウチクトウの黄色い花もこころなしか元気がなさそうに見えた。軽く水をかけてやろうとホースに手を伸ばした時、うちの前の小道をやってくるマルケッタの姿が目に飛び込んだ。
僕はすぐさま家に駆け込んだ。マルケッタはお祖父さんの妹、つまり僕の
マルケッタ大叔母は母さんを憎悪していたのだ。
大叔母は父さんが仕事でうちを留守にしている時を狙ってしばしば訪ねてきた。彼女が現れると母さんはすぐに僕に自分の部屋へ行くように言ったけれど、僕はいつも階段のなかほどで息を潜めて座っていた。きまって聞こえてきたのは大叔母の
大叔母の訪問についてはいっさい父さんに話してはいけないと母さんから言われていたから、父さんはなにも知らない。だがものごころついて以来、僕はバースデーケーキの
大叔母が玄関のノッカーを打ち鳴らす音が家中に響き渡った。僕は咄嗟に映画で覚えた
──立ち去れ、悪霊。
大叔母は自分で扉を開けて入ってきた。両の拳を握りしめて台所に立っていた僕はたぶん妙に力んで見えたのだろう、大叔母は、気味の悪い子だね、と唇を
以前にも増して脂肪をふんだんに蓄えた大叔母は町でいまだにコルセットを使用しているただひとりの女性だった。その装備を外すと、水の入ったビニール袋のように不定形な状態になってしまうのではないかと疑っているのは僕だけではないはずだ。
大叔母は居間のテーブルに重そうなキルトの手提げを置くと、母さんが行方不明であることが町中の噂になっており、
重々しい表情を装ってはいるが、頰はうっすらと紅潮し、帽子についたダチョウの羽が弾むように揺れている。
この大叔母は母さんがいなくなった事実を内心小躍りして喜んでいるのだ。
さっそくとばかりに大叔母は宣言を実行に移した。父さんの仕事用の旅鞄が母さんのミシンの脇に放り出されているのを見つけると、まったくひどいもんだ、と大仰に嘆いて片付けにかかったのだ。
父さんが〈ズタ袋〉と呼ぶその大きな
忍耐の限界だった。
「家のことは僕と父さんでやるからかまわないでください」
大叔母が逆上して
ところがマルケッタは声を荒らげるどころかむしろ穏やかな口調で言った。
「おまえは初等科を終えたはずだね」
どうしてそんなわかりきったことを言い出すのかと戸惑った。
「人生の最初に学ぶべきことを教えるのが初等科だ。一年生の最初に三つの大事なことを教わったはずだよ。言ってごらん、塔の地の人間なら誰だって言えるはずだ」
六歳の時から繰り返し叩き込まれた教えを、大叔母はこの場で僕の口から言わせたいのだ。そうすることで真綿で首を絞めるように楽しみながら僕の抵抗の息の根を止めるつもりなのだ。
僕は唇を固く結び、沈黙で応えた。
「おかしいねぇ、ガスパンがおまえは物覚えがいいと言っていたよ。おまえは父親を噓つきにするのかい?」
父さんは森の涸れ井戸のひとつひとつに縄ばしごを下ろして母さんを捜している。心のどこかで、そんな所にいるはずはないとわかっているだろうに。地べたに座って汗を
僕は目を閉じてひとつめを答えた。
「規則を守ること」
入学と同時に身なりや心構え、行動に関する
「ふたつめは」と、大叔母が促した。
「わがままをせず我慢を覚えること」
大叔母が満足そうに目を細めたのは、抵抗や反抗が〈わがまま〉の典型的行為とされていたからだ。
〈わがまま〉とは文字どおり我のまま、自分がありのままでいることだった。我慢を覚え、克己心を養ってみんなと調和を保つことが求められた。そのような気風がいざというときには瞬時に一丸となって困難に立ち向かう塔の地の伝統を支えているのだと習った。そういう意味では多くの級友が、半分羽虫である僕の存在自体を調和を乱す〈わがまま〉と感じるのは自然ななりゆきなのかもしれない。
「みっつめは」
マルケッタはいまや口角に微笑めいたものさえ浮かべていた。
僕は無力感で足下が沈んでいくようだった。
「指導的立場の人間に従うこと」
子供にとってすべての大人は指導的な立場にあった。大人が大勢いる時は性別や社会的地位、年齢などが勘案され序列の最上位とされた人物の指導に従う。だが、今この家の中では誰が指導的立場にあるかは明白だ。その事実の前では、指導の正当性や僕の意志などなんの意味も持たない。
「片付けは食事をしてからにしようかね、どうせろくなものを食べてないだろうから」
大叔母が居間のテーブルから重そうなキルトの手提げを持ち上げ、台所に運んでくるのを僕は黙って見ているしかなかった。僕は食卓につくよう命じられ、大叔母は手提げから取り出した
生ぐさい臭いがむっと鼻をつき、僕は思わず顔を背けた。見なくてもレバー団子だとわかった。僕がこれだけは食べられないのを大叔母も知っている。臭いだけで酸っぱい胃液が上がってきて吐きそうだった。母さんが行方不明になったと知って大叔母が一番に考えたのが、僕にこれを食べさせることだったのだ。
おまえのためなんだよ、と大叔母は戸棚の引き出しからスプーンを出して僕の手に握らせた。そして、これからは我慢することを覚えなければね、と僕の顔を覗き込んだ。
僕は口を開けて
この女はなにがそんなに嬉しいのか。肉の垂れ下がった顔はまるで勝利に歓喜するかのように輝いていた。
その顔が不意に望遠鏡を逆さに覗いたようにはるか
僕はこのおぞましい内臓の
その時、玄関ノッカーの音がして突如、扉が開かれた。そこに現れた人を見て僕は一瞬、幻覚を見ているのではないかと思った。まるでスクリーンの中から抜け出てきたように、軽やかなレモン色のドレスをまとったコンテッサが立っていた。
お屋敷のコンテッサが家を訪ねてくるなんて想像したこともなかった。たまに映画館のロビーで見かけた時に
コンテッサはあでやかな微笑を浮かべて近づいてきた。一足ごとにシフォンのドレスが揺れ、歩く姿はネラさんの店のモデルたちも到底かなわないほど優雅だ。しかも僕とマルケッタを見つめたまま、ストラップのついたピンヒールは床に散らばった父さんの下着やシャツの隅っこさえ踏まない。その超絶技巧は映画の中で超能力を使って地雷を避けて進む主人公を
ところが台所の手前でコンテッサは不意に歩みをとめた。彼女が眉を曇らせるのを見て、僕は原因がレバー団子にあると確信した。コンテッサは食卓の小鍋に視線を注いだまま言った。
「あなた、帰ってけっこうよ」
マルケッタは自分に言われているのだと気がつくまで数秒かかった。だがそうとわかると黙って引き下がりはしなかった。待ちに待ったお楽しみはこれからなのだ。
「私はこの家の縁者ですからね、この子については責任があるんですよ」
「帰りなさい」
命令形の言葉は二人のうちどちらが指導的な立場にあるかを明確に示していた。
愛人のくせに、と大叔母が内心で歯嚙みしているのは間違いなかった。ドレープのように垂れた喉元まで怒りで赤く染まっている。だがいくら悔しがったところでコンテッサが伯爵の正式な養女である事実は変わるべくもない。
大叔母は
コンテッサはもう臭気に我慢できないというように居間のソファの背に両手をついて体を支えた。
「その鍋に蓋をしてどこかにやって。それから車から荷物を持ってきてちょうだい」
僕はすぐさま言われたとおりにした。ついでに大叔母の靴跡のついた父さんの衣類を階段の下の物入れに投げ込んだ。
居間に戻るとコンテッサがハンドバッグから香水を取り出して辺りに振りまいていた。花とオレンジが溶け合ったような
僕が車から運んできた大きなピクニックバスケットが二つ、居間のテーブルの上に並んでいた。
「開けてみて」
いたずらっぽく微笑んでコンテッサがバスケットを指さした。
蓋を開けると中には、ひき肉とアヒルのゆで卵の包み揚げ、青パパイヤと白インゲンのサラダ、何種類もの煮込みやパイ、デザートの甘いお菓子まで、お屋敷でしか食べられないようなご
「煮込みは食べる時にお鍋ごとオーブンで温めるといいわ」
僕はただ驚いてコンテッサを見つめた。
「お見舞いよ」
コンテッサはバスケットから赤いベリーのたっぷりと載ったお菓子を取り出して僕に渡し、自分もひとつ取った。ちょうど掌ほどの大きさで、こんがりと焼けた生地はまだ温かかった。
「そう、焼きたて。
コンテッサは子供のように豪快に半分を一口で食べた。それから口紅の外にはみ出した赤いソースを
僕はせめてものもてなしに牛乳を赤い花柄のコップに注いだ。僕たちはソファに並んで腰を下ろし、今度は粉砂糖をまぶしたオレンジのスフレに手を伸ばした。
真夏の昼、家の居間でコンテッサと二人でお菓子を食べている。この現実はこれ以上ないほど非現実的な感じがした。
その時、そういえば今日は見張り役のドニーノを見ていないのを思い出した。車にバスケットを取りに行った時、黄色いコンバーチブルには誰もいなかった。僕は思いきって尋ねてみた。
「ドニーノはお休みなんですか?」
コンテッサはちょっと得意そうな笑顔を見せて答えた。
「お屋敷に置いてきたの。でも伯爵は町にいないから、誰も私を?れない。ドニーノだって内心は喜んでるはずよ」
ドニーノは運転手兼見張り役として雇われたが、コンテッサがハンドルを離さないので仕方なく助手席に甘んじているのだという。どうやらドニーノは男が助手席に座るのは恥だと考えているようだった。
「しばらくはお互いに羽を伸ばせるってわけ」
「伯爵はどこか遠くへ?」
「中央府よ。今朝早くクルーザーで
伯爵は始まりの町を代表する議員で、年に数回、中央府で開かれる議会に出席している。
「じゃあまた床屋でみんなが文句を言うんだろうな」
床屋には町でも数少ないテレビが置かれており、散髪に訪れた客は歌謡番組や寸劇などを観るのを楽しみにしている。ところが議会が始まると娯楽番組の代わりに議員が質問したり答えたりする議会場の様子が延々と映される。これがとても評判が悪いのだ。
「そりゃあそうよね。議員っていっても、別に自分たちで選んだ代表でもないんだから」
コンテッサはソファの背に頭をのせて天井を見上げた。それから思いついたように僕に尋ねた。
「トゥーレは〈民選〉を覚えてる?」
「ぼんやりだけど。すごく小さい時に父さんが一度、連れて行ってくれたから。でも〈民選〉が廃止になった時のことはよく覚えてる」
以前は市民が自分たちの代表となる議員を選ぶ〈民選〉と呼ばれる制度があった。だが、投票に行く人がだんだん減って二人に一人を下回るようになった。つまり民選が必要ないと考える人が過半数を占めるという事態を受けて、中央府はすべての町で民選の存続を問う投票を行うことを決めたのだ。
ラジオでは人気の司会者たちが、過半数の人が参加しない民選で予算を浪費するよりも、それを福祉や教育に配分する方が効率的でより多くの人々が恩恵を受けられると説いた。またテレビでは、民選が廃止になった場合の仮想ドラマが制作され、新たに分配された予算で設備の整った憩いの家が造られて老夫婦が幸福に過ごす話や、学校の授業に観劇や演奏会の鑑賞が取り入れられ、芸術的才能に目覚める子供たちの話などが放映された。なかでもこの子供たちの物語は大きな反響を呼び、それ以後、投票権の存続を希望するのは自分の権利ばかりを主張して次世代のことを考えない利己的な人という印象が定着した。
投票の結果、民選の存続の可否は
その前年に日報がなくなっていたので、ほかの町では民選の廃止に対してどのような反応があったのかわからず、大人たちはどことなく不安そうだったが、すぐにラジオで廃止はどの町でもおおむね歓迎されていると報じられ、みんなが賛成ならいいだろうという雰囲気が広がった。
民選の廃止にともなって議員の任期は終身制になり、引退を希望する際は議員が後任を指名することになった。町の人々には結果だけが知らされた。
「僕が民選に連れて行ってもらったことがあるって言ったら、床屋にいた大人たちはみんなびっくりしてた。僕が生まれるずっと前に廃止になったような気がしてたみたい」
美味しいお菓子と冷たい牛乳で僕はいつのまにかすっかり打ち解けた気分になっていた。
「そのせいかな、みんなテレビに議会が映ると、ぐだぐだ議論している暇があったらなんでもいいからさっさと決めて勝手にやってくれって怒るんだ」
「王様をつくればいいのよ」
コンテッサは立ち上がってドレスの
「王様をつくって王様ひとりに任せるの。そうして王様と王様が選んだ人たちがすべてを決めて、私たちは決まったことに従う」
コンテッサは窓際の書棚に並んだ本の背表紙をわずかに首を傾けて眺めていた。いずれもそろいの紺地に金の文字で題名が記されているそれを、僕は一冊も読んだことがない。
「王様が失敗したらどうするの?」
「王様は絶対に失敗しないの」
「どうして?」
「失敗かどうかを決めるのは私たちではなく、王様だから」
コンテッサのアイディアは少し怖いような感じがしたが、今がそれとどう違うのかといえば、本質的にはあまり変わらないような気がした。たしかに民選がなくなってから中央府が誤りを犯したと報じられたことはない。
「ねえ」と、コンテッサが書棚の脇からこちらを振り返った。「テレビに映っているのが実は去年の議会でも、誰も気づかないと思わない? 世の中でなにが起こってるのか、私たちにはちっともわからないんだから」
コンテッサは足早に近づいてくるとバスケットから古い週報に包んだパンを取り出した。
「教えてもらえるのはこういうことだけ」
パンをテーブルに投げ出してコンテッサはくしゃくしゃの週報を広げてみせた。町で唯一の発行物である週報は伯爵の命を受けたイサイさんが作っている。
「『帽子屋のベップさん夫妻に七番目の赤ちゃんが生まれました』『婦人会のレシピコンクールの締め切りは五月三十日です』『魚屋のアーナックさんの長男・コルビ君十八歳とマメル農場の次女・エメさん十六歳が婚約しました』」
腹立たしげに読み上げるとコンテッサは週報を紙くずのように丸めた。
「こんなものは食べ物を包むだけの価値しかないわ」
僕が馴れ馴れしく床屋の話をしたり質問したりしたせいで怒らせてしまったのだと後悔した。ハンドバッグを手に取るのを見て、このまま帰ってしまうのだと思った。ところが予想に反して、コンテッサは唐突に微笑を浮かべて僕に尋ねた。
「煙草を吸ってもいいかしら」
僕は飛ぶように台所に行って客用の灰皿を取ってきた。するとコンテッサは出し抜けにハンドバッグを逆さまにして中身をソファの上にぶちまけた。
僕が取って手渡した方がいいのだろうか。でもコンテッサの持ち物に勝手に触れたりしてかまわないのだろうか。ためらううち、僕はコンパクトのそばに薄緑色の硝子石が転がっているのに気がついた。
コンテッサが視線を上げて僕を見たのがわかった。
「その石、見覚えがあるのね?」
そっと答えを引き出そうとするような声に、僕は黙って頷いていた。
一年生の水泳の授業で海に行った時のことだ。引率のデラリオ先生は、死ぬ気になれば人間は泳げるようにできていると信じていた。僕は本物の死が迫る体験を経て浜辺でひとり目を覚ました。先生が顔の上にのせてくれたらしい麦わら帽をどけると、先生のボートとみんなの海水帽が沖にプカプカと浮かんでいるのが見えた。戻ってくるまで間がありそうだったので、僕は浜辺で貝殻やきれいな石を探した。これはその時に見つけた硝子石で、一年生の僕は博物館に展示されている宝石の仲間だと思って家に持ち帰った。
「これ、僕が母さんにあげたんだ。ペンダントにするといいよって」
コンテッサは煙草を一本抜いて火をつけた。父さんの煙草と違う、ほんのり甘い香りのする煙が広がった。
「どうしてコンテッサがこれを?」
「拾ったの、お祭りの夜に水飲み場で」
きっとハンドバッグからハンカチを出した時に落としたのだ。こんなものを母さんはずっと持ち歩いていたのだと思うと、なんだかせつなかった。
「それはトゥーレが持っているといいわ。お母様のものだもの」
コンテッサの声は思いやりに満ちていた。僕はふと不思議に思った。
どうしてコンテッサは急に僕に関心を持ってこんなに親切にしてくれるのだろう。昨日、僕の自転車を見て引き返してきた時もそうだった。なにかわけでもあるのだろうか。それともこれは純粋な善意、あるいは気まぐれなのだろうか。
コンテッサはいきなり立ち上がると、なぜだか上機嫌で僕の腕を取った。
「車に乗りましょうよ。どこでも送ってあげる」
†
農場の辺りをドライブしたあと、僕は家の方に向かう丁字路の手前で降ろしてもらった。道の南側の雑木林には人ひとりがようやく通れるほどの踏み分け道があり、その
最後に三人でここを歩いてからまだ一週間も経っていないのだと思うと、信じられないような気がした。
草いきれのなか、ひとりで木々の小枝を払いのけて歩いていると、サマードレスの腕に浮き輪をかけた母さんの後ろ姿が見えるようだった。
僕は無人の入り江で少しのあいだなにも考えずにいたかった。
しかしすぐにその望みは
砂浜は広いが、
カイは本を閉じ、傍らの肩掛け鞄からりんごを取り出して、これ、と僕に差し出した。僕は黙って首を横に振った。実際、お菓子でお腹がいっぱいだった。するとカイは、じゃあ持って帰ればいい、とりんごを砂の上に置いた。そして鞄からもうひとつりんごを出して食べ始めた。一緒に食べるつもりで待っていたのだと遅ればせに気がついた。
カイは母さんのことも、僕がカイを突き飛ばしたことも、昨日はあんなに執着していた答案のこともなにも言わなかった。海の方を向いて黙ってりんごを食べていた。
カイの膝の上の本は、昨日も持っていた図書室のものだった。
図書室の蔵書は父さんが初等科にいた頃から徐々に中央府の印の入った書籍に入れ替えられ、今では書架の大半を塔の地の始祖の歴史や説話、その精神性を解説する本などが占めるようになっていた。個人が所有する書籍も特別な理由がない限り中央府の印のあるものと交換するか廃棄するように通達があり、どこの家の本棚にも図書室と同じ紺色の背表紙に金文字で題名が記された本が並ぶようになった。
カイは僕の視線に気づいて、さっきまで読んでいた本に目をやった。
「偉大な始祖たちが今の町を見たらなんて言うと思う」
物思わしげな口調が次第に怒りを帯びていく。
「この町は根が傷んでいるんだ、もうずっと以前から。深い所から腐っているのに、みんな気づかないふりをしてそれを認めようとしない。目をつぶってひたすら過去の栄光にしがみついてるんだ」
カイが学校の講堂でほとんど同じことを叫んだのを僕は覚えていた。新年の祝賀講話で来賓の警察署長が始まりの町の歴史を
それまでのカイはどんな時も堅苦しいくらいに規則や決まり事を重んじていた。服装や髪形はもちろん、お辞儀する時の指先の位置など
「このままでは町はだめになる」
カイは分厚い本を見つめたまま言った。寄せてくる潮が濃く匂った。
「羽虫が増えすぎたから?」
僕は静かに尋ねた。
町の大人が表立って口にしない本音は、家の中でそれを聞いた子供たちによって、羽虫の子である僕に伝達される。常に暴力をともなって。
増えすぎた羽虫が町の土台を食いつくす。やつらは犯罪を
「そのせいで町がだめになると思ってるの?」
僕はこちらを見ようとしないカイに尋ねた。
カイは口元に一瞬、ゾッとするような皮肉な笑みを浮かべた。それから急に挑むように僕を見つめた。
「そうだね。実際、あいつらは盗むからね。勝手に荒れ地に小屋を建てるのだって町の土地を盗んでるんだ。おまけに大人も子供も、隙あらば金や食べ物をかすめ取ろうと身構えてる。貧しいからじゃない。やつらが薄汚い羽虫だからだ」
心にもない言葉でも、充分に人を傷つけることができる。カイはそれを知っていて、そうすることで自分自身をも傷つけているような気がした。
拳を叩きつけるようにカイは言いつのった。
「町の人間は貧しくても盗まない。そんなことは塔の地の誇りが許さない。でも羽虫は違う。やつらは自分たちが困るといつだって人のもの、町のものに手を出すんだ。羽虫は生まれながらの卑しい
「マリのこともそう思っているの?」
口にしたそばから後悔した。こんなふうに言うつもりはなかった。
だが僕たちが映画館に通い、いっときでも親しい友達となりえたのは、カイと僕にどこか似通ったところがあって同じ
客に愛想笑いひとつ見せないマリを町の人たちはふてぶてしい羽虫だと言っていたが、僕は人々の視線を超然と跳ね返して誰にもへつらわずいつもひとりで堂々としているマリに憧れていた。年かさの少年たちに、あの女はむかし監獄にいたらしいぞ、と耳打ちされても僕の心は揺らぐどころか、型破りな存在としていっそうマリを崇拝するようになった。カイも僕と同じ気持ちだったのではないか。
僕の言葉にカイは黙り込んだ。
波の音が大きく聞こえるのが嫌で、僕は砂の上に置かれたりんごを取って
カイがぽつりと
「マリは特別だよ」
うつむいたカイは、さっきとはうって変わってとてつもなく
カイは立ち上がってりんごの
すでに潮は満ちきり、灰色の芯は波に洗われることはない。
いつのまにか影が動き、カイの背中は陽射しの中にあった。
「マリが子供の頃、噓つきのマリって呼ばれてたの知ってるか」
カイが尋ねた。
僕は立ち上がってりんごの芯を海の方に投げた。
やはり波打ち際に届かず砂の上を転がった。
「知ってる。雪の話だよね」
洗濯場で働いていたマリは口をきき始めてすぐ、自分は雪を見たことがあると言い出して人々を驚かせた。というのも、始まりの町で雪を見たことがあるのは先代の伯爵とその奥方だけだったからだ。二人は半年におよぶ新婚旅行のあいだに高い山の上にあるお城のようなホテルに滞在し、そこで一面の銀世界を見たという。その記念に先代の伯爵は巨大なロータリー除雪車を土産に持ち帰り、奥方は町の人々を集めて空から音もなく踊るように降ってくる雪の様子や、掌で溶ける雪片の感触などを語って聞かせたらしい。
奥方の話の方はともかく、お屋敷のガレージに置かれたロータリー除雪車は怪物のような
もちろん町の人間はマリの話を信じなかった。この町に雪は降らないが、おまえのような肌の色をした子供が生まれる町では、なおさら雪は降らないと
「トゥーレは、マリが本当に雪を見たと思うか」
海の方を見つめながらカイが言った。僕は咄嗟に答えられなかった。
マリは本当に雪を見たのか。僕はそんなふうに考えたことがなかった。雪の話はマリという特別な存在にまつわる逸話のひとつのように思っていたのだ。
そのことが不意に後ろめたく感じられた。そして、どうしてだかわからないけれど、カイはマリが雪を見たと信じているのだと思った。
ひとりになってからも、マリは特別だよ、と呟いた時のカイの顔が頭に残っていた。
陽が傾き、埃っぽく乾いた道が柿色に染まっていた。
†
庭の
驚いたことに父さんがコンテッサの持ってきた鍋をオーブンから取り出しているところだった。鍋つかみが見つからなかったのだろう、タオルで鍋の耳を摑んでいる。
父さんが台所でなにかをする姿を見たのは生まれて初めてだった。僕の記憶する限り湯を沸かしたこともない。その父さんがみずから煮込みを温め、しかも食卓には皿やフォークまで並んでいる。
父さんは誰が料理を持ってきたのかという点にはまったく関心がないらしく、僕が食卓につくやいなやこれからの方針について話し始めた。
「涸れ井戸は全部見て回ったから、あとは山しかない。母さんは沼の辺りで目当ての植物が見つからなかったんで山に向かったんだな。それで慣れない道で迷っちまった。でも母さんは用心深いから食べ物や水も少しは持って行っているはずだろ。明日にはきっと無事に見つけ出せる」
そこまでひと息に言うと、白いランニングシャツの父さんは大きく頷いてみせた。
帰宅してシャワーを浴びて着替えるあいだ、父さんは父親として僕を安心させる筋書きを一生懸命考えたのだと思う。そしてそれを僕に語って聞かせることで、自分自身も信じこもうとしていた。
「そうそう、さっきオト先生が心配してようすを見にきてくれたよ」
まるで万事解決したかのように父さんが明るい声で言った。オト先生は父さんの初等科での同級生だった。
「試験じゃ綴り方以外、満点だったそうじゃないか。たいしたもんだ」
父さんは僕が良い成績を取るといつも手放しで喜んだ。初めのうちは母さんも喜んでくれたが、やがて褒めてくれたあと必ず、でも普通でいいのよ、と付け加えるようになった。そういう時、母さんは僕が熱を出した時のような心配そうな目をしていた。半分羽虫であることでただでさえ攻撃の対象になりやすい僕が、このうえ目立って反感を買うのを恐れていたのだ。
だから僕はわざと零点を取った。平凡な順位で母さんを安心させたかった。学年最終日に手渡された僕の
父さんはまるで父子水入らずでキャンプをしているみたいに上機嫌で料理を平らげ、
機嫌良く酔っ払った時の常で父さんは歌い始めた。好んで歌うのは塔の地の始祖を讃えた勇ましい物語だ。その句読点のない延々と続く叙事詩は、居間の書棚に並んだ紺色の背表紙の本におさめられている。もちろん父さんはそこに記された出来事をすべて信じている。自分たちの歴史や伝統に疑いを抱くことは、塔の地への反逆に等しい大罪なのだ。
父さんは目を閉じ、拳を振り、床を踏んでリズムを刻む。神話の時間を呼び覚ますように。
僕の目は居間のキルトのカレンダーに引き寄せられる。
父さんが仕事から戻るはずだった明日の土曜日の所に、母さんが刺した赤いピンが残されている。母さんと僕はこの七年間、父さんが仕事に出かけるたびに無事に戻ることを祈って帰宅日に赤いピンをつけて待っていた。
母さんの手製のカレンダーは毎年、目を楽しませる得意の刺繡で月日を知らせるだけでなく、もうひとつの重要な役割を担っていた。
それは七年前のある出来事を覆い隠すことだった。
その秋、スベン叔父さんが中央府の会計学院を卒業して町に戻ってきた。僕は帰省のたびに海水浴や釣りに連れ出してくれるスベン叔父さんが大好きだったので大はしゃぎだった。スベン叔父さんは秀才で礼儀正しく、父さんの自慢の弟だった。二人は普通の兄弟のように一緒に暮らしたことはなかったけれど、とても仲が良かった。
僕のお祖母さんはスベン叔父さんを産んですぐに亡くなったのだが、その時十一歳だった父さんは初等科をやめてお祖父さんと一緒にトラックに乗る生活を選び、一方スベン叔父さんはお祖父さんの実家にいた未婚の妹・マルケッタ大叔母のもとで育てられることになったのだ。スベン叔父さんの話では、お祖父さんが盗賊の襲撃に遭ってこの世を去ってからは、まだ十代だった父さんが跡を引き継ぎ、大叔母にスベン叔父さんの養育費や学費の送金を続けてきたという。
僕たちはみんなスベン叔父さんの帰郷を喜び、これからは町の銀行に勤めるものだと思っていた。叔父さんは優秀な成績で会計学院を卒業し、申し分のない推薦状を携えて戻ってきたからだ。父さんは叔父さんが面接のためのスーツをあつらえに行くのに付き添ったり、通勤用に最新型の自転車を買ってあげたり、あれこれと嬉しそうに世話を焼いていた。
採用の知らせがもたらされるはずの日、僕たちは朝からお祝いの準備をして待っていた。ところがスベン叔父さんと大叔母は昼になっても姿を現さず、陽が傾いてもなんの
ついに父さんが立ち上がり、帽子を摑んで出ていった。
母さんは料理を冷蔵庫にしまって僕にビーツとハムのサンドイッチを作ってくれた。僕は牛乳と一緒にそれを食べ、母さんと居間のソファに座って父さんの帰りを待った。母さんは水をほんの少し飲んだだけで、壁紙に散らばった小さなスミレの花のように
父さんが戻ってきたのは十時を過ぎた頃だった。シャツのボタンはちぎれ、帽子はなく、頭を
「銀行はスベンを採らない」
父さんの声はひどくかすれていた。
僕はすぐさま理由を尋ねた。その答えを聞くために一日を費やしたような気分だった。だが返ってきたのはこれ以上ないほど人を馬鹿にした回答だった。
「慎重な協議の結果であって、理由を話す必要はないそうだ」
父さんは説明を求めて銀行の人たちと
静まりかえった居間に虫の声が大きく聞こえた。
突然、父さんは
「なんでなんだ、なんでおまえは俺たちと違うんだ」
母さんはなにかが断ち切られたように
父さんは母さんを突き放し、大きなうめき声をあげると、ものすごい勢いで壁に自分の頭を打ちつけた。一度ではなく何度も。額が切れて血が
(つづく)
▼太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000901/(KADOKAWAオフィシャルページ)