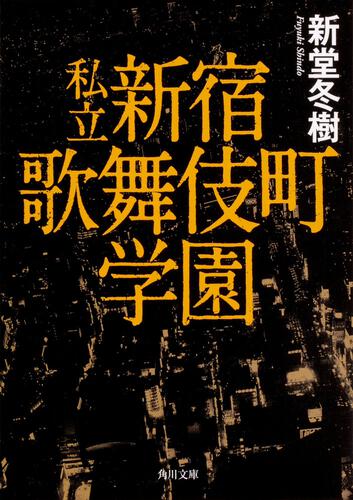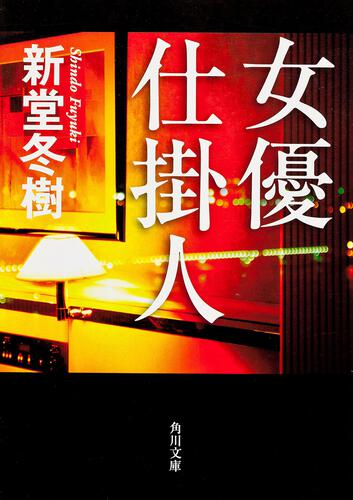【第9回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
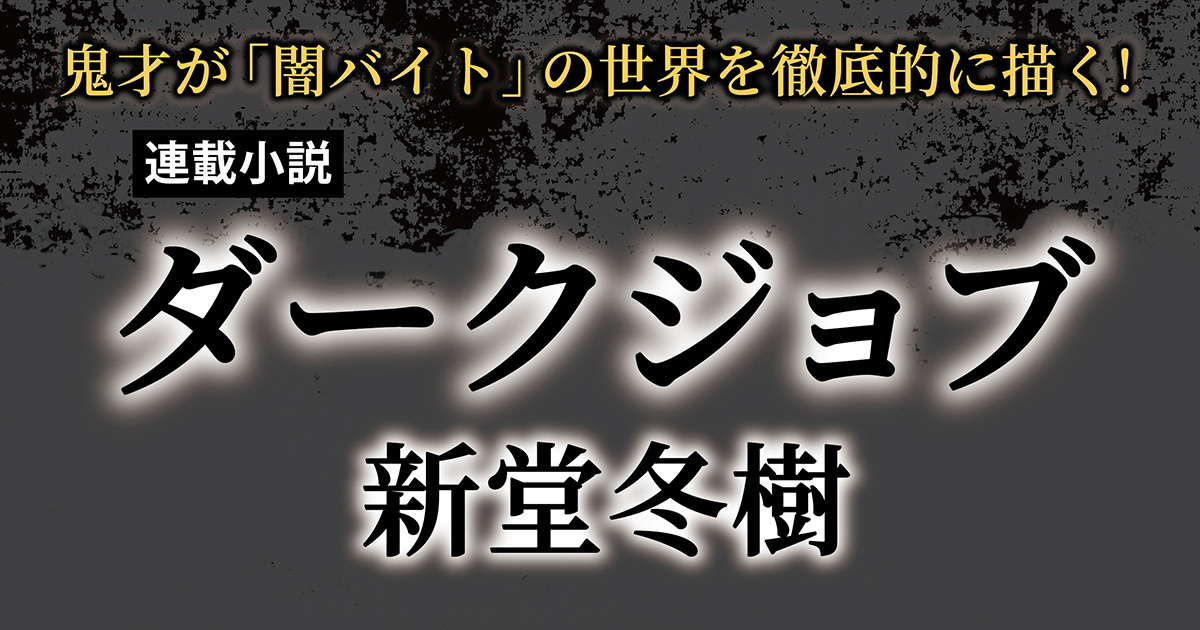
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第9回】新堂冬樹『ダークジョブ』
片桐★2000年夏
「会長はまもなくお見えになるので、少々お待ちください」
白のセットアップ姿の屈強なガタイの坊主頭の青年……部屋住みの若い衆が、応接テーブルに片桐と我妻の日本茶を置くと、頭を下げて部屋を出た。
「凄いですね。何畳あるんですかね?」
片桐は旅館の宴会場さながらの居間に視線を巡らせつつ言った。
ヤクザ映画に出てくる大親分の自宅のセットと錯覚しそうな、白熊、虎、ライオン、狼、豹の剝製や戦国武将の鎧兜が部屋の至る所に飾られていた。
「何畳かはわからねえが、敷地面積は一千坪を軽く超えてるって話だ。『極政会』の会長と言えば、関東一の大親分だ。これくらいの屋敷に住んでてくれなきゃ、下の者が夢を見れねえだろ?」
我妻が日本茶を啜りながら言った。
「赤坂の一等地に一千坪超えの屋敷なんて凄すぎますよ」
片桐は驚きを隠せなかった。
「お前、会長をこの程度の男だと思ってんのか?」
我妻が片桐を見据えた。
「え?」
「ここは別宅だ」
「別宅? ということは、本宅は別にあるんですか?」
片桐は身を乗り出した。
話を合わせたわけではなく、本当に興味があったのだ。
「ああ。八王子に一千五百坪の屋敷がある。そっちが本宅だ。まあ、八王子は交通の便が悪いから、実質的には赤坂邸が本宅みたいなもんだけどよ。ほかにもビルを五棟、マンションを十棟、リゾートホテルを五軒にラブホを二十軒以上所有してるぜ」
我妻が、自分のことのように自慢げに言った。
片桐は、腹の底からふつふつと沸き上がるものを感じた。
闇世界の頂点に上り詰めれば、こんなにも栄華を極めることができるものなのか?
「我妻、国税の犬にチクるつもりか?」
白い着流しに金の帯を巻いた白髪オールバックの男が、
「お疲れ様です!」
我妻が弾かれたようにソファから立ち上がると、膝に額がつくほどに頭を下げた。
こんな我妻の姿を見るのは初めてだった。
「お疲れ様です!」
片桐も慌てて立ち上がり、上半身を九十度曲げた。
「ひと風呂浴びてたところだ。待たせて悪かったな」
会長……阿東が虎の皮のラグマットが敷かれた専用ソファに腰を下ろした。
「なんだ、日本茶か? 気がきかねえな。いいブランデーが入ってたろ? 持ってこい」
阿東が坊主の青年に命じた。
「失礼しました!」
坊主の青年が頭を下げ、部屋を出た。
「いえ、俺ら、日本茶で十分です」
我妻が遠慮する姿を片桐は、長いつき合いで初めて見た。
「馬鹿野郎、血の代わりに酒が流れてる男がなに言ってんだ。若い衆にハンドル握らせてんだろ?」
「はい」
「だったら、変な遠慮するんじゃねえ。お、きたきた。いつもの感じで三つ頼む」
ブランデーを運んできた坊主の青年に、阿東が指示した。
坊主の青年がブランデーグラスではなく、ロックグラスを濃い琥珀色で染めた。
「西の兄弟分が贈ってくれてな。こいつは年代物で、軽自動車が買えるくらいの代物だ」
阿東が言いながら、ボトルを我妻に渡した。
「ルイ13世じゃないですか! こんな高い酒、本当にいいんですか!?」
我妻が叫んだ。
「お前も本家の若頭になったんだ。高い酒の味を知らないと恥かくぞ。ほれ」
阿東が、ブランデーをなみなみと注いだロックグラスを我妻に差し出した。
通常のブランデーグラスで飲む量の三倍はありそうだった。
「ありがとうございます!」
我妻が頭を下げたまま両手でロックグラスを受け取った。
「兄ちゃんも飲め」
阿東が我妻から片桐に視線を移し、ロックグラスを差し出してきた。
着流しのはだけた胸元から覗く和彫りの龍が、よく似合っていた。
「ありがとうございます!」
片桐も我妻に倣い頭を下げて両手でグラスを受け取った。
「とりあえず、乾杯しようや」
阿東がロックグラスを宙に掲げた。
口元は綻んでいるが、我妻と片桐に向けられる眼光は鋭かった。
「失礼します!」
片桐は我妻に続いて阿東のグラスにグラスを触れ合わせた。
「まず、半分だけ一気しろや」
「あれですね?」
阿東が言うと、我妻がニヤリと笑った。
「いただきます!」
片桐は言われたとおり、半分だけ飲んだ。
四十度を超えるアルコールが、喉を甘美に焼いた。
「グラスを出せ。これが俺流の飲みかただ。病みつきになるぞ」
阿東が悪戯っぽい顔で台形のボトルを傾けた――1800テキーラを注いだ。
「一気に行け」
阿東に言われるがまま、片桐はブランデーとテキーラのハーフ&ハーフを飲み干した。
食道から胃にかけて、強烈な刺激が通過した。
酒は強いほうだが、胃袋が燃えて頭がクラクラした。
我妻は呑み馴れているのか、平然としていた。
「どうだ? パンチあるだろ?」
阿東がニヤニヤしながら片桐に訊ねてきた。
「はい、内臓がカッカしてます」
片桐は苦笑した。
「会長がこの酒を勧めるのは、期待してる奴だけだ」
我妻が言った。
「え!? 本当ですか!?」
片桐は驚いてみせたが、わかっていた。
期待していなければ、阿東が構成員でもない片桐と会うはずがない。
「会長、改めて紹介します。こいつは、俺の企業舎弟の片桐です。優秀な奴なので、お見知りおきを。ご挨拶しろ」
我妻が片桐を促した。
「片桐と申します。我妻さんには、いつもお世話になっております。本日は、私みたいな者のためにお時間を作っていただきありがとうございます。伝説の大親分にお会いできるなんて、夢のようです」
片桐はソファから立ち上がり挨拶すると、深々と頭を下げた。
「顔を上げろ。ずいぶんと、我妻を儲けさせているらしいな」
阿東が満足そうに頷きつつ言った。
「いえ、私の仕事が順調なのは、我妻組長が睨みを利かせてくださっているおかげです」
片桐は謙遜した。
我妻が背後に控えているのはたしかに大きいが、代紋の威光を遥かに超える利益を運んでいるという自負が片桐にはあった。
「いい面構えしてるな。わしの正面に立っても、堂々としてるしな。昔のお前みたいだな」
阿東が我妻を見て笑った。
「俺より図太いかもしれませんよ」
我妻も笑った。
「いえ、本当は緊張で吐きそうです」
片桐が言うと、阿東と我妻が揃って大笑いした。
利益を与えているうちは恵比須顔だが、損失を与えた瞬間に鬼になることを、片桐は十二年前に学んだ。
この世界で生き延び、伸し上がって行くには人間性を捨てて金の亡者になるしかなかった。
あなた達を踏み台に、闇世界の頂点を取らせてもらいます。
片桐は心で誓った。
☆
片桐★2015年冬
六本木のタワーマンションのペントハウス――五十畳のリビングルームのソファで、片桐はコーヒーを飲みながらパソコンでネットニュースをチェックした。
正面では百十インチのテレビで朝の情報番組を流していた。
大理石のテーブルには朝刊と週刊誌が並んでいた。
世の中の流れをリアルタイムに把握するのが、片桐の毎朝のルーティンだった。
政治、経済、芸能、スポーツ、芸術、教育、医療、福祉……仕入れる情報のジャンルは問わなかった。
金のなる木は、どこに生えているかわからない。
世の中の流れを知らなければ、金の流れも掴めない。
金の流れを掴めないだけではなく、懲役を食らう可能性も高くなる。
「ヤミ金融対策法」が成立した二〇〇三年に片桐は既に、オレオレ詐欺へと軸足を移していた。
「ヤミ金融対策法」は翌年に施行されたのだが、そこから動くのでは遅い。
情報に疎い者は摘発され、摘発は免れても新ビジネスに乗り遅れてしまう。
オレオレ詐欺も初期に始めたグループが最も利益を上げていた。
後発者が増えて詐欺被害が広まるほどにマスコミに大々的に報じられ、被害者側の警戒心が強まるので成功率が下がってしまう。
ATMには振り込む前に注意喚起のメッセージが表示され、テレビCMではドラマ仕立てでオレオレ詐欺の手口を流すようになった。
それでも騙される者はいたが、初期の頃に比べれば難度が上がり利益率は大幅に下がった。
それに加えて、摘発されるリスクも高くなった。
闇金融に見切りをつけてオレオレ詐欺に
片桐はパソコンのディスプレイからテレビに視線を移した。
情報番組では、警視庁の捜査二課の元刑事がコメンテーターとして出演し、オレオレ詐欺への対処法を熱弁していた。
片桐は腰を上げ、サイフォンから新しいコーヒーを注ぎ窓際のリクライニングチェアに身を預けた。
五十五階からの街並みも、見慣れてしまった。
ステージアップするたびに、もっと高みを、もっと高みを……と飽くなき野望を燃やし続てきた。
片桐は眼を閉じ、記憶を十年前に巻き戻した。
あれは、我妻に初めて阿東の屋敷に連れて行かれてから五年後の出来事だった。
『どうしてあいつが呼ばれたんだろうな?』
『上納額は凄いかもしれねえが、幹部より先ってのは納得いかねえな』
『残り少ない貴重な時間なのに、なんであいつなんだ!?』
『会長の考えが理解できねえな』
大学病院の特別室前の待合室――我妻に続き阿東のもとに向かう片桐に、「極政会」の幹部の面々の不満の声が聞こえた。
『てめえらっ、ごちゃごちゃ文句言ってんじゃねえ! 会長の考えに不満垂れるなら、俺に面と向かって言えや! おお!』
我妻が待合室の幹部に怒声を浴びせた。
『若頭に文句はありませんよ。ただ、俺らもまだ会長の顔を見てないのに、どうしてフロントのこいつが先に呼ばれるんですか!? 俺らは会長の危篤の報せを受けてから、ずっと病院に詰めてるんですよ! それなのにやっと面会できるようになったと思ったら、幹部どころか構成員でもないこいつが真っ先に呼ばれるなんて、あんまりですよ!』
若頭補佐の武藤が、納得いかないとばかりに我妻に訴えた。
『だから、会長の考えがあってのことだと言ってるだろうが! それに文句を言うってことはよ、会長に盾突いてんのと同じことなんだよ! おおっ、こら! まだ文句あんのか!? ああ!?』
『いえ……すみませんでした……』
待合室に乗り込んだ我妻に詰め寄られた武藤がうなだれた。
『おめえらも不満垂れんじゃねえぞ!』
我妻はほかの幹部にも強く言い残し、待合室から出てきた。
『すみません、俺のせいで……』
戻ってきた我妻に、片桐は詫びた。
『お前が謝ることはねえ。とはいえ、あいつらの気持ちもわかるがな。親が死に際に、真っ先に駆けつけた息子たちより親戚を病室に招き入れたようなもんだからな』
我妻が渋い表情で言った。
『あの……会長はどうして、俺を最初に呼んだんでしょう?』
阿東は三ヶ月前に肝臓癌と診断されて入院し、手術で腫瘍を摘出して一時は回復に向かっていたが、肺への転移が判明し抗癌剤治療を受けていた。
頭髪は抜け落ち十キロ以上瘦せはしたものの、病状は小康状態を保っていた。
一昨日、阿東の容態が急変し、「極政会」の幹部が駆けつけたのだった。
『会長の口から語られるだろう』
我妻は言うと、足を踏み出した。
特別室の前に立っていた二人のボディガードが、我妻を認め弾かれたように頭を下げるとドアを開けた。
『お待ちしてました。どうぞ、こちらへ』
ソファに座っていた娘が立ち上がり、片桐と我妻に頭を下げて招き入れた。
阿東は骨と皮だけになり、枯れ枝のような腕には点滴の針が刺され、鼻には酸素を供給するための管が通されていた。
『お父さん、我妻さんと片桐さんがお見えになりましたよ』
娘が声をかけると、阿東が薄く眼を開いた。
『今日は、これでも体調がいいほうなんです。昨日までは、どんなに呼びかけても反応しませんでしたから』
娘が嬉しそうに阿東を見た。
阿東は十年以上前に妻と死別しており、血の繋がった家族は一人娘だけだった。
『お前は……外してなさい……』
阿東が掠れた声で言った。
『大丈夫なの?』
娘が心配そうに訊ねると、阿東が野良猫を追い払うように手を振った。
『なにかあったら、すぐに報せますから』
我妻が娘に退室を促した。
『そうですか……では、よろしくお願いします』
娘が頭を下げ、特別室を出た。
『片桐……』
阿東が片桐の名を呼んだ。
我妻が片桐の背を押した。
『会長、片桐です』
片桐は阿東の耳元で声をかけた。
『きたか……』
阿東が片桐をみつめ、蚊の鳴くような声で言った。
鷹のように鋭かった眼光は、すっかり弱々しくなっていた。
『会長、早く元気になって、また、あのブランデーテキーラを飲ませてください』
片桐は阿東の手を握り励ました。
言葉とは裏腹に片桐は、阿東の命の炎がまもなく消えることを悟った。
阿東が倒れれば、跡目は我妻になるだろう。
そうなれば、片桐の立場はさらに盤石なものとなる。
阿東にはなにかと目をかけてもらい、感謝はしていた。
だが、老いたライオンの率いる群れはいずれ滅びるものだ。
そうなる前に若く力のある獅子が群れを率いるべきだった。
『悪かった……』
『え? なぜ、私に謝るんですか?』
阿東の言葉の意味がわからず、片桐は訊ね返した。
『金を……騙し取ったブローカーは……ウチの枝だった……』
阿東が喘ぐように言った。
相変わらず、阿東がなにを言っているのか片桐には理解できなかった。
『金とは、なんの金でしょう?』
『娘の……移植の金だ……。山根という……フロント企業が……移植の金を奪った……』
『え……』
瞬間、片桐の脳内は白く染まった。
杏の心臓移植の三千万を奪ったのは、「極政会」の企業舎弟だったというのか?
『わしは……あとから知ったとはいえ……娘さんの命を……申し訳……なかった……』
阿東が激しく咳き込んだ。
『会長、とりあえずお休みください。あとは、私から説明しておきます』
呆然自失とする片桐は、我妻に腕を引かれて特別室を出た。
『会長をお願いします』
特別室の前のベンチソファに座る娘を、我妻が促した。
『あのとき、三千万を持ち逃げした私の命を奪わなかったのは、会長が絡んでいたからですね?』
片桐は掠れた声で訊ねた。
「斎藤組」の組員にリンチを受けていた片桐は死さえも覚悟していたが、突然、我妻に忠誠を尽くせば命を助けると言われた。
あのときはわけがわからなかったが、命が繋がるならばと我妻に従った。
『まあ、座ろうや』
我妻がベンチソファに腰を下ろした。
片桐も隣に座った。
『あのとき、本家から電話が入ってな。三千万の件は若頭補佐が絡んでることだから、お前を殺すなと。ブローカーを装った山根って詐欺師は、当時の若頭補佐の曽根の兄貴がケツを持ってた企業舎弟だった。庇うわけじゃないが、会長がそのことを知ったのはお前を初めて屋敷に連れて行った日の少し前だった。俺がお前の話をするついでに、そのことも会長の耳に入れたってわけだ。会長は、お前の娘を死なせたことにひどく胸を痛めてな。お前には、とくに目をかけてやれと言われたよ。因みに曽根の兄貴は八年前に肝臓癌で、山根は五年前に脳腫瘍で死んじまった。天罰というわけじゃねえだろうがな』
携帯電話のコール音が、片桐の回想を断ち切った。
片桐は眼を開けた。
ディスプレイに表示されているのは、組織でナンバー2の菊池の名前だった。
「何人集まった?」
電話に出るなり、片桐は訊ねた。
『現時点で合格者が十五人、保留が五人って感じです。合格者の内訳は、特殊詐欺経験者が十三人で闇金上りが二人です』
菊池が新ビジネスの起ち上げメンバー候補を報告してきた。
菊池は闇金融時代から片桐のもとで働き、オレオレ詐欺に軸足を移してからはかけ子、受け子を統括していた。
「予想通り、闇金組は劣勢だな」
片桐は言った。
『ええ、やっぱり、闇金組は荒事や現場には強いですけど、指示や管理は苦手なタイプが多いですからね』
片桐も菊池の意見に同感だった。
新ビジネスは、顔も素性も知らない者を募集して窃盗や強盗をやらせるつもりだった。
オレオレ詐欺も全国に被害者が増えて社会問題になり、警察と銀行が連携して防止策を強化したことでやりづらくなってしまった。
ターゲットの息子を
だが、イタチごっこを続けても先細りになると判断した片桐は、新ビジネスの準備に取りかかった。
オレオレ詐欺、振り込め詐欺でも儲けたが、ターゲットを騙すというハードルがあるぶん、失敗も多かった。
加えて、指示役と実行犯が通じているのでかけ子や受け子が摘発されたときに捜査の手が上にまで伸びてくるというリスクも高かった。
片桐が考えたのは、指示役と実行犯を完全に切り離すビジネスモデルだった。
そうすれば、実行犯が下手を打っても指示役は安泰だ。
詐欺ではなく窃盗と強盗にシフトしたのは、コストパフォーマンスがいいからだ。
オレオレ詐欺や振り込め詐欺は経験とテクニックが必要であり、かけ子も受け子も訓練しなければ戦力にならない。
その点、窃盗や強盗であれば度胸があればいきなり実行犯として使える。
ネックとなるターゲット選びも、詐欺時代に得た膨大な量の名簿を活用できる。
「新ビジネスは、非情さがより問われる。闇金や詐欺のときは人が死ぬことは皆無に近かったが、今回は違う」
片桐は言った。
『でも、強盗殺人になってしまえば量刑が格段に重くなってしまいますよ?』
菊池が懸念を口にした。
「実行犯は指示役の素性を一切知らない。仮に実行犯が捕まっても、指示役に被害は及ばない」
片桐は一切の情も躊躇もなく言った。
『新たなビジネスは、実行犯は使い捨てということですね?』
菊池が念を押してきた。
「そういうことだ。実行犯はターゲットの命を奪う非情さ、指示役は実行犯にターゲットの命を奪うように命じる非情さが必要になる」
『肝に銘じます』
「午後には事務所に顔を出す」
片桐は電話を切り、パーラメントに火をつけた。
勢いよく吐き出した紫煙を、片桐は冷え冷えとした眼で追った。
『金を……騙し取ったブローカーは……ウチの枝だった……。娘の……移植の金だ……。山根という……フロント企業が……移植の金を奪った……』
死に際の阿東の懺悔――あのとき片桐は、感情のスイッチを完全に切った……いや、切れてしまった。
娘の仇は、片桐が忠誠を尽くした組織のトップだった。
残酷な真実を告げた阿東は翌日に息を引き取り、金を奪わせた当時の若頭補佐とブローカーを装った山根は既に病死していた。
真実を知ったときには、討つべき仇は誰もいなくなっていた。
皮肉にも、移植金の三千万円を身内に騙し取られたおかげで片桐は生き残った。
笑い話にもならなかった。
知らなかったこととはいえ、憎んでも憎み切れない仇に片桐は十数年に亘り大金を運び続けていたのだ。
片桐は哀しみと怒りを封印すると同時に、感情を殺してしまった。
新ビジネスで効率と成功率を優先させるためにターゲットの命を奪うことも厭わない選択をしたことに、微塵の躊躇いも罪悪感もなかった。
人間性を捨てることが、片桐に唯一残された杏への贖罪だった。
「おはようございます」
香織がリビングルームに入ってきた。
「学校は?」
片桐は訊ねた。
腕時計の針は、午前八時を回っていた。
香織は、私立の高校に通っていた。
「お話ししたいことがあります」
抑揚のない口調、無機質な瞳……香織もまた、感情のスイッチが切れていた。
香織は、片桐の組織が狙っていたターゲットの娘だった。
振り込め詐欺時代に、相場師だった香織の父親がかなりの資産家だという情報を得ていた。
新ビジネスに向けての試運転の予定だったが、敵対組織に先を越された。
カモになる名簿は闇世界に出回っているので、ターゲットがバッティングすることは珍しくなかった。
敵対組織が撤収してからターゲットの家に入った片桐は、押し入れに隠れている姉と弟を発見した。
連れ帰ったのは、情ではない。
自分の組織の仕事なら、口を封じていただろう。
これから新ビジネスに乗り出すにあたり、徹底した闇世界の英才教育を施せば憎悪と復讐を胸に刻んだ姉弟は貴重な戦力として成長するという確信があったのだ。
姉はともかく、十一歳の弟の怜也には期待していた。
怜也は見込み通りの素材だったが、想定外だったのは姉の香織がそれ以上のポテンシャルの持ち主だったということだ。
頭の切れ、迅速かつ的確な判断、飲み込みの早さ……なによりも香織の冷静さと非情さには目を見張るものがあった。
二人を引き取り英才教育を始めてからほどなくして、片桐は香織と怜也の両親を惨殺した敵対組織の実行犯とボスを捕らえた。
片桐が痛めつけて半死半生にしたあと、香織と怜也にとどめを刺させた。
手を汚させたのは姉弟に肚を決めさせて後戻りできないようにするため……闇世界では、半端者は獲物にされてしまう。
二人とも、初の殺しとは思えないほどに肚が据わっていた。
とくに香織は、食材を切るとでもいうようにあっさりと仇の喉をナイフで裂いた。
香織は返り血で赤く染まった顔で、崩れ落ち事切れる仇を無表情に見下ろしていた。
それを見た片桐は、女ではあるが香織を後継者として意識するようになった。
「学校が終ってからではだめなのか?」
「はい。できれば、いま、お話ししたいです」
「座れ」
片桐はリクライニングチェアから立ち上がり、クロムハーツのソファに香織を促した。
「話って?」
片桐は、香織の正面に腰を下ろしつつ訊ねた。
「学校をやめさせてください」
香織が冷静な口調で切り出した。
「やめてどうする?」
片桐に驚きはなかった。
むしろ、このときを待っていた。
「新しいビジネスに私を参加させてください」
香織は、片桐が予期していた通りの言葉を口にした。
「俺は親じゃない。闇世界に足を踏み入れる以上、たとえお前でも俺に不利益を与えたら処分の対象だ」
片桐は氷の瞳で香織を見据えた。
「わかっています。私が足手纏いになったら、すぐに処分してください」
香織はまったく動じるふうもなく即答した。
沈黙が空間を支配した――氷の瞳と氷の瞳が交差した。
「新ビジネスで本名は使えない。俺が香織と呼ぶのも今日までだ」
片桐は沈黙を破った。
「氷のように美しく冷酷な花になれ。いまからお前の名前は氷花だ」
片桐は香織が眉一つ動かさずに仇の喉笛を裂いたときに頭に浮かんだコードネームを告げた。
香織……氷花が頷いた。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/