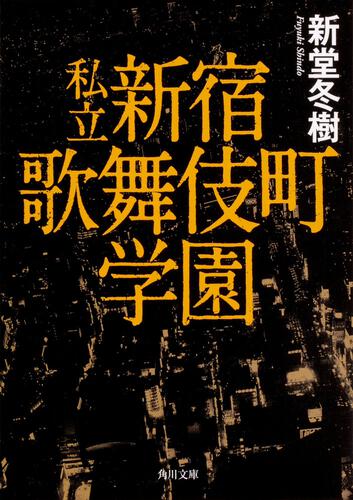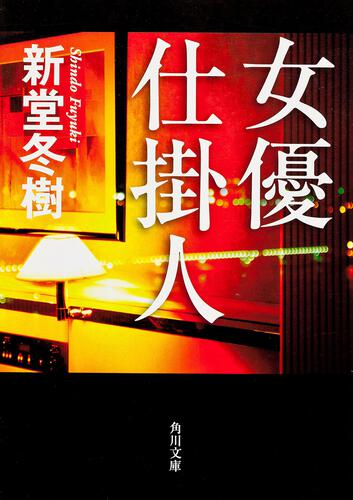【第8回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
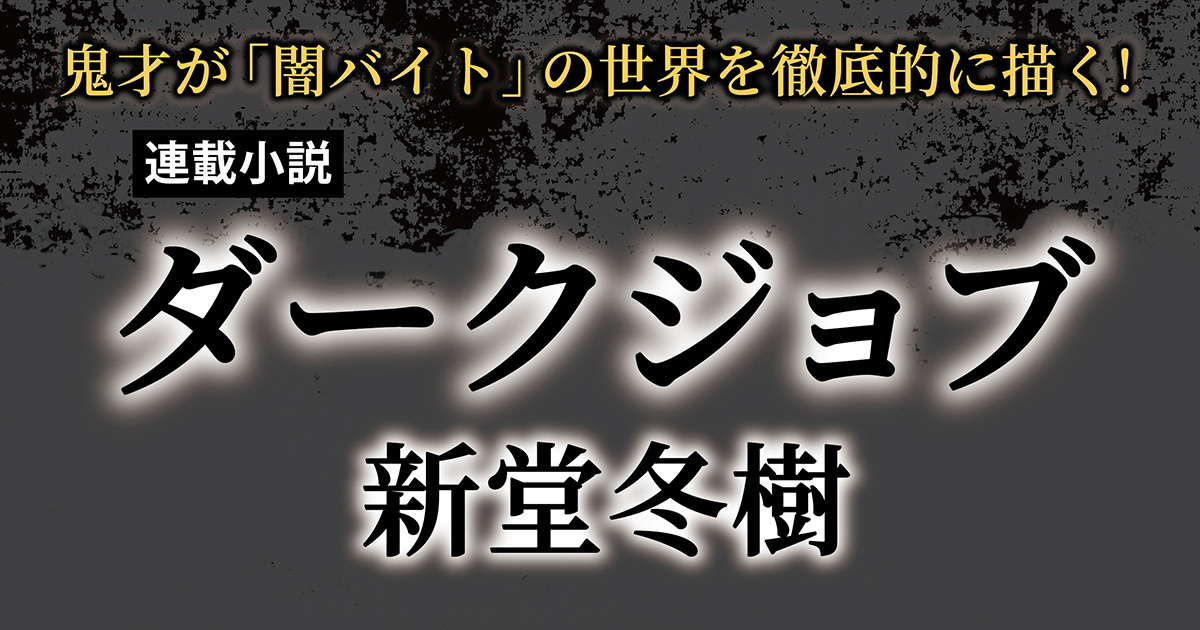
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第8回】新堂冬樹『ダークジョブ』
若宮★2025年夏
若宮は、ヴェルファイアの後部座席に座っていた。
隣には氷花、運転は黒スーツに黒髪をポニーテールにした青年がしていた。
まだ若く、若宮とそう変わらないような歳に見える。
モデル並みの甘いマスクをしていたが、ときおりルームミラー越しに合う眼は猛禽類のように鋭かった。
「弟のレイよ」
スマートフォンを操作していた氷花が、ディスプレイに視線を向けたまま素っ気なく言った。
「え!? 氷花さんの弟さんなんですか?」
若宮は驚きの声で訊ねた。
「二人とも、ボスに拾って貰ったの。もしボスを裏切ったら、すぐにレイがあなたを処分するから」
氷花がさらりと言った。
それが余計に怖かった。
実際に氷花は、ミスしたコングを毒殺するよう眉一つ動かさずに部下に命じた。
レイも姉と同じで、ただならぬ雰囲気を醸し出していた。
どういう経緯で姉弟がボスのもとで働くことになったのかはわからないが、恩を感じているのは伝わってきた。
「絶対に裏切ったりしませんから……」
若宮は言った。
「裏切りますって言う人はいないわ。結果的に裏切った人間を、レイは三人処分してるから。私と同じで、ボスのためならレイは躊躇なく命を奪えるわ」
若宮の腕に鳥肌が立った。
裏切る気は毛頭ないが、ミスをする可能性はあった。
下手を打てば、コングのようになってしまうのだろうか……。
現場から離れることができて、正直、安堵している自分がいた。
考えが甘かった。
管理側に入るということは、より組織の内部を知ることになる。
最悪、裏切ったりミスをしたりしなくても、用が済めば口封じのために消される可能性があった。
「氷花さんと弟さんも、最初は僕と同じような立場だったんですか?」
若宮は思い切って訊ねた。
レイはともかく、少なくとも氷花は処分される側ではなく処分する立場だ。
生き延びるためには、氷花の位置まで……ボスの右腕まで上り詰めるしかない。
「もっとひどかったわ」
氷花の視線は相変わらずスマートフォンに向けられたままだった。
「もっとひどいって……」
「とにかく、結果を出しなさい。あなたは、結果を出してボスに認められることだけを考えていればいいの」
若宮を遮るように、氷花が言った。
やはり、そうだった。
ボスに認められるしか、生き残る道はないのだ。
「あの……どこに行くんですか?」
不安に拍車がかかり、若宮は訊ねた。
赤坂の雑居ビルを出てからヴェルファイアに乗せられ、二十分くらい走っていた。
スモークフィルム越しの車窓に流れる景色は、渋谷の街だった。
「すぐにわかるわ」
氷花が意味深に答えると、ヴェルファイアが裏道に入りスローダウンした。
しばらくすると、ヴェルファイアは雑居ビルの前で停まった。
スライドドアを開けて、氷花が無言で車を降りた。
「降りろ」
初めて、レイが口を開いた。
若宮が車を降りると、レイが背後にピタリとついた。
氷花とレイに挟まれるようにして、若宮は雑居ビルの薄暗いエントランスに足を踏み入れた。
視界に入ったメイルボックスには、商事、興業といったアンダーグラウンドのにおいがする怪しげな名前の会社が並んでいた。
氷花は地下へ続く階段を下りた。
「サブボスに迷惑をかけるな」
耳元でレイがボソリと言った。
「サブボス? お姉さんのことですよね?」
若宮は振り返り確認した。
「サブボスの顔に泥を塗ったら俺が殺す」
姉と同じ一切の情を感じさせない氷の瞳に、背筋が凍てついた。
レイの言葉から、姉への深い思いが伝わってきた。
単なる姉弟愛とは違う、もっと深いなにか……。
「わかってます。生き延びるために、死に物狂いでやります」
若宮は、レイにというより己を鼓舞するために言った。
氷花がドアの前で足を止め、スマートフォンを耳に当てた。
ほどなくすると解錠音に続き、紺色のスーツを着た男がドアを開けた。
若宮は、ドアの分厚さに驚いた。
テレビで見たことのある、銀行の金庫の扉のようだった。
声が外に漏れないように改造したに違いない。
「お疲れ様です。どうぞ」
紺色スーツが頭を下げ、氷花を招き入れた。
氷花に続き、若宮も玄関に足を踏み入れた。
デスクに座った男達が、視界に飛び込んできた。
十人はいるだろうか。
インカムをつけて指示を出している者、スマートフォンを操作している者がいた。
全員がビジネスマンのような紺色のスーツを着用し、各々のデスクには複数のスマートフォンが並べられていた。
「子供は別居で、六十代の夫婦が二人で住んでいる。隣の家まで五十メートルあるから声は聞こえない。ただ、中型犬の番犬がいるから、最初に毒餌を食わせて殺せ。殺鼠剤を使った毒餌の作りかたはネットに出ているから調べておけ。五百万以上の箪笥預金があるのは間違いない。金の在処は、ババアを殴ってジジイに吐かせろ。ジジイが金の在処を言う前に、ババアを殺さないように気をつけろ。ジジイに激しく抵抗されたら、ババアへの見せしめのために殺せ」
三十代と思しきガタイのいい指示役が、無感情に指示していた。
これまで指示される側だった若宮が、指示する側にいることが不思議だった。
「犬の種類なんか知らねえよっ。三田エリカで検索したらAVの画像がたくさん出てくるから顔をチェックしろっ」
スーツのボタンが弾け飛びそうなアンコ型の体形をした指示役が、インカムのマイクに怒声を浴びせていた。
「いいか!? ターゲットは毎朝六時頃に散歩に出かける。その時間は人の出入りも少ねえから、拉致るには好都合だ。オートロックの暗証番号と金の在処を吐かせて、キーを奪え。部屋に行くのは斉藤で、佐山は車にターゲットを監禁しておけ。騒いだら顔を傷つけると脅せ。抵抗したら顔を切り刻めや」
アンコ型の指示役の指示を聞いた若宮は、現場を離れることができて助かったと改めて思った。
ここにいる指示役達は、実行役を比喩ではなく使い捨ての駒としか考えていない。
実行役には顔も名前も知られていないので、警察に捕まっても痛くも痒くもないのだ。
だからこそ、指示役は実行役に平気でターゲットを殺せと命じることができる。
これからは、若宮も指示役に回る。
自分にできるだろうか?
自ら手を下さないとはいえ、殺せ、傷つけろと命じることができるだろうか?
「こっちにきて」
氷花がフロアの奥に若宮を促した。
ドアを開けると、五坪ほどのスクエアな空間が視界に広がった。
通常サイズの二倍はありそうな特大デスクがあり、デスクには五台のモニターが並んでいた。
ほかには、なにもなかった。
「踏み込まれたときのことを考えて、必要最低限のものしか置いてないわ」
また、若宮の心を見透かしたように氷花が言いつつ特大デスクに座った。
若宮はスチールチェアに腰を下ろした。
「彼らはみな、マニュアルを基本にそれぞれアレンジして指示を出してるの。因みに、マイクにはボイスチェンジャーが装着してあるし、スマホはトバシだから指示役の足がつく心配はないから」
氷花がモニターに映る指示役を監視しながら言った。
「マニュアルってなんですか?」
「まずは実行役の性質と精神状態を探る。臆病か強気か? 冷静か感情的か? 情に厚いか無感情か? 臆病で罪悪感を持ちやすいタイプなら、現場で足手
氷花が、まるでファストフード店のマニュアルを説明するとでもいうように、残酷な言葉を淡々と口にした。
このマニュアルも、恐らく氷花が考えたのだろう。
「現場より精神的に楽だと考えたりしないように」
唐突に、氷花が言った。
「情は一切捨てなさい。指示役の迷いは実行役に瞬時に伝わるわ。任務が成功するも失敗するも、指示役次第よ」
氷花は言いながら、ポリグラフが内蔵されているかのような無機質な瞳で若宮の反応を窺っていた。
「ターゲットを殺せと命じるのは、通報されないためですよね? 通報されても、逮捕されるのは実行役で指示役にまで捜査の手が伸びないのなら、口封じをしなくてもいいんじゃないですか?」
若宮は思い切って訊ねた。
納得できる答えが返ってくるとは思わなかったが、それでも訊ねずにはいられなかった。
「一つはマニュアルにあったように、ターゲットを殺せと指示する目的は、二人の場合は一人に恐怖を与えて従順にするため、一人の場合は実行役に後には引き返せない状況に追い込むためよ。足を洗いたいとか、自首したいとか。殺人犯になったら、もう覚悟を決めるしかないでしょう? 一人目より二人目、二人目より三人目と慣れてくるものだから」
氷花が一ミリの罪悪感もなさそうな涼しい顔で答えた。
やはり、予想した通りの答えだった。
氷花が、どれだけ苛烈な人生を送ってきたかはわからない。
逆に、どれだけ苛烈な人生を送れば彼女のように人間性を失えるのだろうか?
「もし、氷花さんの両親が目の前で闇バイトの実行役に殺されたらどうしますか? 心が痛みませんか?」
無意味な質問――わかっていた。
わかっていたが、知りたかった。
氷花がなぜ、悪魔に魂を売ったのかを……。
「ターゲットは私の両親ではないから、心は痛まないわ」
予想通りの答えが返ってきた。
「自分に関係のない人間の痛みは、わからないというやつですか?」
若宮は皮肉交じりに言った。
「痛みはわかるわよ。私の両親も、目の前で押し込み強盗に惨殺されたから」
氷花が他人事のような冷静な口調で言った。
「えっ……」
若宮は絶句した。
「私とレイは、押し入れに隠れていたの。襖の隙間から覗いていたんだけど、父も母もハンマーで頭蓋骨を割られて脳みそが溢れていたわね。強盗が出て行ったあとに、私達は押し入れの中で震えていた。哀しいという感情よりも、恐怖しかなかったわ。腰が抜けて押し入れから出ることができなかった。私とレイの失禁のアンモニア臭は、いまでも忘れられないわ」
氷花がモニターに視線を向けたまま言った。
「そんなとき、いきなり押し入れの襖が開いたの。強盗とは違う男の人が立っていて、無言で私達をみつめていたわ。どうしようもなく暗い瞳が印象的だった。その人は、仇を討ちたいならついてこい、と言った。敵か味方かわからなかったけど、私はレイの手を引き男について行ったわ」
悪夢の記憶のはずなのに、氷花は他人事のように語った。
「まさか、その男の人って……」
若宮の脳裏には、ある一人の男の顔が浮かんでいた。
「そう。ボスよ」
予想が当たった。
だが、若宮の中で大きな疑問が浮かんだ。
「氷花さんの両親を殺した押し込み強盗って、ボスの仲間じゃないんですか?」
「ボスは否定した」
「え? でも、そのタイミングで家の中にいたというのは強盗の仲間ってことですよね?」
「ボスがウチに強盗目的で入ったのは事実よ」
氷花がさらりと言った。
「え!? やっぱり両親の仇ってことですよね?」
若宮は驚き、質問を重ねた。
「ボスは、私の両親を殺した強盗の組織とは別の組織だったの。つまり、現場がバッティングしたということよ」
あくまでも、氷花の口調は他人事だった。
「そうだとしても、ボスは氷花さんの自宅に強盗に入る予定だったわけですよね? そんな人に、よくついて行きましたね」
「でも、結果的に強盗に入らなかったわ」
「そういう問題ですかね」
若宮には、氷花の考えが理解できなかったし理解しようとも思わなかった。
「あなたがいままで好印象を抱いてきた人たちも、状況と時代が違えば
氷花が言った。
「それはそうでしょうけど……」
「それに、ボスは約束を守ってくれた」
「え?」
「両親を殺した強盗二人と組織のボスの頸動脈を、私とレイの目の前で切ってくれた。弱らせてから、私達に止めを刺させてくれたわ」
氷花がモニターに眼を向けたまま、酷薄な笑みを浮かべた。
「ボスは両親の仇を取ってくれた恩人よ」
「それで、この世界に入ったんですか?」
若宮は信じられない思いで訊ねた。
たしかに、恩人かもしれないしボスが仇を取ってくれたのも事実だ。
だが、若宮は氷花のボスにたいしての忠誠心に違和感を覚えた。
「私達姉弟は、あのときに死んだも同然。少なくとも、両親とともに心は死んだ。新しい人生では、ボスに恩返しすることを誓ったわ」
氷花の瞳からも声からも、まったく感情が伝わってこなかった。
両親とともに心は死んだという氷花の言葉に、若宮は妙に納得した。
氷花の言動からは、人間性のかけらも窺えなかった。
「あなたも、今日、この瞬間から心を殺しなさい」
氷花が若宮のほうに向き直り、唐突に命じてきた。
「感情を捨てろということですか?」
「そういうこと。この世界で生きて行く上で情は不要よ。ターゲットに情をかけたら、警察に捕まるだけ。実行役も同じ。使い捨ての消耗品程度に考えなさい」
「消耗品……」
若宮は呟いた。
ついこないだまで自分が実行役だったので、複雑な思いだった。
「実行役にたいしては、いかに速やかに確実にお金を運ばせるかだけを考えて。そのためにターゲットを殺せと命じるし、躊躇したり拒否したりしたら見せしめとして彼らの家族に危害を加えなければならないし。闇バイトの応募は日に五十件以上入ってるから、実行役の替えはいくらでもいるのよ」
氷花が微塵の罪悪感もなく言った。
「わかりました」
まったく納得できなかったが、口にはしなかった。
口にしたところで、状況はなにも変わらない。
それ以前に、氷花に処分されるだろう。
虎穴に足を踏み入れた以上、虎として生きるしかない。
「まず、あなたにやってもらうことは応募者への対応よ」
氷花は言うと、タブレットPCをデスクに置いた。
「あなたも見覚えがあるでしょう?」
ディスプレイに表示されたフォーマットは、若宮が応募するときに入力したものと同じだった。
「本人のデータはもちろんだけど、同じくらい重要なのは家族、親戚、恋人、友人のデータよ。でたらめを書く可能性があるから、必ず裏を取ること」
「裏を取る?」
言葉の意味がわからず、若宮は
「書き込まれたところに、職場の同僚や営業を装って電話を入れるの。住所はグーグルマップでチェックよ。この段階ででたらめを書き込んでいる応募者は不採用ね。こういう人間は、金品をごまかしたり奪って逃げようとしたり必ず問題を起こすから。処分するにも労力が必要だから、不採用にするのはリスクヘッジというやつね」
「優秀な実行役は、指示役にするんですか?」
「それはないわ。実行役と指示役は完全に別物だから」
氷花が即答した。
「別物?」
若宮は首を傾げた。
「何度も言うけど実行役は使い捨ての消耗品。強盗、傷害、殺人……現場を重ねるほどに罪状が増えて指名手配される実行役はウイルスと同じよ。伝染病にかかった人間を部屋に招き入れないでしょう? だから、実行役がどれだけ実績を積んだとしても指示役にすることはないわね」
氷花が無表情に言った。
「じゃあ、どうして僕は使い捨てられずに指示役に回されたんですか?」
若宮は、ずっと引っかかっている疑問をぶつけた。
「ボスから理由は聞いたでしょう?」
「僕が昔のボスに似てるということですよね? ターゲットを殺せと命じて実行役を使い捨てにするような組織のボスが、そんな理由で指示役に回しますか? それに、実行役は警察に眼をつけられているウイルスなんですよね? リスクしかないじゃないですか?」
若宮は、胸に
ボスがそんな甘い男とは思えないのだ。
「そうね。あなたを指示役にするのはリスクが大きいわね」
あっさりと、氷花が認めた。
「やっぱり、そう思いま……」
「私達のときも、そうだったわ」
氷花が若宮を遮り言った。
「え?」
「私とレイを引き取ったのも、リスクでしかなかったはずよ。使い物にならないだけじゃなく、被害者の行方不明になった子供を捜索する警察の捜査線上に上がる可能性もあったわけだから」
「たしかに、そう言われればそうですね。どうして、そんなギャンブルみたいなことをしたんでしょうか?」
若宮は訊ねた。
知らず知らずのうちに、ボスに興味を引かれる自分がいた。
「ボスの中ではギャンブルじゃなくて、投資だったのよ。私達やあなたが、組織に利益を生み出すポテンシャルを秘めていることを見抜いていたんじゃない?」
自分が、組織に利益を生み出すポテンシャルを秘めている?
まったく、ピンとこなかった。
実行役のときも、頭脳も度胸も突出したものがない若宮はむしろ足手纏いだった。
ボスがリスクを背負い投資するだけの価値が自分にあるとは思えなかった。
「こっちにきて」
氷花が席を立ち部屋を出ると廊下を奥に進んだ。
「ここが、あなたの部屋よ」
氷花が突き当りのドアを開けながら言った。
二十畳ほどのフローリング床の洋間に、二台の二段ベッドが設置してあった。
「四人部屋だから。今日からここで暮らしてもらうわ。必要なものがあればこれで用意して」
氷花が封筒を差し出してきた。
「ありがとうございます。え!? こんなにいいんですか!?」
封筒を受け取った若宮は、十万円も入っていたことに驚きの声を上げた。
「勘違いしないで。これは貸し付けよ。あなたが仕事を覚えて配当をもらえるようになったら引くから」
氷花がにべもなく言った。
若宮は
「あの、配当っていつから貰えるんですか?」
どの道引き返せないのなら、桁違いの金を稼ぎ母親に楽をさせてやりたかった。
「それはあなた次第よ。まずは応募者への対応がきちんとできるようになってから実行役に指示ができるようになるの。担当した指示役の間で成功報酬を山分けするわけだけど、配分は貢献度によってケースバイケースね。まあ、配当を貰えるようになるまで時間がかかるから、それまでは五千円の日当が出るわ」
「たったの五千円ですか!?」
若宮は素っ頓狂な声を上げた。
まともな職では得ることができないような大金を稼ぐために身を投じた闇バイトの世界だというのに、日当五千円とは時給千円にも満たない金額だ。
「衣食住完備だから、十分でしょう。弱者が嫌なら、人間性を捨ててすべてを呑み込む闇になりなさい」
氷花の言葉が、若宮の心を貫いた。
負け犬の人生――なにをやっても長続きせず、中途半端に放り出してきた。
実行役のときもそうだ。
闇世界に足を踏み入れていながら、都合のいい理性や良心を理由にブレーキをかけてきた。
いっそのこと、岩田のように振り切ったほうがましだ。
いままでは表世界だったので嫌になれば放り出すことができたが、今度は違う。
逃げ出そうとしたら、命を奪われてしまう。
逃げ出せたとしても、母親に危害を加えられてしまう。
漆黒のサバンナで生き抜くには……。
「わかりました。頑張ります」
若宮は決意を込めた瞳で氷花を見据えた。
誰よりも獰猛な獣になるしかない。
☆
「老人や女性でも殴ることはできますか?」
インカムのマイク越し――若宮は実行役の清水という若者にボイスチェンジャーで変えた平板な声で訊ねた。
指示役側に回ってからの二ヶ月間、感情を封印することを心掛けてきた。
とくに実行役に指示を出すときは、スイッチを切るように努力した。
『老人と女性ですか……? できれば、殴りたくないです』
清水の言葉に、共鳴しそうになる自分がいた。
「ターゲットの家には、七十代の母親と四十代の出戻りの娘が住んでいます。金の在処を吐かせるために、どちらかを殴る必要があります」
ターゲットがお前の母親なら、同じように言うのか?
声がした。
『金がどこにあるかを訊き出せたら、殴らなくてもいいですか?』
清水が食い下がった。
若宮は、清水に実行役時代の己を重ねた。
「タタキは時間との戦いです。数秒でも早く吐かせるためにどちらかを殴ってください。時間短縮だけが目的ではなく、残ったほうに恐怖を抱かせ従順にする目的もあります」
若宮は心の声を無視して抑揚のない口調で命じた。
ここで従わなければ、見張り役と交代させたほうがいいのかもしれない。
『わかりました……』
清水が渋々従った。
「母親は銀行不信で、一千万以上の箪笥預金があると情報が入ってます。すぐに在処を吐いても金額を少なく言う可能性があります。だから、余計なことを考える余裕がなくなるようにまずは殴ってください」
『もし一千万なかったらどうしますか?』
清水が怖々と訊ねてきた。
「こちらの情報に間違いはありません。最低一千万はあるので心配しないでください」
マニュアルには、金額については確信がなくても言い切ること、とあった。
自信のない言いかたをすれば、実行役が金をごまかす可能性があるからだ。
『わかりました』
「終わって車に乗ったらすぐに連絡をください。わかっていると思いますが、怖くなって逃げ出したりお金をごまかしたりしたら、清水君のご家族に危害が及びます」
『そんなことしませんから、親父やお袋には手を出さないでください! お願いします!』
清水の懇願に、若宮の胸が疼いた。
すぐに、意識を切り替えた。
「こちらの言う通りにすれば、問題はありません。では、電話を代わってください」
その後、もう一人の実行役の新田と見張り役の野村にマニュアルに沿った指示を与えて電話を切った。
若宮は大きく息を吐いた。
先月から実行役に指示を出すようになって、清水のチームで三件目だった。
過去二件の成果は四百万円と二百五十万円で、若宮は合わせて六十万円の配当を手にしていた。
このペースで行くなら、月に十件をこなせば三百万円を手にできる計算になる。
堅気の仕事では、とても稼げる額ではなかった。
「ずいぶん、慣れてきたじゃねえか」
初日にいたアンコ型の指示役……室橋が、若宮の肩を叩いた。
室橋は実行役にたいしても言葉が荒々しく、見た目もオールバックに口髭を蓄えているので怖いイメージがあったが、話してみると気さくな男だった。
ほかの八人の指示役は、それぞれ実行役や応募者とやり取りをしていた。
室橋は四人部屋の同室で、氷花から若宮の監視とサポートを任されていた。
「いえ、マニュアル通りに指示するので精一杯です」
若宮は言った。
「三件目にしちゃ上出来だ。俺なんて、最初の頃はマニュアル見る余裕もなかったからよ。だから、アドリブってやつだ」
室橋が豪快に笑った。
「甘やかさないで」
奥の部屋から現れた氷花が、室橋に冷え冷えとした声でダメ出しした。
氷花は指示役の仕事ぶりをモニターでチェックしているのだ。
「用が済んだら殺せと、なぜ指示しないの?」
氷花が若宮に冷眼を向けた。
「すみません、実行役が殴るのも躊躇っていたので……」
「だったら殺せる実行役に指示すればいいでしょう?」
若宮を遮り、氷花が言った。
躊躇ったのは自分も同じだった。
「もし、この任務に失敗したらいままでの配当を没収するから」
無感情に言い残し、氷花が奥の部屋に消えた。
「おお、怖っ。相変わらず、冷血だな。ま、気にするな」
室橋が小声で若宮を慰めた。
清水のチームのスマートフォンが鳴った。
電話を切って十分。恐らく結果報告だろう。
これ以上長くても短くても問題……ちょうどいい時間だ。
「終わりましたか?」
早鐘を打つ鼓動――若宮は平静を装い訊ねた。
『はい……』
清水は激しく息を切らしていた。
「いくらですか?」
『一千二百万です……』
若宮は安堵した。
だが、清水の声が暗く震えているのが気になった。
「ごくろうさまです。では、指定した銀行口座に……」
『おばあちゃんと娘を、殺してしまいました!』
清水が叫ぶように言った。
「えっ……」
若宮は絶句した。
『金を奪って逃げようとしたときに大声で騒がれて……もう、なにがなんだかわからなくなってしまって……』
スマートフォン越しに、清水が激しく取り乱した。
若宮は気を落ち着かせるために深呼吸した。
「よくやりました。これで、もう、後には引けませんね」
若宮は必死に冷静さを装い清水に言った。
己に、向けた言葉だった。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/