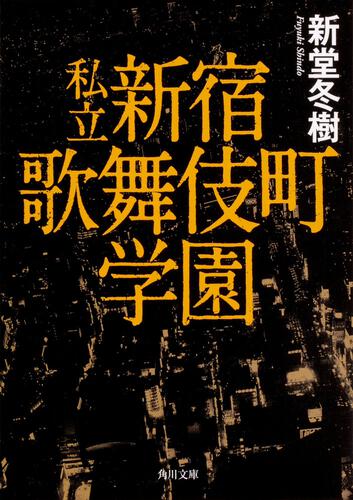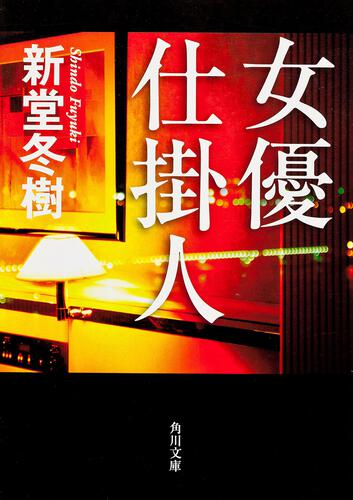【第7回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
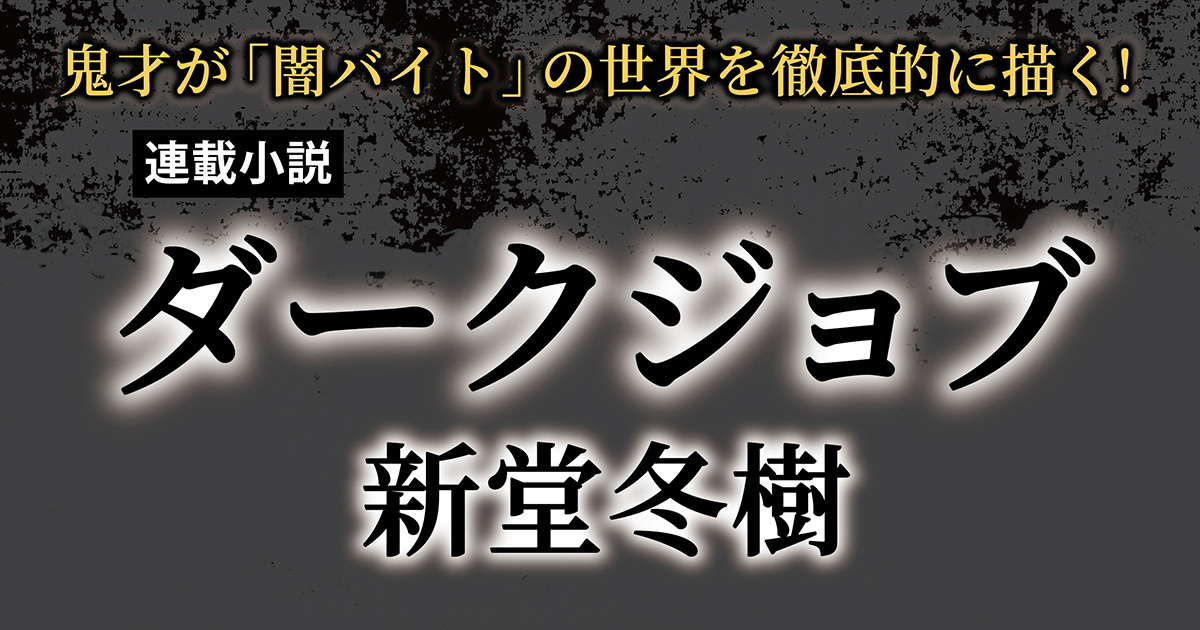
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第7回】新堂冬樹『ダークジョブ』
片桐★2000年夏
「あ、お袋? 俺だけど……正人だよ。え? 声? ああ、昨日も言ったけど扁桃腺がやられちゃってさ。そんなことより、大変なことになってさ」
片桐がリビングルームに足を踏み入れると、かけ子の正人役の三田以外の三人……それぞれのデスクに座っていた村浜、山井、マリが立ち上がり頭を下げてきた。
早朝だが窓にはブラインドが下ろされ、外からは様子を窺えないようになっていた。
フローリング床のリビングルームには、スチールデスクが二台ずつ向かい合っていた。
ほかには休憩用のロングソファ、キッチンには冷蔵庫と電子レンジが設置してあった。
ハコと呼ばれるアジトは、ここ赤坂を含め、新宿、池袋、渋谷の四カ所あった。
赤坂のハコの間取りは1LDKで、十畳のリビングダイニングキッチンにAグループの四人、八畳の寝室にBグループの四人に分かれて作業していた。
片桐はロングソファに腰を下ろし、三田とターゲットのやり取りに耳を傾けた。
「つき合っていた女の人がいたんだけど、その女の人が結婚しててさ……。もちろん俺は知らなかったし、彼女も独身だと言ってたんだ!」
三田が切迫した声でマニュアルのセリフを口にした。
三田は最年少の二十三歳、前職はキャバクラのボーイでキャリアは三ヶ月だった。
最初の頃は声も硬く口調もぎこちなかったが、かけ子の場数を踏むうちにかなり成長していた。
三十七歳の片桐と同い年の村浜はAグループのリーダーでキャリアは二年、前職は健康食品のキャッチセールスマン、山井とマリは二十七歳でキャリアはともに半年、前職はそれぞれ自衛官と保険会社の外交員だった。
「昨日、いきなり部屋に旦那さんが乗り込んできて、俺の妻に手を出すなんてどういうつもりだ、明日、弁護士さんと一緒にお前の会社に行って慰謝料を請求するって……そんなことされたら、俺、会社をクビになってしまうよ」
三田が半べそ顔で言った。
人妻に手を出してしまい追い詰められている絶体絶命のサラリーマンの役に、完全に入り込んでいた。
「旦那さん側の弁護士さんが言うには、人妻だと知らなくて関係を持ってしまったことに情状酌量の余地があるから、示談金を支払うなら会社には内密にしてもいいって。うん、旦那さんが雇った弁護士さんにそう言っているんだって。それで、明日までに四百万を旦那さん側の弁護士さんの口座に振り込まなければならないんだ。そう、そう、そういうこと。示談金の四百万を支払えば会社をクビにならないんだけど、俺の貯金は百万しかなくてさ……。本当に申し訳ないんだけど、不足分の三百万を弁護士さんの口座に振り込んでもらえないかな?」
三田が携帯電話を耳に当てたまま、頭を下げていた。
「で、実はいま、旦那さん側の弁護士事務所にいるんだけど、弁護士さんに電話を代わってもいいかな?」
三田が弁護士役の山井に左手でオーケーサインを作りながら言った。
今週の仕事は明日が最終日なので、心なしか三田の表情も生き生きとしていた。
AグループとBグループの八人は日曜日の夕方にハコに入り、金曜日の夕方に解放される。
つまり、金曜日の夕方から日曜日の夕方までが完全休養日ということだ。
だが、保険証、免許証、パスポートの類は預かり、家族の住所や職場を押さえているので逃げることも自首することもできない。
片桐自身、我妻のもとで働いていたときに、最初の頃は同じように雁字搦めにされていた。
かけ子の八人がハコ入りしてまずやることは、「アポ電」だ。
「アポ電」とは名簿屋と呼ばれる闇業者から仕入れた名簿のターゲット候補に、日曜日の午後六時から午後十時まで準備段階の電話をかけることだ。
闇名簿には、一人暮らしのターゲット候補の氏名、年齢、自宅住所、経済状況、別居する子供の氏名、年齢、勤務先が書いてあった。
【俺(私)だけど、扁桃腺が腫れたから明日病院に行く。携帯電話の番号が変わったから、新しい番号をメモしておいて】というマニュアルに書いてあるセリフをもとに、四時間で一人当たり二百人をノルマに電話をかけまくる。
翌朝から開始する本番で、息子、または娘の声の感じが違ったり、かかってきた電話番号が違ったりしても疑われないというわけだ。
もっとも、それは「アポ電」を信じたターゲットにかぎっての話だ。
「アポ電」の段階で不審に思われたり、信じたとしても家族にオレオレ詐欺だと指摘されて気づかれたりするので、二百人にかけて十人が信じるという確率だ。
かけ子達は月曜日の午前八時半から、「アポ電」を信じたターゲットに順番に電話をする。
要求額はターゲットの経済状況に応じて様々だ。
五十万円の場合もあれば、五百万円の場合もある。
ターゲットは老人がほとんどなので、午後八時には切り上げることになっていた。
ターゲットへの電話が終われば夕食を摂り、シャワーを浴び、就寝時間の十一時まではテレビを観たり漫画を読んだり好きなことをして過ごす。
食事は、A、B両グループ用にそれぞれ一台ずつ設置されている冷凍庫に入った六日分の冷凍食品とカップ麺だ。
外食はもちろん、バレてしまう可能性があるので出前も禁止している。
外部との連絡を絶つために個人の携帯電話は入室する日曜の夕方に取り上げ、ターゲットにかけるために支給した携帯電話も仕事終わりに回収する。
室内には十台の監視カメラが設置されており、片桐がいないときにきちんと仕事をしているか、勝手に退出していないかがわかるようになっていた。
通りを挟んだマンションに監視役として片桐の配下を交代で詰めさせているので、おかしな気を起こすかけ子はいない。
赤坂部隊の毎週の平均的な売り上げは、A、B両グループ合わせて二千万円前後となっていた。
二千万円の六十パーセントが片桐の取りぶんとなり、四十パーセントを八人のかけ子と四人の出し子のうち案件に関わった人数で分ける。
かけ子と出し子は週に約六十万円、月に約二百四十万円の報酬を手にするので、監禁状態で詐欺の電話をかけまくらされていることにたいして、不満も罪悪感もないのだった。
片桐に入る金は週に約千二百万円、月に五千万円弱で、そのうちの二十パーセントを「斎藤組」組長の我妻に上納している。
片桐はほかにも新宿、池袋、渋谷にもハコを持っているので、すべて合わせれば月の純利益は二億円に達していた。
もちろん、ディフェンス面にも最大限の注意を払っていた。
ハコは三ヶ月周期で引っ越し、ターゲットとのやり取りは水溶紙にメモをする。
短期間で引っ越すのは警察に察知されないよう、水溶紙にメモをするのは警察が踏み込んできたときに足元に置いてあるバケツ入りの水に放り込むためだ。
携帯電話に関しては、非常事態の際は電子レンジに放り込み破壊するように指示してあった。
だが、一番警戒しなければならないのは裏切りだ。
かけ子や出し子が金を持ち逃げしたり警察に駆け込んだりという「魔が差す」ことがないように、金と恐怖の飴と鞭で調教するのが大事だ。
初期の頃に、禁止されている酒をハコから抜け出して買い込み飲酒したかけ子がいた。
片桐は我妻の若い衆を使ってかけ子の兄が経営しているスナックを占拠させ、ビール一本でオープンからラストまで居座らせるという嫌がらせを一週間続けた。
風体の悪い男達が大勢で騒いでいれば客足が遠のくのは必然で、三日で閑古鳥が鳴くようになった。
兄を見せしめにしただけではなく、もちろん本人も顔の判別がつかないほどに若い衆に袋叩きにさせた。
たかが酒を買い込んで飲んだだけと甘い対応をすれば、味を占めて次はもっと大胆なルール破りを犯す。
また、ほかのかけ子達もお咎めなしなら俺も……となるのが人間の性だ。
利益を出せばたっぷりと報酬を与え、掟破りをすれば徹底的に恐怖を与える飴と鞭が、かけ子達を従わせるのに一番効果的だということを片桐は身を以て知った。
片桐は眼を閉じ、記憶を巻き戻した。
『人殺し! あなたが杏を殺したのよ!』
水樹のヒステリックな怒声が、室内に響き渡った。
「スマイルローン」から盗んだ三千万円を臓器移植ブローカーを騙った山根に持ち逃げされ、挙句の果てにケツモチの我妻に拉致され半殺しの目にあった。
我妻の舎弟になり生涯を捧げる条件で命を奪われなかったのは不幸中の幸いだが、不運はこれで終わらなかった。
一週間ぶりに解放されて埼玉のビジネスホテルに戻った片桐が眼にした光景は、信じられないものだった。
杏の遺影、小さな骨壺、泣き崩れる水樹……。
『どういうことだよ……どうして……どうして杏が……』
わけがわからず、片桐の頭は真っ白になった。
『あなたと連絡がつかないうちに、杏の容態が急変して……救急車で運ばれて……いったい……どこでなにをしていたのよっ!』
水樹が赤く充血した眼で片桐を睨みつけてきた。
我妻に拘束されていたので、水樹に連絡する手段がなかった。
究極の二者択一――片桐は我妻に忠誠を尽くすことを誓った。
あのときの片桐の頭にあったのは、杏のために生き延びること……杏のために一時間でも早く解放されることだった。
本心では、ヤクザの僕になる気はなかった。
杏に誇れる父親になりたかった。
だが、拒否すれば殺されてしまう状況下では我妻に従うふりをするしかなかった。
甘かった。
我妻は片桐の忠誠の言葉を鵜呑みにはせずに、事務所に監禁してアロハパンチ三兄弟に殴らせては問い続けてきた。
生涯、俺の僕として忠誠を誓うか? と。
毎日、同じことが繰り返された。
誓います。
そう答えても、アロハパンチ三兄弟の拷問は続いた。
朝、起き抜けに殴られることもあれば、昼のこともあれば、夜のこともあった。
いつ殴られるかわからない恐怖に、片桐の心は壊れそうになった。
正直、終わりなき苦痛と底なしの恐怖に水樹や杏のことを忘れた瞬間もあった。
監禁が六日目になる頃には、正常な思考力を失っていた。
もう、どうでもよくなっていた。
ヤクザの僕など冗談じゃない、杏に誇れる父親でありたい……そんなことを考えられるのは、心身共に余裕があるときだ。
人は死を突きつけられた瞬間に、一つのことを除いてすべてを諦められる。
命を失わないこと以外のすべてを……。
生涯を、ヤクザの僕として捧げてもいい……心から、そう思うようになったときに解放されたのだった。
『そんな……嘘だろ……嘘だろ……』
片桐は骨壺を手にし、放心状態で呟いた。
『あなたが移植手術のお金を盗まれなきゃ……こんなことにはならなかった。あなたが、殺したのよっ! 杏を返して……杏を返してよっ!』
水樹の怒声が、鼓膜からフェードアウトした。
『ごめん……ごめん……ごめん……』
片桐は骨壺を抱き締め、うわ言のように呟いた。
とめどなく溢れる涙が頬を伝い、小さくなってしまった杏を濡らした。
水樹は、その日を最後に片桐の前から消えた。
杏の死後、哀しみに暮れる間もなく片桐は我妻の息がかかった闇金融……十日で二割の「東京金融」で働くことになった。
杏を殺してしまった罪悪感から逃れるように、片桐はガムシャラに貸し付け、ガムシャラに取り立てた。
一ヶ月で三千万円を貸し出し、十日ごとに六百万円、月に千八百万円以上の収益を上げた。
「スマイルローン」のときとは別人のように、片桐は非情になった。
期日を一日でも過ぎた債務者は、容赦なく追い込んだ。
債権を回収するために、年老いた両親の実家に乗り込んだ。
債権を回収するために、子供の高校に乗り込んだ。
債権を回収するために、妻の職場に乗り込んだ。
貸金を切り取るためなら、債務者が死んでもいいと思った。
実際に、何人も自殺に追い込んだ。
片桐の「東京金融」の回収率は九十二パーセントで、未回収の八パーセントが自殺者だった。
以前と別人のようになった片桐が非情へと駆り立てられるのは、我妻が怖かったからではない。
相応しい人間になると決めただけ。
杏を見殺しにしてしまった父親に相応しいひとでなしに……。
莫大な利益を運び続ける片桐は、日増しに我妻の信頼を得ていった。
片桐が我妻の企業舎弟になって九年が過ぎた頃、「東京金融」は都内に十店舗を構えるほどに大きくなっていた。
だが、闇金融で金を借りた債務者が起こした犯罪や自殺が社会問題になり、国会で貸金業法の改正が取り沙汰されるようになった。
徐々に闇金融への取り締まりが厳しくなり、片桐は我妻にこれまでプールした資金を基にシノギを別のビジネスに転換する進言をした。
片桐が進言したシノギは、息子を騙り別居する高齢の両親から大金を騙し取る、後にオレオレ詐欺と呼ばれる新手の詐欺だった。
闇金融時代に集めた膨大な名簿を使うことができたので、片桐の新ビジネスは滑り出しから好調なスタートを切った。
闇金融、オレオレ詐欺と片桐から納められた莫大な上納金の後押しもあり、我妻は「斎藤組」の若頭から組長へ、そして本家「極政会」の若頭へと異例のスピード出世を果たした。
我妻の出世に大貢献した片桐は、フロント企業の全権を任されるまでになった。
杏のために……金を稼ぐために裏稼業に足を踏み入れた。
心臓移植の手術費が稼げたら、足を洗い真っ当に働くつもりだった。
杏を死なせたことで、足を洗う理由がなくなった。
杏を死なせたことで、人間でいる理由がなくなった。
「いま、弁護士さんに代わるね」
三田の声で、片桐は記憶の扉を閉めた。
三田が弁護士役の山井に携帯電話を渡した。
「お母様でしょうか? 私、弁護士の輪島と申します。息子さんが関係を持った女性の旦那様からの依頼を受けました。はい、はい……そうです。それで、依頼人とは四百万円の示談金でこの件の鉾を収めると話がついています。息子さんの貯金が百万円しかなく、不足が三百万円ということになります。え? 示談金を支払わなかった場合ですか? 訴訟すると言ってます。裁判になれば会社にも知られることになり、息子さんは解雇されるでしょう」
山井が言葉巧みにターゲットに畳みかけた。
息子の窮地を聞かされた状況で、三百万円が用意できないという理由以外に断る母親はいない。
闇名簿でターゲットを選ぶ段階で、ある程度の資産状況は把握しているので、払えない金額は要求しない。
仮に要求額が払えない場合の、理由をつけて払えるぶんの金額に下げるマニュアルもあった。
「はい、はい、ありがとうございます」
今度は山井が息子役の三田にオーケーサインを作った。
三田が小さくガッツポーズをした。
三百万円が入れば四割の百二十万円を三田、山井、出し子の三人で分けるので、四十万円の収入になる。
「なるほど……来週ですか……」
一転して、山井の顔が曇った。
「大変申し上げにくいのですが、依頼人が出した条件は、今週までに示談金が入ることです。となりますと、明日が金曜日なので本日中に振り込んでいただかなければ間に合わなくなります」
山井が今日中に要求額を支払わせるマニュアル通りに母親を詰めた。
三田が顔前で手を合わせて祈っていた。
振り込み日が遅くなるほどに、詐欺がバレるリスクが高くなる。
本物の息子から連絡が入るかもしれないし、母親のほうから偽息子の不倫を誰かに相談するかもしれないからだ。
オレオレ詐欺の鉄則は、電話を切ってから一分でも早く金を振り込ませることだった。
「ありがとうございます。そうして頂けると、息子さんも助かると思います。では、弁護士事務所代表の私の銀行口座を教えますので、メモしていただいてもよろしいですか?」
山井がふたたびオーケーサインを作ると、三田が安堵の表情を浮かべた。
ターゲットから三百万円が振り込まれたら、銀行付近で待機している出し子の一ノ瀬が偽弁護士の口座から金を下ろし、指定したコインロッカーに入れる手筈になっていた。
コインロッカーの付近に待機している片桐の配下が、現金を回収するという流れだ。
今週の詐欺テーマは「不倫妊娠示談金事件」だが、足がつかないようにターゲットごとに口座は変えていた。
以前は息子の上司や友人を装わせた受け子をターゲットのもとに向かわせ、金を受け取らせていたが、直接対面はリスクが高いので銀行口座に振り込ませるスタイルに変えたのだった。
もちろん、銀行に警察が張り込む可能性があったり防犯カメラの問題があったりと出し子にもリスクはあるが、それはターゲットにバレた場合の話だ。
バレない状態を前提に比べれば、出し子より受け子のほうがリスクが高い。
片桐はAグループのリーダーの村浜を手招きし、ソファから腰を上げるとシャワールームに向かった。
「今週、いまの三百万を含めていくらだ?」
片桐はシャワールームのドアを閉め、浴槽の縁に腰を下ろしながら訊ねた。
「……六百万です」
村浜が言いづらそうに、月曜日からの四日間の売り上げを報告した。
「少ないな。Bは昨日の段階で九百万だ」
片桐は冷え冷えとした眼で村浜を見据えた。
「す、すみません。家族が邪魔したりアクシデントが続いて……」
「言い訳するな。条件はBと同じだ。ラストの明日までに一千万まで持っていけなければ、リーダー交代だ」
村浜を遮り、片桐は抑揚のない口調で言った。
「すみません! わかりました!」
村浜が弾かれたように頭を下げた。
「戻れ」
片桐は村浜がシャワールームを出るのを見届け、我妻の携帯番号を呼び出しプッシュした。
『儲かってるか?』
電話に出るなり、我妻の野太い声が受話口から流れてきた。
「お疲れ様です。新宿2100、渋谷1900、池袋1800、赤坂1500です」
片桐は、各ハコの現時点での売り上げを報告した。
『週計が七千三百か? 相変わらず稼ぐねぇ~。上納金を二十っパーにしたの失敗だったぜ』
我妻が本気とも冗談ともつかぬ口調で言うと、下卑た声で笑った。
「もっと、パーセンテージを上げてもらっても構いませんよ」
すかさず片桐は言った。
駆け引きではない。
我妻が本気なら、上納額を収益の二割から三割にアップしても構わなかった。
だが、わかっていた。
我妻にその気はないことを。
『冗談だ、冗談。お前にゃ、もう十分に稼がせてもらった。最速記録で「極政会」の若頭にもなれたしな。これ以上、お前にたかるとバチが当たるぜ』
この十年で、我妻に上納した金は十億を下らない。
我妻の片桐にたいしての信頼は絶大で、いまや最強の片腕であり不可欠な存在になっていた。
『それより、今夜、時間取れるか?』
「大丈夫です。どこに行けばいいですか?」
片桐は即答し、訊ねた。
本当は日葵のクラブに顔を出す予定だったが、もちろん我妻を優先した。
女の替えはいくらでも利くが、我妻の替えは利かない。
十二年前にすべてを失った片桐が手に入れようとしているのは、闇世界の覇権だった。
そのためには、もっと財力をつける必要があった。
表も裏も、最後に物を言うのは金だ。
我妻に半殺しにされたチンピラにもなれない半端者……片桐は、金の力で我妻に気を使われるまでに伸し上がった。
娘を救えなかった父親……娘を見殺しにした父親に相応しい、天国の杏に愛想を尽かされるような男になることを誓った。
真っ当な人生を生きる資格は、自分にはなかった。
人間らしく生きることを考えると、罪悪感に押し潰されてしまう。
だから、杏を殺した瞬間に人間性のスイッチを切った。
我妻を徹底的に利用して、強大な力を身につけ、誰も手出しができないほどの男になるつもりだった。
『七時に歌舞伎町の組事務所にきてくれや』
「組事務所から、どこかに行くんですか?」
『褒美に、本家の親父のとこに連れて行ってやる。っつーことで、あとでな』
我妻が電話を切った。
ビジートーンが漏れる携帯電話を氷の瞳でみつめ、片桐は酷薄な笑みを浮かべた。
ついに、チャンスが訪れた。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/