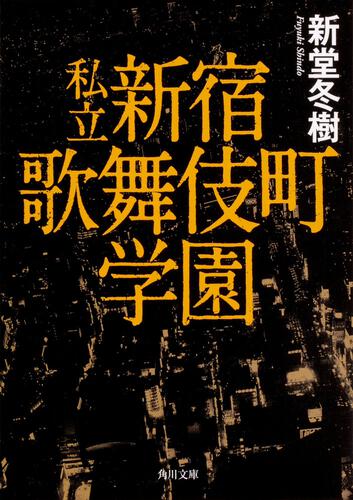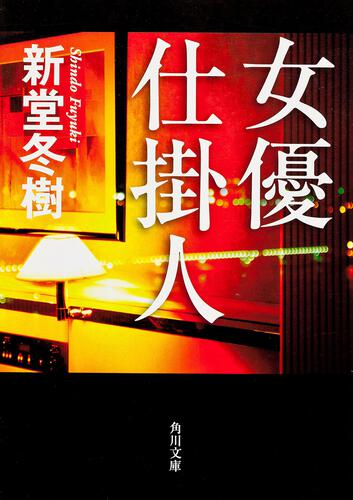【第6回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
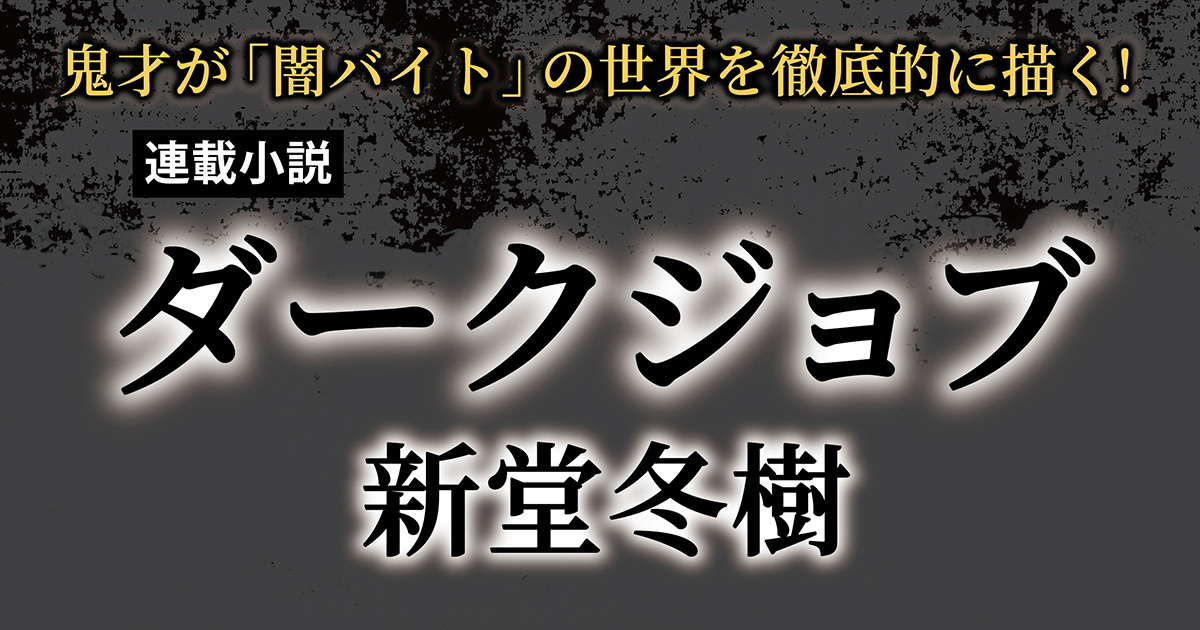
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第6回】新堂冬樹『ダークジョブ』
若宮★2025年夏
青山の骨董通り――金融流れのアルファードは、ターゲットの宝飾店から十メートルほど離れた斜向かいの路肩に停まっていた。
「お前、その体で本当に大丈夫か?」
ドライバーズシートに座る中井が振り返り、若宮の隣……シリコーン製の狼のパーティーマスクを被った岩田に訊ねた。
岩田のマスクの下の顔は、赤紫に内出血してパンパンに膨れ上がっていた。
コングに馬乗りの体勢から数十発も殴られているので、無理もない。
入院もせずにこうして車に乗っていること自体、尋常ではなかった。
因みに若宮はヴァンパイア、パッセンジャーシートに座る新メンバーの南城はライオンのマスクを被っていた。
南城は最年少の二十歳で、東大中退でホストをやっていたという変わり種だ。
マスクを被る前に素顔を見たが、モデル事務所に応募しても通用するビジュアルだった。
頭も顔もよくて、その気になれば金も女も思いのままのはずの南城が、どうして闇バイトに応募する気になったのか若宮には理解できなかった。
「ふるへえ! しゃひょうころひてほうへきふぉふぇんぶふばっふぇやる!」
うるせえ! 社長殺して宝石を全部奪ってやる!
前歯が全損したため空気が漏れて不明瞭な岩田の言葉を、若宮は心で翻訳した。
『いまの、見たでしょう? 私は無能な人間は処理するタイプなの。あなた達は私に有能であることを証明しなければならないの。断るのは勝手だけど、あなた達はもちろん、家族もすべて処理することになってもいいの?』
闇組織の女性幹部の恫喝が、若宮の脳裏に蘇った。
正座させられた若宮の目の前で、毒薬らしき液体を飲まされ白泡を吹き痙攣して事切れたコングの姿が
出口なき地獄の迷宮……この先、どうなってしまうのか?
仮に今回の闇バイトが成功しても失敗しても、次の指令がくるだろう。
警察に捕まるまで、強盗殺人を続けさせるつもりに違いない。
嫌でも、走り続けるしかなかった……止まったら爆発する車に乗っているようなものだった。
とにかく、いまは、目の前の闇バイトを成功させることが先決だ。
「みんな、聞いてくれ。情報通りなら、あと十分で昼休憩に入り、バイトが昼飯を食いに出てくるはずだ。これも情報通りなら、店内にはオーナー一人が店番をしながら愛妻弁当を食ってるはずだ。まあ、開店してから店にはオーナーとバイトの男しか入ってないから、情報通りだと思う」
中井が切り出した。
「もう一度、段取りをおさらいしておこう。バイトが出かけてからお前ら三人が乗り込む。通行人に怪しまれないように、南城は岩田と若宮をカメラで撮影しながら走るんだ。パーティーマスクをつけた三人がカメラを回しているのを見たら、通行人はYouTubeの撮影かなにかだと思うだろう。少なくとも、真っ昼間から堂々と強盗するとは思わないはずだ。岩田は最初にオーナーを襲撃する。上からは殺してもいいって言われてるから、容赦なく叩け」
「おまへにひわれなふふぇも、ぶっころふ!」
お前に言われなくても、ぶっ殺す――岩田が叫び、レンチでパッセンジャーシートの背凭れを殴りつけた。
「わかったから、そう興奮するな。で、岩田がオーナーを叩いている間に、若宮と南城はできるだけたくさんの宝飾品をバッグに詰め込むんだ。時間は五分以内だ。警察が通報を受けてから現場に到着するまでの時間は、全国平均で八分二十四秒らしい。余裕をみて五分以内に逃げれば、捕まることはないからな」
「五分ではなくて、三分以内にしましょう」
南城が中井に進言した。
「ん? どうしてだ?」
中井が怪訝そうに訊ねた。
「警察は大丈夫でも白昼の犯行ですから、通行人が乗り込んでくる可能性があります。なので、犯行時間は短ければ短いほうがいいと思います」
南城が理路整然と理由を説明した。
「なるほど、それもそうだな。よし、三分以内に変更だ」
中井があっさりと受け入れた。
「それから、店に乗り込むのはバイトが出かけてすぐではなく、五分後にしましょう。忘れ物かなにかで、戻ってくるかもしれませんし」
南城がふたたび進言した。
「お前、頭が回るな。さすが東大出は違うな」
中井が感心したように言った。
「たいしたことはありません。それに、東大出ではなくて中退ですから」
南城が謙遜した。
「ほうだいだからっふぇ、へらふぉうにふるんひゃねえ! ほまえ、ひふぉふぉろしふぁことがはるのか!? ふぉ!? ヒヒファファのはたま ふぁちわっふぁこふぉがはるのふぁ!? ふぉ!?」
東大だからって、えらそうにするんじゃねえ! お前、人を殺したことがあるのか!? お!? ジジババの頭かち割ったことがあるのか!? お!? ――岩田がパッセンジャーシートの南城に嚙みついた。
南城はまるで岩田が透明人間であるかのように、無反応だった。
「そのへんにしとけ。お前は真っ先にオーナーを叩くっていう重要な役割だ。今回も失敗したら、俺ら全員殺されるんだぞ」
中井が岩田を窘めた。
「どうしても、オーナーを殺さなきゃならないんですか?」
若宮は、ずっと引っかかっていたことを思い切って口にした。
もう、誰かが死ぬのを見るのはごめんだった。
「お前も聞いていただろう? 上からの命令だ」
中井が淡々とした口調で言った。
「フォーナーふぉふぉろふ! ふぉれがふぉろふ!」
オーナーを殺す! 俺が殺す! ――岩田が叫び、レンチでシートを叩いた。
元からイカれた男だったが、コングに半殺しにされてから狂暴度が増していた。
「抵抗する意思を奪えば、殺す必要はないと思います」
若宮は食い下がった。
組織に家族や親戚を人質に取られているので強盗を続けるのは仕方がないにしても、これ以上の殺人は避けたかった。
「僕も同感です。万が一捕まっても強盗罪で初犯なら五、六年の懲役で済みますが、強盗致死罪となれば死刑か無期懲役ですからね」
南城が口を挟み若宮を擁護した。
「え!? そうなのか!?」
中井が驚いた顔で訊ね返した。
「もしかして、知らなかったんですか?」
南城が呆れた口調で言った。
「マジか……。それは、ヤバいな。よし。作戦変更だ。おい、若宮。お前がオーナーをおとなしくさせろ。岩田は宝石を奪う係に変更だ」
中井が若宮と岩田に命じた。
「ふひゃけんふぁ! フォーナーふぉふぉろふ! ふぉれがふぉろふ!」
ふざけんな! オーナーを殺す! 俺が殺す! ――案の定、岩田がキレた。
「言う通りにしてくれたら、俺の分け前を半分やるから!」
若宮は咄嗟に言ってしまった。
「ふぉんとうふぁ!? ふぉんとうに、ほまえのふぁけまえをふぁんぶんふぁたふのふぁ!?」
本当か!? 本当に、お前の分け前を半分渡すのか!? ――顔を近づける岩田のマスク越しの眼は、赤く充血していた。
「ああ、約束する。だから、中井さんの言う通りにしてくれ」
危ない橋を渡って手にした報酬の半分を渡すのは嫌だったが、これ以上殺人の共犯にされるのはもっと嫌だった。
女幹部の話では、宝飾店のオーナーは還暦過ぎだという。
武器としてレンチも持っているので、荒事に慣れていない若宮でも制圧できるだろう。
いや、制圧しなければ岩田が殺してしまうので、なんとしてもおとなしくさせなければならない。
「おっ、バイトが出てきたぞ。スタンバイしろ。武器とバッグを忘れるな」
中井の言葉に、若宮の全身の筋肉が緊張で強張った。
宝飾店から出てきた三、四十代の男性が、スマートフォンを見ながら歩いていた。
バイトは、四、五十メートルほど離れたカレー店へと入った。
「カレーだと三十分くらいで出てくるだろう。突入だ。三分以内で出てこいよ!」
中井が言うと、岩田と南城が同時にスライドドアを開けて飛び出した。
慌てて、若宮も二人の後を追った。
目論見通り、南城がカメラを回しながら走っているので通行人は好奇の顔で振り返るが、若宮たちを怪しんでいるふうはなかった。
若宮は二人を追い抜き先頭に立った。
岩田が真っ先に飛び込むと、なにをしでかすかわからない。
店まで五メートル、四メートル、三メートル、二メートル、一メートル……自動ドアが開いた。
「いらっしゃいま……」
店の奥のデスクで弁当を食べていた白髪ポニーテールの男が、三人を認め表情を強張らせた。
年は還暦過ぎで間違いはなさそうだが、筋骨隆々の体に若宮は怯みそうになった。
だが、ここで臆すれば岩田が暴走してしまう。
「怪我したくなければ、じっとしてろ!」
若宮はレンチを振り上げ、オーナーを威嚇した。
南城と岩田がショーケースを叩き割る破損音と警報ベルの音が店内に響き渡った。
「若造がナメやがって!」
予想外の展開――オーナーが立ち上がり、怯えるどころか若宮に詰め寄ってきた。
「座れ! これ以上近寄ると、怪我することになるぞ!」
若宮はうわずる声で警告した。
「上等だ! 若い頃は修羅場を潜ってきた身だ! やれるもんならやってみろや!」
オーナーが若宮のレンチを掴んだ。
「離せっ……」
オーナーの手を振り払おうとしたが、物凄い力でレンチはピクリとも動かなかった。
「ふぁからふぉろふぇってひっふぁだろう!」
だから殺せって言っただろう! ――突進してきた岩田が、微塵の躊躇もなくレンチをオーナーの頭に叩きつけた。
オーナーの頭から、噴水のように鮮血が噴き出した。
「この……クソガキが……」
信じられないことに、オーナーは血に染まった赤鬼のような顔で岩田の胸倉を掴み、狼のパーティーマスクを剥ぎ取った。
「ひにふぉこないのふほぉひひい! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね!」
死に損ないのくそじじい! 死ね! 死ね! 死ね! 死ね! 死ね! 死ね! 死ね! ――腐ったジャガイモのように赤紫に腫れ上がった岩田が、叫びながらレンチをオーナーの脳天に叩きつけた。
オーナーは崩れ落ちながらも、岩田の右足の脛を掴んで離さなかった。
ホラー映画のような光景に、若宮の足が竦んだ。
「ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね! ひね!」
狂気のフルスロットル――岩田がオーナーに馬乗りになり、オーナーの顔面をレンチで数十発殴りつけた。
オーナーの顔はパンクしたバレーボールのように凹み、眼も鼻も口もわからないほどぐちゃぐちゃにひしゃげていた。
「お、おいっ、やめろ! 殺す気……」
「もう死んでます」
我に返り岩田を止めようとした若宮の声を、南城の声が遮った。
「残り二分です。こっちを手伝ってください」
南城が日常会話のように落ち着いた声で言った。
「あ、ああ……」
南城に促され、若宮は高級腕時計が陳列されたショーケースにレンチを叩きつけた。
思ったよりも頑丈で、ガラスには罅が入っただけだった。
二度、三度……四度目で、派手な破損音とともにガラスが砕け散った。
ヒステリックに鳴り響く警報ベルに急かされるように、若宮は手当たり次第に腕時計を鷲掴みにするとボストンバッグに詰め込んだ。
腕時計がなくなると、若宮は隣のショーケースを叩き割り、ハイブランドのネックレスとブレスレットを次々とバッグに放り込んだ。
岩田は、既に事切れているオーナーの崩壊した顔面をレンチで殴り続けていた。
「二分半経過です。もうそろそろ、行きましょう」
南城がスマートフォンのストップウォッチを見ながら言った。
「ここが最後だ」
若宮は一番高そうなダイヤの指輪の入ったショーケースにレンチを振り下ろした。
ほかより強度の高いガラスなのか、罅も入らなかった。
二度、三度、四度……五度目で、ガラスにようやく小さな罅が入った。
「もう十分に収穫はあります。欲をかかないほうがいいです」
南城が若宮の腕を掴んだ。
「欲をかかないでどうする!」
南城の腕を振り払い、若宮は渾身の力でレンチを振り下ろした。
地獄に足を踏み入れた以上、見合うだけの対価は貰う……後戻りできない以上、前に進むだけだ。
非常ベルと甲高い破損音の二重奏――無我夢中で、ダイヤの指輪を鷲掴みにした。
「若宮さん、早く……」
「うるせえっ、ぶっ殺すぞ!」
若宮は南城を一喝した。
思わず出た自分の言葉に、若宮は驚きを隠せなかった。
「行くぞ」
三分ジャスト――若宮は一つ残らずダイヤの指輪をバッグに詰め込むと、南城を促しドアに向かった。
「まへっ! ふぉれをほいてひくな!」
待てっ! 俺を置いて行くな! ――岩田が若宮を追い抜き、外に飛び出した。
「おいっ、マスクを被れ!」
若宮は叫んだ。
あんな返り血に塗れた顔で白昼の骨董通りに飛び出したら、通報してくださいと言っているようなものだ。
「警察っ……警察ぅーっ!」
案の定、岩田の顔を見た中年女性が悲鳴を上げながらスマートフォンを取り出した。
「ひねっ、くふぉふぁぶぁ!」
死ねっ、くそばばあ! ――岩田が血に濡れたレンチで中年女性の顔面を殴りつけた。
「馬鹿っ、やめろ!」
若宮は叫び、倒れた中年女性になおも襲いかかる岩田の腕を掴んだ。
岩田は若宮の腕を振り払い、中年女性の後頭部を何度も踵で踏みつけた。
「ほっときましょう!」
南城に腕を引かれ、若宮は中井の待つ車へと走った。
「強盗だーっ!」
「誰かーっ! 110番!」
「警察に通報して!」
「あいつらを捕まえろ!」
悲鳴、怒号、絶叫、クラクションの渦の中を、走った、走った、走った!
不幸中の幸いは、野次馬たちの注意が岩田に向いていることだった。
「早く乗れ!」
スライドドアを開けた中井がドライバーズシートから大きく手招きした。
若宮、南城の順で車内に乗り込んだ。
「岩田は!?」
中井が訊ねてきた。
「通行人を襲ってます……」
若宮は暗鬱な声で言った。
あの女性は、恐らく死ぬだろう。
なんの罪もないのに、たまたま岩田と出くわしたことで殺されてしまった。
罪がないのは、宝飾店のオーナーも同じだった。
二日で、五人の人間が殺されるのを間近で見た。
これから、どれだけの死体を見なければならないのか……。
遠くから、サイレンの音が聞こえてきた。
「あのイカれ野郎が!」
中井は吐き捨て、スライドドアが半開きのまま車を発進させた。
「ブツは!?」
中井が思い出したように訊ねてきた。
「店の半分以上の商品は、持ってこられたと思います。それに、若宮さんがダイヤリングをごっそりいきましたから」
南城がマスクを外しながら、押し込み強盗をした直後とは思えない落ち着いた口調で報告した。
「そうか……よかった」
中井が安堵の表情で言った。
パトカーが追ってくる気配はなかった。
皮肉にも、岩田の暴走で若宮と南城はノーマークのまま車に乗れた。
「あいつ、オーナーを殺しました」
若宮もマスクを脱ぎ、放心状態で言った。
「オーナーは計画通りだが、通行人まで襲いやがって」
中井が舌打ちした。
「計画通りって……人が死んでるんですよ!? よくそんな平然とした顔で言えますね!」
若宮は自分でも驚くほどの大声で中井に食ってかかった。
「なんだよ、俺にキレるなよ。上からの命令だから、仕方ないだろ? 逆らったり下手をうったりして、コングさんみたいに殺されるのはごめんだ」
「だからって……」
「気持ちはわかりますけど、岩田さんがやらなければ失敗していたかもしれません」
中井に反論しようとする若宮を、南城が遮った。
「どういう意味だ?」
訊ねはしたものの、南城の言わんとしている意味はわかっていた。
「オーナーが思いのほか屈強な武闘派で、若宮さんは動きを封じられていました。たしかに岩田さんはやり過ぎでしたが、オーナーを殺したのは正解だったと思います」
南城が淡々とした口調で言った。
反論はしなかった……できなかった。
言われなくても、自覚していた。
あのままだったら自分は、オーナーの逆襲に遭ってやられていたかもしれない。
「でも、若宮さんには驚きました。僕が時間がないから逃げましょうと言ったときに、凄い顔つきで怒ってダイヤのショーケースを叩き割りましたよね?」
「危険をおかして強盗に入ってるんだから、高い物を狙うのはあたりまえだよ」
「それはそうなんですけど、若宮さんはぶっ殺すぞとかいうキャラに見えなかったので意外でした」
南城が驚くのも無理はない。
若宮自身、自分ではない自分が現れたようで一番驚いていた。
「案外、こういう奴が一番犯罪に向いているのかもな。自分の才能に気づいてないだけで、どこかのタイミングで覚醒したりして」
中井が茶化すように言った。
「僕もそう思います」
南城は中井と違って真剣な表情で言った。
「二人とも、やめてください。命懸けでやってるわけですから、高い報酬を貰いたいだけです。ところで、岩田は逮捕されましたよね? どうなるんですかね?」
若宮は気になっていることを訊ねた。
「まあ、通行人が死んだら合計で四人も殺してるんだから死刑だろうな」
「俺らは大丈夫ですか?」
岩田が死刑になろうと自業自得だが、とばっちりを食わないかが心配だった。
「俺らの本名も知らないわけだし、車も金融流れだし、もちろん、共通の知人もいない。奴から俺らを辿れる要素はなにもないから安心しろ」
中井が言った。
「逆に言えば、俺らが捕まっても上は困らないから使うだけ使って捨てる……そういうことですね?」
若宮は暗鬱な瞳で、ルームミラー越しに中井の眼を見据えた。
「まあ、暗い話はやめようや。とりあえず、今回は成功したわけだしな。それより、大金の使い道を考えよう」
中井が明るく振る舞い話題を変えた。
「そう言えば、今回の報酬額はいくらなんですか?」
南城が訊ねた。
奪ったのが現金なら総額の一割を分配するなど報酬の計算がしやすいが、今回は宝飾品なので見当がつかなかった。
「あ、そうそう、それを言わなきゃだったよ。上から連絡が入って、これから赤坂に向かうところだ」
思い出したように中井が言った。
「赤坂でなにするんですか?」
若宮の脳裏に、昨日の悪夢が蘇った。
「ブツの確認だろう。確認しなきゃ、報酬額も決められないからな」
中井が心配しているふうはなかった。
「昨日みたいなことはないですよね?」
若宮は不安を口にした。
「今回は成功してるんだ。そりゃないだろう」
中井が楽観的な口調で言った。
言われてみれば、たしかにそうだった。
理屈ではわかっていたが、コングの屍が頭にチラついて離れなかった。
「それより、本当に報酬をくれるんですかね?」
南城が口を挟んだ。
「どういう意味だ?」
中井が怪訝な表情で訊ね返した。
「上の人は僕らの情報をすべて押さえてますけど、僕らは彼らの素性をなに一つ知りません。戦利品だけ取り上げられて、消されたりしませんか?」
南城の危惧に、若宮の不安がふたたび膨らんだ。
「上の人達が殺すのは金を運ばない奴だ。俺らは大金を運んでいる。結果を出したんだから、次の闇バイトにも使うに決まってるだろう?」
中井の説明は一理あった。
あの氷のような女性幹部も言っていた。
処理されたくなければ、有能であることを証明しろと。
バッグの中には、恐らく数億円相当の宝飾品が入っている。
大きな成果を挙げた駒を捨てるわけがない……若宮は己に言い聞かせた。
「次のバイトでも僕達が成功する保証はありませんし、失敗しないまでも大した金を運べないかもしれません。僕達にまともに報酬を払うなら、数千万になるはずです。数千万を払わないで僕達を消して、新しい駒を使うという考えになっても不思議はありませんよ」
南城の危惧は説得力十分だった。
「それは考え過ぎ……」
「その可能性がゼロとは言わない。だけど、行かなきゃ警察に自首しないかぎり百パーセント殺される。上が俺らを殺そうと思わないほど大きくなるしかない」
若宮は中井を遮り、不安を打ち消すように自らにも言い聞かせた。
☆
赤坂の古い雑居ビル――両手にボストンバッグを持った若宮は、強張った顔で上昇するエレベーターの階数表示のランプを眼で追った。
「なんで俺だけ……」
若宮は
『えっ……お前一人でこいってさ』
指定された赤坂の雑居ビルの前の駐車場に停めた車内で、指示役からのテレグラムのメッセージを見た中井が怪訝な顔で言った。
『俺だけ!? どうしてですか!?』
『俺に訊かれても、わかるわけないだろ。お前、なんか睨まれるようなことしたのか?』
『してませんよっ。ずっと、一緒に行動してたじゃないですか!』
『たしかにな。じゃあ、なんで若宮だけ呼び出されたのかな』
『身バレのリスクを減らすためじゃないですか?』
南城が冷静な口調で言った。
『身バレのリスクを減らすため?』
若宮は南城の言葉を繰り返した。
『はい。顔を隠してても、極力会う人数は減らしたいでしょうから』
『だとしても、なんで俺なんだよ? 一人呼び出されるなら、リーダーの中井さんだろう?』
『上の人に、なにか考えがあるのかもしれませんね』
エレベーターの扉の開閉音が、若宮を現実に引き戻した。
早鐘を打つ鼓動――指定された七〇二号室のドアの前で、若宮は足を止めた。
バッグを奪われて、消されるかもしれない……。
南城に偉そうに言ったものの、不安に押し潰されてしまいそうだった。
バッグを持ったまま非常階段から逃げれば、中井達に気づかれることもない。
バッグの中身を換金すれば、一億円にはなるだろう。
それだけの大金があれば逃げ切れるかも……。
すぐに、馬鹿げた考えを打ち消した。
仮に自分が逃げきれても、母親が殺されてしまう。
闇世界に足を踏み入れた以上、南城に大見得を切ったように消されないほどの大物になるしかない。
だが、大物になる前に殺されてしまったら……。
消えては現れる不安――思考を止めた。
グジグジ考えても、若宮に選択肢はない。
自分にできるのは、前に進むことだけだ。
若宮は震える指先でインターホンを押した。
「若宮です」
スピーカーに名乗った直後にドアが開き、二人の大柄な黒スーツにサングラスをかけた男に両腕を掴まれ引き込まれた。
五十坪ほどの空間、打ちっ放しのコンクリート壁、剥き出しの配線……リフォーム前の事務所のようだった。
「離してあげなさい」
聞き覚えのある声がした。
黒スーツ姿の男達が若宮の腕を解放した。
奥から歩いてきた小柄でスリムな女性を見て、若宮は息を呑んだ。
コングを処理させた女性幹部だった。
昨日はベネチアンマスクをつけていたが、今日は素顔だった。
あまりの美しさに、若宮は置かれた状況を忘れて見惚れてしまった。
「こっちに持ってきて」
女性幹部が命じると、黒スーツ達が若宮の手からボストンバッグを奪い取った。
我に返った若宮の頭に、ある疑問が浮かんだ。
なぜ、女性幹部は素顔なのか?
顔を見られてもいい理由……頭から血の気が引いた。
「今回は、有能であるところを見せてくれたわね」
女性幹部が、ボストンバッグの中身をチェックしながら抑揚のない口調で言った。
「あの……どうして俺だけ呼ばれたんですか?」
若宮は干涸びた声で訊ねた。
「心配しなくても、結果を出した人間は処理しないから」
若宮の心を見透かしたように、女性幹部が言った。
「一割をあなた達の報酬としてバックしてあげるから、三人でわけなさい。二千万くらいは、渡せると思うわ」
「岩田が捕まったの、知ってるんですか?」
「ニュースで派手に報じていたわ。想定内ね。捕まらなくても処理しようと思っていたところだから、手間が省けたわ」
女性幹部の口調は、壊れた冷蔵庫を新しく買った店に引き取ってもらえてラッキーとでも言うようだった。
「じゃあ、俺は戻っていいですか? 報酬の連絡は中井さんに……」
「あなたに、会いたいっていう人がいるの」
若宮を遮り、女性幹部が言った。
「俺にですか!?」
とてつもなく、嫌な予感がした。
「ついてきて」
女性幹部がフロアの奥に若宮を促した。
奥には鉄製のドアがあった。
女性幹部はドアをノックした。
「入れ」
中から聞こえる男性の声に、若宮の全身に緊張が走った。
「失礼します」
女性幹部が敬語を使う相手ということは……。
若宮の緊張に拍車がかかった。
女性幹部がドアを開けると、十坪ほどの空間が現れた。
広いフロアと同じように、配線とコンクリートが剥き出しの状態だった。
窓際に、モスグリーンのスーツを纏った長身の男性が背を向けて立っていた。
「ボス、若宮を連れてきました」
女性幹部が声をかけた。
「ボス!?」
思わず、若宮は声を上げた。
「挨拶しなさい」
女性幹部が冷え冷えとした声で命じた。
「は、はじめまして! 若宮と言います」
若宮は、弾かれたように体を九十度に曲げた。
「ここは、十五年以上前にオレオレ詐欺の事務所に使っていたところでね」
唐突にボスが語り始めた。
「最初の頃は闇金の取り立て現場で、追い込みをかけられる債務者に同情していた。首吊り自殺している債務者の死体を見て飯が喉を通らなかった。一日も早く、こんな世界から足を洗いたいと思っていた。大切な人のために大金が必要だった。この世界は向いていない、金が溜まるまでの我慢……そう自分に言い聞かせていた。時は流れた。自らの意思とは関係なく、俺は闇世界で伸し上がった。いつしか、人を不幸にしても平気になった。人が死んでも平気になった。あれほど苦しめられた罪の意識を、まったく感じなくなっていた」
ボスは、背を向けたまま語り続けた。
どうして自分に身の上話をするのかわからなかった。
なにより、どうして自分と会いたかったのかが……。
「なぜ、こんな話をするんだと思っているだろう?」
言いながら、ボスが振り返った。
反射的に若宮は、ボスの顔を見ないように俯いた。
「殺すために呼んだわけじゃない。顔を上げろ」
ボスの言葉に、若宮は恐る恐る顔を上げた。
切れ長の瞳……氷の瞳が若宮を見据えていた。
体温を奪われそうな冷たい瞳に、若宮は金縛りにあったように動けなかった。
「あの……どうして、俺だけ?」
若宮は掠れた声で、怖々と訊ねた。
まだ、安心したわけではなかった。
ボスも女性幹部も、人を虫けらのように殺して金を奪う闇バイト組織のトップなのだ。
「今日から、お前を管理側に回す」
「えっ……」
思わぬ言葉に、若宮は絶句した。
「まずは氷花について、指示役としてのノウハウを身につけろ」
ボスが女性幹部……氷花に視線を移して言った。
「ちょ……ちょっと待ってください! 俺に指示役なんて無理ですっ」
我に返った若宮は、ボスに訴えた。
「なら、いつまでも現場のままがいいか?」
「いえ……そういう意味じゃなくて……」
「命じられるまま金を奪い人を殺し続けるか、指示役に回り結果を出してこの世界で上を目指すか……お前には二つの選択肢しかない」
若宮を遮り、ボスが平板な口調で言った。
「でも、俺はこういう世界に向いてませんし、伸し上がるなんて無理ですよっ」
謙遜ではなく、本音だった。
「お前、黒は最初から黒だと思ってないか?」
不意に、ボスが言った。
「え?」
若宮にはボスの言葉の意味がわからなかった。
「白も染まれば黒になる。俺も最初は白だった」
ボスの瞳が、瞬間、哀しげに揺れたような気がした。
「それは、どういう意味ですか?」
「お前も、俺みたいになれる可能性があるということだ」
若宮は耳を疑った。
自分に、ボスになれる資質があるというのか?
俄には信じられなかった。
「どうして……俺なんですか!? 度胸はないし、揉め事は嫌いだし、人を傷つけたくないし……俺より向いている人は、ほかにたくさんいるはずですっ」
若宮は一番の疑問を口にした。
ボスには、若宮のような駒は数百人単位でいるだろう。
今回のヤマは結果的に成功したとはいえ、たいした成果を挙げていない自分が選ばれた理由がわからなかった。
「たしかに、お前より度胸がある奴、腕が立つ奴、肚が据わった奴は大勢いる。だが、お前じゃなきゃならない理由がある」
「それは……なんですか?」
若宮は掠れた声で訊ねた。
「お前は、昔の俺に似ている」
ボスが若宮の双眼を射貫くように直視してきた。
「俺があなたに!?」
若宮の素っ頓狂な声が、剥き出しのコンクリート壁に囲まれた空間に響き渡った。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/