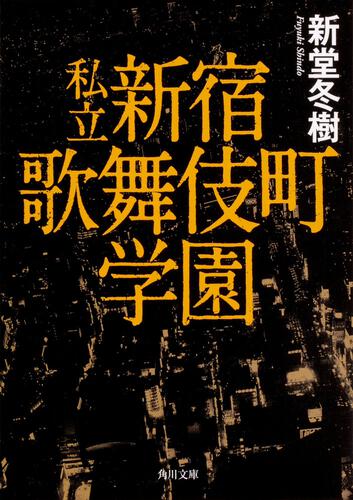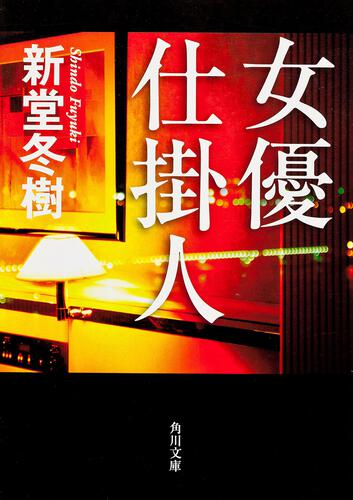【第5回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
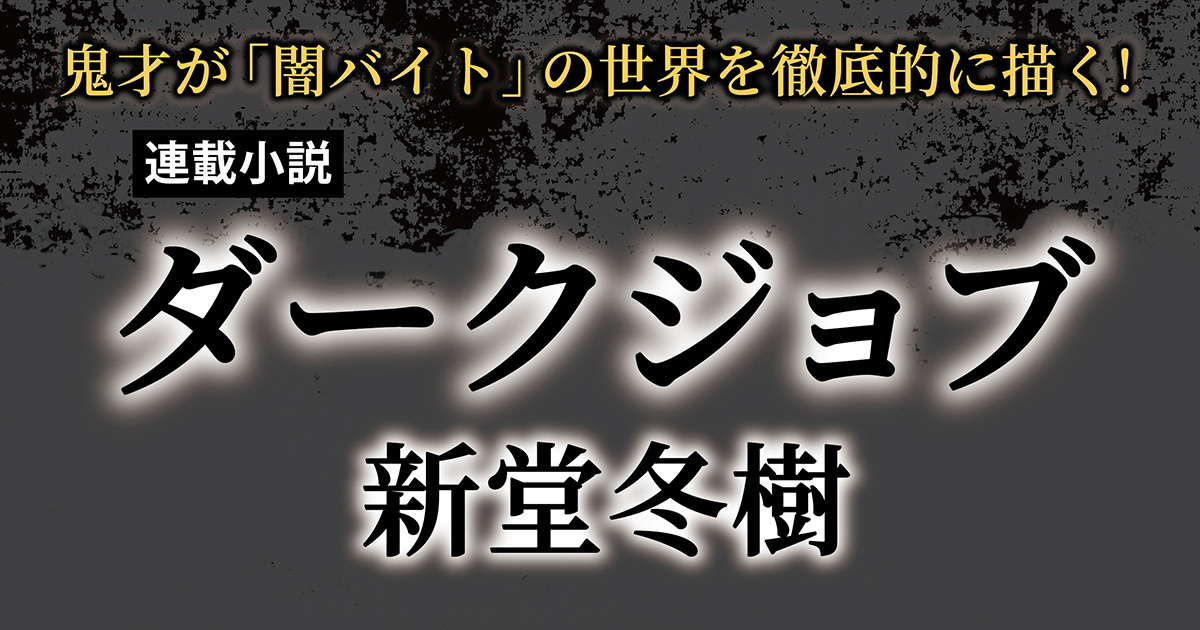
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第5回】新堂冬樹『ダークジョブ』
片桐★1988年夏
「必要なものは向こうで買えばいいから、最低限のものだけ持って行こう」
埼玉のビジネスホテル――明後日の渡米のための荷造りをしていた水樹に、片桐は言った。
水樹は心配性且つ貧乏性で、一泊の国内旅行でもスーツケースを二つ持って行くようなタイプだ。
国内旅行ならまだしも、今回の渡航先はアメリカだ。
しかも、三千万円を「スマイルローン」の金庫から盗んだので、いま頃、ケツ持ちの「斎藤組」の組員達が血眼になって捜していることだろう。
空港近辺で組員が張り込んでいる可能性もあるので、できるだけ身軽で目立たないようにしたかった。
「誠、英語できるの?」
水樹が手を止め訊ねてきた。
「できるわけないじゃん」
「だったら、言葉が通じないアメリカで買い物するのも一苦労よ。しかも、あっちの人はみんな大きいから、このサイズは売ってないと思うし」
水樹がスーツケースから下着を取り出し宙に掲げた。
「買い物くらい、俺のジェスチャーでなんとでもなるから。パンツなんてぶかぶかだって……」
「もう朝?」
ベッドで寝ていた杏が、眼を擦りながら身を起こした。
ビジネスホテルの狭い部屋なので、二人の話し声に目が覚めてしまったようだ。
「あ、ごめん、起こしちゃったね。まだ夜だから、寝てなさい」
杏はもろもろの検査ののちに、一ヶ月後には移植手術を受けることになっている。
心臓移植は全身麻酔をかけて五時間以上の大手術になるので、できるだけ杏の体力を残しておきたかった。
「アメリカに行ったら友達できるかな?」
不意に、杏が言った。
「できるさ。元気になって、いままでのぶんまで、たくさん遊ぼうね」
片桐は微笑み、杏の頭を優しく撫でた。
「杏、死にたくないな」
杏が不安そうに呟いた。
「あたりまえじゃないか! 杏が死ぬわけないだろう? 杏はアメリカで手術を受けたら、これから百年くらい生きるんだから!」
片桐は力強く言うと、杏を抱き締めた。
アメリカで手術を受ければ、きっと治るに決まっている……。
片桐は自らに言い聞かせた。
「本当?」
「ああ、本当だよ。パパが嘘を吐いたことある?」
杏が首を左右に振った。
「だから、安心してねんねしな」
杏が安心した顔で頷いた。
「よし、いい子だ」
片桐は言いながら、杏をベッドに寝かせた。
ほどなくすると、小さな寝息が聞こえ始めた。
「元気になるよね?」
片桐の隣で杏の顔をみつめながら、水樹が不安そうに言った。
「なんだよ、君まで。健康な心臓をもらうんだから、元気になるに決まってるだろ?」
「だよね! 万が一、この子の身になにかあったら……って思うと、頭がどうにかなっちゃいそう」
「それは、僕も同じさ。でも、僕ら親が不安がっていたら、杏に伝わっちゃうだろ?」
「そうね。私達が気持ちを強く持たなきゃだよね。明後日のフライトだよね? チケットはいつ貰うんだっけ?」
「明日の……あ、そう言えば、連絡がきてないな」
片桐は電話に視線をやった。
「連絡? 誰から?」
「君が看護婦から紹介された山根さん……ブローカーだよ。航空券だけじゃなくて、病院やホテルの手配も全部してくれてるからさ」
山根とは一昨日、大宮の喫茶店で待ち合わせをして初めて顔を合わせた。
「スマイルローン」から三千万円を持ち逃げしているので、都内には近寄りたくなかった。
臓器移植ブローカーということで胡散臭いイメージを持っていたが、濃紺のスーツに身を包んだ七三に銀縁眼鏡をかけた山根は銀行員のように堅い印象だった。
移植手術までに気をつけること、渡航日、現地の病院とホテルの説明を受けた片桐は山根に三千万円を渡し、ビジネスホテルの電話番号を教えて別れた。
明日の、航空券、ホテルと病院のパンフレットを受け取る時間と場所を決める電話がかかってくる予定だった。
「電話してみたら? ブローカーさんの名刺、貰ったんでしょ?」
「ああ、そうだね」
片桐は財布から山根の名刺を取り出した。
NPO法人 臓器移植協会
アドバイザー 山根真一
名刺には会社と自宅の電話番号が印刷してあった。
「八時か……。もう会社にはいないな。自宅にかけてみるよ」
片桐は受話器を取り、プッシュボタンを押した。
『アナタガオカケニナッタデンワバンゴウハゲンザイツカワレテオリマセン……』
「え?」
受話口から流れてくるコンピューター音声――片桐は、もう一度かけ直した。
『アナタガオカケニナッタデンワバンゴウハゲンザイツカワレテオリマセン……』
ふたたび流れてくるコンピューター音声に、片桐は胸騒ぎに襲われた。
「出ないの?」
水樹の問いかけを無視して、片桐は会社の電話番号をプッシュした。
コール音が鳴って、片桐は安堵した。
三回目でコール音が途切れた。
「もしも……」
『ウチは臓器移植協会ではありませんよ』
片桐の声を、女性の声が遮った。
「あの……『NPO法人 臓器移植協会』の山根さんという方の名刺を見てかけているんですけど……」
『昨日から、あなたみたいに臓器移植協会ですか? って問い合わせが十件以上かかってきて迷惑しているんですよね』
女性が、言葉通りに迷惑そうに言った。
「じゃあ……そちらは、全然違う会社なんですか?」
片桐は恐る恐る訊ねた。
『ウチは会社じゃなくて、個人の家です』
「そんな……そんなはずはありません! もう一度番号を言いますから!」
片桐は、名刺に印刷してある臓器移植協会の電話番号を読み上げた。
『はい、電話番号は合ってます。でも、ウチは高柳という個人宅ですから』
「からかわないでください! 娘の命がかかってるんですよ!」
思わず、片桐は大声を張り上げた。
『からかってなんかいませんよ! 嘘だと思うなら、一〇四に問い合わせてください。ウチの主人、高柳清介の名前で登録してありますから。住所は……』
女性は住所を言い終わると、一方的に電話を切った。
「あっ、ちょっと……もしもし!? もしもし!? くそっ!」
片桐は受話器をフックに叩きつけた。
「誠、どうしたの!?」
水樹が不安げに訊ねてきた。
片桐は一〇四にかけ、女性から聞いた住所と名前をオペレーターに告げた。
ほどなくして、オペレーターの口から出た電話番号は臓器移植協会の名刺に印刷されたものだった。
瞬間、頭が真っ白に染まった。
「誠っ、ねえっ、いったい……」
「やられた……」
片桐は震える声で水樹の声を遮った。
声ばかりではなく、受話器を持つ手も、唇も、膝も震えていた。
「え!? なに!? どういうこと!?」
「嵌められたんだよ……」
片桐は、うわ言のように呟いた。
「嵌められたって、誰によ?」
水樹が怪訝な顔で質問を重ねてきた。
「ブローカーの山根だよ!」
片桐は投げるように受話器を置いた。
「え!? まさか……三千万を持ち逃げされたの!?」
水樹が大声を張り上げた。
「ああ、そのまさかだよ……」
比喩ではなく、地獄の底に叩き落とされたように目の前が闇に包まれた。
「じょ……冗談じゃないわ! あのお金がなきゃ、杏は移植手術を受けられないのよ!? どうするつもりなの!?」
水樹がヒステリックに問い詰めてきた。
「もっと声を落として。杏が起きるだろ」
片桐は唇に人差し指を立てて言った。
「そんなこと言ってる場合じゃないでしょ! 手術を受けられないと、杏は死んじゃうのよ!」
「そんなこと、わかってるよ。どうするか考えるから、少し黙っててくれないか?」
「どうするか考えるって、なにを呑気なこと言ってるのよ! だいたいさ、怪しいと思わなかったわけ!? 本物のブローカーか偽者かくらいわからなかったの!?」
水樹が片桐を責め立ててきた。
「君の責任もあるんだぞ!」
片桐の抑えていたイライラが爆発した。
「どうして私に責任があるのよ!?」
「君が看護婦から紹介してもらったのが山根……その看護婦は、なんて名前なんだ!?」
片桐は水樹に訊ねた。
「え!? なんでよ!?」
「山根を紹介したのは看護婦なんだから、グルに決まってるだろ!?」
「里見さんって人よ。私の友達と同じ苗字だったから、覚えてるの」
「病院に行ってくる!」
「あ、ちょっと待って……」
片桐は背中を追ってくる水樹の声を置き去りに、客室を飛び出した。
☆
「里見はお休みを頂いてます」
池袋の「関東共済病院」のナースステーション――応対した婦長が片桐に言った。
「じゃあ、里見さんの電話番号を教えてください」
「個人情報なので、それはできません」
婦長がにべもなく言った。
「お願いしますっ。里見さんに緊急の用があるんです!」
片桐の大声に、カウンターデスクの奥で作業していた看護婦の視線が集った。
「ここは病院です。大声を出さないでください。ご用件をおっしゃってくれれば、伝言しておきますから」
「里見さんから紹介された臓器移植ブローカーに、三千万を持ち逃げされたんですよ!」
「こちらへきてください」
婦長が強張った顔で、ナースステーションから死角になる階段の踊り場に片桐を促した。
「里見の件ですが、当院でも警察に被害届を出しています」
婦長が声を潜めて言った。
「被害届!?」
片桐は眼を見開いた。
「ええ。片桐さん以外の患者さんからも同様の問い合わせが何件かありまして、里見に事情を聞こうと連絡をしても繋がらないのでアパートに行ったのですが、もぬけの殻でした。もしよろしければ、被害者の会の連絡先をお教えしましょうか?」
婦長の声が、鼓膜からフェードアウトした。
追われる身でなければ、もちろんそうしていただろう。
だが、ヤクザのフロント企業から三千万円を持ち逃げした片桐が、悠長に被害者の会で返金を求める訴訟など起こせるわけがない。
視点を変えれば、片桐も山根や里見と同じ犯罪者なのだ。
それに、タイムリミットが迫っている杏の心臓に、そんな時間的余裕はない。
「片桐さん? どうなさいます?」
婦長がなにか言っているが、耳に入らなかった。
毒を食らわば皿まで――杏の命を救うために、背に腹は代えられなかった。
片桐は病院を飛び出し、タクシーを拾った。
「渋谷の道玄坂」
片桐は運転手に告げた。
二服目の毒は、「スマイルローン」の系列の闇金融だ。
☆
雑居ビルの十階の非常口のドアを薄く開き、片桐は階段に腰を下ろしていた。
病院から移動して、既に十時間が経っていた。
一晩中非常階段に座って過ごしたが、苦にはならなかった。
杏の窮地に比べれば……。
片桐の視線は、ドアの隙間越しのエレベーターに向けられていた。
片桐は腕時計に視線を落とした。
午前七時五十五分。
八時には、小湊が出社するはずだった。
小湊は「スマイルローン」の系列店の闇金融、「大吉ファイナンス」の店長だった。
片桐もそうだったが、金庫の鍵を持っている店長は午前八時に事務所を開ける決まりになっていた。
三千万円はないにしても、種銭と売り上げを合わせて二千万円はあるはずだった。
とにかく、一刻も早く現金を集めなければならない。
こうしている間にも、杏の命のカウントダウンは進んでいるのだ。
片桐は足元に置いていた出刃包丁を手にした。
二十四時間営業のスーパーで購入したものだった。
顔を隠すための目出し帽は、ディスカウントショップで調達した。
「スマイルローン」の取り立て現場で、初めて首吊り自殺をした債務者を見たときに思った。
どうして、こんな職場に飛び込んでしまったのだろう……と。
だが、いま思えばあの頃は遥かにましだった。
三千万円を持ち逃げし、いま、犯罪を重ねようとしている。
エレベーターの作動音に、片桐の心拍が跳ね上がった。
上昇する階数表示のオレンジ色のランプ――全身に緊張が走った。
二、三、四階……出刃包丁を握り締める掌が汗ばんだ。
十階……エレベーターの扉が開いた。
ゴキブリの翅のようにテカったオールバック――下りてきたのが小湊だと認めた片桐は、そっと非常口のドアを開けた。
「大吉ファイナンス」のドアの前に立つ小湊の背後に足音を殺して近づいた。
「声を上げると刺すぞ」
片桐は小湊の背中に出刃包丁の切っ先を当て、声色を変えて言った。
「て、てめえ……誰を脅してると思ってるんだ!? ウチは『斎藤組』の……」
「余計なことを言うとぶっ殺すぞ。さっさと開けろ」
片桐は言いながら、出刃包丁の切っ先を強く腰に押し付けた。
「お前……もしかして、片桐か?」
不意に、小湊が訊ねてきた。
目出し帽で顔を隠して声色を変えても、毎週月曜日の店長会議で会っているのだからバレても仕方がない。
「余計なことを言うなと言ってるだろ!」
「もしお前が片桐なら、武士の情けで忠告してやる。命が惜しければこのまま帰れ」
小湊が言った。
背後から包丁を突き付けられた状況で、脅しが通用するとでも思っているのか?
小湊は単純なところはあるが、馬鹿な男ではない。
だとしたら、どうして……。
「お前こそ、死にたくなければドアを開けろ」
「馬鹿な男だ」
小湊は言うと、シリンダーに鍵を差すことなくドアを開けた。
鍵がかかっていない……。
片桐は違和感を覚えつつ、事務所に足を踏み入れた。
「金庫のある場所に案内しろ」
片桐が命じると、小湊は奥の部屋……店長室へと向かった。
「お前のことは、嫌いじゃなかった」
不意に、小湊が言った。
「無駄口を叩いてないで……」
小湊が店長室のドアを開けた瞬間、片桐は表情を失った。
「久しぶりだな。まさかこんなに早く再会できるとは思わなかったぜ」
デスクチェアに座っていた大男……矢島が、ニヤニヤしながら片桐に言った。
「あんた……どうして、ここに!?」
「現れそうな場所に網を張る。切り取りの基本だろうが。『スマイルローン』の次は、ここだろうってな」
矢島が言いながら、デスクチェアから腰を上げた。
「動くな! こいつがどうなってもいいのか!?」
片桐は出刃包丁を小湊の喉元に突きつけ矢島を牽制した。
「お前はよ、頭はキレるが昔から脇の甘いところがあるんだよな」
矢島の意味深な言葉の数秒後、背後で勢いよくドアの開く音がした。
振り返った片桐は息を呑んだ。
白、赤、黒のアロハシャツを着たパンチパーマをかけた男達が物凄い形相で乗り込んできた。
三人とも同じ顔をし、手にはナイフを握っていた。
「アロハパンチ三兄弟……」
片桐は呟いた。
「斎藤組」に手のつけられない凶暴な三人組がいると、噂では聞いたことがあった。
若頭の我妻が目をかけている三人は三つ子で、抗争があれば真っ先に敵陣に乗り込む武闘派中の武闘派だ。
三人ともまだ二十代だが、それぞれが殺人や傷害で五年以上の懲役を経験しているという。
「俺達のことを知ってるなら、竿とタマをトビズムカデの餌にされねえようにおとなしく従うぜよ!」
「タランチュラの餌のほうがいいばい!」
「ガマガエルの餌のほうがいいき!」
白アロハパンチの恫喝に、赤アロハパンチと黒アロハパンチが続いた。
どうやら、白アロハパンチが長兄のようだった。
「従わねえと、お前の親父の竿とタマも切り取るぜよ!」
「親父がいなけりゃ、お袋のアワビと豆でもいいばい!」
「親父もお袋もいなけりゃ、ダチの肛門と臍でもいいがや!」
ふたたびの白アロハパンチの恫喝に、赤アロハパンチと黒アロハパンチが続いた。
片桐の全身に鳥肌が立った。
なぜ、バラバラの方言を使うのか考えている余裕はなかった。
三人が言うと、単なる脅しに聞こえなかった。
「こいつが人質に取られていることを忘れるな」
片桐は弱みを見せないように、落ち着いた声で警告した。
ここで拉致されるわけにはいかない……杏のためにも、なんとしてでも切り抜けなければならない。
「人質って、こいつのことぜよ?」
白アロハパンチがずかずかと片桐のほうに歩み寄り、小湊の股間を刺した。
「うぎゃわーっ!」
小湊の叫び声が、室内に響き渡った。
床には、あっという間に血だまりができた。
動転、動揺、狼狽――身内を刺す予想外の行動に、片桐の思考が氷結した。
「さっき、聞こえたぜよ! もしお前が片桐なら、武士の情けで忠告してやるぜよ! 命が惜しければこのまま帰れぜよ!」
白アロハパンチが、さっきの小湊の口真似をした。
「もし貴様が片桐なら、武士の情けで忠告してやるばい! 命が惜しければこのまま帰ればい!」
「もしおぬしが片桐なら、武士の情けで忠告してやるき! 命が惜しければこのまま帰るがや!」
赤アロハパンチと黒アロハパンチが、小湊のセリフをそれぞれアレンジした。
三人とも、噂以上に常軌を逸していた。
出刃包丁を持つ手が震えた……心が震えた。
底知れない恐怖――片桐は、アロハパンチ三兄弟のイカれぶりに心底怯えた。
「ん? どうしたぜよ? 人質を刺さないぜよ?」
白アロハパンチが、不思議そうに首を傾げた。
「ん? どうしたばい? 人質を切らんとや?」
赤アロハパンチが、不思議そうに首を傾げた。
「ん? どうしたき? 人質を抉らないちゅうがや?」
黒アロハパンチが、不思議そうに首を傾げた。
もはや、小湊には人質の価値はなかった。
片桐は小湊を白アロハパンチのほうに突き飛ばし、ドアにダッシュした。
ノブを掴もうとしたときに、ドアが開いた。
「白組大トリの、北島三郎さんの登場ぜよ!」
司会者を気取る白アロハパンチの声が背後から聞こえた。
「俺の米櫃に手を突っ込むとは、いい度胸じゃねえか」
狂気の宿る瞳、右の目尻から口角を繋ぐ三日月形の刀傷、白のダブルスーツに白のエナメルシューズ――我妻がドスの利いた声で言った。
「よっ、サブちゃん!」
「よっ、大統領!」
赤アロハパンチと黒アロハパンチの合いの手が凍てついた脳内でこだました。
☆
「ち、近寄るな!」
片桐は、追い詰められた野良猫さながらに出刃包丁を両手に構えて我妻とアロハパンチ三兄弟を牽制した。
足元では、白アロハパンチに刺された血塗れの股間を押さえて小湊がのたうち回っていた。
「おい、盗人! そんなへっぴり腰で、俺ら全員を倒せると思ってんのか!? おお!?」
我妻が下腹を震わせる怒声を浴びせてきた。
多勢に無勢……わかっていた。
全員どころか、我妻一人も倒せないだろう。
なぜ、片桐がここに現れると感づいたのか?
「スマイルローン」で金が手に入らなければ系列の「大吉ファイナンス」を狙うかもしれないが、我妻達は片桐が三千万円を騙し取られたことを知らない。
なのに、なぜ、片桐が二度目の犯行に及ぶと予想したのか?
矢島だけならまだしも、相当な確信がないかぎり「斎藤組」若頭の我妻やアロハパンチ三兄弟まで待ち構えるはずはない。
どうして……。
思考を止めた。
理由がわかったところで、窮地を脱することはできない。
いまは、この絶体絶命のピンチを切り抜けることが先決だ。
事務所を脱出するには、ドア口にいる我妻をなんとかするしかない。
我妻の凶暴さと腕っぷしの強さは、嫌というほど見てきた。
包丁一本でライオンと戦うようなものだ。
それでも、ライオンに立ち向かわなければ片桐の人生はここで終わる。
もたもたしているうちに飢えたハイエナ達……アロハパンチ三兄弟の餌食になってしまう。
杏のために、こんなところで犬死にするわけにはいかない。
意を決した片桐は、出刃包丁を両手に構えたまま我妻に突進した――眼を閉じ、全体重を乗せて体当たりした。
足が止まった。
恐る恐る、眼を開けた。
「えっ……」
片桐は、眼を疑った。
出刃包丁の刃を、我妻が右の素手で握り締めていた。
我妻の右手からは血が滴り落ちていたが、ニヤニヤと笑っていた。
「飛んで火に入る、夏のゴキブリってか!」
我妻の膝蹴りが片桐の股間を突き上げた。
視界が蒼褪め、息が詰まった。
体をくの字に折った瞬間……顎を蹴り上げられた。
脳が揺れた。
気づいたときには、仰向けに倒れていた。
「とりあえず、爪剥がせや」
我妻が命じると、アロハパンチ三兄弟が川に落ちた獲物に襲いかかるピラニアのように群がってきた。
「俺は長兄だから両手を貰うぜよ!」
白アロハパンチが嬉々として片桐の右手を掴み人差し指の爪を噛むと、勢いよく顔を反らした。
ありえない激痛に、片桐は悲鳴を上げた。
「おいどんは右足貰うばい!」
「わしは左足を貰うき!」
赤アロハパンチが右足の親指の爪を、黒アロハパンチが左足の親指の爪を噛むと、それぞれチキンの太腿でも食いちぎるように顔を横に振った。
片桐の声量を増した悲鳴が事務所内の空気を切り裂いた。
「あと九枚剥がすぜよ!」
白アロハパンチが右手の残り四指の爪と左手の五指の爪を立て続けに口で剥いだ。
「うわあぁぁぁーっ! うわあぁぁぁーっ! うわあぁぁぁーっ!」
絶叫、絶叫、絶叫――片桐は声帯が潰れるほどに絶叫した。
「あと四枚剥がすばい!」
「あと四枚剥がすがや!」
赤アロハパンチと黒アロハパンチが、まるでスイカを持つようにそれぞれ左右の足を両手で抱えて中指から小指まで爪を剥ぎ取った。
もう、叫ぶ気力もなかった。
「おいどんの勝ちばい!」
「わしの勝ちじゃき!」
赤アロハパンチと黒アロハパンチが、口から爪を吐き出しながら己の勝利をアピールした。
「おいどんのほうが早く剥がし終わったばい!」
「わしのほうがコンマ二秒早かったき!」
「ぶぁーか! 俺が一番早かったぜよ!」
三人の内輪揉めの声が、鼓膜から遠ざかった。
「うあっ……」
遠のきかけた意識が、これまでを超える激痛で引き戻された。
赤く燃える視界――我妻が、爪を剥がされ露出した肉にアイスピックを突き立てていた。
「あぁぁぁぁぁぁーっ!」
もう出ないと思っていた悲鳴が室内に響き渡った。
「爪剥がされたくれえで、気ぃ失うんじゃねえぞ! 俺の米櫃から三千万も盗んだお仕置きは、これからが本番だ!」
我妻が片桐の髪を鷲掴みにして顔を近づけると、サディスティックな冷笑を片頬に張りつけながら言った。
「若頭っ、俺にこいつの竿を切らせてくださいぜよ!」
「若頭っ、おいどんにこいつのタマを切らせてくれんですか!」
「若頭っ、わしにこいつの肛門を切らせてくださいがや!」
アロハパンチ三兄弟が、口角泡を飛ばし我勝ちにお仕置き人に立候補した。
「てめえらっ、ごちゃごちゃうるせえ! こいつは俺の獲物だ! これ以上口出すと、てめえらの唇を切り取って歯を全部引っこ抜くからな!」
我妻が三人を恫喝し、片桐の手足の爪を剥がされたあとすべてにアイスピックを突き刺した。
視界が暗くなった。
もう、痛みも感じなかった。
もしかして、このまま死んでしまうのか……。
そうでなくても、我妻に殺されるだろう。
杏を救うことができなかった。
ごめんな……。
体に力が入らなかった。
情けないパパで……。
頭も回らなくなってきた。
急に、体が浮いた。
我妻が片桐の体を重量挙げのバーベルのように頭上に持ち上げていた。
「だから、この程度で気ぃ失ってんじゃねえよ!」
我妻が言いながら、窓際に歩み寄った。
「おいっ、開けろや!」
我妻に命じられた矢島が、窓を開けた。
「十階から投げ捨てられりゃ、脳みそぐちゃぐちゃか半身不随の二択だな。俺から金盗んで車椅子生活ならラッキーだと思えや」
我妻が嗜虐的に言いながら、窓の外に身を乗り出した。
終わった……。
片桐は眼を閉じた。
ニュースで片桐がヤクザに殺されたと知ったら、水樹はどう思うだろうか?
こんなろくでなしの夫で……こんなひとでなしの父親で悪かった。
「生涯、俺に忠誠を尽くす
不意にかけられた我妻の言葉に、片桐は眼を開けた。
「特別に、もう一つの選択肢を与えてやるぜ」
我妻は片側の口角を吊り上げた。
神は自分を……いや、悪魔は自分を見捨てていなかった。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/