彼らは世界にはなればなれに立っている
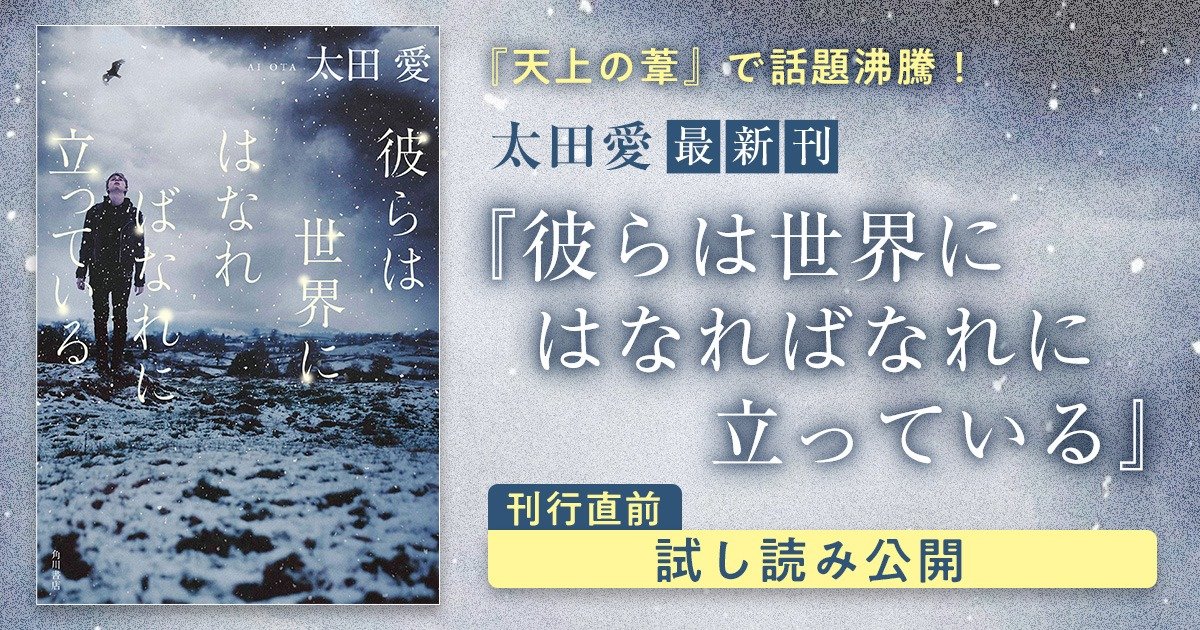
「これは、過去でも未来でもない『今』だ」鴻巣友季子氏推薦! 太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』特別試し読み#4
〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれ、公然と差別される存在だ。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレの一家に浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した――。
最注目の著者による衝撃作、10月30日の刊行を前に特別試し読み!
>>前話を読む
あのキルトのカレンダーの下は化粧板が割れてへこみ、破れたスミレの小花柄の壁紙には黒っぽい血の痕が残っている。
あの時の父さんの問いに僕自身、答えられない。
──なぜおまえは俺たちと違うんだ。
それは、なぜおまえはおまえなのだ、と問われているに等しい。
スベン叔父さんは大叔母の面倒を見るために町に残り、葬儀屋の事務員の職を得た。父さんは長期の仕事を志願して町を離れ、母さんはキルトのカレンダーを作り始めた。
暮れになって帰ってきた父さんは、母さんのために晴れ着用の目の覚めるような美しい布地を買ってきた。早朝の浅瀬のような淡い緑色で、母さんの明るい緑の目の色によく似合っていた。母さんはびっくりして声もなく眺めていたが、やがて
父さんは会心の笑顔を見せて言った。
「人の晴れ着はたくさん縫ってるんだから、自分のも一着くらいは持っておかないとな」
たぶん父さんは自分の鬱屈の根がどこからきているのかわからないのだと思う。だからなにかこじれるたびに突飛な思いつきで母さんを喜ばせようとした。
修繕屋の火事の時もそうだった。
火事のせいで塞ぎ込んでいる母さんに、父さんは腹を立てた。久しぶりに仕事から戻ったというのに、どうして明るく迎えられないのか、ねぎらう気持ちさえないのかと母さんを責めた。母さんはうな垂れてごめんなさいと謝り、父さんは握っていた硝子コップを投げ捨てて出ていった。
それからすぐ、週報に二十年ぶりに客船が来るという大見出しが躍った。船が入港する日曜日は夕方から塔の広場でお祭りが催されると報じられていた。
父さんは夜、運転手の詰め所から戻るなり、休みを代わってもらったのでみんなでお祭りに行こうと言い出した。
「その日はいちにち、家族で楽しむんだ。朝から海水浴に行って、それからお祭りだ」
父さんは意気揚々と宣言してみずからビールの栓を開けた。もちろん僕は歓声をあげた。外に出て楽しいことをすれば、きっと母さんも笑顔を取り戻すと思った。父さんは口のまわりの白い泡を拭うと、素晴らしいアイディアを思いついたように言った。
「そうだ、お祭りにあの晴れ着を着ていけばいい」
薄緑色の豪華な布地は七年前に晴れ着に仕立てられたまま、着る機会もなくしまわれていた。母さんは躊躇したが、寝室の
広がった長い
「ここに刺繡をするといいよ」
僕はドレスの胸の部分を指さした。刺繡は母さんの晴れ着に欠かせないものだ。
「ああ、それだ」と父さんも声をあげた。「刺繡だよ」
母さんは父さんと僕に背中を押されるようにしてその日からドレスに刺繡を施し始めた。もともと好きな仕事だからだろう、母さんは久しぶりに集中し、静かな喜びを感じさせるリズムで針を動かしていた。
もし時間を巻き戻してやり直せるなら、僕は箱にしまった晴れ着を取りに行ったりはしないし、決して刺繡のことなど口にしない。
だがもうすべては起こってしまった。
あの夜、たくさんの間違いの種が
お祭りの日のことは、何度も繰り返し観た映画のように、隅から隅まで覚えている。
†
日曜日、僕たちは自転車に乗っていつもの入り江へと出発した。僕の自転車の荷台には飲み物の入ったクーラーボックスと弁当のバスケットが紐で縛ってあった。前を行く父さんの自転車の荷台には、麦わら帽を
入り江には誰もおらず、父さんと僕は
泳いでは昼寝をしたり砂浜で遊んだり、ホルトノキの木陰で遅い昼食を取る頃には三人ともすっかり陽に焼けて肩や背中が赤くなっていた。
最初に船影に気づいたのは母さんだった。食べ終えたばかりの揚げ
「まえに来た客船もあんなふうだったの?」
僕たちの中でただひとり、二十年前に来た最後の客船を見ている父さんは面食らった顔で首を横に振った。
「こりゃ、まえのよりデカいぞ」
壮麗な船体は動く白亜の城を思わせた。あの客船にはいったいどんな人たちが乗っているのだろう。僕は港に行きたくてたまらなくなった。
「見に行っていい?」
「夕方までには帰れよ」
父さんが答えると同時に僕はシャツと半ズボンを摑んで駆け出していた。
船尾に掲げられた旗によって、客船は塔の地と盟友関係にある〈潮の地〉から来たのだとわかった。とすると、タラップ脇で伯爵と握手を交わしているいかにも要人らしい
ホテルに宿泊する人も多いらしく、大きなトランクや円い帽子の箱が船から馬車へと運ばれていたが、荷役は全員、長い髪を複雑に編み込んだ小柄な男たちだった。それまでそういう人々を見たことがなかったので、僕は興味津々で眺めた。
馬車の後ろを回り込んでタラップの方に近づくと、乗客たちの話し声が聞こえてきた。どうやらそれは塔の地の言葉ではなく、僕らが授業で習う共通語のようだった。学校と映画館以外で共通語を聞いたのは初めてだったが、先生の発音とはかなり異なっている。
見ると、タラップのそばに黄色いコンバーチブルが停まっており、コンテッサが車から少し離れた所で乗客らしい同世代の男女と立ち話をしていた。個性的な服を
久しぶりの再会を喜び合っているのだろうと思いながら近づくと、予想に反して三人は険しいほど真剣な表情でなにやら小声で話し合っていた。それは塔の地の言葉でも共通語でもない、僕の聞いたことのない言葉だった。
コンテッサが僕に気づいて話をやめた。音楽が小節の途中で終わったような不自然な感じだった。なにか悪いことをしたような気がして僕は立ち去ろうとした。だがコンテッサが素早く僕に歩み寄り、一緒にいた男女に向かって〈映画好きの私の小さなお友達〉と紹介した。
男女はたちどころに僕を輪の中に迎え入れた。女の人はティティアン、男の人はラウルといって二人とも地理学者で調査のために旅をしているのだという。学者というとなんとなくかび臭い老人のように思っていたので、僕は若くて映画スターのような二人にびっくりした。
ティティアンとラウルはいくつもの土地の言葉に堪能で、塔の地の言葉も
そして髪を編み込んだ荷役たちは、潮の地の羽虫なのだと教えてくれた。客船でも、洗濯場や
二人は僕が尋ねるままにこれまで客船で巡ってきた土地のことや、これからの旅程について詳しく話してくれた。彼らは僕の想像もできないような広い世界に関する膨大な知識を持っていて、それを対等な友人に話すように僕に語ってくれた。
僕は素晴らしい人たちに出会った興奮を一刻も早く父さんと母さんに知らせたくて、全速力で自転車を走らせた。家が見えるとスタンドを立てるのももどかしく、自転車を投げ出して玄関に駆け込んだ。ところがどうしたことか居間にも台所にも父さんたちの姿はなかった。廊下に出てみたが、浴室を使っている音も聞こえない。
なにか張りつめたような静寂が家の中を満たしていた。僕はL字の階段を二階へ上がった。
父さんと母さんの寝室の扉が開いており、室内によそゆきのシャツを着た父さんが立っていた。父さんは部屋の隅のなにかを、息をつめてじっと見つめていた。空気を揺らすのを恐れながらも、僕は引き寄せられるように近づいた。
扉の脇の大きな姿見に、父さんが見入っているものが映っていた。
僕の足はその場に
鏡の中に晴れ着を着た母さんがいた。薄緑色のドレスの胸元に極彩色の華麗な鳥が刺繡されており、その鮮やかな色合いが晴れ着に合わせて化粧した顔に映えて、母さんはまるで遠い地の王族の姫君のようだった。
「そのスカーフを、あの頃みたいに髪に巻いてくれないか」
父さんが夢見るように言った。
母さんは後ろに長く垂らした共布のスカーフを外し、ふんわりと髪を覆うように巻きつけた。目を伏せたままスカーフに
父さんに初めて出会った頃、母さんはまだ故郷の髪形をしていたと聞いたことがある。この町に来る以前、きっと母さんはこんなふうだったのだ。
鏡の中の母さんがゆっくりと目を上げ、僕を見つめた。いつから気づいていたのかわからない。ただ母さんの中には僕の知らない長い時間があるのだと思った。
薄紫に暮れていく空の下、広場には色とりどりの電球が輝き、塔を背に作られた仮設舞台では、タキシード姿のバンドマンを従えて、中折れ帽を被った男性歌手が
父さんは奮発してテーブル席の券を買っていたのだが、僕たちが広場を横切って所定の席へ向かうあいだ、女たちはお喋りを中断し、男たちはビールジョッキを宙に浮かせたまま、そろって母さんに驚嘆の目を向けた。
父さんは誇らしさで舞い上がったようにどちらでもいいことを喋り続けていた。子供の頃の揚げ菓子の方がひと回り大きかったとか、しばらくは晴天が続くだろうとか、人々の視線を意識するあまり声もいつもより少し大きくなっていた。警察署長のダーネクさんが母さんに感服したように署長帽を上げて会釈するに至って、その声量は二倍に跳ね上がった。
僕は母さんのためになにかしたかった。そこでテーブル席に
「俺とトゥーレは飲み物なんかを買ってくるから」
一緒に行こうと立ち上がりかけた母さんの肩を父さんがそっと押さえた。
「今日はなにもしなくていいんだって」
僕は父さんと二人で屋台の方に向かった。
「これで好きなものを買ってこい」と、父さんが小遣いをくれた。
テーブル席を振り返ると、ひとりで座っている母さんが心細そうに見えた。僕はできるだけ早く戻ろうと、すいている屋台を探した。
広場を縁取るように建ち並んだ屋台は、肉の焼けるこうばしい匂いや食欲を刺激する様々な香辛料の匂いを張り合うようにまき散らして、すでにそこここに行列ができていた。僕はすぐさま揚げ菓子の列に並んだ。
生地を巻きつけた
揚げ菓子とレモン水を手に戻ってみると、予期せぬ事態が待ち受けていた。母さんを取り囲むようにして男たちが席に座っていたのだ。うつむいている母さんに顔を寄せて話しかけているのは洗濯場のラシャだ。以前は他の町でなにか商売をしていたらしいが、両親が死んだのを機に町に戻って跡を継ぎ、洗濯場を取り仕切っている。葉巻屋の話では、農場の青年や職にあぶれた町の若者に酒を
僕は粘り着くようなラシャの視線を一秒でも早く母さんから引き剝がしたくて、まっすぐにラシャに近づき、ここは僕たちの席です、と言った。ラシャは鼻で笑っていきなり僕のシャツの襟を摑んだ。母さんがとめようとラシャの腕に取りつき、紙コップのレモン水がこぼれて石畳を濡らした。突き倒される前に、残ったレモン水をラシャの顔面に浴びせるという考えが頭をよぎった。だが実行に移すより早くラシャは短い叫びをあげてのけぞった。片手にビールジョッキを二つ持った父さんが、もう一方の手でラシャの後頭部の髪の毛を摑んでいた。
「うちの家族になにか用か」
父さんが手を離すとラシャはおたおたと立ち上がった。そしてひどく当惑した様子で母さんと父さんを見比べたあげく、やっと合点したらしく口を開いた。
「てっきり外の人かと思ったもんで」
ラシャたちはひとりで座っていた母さんを客船の乗客と勘違いしたようだった。母さんは日頃からあまり出歩かないし、今日は見違えるようだから無理もないかもしれない。
そそくさと立ち去るラシャたちの背中に父さんが得意顔で大きな声をかけた。
「青年団に入れなくて残念だったな」
ラシャは青年団の入団テストで不正を働いたのが露見して週報に載ったことがあった。
人混みの向こうでラシャが立ち止まり、
「羽虫のくせに」
鋭い囁きは父さんの耳には届かなかったらしく、腰を下ろして旨そうにビールを飲んでいる。
だが、離れた席でラシャの言葉に身をこわばらせた赤毛の少女がいた。
ハットラは表情を殺して卓上のランタンを見つめていた。彼女が赤毛を受け継いだ母親のディタさんは、うな垂れまいとするように
半分羽虫であること。それがハットラと僕の共通点だった。そしてそのような子供は、町では彼女と僕だけだった。ハットラは中等科の三年生だったが、秋の大会の短距離の部で優秀な成績をおさめれば、五年制の中等科を飛び級して中央府の体育学院に進むことも可能だといわれていた。ハットラならきっとできると僕は思っていた。
母さんがハットラの一家に気づいて会釈した。ディタさんはわずかに顎を引いて頷いただけだった。ハットラは母親に気を遣ってのことだろう、ランタンを見つめたまま困ったようにまばたきをした。まともに会釈を返したのはアルタキさんだけだった。
子供同士の共通点にもかかわらず、僕はこれまでうちの両親がハットラの両親と話しているのを見たことがない。父さんがディタさんのように気性の強い女の人をあまり好まないだろうことは想像に難くない。ただそれとは別に、僕はどことなく父さんがハットラの一家を自分たちとは違うものと考えているような気がしていた。ディタさんの冷淡な態度はそれを感じ取った反映のように思えた。
突然、円テーブルのひとつから若い女性たちの悲鳴のような歓声が沸き上がった。見ると、客船の乗客らしいヘッドドレスの女性たちが手を取り合って喜んでいる。
「なに?」と、僕は母さんに尋ねた。
「福引きに当たったの」
母さんが目で舞台の上を指した。
いつのまにか歌が終わり、蝶ネクタイの司会者が
「さあお嬢さんがた、どうぞこちらへ」と腕を振って招き、バンドが軽快な音楽を演奏し始めた。若い女性たちは席を立ち、拍手と音楽に促されて舞台にあがった。それからシャンパン一ケース分の目録を受け取り、弾んだ声で始まりの町への好意的な印象を述べた。
「うちも福引きを買っとくんだったなぁ」と、父さんがぼやいてふと僕の揚げ菓子に目をとめた。「それ、
「そうじゃなくて、壺の中に一度埋めたんだよ」
父さんは意図的な行為らしいと理解したものの、砂糖まみれのそれが美味しいという意見には共感しがたい表情でポケットから落花生の小袋を取り出した。
僕はかまわず串に刺された揚げ菓子にかぶりつき、深い満足感に浸りながら広場を見まわした。お祭りとあって羽虫たちも遠巻きに見物に来ていた。
後方の射的屋台の前に怪力と葉巻屋が立っていた。制服姿の怪力はハッカ水の瓶を手にのんびりと舞台を眺めていた。鳥打ち帽の葉巻屋は、吸い殻を集めるいつもの革のショルダーバッグを提げて、嬉しさの隠せないほくほくした顔をしている。これだけの人がひとところに集まっただけでも儲けものなのに、客船の人々の上等な煙草の吸い殻が大量に収集できるのだ、笑いがとまらないのも当然だろう。
客席をはさんで反対側にカイの姿があった。舞台近くのテーブル席に両親がいるのにそちらへ行く様子もない。カイは図書室の本を抱えて人混みの中に立ち止まったまま、舞台下手の方を見つめていた。
カイの視線の先、舞台下の石畳にくわえ煙草のマリがいた。両手を腰に当て、顎を上げ、広場を
脇の屋台の隙間から現れたのはパラソルの婆さんだった。みすぼらしい身なりの老婆が黄色いパラソルの縁飾りを揺らしてしゃなりしゃなりと歩くさまに酔客から、奥様どちらへ、とからかう声が飛んだ。パラソルには賛美の言葉に聞こえるのだろう、
「じろじろ見てはだめよ」
母さんが僕の腕に手を置いてたしなめた。僕は頷いて揚げ菓子を頰張った。母さんはパラソルを気の毒な人と呼び、父さんは頭のネジが緩んだ婆さんと呼ぶ。僕はどちらも正しいと思うけれど、パラソルの怪力に対する蛮行には閉口していた。
案の定というべきか、いきなり夜空を突き上げるようなパラソルの奇声がとどろき、続いて人々の爆笑が起こった。僕は振り返りたくてたまらなかったけれど、母さんの目顔の戒めには従わざるをえなかった。だが見なくてもなにが起こったのかはわかっていた。パラソルが怪力の巨体を認めて襲いかかり、怪力はほうほうの体で逃げ出したのだ。
「おい、魔術師が来てるぞ」
父さんが舞台の上手脇を指さした。
魔術師が長いローブを尻までめくり上げて吸い殻を拾っていた。このところしきりと足腰の衰えを口にするようになっていたのに、驚嘆すべき敏捷さで次々と吸い殻を集めている。上等な吸い殻を葉巻屋に持っていき、少しでも煙草を安く売ってもらいたいという熱い願望がひしひしと伝わってきた。
「今日はどんな演目をやってくれるのかしら」
母さんが待ち遠しそうに言った。
昔から母さんは魔術師の出し物が好きだった。仕掛けが見えてもおかまいなし、典雅な動きで笑顔を振りまく魔術師を見ていると、いつのまにか胸のつかえを忘れて心から笑っているのだという。
「楽しみだね」と僕は言った。
母さんが久しぶりに朗らかに声をあげて笑うのだと思うと、とても嬉しかったのだ。
「88番のかた、いませんか」
司会者が大きな声で繰り返し、次第に人々がざわつき始めた。どうやら賞品の当選者が名乗り出ないらしい。
「福引き券をお持ちの方は今一度番号をご確認下さい。またテーブル席の方はもれなく福引きがついておりますので、裏面の番号をご覧下さい」
父さんは席に福引きがついているのを知らなかったらしく、卓上で落花生の殻に埋もれかけていた券をつまんで裏返した。
『88』と記されていた。
僕と母さんは驚いて顔を見合わせ、父さんは慌てて手をあげて立ち上がった。
やきもきしていた司会者はすぐさまバンドに合図を送ると、大きな身振りで僕たちを紹介した。
「幸福なご家族が幸運に恵まれたようです、さあ、こちらへどうぞ」
拍手と音楽に
辺りはすっかり暮れて色鮮やかな電飾が濡れたように
アナウンスされたとおり、その時までは、僕たちは幸福な家族だった。
†
玄関ポーチに『賞品』と貼り紙をされた段ボール箱が置かれているのに気がついたのは、居間の掃除を終えたあとだった。あの晩、舞台に上がった時は父さんも母さんも僕も、なにが当たったのかさえ知らなかった。玩具屋の店員は迷信深いから、変事の起こった家の空気に触れたくなかったのかもしれない、ノッカーを叩かずに賞品だけを置いていったようだ。
貼り紙を外すと、段ボール箱に『手回しハンドル式シャボン玉製造機』の絵が印刷されていた。僕はシャボン玉で大喜びする年齢をとうに過ぎていたが、司会者に目録を渡された時は、来月の母さんの誕生日に使うと楽しいかもしれないと思った。
僕は賞品が目につかないように納屋に運んだ。戸が開けっぱなしになった納屋の中に、きのう父さんが使った縄ばしごが投げ出してあった。それを元どおり畳んで麻袋にしまい、シャボン玉製造機を棚の下に押し込んだ。
父さんは夜が明けるとすぐに山へ向かったらしい。僕が起きてきた時には台所に書き置きが残されており、『昼には一度もどる』とあった。
僕は手を洗うと、洗濯より先にとりあえず昼食を用意しておこうと食料戸棚を開けてソーセージの缶詰を手に取った。そのとき突然、僕の最終的な目的をより確実に達成する選択肢が頭に浮かんだ。
家に昼食がなければ、父さんと二人で海岸公園にある軽食屋に行くことになる。軽食屋はホテルの喫茶室の出店で開店時刻は十一時。雇われ店主の老人は話し好きの好人物として知られているが、その避けがたい結果として仕事が遅く、仮に僕たちが開店時刻に入店したとしても、家に戻ってくるのはどんなに早くても間違いなく正午を過ぎる。この時刻はとても重要な点だった。
僕は缶詰を元に戻して食料戸棚を閉じた。そうして、気象ニュースを聞いたあとマルケッタの靴跡のついた父さんのシャツのたぐいと木曜日からたまっている洗濯物を丁寧に洗って庭に干した。
風力発電のプロペラの向こうに波頭のような積乱雲が湧き上がっていた。
昼にはまだ間があった。
僕は不意に映画館に行こうと思いついた。マリに訊いてみるのだ。水曜日の午後、母さんはなんのために三階建てにあるマリの部屋を訪ねたのか。
僕に出くわした母さんがなぜあれほど狼狽したのか、その理由を知ったところでなにかが変わるわけではないとわかっていた。僕はただ、マリと母さんの話がしたかった。
すぐさま自転車に乗って家を出た。
土曜日の初回が上映されている時刻だから、きっとマリはいつものように受付の机に突っ伏しているだろう。だが、なまけ者のマリと呼ばれるゆえんであるその姿には、ひとつの秘密が隠されている。
僕がそれを知ったのはマリに出会ってすぐの頃だ。マリはどんな顔をして眠るのだろう、という単純な好奇心に動かされて、僕は通りにあったジュースの木箱にのぼって突っ伏しているマリの顔を覗いてみたのだ。
マリはみんなが考えているように居眠りしているのでもなければ、ただぼんやりとしているのでもなかった。
片方の腕に頭をのせたまま、まばたきもせずにマリはじっと一点を見つめていた。いったいなにを見ているのかと僕は首を伸ばした。しかし、そこには古ぼけたスタンプの箱があるだけだった。不思議な気持ちで眺めるうち、あの動かない
そのことを僕は誰にも話していない。もちろんただの勘違いかもしれない。にもかかわらず、それを黙っていることで僕はずっとマリを守っているような気がしていた。
もしかしたら、母さんもマリの秘密を知っていたのではないか。そんな奇妙な考えが浮かんで消えた。
映画館の前には一台の自転車も停まっていなかった。スタンプカードを持たずに館内に入るのは、初めてひとりで映画を観にきたとき以来だと気づき、その時よりも何倍も緊張しているのを感じた。映画館に通い始めてからも、会話と呼べるほどの言葉をマリと交わしたことはないのだ。
マリはやはり受付に突っ伏していた。カウンターの向こうに見える強いウェーブのかかった髪とノースリーブの肩は動く気配もない。赤い扉の向こうから外の地の言葉らしい男女の台詞が小さく聞こえていた。
名前を呼ぶ勇気はなかった。
「すみません」
自分の声がひどく弱々しく聞こえた。
マリは大儀そうに身を起こし、ろくにこちらも見ずにスタンプに手を伸ばした。
「映画を観に来たんじゃないんです」
その言葉にマリはあからさまな非難の色を浮かべて顔を上げた。次の瞬間、意外なものを見たようにマリの目がわずかに見開かれた。
アレンカの息子だと認めたのがわかり、僕はそれに力を得て言った。
「水曜日の午後、母さんはなにか用事があって三階建てを訪ねたんですよね」
僕はマリが頷いて母さんのことを話してくれるのを待った。
「いなくなる前の日のことが、今さら気になるのかい?」
おめでたい人間を眺めるような冷ややかなまなざしだった。そのまなざしは僕が気づかないふりをしていた浅ましい願望を見透かしていた。心のどこかで、僕はマリが可哀想に思ってほんの少し優しくしてくれるのを期待していたのだ。
後悔と恥ずかしさで体が震えるようだった。
僕にそんな資格があるはずがない。引き返せないところまで母さんを追いつめたのは、僕自身なのだ。
マリは容赦なく僕の愚かな子供の仮面を剝ぎ取った。
「こうなるってことは、おまえにもわかっていたはずだよ。知らなかったって言うつもりかい?」
僕は後ずさり、逃げるように映画館を出た。
マリにはなにもかもわかっているのだと思った。
ああそうだ、僕はみんなの前で母さんを消してしまった。
†
蝶ネクタイの司会者が、もっと拍手を、と人々を
突然のことで僕はすっかり上がってしまってなにを喋っていいかわからなかった。マイクの声が途切れたその時だった。客席の一角から大きなヤジが飛んだ。
「羽虫が一匹まじってるぞ」
「なんで舞台に羽虫がいるんだ」
酔っ払ったラシャと取り巻きたちだった。
母さんの胸が大きく波打ち、極彩色の刺繡の鳥が震えるようだった。
僕は助けを求めて傍らの父さんを見た。父さんは硬い表情でじっと黙って前方を見つめていた。母さんにも僕にも目を向けることなく、
僕は初めて気づいた。父さんは聞こえていないふりをしているのだ。そうすることで無視できる、いや、なかったことにできると思っている。ラシャが僕たちの席から去る時に母さんを羽虫と言ったのも、本当は聞こえていたのだ。聞きたくないことは聞こえないふりをして、なかったことにする。たぶん父さんはこれまでもずっとそうしてきたのだ。
誰もラシャたちのヤジをとめず、青褪めた母さんをみんなが見ていた。あいつらを黙らせなければ。僕は考える前に喋り出していた。
「僕は半分が町の人間でもう半分が羽虫だから、父さんと僕で1.5の町の人間。母さんと僕で1.5の羽虫。だから1.5と1.5で帳消しになるんです」
ラシャたちの酔いに濁った頭はどう反応すべきか判断がつかなかったらしく、口を開けたままどんよりとした顔を
どちらにはじけるかわからないような不穏なざわめきが辺りに広がっていた。
そのとき突如、
警察署長のダーネクさんが気の利いた冗談を聞いたように手を叩きながら笑っていた。同じ席の看守長や警官たちがすぐさま後に続いて笑い出した。笑いは増幅し、突風のように広場を
なんだか僕もおかしくなってひとりでに頰が緩みかけた。だがその時、客席のなかほど、ひとつのテーブルから静かに立ち去る人々の姿が目に飛び込んだ。
ハットラの一家だった。
ディタさんとアルタキさんとハットラが無言のうちに抗議の意志を示すかのように、笑いの発作に背を向けて帰っていく。
僕は自分のしたことに気づいて
僕は『父さんと僕の半分』で、まるで恥ずべき汚点を拭うかのように母さんを消してしまったのだ。
これまで僕は父さんがまるで自分の意志でこの町の人間に生まれてきたような口ぶりで荒れ地の羽虫を蔑むのが嫌だった。その僕が、母さんを守ろうとしてやったことは、父さんと少しも変わらない。僕は町の意識に同調したのだ。学校で教えられたとおりみんなと調和を保ち、卑しい羽虫を家族の汚点として町の人間の血脈で帳消しにした。
むやみに狂騒的な笑いの中で、母さんはほとんど表情もなく目を伏せて立っていた。心がくしゃくしゃになって、まるで体の中に残っていた最後の一本の骨が折れてしまったようだった。
「帳消しだ、帳消しだ」と誰かが
たった今まで
そのときマリの低く太い声が、笑いを貫いて走った。
「あれはあたしがふるさとで見た鳥だ」
人々が顔に笑いを貼り付けたまま、舞台の下手近くにいるマリを見つめた。
「何百羽ものあの鳥が、太陽のふちを飛ぶのを見たよ。雲を透かして、鮮やかな羽の色がはっきりと見えた」
あちこちから、噓つきのマリ、と声があがり、揺り戻すように笑いが起こった。
だがマリは超然と刺繡の鳥を指さした。
「あの鳥は飛ぶよ」
そうして上手に向かってひときわ大きな声で言った。
「飛ばしておくれ、魔術師」
魔術師は
しかし、僕には魔術師の様子がいつもと違うように感じられた。平素の魔術師然とした
一斉に茶化すような指笛が巻き起こった。魔術師はローブの裾をたくって素早く舞台の上手端まで後退した。それから深くゆっくりと息を吐きながら右腕を前に突き出すと、掌を母さんの胸元の刺繡の方に向けて
三分ほど待ってもなにも起こらず、退屈した人々は今のうちに用を足しておこうとぞろぞろと仮設トイレに向かい始め、業を煮やした司会者が僕の手からマイクを奪い取って福引きの再開をアナウンスしようとした。
その時だった。鳥の首の付け根のあたりがわずかに膨らんだような気がした。
極彩色の刺繡糸が見る見る盛り上がって羽毛となり、その目がなめらかな水のように光を映し込んだと思うと、胸元から一羽の鳥が舞台に転げ落ちた。
母さんが小さく声をあげた。
広場は時間が停止したかのように静まりかえった。すべての人が息をつめて一羽の鳥を見ていた。静寂の中に、この世に生まれたばかりの鳥が初めての
魔術師が気流を作るように両腕を交互に動かした。すると鳥は懸命に翼で床を打ちながら滑るように舞台の上を進み始めた。魔術師の筋張った腕の動きが激しさを増す。ついに低角度で体が浮いた。離陸から飛翔へと移行する瞬間、両翼に力を込めて中空から高みへと羽ばたこうとしたその時、石つぶてがその脇腹に命中した。
火がはぜるような乾いた音とともに鳥の姿がかき消え、使用済みの屋台の紙コップと数本の揚げ菓子の串となってばらばらと中空から落下した。
夢から覚めたように静止した時間が動き出した。
人々はどんな演目もけしてきちんと成功しないのが魔術師の魔術なのだと思い出し、汚れた紙コップと揚げ菓子の串を指してゲラゲラと笑った。
青年団から
「マリのふるさとじゃ、雲の上に屋台が出てたんだろうよ」
団長のウルネイの隣に薄ら笑いを浮かべたサロがいた。舞台にいた僕は、彼らのいる方向から石つぶてが飛んできたのをはっきりと見ていた。
魔術師は普段の演目を終えた時と同じように悦に入った身振りで客席に向かって恭しくお辞儀をしていた。
気がつくといつのまにか舞台の上から母さんの姿がなくなっていた。
(つづく)
▼太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000901/(KADOKAWAオフィシャルページ)






























