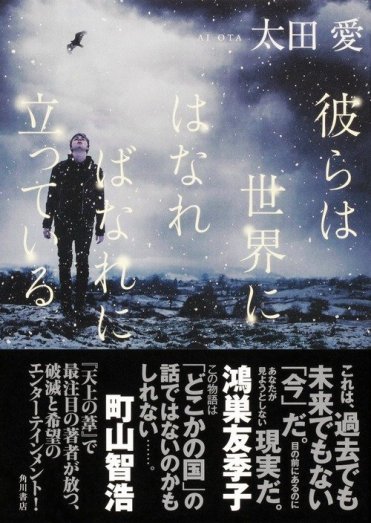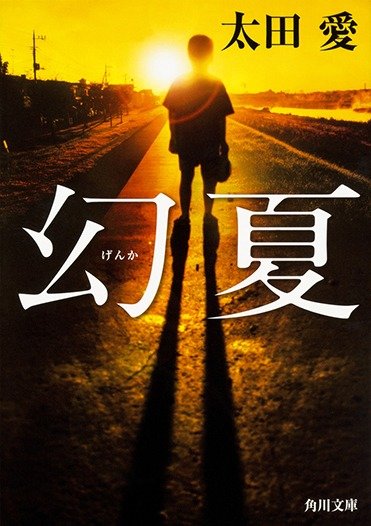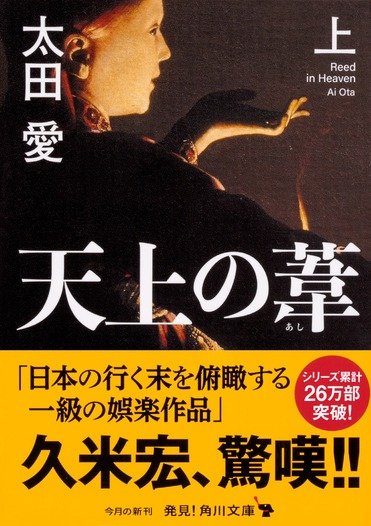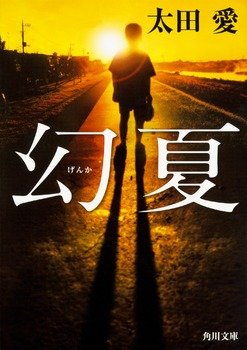彼らは世界にはなればなれに立っている
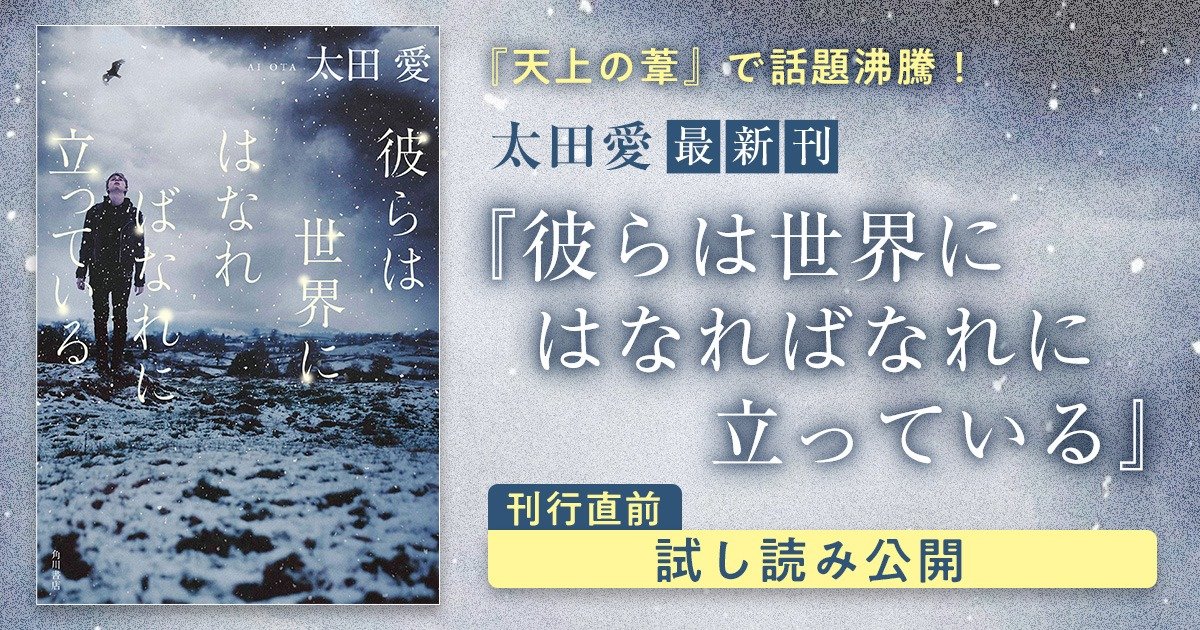
「この町はとっくにひっくり返っている。みんなが気づいていないだけでな」 太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』特別試し読み#5
〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれ、公然と差別される存在だ。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレの一家に浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した――。
最注目の著者による衝撃作、10月30日の刊行を前に特別試し読み!
>>前話を読む
もとの席にも母さんは戻っていなかった。運転手仲間たちがビールジョッキを手になだれこんできて、父さんは彼らと仕事の話を始めた。僕は、母さんを捜してくるよ、と言って席を離れたけれど、父さんに聞こえていたかどうかはわからない。
雑踏の中、広場を何度往復しても母さんは見つからなかった。福引きはとうに終わり、広場にはフィナーレを飾る男性歌手の力強い歌声と手拍子が響いていた。
もしかしたら、と僕は駆け出した。広場に入る通りに水飲み場がある。生け垣に囲まれたそこには、サルスベリの木陰で休憩できるようにベンチがひとつ置かれている。母さんはそこにいるのではないか。
舞台が見通せない所に来ると噓のようにひとけがなかった。通りに設けられていた案内係の仮設テントも無人で、
銀色の葡萄の粒のような蛇口から緩く水が立ちのぼっていた。
母さんはその傍らで、小さな鈴のように躍る水を見つめていた。
なにか言わなければと思った。だが僕が声をかけるより早く、母さんが気配に気づいてこちらを見た。放心したような、同時に白熱したような大きな目が僕を
「どうかしたの?」
もう、追いつけないと思った。
母さんはもう僕が追いつけない所に行ってしまったのだ。
蛇口を締めると、母さんはベンチに置いてあったハンドバッグを取り上げ、ハンカチを出して濡れた唇を押さえた。
「急にいなくなるから」
僕はかろうじて答えた。
「喉が渇いたのよ。行きましょう」
母さんは当たり前のように僕と並んで歩き出した。
だが僕の不安を感じ取ったのだと思う、母さんは立ち止まって小さい頃よくしてくれたように隣に並んだ僕の肩を抱いてくれた。
僕は安心したふりをして母さんの肩に頭を預けた。母さんがそう望んでいるのだと自分に言い訳をして、僕は幼い子供になった。
名残を惜しむような爆竹の音が響いていた。
散らばった紙くずや紙吹雪を踏んで町の人々が家に帰っていく。その姿がとてつもなくゆっくりと見えた。一歩ごとに弾む髪の毛、笑い崩れる体、肩車の上で揺れる子供まで、なにもかもがゆっくりと動いて見えた。ひときわ目を引くコンテッサが、伯爵と腕を組んで歩きながら水の中にでもいるように首を動かして母さんを見ていた。
翌日の月曜日に父さんは仕事に出た。僕は母さんの顔をまともに見られず、放課後は家に戻らずに人の来ない入り江や倉庫街で過ごした。避けられないなにかに向かって進んでいるような恐ろしい予感だけがあった。
水曜日、母さんが三階建てから出てくるのを見た日の夜、僕はベッドに入っても眠れず寝返りばかり打っていた。母さんが階下から上がってくる気配がした時、どうしてか僕は母さんが部屋に来るのだとわかった。そうして音もなく入ってきた母さんがベッドの傍らに立っているあいだ、僕は目を閉じて健やかな寝息をたてた。なにを思っているの、と尋ねる代わりに、それが僕にできる最良のことに思えた。
長いような一瞬のような時間の後、母さんはそっとシーツをなおして立ち去った。
僕は部屋でじっとしているのが苦しかった。
着替えてベッドの下に隠したバックパックを引っ張り出すと、それを背負って窓からポーチの屋根伝いに庭に下りた。物音をたてないように慎重に納屋から自転車を出し、庭のフェンスの外まで押していく。それからサドルにまたがってペダルを踏み込むと一気にスピードを上げた。
まとわりつくような湿った風が雨を予告していた。
先代の伯爵の胸像の辺りまで来ると、桟橋に停泊した客船から賑やかな音楽が聞こえた。広々とした甲板だけでなく巨大な船体が眩しいほどの電飾で輝いている。明日の早朝には出帆するので、客船とホテルの双方で夜通しのお別れパーティーが開かれているのだ。
僕はハンドルを切って船に背を向け、暗いマーケット通りを北上する。緩い上り勾配にたちまち体が汗ばむ。修繕屋の火事場跡を越えて延々と行くと、やがて東西に走る太い道に出る。街灯もなく闇に満たされたこの道は一日に一度、夜明け前にやってくる水色の長距離バスのためにある。この世界を貫く長距離バスの道はどこの地にも属していない。様々な理由でふるさとを失った人々にとって、その水色のバスが生き残るための最後の希望なのだという。
その太い道を突っ切って、自転車のオートライトだけをたよりに山道に入る。ここからは自転車を押して上がらなければならない。空全体が鳴るような低い雷鳴が
緩やかなカーブの外側にわずかに開けた平地があり、野菜や薬草が栽培されている小さな菜園がある。いつものようにそこに自転車を停め、僕は先にある
「どなた?」
空き缶を糸で繫いだいわゆる缶電話で窟の中と通じているのだ。
僕は缶に口を寄せ、雷鳴に消されないよう少し大きな声で言った。
「トゥーレ。本を返しに来た」
内側から
窟の中央に食卓兼仕事机である大きな四角いテーブルがあり、魔術師が舞台衣装のローブを着たまま手づかみで骨付き鶏を
それを見れば、魔術師がホテルで催されているお別れパーティーの余興に呼ばれ、報酬としてレストランの余り物をもらって帰り、着替えるのももどかしく空腹を満たしている最中だとわかった。
「客船の方々は私の鳩の演目を、魔術の概念を覆す
魔術師は僕に焼き菓子を取られまいとするように紙箱を引き寄せて言った。
鳩の魔術といえばタネが派手にまる見えになってしまう演目だ。斬新かどうかは別にして、予想外だったことは間違いない。主演の二羽の鳩、ウォルフレン九世とエルネスティナ十八世はたっぷりと
空の高みで巨大な
僕は網戸を開けてエルネスティナ十八世の頭を撫でてやりながら尋ねた。
「パーティーにはウルネイたちも来てたの?」
伯爵主催のパーティーにはもれなく町のお歴々が招待される。警察署長のダーネクさんはそのひとりだったが、青年団の団長・ウルネイはいずれその役職を継ぐ長子だ。
「ウルネイは招待されていたが、団長として青年団を引き連れて出席したいと申し出てな、伯爵に断られたそうだ」
伯爵の誕生日パーティーで酒に酔った青年団がシャンパンタワーに突っ込み、ホテルのバーに多大な損害をもたらしたことを伯爵は忘れていないらしい。週報に載った写真は夥しい数のグラスの残骸を活写していた。
「今頃はまず、〈踊る雄牛〉で
「もう店にはいないと思うよ」
僕は卓上時計を見て言った。時刻は午前零時を二分ほど回っていた。
〈踊る雄牛〉の主のホッヘンさんは酒を飲みながら新しい一日を迎えるのは人生への
魔術師は時計に目をやると小気味よさげな笑みを浮かべて言った。
「泣きっ面に蜂だな」
ホテルと客船では明け方まで華やかな
「これ、返すね」
夜、
僕が生まれるずっと以前に、個人が所有する書籍は特別な理由がない限り中央府の印のあるものと交換するか廃棄するように通達があったのだが、それに従わなかった人たちがいたのだ。彼らは小さな友人を
その後、家々で葬儀が行われるたびに、台所の隅や階段の踊り場で「実は困ったものが」「それなら魔術師に」という会話が繰り返された結果、この窟に木箱やトランクに収められた印のない違反書籍が大量に蓄積されることになったらしい。
魔術師が豆入りパンを頰張りながら言った。
「その本だがな、ただで貸した覚えはない」
「わかってるよ」
本を貸してもらうお礼に、ウォルフレン九世とエルネスティナ十八世の餌を持ってくる取り決めになっている。僕はポケットからヒマワリの種を包んだハンカチを取り出した。
「これっぽっちか」
ハンカチを開いた魔術師は芝居がかった口調で
「鳩の一生はほんの六年ほどしかないんだぞ。死ぬまでに一度くらい、たらふく食わしてやりたいと思わんのかね」
まさにそう思って以前ヒマワリの種をどっさり持ってきた時は、魔術師が
「僕は死ぬまでに一度でいいから、魔術師が
魔術師は聞き捨てならないことを耳にしたとでもいうように、握っていたソーセージを紙箱に戻して僕に向き直った。
「いいかね、トゥーレ。真の魔術師の仕事は、人々に奇跡を信じさせないことなのだ。それこそが、奇跡を行う力を授かった者の使命にほかならない。なぜなら奇跡とは劇薬、つまり毒なのだから。何度説明したらわかるのかね?」
平たく言えば、魔術師は本当は奇跡を起こせるのだが、あえてそれを行わないでいるのだと主張しているわけだ。
「わざとタネを見せて演じるのって大変だよね」
「さよう。その点、非常に高度な技術と精神力を要するのだ」
僕の皮肉はまったく通じなかったようだ。
魔術師は自戒するようにかぶりを振ってしみじみと言った。
「お祭りではつい自分を見失って、すんでのところで奇跡を起こしてしまうところだった」
「そうだね」
僕は適当に聞き流し、新たに借りる本を決めるべく木箱の中を物色し始めた。実際、あの晩は僕もあやうく
「おまえ、私の話を信じていないね?」
心の内を見抜くような目で魔術師が言った。
ようやく気づいてくれたようなので、僕は正直に気持ちを伝えた。
「魔術師がひとつでも奇跡を見せてくれたら、なんだって信じるよ」
「おまえのいう奇跡とはどんなものかね?」
「死人を蘇らせるとか、水の上を歩くとか、空を飛ぶとか」
魔術師はここぞとばかりに嬉しそうに身を乗り出してきた。
「それに似たようなことならあるぞ」
すぐさま僕は両手をあげて魔術師を制した。
「雑貨屋のオーネさんの話なら、僕、もう何回も聞いたからね」
僕が生まれる前の話だが、町中が大騒ぎしたこの出来事を知らないものはない。しかしそれも、『からくりはわからないが結局は失敗に終わった』という点では、お祭りの夜と同じだった。ただ、オーネさんの一件は人々の爆笑ではなく、激しい怒りをもって幕を閉じたのだが。
魔術師はことの
気がつくと雨音がほとんど聞こえなくなっていた。
卓上の白い紙箱はいつのまにかオイルランプに取って代わり、鼻眼鏡の魔術師が天球儀の描かれた大判の本を読みふけっていた。僕は持参したメモ帳に選んだ本の題名と日付を記し、その一枚を木箱にピンで留めた。それから本が雨で濡れないように古い週報で巻いたうえ、ホテルの紋章のついたビニールの
「それじゃあ行くね」
声をかけると、魔術師がふと目を上げて言った。
「ときにトゥーレ、仮に奇跡が起こせるとしたら、おまえはなにを望むかね?」
もし奇跡が起こせるのなら、僕は母さんのために奇跡を願いたかった。だがどんな奇跡が起これば、母さんはつらい思いをせずにすむようになるのだろう。母さんが母さんであること、それ自体で傷つけられる世界で。僕には答えが見つからなかった。
「わからない」
自分がひどく無力に思えた。
「僕にわかっているのは、僕がなにをしても世界は変わらないってことだけ」
「当然だ。おまえは独裁者ではないからな」
「ドクサイシャ?」
「そう。その行為がたちまち世界を変える。欲すれば叶う、最もいびつで欲深い奇跡の体現者だ」
ランプの火影で魔術師の顔が不思議な仮面のように見えた。
「おまえの行為によって世界が変わることはない。なにかすることで、おまえ自身が変わることはあってもな」
驟雨は静かな霧雨に変わっていた。
僕は頭を空っぽにして下り勾配に自転車ごと体を預けた。瞬く間に山も長距離バスの道路も後方に退き、マーケット通りに入った。
桟橋で光を放つ客船は真珠のリボンをかけられた贈り物のようだった。次第に大きくなる船体を見ながら通りを下っていく。もうすぐ先代の伯爵の胸像という所まで来た時だった。僕は咄嗟に両腕に力を込めてブレーキを握った。視覚で捉えていたものを脳が認識した瞬間、それは動かしがたい現実になった。
電飾に照らされた甲板に霧雨が白く光りながらゆっくりと落ちていく。
そこに、お祭りの夜の晴れ着を着た母さんがひとり立っていた。
早朝の浅瀬のような淡い緑色の晴れ着とヘアスカーフをまとって、母さんは暗い水平線の方を眺めていた。
母さんはこの町を出て行く。客船に乗って誰も知らない遠い地へ行く。
僕は身動きもできずに甲板に立つ母さんを見つめていた。
これは、僕にとって不意打ちであるはずだった。しかし、本当は水飲み場で母さんを見つけた時から、痛みをともなう予感として僕の中にあったのだと初めて気がついた。
母さんのためになにを望めばいいのか、僕はどこかでわかっていたのだと思う。ただ、認めたくなかったのだ。こうすることが母さんにとって一番いいことなのだと。
僕がなにをしてもこの世界は変わらない。どうしてか母さんは母さんであり、父さんは父さんであり、僕は僕でしかない。だが、魔術師が言ったようになにかすることで自分が変われるのなら、僕は変わりたいと思った。
もう水飲み場の時のように子供のふりはしない。
僕は、母さんを行かせる。
ハンドルを切って胸像の角を曲がり、ペダルを踏む一足ごとに母さんが遠くなるのを感じながら暗い道を走った。
誰もいない家に帰り、僕は地下室に下りて母さんの意志を確認した。それから自分の部屋のベッドに腰を下ろした。
長い夜だった。
夜明け前に雨がやんだ。
辺りが白み始めると、僕は窓を開けてその時がくるのを待った。今すぐ港へ向かえばまだ間に合うかもしれない。ベッドに座った時からずっとねじ伏せてきた衝動が出口を求めてもがくようだった。駆け出してしまわないように両足に力を込めて立ち、山の
早朝の大気を震わせて出帆の汽笛が響き渡った。
行ってしまう。
長い汽笛が三度。
海はさざ波に朝日を受けて、無数の
†
母さんはああするしかなかったのだと、マリにはわかっていたのだ。
映画館を逃げるように立ち去ってからどれくらい経ったのだろう、僕は空っぽの桟橋の端に腰かけて客船の消えた方角を眺めていた。
あの朝白銀に輝いていた海は、高高度の太陽の下で青く澄み渡っていた。土曜日のせいかレジャーボートやヨットの船影が散らばっている。だがそれら眼前の風景を
僕は立ち上がって自転車に向かった。昼には父さんが家に帰ってくる。僕たちは二人で軽食屋へ行く。そしてこのさき何度もそうするようにカウンターに並んで座り、煮え過ぎた豆と揚げた魚を食べる。
居間の時計を見て思ったよりも遅い時刻になっているのに気がついた。正午を二十分あまり回っている。流しが水で濡れているのを見て父さんが帰っているのがわかった。
地下室の扉が開いていた。
僕が階段を下りていくと、父さんがあの大きな衣装箱の蓋を手に壁際に座り込んでいた。僕は黙って近づいた。衣装箱の中は、僕が誰もいない家に帰ってきたあの雨の夜と同じだ。父さんは僕の様子を見てひどく混乱しているようだった。
「おまえ、知ってたのか」
僕は頷いた。
二十歳を過ぎたばかりの母さんは、父さんのトラックの助手席に乗ってこの町にやって来た。新しい生活への期待と不安で胸をいっぱいにして。そのとき母さんが持ってきたのは、胡桃色の小さな革のトランクひとつきりだった。
トランクはやがて思い出の品として衣装箱にしまわれ、地下室に運ばれた。そして僕のベビーベッドやお祖父さんの肘掛け椅子に迎えられて二度と使われない懐かしいものたちの仲間に加わった。
けれどもあの夜、衣装箱から胡桃色のトランクは消えていた。母さんはこの町に来た時と同じようにあの小さなトランクに身の回りのわずかなものだけを詰めていったのだ。
僕は、父さんと僕自身にしっかりと
「母さんはもう戻らない。客船に乗って町を出ていったんだ」
父さんは僕を突きのけるようにして階段を上がり、居間に向かった。そして本棚の横にある電話機の受話器に飛びついた。
「船舶通信所に電話しても無駄だよ」
父さんが通信所から客船に連絡して母さんを保護してもらうつもりなのだとわかっていた。もちろん僕だけでなく、母さんにもわかっていたはずだ。だとすれば母さんの取るべき行動はひとつだ。
「母さんはもう船にはいない」
父さんは自分の家の居間に見たことのない人間がいるのを発見したような驚きと不審の入り交じった顔で僕を見ていた。
僕はティティアンとラウルから聞いた客船の航路と旅程を詳細に記憶していた。ここ数日のラジオの気象ニュースで航路上に嵐がなかったことはわかっている。客船は予定通り今日の正午に次の港に到着した。ティティアンたちによるととても大きな商業都市らしい。母さんはすでに船を下り、都市の雑踏にまぎれてもうどこにいるのかわからない。
「どうしてなんだ」
受話器を置き、父さんはとんでもなく理不尽な話を聞かされたように両手を広げて訴えた。
「ここを出ていく理由なんてないはずだぞ」
「本当にそう思ってるなら、なぜあの衣装箱を開けたの?」
父さんの視線が揺らぎ、やがて顔を背けて黙り込んだ。
遠い町で母さんを見初めた父さんは、居住区で大勢の羽虫と暮らしていた母さんをきれいな捕虫網ですくい取るようにしてこの町に連れ帰った。だが父さんの妻となっても、母さんはまるで透明な二枚の硝子板に挟まれて顕微鏡で観察される生物のように町の人間からも羽虫からも隔てられ、身動きもできず、寒々とした蔑みの中で息をひそめて生きるほかなかった。
長いあいだ母さんはおそろしく孤独だったのだ。
父さんは腹立たしげにポケットから煙草を取り出した。
「礼のひとつも言わずに」
その一言が許せなかった。僕はうなり声をあげて頭から父さんに突進し、自分の体ごと突き倒した。電話台が倒れ、僕は父さんと組み合ったまま床の上を転がった。
この家の中の母さんの暮らしは、父さんの施しだったのか。
僕は組み敷かれても父さんの髪の毛を摑み、喉を殴り、がむしゃらに抵抗した。父さんの鉛のような一撃で頭の芯が痺れ、手足から力が抜け落ちた。
ミシンに立てかけたままだったズタ袋が倒れ、中から新しいノートの束と紙箱入りの鉛筆が飛び出しているのが見えた。僕が中等科へ進むものだと思って父さんがお土産に買ってきたのだ。都合のいい部分だけを繫ぎ合わせて、勝手に見たい世界を作り上げて。
床にのびた僕の胸ぐらを摑んで、父さんが尋ねた。
「あいつは、おまえに出ていくと言ったのか」
そんなことがまだ気になるのかと腹が立ち、僕は叩きつけるように答えた。
「母さんはなにも言わなかった。僕は母さんが晴れ着を着て甲板に立ってるのを見たんだ」
父さんはまるで顔面に一発食らったかのように身を引いた。それから座り込んだまま茫然とキルトのカレンダーに目をやった。父さんはカレンダーの赤いピンにそっと掌を触れると、背中を丸めて深く頭を垂れた。
「そんなはずはない」
絞り出すような声だった。分厚い胸も肩も震えていた。
「晴れ着を着て出ていくなんて」
涙が床に落ちて音をたてた。その床を父さんは両の拳で叩いて突っ伏した。
「そんなふうに、俺たちを憎んでいたはずがない」
父さんは身をゆすりあげるように号泣した。
僕は床にのびたまま、父さんの無惨な声を聞いていた。いつのまにか涙が耳を濡らしていた。
ふるさとの町は父さんにとって、母さんと僕が帰りを待っている町だったのだと思った。月の半分は遠い地にいる父さんは、羽虫ではないけれどどこへ行ってもよそ者だったのだ。ふるさとはいつも遠くにあり、そこには穏やかな家庭がある。しかしようやく町に戻ってみると、母さんが羽虫である事実とどう折り合いをつければいいのか父さんにはわからなかったのだ。羽虫の娘を町に連れ帰って妻にすればそれだけで幸福にしてやれると思っていたのだろう、そうではないとわかった時、不都合はすべて無視してなかったことにしてやり過ごすほか思いつかなかったのだ。そこには母さんの日々の現実も孤独も認める余地はなかった。ひとつの家で暮らしながら、父さんもまた孤独だったのかもしれない。
僕は中等科には進まず、トラックに乗ろうと決めた。
父さんもそうだったように助手席に座って見習いから始めるのだ。一緒に朝食をとっている時にそう告げると、父さんはゆっくりとゆで卵の殻をむきながら、それもいいかもしれないな、と言った。僕はなんとなく母さんもそう望んでいたような気がした。
学校のロッカーの荷物を取りに行き、オト先生に挨拶した。先生は父さんから聞いていたらしく、健康に留意するようにと言って送り出してくれた。
帰りにカイに会って僕が決めた進路を話した。カイは少し淋しそうな顔をしたが、もう交わることのない僕たちのこれからの時間に思いを
翌日、カイがお祭りの日の写真を持ってきてくれた。週報を発行しているイサイさんが撮影していたのを覚えていて、その中から母さんが写っているものを探してくれたのだ。小さいけれど母さんの表情がみてとれる。僕たちは、元気で、と言って別れた。
もし僕が町の人間だったら、僕たちは今とは違っていただろうか。庭のフェンスを出ていくカイを見送りながら、初めてそんなことを思った。
放棄された農場で父さんから運転を習い、盗賊から身を守るために回転式の銃の扱いも覚えた。
僕と父さんの出発は真夜中の便に決まった。
その日の午後、僕は父さんの煙草や缶詰の買い出しに行った。自転車の前籠に大きな紙袋を載せて戻ってくると、父さんが花壇の花をすべて引き抜いていた。
「少しずつ死んでいくのは可哀想だからな」
父さんはズタ袋に入れる肌着を畳みながら言った。この暑さで水を与えられなければ、丹精された繊細な花たちは僕たちが戻るまで到底もたない。言われるまで思いつかなかった気の重い作業を、父さんは僕がいないうちにひとりで終えていた。
要領よく肌着を畳んでいく手つきは僕が生まれる以前の父さんを思わせた。母さんと暮らし始めるまで、小さい時分からずっと父さんは自分で荷造りをしていたのだ。
無人になる家の戸締まりをし、
詰め所には同じ便で出発する運転手たちが集まっていた。僕は新しく作ってもらった認識票を首にかけた。煙草を吸い、コーヒーを飲み終えた男たちが、大きな雄鹿の剝製の頭を撫でて出ていく。僕も父さんのあとに初めて雄鹿の頭に触れた。そして立派な角に提げられた認識票の運転手たち、死んだ男たちに僕らを
エンジンをかける父さんの隣で、自分より二年早く父さんはお祖父さんの助手席に座ったのだと思った。
長距離バスの道を突っ切ってまっすぐに山越えの進路を取る。峠のトンネルに入る手前で父さんがトラックを停めた。初めて父さんが助手席に乗った時、お祖父さんがここから町を見せてくれたのだという。
車を降りると湧きあがるような虫の声がしていた。
消え残った家々の灯りの中にひときわ眩しく映画館の屋上のネオンが輝いていた。最終回はとうに終わっているから、マリが消し忘れたのだ。あのネオンの下に、初等科の僕がスタンプカードを握って通った映画館がある。カイと話すようになったロビー、母さんと初めて観た映画、マリにもらった招待券。僕は子供時代の自分に別れを告げて再び助手席に乗り込んだ。
トラックは
ダッシュボードにはいざという時の冷たく重い武器がしまわれている。この先になにが待っているのかわからない。
でも僕はもう前しか見ない。
§ § §
明日、受付に座った途端に電話が鳴るだろう。あの
──マリ、おまえはゆうべネオンを消し忘れていたぞ。
おあいにくさま、わざとつけておいたのさ。どうせ伯爵が道楽でやってる映画館だ、赤字続きでも潰れないのに誰が電気代なんて気にするものか。あの子へのはなむけに、あたしがちょいとネオンを使ったくらいでばちは当たらない。テイルライトが峠で一度停まったようだったから、きっとあの子は見ただろう。
運転手たちのあいだでは、アレンカは晴れ着を着て客船に乗り、海の向こうの遠い町に消えたという噂。でもそれは間違いだとあたしは知ってる。
アレンカは心を決めて行動を起こした。なにもかもトゥーレのために。あの子は賢いけれど、すべてをわかっているわけじゃない。
ああ、お湯が沸いたようだ。
そろそろ熱いお茶を
やけどするほど熱いお茶に蒸留酒をひとさじ。
ほら、階段を上がってくる足音が聞こえる。三階建ての階段の先にあるのは、あたしが住んでいるこの部屋だけだ。
ノックはない。外から鍵穴に鍵が差し込まれる。
あたしが内側からかけた鍵が、カチリと音をたてて外される。
そして卵型の白いドアノブが回る。
こんな時、あたしはいつも考える。
オルフェオならどう言うだろうかと。
(このつづきは本書でお楽しみください)
▼太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』詳細はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000901/(KADOKAWAオフィシャルページ)