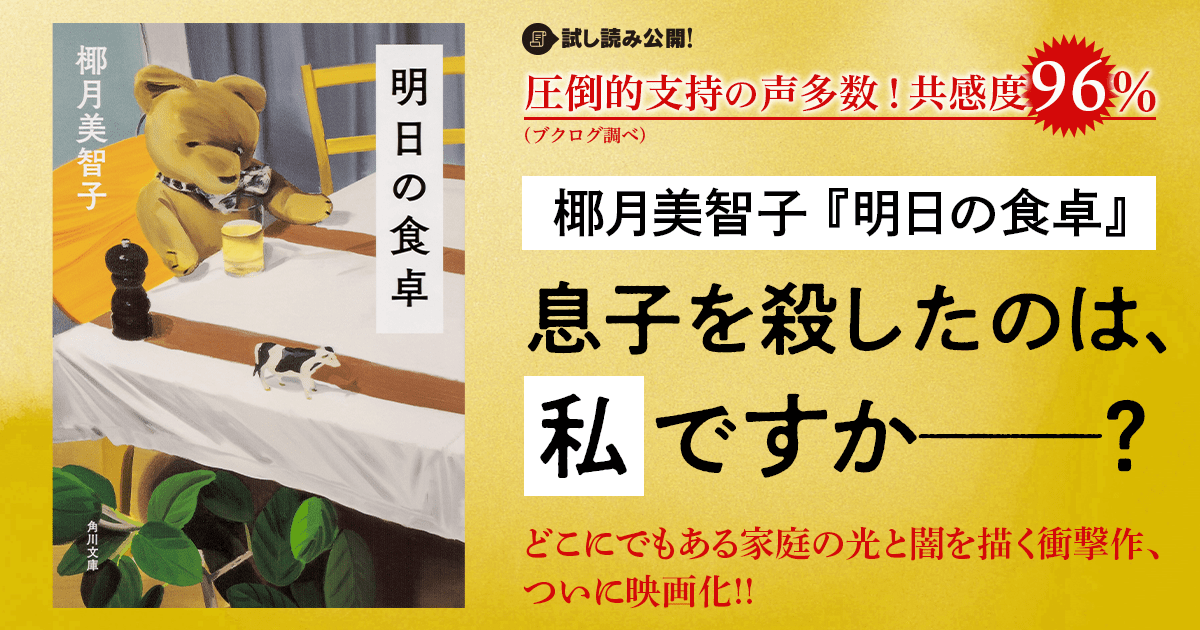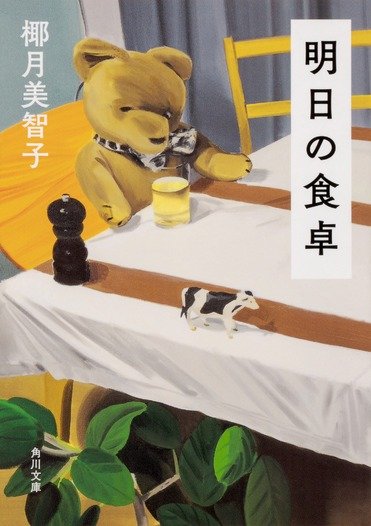単行本時に共感度96%(ブクログ調べ)を叩き出し、圧倒的支持を得た椰月美智子さんの『明日の食卓』。どこにでもある普通の家族に起こり得る光と闇を描き切った本作が、満を持して映画化されます!
フリーライターの石橋留美子を菅野美穂さん、シングルマザーの石橋加奈を高畑充希さん、専業主婦の石橋あすみを尾野真千子さんが熱演。それぞれ小学校3年生の「石橋ユウ」を育てる母たちの行く末は――?
5月28日からの映画公開に先駆け、3つの「石橋家」が良くわかる冒頭部分を公開します。
◆ ◆ ◆
>>第1回へ
悪い気はしなかったが、ママ友の厄介さを、あすみは充分承知していた。優が幼稚園の頃、つまらないママ友同士のいざこざは嫌というほど見てきたし、巻き込まれたこともあった。基本あすみは、特定のママ友はいらないというスタンスだった。夫と子どもさえいれば、それでよかった。
実家のある横浜には地元の友人がいるし、大学時代の仲間とも連絡をとろうと思えばいつでもとれる。わざわざ仲のよいママ友を作らなくても、さみしさや
もちろん優が仲よくしている友達のママとは、自分の好みはさておき、良好な関係を築いている。優のためを思えば、多少の支出や時間の
「あすみちゃんは、他にもなにか習い事してるの?」
「ええっと、お菓子教室に」
菜々の質問に少し戸惑いつつ、あすみは答えた。あすみは、習い事をしていることを、他のママ友に話したことはなかった。あっという間に噂が広がるに決まっていた。余裕があっていいわねえ、などと、顔を合わせるたびに言われることだろう。
「わあ、あすみちゃんにぴったりね。レースのエプロンが似合いそうだもの」
嫌みにとれそうな言葉も、菜々が言うと、むしろ褒められているような気がするから不思議なものだ。
「菜々さんは、なにか習っているんですか」
「もう、敬語やめてって。わたしは、クラシックバレエと英語」
驚いた。子どもがいて、三つも習い事をしているなんて。それこそ余裕があるのだと、ひそかに感嘆した。
「クラシックバレエのほうは、子どもも習ってるの」
「え? 男の子なのに?」
言ってから、言い方がまずかったと、あすみは唇を結んだ。
「あはは、そうなの。びっくりするでしょ? 男の子なんてうちの子だけよ。わたしが習いはじめたら、自分もやりたくなったんだって。男の子がバレエなんてって思ったけど、『リトル・ダンサー』もすてきな映画だし、日本の男性のバレエダンサーも活躍してるしね。あっ、『リトル・ダンサー』って知ってる? 男の子がバレエに夢中になる映画なんだけど」
「知ってる。大好きな映画よ」
あすみは、その映画を見たときの感動をまざまざと思い出していた。そして、菜々の息子のことを、とても好もしく感じた。
「息子さんは、他にも習い事してるの?」
「あとは将棋だけ。将棋は習ってるというか、ただ指しに行ってるだけよ。バレエに週四回も行ってるから、他の習い事をする時間がないのよ。わたしはもっと、他のものも習わせたいんだけどね。空手とか水泳とかそろばんとか」
ますます感心した。ひとつの物事に打ち込める息子さんを、あすみは純粋に尊敬した。しかも、男の子には珍しいクラシックバレエだ。四年生ともなればまわりの目が気になって、たとえ本心でやりたいと思っていても、恥ずかしがって辞めてしまう子もいるだろう。将棋というのもすてきだった。きっと、とても賢い息子さんなのだろう。
「息子さん、バレエはいつから習ってるの?」
「二年生のときからなの。まったく、男の子なのに不思議な子よね。ちなみにわたしは、月に二回しか行ってないんだけど」
そう言って笑う菜々の態度にも好感が持てた。ひけらかすこともなく卑下するわけでもなく、いい距離感で息子さんに接しているのが伝わってくる。
菜々の息子は、隣の市にある私立校の初等部に行っているとのことだった。幼稚園から通わせているのだという。
「このあたりは、選べるほどの学校がなくて。わたしとしては、中学生になったら少し遠くに通っても大丈夫かなって思っていて、べつの中学を受験させようと考えてるんだけど、本人は今の学校がすごく居心地がいいらしくてね」
と、菜々は言ったが、菜々の息子が通っているのは、あすみも考えていた一貫校だった。あすみは、優を受験させたい旨を伝え、いろいろと質問をした。菜々はなんでも快く答えてくれた。ドリンクのおかわりをする間も惜しく、学校や子どもの話でひとしきり盛り上がった。
菜々の夫は、県東地域で大手スーパーチェーンを展開している社長だということだった。あすみもよく利用している店だ。地元スーパーより少々値は張るが、生鮮食品は新鮮だし、調味料の品数も多く、評判の菓子類なども置いてある。
あすみは自分のなかに芽生えた、外に向かって放たれていくような広々とした感覚に胸が躍った。この地に来て、ようやく気の合う友達に出会えたような気がしたのだった。
優の通う小学校にも、会えば話をするママ友はいるが、男の子で中学受験を考えている人など聞いたこともなかったし、習い事をしているママ友も知らなかった。
また、菜々のところもあすみと同じ一人息子ということに、親近感を覚えた。優のクラスで一人っ子は少なかった。あすみも太一も二人目を切望していたが、授かることはなかった。
「地元で話が合う人がなかなかいなくて、つまらない思いをしてたところなの。今日、声をかけさせてもらって本当によかったわ。あすみちゃんとは仲よくなれそう」
菜々の言葉に、身の内から喜びがあふれ出てくるのをあすみは感じていた。
「わたしのほうこそ、声をかけてくれてどうもありがとう。お話しできて本当によかったわ。とてもたのしい時間だった」
こんなふうに、偽りのない自分の気持ちを友達に伝えたのは一体いつ以来だろう。素直な言葉を言えた自分が、あすみはうれしかった。
「すごくすてきな人なの。バレエをやってるから背筋もピンとしてるし。一見カジュアルなんだけど、よく見れば洋服だって髪だって、ちゃんと手をかけているのがわかるの。ご主人がハイマートの社長さんだっていうのに、ぜんぜん気取ってなくてね」
今日は太一の帰宅が早かったので、あすみは太一をつかまえ、菜々のことを話した。誰かに聞いてもらいたくて仕方なかった。
「なんだよ、あーちゃん。おれとハイマートの社長を比べないでくれよ。こっちは一介の会社員なんだからな」
困ったような笑顔で、太一が言う。
「そんなこと言ってるんじゃないわ、たいちゃん。わたし、なんだかうれしいの。こっちに来て、ようやく本当の友達ができたような気がするんだもん」
そう答えたら、思いがけなく語尾が震えて、あすみ自身驚いた。
「なに、どうしたの、あーちゃん。泣かないで。そっか、ごめんね。もしかしたら、東京から引っ越してきてから、ずっとあーちゃんに
「ううん、違うの違うの。ただうれしくて」
言うそばから、涙があふれてくる。
「ごめんね、あーちゃん」
太一が謝り、あすみの髪をなでる。
「ゴールデンウィークは、奥さんサービスしなくっちゃな」
太一が言う。
「十周年記念だから、ダイヤモンドでも買うかあ?」
太一の、その冗談みたいな口調がおかしくて、あすみは笑った。なんともいえない、気恥ずかしいような幸福感に満たされる。自分はとても恵まれているし、幸せだと、あすみは思う。
「ママ! 友達んち、遊びに行っていい?」
学校から帰ってきて、ランドセルを下ろす間もなく、優が言う。三年生になってから、優の活動範囲は一気に広がった。友達と遊びたくて仕方がない様子だ。
「宿題は?」
「あるけど、帰ってきたらすぐやるもん」
「ふうん。いいわ、約束ね。誰のおうちに行くの?」
「レオンのうち!」
お母さんはおそらくまだ二十代だ。十代で長男を産んだと聞いたことがあった。授業参観や懇談会で何度か見かけたことはあるが、まだ話したことはない。このところ、頻繁にレオンくんの名前が出てくるので、優とは仲よしなのだろう。
よく遊ぶ子のお母さんとは、連絡先を交換し合うのは最低限のルールだが、レオンくんのお母さんだけは、なんというのか、自分からは遠い存在のように思えて気がひけていた。けれど、近いうちに連絡先を聞かなければならないだろう。
「レオンくんち、おうちにお母さんはいるの?」
「いないよ。お仕事だもん」
「誰もいないおうちで遊ぶの?」
「お兄ちゃんがいるから大丈夫だよ。たまにお父さんもいるし」
お兄ちゃんといっても、小学五年生では頼りない。それに、お父さんが日中在宅しているというのも気にかかる。
「五時までに帰ってきなさいね」
「えー? みんな六時だよ。ぼくだけ先に一人で帰るの? やだよう」
そう言って、ぐずりはじめる。まだまだ子どもらしくてかわいいけれど、いつまで経っても、こんな泣き虫で大丈夫だろうかと心配にもなる。
「だーめ。今日は五時までよ。いいわね」
優は涙を
「このお菓子持っていって、みんなで食べてね」
既製品の菓子をいくつか持たせた。
「行ってきまーす」
「はい、行ってらっしゃーい」
優の笑顔は本当にかわいらしい。色白で、笑うと両頰にできるえくぼ。幼稚園のときママ友から、ジャニーズに入れなさいよ、と言われたこともあった。
「気を付けてね」
大きく手を振って、いつまでもこちらを振り向いて走っていく息子。親の自分が言うのもなんだが、優はとてもやさしいし、賢い。幼稚園のときには、すでにひらがな、カタカナも書け、自分の名前は漢字で書けた。足し算や引き算も、あすみが教えるとすぐに理解し、学校で習う前にできていた。
動物が大好きで、犬を見かけると触らないと気が済まないし、猫を見かければ辛抱強く近くに来てくれるのを待っている。ディズニー映画を見て涙を流し、募金箱があると自分のお小遣いを寄付する。幼稚園のときも、一、二年生のときも、先生に、「優くんはとてもやさしくて、友達思いです」と、言われていた。
よく耳にする、男の子特有の乱暴さや落ち着きのなさなど、幼児のときからまるでなかった。優を産んだとき、この子は天使だ、と思った感覚のまま、子育てができている。ママ友にうらやましいと言われるたびに、優のかわいさは募っていく。けれど、たとえ優が乱暴で落ち着きがない子どもだったとしても、自分は今と寸分
かわいい優。あすみは、優のことが好きで好きでたまらない。もちろん、親だから当たり前なのだが、優とは心が通じ合っていると感じる。男の子だからというのもあるのだろうか。女の子は口が達者で生意気よ、と口をそろえて、女の子のママたちは言う。
将来、優に彼女ができたとき、自分はどんな気持ちになるだろうと、あすみは考えることがある。三年生の今は、優の口からクラスメイトの女の子の話などが出ると、優と仲よくしてくれてありがとう、と素直に思う。けれど、本当の彼女ができたら、自分はその子にやきもちを焼くのだろうか。あすみは、そんな先の心配をする自分がおかしかった。
(つづく)
▼椰月美智子『明日の食卓』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321806000298/