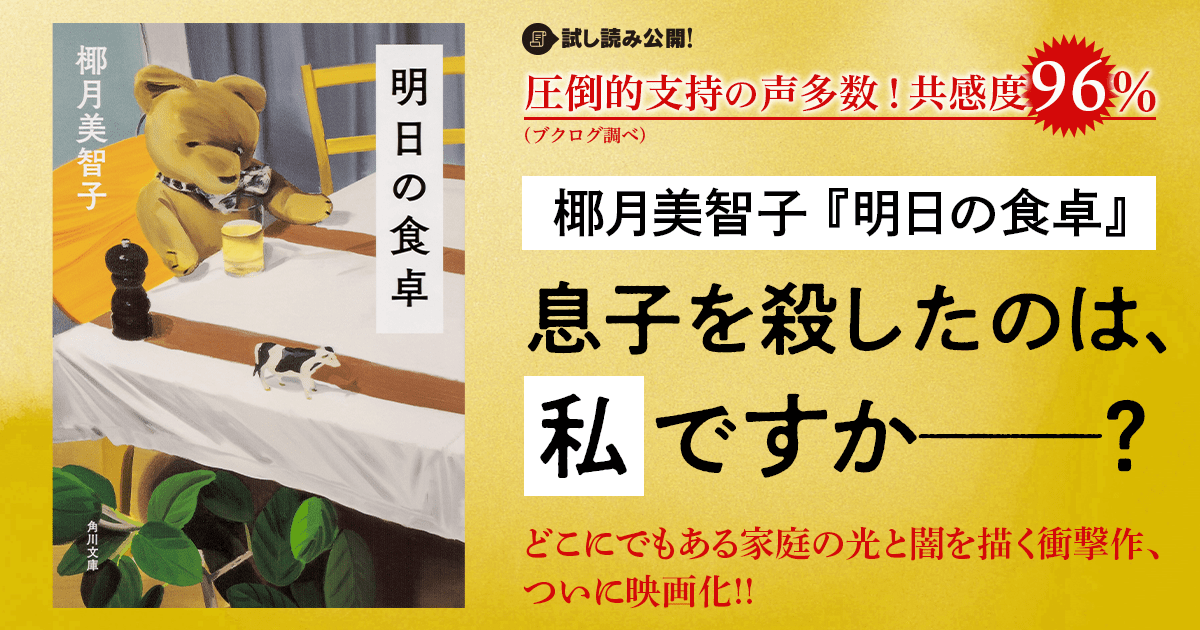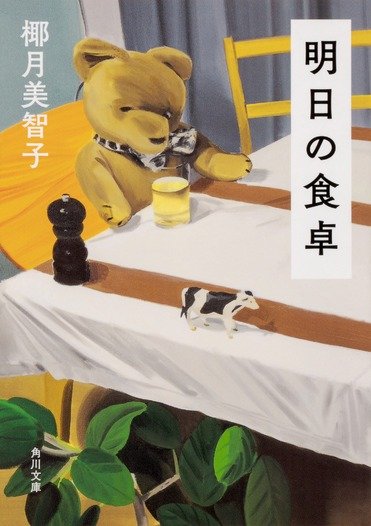単行本時に共感度96%(ブクログ調べ)を叩き出し、圧倒的支持を得た椰月美智子さんの『明日の食卓』。どこにでもある普通の家族に起こり得る光と闇を描き切った本作が、満を持して映画化されます!
フリーライターの石橋留美子を菅野美穂さん、シングルマザーの石橋加奈を高畑充希さん、専業主婦の石橋あすみを尾野真千子さんが熱演。それぞれ小学校3年生の「石橋ユウ」を育てる母たちの行く末は――?
5月28日からの映画公開に先駆け、3つの「石橋家」が良くわかる冒頭部分を公開します。
◆ ◆ ◆
ユウが、おもねるような表情でこちらを見る。その顔が腹立たしく、頰を思い切り打つ。恐怖と怒りでゆがむ顔に、さらなる憎悪が湧いてくる。さっきとは反対側の頰を打ち、肩を押してその場に倒す。
馬乗りになって平手打ちをし、髪をつかんで頭をゆする。立ち上がろうとするユウを、力いっぱい突き飛ばす。まだまだこちらの思い通りになる九歳の身体。
壁にぶつかったユウが、大げさなうめき声をあげる。その声に神経を逆なでされ、思わず
血液が逆流したみたいになって全身が熱くなる。なにかに突き動かされるように、髪をつかんで力任せに頭を床に打ちつける。肩が持ち上がるほど息が荒れ、汗がしたたり落ちる。
ぐったりしたユウを見て、ひとつ仕事を終えたような感覚になる。もやが晴れるみたいに、ようやく頭のなかがクリアになっていく。
*
朝六時三十分。あすみは、夫の
駅のロータリーに一時停止したところで、太一が「行ってくるね」と、右手人差し指の節であすみの頰に触れる。新婚当初は頰にキスだったが、いつの間にかこれに変わった。人目を気にしてのキスよりも、人差し指でやさしく頰をなでられるほうが愛情を感じられると、あすみは思う。
「行ってらっしゃい、たいちゃん」
運転席から手を振って、太一を見送る。ここから新幹線で、品川まで五十分弱。職場は
あすみはそのままロータリーを一周して、今来た道を戻って家に戻る。七時。
「優、起きて。朝よ。おはよう、優」
二階に上がって、優の部屋のカーテンを開ける。薄暗かった部屋が一気に明るくなる。
「ほら、起きて。遅刻しちゃうわよ」
ううん、ふうん、と声にならない声を出しながら、優が目をこする。朝の光が優の顔を照らし、金色の産毛が白い肌を輝かせる。顔を近づけて、さっき太一になぞられた自分の頰を、優のほっぺたにくっつける。とても柔らかくて温かい。
優、起きてー、と言いながら、あすみは、ぎゅうっと優を抱きしめる。子ども特有の甘い匂い。小学三年生に進級したばかりで、小柄な骨格はまだあどけない。かわいい息子。あすみは優が、かわいくてかわいくて仕方ない。
「チュッ」
わざと大げさに音を立てて、優のほっぺたにキスをした。
「やめてよう」
「さっさと起きない優がいけないのよ。ほら、早く起きなさい。ご飯できてるから、顔洗って、着替えたら下りてきてね」
のろのろと起き上がった優を確認して、あすみは階下に下りていく。
トースターに食パンを入れて、コーンスープを温め直す。ブロッコリーの芽とトマトとレタスのシーザーサラダに、ハムエッグ。優の好物のピーナッツバターを、トーストに塗って食卓に出す。
「あら、優。また、その服着たの? 他のお洋服がたくさんあるのに」
二階から下りてきた優が、おとといと同じ
「これが好きだからいいの」
そう言って、はにかんだように笑う。
登校班の待ち合わせ時間は、七時五十五分だ。朝食を食べ終えるのを見届けて歯を磨かせ、家の前の道路まで一緒に出る。
「忘れ物ない?」
「うん」
「行ってらっしゃい」
「うん、行ってきます」
優の小さな背中に、ランドセルはまだ少し大きい。校帽をかぶって走っていく背中を見つめているだけで、涙ぐんでしまいそうになる。優の姿が見えなくなっても、あすみはしばらく手を振り続ける。今日も一日、たのしいといいね、友達と仲よくできるといいね、と祈るように思いながら。
太一と優を送り出して、ようやくほっとひと息つける。リビングの大きなテラス戸から見える庭を眺めながら、あすみはゆっくりと朝食を食べる。自分用に、甘さ控えめに作ったイチゴジャムをトーストに塗ってかじりつく。サクッとした歯触りのあとの、ジャムのしんなり感。ああ、今日もいい一日になるなあと、なんの根拠もなく思う。
春の薄黄色の光が、テラス戸から差し込んでいる。水色のきれいな空。四月半ばの火曜日。今日は午後から、習い事の書道教室がある。さあ、洗濯物を干して掃除にとりかかろう。
窓際に立って、大きく腕を伸ばし深呼吸をする。昨日の雨で、ウッドデッキが汚れているのが目に入った。ここを作るとき、人工木にするか天然木にするか迷ったけれど、天然木にしてよかったと、あすみは思う。いつもきれいにしていれば問題ないし、時が経つにつれての風合いも趣がある。そろそろ、デッキで食事ができる季節だ。ここで朝食を食べたり、バーベキューをしたり、優が寝たあとに、たいちゃんと二人で星空を見ながらお酒を飲んだり。あすみは半月後の自分の姿を思い浮かべ、すでに満たされたような気持ちになった。
静岡県にある太一の実家を建て直したのは、優が小学校にあがるときだ。それまでは都心のマンションに住んでいたが、一人暮らしの太一の母のこともあり、いずれ一緒に住むのだからということで、引っ越しを決めた。子育てするにも、緑の多いこの土地のほうがいいだろうと、夫婦で話し合った。
唯一、気がかりだったのは、優の学校のことだ。あすみは、私立の一貫校に通わせたいと思っていたが、引っ越しのあれこれで事前準備が間に合わず、結局公立の小学校に入学させてしまった。暇を見つけては、ここから通える私立中学をさがしているが、めぼしいところはまだ見つかっていない。
ウッドデッキの掃除をしていると、義母が顔を見せた。同じ敷地内に平屋の一軒家を建て、義母はそこで暮らしている。あすみたち家族とは生活を共にしておらず、あすみにとっても、まだまだ元気な義母にとっても、互いに快適な距離感を保っている。
「おはようございます。いいお天気ですね」
「ええ、とても心地いい気候ね。春はいちばん好きな季節よ。あすみさん、お掃除に精が出るわね。偉いわ」
「いえいえ、きれいなほうが気持ちいいですから」
義母がゆっくりとうなずく。義父が早くに亡くなったため、茶道と華道の教室をしながら、太一を育てたと聞いた。義父は入り婿で会社員だった。地主である義母の収入は、教室の月謝よりも多かっただろうと思う。
「わたし、これからお友達と歌舞伎に行ってくるので、今日は遅くなるわね」
「はい、わかりました。行ってらっしゃい」
笑顔で義母を見送る。こうして家族に「行ってらっしゃい」と言える今の生活を、あすみは気に入っている。家内を整えて、おいしい食事を作り、子どもの世話をし、夫に気持ちよく過ごしてもらう。自分には主婦が向いていると、あすみはつくづく思う。
庭木の新緑がきれいだ。そろそろ庭師に連絡して、草むしりと
習字を習おうと思ったのは、冠婚葬祭が思った以上の頻度であったからだ。頼まれて
市内に名の知れた書道家の先生がいると知り、去年から通っている。純和風の先生の自宅の一室で、落ち着いた雰囲気のなか指導してもらえる。火曜のこの時間の生徒は六人で、年配の男性と女性が二人ずつ。もう一人は先月入会したばかりの、あすみと同世代の女性だ。
「筋がいいですよ、石橋さん」
優は現在、スイミングと絵画教室に通っている。スイミングに行きはじめてからは、風邪をひかなくなった。絵画教室は大好きで、絵を描くのがたのしくて仕方ない様子だ。そろそろ、塾にも通わせたい。中学受験をさせるなら、早いうちから準備をしておかなければならないだろう。
「ここは一度とめてから、はらってくださいね」
「あ、はい、すみません……」
少しでも他のことを考えていると、すぐに先生に見抜かれる。あすみは雑念を振り払って、そのあとの時間、集中して筆を動かした。
「もしお時間ありましたら、お茶でもしていきませんか」
教室が終わり、帰ろうとしたところで声をかけられた。
それは、木曜に通っているお菓子教室でも同じだった。生徒同士の仲が悪いわけではなく、教室が終わったらすぐに解散するのが、暗黙の了解となっていた。嫁入り前の若い娘さんたちは、声をかけ合って一緒に帰ったり寄り道をしているようだったが、いわゆる家庭のある主婦たちは、まっすぐに帰宅していた。
あすみはスマホで時間を確認した。二時をちょっと過ぎたところだ。優の今日の授業は六時間。帰宅は四時頃だろう。その前に夕飯の買い物に行かなくてはならない。
「少しだけだったら」
あすみがそう返事をすると、若杉さんは「わあ! うれしい」と言って、その場でぴょんと跳ねた。まるで子どもみたいだ。思わず、くすっと笑った。
「このあたりは気の利いたカフェがないので、ファミレスでいいですよね。国道まで出てもらっていいですか」
あすみは車だったし、その店は帰り道の途中なのでちょうどいい。
「わたしも車なので、それぞれに行って、向こうで待ち合わせしませんか」
「ええ、そうしましょう」
五分とかからず互いに店に着き、あすみはドリンクバーを頼んだ。
「石橋さん、それだけなんですか? わたしスイーツも頼んでいいですか」
「もちろんどうぞ」
彼女はベイクドチーズケーキとドリンクバーを注文した。
「失礼ですけど、石橋さんっておいくつですか?」
「え?」
「あ、ごめんなさい。そういうのって聞いちゃいけないんでしたっけ」
屈託なく若杉さんが笑う。それは決して嫌な感じではなかった。
「三十六歳です」
「あ、同世代。わたし三十八歳です」
もっと若いと思っていたので驚きだった。あすみもたいていは若く見られがちだが、若杉さんは自分よりも年下だと思っていた。二つ年上ということは、夫と同い年だ。
「お子さんいらっしゃるんですか」
結婚の有無を聞かずに、いきなり子どものことをたずねてきたのは、あすみの左手薬指の結婚指輪を確認したからだろう。それにしても、とてもあけすけな人だ。
「三年生の男の子が一人います」
「うちは四年生の男の子が一人」
子どもがいるように見えなかったので、あすみはまた少し驚いた。彼女の薬指には、オレンジがかったブラックオパールが輝いていた。
「若杉さん、お若く見えるので独身かと思っていました」
そう言うと、ちょっとやめてえ、と若杉さんは明るく笑った。
「敬語もやめようよ。若杉さんもやめて。わたし、
「あすみです」
「あすみさん、って呼んでいい? あ、やっぱり、あすみちゃんでもいい?」
くるくると変わる表情が豊かで、あすみは笑ってうなずいた。
「じゃあ、わたしも、菜々さんで」
年上だと聞いたので、菜々ちゃんというのは、いくらなんでもと思った。
「わたし、お習字をはじめたときから、ずっとあすみちゃんとお話ししたいって思ってたの。なんとなく気が合いそうだなあって」
(つづく)
▼椰月美智子『明日の食卓』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321806000298/