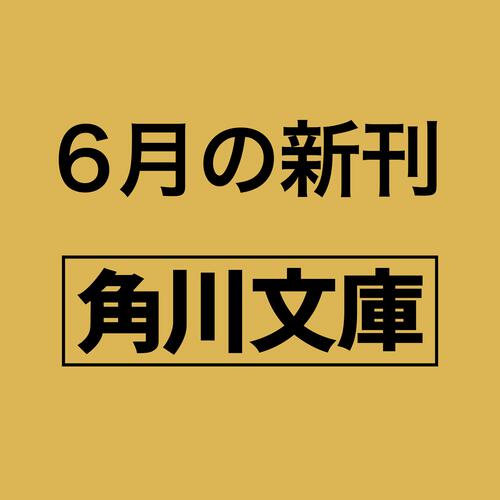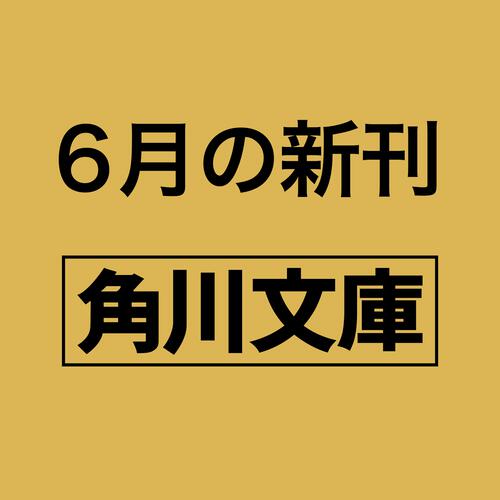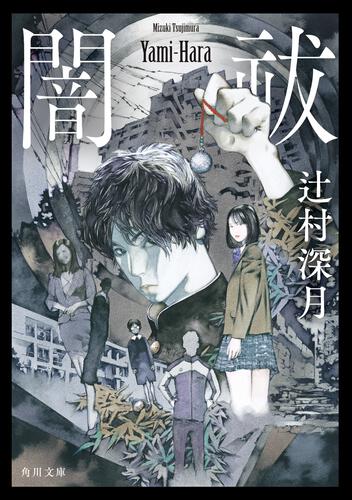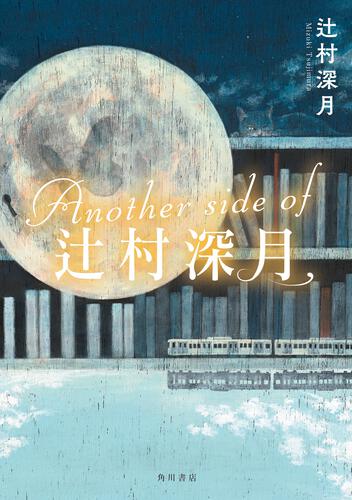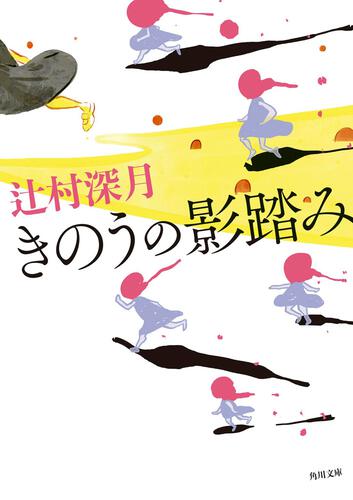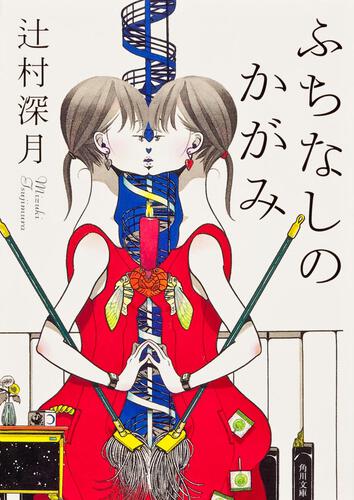2020年コロナ禍の日本各地を舞台に、天文部に所属する中高生たちの青春模様をつづった辻村深月さんの人気作『この夏の星を見る』。その映画化を記念して、辻村さん、映画監督の山元環さん、脚本家の森野マッシュさんのお三方による鼎談が実現。原作の魅力や映画の見どころなどについて語り合っていただきました。
取材・文=髙倉優子 写真=干川修
『この夏の星を見る』映画化記念鼎談 辻村深月×山元環×森野マッシュ
スターキャッチのシーンは
「かっこよく撮る」のが目標だった
――まず原作小説『この夏の星を見る』を書かれた経緯から教えていただけますか。
辻村:新聞連載の担当者から「青春小説を」というオファーがあり、なんとなく「部活もの」がいいなと考えました。連載が始まったのが2021年だったので作中にコロナ禍を出すかは決めていなかったのですが、その時期はマスクのない青春小説を書くことの方が私の中ではリアリティーがなかった。「コロナ禍でもできる部活ってなんだろう?」と考えて、屋外で活動しやすい天文部に決めました。あとは単純に「星を見るってロマンティックじゃない?」くらいの単純な発想で。けれど実際に取材を始めてみたら「ガチ理系」の世界で青ざめたんです。早々に壁にぶつかりましたが、もう後戻りはできなかったですね(笑)。
山元:最初の取材は(綿引先生のモデルになった)岡村先生に?
辻村:はい。岡村先生には別件で取材を申し込んだことがあるのですが、東日本大震災の影響を受けて企画がなくなってしまい、断念した過去があったんです。そんな経緯を編集者に伝えたところ、「岡村先生は今、茨城の土浦第三高校にいらっしゃいますよ」と探してくれて、まずはリモート取材をお願いしました。取材中、いろんなお話を聞いたのですが、その際、何の前置きもなく「スターキャッチコンテストが~」と語り始められたので、「先生、ちょっと待ってください! スターキャッチってなんですか?」と。
森野:私たちも取材や映画の監修でお世話になったのでわかりますが、すごく岡村先生らしいエピソードです。
山元:そうそう。1聞いたらバーッと100くらい返ってくるお話し好きな方だし、お茶目なところがあるから(笑)。
辻村:最初は私も聞き逃してしまいそうなくらいスルッとお話されるから、みんなが知っていて当然の知識なのかな?と思っていたところ、岡村先生が生徒さんたちと作られた活動だと聞いて驚きました。スターキャッチコンテストとは「手作りの望遠鏡を使って星を見つける速度を競う競技」。その頃から漠然と、小説の舞台を複数の土地にしたいという発想があって、東京、茨城、長崎・五島列島の3ヵ所にしようと思い描いていたものの、それぞれの場所で暮らす彼らをどうつなげていったらいいかは、まったく思いつかなかったんです。
そこで改めて岡村先生に「スターキャッチコンテストってリモートでもできると思いますか?」とお聞きしてみたら、「できると思うし、ぜったい盛り上がりますよ!」とお返事があって。その言葉を聞いた瞬間、ストーリーの構成が広がっていきました。岡村先生にはどれだけ感謝しても足りないですね。映画では、私が見たかった以上のスターキャッチコンテストの光景を見せてくださって、すごく嬉しかったです。
山元:スターキャッチコンテストはこの映画の見どころなので、「とにかくかっこよく撮る」というのが目標でした。たとえば、星をつかまえるための基本姿勢を「北極星ポジション」と名づけ、望遠鏡をスピーディかつスポーティに扱ってもらう、など。
辻村:「北極星ポジション」を取るときの足の開き方とか、「ロック!」の声をかけて観測するチームとしての動きのキレがとてもかっこよかったです。土浦第三高校の科学部を取材させてもらったときにも感じましたが、天体観測って体幹がしっかりしていないとできないんですよね。望遠鏡をのぞいていた生徒たちが「体がつる!もう限界!」と話す姿などもすごく印象的だったので。
山元:最初は望遠鏡をぎこちなく触っていた俳優さんたちも、「もっとかっこよく!」「もっと速く!」と指示を出すうちに、どんどん上達していきました。撮影中、ISS(国際宇宙ステーション)が通ったことがあるんですけど、真宙を演じた黒川想矢くんは「いま望遠鏡に入っています!」と。望遠鏡の扱いに慣れただけでなく、体幹が鍛えられ、さらに待つための忍耐力も身についた成果だと思いました。
辻村:東京・渋谷の撮影現場に見学に行かせてもらったとき、俳優さんたちが望遠鏡を動かしている姿を見て、「私、この場面書いた!」とものすごく感動したんです。スターキャッチコンテストの小説を書かなければ、いまこの風景を見ることはなかった。書いてよかった、と。
でもね、実は少し申し訳なさも感じています。何気なく書いたシーンのせいで皆さんに大変な思いをさせてしまった部分もあるから。たとえば、茨城で「早朝から電車を借りてロケをやる」と聞いたとき。「凛久が亜紗に電車の中で大切な話をする」と私が書いたことで、皆さんに早朝からロケをさせることになってしまって(笑)。
山元:いや、あそこは「電車の中」と書いていただいて本当によかったです。あのシーンは合成ではなく、一車両を借りて本当に電車を走らせながら撮ったんですが、エンジンが真下にあるものだから、キーキーカーカーとうるさくて(笑)。本来なら控えめにぼそぼそと話すべきシーンなのに、凛久役の水沢くんはけっこう声を張っていた。それってめっちゃリアルじゃないですか? 茨城の田園風景をバックにすごくいい絵が撮れたし、最高のシーンになりました。
辻村:よかったです。もっと言うと、私が舞台のひとつを五島列島と書いたばかりに、五島列島に行ってくれたんですね!?とか、書いたことが想像を超えた形で映像になって出てくるから、本当に魔法みたいだった(笑)。私が取材に行った場所の奥で、本当に登場人物たちが生活をしていたんだと思えるような不思議な感慨と感動がありました。
今回、執筆時に取材させていただいた方々が映画の監修にも携わってくださったこともあり、小説・映画がひとつのチームだったような幸せな感覚がありました。別々の場所で取材に応じてくださっていた人たち同士が映画の撮影を通じて実際に知り合い、繋がってくださったと聞いて、映画の中で起こっていたことが現実になったようで、それもとても嬉しかったです。
「森野マッシュらしい脚本に」と
言われてからすべてが変わりました
――原作は長尺ですし、脚本化するのは大変だったのではないですか?
森野:私が辻村さんの大ファンだったこともあり、「原作の台詞をなるべくそのまま使いたい」「キャラクターを削りたくない」という思いが強すぎて、なかなかうまく書けませんでした。
山元:最初にマッシュが書いたプロットは40ページくらいで4時間くらいの映像になる分量だったんです。どこを削りどこを生かすか。みんなでアイデアを出し合ってマッシュに書いてもらい、それを読んでまた意見を出し合うという感じ。まさに合宿状態でした。
森野:なんとか書き上げた第1稿を辻村さんにお送りしたら、「もっと自分らしく」「森野マッシュの作品を書いてください」と言ってくださいましたよね。その一言ですべてが変わりました。めちゃくちゃ気が楽になったんです。
辻村:第1稿は、森野さんの原作への思い入れや遠慮が感じられるもので、それが森野さん本来の持ち味や魅力を損ねてしまっている気がして、もったいない!と思ったんです。その後にいただいた第2稿は、原作通りではない部分があっても原作で私が表現したかったことが凝縮されたような場面が多くあり、森野さんがストーリーとキャラクターを完全にご自分のものにしてくださったことが伝わってきて感動しました。ただ、「森野さんらしく」というのは、実はけっこう難しいオーダーだったんじゃないかと思うんです。「このシーンをこう変えてほしい」「キャラクターのセリフをこう書いてほしい」といった具体的な訂正だったら直しやすいけれど、私のアドバイスは漠然としていたので。「もっと細かく言ってくれよ」と思わなかったですか?
森野:いやいやいや、そんなことないです。ただただ嬉しかったです(笑)。それ以来、他の作品に対しても原作の捉え方や、どうやって自分らしさを加えていくかということが考えられるようになった気がします。
辻村:私が特に好きなのは、亜紗と凛久が、天文部でやりたいことを書いたノートを互いに見せ合って、無言で握手するシーンです。言葉(台詞)に頼らず、感情を描く。見えないものを表現することはすごく難しいと思うのですが、それを脚本と演出の力で見事に形にしてくださった。素晴らしいと思いました。森村先生と天音が言葉を発さず、見つめ合ってサムズアップするシーンも、この二人が裏でどんなやり取りをしたのが一気にストーリーが広がり、いいですよね。
山元:ありがとうございます。映画のよさは言葉にならないト書きの部分が表現できるところだと思います。サムズアップのシーンは「カット」と声をかけずにいたら、最終的に2人が自然とあのポーズをしてくれたんです。僕も感激しました。チームワークのいい現場だったおかげで、本当にいい映画が撮れたと嬉しく思っています。
監督・脚本家・すべての出演者の
代表作になるはずと思っています
――最後になりますが、改めてこの映画の見どころを教えてください。
辻村:今回、スタッフやキャストの皆さんはもちろんのこと、すでに観てくださった方たちからの熱量が高くてとても驚いているんです。観たことで、自分もこの映画の仲間というか、関わった一員のように興奮してくださっていることが伝わる。この映画は、主演の桜田さんをはじめ、出演してくれた俳優さんたちみんなの代表作になるはずと思っているんです。監督もこの映画が長編デビュー作ですよね? だから今なら、「山元監督はオレ、デビューの時から観てるよ」とか「森野マッシュは『この夏の星を見る』のときからすごいと思ってた」と堂々と周囲に自慢できるという特典もついてきます(笑)。ぜひみんなに観てほしい。
山元:どんな状況であっても、歩みを止めずに前に進んでいく若者たちの躍動を感じてもらえる映画になっていると思います。また映画「ルックバック」で音楽を担当されたharuka nakamuraさんの純度の高い映画音楽をはじめ、音響や星空の解像度など、すべてにおいてこだわり抜いた作品です。それらをぜひ映画館で体感してください。きっと満足していただけると思います。
森野:個人的にはコンテストに向けて、中高生が準備をしている日常のシーンがすごく好きなんです。「今やれることを、やる」という前向きなエネルギーが満ちていて、見ているだけで浄化されるというか、なんだか癒される。もう2度と経験したくはないけれど、次にコロナ禍のような事態が起こったとき、自分ならどう過ごし何をするのか――。振り返ったり、考えたりするきっかけにもなる映画だと思います。
プロフィール
辻村深月(つじむら・みづき)
千葉大学教育学部卒業。2004年、『冷たい校舎の時は止まる』でメフィスト賞を受賞し、作家デビュー。2011年『ツナグ』で吉川英治文学新人賞を、2012年『鍵のない夢を見る』で直木賞を受賞する。2018年『かがみの孤城』で本屋大賞第1位に。その他『スロウハイツの神様』『島はぼくらと』『ハケンアニメ!』『朝が来る』『傲慢と善良』『闇祓』『嘘つきジェンガ』など著書多数。
山元環(やまもと・かん)
1993年大阪府生まれ。大阪芸術大学映像学科卒業。ショートフィルム「ワンナイトのあとに」がYouTubeで300万回再生を記録。監督・脚本を務めたBUMP配信ドラマ「今日も浮つく、あなたは燃える。」はSNS総再生回数4億回を超えている。「夫婦が壊れるとき」(日本テレビ)、「沼オトコと沼落ちオンナのmidnight call~寝不足の原因は自分にある。~」(テレビ東京)などテレビドラマも手がける。「この夏の星を見る」は初めての長編監督作となる。
森野マッシュ(もりの・まっしゅ)
1996年埼玉県生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業。広告代理店勤務を経て、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻脚本領域を修了。坂元裕二のもとで脚本を学び、修了作品「FIN」が第47回城戸賞最終選考に選出された。「ケの日のケケケ」で第47回創作テレビドラマ大賞を受賞し、脚本家デビュー。「未成年~未熟な俺たちは不器用に進行中~」(読売テレビ)や「VRおじさんの初恋」(NHK)などテレビドラマの脚本も手がける。
作品紹介
書 名:この夏の星を見る 上・下
著 者:辻村深月
発売日:2025年06月17日
この物語は、あなたの宝物になる。
亜紗は茨城県立砂浦第三高校の二年生。顧問の綿引先生のもと、天文部で活動している。コロナ禍で部活動が次々と制限され、楽しみにしていた合宿も中止になる中、望遠鏡で星を捉えるスピードを競う「スターキャッチコンテスト」も今年は開催できないだろうと悩んでいた。真宙(まひろ)は渋谷区立ひばり森中学の一年生。27人しかいない新入生のうち、唯一の男子であることにショックを受け、「長引け、コロナ」と日々念じている。円華(まどか)は長崎県五島列島の旅館の娘。高校三年生で、吹奏楽部。旅館に他県からのお客が泊っていることで親友から距離を置かれ、やりきれない思いを抱えている時に、クラスメイトに天文台に誘われる――。
上巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000850/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
下巻詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000849/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
作品特設サイト
https://kadobun.jp/special/tsujimura-mizuki/kono-hoshi/