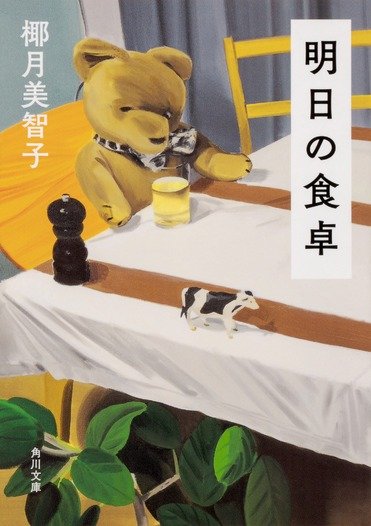※物語の結末に触れているため、本編読了後にお読みください。
三人の石橋ユウ。同姓同名だが、字が違う。優と悠宇と勇。そしてそれぞれの母親。三組の親子が登場する。石橋あすみと優、石橋留美子と悠宇、石橋加奈と勇。そしてもう一組の親子、石橋耀子と祐。イシバシユウという名の少年が、母親によって虐待死したことで、三組の親子がつながる。あれはうちのユウだったかもしれない……と。だが、この三組の親子は居住地もライフスタイルも違い、互いに接点はない。
イシバシユウくん、九歳、小学校三年生。高学年に移行する前の、子どもらしさが残る端境期の年齢だ。その後は少年になって、変声期を迎える。力は強いが、まだオトナの女が抑えつけることのできる、ぎりぎりの年齢でもある。
冒頭に壮絶な暴力シーンが登場する。終わり頃になって、イシバシユウくんが母親によって殺害されたという報道記事が登場する。読者はどのイシバシユウくんが殺されたのだろうか? と気が気でない。物語の展開から目が離せなくなる。
石橋あすみ(36歳)は静岡在住の専業主婦。夫の太一の収入は安定し、義母と同じ敷地内の一戸建てに住み、ひとり息子の優は優等生で、このなかではもっとも経済的に恵まれた母親だ。手のかからないよい子だったはずの息子は、手の込んだいじめを障がいのあるクラスメートにしかけ、父親を侮蔑し、認知症になった祖母を足蹴にする。最愛の息子は、他人の痛みのわからないエイリアンのような存在に変身していた。息子を責める母に、息子は言い放つ。「ママだってぼくを試してるじゃない。……ママ好みにしてあげてただけ」と。母親が、夫の顔色を見て暮らし、義母との距離をうまくやりくりし、そつなく演技して、欺瞞的な人生を送っていることを、見抜いている。子どものトラブルを聞いても、夫は無責任で逃げ腰。かえって「オマエのしつけがなってない」と妻を責める、そのへんのフツーの父親だ。その夫を「それもわかる」と許容し、息子の豹変ぶりを「反抗期」で片付ける妻にも、子どもの現実と真剣に向きあおうという姿勢はない。
石橋留美子(43歳)は神奈川県在住のフリーライター。悠宇と二歳違いの巧巳の兄弟がいる。男の子たちは野蛮人でモンスターだ。ちょっとしたことで取っ組み合いの喧嘩をし、家中騒然として落ち着かない。夫の豊はフリーのカメラマン、年齢をとって嵩高になり、編集者にとって使いにくくなったのか、めっきり仕事が減った。入れ替わりに留美子は、子育てで一時中断していたフリーライターの仕事を、再開しようとする。「今度はわたしが稼ぐ番……」と。留美子のしごとは順調に進み、夫の収入を上回る。それと共に夫はとみに無気力になり、留美子に嫌みを言うようになる。自分が稼いでいるのだから、家事や育児を分担してほしいという留美子の期待にも、いやいやしぶしぶにしか応えない。締め切りに追われながら充実感を感じる妻に対して、夫はますます卑屈に自己中になっていく。絵に描いたような展開が、わかりやすすぎる。ライターの職場は職住一致、自分のしごと場は聖域だから立ち入らないようにと、息子たちに命じるが、いっこうに効き目はない。ちらかったリビングを片付けるように夫や息子たちに言い渡すと、夫は息子のゲーム機をやにわにとりあげ、おもちゃをこわす。父親に挑みかかる息子を蹴り飛ばし、まるで三番目の息子のようなおとなげない暴力をふるう。だが息子と違ってガタイの大きい大人の男の暴力に、留美子はおびえる。
石橋加奈(30歳)は大阪在住のシングルマザー。ここだけ大阪弁だ。女をつくって出て行った夫とあっさり別れた。子どもも産んだのに「知らんがな。お前が勝手に産んだんやろ」とつきはなす無責任な男だ。慰謝料も養育費ももらえないばかりか、借金の返済に追われる母子家庭を、ダブルジョブで支えている。サッカーの好きな息子に、装具を買ってあげたいが、それもままならない。息子の勇は親思いのやさしい子に育ったが、気がかりなひとり暮らしの老母と、しょっちゅう金の無心に来る弟がいる。勇はクラスメートにはめられて盗みの疑いをかけられる。そのクラスメートの母親、風俗で働いているシングルマザーの西山さんから、同じ仕事に誘われるが、断る。「あんたのそういうところがムカつくねんっ!」と西山さんは言い放つ。
ある日。
石橋あすみが夫や義母といる場で、父の太一がマザコンだと知っている優が、認知症になった祖母を「汚い」という。浮気の証拠をつかんだ父親にも「汚い」と言い放つ。激昂した太一は優の頬を打つが、それを優は「児童虐待」だと叫んで、隣人に通報される。父親を「逮捕してくれ」と警察官に頼む息子を前に、太一は怒りと羞恥で逆ギレする。「ただで済むと思うなよっ!」と周囲のモノに当たる父親を、優は「それを虐待っていうんだよ」と勝ち誇ったように言う。
ある日。
石橋留美子は、いつものように兄弟げんかを始めた悠宇と巧巳に、父らしい介入もしない豊を責める。散らかした悠宇を豊は殴りつけ、「全部こいつらのせいだ」という豊に、留美子の忍耐の緒が切れる。あなたはこれまで父親らしいことをしたのか、と。平手打ちをした留美子を豊が殴り返す夫婦げんかを、ふたりの息子が止めようとして突き飛ばされる。留美子はふたりの息子を守るために、「あんたなんか出てってよ!」と豊に絶縁状を叩きつける。だが、自分の聖域だった仕事部屋が、守りぬいたはずの息子に荒らされたとわかったとき、留美子の中で何かが切れる。怒りで熱くなりながら、留美子は悠宇に馬乗りになって、頭を床に打ち付ける。
ある日。
職場でリストラされた加奈を家で待っていたのは、自分の失敗からやけどをした勇。病院へ連れて行ったあと、虐待を疑われて児童相談所から訪問を受ける。母をかばう勇。実際に虐待を受けたのは、西山さんが同居している男から木刀で殴られた、西山さんの息子だった。男の暴行を座視したとされる西山さんは、「わたしは止めた」と主張する。自分も殴られながら、きっと必死で息子を守ろうとしたのだろう、と加奈は同情する。
そしてもうひとつの、ある日。
イシバシユウくんが石橋耀子という母親の手にかかって殺された。
殺されたイシバシユウくんは、三組の親子のどれにもあてはまらなかった。だが三組の親子の誰であっても、ふしぎはなかった。
それにしても。ここに登場する夫たちは、そろいもそろって、なんと小心で卑劣で幼児的で自己中なんだろう? 男ってそんなもの……ですまされるだろうか? 男性の読者が読んだら、「男が書けてない」とか、言うだろうか? 「オレは違う」と自己弁護するだろうか? それにしても「あるある感」が満載なのが、情けない。この国の男たちは、ついに父親にならないままなのだろうか?
あすみはごまかしの上に安住した専業主婦。「あの日」の後に妊娠し、夫の浮気を問い詰めずに二子めを出産しようとする。
留美子は「あの日」の後に経済的自立を果たして夫と離婚し、息子ふたりと三人でやり直そうと決意する。
加奈は夫に未練はなく、「あの日」に関わりないシングルマザーの日常を必死に守ろうとする。
作者はこの三人のうちで、男に頼らない、貧しくてもけなげな加奈にいちばん甘い。石橋加奈の息子、勇だけが、親思いのやさしい子だからだ。
だが、と思う。いわれのない盗みの嫌疑をかけられた小三男児が、それに耐えて学校へ行き続けることができるだろうか? ゆとりのないシングルマザーの母親に、すねたりぐれたりせず、こんなに思いやりをもてるだろうか? もし、勇がもっと心の折れやすい子だったら? もし、勇が不登校になり、メンタルをやられ、「死にたい」と自殺企図をくりかえすようになったら?……そうなっても少しもふしぎではないのに、作者は石橋加奈と勇の親子にだけ、救いを与える。石橋加奈と勇にだって、「最悪の事態」はありうるだろうに。
この作品の主題は虐待だという。だが、虐待事件の多くは三歳から五歳、親に完全に依存し、反抗する力もない、生殺与奪の権を親が一手に握っているようなケースが大半だ。九歳になった、しかも親につかみかかってくる男の子を、虐待死させるケースは多くない。
単行本時の帯に宮下奈都さんが「暴力の衝動は、きっと誰の中にも潜んでいる。」と書く。
が、主題はきっとそれではない。
四人の母親は、息子が大好きだった。自分の存在理由とまで思えた。この留保なしの愛情を注ぐ相手には、娘でなく息子でなければならなかっただろう。九歳の娘なら、自分と同性であることで、愛憎アンビバレンツが生まれるからだ。四人の母親は、息子を守るために必死だった。その守り方がそれぞれに違っていた。石橋あすみは、経済的安定や両親のそろった家庭を息子に与えることで。石橋留美子は、無責任で暴力的な夫から、ふたりの息子を守ることで。石橋加奈は、頼りにならない男に依存せずに、必死で働くことで。
最後の石橋耀子は、親子げんかの果てに最愛の息子から「お母さんなんて、死んじゃえよおっ!」と殴られた怒りから、息子に手をかけた。その後で「ユウに会って抱きしめて百万回謝りたい」という。子どもへの憎悪からではない。「こんなにあなたのことを大事に思っているのに、なんでそれがわからないの?」という母の悔しさと惨めさからだ。
だが「守る」とは何だろうか?
愛してやまず、そのためにありとあらゆる苦難に耐え、いかなる犠牲もいとわない……母性の果てにあるのは、相手を思うようにしたい、という支配欲だ。石橋加奈を除いて、残り三人の母親は、息子が「思うように」ならないときに、切れた。加奈が例外なのは、息子が「思うように」育っているからにすぎない。こんなはずじゃなかった、こんな子じゃなかった、という失望と怒りが、コントロールを失わせる。九歳という年齢の設定は、子どもが意のままにならないことが次第にはっきりする年齢だからだろう。この支配欲を暴力と呼ぶなら、それだって暴力だ。だが、母親の暴力は父親の暴力より、屈折して入り組んでいる。
この作品から伝わるのは、母であることの恐ろしさだ。
そしてその背後にある、父であることの無責任さだ。母はたったひとりで息子を守ろうとし、それに男はなんの役にも立たないばかりか、時には妨害にさえなる。ある人が言った、「父の不在」という暴力、と。それこそが最大の暴力にちがいない。
息子を守りたい母の愛は、そのまま産んだ息子の生命を奪う権利にも通じる。その寓意を、まるで現場にいたようなリアルさで描き出したのが、この作品の功績だろう。
そしてこの三組の親子のなにがしかが、読者の経験のなかに思い当たるなら、本書は警世の書となるだろう。
書誌情報はこちら≫椰月 美智子『明日の食卓』
>>特設サイト