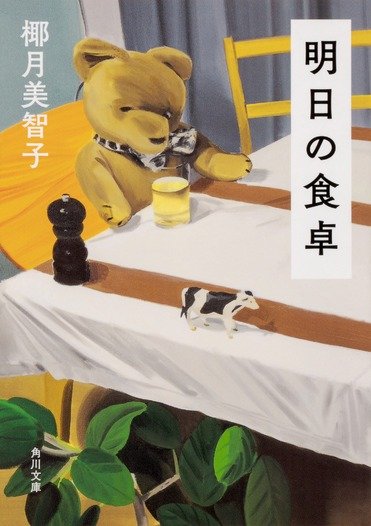【連載小説】男は男らしく、子育てに励み家事をする。女は女らしく、家族のために働く。 椰月美智子「ミラーワールド」#1-1
椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。
第一話
今日もAくんはかっこいい。ジャニーズに入ればいいのにと思う。いや、でも芸能界入りしたら、それこそ本当に手の届かない人になってしまう。やっぱりこのままでいい、と思い直す。
見ようによっては寝癖のようにも見えるけれど、あれはきっとさりげなさを装った、計算された髪型に違いない。だって、どこから見てもキマってる。寝坊なのか寝不足なのか、いつもより少し腫れぼったい
おはよう、の挨拶は今日もできなかった。いつか、当たり前に「おはよう」や「バイバイ」が言える関係になれたらいいな。
*****
池ヶ谷辰巳
「
四年生の
「こんにちは、莉茉さん。すてきなマスクだね」
「はい、お父さんが作ってくれました」
大胆な青いドット柄のマスク。莉茉によく似合っている。
「こんにちは、池ヶ谷さん」
続いて、四年生の
「こんにちは、隼斗さん」
次々と子どもたちがやって来て、辰巳は一人一人と挨拶を交わす。はきはきと挨拶する子もいれば、ただニヤニヤとこちらを見るだけの子もいる。一人を除く全員がそろったところで、辰巳は廊下に出た。
「青さん、こんにちは」
少し声を張る。青は廊下の向こう端から上目遣いで辰巳を見ていた。辰巳は青のところまで出向き、行こう、と声をかけた。青はしぶしぶといった感じで、辰巳のあとをついてきた。
「『
辰巳の言葉に、青がほんの一瞬目を大きくする。
「一緒にやろうよ」
やさしく声をかける。
「……ジジイ」
「は?」
「クソジジイ!」
青はそう叫び、辰巳を置いて一人で青空教室にかけて行った。
「はあーっ」
大きなため息が自然と出る。
青空教室というのは、
青を見ると、ランドセルもおろさずに一人で人形遊びをしている。ミニカーにシルバニアファミリーのうさぎを乗せてテーブルの上を走らせ、勢いよく床に落下させるということを繰り返している。辰巳はその行動の意味をさぐろうとしたが、低学年にはよくある遊びだと思い直す。
「池ヶ谷さーん、見て見て。百点とったよ」
莉茉が、今日返してもらったという算数のテストを掲げる。
「おお、すごいじゃない。やったね」
辰巳はそう言って、莉茉とハイタッチをした。学童保育は一年生から四年生までなので、莉茉は青空教室では最高学年となる。しっかり者の莉茉は、青空教室のリーダー的存在だ。自ら進んで、宿題の問題を解いているのは隼斗。面倒見のいい隼斗は、小さい子の宿題まで見てやっている。
「いてっ」
思わず声が出た。青がミニカーを辰巳の背中に投げつけたのだった。
「青さんっ!」
その様子を見ていたらしい
「……ハゲ」
ぼそりと言った青の言葉に、田島さんの顔は見る間に
「……なんだって? 今なんて言った?」
わなわなと頰の肉が震えている。
「まあまあ、田島さん。落ち着いてください。ぼくは大丈夫ですから」
辰巳は、今にも青につかみかからんばかりの田島さんを制した。
「ってかさ、この子。どう考えても学童なんて無理でしょ。親は一体なにしてるんだ」
わざと青に聞こえるように言う田島さんに、殺意のようなものを一瞬覚えたが、辰巳はすぐさま青に向き直って、大丈夫だからねと声をかけた。
「まったく、池ヶ谷さんが甘いから……」
聞こえよがしに言う田島さんを無視し、辰巳は青にミニカーを返す。
「青さんは、塗り絵をやりたいんだよね。はい、これ、どうぞ」
A4サイズの紙に印刷した「鬼滅の刃」の塗り絵を渡すと、青は奪い取るように受け取り、色鉛筆で色を塗りはじめた。
四時からは、運動場を使っていいことになっている。運動場では、いったん家に帰ってから遊びに来た生徒や、明知地区のサッカークラブの子たちが練習している。青空教室からサッカーの練習に参加する子どももいる。隼斗もそのうちの一人だ。すっかり身支度を整えてサッカーボールを蹴っているのが、窓から見える。今日は田島さんが屋外の担当なので、辰巳は教室に残った。
青は塗り絵に集中している。一色で塗るようになっている小さな空白にも三色の色鉛筆を使っている。枠からはみ出すことなく、きっちりと塗る。小学二年生で、ここまでできる子は少ないのではないだろうか。これも一種の才能だと、辰巳は思う。
青の家はシングルファザーだ。学童のお迎えはいつも六時半ギリギリで、かなりの頻度で刻限を過ぎることがある。
「父親のくせに信じられないな。だから青があんなふうになるんじゃないか」
青の父親が遅れるたびに、田島さんはそう口にする。田島さんのところの一人娘は、有名大学に通っていると聞いた。それまでずっと専業主夫だった田島さんは、娘さんの大学入学を機に学童指導員として働くことにしたそうだ。社会に貢献したいと言っていた。ボランティア精神は大事ですよ、としょっちゅう口にする。
学童指導員はボランティアではない。給料はもちろんもらっているし、大切なお子さんを預かる立派な職業だ。なにより、働くお父さんの役に立っている誇り高き仕事だと、辰巳は思っている。
「ぼくの妻はIT企業に勤めていて部長にまでなったんです。五十三歳になった今でも第一線でバリバリ働いていますよ」
田島さんの家族自慢は聞き飽きたし、そのついでといった感じで、「池ヶ谷さんのところは息子さん二人ですよね。男の子は育てやすいでしょう? うらやましいですねえ」と、付け足すところもモヤモヤする。男の子は育てやすくて、女の子は育てにくい? 誰がそんなことを決めたのだろう。なにも考えずに親世代からの口伝えを声に出す、田島さんのような人の多さにも閉口してしまう。
運動場では、田島さんが低学年の子の鉄棒を補助している。ここ四階の窓からでも、田島さんが大きな声で指示を出しているのがわかる。なぜ至近距離なのに、大きな声を出す必要があるのだろうか。男はヒステリックだと言われがちだが、辰巳は女性のほうがヒステリックな傾向があるとひそかに思っている。しかしながら田島さんに関しては、合っていると言わざるを得ない。辰巳は、田島さんがとても苦手である。
五時半を過ぎ、お迎えの保護者たちが続々とやって来た。青空教室は六時半までだ。青以外の生徒は全員迎えが来て帰宅した。今日もまた、青だけが残っている。
「青さんのお母さんは、男を作って出て行ったらしいね」
田島さんが耳打ちする。ほんの小さい声だったけれど、青がいる教室でそんなことを口にすること自体、信じられなかった。田島さんに対して、本日二度目の殺意のようなものが湧く。「男の敵は男」とよく耳にするが、これまた田島さんに関しては、残念ながらその通りなのだ。
「ぼくが残りますから、田島さんはどうぞ先に帰ってください」
「そう? いつも悪いですねえ」
田島さんはまったく悪く思っていない態度で、さっさと帰っていった。
「お腹空いたね」
辰巳は青に声をかけた。青は辰巳の声も聞こえないのか、集中して塗り絵に取り組んでいる。
夕食は用意してきた。今日はカレーだ。朝から煮込んできたから、おいしいはずだ。と、家のキッチンを思い浮かべた瞬間、辰巳は、あっ、と声が出た。しまった! 炊飯器のタイマーを押すのを忘れた! 時刻はもう七時になるところだ。長男の
次男の
どうにもならないのはわかっていたが、辰巳はどうしても気になって、携帯電話を手にとった。家にかけようとしたところで、教室の電話が鳴り、思わずびくっとする。
「もしもし、明知小学校、青空教室です」
「あ、もしもし。お世話になっております。神崎です」
青の父親だ。
「今どちらですか」
「すみません! まだ会社なんです」
「えっ?」
「さっき父に連絡したので代わりに行ってもらいます。本当にすみません」
「そういう連絡は、もっと早めにお願いします」
辰巳は学童保育の決まり事について話そうとしたが、青の父親は「すみません」を連呼し、通話を切った。自然とため息が出る。
「青さん、今日はおじいちゃんのお迎えだって」
青に告げると、青は顔を上げてこくりとうなずき、そそくさと塗り絵を片付けはじめた。ちゃんと聞いていたらしい。青はおじいちゃんのことが好きなようだ。
それから間を置かずに呼び鈴が鳴り、青の祖父が迎えに来た。遅くなって申し訳ありません、と深々と頭を下げ、青の手を引いて帰って行った。
すぐに辰巳も教室を出た。立ちこぎでペダルをこいで家路を急ぐ。
「ただいま」
ドアを開けリビングに入った瞬間、まったくさー、と妻の
▶#1-2へつづく
◎全文は「小説 野性時代」第205号 2020年12月号でお楽しみいただけます!