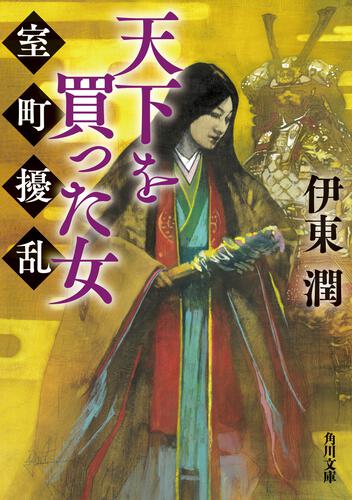伊東 潤『天下を買った女 室町擾乱』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
伊東 潤『天下を買った女 室町擾乱』文庫巻末解説
解説
累代の将軍御台所・将軍生母を輩出してきた日野家の娘として生まれた富子の生涯は平時であれば輝かしいものであったはずだ。しかし、時代は彼女に豊かで平穏な人生を歩ませてはくれなかった。乱世に向かいつつあるこの時期に、意欲に乏しく優柔な夫、その果断さに見合う実力のない息子を持ち、厳しい財政のなかで政権維持をはかるという難題に立ち向かうこととなる。そして、その挑戦は一定の成果をあげている。
富子が悪女と目されてきた理由の一つは、とほうもない額の蓄財にある。その遺産は七万貫(一貫=一〇〇〇文であることから七〇〇〇万文)といわれる。米価などを基準に現在の価値に直して七〇億円相当と説明されることが多い。しかし、物価を用いた価値換算だけでは七万貫のインパクトが伝わらない。賃金やGDPと比較したほうが直感的な規模を把握できる。
当時の上級技術者である大工の日当は一〇〇文、年収はおよそ二〇貫‐三〇貫、生涯所得は五〇〇貫ほどだ。七万貫は上級技術者の生涯年収一四〇人分にあたる。近年の大企業サラリーマンの生涯所得(三億円前後)を基準に換算すると七万貫は四〇〇億円以上のインパクトがあると言えよう。また、富子の生きた
政治家が二兆円以上の資産を保有していたら、メディアがどのように報じるのか想像してみてほしい。現代ですら、首相が三五〇〇円のカツカレーを食べたと言って批判する人がいるくらいである。当時の人々がこの遺産額を知るすべはなかろうが、それだからこそ、さらに尾ひれのついた噂が彼女への
本作中盤の重要テーマであるため詳述は控えるが、富子の蓄財は資金の貸付によって獲得されたといわれる。金貸しはいつの世も嫌われ者になりやすい。これもまた日野富子悪女説を導いた大きな要因だろう。
一方で、金融業の発展は室町期の経済や幕府財政を理解するに欠かせないテーマだ。
室町期に金融業は長足の進歩を遂げた。その一つが、現代風に言うならば、ポートフォリオ・マネジメントの発見である。ポートフォリオ・マネジメントの基本は「卵を同じカゴに入れないこと」と言われる。カゴを落とすと全ての卵が割れてしまうからだ。卵(資産)はさまざまな場所・入れ物に分散する必要がある。
それまでの小口融資は領主やその代理人から地域の農民に対して行われるものが中心だった。すると、貸し手は同じ地域の住民ばかりに貸付を行っている状態になる。その結果、地域で自然災害などが発生すると、貸付金は一斉に債務不履行状態になってしまう。さらに、自身の所領の住民に対して強硬な取り立てを行うことは難しい。返済不能になった地域住民を全部
一方で、室町期になると寺社が金主となり、専門的な金融業者(土倉)を仲介して小規模な融資を行う仕組みが整備されていく。金融業の大規模化とシステム化は、様々な地域への分散貸付を可能にする。金融業の隆盛のためには「信頼できる債務者」が欠かせない。「信頼できる」とは──手段は何であれ債権回収できるという意味だ。領主ではない専門業者は、遠慮や
京都の寺社と土倉による金融システムは、一六世紀に入って地域を一円支配する戦国大名が登場することで衰退していく。自身の領国の民を勝手に他国に売り払われてはたまらない。領国の治安と統治・裁判を一手に支配する戦国大名は、自領外の金融業者を許さない。かくして室町期の金融システムは
話を富子の利殖に戻そう。富子が金融業を通じて膨大な富を蓄積できたのは、同時期に室町期の金融システムが十分に機能していたからに他ならない。大名・小名は自身で裁判をできず、金融業者による領民への取り立てを阻止することもできない。多くの大名に権力を分散させ、その扇の要として成立していた室町幕府のシステムそのものが金融システムを支えていた。富子が「天下を買った」ことで戦乱を鎮めることができたことは──本作で富子が目標とした幕府権威の維持が保たれていたことの証左と言える。
富子の晩年は幸福なものとしては描かれないことが多い。確かに期待をかけた息子の早逝は、人の親として、大きな不幸だろう。その一方で政治家としての富子、日野家・足利家にとっての富子の存在はその私生活における不幸とは一線を画すものだ。本拠地での十年に及ぶ戦乱を経てなお権力・権威を保った政権が他にあるだろうか。その功績が大きいからこそ、
作品紹介
書 名: 天下を買った女 室町擾乱
著 者: 伊東 潤
発売日:2024年08月23日
ひとりの女性が、「応仁の乱」に立ち向かった――
経済の力で平穏をもたらしてみせる――。
名門日野家の姫君・富子は、一族の期待を背負って室町幕府八代将軍・足利義政のもとに輿入れする。
家中では「三人の魔」と呼ばれる曲者たちが息を潜め、政治壟断の機会をうかがっていた。
やがて管領・畠山家の家督争いに端を発し都が戦乱の渦に巻き込まれると、富子は自らの才覚で戦乱を収めようと立ち上がる。
「三大悪女」と呼ばれた女性の知られざる信念を描く、骨太歴史小説!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000876/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら