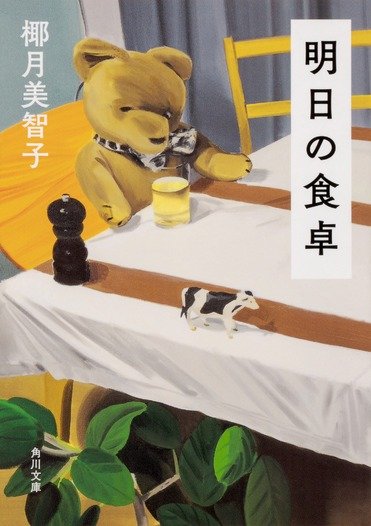【連載小説】男は男らしく、子育てに励み家事をする。女は女らしく、家族のために働く。 椰月美智子「ミラーワールド」#1-2
椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「疲れて帰って来て、さあ夕飯、って思ったら、ご飯が炊けてなくてがっかり!」
「悪かった。タイマーするの忘れちゃって。俊太は?」
「書道でしょ」
由布子が不機嫌に答える。そんなことはわかっている。
「俊太はなにか食べてったか?」
耕太にたずねるも、まだ制服姿の耕太は、
「今帰ってきたばっかりで知らないよ。俊太には会ってないし」
と、どうでもいいように言った。
「あー、お腹空いた。ほんとがっかり」
妻がぼやき、なんか食べるもんない? と冷蔵庫を開け、辰巳が答える間もなく、ちくわの袋を取り出してその場で封を開けた。
「もうすぐ炊けるんだから、少し待ってなよ」
「待ってられないから食べてんのよ。ついでにビールも飲んじゃお」
辰巳の言葉に耳を貸さず、由布子はちくわをつまみにビールを飲みはじめた。由布子に勧められるがまま、耕太もちくわを食べはじめる。辰巳は大きなため息をついた。
未開封だった食パンの封が開き、数が減っていた。おそらく俊太が食べていったのだろう。腹はふくれただろうけど、これじゃあ栄養が足りないと思い、タイマーをセットし忘れたことが悔やまれる。
「ったく、なんでわたしがバレー部の顧問なのかなあ。バレーなんて、中学のときの体育の授業以来やったことないっての」
もう酔いが回ったのか、由布子が大きな声を出す。由布子は公立中学校の音楽教師だ。辰巳も以前は公立中学で社会科を教えていたが、耕太が生まれたときに教師を辞めた。教師の仕事はおもしろかったが耕太の預け先が見つからず、たとえ見つかったとしても、生まれたばかりの幼子を親元から離すのは忍びなかった。
教員同士の夫婦は多い。辰巳の両親も教師だった。辰巳が仕事を辞めたとき、父はたいそう残念がった。子どもの頃から、手に職をつけろとさんざん言われてきた。職種は教師がいいだろう、とも。
トマトを切ってレタスをちぎりサラダを作ったところで、ご飯が炊けた。耕太は勢いよく食べはじめたが、由布子は、なんだかお腹がいっぱいなどと言って、カレーには口をつけず、サラダをちょこちょことつまんでいるだけだ。そのうちにチョコレート菓子を出して食べはじめている。
「身体に悪いぞ」
「身体より、精神的安定のほうが大事ー」
辰巳はそれ以上言うのをやめ、由布子から顔をそむけた。
「サッカーはどうだ」
気を取り直して、二杯目のカレーを食べている耕太にたずねる。
「三年が引退したから、今度から試合に出られることになった」
「よかったな」
「まーねー」
去年、耕太は反抗期甚だしかったが、高校に入ったら驚くほど落ち着いた。高校の水が合っているのだろう。目下の問題は次男の俊太だ。中学生になったとたん、目に見えて態度が悪くなった。身体も一気に大きくなってきたので、大人への過渡期だとは思うが、男の子が育てやすいなんて誰が言ったんだと改めて思う。その根拠を教えてくれと。
辰巳は、去年から学童指導員として働きはじめた。十六年ぶりに働きに出たことと、俊太の反抗期とに因果関係はないと思っているが、辰巳の両親に言わせると「ある」のだそうだ。
辰巳が教師を辞めないでずっと続けていたとしたら、子どもたちは自然と自立心が育まれ、親に反抗するようなことはなかったのではないかと、父は言う。男でもしっかりと社会に出て稼ぐことが大事だという姿勢を見せるべきだったと。
確かに、共働きの両親のもとで育った辰巳は、俊太のように父親に向かって「クソジジイ」などと言うことはなかった。けれどそれは両親が共働きだったからではなく、三つ上の姉が辰巳より先に盛大にぐれていたからだ。長いスカートをひきずり髪を爆発させ、当時流行っていた男子プロレスラーのようなメイクをし、無免許のバイクを走らせ、暴走行為で何度も補導された。両親、特に父は苦労したと思うが、女は仕方ないと言って、頭を振るだけだった。
一方の母は、辰巳が夕食の時間近くまで働く学童指導員などをはじめたせいで、家事がおろそかになったことが俊太の反抗の原因だと言う。自分たちだって共働きだったじゃないか、と辰巳が反論すると、それは生活が苦しかったからだと答えた。困窮している親戚がいて、仕送りをしていたそうだ。それさえなかったら、夫(辰巳の父親だ)には家に入ってもらいたかったと母は言った。
なによりも、男は家庭をいちばんに考えろと母は言う。由布子さんの言うことをよく聞いて、由布子さんが気持ちよく外で働けるためにサポートしなさい、と。辰巳は、いまだにそんなことを平気で口に出す母に
母に受け持たれた生徒たちはかなり気の毒だったと辰巳は思うが、母が教壇に立っていた時代は、残念ながらそれがかろうじて成り立っていた時代だった。辰巳の学生時代に、男にも権利を、なんて言葉は聞いたことなかったし、たとえそんな言葉があったとしても、辰巳の耳には届かなかったし、届いたとしても当時は深く考えなかっただろう。
男の権利などというものを考えはじめたのは、結婚して子どもができてからだ。夢だった教師をあきらめ、家事と子育てに費やしてきた十六年間。子育てはたのしかったが、日常のさまざまな場面で理不尽な目に数多く遭ってきた。男というだけで嫌な目に遭ったことを書き連ねていったらキリがない。
由布子は一本目のビールを飲み終わり、いつの間にか赤貝の缶詰を出してつまんでいる。
「これ、おいしいね。パパ、この缶詰また買っておいてよ」
「今日の朝、あなたがカレーがいいって言うから、カレーにしたんだけど」
「あはは。人は気が変わる生き物だから仕方ないよねー。ほんっと、パパって心が狭いよねえ」
由布子はそう言って立ち上がり、トイレトイレ、と言わなくていいことを口にして、辰巳の横を通る際に、小さい子どもによしよしとやるように頭をポンポンと触った。辰巳はとっさに
「そういうこと、二度としないでほしいって前に言っただろっ!」
「はあ? そんなに怒らないでよう。頭ポンポンがそんなに嫌なのお? パパって、へんなの」
そう言って今度はあごを触ろうと手を伸ばす。辰巳は妻の腕をバシッと払った。
「いったーい、これってDVだよねえ。おお、こわっ」
由布子はにやにやと笑っている。辰巳は由布子をにらみつけたが、由布子はおもしろそうにニヤつくだけだった。
▶#1-3つづく
◎全文は「小説 野性時代」第205号 2020年12月号でお楽しみいただけます!