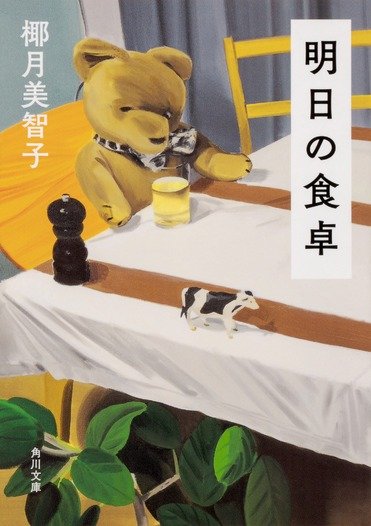【連載小説】妻のことはもう好きじゃない。離婚したい、離婚すべきだ。 椰月美智子「ミラーワールド」#1-3
椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
「やだっ、遅刻じゃない! なんで起こさないのよっ!」
由布子が二階からどたどたと降りてきて、開口いちばん怒鳴るように言う。
「何度も起こしたさ。大人なんだから自分で起きろよ。耕太も俊太もアラームかけて、自分で起きてる」
「もう間に合わないっ! 遅刻したらパパのせいだからね! もうっ、朝ご飯食べる時間もないじゃない! 貧血で倒れたらどうするつもりよっ!」
洗面所で歯磨きや洗顔をしながら、口が開くタイミングで文句を言っている。辰巳はもういいかげん、由布子を起こすのはやめたのだ。なぜ忙しい朝に、いい歳をした大人を二階になんべんも行って起こさなければならないのだ。朝食の準備をして、耕太の弁当を作るだけで手一杯だ。
「車のなかで食べて行くからおにぎり作って! 急いで!」
辰巳は大きくため息をつきながら、おにぎりを握った。大きな塩おむすびをひとつラップに包むと、由布子は引ったくるようにしてつかんだ。
「おいっ、ゴミ出し」
「うるさいっ! そんな時間ないわよ! バカじゃないのっ!」
叫ぶように言って、由布子は出て行った。辰巳は、出すだけにしておいた指定のゴミ袋を見て、ため息をついた。今日は燃えるゴミの日。ゴミ出しは由布子の仕事だ。家のすぐ隣がゴミ置き場だというのに、こんな簡単なこともできないのかと、怒りを通り越して呆れる。
ゴミをこの状態にするまでに、辰巳は各部屋からゴミを収集し、風呂場や洗面所、台所の排水口を掃除し、髪の毛やら生ごみやらを処分するという面倒な作業をしたのだ。それに比べれば、ただのゴミ出しなんてアホみたいに簡単だ。
「ほんっと、朝からうるせーなー」
それまで黙って朝食を食べていた俊太が口を開く。耕太は朝練があるので、とっくに出て行った。
「お母さんってマジうぜえ。お父さんもさ、あいつにおにぎりなんか作ってやらなくていいのにさ」
「お母さんのことを、あいつなんて言うなよ」
俊太はなにも答えずに席を立って、食べ終わった食器をシンクに運んだ。反抗期とはいえ、きちんと決められたルールを守る俊太は、由布子よりもよほど大人だ。昨日は、書道から帰ってきて、黙々とカレーを平らげた。
「今日は部活あるのか?」
俊太はバスケ部だ。
「……うざい。おれにしゃべりかけないでくれる?」
すぐにこうだ。うざい、うるさい、のオンパレード。けれど、憎まれ口を叩きながらもきちんと食器は洗っている。耕太も自分が食べた分はちゃんと洗ってから出て行った。自分で使った食器を洗わないのは、トイレで用を足したあと拭かないのと一緒だぞ、と子どもたちには言ってきた。この家で、自分が使った食器を洗わないのは由布子だけだ。きっと尻も拭いていないのだろう。
俊太を送り出したあと、辰巳は新聞を読みながら朝食をとる。その後、洗濯機を回し、掃除機をかける。掃除機を一階と二階の隅々までかけるとかなりの重労働だ。特に階段は面倒だしきつい。ゆうに三十分以上かかる。
掃除のあとは洗濯物干し。耕太の体操着とユニフォームは泥だらけなので、洗濯機に放り込む前に手洗いが必須だ。辰巳は、昨晩風呂に入りながら予洗いした。
洗濯を干したら、玄関を掃く。子どもたちのスニーカーに付いた土や砂のせいで、一日でザラザラになる。そのあと、ほんのわずかながらの庭に出て、雑草をいくつか抜いた。一週間もすると手に負えなくなるので、こうして毎日雑草の処理をしている。
庭には何本かの木が植わっている。鉢植えもいくつかあったが、すべて処分した。由布子が買ってきては置いていたが、世話をするのは辰巳ばかりで、興味のない辰巳が水やりしても花のほうでなにかを感じるのか、結局は枯れてしまう。不要になった土や鉢を処分するのもひと仕事だ。世話をしないのに、なぜ買ってくるのかわからない。
庭掃除が終わったあと、買い物に出かけた。自転車で十分ほどのスーパーマーケットだ。一台しかない車は由布子が通勤に使っているので、辰巳は専ら自転車となる。合い挽肉とナスが特売だった。ナスを小さくサイコロ切りにして挽肉と炒め、めんつゆベースで味付けしたメニューは、由布子は手抜き料理だと言うが子どもたちは大好きだ。
帰宅してひと息つく間もなく昼になり、ようやくここでテレビをつける。首相の
長く政権に居座っている分、腐敗や噓が隠しようもなく漏れ出しており、それをさらなる噓でごまかすことを繰り返している。口封じのための人身御供として逮捕者を出し、口止めできない輩には優遇処置をとるという最悪のシナリオを演じ続けている状況だ。記者のレイプ事件、収賄、自殺者まで出しておいて、しれっと我関せずを通している。国民にバレていないとでも思っているのだろうか。秋葉の厚塗り化粧顔を見るだけで、辰巳は
そもそもこの政党自体が、女尊男卑の保守派で金持ちのお嬢軍団が古い因習に
その前の国会では、同性婚について質問した男性議員に「お前のケツの穴は一体どうなってるんだ!?」というヤジを飛ばした男性議員がおり、吐き気がした。どこにでも「オバサンオジサン」はいる。同じ男だからといって、こちら側の人間ばかりとは限らないとつくづく思い知った。
また、その前の国会では、夫婦別姓に賛成の男性議員に向かって、「モテない男のひがみ」「使い物にならない下半身」「インポテンツ」などと、国会とは思えない言葉がお嬢たちの口から飛び交い、男性蔑視だと大きな問題となった。
辰巳はそのたびに、はらわたが煮えくり返るような怒りを覚える。それらの怒りは辰巳の胸にたまりにたまって、すでに許容範囲を大幅にオーバーしている。これが国会議員だろうか。これが日本の政治を動かす人間の所業だろうか。情けなくて恥ずかしくて、耳から内臓が出てきそうになるのだった。
秋葉首相の顔が画面いっぱいのアップになったところで、チャンネルを替えた。
──この秋のモテ男子服大全集
──女子をノックダウンさせる仕草
──最新脱毛情報
若手男性芸人が、この秋に流行る女子受けのいい服を着て、女子の気を引く仕草を試し、胸毛の脱毛にチャレンジするというものだ。辰巳はうんざりしてまたチャンネルを替えた。どこも同じような番組ばかりだ。年配の男優が二人でバスの旅をする番組に落ち着いたが、べつに見たくないことに気付き電源を切った。
昼食のあとは、夕飯の準備だ。挽肉とナスの炒め物。豆腐とワカメの味噌汁。米を研いで炊飯器のタイマーをセットする。昨日忘れたから二度確認した。
青空教室に行くまでにまだ少し時間があったので、辰巳は読みかけの本を開いた。『ガラスの天井/男たちの未来』という、セクハラ、パワハラについて書かれた本だ。さまざまな体験談が掲載されており、読むだけで胸が苦しくなる。だったら読まなければいいのだが、読まずにはいられない。
時代が変わり、辰巳の学生時代からは想像もできなかったような男性解放の気運が高まっている。SNSの普及のおかげで、個人が自分の意見を発表する場ができたことが、追い風になった。ニューヨーク・タイムズがアメリカの映画プロデューサーによる長年のセクシャルハラスメントを告発したことがきっかけで、日本でも男性運動が巻き起こり、我も我もと男性たちが体験談を語り出したのだ。
SNSでさまざまな人のさまざまな体験談や意見を読んでいくうちに、辰巳の脳裏に忘れていた過去の記憶が蘇ってきた。男らしくしろと、女子のうしろを歩かされた小学校時代。足が臭い、汗がキモいと女子に言われ続けた中学生時代。制汗スプレーは必須アイテムだったし、早々とすね毛が生えてきた男子は即座に処理を強いられた。
高校生の頃、野球で背中を痛めて受診した整形外科では、X線写真を撮る際にパンツまで脱がされた。そのあとの触診では、笑いながら女の医者に股間をはじかれた。通学に使っていた電車では何度も痴女に遭い、男性専用電車に乗ろうとしたら見ず知らずのオバサンに「ブサイクのくせに」と言われたこともあった。大学生のとき、教育実習で行った中学校の校長に食事に誘われ、帰り際わざと
錆び付いていた記憶の蓋が開いたとたん、長年被ってきた理不尽な体験を山のように思い出したのだった。傷に塩を塗りながらの浄化作業はつらいものがあったが、辰巳はもはやこれまでのように黙ってはいられなかった。当時、仕方がない、こういうものだと思っていた出来事は、まったく仕方ないことでも当たり前のことでもなかったのだ。悪はいつだって女の側だ。いつまでも女に従順な男でいる必要はないのだ!
なによりも辰巳の、女社会への疑問に拍車をかけたのは妻である由布子の存在だった。辰巳は、頭のなかのカレンダーを十年前の三月二十八日に巻き戻す。この日にちを忘れたことは一日たりともなかった。
耕太の幼稚園の卒園式を終え、就学の準備に忙しい頃だった。春休みということもあり、六歳の耕太と三歳の俊太は家にいた。その日は日曜日で、由布子も在宅していた。休みの日に限って早起きする子どもたち。逆に休みの日はいつまでも寝ている妻。辰巳は朝から体調が優れなかった。だるさが抜けず、頭痛があった。幼稚園の保護者会役員だった辰巳は、卒園式での謝恩会の疲れも残っていた。
家のなかのなにもかもが片付かず、まとわりついてきては部屋を汚す子どもたちの世話で疲れはピークに達していた。台所に立つことすらおっくうで、子どもたちには卵かけご飯とインスタントの味噌汁で昼食を食べてもらった。
そのうちに身体中が痛くなってきた。なんの気なしに熱を測ると三十八度を超えていた。まずいな、と思いはじめた頃、妻がのろのろと起き出してきた。そうこうしているうちに、悪寒がはじまり、身体に力が入らなくなった。熱は瞬く間に三十九度近くになった。
「マジ? まさかインフルエンザじゃないよね」
由布子の言葉にハッとした。そうではないと言い切れない。休日診療に行ったほうがよさそうだった。
「悪いけど、車出してくれるかな。運転できそうにない」
由布子に頼むと、はあ? と頓狂な声を出された。
「子どもたちどうするのよ。一緒になんて連れて行けないわよ。うつったら大変じゃない」
確かにその通りだった。タクシーを呼ぶことにした。支度をしている間も、子どもたちがまとわりついてくる。
「子どもたち頼むよ」
「ちょっと待ってよ。わたし、まだなにも食べてないんだけど。わたしのご飯は?」
「……子どもたちは卵かけご飯を食べた……」
しゃべるのも辛かった。
「うそでしょー。それしかないの? わたし、今すごく忙しいんだよね。春休みの教職員たちの慌ただしさ、あなたも知ってるよね?」
由布子はぶつぶつと文句を言っていたが、相手にする気力はなかった。到着したタクシーに乗り込み、辰巳は休日診療に向かった。
結果は、やはりインフルエンザだった。予防接種をしていたから軽くて済むでしょう、と先生が言うわりに、身体は鉛のように重く、財布を開けることさえままならなかった。由布子にはすぐに電話をして、インフルだったことを知らせた。由布子は大きな声で、「サイテー! なに考えてんの!?」と、ののしった。
▶#1-4へつづく
◎全文は「小説 野性時代」第205号 2020年12月号でお楽しみいただけます!