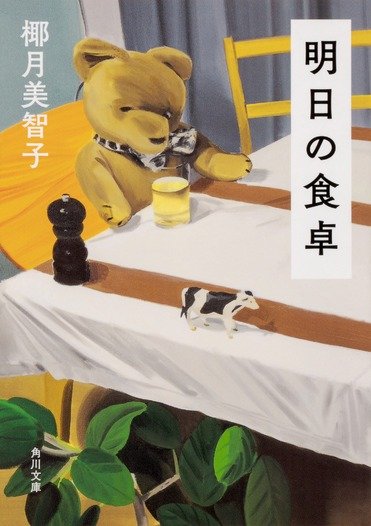【連載小説】妻のことはもう好きじゃない。離婚したい、離婚すべきだ。 椰月美智子「ミラーワールド」#1-4
椰月美智子「ミラーワールド」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
帰宅すると、子どもたちが「パパー」と飛びついてきた。
「ごめん、パパの風邪がうつると大変だから離れててね」
由布子は一体なにをやっているんだと思いつつリビングに行くと、カップラーメンを食べながらテレビを見ていた。
「おれ、寝るから」
「えー、寝るの? 薬飲めば治るよね?」
「うつるといけないから、二階の和室で寝る。子どもたちを近寄らせないでくれ」
「夕飯はどうすればいいの?」
「……なにか買ってくればいいだろ」
「ねえ、だって、明日からどうするの? 子どもたちの面倒、誰が見るわけ?」
「……悪いけど具合悪いから……」
明日のことは心配だったけれど、身体が悲鳴をあげていてなにも考えられなかった。薬を飲み、普段使っていない和室に、最後の力をふりしぼって自ら布団を運び、枕元に水とスポーツドリンクを用意した。なんとか着替えを済ませ、辰巳はそのままほとんど気絶するように眠った。
目が覚めたとき、部屋に置いてあったデジタル時計の時刻は2:24だった。喉がひどく渇いていて、スポーツドリンクを一気に飲んだ。身体はかなり楽になっていた。障子窓から差し込む光が明るかった。深夜の二時だと思っていたけれど、まさか昼なのだろうかと思い、辰巳はのろのろと起き出して下に行った。リビングは泥棒にでも入られたかのようなひどい有様だったが、誰もいなかった。
テレビをつけ、今が月曜日の昼だということを知った。丸一日寝ていたことになる。由布子は職場の中学校に行ったのだろう。子どもたちはどうしたのだろうか。病児保育に依頼したのだろうか。携帯電話を手に取ると、何件もメールが入っていた。すべて由布子からだった。
ふざけないでよ! ご飯も作らないで寝てるんじゃないわよ! 子どもたちの世話どうすんのよ! なんで予防接種してるのにインフルになるのよ! 規則正しい生活をしてないから、インフルになったのよ! わたしにうつったらどうするの! 主夫が健康管理できなくてどうするつもり! 何回も起こしているのになんで起きないのよ! わざと寝てるんでしょ! ほんとムカつく! 存在意味なし!
膨大な量の感情的な言葉が、ずらずらと羅列されていた。永遠ともいえる罵詈雑言が続いたあと、「耕太と俊太は、わたしの実家に預けることにしたから!」とあった。「うちの父に感謝してよ! ダメ主夫!」で締めくくられていた。
辰巳は由布子の暴言に引っ張られないように、気を張った。子どもたちのことがなにより心配だったが、ひとまず安心した。昨日は子どものことが気になりつつも、身体の不調にすべての思考が持って行かれてしまい、自分のことだけで精一杯だった。妻がいたからよかったものの、シングルファザーのお父さんたちは本当に大変だとつくづく思った。おちおち風邪も引いていられない。
冷蔵庫に子ども用に買っておいたヨーグルトが一つあったので、それを食べてまた横になった。由布子には、どうもありがとう、とだけ返信をした。義父に電話を入れようかと思ったが、まだ頭がはっきりと働かなそうだったのでやめた。
由布子の両親は家から車で四十分ほどの場所に住んでいる。義父は気のいい人で、頼めば子どもたちの面倒を見てくれるが、辰巳からはなかなか言い出せず、頼むことはほとんどなかった。辰巳の実家は新幹線で二時間以上かかり、気軽に頼める距離ではない。
その日帰宅した由布子は、和室の
「誰の稼ぎで生活できてると思ってんのよ!」
といきなり言い放ち、壊れるんじゃないかというくらいの音を立てて襖を閉めた。バンッという音が頭に響いて、辰巳は耳をふさいで枕に顔をうずめた。うずめていたら、涙が出てきた。泣くつもりなんてまるでなかったのに、勝手に涙がぼろぼろと流れてきて自分でも驚いた。涙はその後しばらく止まらなかった。
頭のなかは、なんで? どうして? でいっぱいだった。なんで、あんなふうに言われなきゃならないんだ? どうして、おれが怒られなきゃいけない? なんで怒鳴られる? どうして、こんな目に遭わなきゃいけない? 妻に対する疑問は次々とあふれてきた。
誰の稼ぎで生活できてると思ってんのよ! まさかそんな言葉を、現実に自分が言われるとは思っていなかった。確かに、自分は現在勤めていないから収入はない。けれど、働きに出ている妻の分まで家のことをやっている。
掃除、洗濯、料理、子どもの世話。八時間労働どころではない。子どもたちが赤ん坊の頃は二十四時間労働と言ってもよかった。夜泣きへの対応、ミルク作り、おしめ替え。動き回る子どもたちを追いかけ、お茶を飲む間もなかったし、風呂では目を離したすきに溺れるのではないかと、シャンプーの泡だってろくに洗い落とせなかった。
女は子どもを産みっぱなしだ。産前産後の半年間ずつ、国から生活のすべての保障がされる。産前半年は出産に向けて身体を整える期間で、産後半年は赤ん坊に母乳をやる期間だ。妻の産前産後一年間、辰巳の慌ただしさは変わらなかった。むしろ一人増えた分、家事労働もかさんだ。人が作った飯を食い、横になるだけの妻は、はっきり言ってただただ邪魔だった。
もちろん職を持っていたって、率先して家事をする女性は多くいる。けれど、由布子はそうではなかった。イクジョが叫ばれてひさしいが、由布子は時代に逆行していると言わざるを得ない。
涙はしばらく止まらなかった。同じ中学校で同僚だった由布子と恋愛をして、結婚に至った。二人でお金を出し合い、マイホームを購入した。子どもができたとき二人で話し合い、辰巳が家庭に入ることになった。それは由布子の望みでもあった。
「二人で分業しよう。わたしがバリバリ働くから、たっちゃんは子どものことと家のことよろしくね」
由布子はそう言った。辰巳も異存はなかった。家族を支え、生活をやりくりしていくための分業。由布子は仕事、辰巳は家事育児。それなのになぜ、「誰の稼ぎで生活できてると思ってんのよ!」などと、恫喝されなければいけないのだろうか。インフルエンザにかかっても、大丈夫? のひとこともなく、布団も敷いてくれなければ、弁当のひとつすら買ってきてもらえないのだ。
悲しみのあとに訪れたのは、怒りだった。猛然とした怒りの炎は辰巳を一気に取り巻き、辰巳の芯部に小さな火種を残した。
その後、辰巳は由布子と何度か話し合いの場を設けた。その場では、「そうだね、パパの言う通りかもね」などと殊勝に言うが、由布子の態度が変わることはなかった。自分の仕事が忙しくなると感情的になり、些細なことで辰巳に当たりつっかかってきた。子どもに当たることもしばしばだった。子どもたちに音楽を教える教師の裏の顔だ。音楽をやるからといって、人間ができているわけではないのだ。由布子には、ヒステリーという言葉がぴったり合う。
妻は変わらない。
あれから十年経って、辰巳が学習したのはそれだった。なにをしたってなにを言ったって、由布子は変わらないのだ。
スマホのタイマーが鳴った。時刻は午後二時半。辰巳は本を閉じ、家の戸締まりを確認して、自転車にまたがった。今日の青のご機嫌はいかがだろう。心を開いてくれるだろうか。そんなことを思いながら、秋晴れの青空を見上げる。
「専業主夫になったことによる、いちばんの弊害はー」
と、辰巳は声に出す。辰巳は、自転車を走らせながら気持ちを吐き出すのが好きだ。口に出した瞬間、言葉はどんどんうしろに流れて消えていく。
「妻のことをー、好きじゃなくなったことに尽ーきーるー」
いや、好きじゃなくなった、なんて甘い言い方では足りない。妻のことはもはや嫌いだった。
「りーこーんー」
離婚してもいい、いや、むしろ離婚したい、離婚すべきだ、と辰巳は思っている。
▶#1-5へつづく
◎全文は「小説 野性時代」第205号 2020年12月号でお楽しみいただけます!