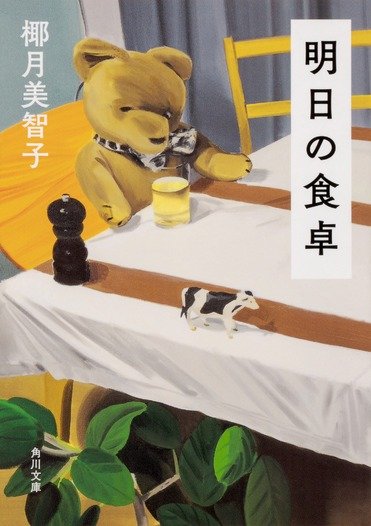幸福な家庭はどれも似ているが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である、と言ったのはトルストイだが、これ、子育ても同様だと私は思っている。子育てに手を焼いている親(とりわけ母親)にとって、その理由は千差万別であり、それこそ子どもの数だけある、といっても過言ではない。ものすごく乱暴に言ってしまうのだが、うまくいかないからこそ、の子育てだ、ぐらいの気持が、私の中には、ある。子育てがうまくいっていない親の僻みだ、開き直りだ、と言われてもいいよ。でも、僻みでもなんでもいいから、そんな風に思うと、ちょっと気が楽になりませんか? 世の子育て真っ最中のみなさま、私には十八歳になる息子がいるのですが、そして十八歳になっても子育てかよ!というツッコミがあるかもしれませんが、マジ、うまくいかない日々ですわっ!(すみません、愚痴りました)
本書に登場するのは、文字どおり、子育て真っ最中の母たちである。専業主婦の石橋あすみ、フリーライターの石橋留美子、シングルマザーの石橋加奈。彼女たちの息子は、それぞれ、優、悠宇、勇。苗字も名前の読みも年齢も同じ、八歳のイシバシユウなのに、母子の日々は三者三様で、暮らしの背景も異なっている。あすみはメーカー勤務の夫と、夫の実家の敷地に建てた一戸建てに暮らしている。留美子は、フリーカメラマンの夫とマンション暮らし。悠宇の二つ下には巧巳もいる。加奈はパートをかけもちして、早朝から夜まで働きづめに働いている。
優は、聞き分けの良い手のかからない〝いい子〟で、スイミングと絵画教室に通っている。あすみは私立中学受験を考え、学校探しを始めているところだ。悠宇は、やんちゃ仕放題、留美子の言うことを聞くどころか、弟と一緒になって騒ぎまくり。勇は、根を詰めて働く母親を気遣う優しい子だ。
三人のユウと三人の母、それぞれの日々が実にリアルなのだが、なかでも歳の近い兄弟を育てている留美子の日々が、男児の母にとっては〝あるある〟満載。これは、実際に小学生男児二人の母である椰月さんの実感も、多分に込められているからだろう(留美子の仕事をも含めて)。仕事でテンパっている時に限って、やらかしてくれる悠宇と巧巳に、読んでいて思わずこちらが雷を落としたくなるほど。
子どもだけではない。あすみの夫は優しいけれど、何か問題があるとあすみに押し付けてしまう。留美子の夫は、一家の経済的な基盤でもあった撮影の仕事を打ち切られてしまったことで、やさぐれていく。加奈は加奈で、夫こそいないものの、仕事を辞めて実家に戻った弟からお金の無心をされる。
兄弟の子育てと仕事との両立で、文字どおりキリキリ舞いの留美子、常に経済的な問題を抱える加奈と比べると、暮らしにも息子にも恵まれていると思われたあすみだったが、あることをきっかけに、その幸せが根底から揺らいでいくことに……。
本書の冒頭に、「ユウ」という子どもが出てくる。この「ユウ」とは、優なのか、悠宇なのか、勇なのか、それとも……。この冒頭があるために、読み進めるにつれじわじわと不穏なものが胸の中に積み重ねられていく。「ユウ」が誰なのかは、実際に本書を読まれたい。このあたりの椰月さんの筆さばきは、実に鮮やかである。
人生には、ぼこぼこと落とし穴がある。なかでも子育ての落とし穴は、一見〝穴〟には見えないものもあったりするので、知らずしらずその穴に落ちてしまうことがある。その穴が思いがけなく深かったりすることも。人生にも子育てにも、正解や〝当たり〟はないのだ。あるのは〝明日〟だ。今日は辛くても、明日は。今日は陽が差さなくても、明日は。大事なのは、その明日を信じること。強く、強く、信じることなのだ、と本書は教えてくれている。