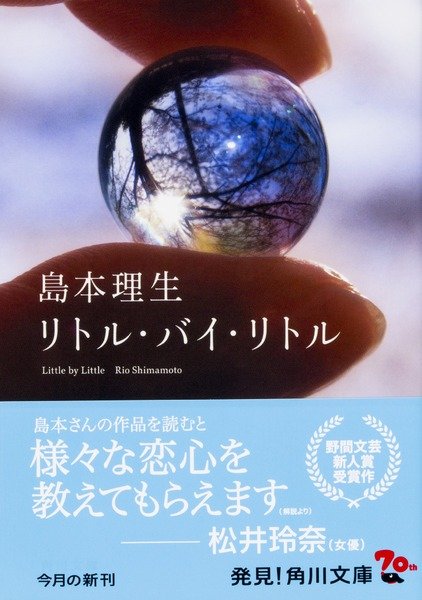解説 静かに燃える炎
今回、新装版として刊行された本書には、三つの作品が収録されている。いずれもずいぶん前に書かれた作品で、もっとも古いものは、約二十年前に書かれたものだ。二十年! 年月の長さにまずは驚き、その長さに反し、まるで色褪せない作品たちのすごさを、しみじみと噛みしめてしまった。
説明するまでもなく、現在、
表題作である「シルエット」は、出だしからしてぐっと心をつかまれる。
何ヵ月も何ヵ月も雨が降り続き、もしかしたらこのまま雨の中に閉じ込められるかもしれない。そう予感するような季節の中にいた。もちろん、わたし自身が。(中略) ただ一切を無視して、わたしの中に雨は降り続いた。そして自分の体内に確実に響く雨音をいつまでも聞いていた。まるでもう一つの鼓動のように。
とても美しく、続きを読まずにはいられなくなるような文章。島本さんの他の作品にも、印象的な雨のシーンは出てくるが、改めて、雨の似合う作家であると感じた。しとしとと降る、静かな雨。
また、テーマそのものも、その後の島本作品の軸となっているものだ。恋愛をベースにしながら、心から他者を必要として、求める気持ち。どうしても分かり合えない孤独さ。恋愛における喜びと悲しみを、砂金を見つけ出すようにして、巧みに
短めの作品でもあり、ストーリーはわりとシンプルだ。母子家庭で育った主人公の女子高生が、同級生の
登場回数は少ないが、主人公の母親の存在が魅力的だ。立場もあって、主人公への言葉は、説教めいたことが多いのだが、どれも本質的で無駄がない。作中には描かれていない、主人公と母親との二人の日々には、しっかりと信頼関係が生まれているのだということが伝わってくるようになっている。
そして、はじめの存在。問題や悩みを抱える人が多い作品の中で(もちろん現実世界においても悩みを抱えていない人なんてほとんどいないのだけれど)、いつも《りんとしたまっすぐな姿勢》である彼の存在が、清涼剤のように感じられる。
そしてラスト。情景が頭に浮かんでくるかのようなそのシーンに、さまざまな感情を喚起させられる。息が詰まりそうで、それでいてずっと浸っていたいと思わせるような空間。聞こえるはずがない電車の音や、ホームのアナウンスが、確かに聞こえてくるような気がするのだ。
二作目の「植物たちの呼吸」は、短篇というよりも、ショートストーリーというくらいの短い作品である。
恋人の江島君の帰りを、彼の部屋で待っている主人公。筋としてはそれだけの話なのだが、やはり一筋繩ではいかない。主人公が彼の部屋で居候を始めることになった経緯や、江島君の背景が、自然なエピソードの中で明かされていく。淡々と、今の恋愛がどれほどの情熱を持ったものであるのかも。
奇妙な夢の描写があり、読者は不穏な展開を思わずにはいられなくなるのだが、直後にラストが訪れる。続きを知りたいという気持ちが生まれるが、あえてここで物語を終わらせるのだという作者の決意がかっこいい。読者のそのときの心境によって、まるで違った感触を持つことができる。
そして三作目の「ヨル」。こちらも「植物たちの呼吸」と同様に、短い作品となっている。
作者のプロフィール的な背景というものは、本当はあまり関係のないものなのかもしれないが、執筆当時、島本さんは女子中学生だった。それを知ったうえで読むと、本当に? と疑ってしまうくらい、完成度の高いものだ。
主人公は女子中学生であるが、細かな情報は特に明かされない。最近恋人と別れたこと、母子家庭であるということくらい。彼女が夜に出かけた古本屋で、クラスメートの神谷君と偶然に出会い、ぽつぽつと会話を交わし、一冊の本をもらう。
神谷君のことは、主人公以上に謎だ。少しだけ見た目の描写があるものの、なぜそこにいたのかといったことや、起こした行動の理由は語られない。
すぐに読み終えてしまう長さだが、妙に心に残る。夜の中で神谷君の後ろ姿を見つめる主人公を、しばらく思ってしまう。
島本さんの文章は、静かに組み立てられている。そうでなければ壊れてしまうのではないかと思うほど
しかし静かで美しい、読みやすい文章でありながらも、そこには時おり、驚くような激しさも潜んでいる。
優しさや柔らかさを感じながら読み進んでいると、突然、火傷したかのような衝撃が胸に走るのだ。
「シルエット」にもそうした箇所はいくつもある。冠くんのお母さんが寝たきりとなっている理由が語られる部分。冠くんが自分の手を《おそろしく自然な動作で引っ込めてしまう》という描写。主人公の「せっちゃん。したい」というまっすぐな発言。
島本さんの作品の中には、いつだって熱が宿っているのだ。口当たりのよさからはとても想像のできないほど、熱くて、うかつに流してしまえないほど切実なもの。
読者であるわたしたちは、フィクションだと割り切れないほどのその熱に、驚き、戸惑う。かつての自分自身の傷を思い出し、胸を激しく痛めたりもする。だからといって、読むのをやめることはできない。むしろ、その熱を求めて、信じるように、つい島本作品に手を伸ばしてしまうのではないかと思う。
最後に個人的な話になってしまって恐縮だけれど、島本さんとわたしは、年齢も同じで、デビューの時期もほぼ同じという共通点があることもあり、ずいぶん昔から親しくさせていただいている。
一緒に飲んでいるときは、小説の話題はほとんど口にのぼらず、くだらない話ばかりしては笑い合っているのだけれど、内心ずっと、島本理生という存在に支えられつづけている。こんなにもエネルギッシュで、書くことに貪欲な人は、そうそういないのではないかという気がする。
そのエネルギッシュさを、「理生ちんは元気だからなあ」とわたしは冗談めかしていつも挨拶のように口にしてしまうのだけれど、本当に、あの細くて華奢な身体のどこにそんなにもエネルギーが詰まっているのだろうと不思議で仕方ないほど、いつだって力に溢れている。常に作品を生みつづける姿勢が、読者としてものすごく嬉しいし、同業者としてものすごく憧れる。次の作品が待ち遠しい。