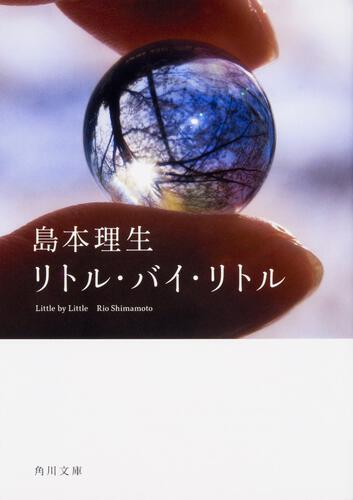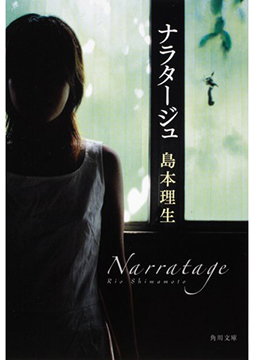十九歳の時、私は何をしていたでしょう。高校を卒業して、大学には行きませんでした。仕事を始めて二年が経ったくらい。段々と仕事に慣れてきた頃の様な気もするし、バタバタと新しい環境になって行っていた頃の様な気もします。
アイドルグループに身を置いて、愛知県から東京に通っていると、同年代の子達と同じ様に男の子に接する機会はないに等しかったし、男の人は現場にいるスタッフさんくらい。当時は仕事に夢中だったから、自分に埋めるべき大きな穴がある事にも気が付かないで、そのままにしていました。
私は家族の事は好きだけれど、中高生の頃、今思えばなかなか妙な距離感で生活をしていた気がします。部屋に篭ることも多く、ゲームをしたり、ネットサーフィンをしたりする時間が大切で、食事もなんとなく、部屋で一人で食べることが増えていました。その流れで仕事を始めてしまったから、帰っても疲れているからと、家族と特に話す事もなく、部屋に篭り、寝て、起きて、朝また仕事へ向かうという生活をしていました。
最近になってやっと、昔の様に、家族との時間を大切にする余裕が自分に生まれて来ました。私には三つ歳の離れた兄がいます。兄の仕事と、私の仕事の時間が違うから、なかなか帰っても会える機会がなく、年に何回か顔を合わすくらい。とてもユーモアのある人で、小さい頃はお兄ちゃんっ子だっただけに、知らないうちに出来てしまった溝にここ数年戸惑っていました。
一年前くらいに、兄と二人でライブを観に行った事があります。好きと言っていたアーティストだったから、誘ったら喜んでくれるかなと思ったんです。初めてライブハウスに来た兄は、プラスティックのカップに入ったビールを片手に立ち尽くしていました。来る事ができて嬉しいけれど、盛り上がり方がいまいち分からないという様子でした。
帰りの電車の中、最寄り駅まで一時間弱の間、兄との会話は数分しかなくて、楽しかった、知ってる曲もあった、とかポツリポツリとしたワード。その後駅に着くまで会話はほぼ無し。兄がやっていたスマホのゲームを覗き込んで、それは何? と聞いても気の無い返事が返って来るだけでした。
翌日、母からメールが来て、「お兄ちゃん、楽しかったって言ってたよ」と。楽しんでもらえたのはとても嬉しかったけれど、兄と会話が全く成立しなくなっていた事に、私は認めたくないけれど落ち込みました。
どうやって話したらいいのか、どんな話題を振るべきか、顔色ばっかりうかがって。兄妹なのに変だなって。
今年の頭にまた兄とライブを観に行きました。名古屋駅で待ち合わせをして、会場に向かうホームで、突然兄から彼女と別れたという話を聞かされました。十年はいっていなかったけれど、八年、九年付き合っていた人で、てっきり結婚をするものだと私は思っていたんです。彼女に振られたと言う兄は空元気で笑っていたけれど、理由を聞いたら兄の人生を否定された様な気がして、なんでか私が悔しくなりました。泣かなかったけれど、泣きたいくらいにです。
その日のライブが始まる前に、「この曲歌われたら泣くなー」と兄がつぶやいていた曲が流れて、ステージの明かりを受け、黒くシルエットになった肩が震えていました。見てないふりをしながら、私は、本来十代にあるべき兄妹のコミュニケーションがすっぽり抜けていた事、それがこの日に数年分埋まった様な気がしました。兄が話して分けてくれた痛みを、私は全部まるっと共有はできないけれど、その端っこを持たせてもらえたんだなと。
長々と私的な話をしてしまいましたが(しかも兄をネタにするという。ごめんよ、お兄ちゃん)、『リトル・バイ・リトル』は家族や、自分にとって近しく、大切な人たちとの触れ合いの話だと感じて、この話をふと思い出したのです。
物語の中でふみにとって父親の存在が大きく書かれています。両親が離婚した後も、毎年誕生日には池袋で待ち合わせをして出掛ける。同じ星座をプラネタリウムで見たり、ファミレスに行ったり、プレゼントを買ってもらったり。ふみにとってその時間は、とても特別だったんだと思います。普通なら日々少しずつ与えられる、父親からの愛を、その日一日、スポット的にかもしれないけれど受けることで、彼女の心は少なからず満たされていたんだろうと。
あったはずの物が無くなると、どうも落ち着かず、何がいけなかったのか、どうしたらこの穴は埋まるのだろうかと、中の見えない箱に手を突っ込んで探している気分になります。ふみにとってそれは父親の存在なんでしょう。
虐待をされていたとしても、もう会いに来てはくれなくても、割り切れず、期待してしまう。仕方ないと受け入れてしまう。想像の中で生きている父親に幻想を抱き、美化してしまう気持ちはよく分かります。その人の存在が大切であればあるほど、ダメだと思う気持ちと裏腹に肯定的な感情が溢れてくるんです。
ふみの中にある穴をそっと埋めてくれるのが周。
『リトル・バイ・リトル』は島本さんの作品の中で、いい意味でドラマチックな恋愛ではない、淡々とした恋愛の作品だと思います。ふみと周の何気ない会話が、本当は大切で、物語を進め、二人の距離も縮めていく。とても日常的でリアルだな、と思いました。
整骨院でうなり声をあげながらの初めまして。その後に二人でカレー屋さんに行く。ポツポツと話しながら、自然に周に惹かれて行くふみを可愛らしく感じました。
二人が会う時には、たくさんの食事の場面が出て来ます。最初はカレーを食べていて、その次は中華料理。誰かと食事を共にするとぐっと距離が縮まる様な気がします。ぐっと縮まるというのは、まあ相手との相性が上手く行った時なんだとは思いますが、二人で食事が出来るというのは、私としてはかなり心を許していないとできない事だなと思います。これは恋愛関係に限らず、友人でもですね。
よく、グループでなら話せるけれど、この人と二人きりになると何を話したらいいか分からなくなる人っていませんか? そういう人と食事になんてなったら、もう緊張しかしません。とにかく話を繋がなくちゃと気を遣うし、考えすぎて食事ばかりが進んでしまったらどうしようと、不安になり、美味しいはずの食事も味を忘れてしまうほどです。好きな人との、ドキドキしてしまう食事とは、また違うのです。気を遣う相手との食事は不慮の事故だと言い聞かせようと考えています。
ふみと周、二人の会話は、自然にお互いのことを話したり、食事を楽しんだり、私にとっての理想に近いです。きっと沈黙があったとしても、その間さえ会話として、二人の時間として成立しているんだろうなと。
その対比として、ユウちゃんのお父さんを交えた家族四人での食事のシーンが効いているなと思いました。言葉を返しても、そこで会話が途切れてしまうし、発展することもあまりない。ふみに勉強のことを聞いて
「少しは勉強もしないと。使わないと覚えたことっていうのはどんどん忘れていくから」
とひとごとの様に話す姿は、お互いにどんな距離感で話していいのか分からない、間合いの合わない事故です。
私が特に好きなふみと周の場面が、コインランドリーの場面。 ふみが貸した服を洗って、洗濯機が回るのを二人で眺める姿がとても映像的。思い浮かべると映画のワンシーンの様で生活の匂いが閉じこめられた文章です。
二人でお弁当を食べて、「周といるときは、いつも食が充実している気がする」と言って、そんなことはないと言い合えたり、「平和だねえ」と言える時間。何気なく、今日失敗してしまった事を打ち明けたり、自分の抱えてる痛みの端っこを分け合える、そんな関係はとてもうらやましいです。
私が悩んでいたとき、それを打ち明けていないのに、何か思いつめていることがあるでしょうと、当てられたことがありました。一人で抱え込んでいるわけではないですが、自分の中にあるモヤモヤを言葉にしようとすると、それ自体が本当のもやの様に、掴み所なく、飛んで行ってしまう様な気がして、一番肝心な事を人に打ち明けられないんですね。そのときは無理して明るくしていたわけでもなく、普段どおりに振舞っていたので不思議でしょうがなかったのを覚えています。不思議すぎて、すっとんきょうな声で返事をしてしまうという、恥ずかしい思い出にもなりました。その時に言われた言葉と周の言葉がとても良く似ているんです。
「なんで怖いって言わないんですか」「言わなきゃずっと分からないままですよ」「毎回怖いって思うたびに、そう言えばいいじゃないですか」
こんな風に言われたらとても勇気をもらえます。背中を支えてもらっている気持ちになれます。不安なことを打ち明けるのって、もの凄く、最初の一歩が怖いものです。ふみの言う様に、自分にとっての『怖い』は口にしてしまうと形になってしまいそうだから。
私の友達は、悩みを話すのが下手くそな私に「どんだけ時間がかかっても、根掘り葉掘り、全部質問して聞いてあげるから。言わなきゃ分からないし、言っても大丈夫なんだよ」って。その友達のお陰で私は救われて、落ち込む事があっても、どうにかこうにか楽しくやっていられている気がします。自分自身も、相手が落ち込んでいるなら、全力で受け止めたいと思えます、そうやって、心を許せる人がいる事でお互いが満たされて、安心できて、楽しく生きて行こうと思える事を、作品に思い出させてもらえた気持ちです。
こんな十代の青春は私には無かったけれど、島本さんの作品を読むと様々な恋心を教えてもらえます。経験できていない感情に溢れているから、何度読んでも、驚きと苦しさで胸がいっぱいになる。私の恋心のバイブルとして、これから先も本棚に大切にしまっておきたいです。