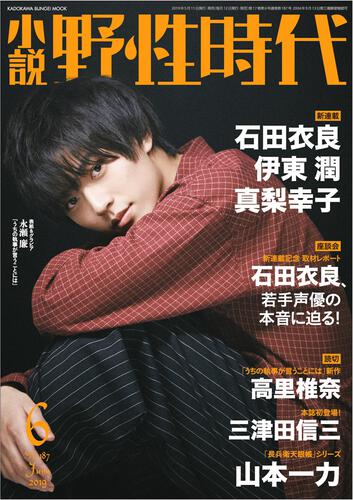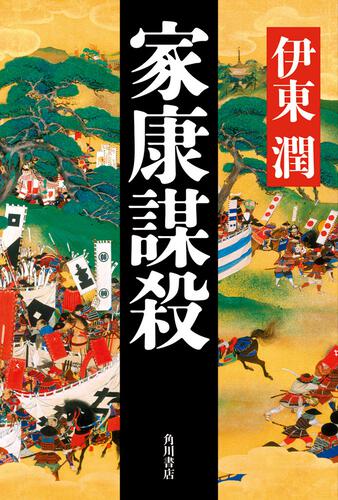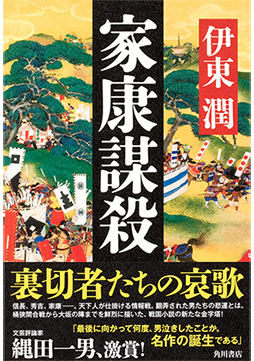5月11日(土)発売の「小説 野性時代」2019年6月号では、伊東潤「悪しき女 室町擾乱」の連載がスタート!
カドブンでは、この新連載の試し読みを公開します!

将軍・足利義政に嫁ぐ十六歳の日野富子の前に立ちふさがる「三人の魔」とは?
稀代の悪女と謗られた御台所の生涯を描く!
第一章 かくれなき美婦人
一
足利家の男たちは日野家の女を好んだ。
日野家の女が総じて美しかったこともあるが、それよりも足利家が天下人となれたのは、日野家のお陰だと言ってもいいからだ。
後醍醐天皇の建武の新政が行き詰まると、足利尊氏・直義兄弟は反旗を翻した。だが朝敵とされた不利は否めず、実力頼みの戦いはすぐに行き詰った。そこで尊氏らは、後醍醐天皇の大覚寺統と皇統を争っていた持明院統を担ぐことにした。
この橋渡しをしたのが醍醐寺三宝院の賢俊だった。賢俊は権大納言・日野俊光の息子で、兄は討幕活動の中心にいた日野資朝だった。賢俊も兄に協力して討幕に加担したが、後醍醐天皇は賢俊と仏教界の盟主の座を争っていた真言宗立川流の密教僧・文観を寵愛する。そのため賢俊は持明院統の光厳上皇と通じて院宣を賜り、尊氏らの逆転勝利に陰から貢献したのだ。
その結果、賢俊は権大僧正・醍醐寺座主となって仏教界に君臨することになる。
こうしたことから、足利・日野両家は切っても切れない間柄となった。
その後、日野家の娘たちは、三代義満の正室を皮切りに、次々と足利将軍に嫁いでいく。
そうした日野家の女に生まれた運命を富子が知ったのは、いくつの頃だったか今では思い出せない。
いずれにせよ、この輿が将軍義政の住む烏丸第に着けば、自らもその系譜を引き継ぐことになる。
富子が生まれ育った伏見の日野家から、足利将軍家の邸宅の烏丸第までは、半日も輿に揺られていれば着く。
上京に入ると、外の喧騒が激しくなった。物売りの声や笛太鼓の音が混ざり合い、賑やかなことこの上ない。
富子は輿窓を少し開け、外の風景を見た。そこには、伏見とは比べようもないほど多くの人が行き来していた。雑踏の中には、郊外から野菜を担いで売りに来る農民の姿もあった。
その中に、年恰好が同じくらいの娘がいた。娘は母親と一緒に野菜を売りに来たらしく、頭上に籠を載せていた。その着ているものは襤褸を継ぎ合わせたようなもので、娘が貧しい生活をしていると察せられた。
娘も行列に気づいたのか、こちらを見た。
富子は視線を合わせたかのような気になり、自らの着る金襴で亀甲模様をあしらった豪奢な絹小袖に目を落とした。
――いかに出自が違うとはいえ、これほどの違いがあってよいのか。
それが「この世」だというのは、十六歳になれば分かってくる。だが多くの民が食うや食わずで苦しんでいるにもかかわらず、位の高い武家や一部の公家は当たり前のように豊かさを享受している。
娘は野菜を売ることを忘れたかのようにぼんやりと佇み、富子の乗る輿を見ていた。その表情から、「どんな貴人が乗っているのだろう」と想像しているのが分かる。
――あの子は幸せになれるのかしら。
ふと、そんなことを思った。
その時、「ニャン」という鳴き声が聞こえた。愛猫の小藤次だ。
「もうすぐだから、大人しくしていてね」
小藤次は「どこに行くの」と問わんばかりに、つぶらな瞳を富子に向けていた。
それでも先ほどの娘のことが気になり、再び外を見たが、すでに娘の姿は雑踏の中に消えていた。
――どうかお幸せに。
富子は娘の幸せを祈った。
しばらくすると烏丸第らしき敷地に、牛車が入っていった。
康正元年(一四五五)九月二十七日、京の風が冷たくなり始めた頃だった。
「お久しぶりね」
「ご無沙汰いたしておりました」
平伏して待っていた富子に声を掛けたのは、すでに尼となっている大叔母の日野重子だった。
六代将軍義教の側室だった重子は、いまだ四十五歳で、足利将軍家を取り仕切る「影の将軍」と呼ばれる存在になっていたが、病がちと聞いていた。
重子が隠然たる力を持ち得たのは、七代将軍義勝と八代将軍義政を産んだからだ。不幸にして義勝は将軍位に就いてからすぐに亡くなったが、義政は十四歳の文安六年(一四四九)に将軍になってから、今年で六年目の二十歳になる。
重子は「花の御所」こと室町第に住んでいるが、義政は烏丸第を本拠としているので、この日は室町第からやってきていた。
将軍になる少し前、義政は烏丸第から北小路と万里小路が交差する場所に築かれた新築の将軍邸に移ったが、一年も持たずに烏丸第に戻ってきた。幼少の頃から親しんできた人たちに囲まれて暮らしたいというのが、その理由だと聞いたことがある。
「面を上げなさい」
富子がゆっくりと顔を上げる。むろん顔を上げ切らず、上目遣いに上段の間に座す目上の人を見るのが礼法となる。
「私のことを覚えておいでか」
「いえ――」
「そうであろう。最後に会ったのは、そなたがまだ七つか八つの頃だった」
日野家には権門勢家の貴顕がしばしば訪れる。それをいちいち覚えておくのは容易でない。だいいち会ったことがあるにしても、貴顕の顔はまともに見ることが許されないのだ。それでは覚えようがない。
「そなたも輿入れのできる年になったのですね」
「はい。十と六になりました」
「もうそんなになりますか」
重子が遠い目をする。そこには、万感の思いが籠もっているように見える。
「此度の輿入れにお骨折り下さいまして、真にありがとうございました」
義政と富子の婚姻は、富子の同腹兄にあたる日野勝光が重子と折衝して決まった。
「日野家の娘が将軍の正室になるのは、当然のこと。私は筋を通しただけです」
そこには、将軍に輿入れした歴代の娘の中で、唯一側室とされた重子の口惜しさが籠もっていた。
日野家の娘が将軍に嫁いだのは、三代将軍義満に嫁いだ業子に始まる。業子が没した後、義満は継室として業子の姪の康子を娶った。その後、四代義持には康子の妹の栄子が、六代義教には康子の姪の宗子が嫁いだ。ところが宗子も義教の側室たちも、姫君しか産めなかった。
この頃、独裁色を強めていた義教は、側室の三条尹子を寵愛し、正室に格上げする。そのため宗子と尹子の二人が正室となる。しかし義教は宗子を嫌い、遂に離別する。そのため日野家では血統が途絶えることを防ぐべく、「二の矢」として重子との婚儀を進めた。
これまでの日野家との関係から義教もこれを認め、晴れて重子の入輿が実現した。しかし重子は、正室に三条尹子がいるため、側室の座に甘んじなければならなかった。
だが義教と尹子の間に子は生まれず、一方の重子は二人の男子を産んだ。これにより三条家に持っていかれそうになった将軍の血統を、日野家は守ることができた。
だが事は、これで済んだわけではない。
嫡男誕生を祝い、日野邸を訪問した人々に対し、日野家の繁栄を快く思っていなかった義教は怒りを爆発させ、六十余人を厳罰に処した。日野家当主の義資の所領も没収され、さらに義資は何者かによって暗殺される。これが「公方御沙汰(将軍の命令)」であることは公然の秘密であり、日野家は存亡の機に立たされた。
義資の子で勝光と富子の父にあたる重政(政光)も、身の危険を感じて出家せざるを得なかった。
義教は自分の権力が及ぶ範囲で、気に入らない者はすべて弾圧ないしは粛清した。というのも、この頃の幕府の権威は強固で、守護大名たちも命令に服していたので、奉公衆という将軍の直属軍の編制が容易だったからだ。
一方、義教の側室とされた重子は、日野家に対する弾圧にも文句一つ言わず義教と睦み、次男義政を産んだ。そのおかげで嘉吉元年(一四四一)の嘉吉の乱で義教が横死した後、日野家は徐々に家勢を盛り返すことができた。
――大叔母上は日野家にとって大功労者。
そう聞かされてきた富子は、足利家中で絶大な権力を振るう重子に、最初から頭が上がらなかった。
「現将軍家は、側室との間に三人の子をなしていますが、すべて姫君です。そなたの使命は、何としても将軍家の男子を産むことです」
男子を産まねばならないことは、富子も重々承知している。だがこればかりは、どうにもならないことだ。
「そなたはなぜ、私だけが男子を産めたかご存じか」
「いいえ、知りません」
また何かを食べてはいけないとか、どこどこの寺社にお百度参りしろといった類の「産み分け法」を聞かされると思い、富子はうんざりした。
「それは、さほど難しいことではありません。男子がほしいと、ひたすら念じるのです」
「えっ、それだけで男子が授かれるのですか」
食べ物や信心の話ではなかったものの、重子の「産み分け法」も根拠に乏しいものだった。
「そうです。私はひたすらそれだけを念じました。結句、二人の男子を授かりました」
重子が胸を張る。
「貴重なお話、ありがとうございます。私もそういたします」
「むろん何事も、将軍家のお心を取ってのものです。わが姉は――」
姉とは、六代将軍義教に離別させられた宗子のことだ。
「誰もが羨むほどの美しい女性でした。しかし気が強く、可愛らしさがなかった。それゆえ普広院様(義教の戒名)のお心を取れなかった。あれほど美しかった姉上が離別されるなど、日野家の誰もが考えませんでした」
「はあ――」
富子には、何とも答えようがない。
――しかし、宗子様が離別されたお陰で、大叔母上はここにいる。
人の運命とは奇妙なものだ。義教と宗子の仲が睦まじくとはいかないまでも、常の夫婦と同じくらいならば、重子はどこかの貧乏公家にでも嫁がされ、愚痴をこぼしながら生涯を終えたに違いない。そうなれば義教は男子に恵まれず、後継将軍が誰になったかは分からない。
「あなたは男子を産むと同時に、将軍家の御台所として家中を守っていくのです」
「はい。心得ております」
それは輿入れが決まった時から、教育係の者たちによって徹底的に教え込まれていた。
「たとえ外でいかなる嵐が吹き荒れていようと、そなたは家中の平穏無事だけを考えるのです」
「それほど家中の統率は難しいのですね」
「そうです。私とて――」
重子の眉間に皺が寄る。
「家中をまとめ上げられているとは言えません」
「大叔母上が――」
「そうです。家中には三人の魔がいるからです」
「三人の魔――」
日野家にいるうちから、様々な噂を聞いていた富子だったが、三人の魔というのは初耳だった。
「その三魔とは誰のことですか」
「おい魔、からす魔、あり魔の三人です」
重子が声をひそめる。
「この中の有馬上総介は、父の兵部少輔持家と共に幕府(当時の呼び名は柳営)の政治を壟断していましたが、今は失脚したので気にすることはありません」
有馬上総介元家は昨年、赤松則尚が反乱を起こした折、裏で支援した疑いで失脚し、今は出家遁世していた。とはいうものの、勢力挽回の機会を虎視眈々とうかがっているのは言うまでもない。
「そなたは烏丸宰相をご存じか」
富子が首を左右に振る。
「そうか。では教えてあげよう」
義政は幼少の頃から、日野家の同族の烏丸家で育てられた。烏丸資任の父の豊光が乳父とされたからだ。そのため二十歳年上で、今年三十九歳になる烏丸宰相こと資任を兄のように慕っていた。義政の住む烏丸第も本を正せば資任の家だったが、義政が戻ってきたので、今は近くに別の邸を構えていた。
ちなみに宰相とは、資任が就いている官職である参議の唐名になる。
「そして最も恐ろしき相手が第三の魔の――」
そこまで話した時、障子を隔てて声がした。
「尼御前様、ご無礼仕ります」
その声を聞いた時、重子の顔色が変わったのを富子は見逃さなかった。
「宰相様が、ご挨拶に参っております」
「何と――」
重子の唇が震える。
「富子は政所執事の伊勢兵庫助(貞親)とも挨拶しておりません。物事には順序があるはず」
「仰せの通りではございますが、宰相様がお話ししたいのは、御婚の儀の段取りなどについてです」
これまで幕政は伊勢貞国が牛耳っていたが、一年以上前に病死し、今は息子の貞親の代になっていた。いわば貞親が幕府の表の顔であり、烏丸資任が裏の顔、すなわち足利家の家政を取り仕切っていた。家政とは幕府とは切り離された足利家の財務や人事のことで、その経路から義政に意を通じることもできるので厄介だった。
「分かりました。では、別の間に控えさせておくように」
「はい。すでに『桜の間』に控えております」
「それで、お今――」
――大叔母上は、お今と言ったのか。
富子がわが耳を疑う。
「そなたは、富子に会ったことがおありか」
「はい。日野家に使いした折、何回かご尊顔を拝し奉っております」
「そうか。では、とくに顔合わせも要らぬな」
「とはいうものの奥のこともありますので、宰相様がご挨拶した後、私もご挨拶させていただきます」
重子が富子を見つめる。
――三魔のうちの二人と会うのか。
気後れしそうになるのを堪え、障子に向かって半身になった富子が言った。
「お今とやら、後ほどな」
「はっ、はい」
悠然とした富子の物言いに、お今こと今参局は戸惑ったようだ。
「では、これにて」
今参局が、衣擦れの音も派手に去っていく。それが、今参局の狷介な性格を表しているかのように感じられた。
重子を見ると、笑みを浮かべてうなずいている。
「そなたなら、この家を切り回していけそうです」
「お言葉、ありがとうございます」
富子も笑みを浮かべて頭を垂れた。
(このつづきは「小説 野性時代」2019年6月号でお楽しみください)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。