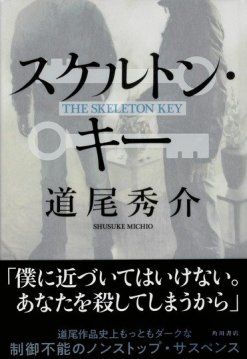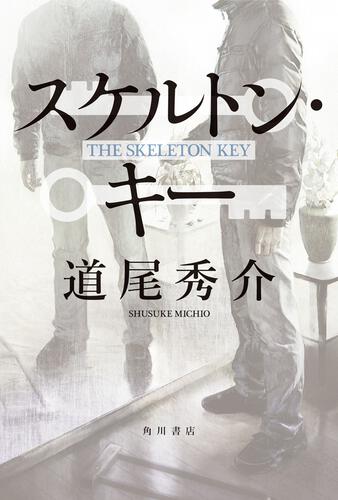直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
>>前話を読む
児童養護施設・青光園にいた僕は、園長から初めて自分の生い立ちのことを知らされる。それは、母の不在の真相で――。
◆ ◆ ◆
(四)
うどんとの待ち合わせは六時に大宮駅だった。
新宿からだとバイクで三十分もあれば着くので、待ち合わせの前に大宮駅の近くで新しい上着を買うつもりだった。会うのは、うどんが僕より一年先に青光園を出て以来なので、二年九ヶ月ぶりだ。袖の破れたダウンジャケットで登場するわけにはいかない。
暮れかけた路地を歩きながら、バイクを停めてきた場所へ向かう。さっきの喫茶店で間戸村さんと会うときは、必ずそこに停めている。新宿御苑の近く、歩道が広くなったところにイチョウの木が一本とベンチが二つ並んでいて、そのイチョウとベンチを囲い込むように、いつも自転車やバイクがやたらと置かれている場所だった。まるでそこだけ警察の目から見えていないように、常に停め放題の状態で──。
「……何してるの?」
茶色い髪を噴水みたいなかたちに固めた男に、僕は声をかけた。
出勤前のホストだろうか。ノーネクタイの白シャツに黒いスーツ。どうして声をかけたかというと、彼が僕のバイクを蹴飛ばしていたからだ。一回でなく二回。二回目のキックで、僕のヤマハWR250Rは植え込みのほうへ倒れ、左のハンドルの先端が、イチョウの幹に縦線を引いて食い込んでいた。
男はまず目だけをこちらに向け、僕の風貌を確認すると、今度は全身で向き直った。僕よりも二十センチくらい背が高い。表情はわざとのように不機嫌そうで、目つきは攻撃的で、口は半びらき。口のかたちをそのままに、男は「あ?」と、ひどく頭の悪そうな声を発した。店のおつかいで買い物にでも出てきたのか、お酒のボトルが二本入ったレジ袋を提げている。茶色い瓶なので、ウィスキーかブランデーだろうけど、僕にはよくわからない。
「それ、僕のバイクだよ」
「んだてめ」
「たぶん傷ついたから、弁償して」
男は上瞼を引き上げるようにして両目を広げ、下顎を突き出して「おぁ」と呼びかけながら僕に近づいてきた。
「場所考えて停めろぁ」
「何で僕のバイクを蹴ってたの?」
「おめえのバイクが俺の袋にぶつかったんだよ」
よく見ると、たしかに男が持っているレジ袋には横に短く破れた傷がある。
「その袋が僕のバイクにぶつかったんだよね」
「んだてめ」
さっきと同じことを言いながら、男は僕の胸に手を伸ばしてダウンジャケットの生地を摑み、それを巻き込みながら拳を裏返して引き寄せた。引き寄せられながら僕はスマートフォンを出して時刻を確認した。いまここで少しくらい時間を使っても、まだ大宮で上着を買う余裕はありそうだ。脇に目をやると、古くて小さなビルが建っている。両びらきのガラスドアの向こうは薄暗くてよく見えない。でも、そこに人がいないことだけはわかった。管理人室のようなものもなさそうだ。僕は胸もとを摑む男の手が緩むのを待った。ほんの五秒ほどで、それは緩んだので、男がぶら下げているレジ袋から茶色い瓶を一本抜き出し、そのままビルのほうへ移動してガラスドアの中に入った。そんな動きをまったく予想していなかったようで、男は一瞬遅れて、何か喚きながら追いかけてきた。男がビルのガラスドアを開けて入ってくるのと同時に、僕は右手に握った瓶を振り抜いた。男の顔面が横向きに吹き飛び、全身がぐるんと回転して床でねじれ、そのまま動かなくなった。いや痙攣しはじめた。機械の歯車が一ヶ所ずれているように、がくがくと全身が震え、咽喉の奥から壊れた笛のような音が断続的に洩れて狭いエントランスに反響した。やがて男は手足の感覚を少し取り戻したらしく、自分の顔面を両手で摑みながら、むやみに足をばたつかせはじめた。目だけはぐるんと僕に向けられて、そこにみるみる細かい血管が浮き出していく。フローリングの上でチワワが走ろうとしているように、革靴は床のコンクリートをこするばかりで、口の中からは血がどんどんあふれ、顔を覆った指のあいだからこぼれて床を濡らす。──と、無意味に暴れていた足がやっと床を捉え、男は急に跳ね起きた。壁際に設置された郵便受けに顔面を激突させたあと、関節が蝶番でできているように、そのままぎくしゃくと壁のそばで変な動きをつづけ、またずるずると床に沈み込む。灰色の壁に、縦の血の跡が残る。僕が手のひらを上に向けて差し出すと、男は顔を覆った指のあいだから、闘牛みたいに瞼がめくれあがった両目を覘かせて僕を見た。
「バイクの修理代」
吐息に合わせ、はい、はい、はい、はい、とかすれた声が洩れてくる。
「三万円くらいでいいよ」
男が動かなかったので、僕は右足を持ち上げて力いっぱい振り下ろした。男の片手が顔から引き剝がされ、ブーツと床のあいだでつぶれた。男の咽喉から初めて絶叫が飛び出した。長い絶叫だった。口だけでなく目も叫んでいた。
「急いでるから早くして。もしお金が足りなかったら、あるだけでもいいし」
男はつぶれていないほうの手をお尻に回し、ポケットにささっていた長財布を、そこに喰らいついた獰猛な生き物みたいに勢いよく摑んだ。ぶるぶる震える手で、財布を僕のほうへ差し出す。中を見てみると、二万三千円しか入っていなかった。僕はそれを自分の財布に移し、持っていた酒瓶を男のレジ袋に戻した。
ビルを出て、倒れたバイクを起こす。曲がってしまったミラーの角度を直し、シートにまたがってイグニッションキーを挿す。時間を確認すると、二分しか経っていなかったので、うどんとの待ち合わせの前に、新しい上着を買う余裕はまだ充分にあった。でも大宮駅周辺の店はよく知らないので、なるべく急いだほうがいいだろう。僕はバイクのエンジンをかけ、車道を走る車のあいだに滑り込んだ。
うどんから連絡があったのは、ゆうべのことだ。
そのときちょうど僕は、チキンラーメンに生卵とお湯を入れ、スマートフォンで三分のタイマーをセットしたところだった。そのスマートフォンが鳴り、間戸村さんかなと思ったら、ディスプレイに表示されていたのは《うどん》だった。青光園を出るとき、バイク便の仕事で必要になるのでスマートフォンを買い、以前にうどんから聞いていた電話番号もそのとき登録してあったのだけど、電話が来たのは初めてだった。
──錠也か?
──うん、久しぶり。
これまで連絡せずにいたことを、まずうどんは謝った。
──とにかく忙しくてな。
うどんは僕より一年先に青光園を出たあと、磯垣園長が斡旋した中古車販売のチェーン店「カー・ドンキー」で営業の仕事に就いた。いまもやっているのかと訊くと、やっているという。
──俺けっこう成績よくて、月によっては店舗で一番になることもあるんだ。
──うどん、そういうの向いてたんだね。
──どうかな。運もあるだろうし。
三分のタイマーが終了し、耳元でスマートフォンが鳴った。僕はタイマーを止め、電話機を肩と耳で挟みながらチキンラーメンの麵を箸でほぐした。電話しながら食べようと思ったのだけど、けっきょくそのチキンラーメンは、うどんとの電話が終わってから食べることになった。それほど長い電話ではなかったので、麵も大してぶよぶよになってはいなかったが、味がほとんどしなかった。電話の内容が気になって仕方がなかったからだ。
──錠也は、いまは一人暮らしか?
──そう。そっちは?
──園を出てすぐ引っ越したとこに、そのまま住んでる。
──やっぱり一人で?
うどんは短く黙ったあと、父親といっしょに暮らしていると答えた。僕は麵をほぐす箸を止めた。
──出てきたんだ?
──出てきた。それで、いまアパートで二人暮らししてる。ちょうど二週間。はじめは池袋のラブホテル街で、寝泊まりしてたらしいんだけど。
──お父さん?
──うん、一人で。ああいうとこ、昼間はすごい安い値段で使えるらしいんだ。池袋に、とくに安いとこがあったみたいで、お父さん、そこで昼間に寝て、夜は外でうろうろして、しばらくそんなふうにしてたんだけど、お金がなくなってスーパーで万引きして、警察に捕まって。
警察が親戚に連絡し、その親戚がうどんの電話番号を教え、うどんはスーパーまで父親を引き取りに行き、それからいっしょに暮らしているのだという。
──電話したのは、そのお父さんのことでな。
と言われても、まったく見当がつかなかった。
──どんなこと?
しかし、うどんは答えなかった。
──直接会って、話したい。
というわけで、今日の六時に大宮駅の東口で待ち合わせることになった。
大宮は、うどんが就職した中古車販売店がある街だった。
(五)
埼玉方面の道は思ったよりも混んでいた。
僕は信号待ちでいったんバイクを降り、後ろに回ってナンバープレートを折り上げた。プレートはかちかちと音を立てながら収納され、すっかり見えなくなった。商品名は忘れてしまったけれど、インターネットで四千四百円を払って買ったキットで、簡単にナンバーを隠せるので便利だった。間戸村さんから引き受けた仕事をこなすときも、必ずこうして折りたたむようにしている。
信号を無視して大通りを飛ばしながら、僕は青光園での生活を思い出していた。
忘れがたい最初の記憶は、初めてヒーローになった、五歳のときの出来事だ。青光園の職員に、キリカワという男の先生がいた。熱血という言葉から想像する人物像に、あとから自分を嵌め込んだような、わざとらしい厳しさを発揮する人だった。煙草くさい息を吐きかけながら、キリカワ先生はいつも僕たちを怒鳴り、僕たちを叩き、叩いた手のほうが痛いなどと意味不明のことを言いながら涙ぐみ、最後にはいつも自分だけ爽快な顔つきになって笑った。
キリカワ先生は誰も見ていないところで僕たちを怒鳴ったり叩いたりしたから、僕たちがそんなふうに扱われていることに、磯垣園長もほかの先生たちも気づいていなかった。あるとき中学生の何人かが、キリカワ先生のことを園長先生に言いつけようと相談をまとめ、ほかのみんなも同意したけれど、実行する前に高校生たちに止められた。いまよりもひどいことをされる可能性があるというのが理由だった。あきらめることには誰もが慣れていたので、けっきょくその意見に頷いた。そうして毎日キリカワ先生を怖がりながら、みんな濡れた埃みたいなものを胸の底にびちょびちょため込んでいた。みんなというのは僕以外のことだ。
僕は、その濡れた埃みたいなものが、青光園で暮らす子供たちの喉元いっぱいまで詰め込まれるのを待っていた。キリカワ先生に仕返しをするタイミングは、そのときが一番いいだろうと思ったからだ。
そのタイミングは、ある夏の昼にやってきた。
僕よりも一歳上の、六歳の男の子がいた。後に運良く里親にもらわれていったので、名前は憶えていない。くるくるパーマで、肌が紙みたいに白くて、すごく瘦せた男の子だった。あの日の午後、その子が投げたフリスビーが、駐車場に停めてあったキリカワ先生の車にぶつかった。白い跡が残った。それをたまたまキリカワ先生が見ていた。先生は男の子を園舎の脇に連れて行き、ものを大切にする気持ちを教えたあと、頭を強くはたいた。頭は勢いよく横倒しになったけれど、男の子は細い両足を踏ん張って、動かなかった。そして、しばらく頭をぐらぐらさせていたかと思うと、まだ少し傾いだ位置で、ぴたっと静止させた。両目がキリカワ先生を睨んでいた。強い目だった。心配して覗きに来た何人かの子供たちがそれを見ていて、僕も少し離れた場所から二人を眺めていた。
睨みつける男の子に、キリカワ先生が低い声で何か言った。男の子は言葉を返さず、刺すような、ぜんぶの思いを込めた目で、キリカワ先生を睨みつづけた。声は発しなかったけれど、それは怖いからではなく、たくさんの言葉がいっぺんにこみ上げて、咽喉に詰まっているからだとわかった。キリカワ先生はまた何か言いながら片手を持ち上げて、男の子の肩に置いた。右利きなのに左手を置いていたし、そのあとキリカワ先生が少し膝を曲げたので、つぎに何が起きるかがわかった。予想は当たり、キリカワ先生は右手を握って男の子の腹に打ち込んだ。男の子の身体がくの字になり、にごった息のかたまりが口から飛び出した。両足の膝から下が消えたみたいに、身体ががくんと下へ移動し、つぎの瞬間、男の子はびゅっとげろを吐いた。
げろを片付けろと、キリカワ先生は男の子に言った。もう少しくらい抵抗するかと思ったけれど、そうはならなかった。げろといっしょに気持ちも出ていってしまったように、男の子は言いつけに従った。たぶんぞうきんを取りに行こうとしたのだろう、ふらふらと園舎のほうに歩きかけ、しかしキリカワ先生が、自分の手でやれと命じた。
男の子が両手で自分のげろを地面から少しずつすくい、園舎の脇にある水道まで運んで流し、また戻ってきてすくうのを、みんなで眺めていた。そうしながら僕は、その夜が、夏に恒例の「花火ナイト」だったことを思い出し、ずっと待っていたタイミングがようやく来たと思った。
〈第4回へつづく〉
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/