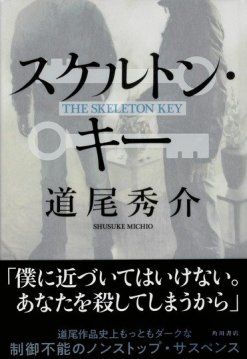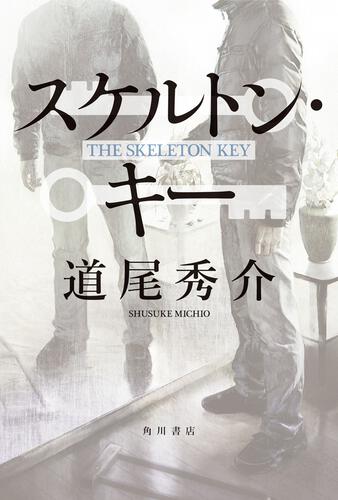直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
>>前話を読む
週刊誌記者のスクープ獲得の手伝いをしている僕こと坂木錠也は、この仕事をすることでなんとか“まとも”でいられた。
◆ ◆ ◆
(三)
自分の生い立ちを初めて知ったのは去年の春、青光園を出る直前のことだ。
それまで実際のところ、僕は自分の生い立ちに興味を持ったことさえなかった。どうせほかの子供と同じように親の暴力や育児放棄で引き離されたか、金銭的な理由で捨てられたのだろうと、敢えて興味を向けずにいた。だから、磯垣園長に駐輪場で話しかけられたとき、僕が知っていたのは、母の名前が坂木逸美であるということくらいだった。
日が沈む、少し前。青光園の駐輪場で、僕がバイクのシートの破れ目を黒いガムテープでふさいでいると、背後から磯垣園長の声がした。
──面接、受かったんだってな。
振り返ったとき、園長先生は夕日を背負っていたせいで、顔が真っ暗だった。四角く尖った髪のかたちと、凸凹した耳と、その耳の上にある眼鏡の蔓のシルエットばかりがはっきりと見えた。
──お前に向いてる職場かもしれないけど……事故には気をつけろよ。危ない仕事だっていう話は、よく聞くから。
その日、以前に面接を受けていた都内のバイク便から採用の連絡があったのだ。それまでの三年間、僕は園長先生が紹介してくれた林業土木の会社でアルバイトをして高校の学費を稼いでいた。学費は年間四十万円ほどで、それを払いつつ現金も貯め、高校二年生のときにバイクの免許を取った。三年生になるとヤマハWR250Rを中古で買った。オンロード車に匹敵するスピードが出せるオフロード車だ。売値が異様に安かったので、たぶん事故車なのだろうけど、見た目は綺麗だったし、故障もこれまで二度くらいしかしていない。
──気をつけます。
僕が言葉を返したあと、園長先生は黙ったまま、その場を動かなかった。僕はバイクに向き直ってシートにガムテープを貼った。貼りながら考えた。園長先生は僕に何かを話しに来たらしい。それはきっと、自分の感傷を押しつける類のものだろう。青光園の中で、僕はずっと特別な子供だった。先生たちはみんな、僕がようやく園を出ることになって安心している。その安心を、懐かしさのようなものにすり替えて、僕に押しつけに来たに違いない。
という予想は、しかし外れた。
──先生も児童養護施設で育ったっていう話は、したことがあるよな。
用意していた言葉を口にする調子で、園長先生は切り出した。
あれは小学二年生の冬だったか、食堂で鍋パーティをやっているときに聞いたことがあった。園長先生も僕たちと同じように児童養護施設で子供時代を過ごしたらしい。茨城県にあるその施設で、先生は小学生から高校生までを過ごした。その暮らしの中で、いつか自分も同じような施設をひらくことを夢見るようになった。そしてその夢を大人になって実現させ、青光園をつくったのだという。園長先生が青光園をひらいたとき、最初に引き取った子供が、乳児院にいた二歳の僕だった。
──先生が育った、茨城県のその施設に──。
短く言いよどんだあと、いきなり話が意外な方向に進んだ。
──お前のお母さんもいたんだ。
僕はガムテープをシートに置き、立ち上がって園長先生に身体を向けた。僕は小柄だから、立ち上がってもまだ相手の顔を見上げる恰好だった。先生が背負っていた夕日も、相変わらず相手の顔の向こうにあった。だから僕は、自分自身の生い立ちに思いを向けるとき、磯垣園長の四角ばった顔のシルエットを必ずいっしょに思い出す。
──お前のお母さんも、同じ施設で育った。
母も児童養護施設で育ったという事実自体は、別段驚くべきことではなかった。シセツの子の親にシセツの出が多いというのは、僕たちのあいだではごく一般的な常識だ。不利が不利を呼び、あきらめがあきらめを呼ぶ袋小路の中にいることを、僕たちは知っている。それよりも、母と幼馴染だったことを、どうして園長先生はいままで黙っていたのか。
──お前が……錠也が、事実を受け入れられる歳になるのを、待とうと思ってな。
そう答えられても、まだよくわからなかった。
──いまから言うことは、誰にも話したことがない。戸越先生でさえ知らない。
戸越先生というのは、青光園が一番最初に雇った職員で、僕が園を出たときは五十代半ばだった。
──これは、お前にとってはとても哀しい話かもしれない。でも、いずれはきっと知ることになる。どんなかたちで知るとしても、先生の口から先に話しておいたほうがいいと思ってな。
そんな前置きをしてから、ようやく園長先生は話をはじめた。
親の事情で、園長先生は小学五年生のとき、その児童養護施設に預けられた。僕の母が入園してきたのは、そのすぐあとのことだったという。
──当時、お前のお母さんは四歳で、みんな、いっちゃん、いっちゃんって呼んで、可愛がっていた。
母が施設に入れられたのは、母の両親、つまり僕の祖父母が、螺子工場の経営に失敗して無一文になったのが理由だったという。母が預けられたすぐあと、祖父母の乗った軽トラックが茨城県の鹿島港に沈んでいるのが見つかった。夫婦仲良く自殺したらしい。
──先生はその話を、いっちゃんから聞いたんだ。お父さんとお母さんの葬式で、遠縁の人が話してるのを耳にして、自分で理解したみたいでな。
かしこい子だったから、と園長先生が言ったとき、その口調から僕は、母はもう生きていないのかもしれないと思った。
その予想は結果的に当たっていたけれど、死にかたに関しては予想外だった。
──先生は、十八歳になるとその児童養護施設を出た。昼間は建設会社で働きながら、将来、児童養護施設をひらくための資金をつくって、夜は勉強をつづけた。でも、ときどき施設に電話をかけたり、遊びに行ったりして、お前のお母さんとは仲良くしていたんだ。
母は里親を希望していたのだが、恵まれず、園長先生と同じく十八歳までその施設にいた。その後、職員のつてで、埼玉県の観光地にある割烹料理店で仲居として働きはじめた。
──その頃から、お前のお母さんと連絡を取り合うことがあまりなくなったんだが、ここを、この青光園をつくるための準備がようやく整ったとき、久しぶりに連絡を取ろうと思ったんだ。自分と同じように施設に預けられて、そこで育ったいっちゃんに、いろいろと相談もしたくてな。
以前に母から聞いていた割烹料理店に、先生は電話をかけてみた。秋の終わりのことだったという。しかし電話は通じなかった。後日そこへ行ってみると、店はつぶれて雑草の中に放置されていた。近くの飲食店に足を向け、割烹料理店のことを訊ねたところ、つぶれたのは半年も前だという。そこで仲居をやっていた坂木逸美という女性のことも訊いてみたけれど、誰も知らなかった。先生は近くの店を片っ端から回ってみた。
──何軒目かに入った小料理屋に、いっちゃんの居場所を知ってる人がいた。
先生はすぐに、教えられた場所へと向かった。
そこは夜から明け方までやっているパブで、母はお酒をつくったり、客の話し相手になったりして働いていた。店の中は綺麗ではなく、煙草の煙でいっぱいで、母も働きながら煙草を吸い、お酒を飲んでいた。
──酒も煙草も、なんだか、無理にやってるように見えた。
先生が店に入ったときは、ヤクザみたいな、柄の悪い客が何人かいて、母がその店で使っていた名前を呼び捨てにしながら、母に煙草の箱とライターを放ったり、母のグラスに勝手にウィスキーを入れたりしていたのだという。
やがてその客が帰ったので、先生は母と話をすることができた。
──店のすぐそばにある、安アパートで暮らしていると言っていた。そのアパートの大家さんが、パブのオーナーだったらしい。
以前に働いていた割烹料理店がつぶれたとき、母は住んでいたアパートの家賃を払うことができなくなり、新しい働き口を探した。しかしなかなか見つからず、最終的に受け入れてもらえたのが、その店だった。オーナーが所有するアパートで暮らすのが、従業員として使ってもらうための条件で、そのかわり保証人なしで入居することができたのだという。
──働きはじめて三ヶ月だと言っていたけれど、あの店の環境は、とてもじゃないがいいとは言えなかった。いっちゃんには、そんな場所で働いていてほしくなかった。でも、先生には口を出す権利なんてないから、何も言えなくてな。
しかし。
──帰り際、いっちゃんが店の外まで送りに出てくれたとき──。
お腹に子供がいることを打ち明けられた。
──五ヶ月だって言うんだ。ゆったりしたブラウスを着てたから、先生、まったく気づかなかった。
それを聞くと、先生はさすがに黙っていられなかった。お腹に赤ちゃんがいるのなら、お酒も煙草も絶対に駄目だと叱った。しかし母は、断ると怒り出す客が多いから、やめるのは無理だと言う。それに加え、お酒に関しては、自分のグラスに注がれたぶんは自分の売り上げにもなり、出産と子育てのためのお金をつくらなければいけないから、仕方がないのだと。
先生は子供の父親のことを訊いた。
──でも、いっちゃんは教えてくれなかった。
そう言ったとき、園長先生の後ろで、青光園の屋根に夕日が沈んだ。夕日は屋根の向こうに隠れる直前、わっと赤く、強く光って、それからすぐに、しぼんで消えた。消えてから、むしろ園長先生の顔つきがよく見えるようになった。薄闇の中で、先生の目は真っ直ぐ僕に向けられていた。真剣というよりも、冷静な目だった。自分が話していることを、相手が疑いなく受け入れているかどうかを確認している目だった。物心ついたときから僕は、人の表情を読むことができた。相手が子供でも大人でも、本当のことを喋っているのかどうか、話を鵜吞みにしたら自分が損をするかどうかを感じることができた。だから僕は、あのとき園長先生の中に何かの噓が含まれていることに気づいていた。
──で、どうなったんですか?
僕が話の先を促したとき、園長先生の目に一瞬だけ、安堵のような表情が浮かんだ。そのことで僕は自分の考えが正しかったことを知った。でも、何も訊かなかった。知ってしまったら損をする予感があったからだ。僕はいつもその予感に従ってきた。
──先生はいっちゃんのために、できるかぎりのことをしたいと思ったし、実際にした。もちろん充分ではなかったけど、できることはぜんぶ。
園長先生は、児童養護施設の開業資金として用意していたお金の一部を、生活費に充ててほしいといって振り込み、母の新しい働き口がないか、住む場所はないかと、あれこれ探し回ったりもした。しかし、上手く見つけることはできなかった。先生自身も、当時働いていた建設会社にもう退職の話をし、いろいろと見切り発車で進めてしまっていたので、金銭的にも精神的にも余裕がなかった。行政から児童養護施設の指定を受けられるかどうかさえわからなかった。
──でも、上手く指定をもらえて、開業までこぎつけることができたら、そのときはいっちゃんを職員として招こうと考えていたんだ。
もし本当にそうなっていたら、母の人生も、僕の人生も、ずいぶん違うものになっていたに違いない。母に関して言えば、そもそも人生の長さ自体が大きく変わっていたことになる。しかし、先生が児童養護施設の開業に奔走しているあいだに、
──事件が起きてしまった。
以前、間戸村さんに頼んで記事を取り寄せてもらった、あの事件だった。
いまから十九年前の十二月夕刻。母が働いていたパブ「フランチェスカ」に、散弾銃を持った三十代後半の男が押し入った。散弾銃は、男の父親が鹿猟に使っていたもので、そのとき店内にいたのは、開店準備のために来ていた母一人だった。男は母に、店の現金を出すよう言った。現金は置いていないと、母は答えた。しかし実際には、店長をつとめる女性が前夜の売り上げ金を家に持ち帰っていなかったので、カウンターの内側の棚に、かなりの額の現金があった。それを嗅ぎ取ったのか、男はカウンターの中に入り込み、そこらじゅうを荒らしはじめた。
母はそれを止めた。
──店のお金というよりも、いっちゃんは、自分自身の生活資金や出産費用のことを考えていたんだと思う。店のお金がなくなってしまったら、自分に支払われるはずの給料もなくなってしまうかもしれないから。
まさか男が何のためらいもなく銃の引き金を引くとは思っていなかったのだろう。
──男が発砲したとき、いっちゃんは咄嗟に身をひるがえして直撃をまぬがれたけど──。
飛び散ったいくつもの散弾が、その身体をえぐった。
銃声を聞きつけ、近所の農家の男性が店を覗いたとき、床に倒れ込んだ母を前に、男はじっと立ち尽くしていた。その男性が一一〇番し、警察官が駆けつけたときも、まだ立ち尽くしていた。
男はすぐに逮捕された。
田子庸平という無職の男で、十代後半に強盗致傷の前科があった。
──いっちゃんは、意識不明の状態で病院に運ばれた。
妊娠八ヶ月の母は散弾の摘出手術を受けた。しかし、斜め後ろから受けた散弾のいくつかが脊髄や腰椎のすぐそばに埋まっていたため、すべてを摘出することができず、数個の散弾を母の身体に残したまま、医師は手術を終えざるを得なかった。手術後、母は一時的に意識を取り戻し、警察や医者や園長先生と会話を交わしたものの、また容態が悪化し、ふたたび意識不明の状態となった。
──すぐに、帝王切開で、お前が取り出された。でもいっちゃんは、そのまま意識を取り戻すことなく病院で死んだ。
それから二年ほどして、園長先生は青光園をひらいた。
──最初に引き取った子供が、乳児院に入れられていたお前だった。
先生の話はそこで終わった。
パブ「フランチェスカ」での事件は、それほど世間の注目を集める出来事ではなかったらしい。間戸村さんが見つけてくれた第一報からしてほんの小さなものだったし、その後に政界や芸能界で大きな出来事がつづいたせいで、続報もほとんどなかった。埼玉県の小さな酒場で起きた出来事は、そうしてすぐに世間から忘れられた。犯人の田子庸平が現在どこで何をしているのかも、わからない。
このままわからないのが、きっと一番いいのだろう。
ひかりさんが教えてくれたおかげで、僕は自分が何者であるかを知っている。もし田子庸平という男の所在を知ってしまったら、きっと僕はそこへ行く。行って、仇を取る。殺された母の仇じゃない。顔も憶えていない母親に、いまも昔も僕は、はっきり言って何の感情も抱いていない。園長先生に教えられた母の人生が、どんなに惨めであっても、母がどんなに可哀想な人だったとしても、それは変わらない。僕が取ろうとするのは自分自身の仇だ。園長先生の話を聞きながら僕が抱いたのは、あったかもしれないもう一つの人生を、この僕から奪い去った男への恨みだ。いまの人生と、どちらがより良かったか、どちらがよりまともだったかなんて関係ない。僕は自分から何かを奪う人間を許さない。
〈第3回へつづく〉
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/