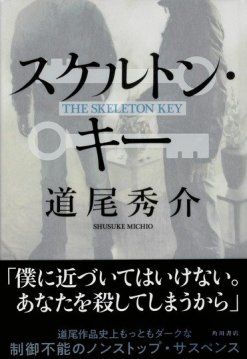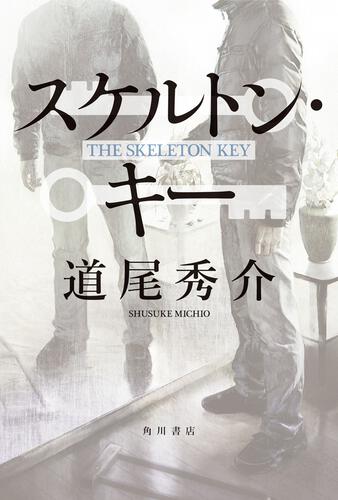直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
◆ ◆ ◆
la clef ferme plus qu'elle n'ouvre. La poignée ouvre plus qu'elle ne ferme.
(分類するならば、鍵は、開くよりも閉じるものだ。把手は、閉じるよりも開くものだ。)
──ガストン・バシュラール『空間の詩学』
You can straighten a worm, but the crook is in him and only waiting.
(芋虫を真っ直ぐに伸ばすことはできるが、その湾曲は身体の中で、ただ待っている。)
──マーク・トウェインの言葉
一章
(一)
追っているクーペは二台前を走っていた。
行く手の信号が黄色に変わるが、クーペはそのまま交差点に入っていく。しかしその後ろ、僕のバイクとのあいだを走るタクシーがブレーキランプを点灯させた。アクセルをひらきながらバイクを素早く左へ倒す。深夜の街灯が一直線につながってヘルメットの向こうを流れる。タクシーの左脇をすり抜けて交差点に突っ込んだ瞬間、右前方から軽トラックのヘッドライトが急速に迫ってきた。対向車線で右折待ちをしていた車が発進していたらしい。右によけるか左によけるか──左によけた場合、相手がよほど急ブレーキをかけてくれないかぎり衝突してしまうので、全身でバイクを押し込むようにして右へ倒した。しかしその瞬間、軽トラックがタイヤを鳴らして急ブレーキをかけた。どうやら左によけるのが正解だったらしい。交差点の真ん中で停車した軽トラックの車体が眼前に迫ってくる。このままだと確実にぶつかる。バイクをさらに下へ押し込み──もっと押し込み──スピンする直前に勢いよく車体を立て直す。ダウンジャケットの左袖が軽トラックの荷台をこすり、千切れた生地の内側から白い羽毛が飛び散る。しかしバイクも身体もぎりぎりで接触を逃れ、軽トラックと後続車のあいだにある一メートルほどの隙間を無傷で突き抜けた。
もとの車線に戻り、クーペの尾行を再開する。
しばらく走っていると、道の左右から飲食店の明かりが消え、かわりに工場らしい四角い建物やマンションなどが増えてきた。
クーペが左折して路地に入る。
バイクのヘッドライトを消してそのあとにつづく。
政田が運転するクーペは住宅街の角を二度曲がってから、コインパーキングの看板のそばで減速した。僕は一つ手前の角を左へ入り、民家のブロック塀にバイクを寄せてエンジンを切った。デニムのポケットからスマートフォンを取り出す。誕生日のパスコードを打ち込んでカメラを起動させながら路地の角まで戻る。カメラの露出を目一杯まで上げた状態で、路地にスマートフォンだけを突き出してディスプレイを確認する。暗がりでは、肉眼よりもこのほうがよく見える。クーペはコインパーキングに停まっている。しかし政田はまだ車内にいる。顔が下から白く照らされているのは、携帯を操作しているのだろうか。スマートフォンのシャッターボタンを押し、僕はその様子を撮影した。
政田が車を降りる。
周囲を気にしながら、こちらに背を向けて歩き出す。
僕は足音を立てずにそれを追う。
政田が入っていったのは、それほど高級そうでもないマンションのエントランスだった。細長い身体を曲げてインターフォンでルームナンバーを押し、応答した相手と短く言葉を交わす。奥の自動ドアがひらく。政田はそこを抜け、エレベーターホールへと去っていく。僕はその様子をすべて写真におさめる。
政田の姿が消えたあと、ダウンジャケットの左袖を見てみると、軽トラックの荷台にこすった部分は十センチくらい破れていた。
撮った写真を間戸村さんにメッセージアプリで送信し、ついでに書き添えた。
《尾行中に上着が破れたので請求させてもらいます》
すぐに間戸村さんからの着信があったので応答した。
「坂木です」
『さすが錠也くん!』
大声が鼓膜に突き刺さり、僕はスマートフォンを耳から離した。
『これ、すごいよ! マンションのエントランスのやつなんか、政田の顔が完璧に写ってるし最高だよ!』
政田宏明は芸歴二十年以上の大御所俳優だ。事前に間戸村さんから教えられたところによると、年下の奥さんは現在妊娠中。近ごろ政田は、現場仕事が終わると、運転手兼マネージャーを先に帰らせ、自宅のある杉並区とは別方面に車を走らせるようになった。その情報を週刊誌記者である間戸村さんが摑んだ。何かあるに違いないと感じ、間戸村さんは二度ほど政田のあとを尾けようとしたのだが、いずれの場合もまかれてしまい、いつものように僕のところへ依頼が来たというわけだ。
『これどこ? いますぐ行くから場所教えて』
「いったん切って現在地を送ります」
地図アプリで現在地を確認し、そのURLを送ると、すぐにまた着信があった。
『会社からタクシー乗って三十分くらいで着く。あ、上着っていくら?』
「二万六千円です」
四千二百円だった。
『うっわ錠也くん、いいの着てるじゃん。俺、十九歳のときなんて五千円くらいの安物ばっか着てたよ。よし、いまタクシー乗ったからね』
運転手に行き先を指示する声。
「間戸村さん、僕、もう帰っていいですか」
『え、急いでんの?』
「いえ、でもどうせ三十分以内には政田も出てこないだろうし」
『ううん、もしかしたら出てくるかもしれないから、俺が行くまでいてくれないかな』
「でも間戸村さん前に、退屈なことはしなくていいって」
『まあ……そうか、うんわかった』
二日後にいつもの場所でお金を受け取る約束をし、電話を切った。
スマートフォンをデニムのポケットに戻すと、キーが指に触れた。バイクのキーでもアパートのキーでもない。それらといっしょにリングに通してある、小指ほどの長さの、古い銅製のキー。円柱の軸の先に、単純な形状の凸凹の歯がついている。何を開けるためのものなのかは知らない。オモチャみたいに安っぽいから、べつに何を開けるものでもないのかもしれない。わかっているのは、これが乳児院に預けられた僕の唯一の持ち物だったということだけだ。赤ん坊の僕は、このキーとともに乳児院に預けられ、二歳になると、埼玉県にある児童養護施設「青光園」に移された。もちろんその頃の記憶はなく、気がついたときには、僕は青光園で、このキーをいつもポケットに入れ、同年代から高校生まで二十人くらいの子供たちとともに暮らしていた。
右手をダウンジャケットの襟ぐりから差し入れ、シャツごしに左胸に押しつけてみる。心臓は相変わらずゆっくりと鼓動している。どんなに危険なことをしても、この心臓は鼓動を速めてくれない。持ち主が置かれている状況に興味さえ持っていないように、いつもこうして淡々と、低い心拍を刻みつづける。
これは、僕みたいな人間が持つ特徴の一つらしい。
──錠也くんが何なのか、わたし知ってる。
僕が何者であるかを教えてくれたのは、大好きなひかりさんだった。
──錠也くんみたいな人はね。
青光園の園庭にあった、暗い遊具倉庫の中で、彼女はその呼びかたを教えてくれた。
──サイコパスっていうのよ。
(二)
「錠也くんもコーヒーでいい?」
「はい」
「じゃ、コーヒー二つお願い」
「ホットでよろし」
よろしいですと間戸村さんはウェイトレスの言葉を遮った。それに対する仕返しのつもりなのだろう、彼女は作り笑いであることを強調した笑顔を返してテーブルを離れていく。
「可愛いねえ、にこにこしてて」
冗談でもなさそうに言いながら、間戸村さんは電子煙草のスイッチを入れた。三ヶ月くらい前に本物の煙草から切り替えたのだが、ひと口吸うたび、いつもすごく不味そうな顔をする。どうして不味いのに吸うのかは、訊いたことがないのでわからない。
「あ、そういえば破れたってどこよ?」
僕はダウンジャケットの左袖を見せた。
「うわそれ、どんなふうにして破れたの?」
バイクで政田宏明を追いかけたときの様子を説明すると、間戸村さんは僕の目と口許に視線を細かく往復させながら聞き入った。話が終わると、電子煙草のことを思い出してニコチン入りの水蒸気を吸った。不味そうな顔をするかと思ったら、しなかった。
「……相変わらずすげえな錠也くん」
僕をもっとよく見ようというように、上体を引き、ゆっくりと視線を縦に動かす。
「よし、じゃ、まずこれ上着代ね」
差し出された封筒には二万六千円が入っていた。僕は中身だけ財布に移し、封筒はいらないので返した。間戸村さんはそれを受け取りながら、僕の「二万六千円」するダウンジャケットをもう一度見て、二秒くらい表情を止めたが、何も言わなかった。
「そんで、ギャラなんだけど、上乗せさせてもらうことにしたから」
「でかかったんですか?」
間戸村さんはぐっと顎を引き、両目をみはって頷く。
「ばかでかい」
政田が入っていったマンションには、樫井亜弥が住んでいたのだという。
「いや、びびったね」
樫井亜弥は僕でも知っている若手女優だ。一つ前の朝ドラで準主役を演じ、同じく新人だった同年配の主役女優よりも注目を浴びて、いまでは都市銀行から缶チューハイからコンタクトレンズから、いろいろなテレビCMに出ているし、電車の中でも街中でも、彼女が大写しになった広告をよく見かける。間戸村さんによると、来月からはじまるゴールデンタイムのドラマではとうとうヒロインに抜擢されたらしい。
「まあそれも、どうなるかわからなくなってきたんだけどさ。というのも」
「お待たせしました」
コーヒーが来た。
「そこ置いといて。これ、ミルク下げてくれる、邪魔だし」
「ご注文は以上でおそ」
おそろいですと間戸村さんがまた遮ると、今度は作り笑顔を見せつけるのも嫌になったのか、彼女は素早く背中を向けて立ち去った。
「で、樫井亜弥」
勢いをつけるように音を立ててコーヒーをすすってから、間戸村さんは息継ぎの少ない独特の喋り方で説明した。
僕との電話を切ってから三十分ほどで、間戸村さんはあのマンションに到着し、それから二時間ほどすると、政田が一人でエントランスから出てきたらしい。
「それはとりあえずスルーしたのよ、ほら中の女に連絡されちゃうかもしれないから。いや、そんときはまだ女だって確信してたわけじゃないし、そこが樫井亜弥のマンションだってことも知らなかったんだけどさ、あとから誰か女優でも歌手でも売れないアイドルでも何でもいいから出てきてくれって祈ってたの」
そうして朝まで祈っていたところ、
「いや震えたね。眼鏡と帽子で顔隠してたけど、細いし美人だし、やっぱし遠目でも目立ってさ、何秒か経ってから俺、わ、これすげえぞ樫井亜弥だぞって気づいて、突っ込んだわけ、取材したわけ。そんでこういうときのテクニックなんだけど単刀直入に、政田さんとはどういうご関係なんですかって訊いてやったらさ、顔真っ白にして固まっちゃって、もうこれイエスじゃん」
その後、間戸村さんは樫井亜弥にあれこれと訊ね、彼女は顔面蒼白のまま何も答えず、最後には震える声で「事務所を通してください」と呟いたのだという。この彼女の台詞を間戸村さんは、わざわざ物真似で披露した。
「これって要するに、白状だよ、自分はとんでもないことをしちゃいましたって言ってるようなもんだよ。だってこうだぜ」
もう一回真似をしてみせ、それが終わると、間戸村さんは僕に向き直った。相手の反応に対する期待から、両目がどんどん広がっていき、やがて黒目のふちがぜんぶ見えるくらいまで大きくなったが──急にまた細くなった。
「いつもながら、興奮のふの字も見せないね」
「この字ですか」
「そうそう」
間戸村さんは僕より十五歳上の三十四歳だが、不規則な生活のせいか顔に皺が多い。僕ほどではないけれど小柄で、そのくせひどくボリュームのある直毛が、頭からあふれるように伸びているので、もともと大きかった人が縮んだようにも見える。最大手の出版社である総芸社で「週刊総芸」の記者を五年つづけていて、一年ほど前から何度も大きなネタをものにしているスクープゲッターだ。そしてそのスクープのほとんどは、僕が協力して摑んだものだった。
仕事の依頼をされるときは、いつも間戸村さんがICレコーダーを回し、これこれこういう場所で何々の可能性があって、もしそれが確かめられれば金になるんだけどなあ、といった言い方で僕に話す。あとで何か問題が起きたとき、間戸村さんが僕に頼んだわけではなく、あくまで僕が勝手に動いたのだと言い逃れをするための策らしい。未成年を雇って危ない仕事をさせているのだから、そうした備えも必要なのはわかるけれど、そんな録音がじっさい役に立つのかどうかは知らない。たぶん役には立たないだろう。
が、どのみち僕は、たとえ警察にあれこれ訊ねられるようなことがあっても、総芸社や間戸村さんの名前を出すつもりなんてなかった。単純に、自分にとって損だからだ。唯一の収入源であるこの仕事が、なくなってしまっては困る。
「ま、とにかく来週号に載るから楽しみにしてて、巻頭と特集ページでいくから」
間戸村さんから仕事を依頼されるようになったきっかけは、青光園を出ると同時にはじめたバイク便だった。
急ぎの資料や記録メディアの受け渡しなどで、出版社はよくバイク便を使う。間戸村さんも以前から、僕が働いていた「スピード太郎」にしばしば依頼をしていた。何度も配送を頼んでいるうちに、僕が担当したときだけ段違いに早く荷物が届くことに気づき、やがて指名で僕を使うようになった。大雨でも大雪でも、僕は素早く荷物を届けた。給料が歩合制だったし、何より自分がまともでいるために、それが必要だったからだ。あるとき総芸社の集荷所に荷物を取りに行ったら、間戸村さんが声をかけてきた。何でいつもあんなに早く配達できるのかと訊かれ、単に速く走っているのだと僕は答えた。
──でもさ、雨降ってたり雪降ってたりするときとか、怖くない?
怖いという感情を、僕は持ったことがない。
物心ついてからいままで、一度も。
間戸村さんの質問に、具体的に何と答えたのかは憶えていない。でも、あとで聞いたところによると、そのとき間戸村さんはこう思ったらしい。
──やばいなこいつって。
そして考えた。
──仕事を手伝ってもらえたら強力な武器になるなって。
間戸村さんはその場で僕に交渉を持ちかけた。けっこうなお金を払うから、車を尾行したり、どこかへ忍び込んだり、危ないことをやってくれる気はないかという、じつにダイレクトな交渉だった。僕は具体的な金額を訊ね、その答えを聞いて、悪くないと思った。その日の配送が終わったあと、僕はまた総芸社の受け付け前まで行き、間戸村さんに教えてもらっていた携帯番号にかけた。間戸村さんはすぐにエレベーターで降りてきて、僕を近くの喫茶店に連れていった。いまいるこの喫茶店だ。以来、僕たちはここを打ち合わせやギャラの受け渡しに使っている。
間戸村さんに頼まれる仕事はいろいろで、たとえば何らかの事実を確かめるためにどこかの建物へ忍び込んだり、誰かのあとをつけて写真を撮ったり。今回のように、撮影した写真がそのまま紙面に載るときもあれば、僕が手に入れた証拠をもとに間戸村さんが取材を進め、最終的な記事をつくるときもある。事前に、簡単な状況と、行くべき場所や撮るべき写真、確認すべきことなどについて間戸村さんがICレコーダーを回しながら話し、僕は自分のやり方でそれを実行する。一番得意なのはバイクを使った追跡だけど、ほかにも、マンションの部屋に出入りする人間を撮影するため、二軒隣のビルから隣のビルまで飛び移ったりもしたし、サンタクロースみたいに排煙ダクトから入り込んで、ヤクザがらみの詐欺集団が借りているテナントに、天井裏から聞き耳を立てながら会話を録音したりもした。間戸村さんはそれらの情報によってスクープを手にし、僕はお金をもらえる上、この仕事をすることで、なんとかまともな状態を保っていられる。
「これギャラね」
間戸村さんがバッグから封筒を取り出す。僕は中身の八万円を財布に移した。基本の六万円と、今回はプラス二万円。いつも受け取っているお金が、間戸村さんのポケットマネーなのか会社の経費から出ているのかは知らない。でも、まさか会社ぐるみで未成年にこうした仕事をさせるとは考えにくいから、たぶんポケットマネーなのだろう。スクープ記事を書くと、会社から「スクープ料」というものが支払われるらしく、高いときにはそれだけで中堅サラリーマンの月収くらいになるというから、ポケットマネーだとしても間戸村さんの手元には充分な金額が残るはずだ。
「あそうだ錠也くん、薬」
僕が返した封筒を仕舞うついでに、間戸村さんがバッグから錠剤の箱を二つ取り出した。
「今回は、俺のおごりね」
「いいんですか」
「安いもんよ」
間戸村さんが登録している輸入代行の製薬通販サイトで定期的に買ってもらっている、抗鬱剤のトリプタノールだった。本来は医者にしか処方できない薬剤だけど、そのサイトを使えば処方箋なしで海外から購入できる。僕は未成年なのでサイトに登録することができず、間戸村さんに話すと、かわりに買ってあげるよということで、いつもこうして頼んでいる。でも僕はべつにそうした病気に罹っているわけではない。僕がほしいのはトリプタノールが持つメインの作用ではなく、副作用──心拍数を上げるという副作用のほうだった。
「さ、て、と」
背もたれに背すじを押しつけるようにして、間戸村さんが腕時計を見る。
「五時前か。錠也くん、たまにはいっしょに飯でも食う?」
「いえ、友達と待ち合わせがあるんで」
間戸村さんの眉がふっと上がり、しかしすぐに下りた。僕の口から友達という言葉を聞いたのが初めてだったからかもしれない。僕自身、間戸村さんと出会ってからこの一年間、口にした憶えがない。
「んじゃ、またネタ摑んだら連絡するわ。しばらくちょっと、今回のこれがあれだから、かかりっきりになっちゃうかもしれないけど」
「連絡待ってます」
僕はショルダーバッグを摑んで席を離れようとしたが、
「そういえば、間戸村さん」
ふと思い立って振り返った。
「うん?」
「あの事件──」
「どの事件?」
「前に、記事を取り寄せてもらった──」
十九年前の冬、週刊誌に載った記事。
埼玉県で一人の妊婦が散弾銃で撃たれた事件。
「……いえ、いいです」
何か言いかける間戸村さんに一礼し、僕はショルダーバッグを斜めがけにして喫茶店を出た。新宿の裏路地では居酒屋が店を開けはじめ、ウィンドウには「忘年会」の文字が貼り出されている。真冬の日はもう暮れかけて、空のあちこちに伸び上がるビルは四角い光の集まりに変わろうとしていた。
〈第2回へつづく〉
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/