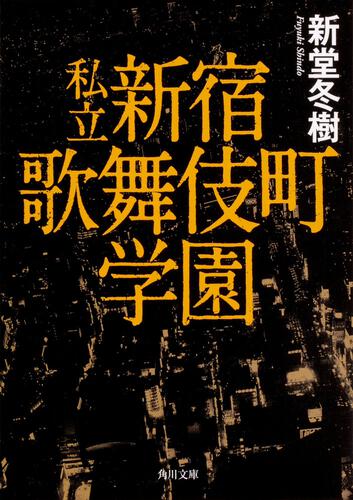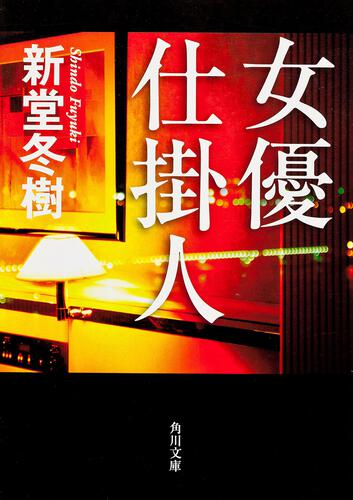【第10回】連載小説『ダークジョブ』新堂冬樹
【連載小説】新堂冬樹『ダークジョブ』
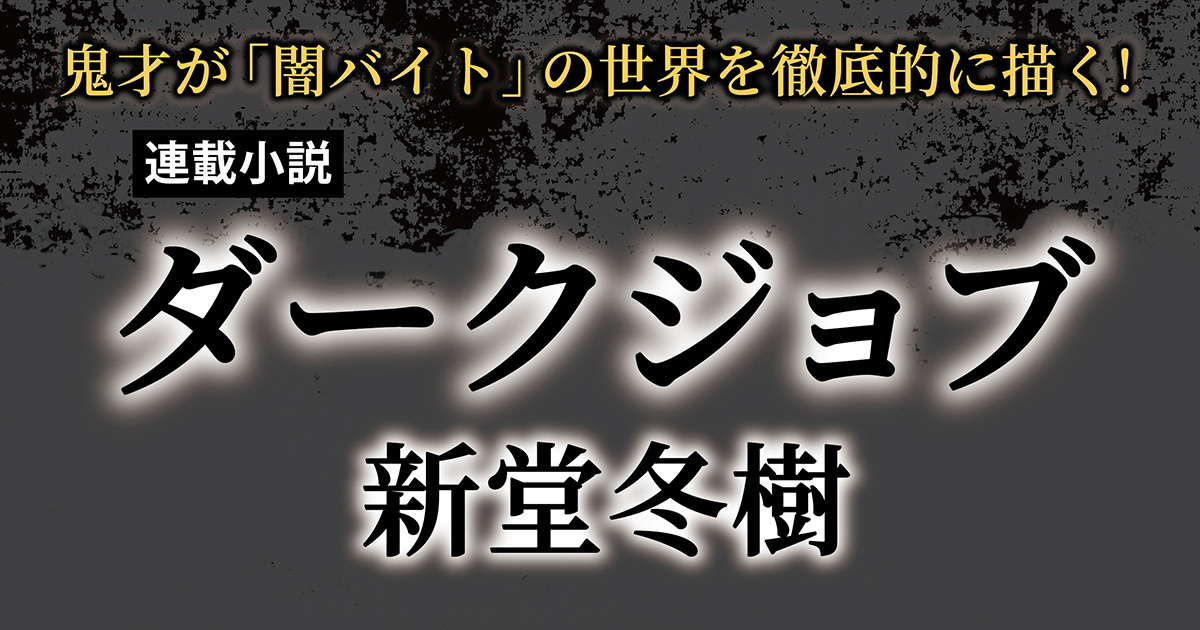
新堂冬樹さんによる小説『ダークジョブ』を連載中!
1985年――東京・歌舞伎町で闇金融の世界に飛び込んだ片桐は、激しい「切り取り」に辟易しながらも、いつしかその世界に魅入られていく……。
闇金、特殊詐欺、そして闇バイトへと繋がる裏社会を、鬼才が徹底的に描く!
【第10回】新堂冬樹『ダークジョブ』
若宮★2025年冬
「店は五十代の夫婦でやっています。クレジット決済と電子マネーは不可なので、おそらく奥の金庫室に売り上げ金がプールされています。売り上げ金以外にも、こちらの情報では買い取り資金を二千万用意しています。二人はカードを買う振りをして、須藤さん、あなたが夫を人質に取ってください。嶋村さんには、妻に金の在処を吐かせ、金庫を開けさせるように指示してください。男性は力が強いので、抵抗されたら厄介です。須藤さんは、最初に金槌で夫の膝と肘の関節を砕いて戦闘力を奪ってください」
渋谷のアジト――若宮はインカムのマイク越しに、淡々とした口調で須藤に命じた。
『抵抗しなければ、やらなくてもいいですか? 必要ないのに骨を折るっていうのは、あんまり気分がよくないんで……』
須藤が訊ねてきた。
「抵抗されてからでは遅いんです。必要があるかどうかは、こっちで判断します。あなた達は、こちらの言う通りにしてください」
若宮は平板な声で窘めた。
『おばあちゃんと娘を、殺してしまいました! 金を奪って逃げようとしたときに大声で騒がれて……もう、なにがなんだかわからなくなってしまって……』
三ヶ月前……指示した清水からの取り乱した声が、若宮の脳裏に蘇った。
清水を人殺しにしてしまったこと、罪なき老婆と娘の命を奪ったことが、ずっと頭から離れなかった。
いまでも、夢でうなされていた。
実行役時代に、目の前でターゲットが殺されるのを目撃したのも相当なトラウマだが、指示して命を奪わせるのは、別の後味の悪さがあった。
三ヶ月前と変わったのは、感情のドアを閉める術を覚えたことだ。
罪悪感と自責の声は、ドア越しにも聞こえる。
何度かドアを開けようとしたこともあったが、そのたびに思いとどまった。
ドアを開けたとしても、もう昔の自分には戻れない。
初めて現場に足を踏み入れた瞬間から、若宮には引き返す道は残されていなかった。
『……わかりました。金が二千万なかったら、どうしますか?』
須藤の強張った声が、若宮を現実に引き戻した。
「心配しないでも、最低、二千万はあるから大丈夫です。二千万なければ、あなた達がごまかしたと判断します」
若宮は感情のない声で断言しながら、氷花との会話を思い出していた。
『お金をごまかそうとする人間が出てくるから、実行役には金額を断言しなさい』
氷花が淡々とした口調で命じた。
『こっちに入っている情報より、少ない場合はどうするんですか? 僕も実行役時代に、指示役から聞かされていた金額より少なかったことがありましたから』
『もちろん、そういうこともあるわ……というより、そういうことのほうが多いでしょうね。私達に情報が入ったときには箪笥預金が五百万あったとしても、実行するまでに減っているかもしれないから』
『断言するのはわかりました。でも、実行役が嘘を吐いているかどうかを、どうやって見極めるんですか?』
若宮は、一番の疑問を口にした。
『コングの情報が間違っていたときのことを思い出しなさい。目の前でコングが処分されるのを見て、それでもお金をごまかそうと思う? 究極の恐怖の前で人間は、お金より命を選ぶものよ』
『見せしめのために、コングさんは殺されたんですか?』
若宮は掠れた声で質問を重ねた。
『あなた、歴史は好き?』
唐突に氷花が訊ねてきた。
『え? まあまあ好きなほうです』
氷花の質問の意図が読めなかった。
『歴史上の武将たちは例外なく見せしめのために、家臣が逆心を抱かないように定期的に身内に罪を被せて首を刎ねていたわ』
『いまは、戦国時代とは違います』
若宮は勇気を振り絞り反論した。
『人間に欲望があるかぎり、戦国時代も令和も変わらないわ。ただ、勘違いしてほしくないのは、優秀であれば一度のミスで処分することはないということ。コングは過去に何度も同じようなミスを犯していたの。だから、見せしめとしてはちょうどいい素材だったわね』
氷花の口調は、まるで料理の具材の話をしているようだった。
『生き残りたいなら、一切の情を捨てなさい。肉食獣が獲物に同情して仕留めなかったら、飢え死にするでしょう? あなたが情けをかけたとしても、ほかの肉食獣が仕留めるだけの話よ。いい? あなたが放り込まれた世界は弱肉強食……狩るか狩られるかの世界よ』
『そんな……。そちらに情報が入ったときには買い取り資金を二千万用意していても、いまは少なくしているかもしれないじゃないですか!?』
怯えながらも、須藤は懸命に食い下がってきた。
彼の気持ちは痛いほどわかるが、悟られるわけにはいかなかった。
「私達が掴んでいるのは、最新情報です。安心してください」
最新情報というのは嘘だが、微塵の躊躇いも見せずに若宮は断言した。
『買い取り資金だから、カードを買い取って減っているかも……』
「開店と同時に、あなた達は踏み込みます。その心配は無用です。では、成功を祈ります」
若宮は、須藤の不安を完全にシャットアウトして電話を切った。
「ずいぶん、様になってきたじゃねえか」
アンコ体型、口髭にオールバック――隣のデスクで実行役に指示を出している室橋が、若宮の肩を叩いた。
「仕事ですから」
若宮は素っ気なく言った。
室橋のことが鬱陶しいわけではなかった。
逆だ。
指示役に回ってからの数ヶ月、戸惑いと動揺の連続の若宮を室橋はなにかと気にかけてくれた。
実行役の清水が老婆と娘を殺してしまったときに、罪の意識に苛まれていた若宮を励ましてくれたのも室橋だった。
だからこそ、距離を置きたかった。
若宮の命令で、これから何人……いや、何十人もの命が奪われてしまう。
若宮の命令で、これから何十人もの青年を殺人者にしてしまう。
若宮の命令で、殺すほうと殺されるほうの人生を奪ってしまう。
そんな自分に、誰かに気遣ってもらったり誰かと仲良くしたりする資格はない。
多くの罪なき者の人生を奪うのだから、若宮も人生を捨てなければならない。
「短い間に、肚が据わってきたじゃねえか」
若宮のつれない態度にも気を悪くしたふうもなく、室橋が肩を叩いた。
「室橋さん、ネットニュース見ました? またやられましたよ」
室橋の隣のデスクでスマートフォンを見ていた長岡が強張った顔で言った。
長岡の年は若宮と同じだが、指示歴は半年と先輩だった。
「なんだよ? ネットニュースなんか見てると、どやされるぞ」
室橋が天井の隅から睨みを利かせるカメラにちらりと視線をやった。
指示役の仕事ぶりを、別室で氷花やレイが監視していた。
今日は氷花は不在で、レイが監視役だった。
「この摘発されたグループ、ウチのグループじゃないですか?」
長岡がスマートフォンのディスプレイを指差した。
「え? どれどれ……あっ……」
長岡のスマートフォンを覗き込んだ室橋の顔色が変わった。
「ね? そうですよね?」
「ああ、ウチの系列のグループだ」
硬い声で室橋が言った。
若宮も長岡のスマートフォンを覗いた。
ネットニュースでは、池袋の事務所を拠点にしていた闇バイトのグループが摘発されたと報じていた。
「摘発されたリーダー格の男は、前に現場が一緒になってな」
室橋のこんなに動揺した顔を見るのは初めてだった。
「これで、三ヶ月のうちに三件目ですよ? 偶然ですかね? どう思います?」
長岡が矢継ぎ早に室橋に訊ねた。
「偶然なわけねえだろう。こりゃ、完全にロックオンされてるな」
「ロックオン……誰にですか?」
「あくまでも噂だが、桜田門のラーテルがウチをマークしてるらしいぜ」
「桜田門のラーテル? 何者ですか?」
長岡が怪訝な表情で訊ねた。
「アフリカに棲む、イタチ科のスカンクみてえな動物だ。こいつがとにかく勇敢で執拗で、どんな相手にでも怯まずに立ち向かう。体重が十キロ前後しかねえのに、狙われたらライオンにも反撃する。ライオンの腹の下に潜り込んで、金玉に咬みついて絶対に離さねえ。ライオンが逃げるかラーテルが咬み殺されるかしねえと、闘いは終わらねえ。ラーテルは組織犯罪対策課の刑事だが、強大で危険な組織のアジトにも単身乗り込んで、狙った星は逃さねえ姿からそう呼ばれるようになったらしい」
室橋が渋い表情で言った。
「そんな奴にマークされたら、ヤバいじゃないですか……」
長岡の顔から血の気が引いた。
「ラーテルを一躍有名にしたのは、トクリュウのアジトに単身で乗り込んで中国系の犯罪組織を一掃した一件だ。奴らは日本人と違って、警察官でも躊躇いなく殺しにかかる。だから、警察も中国系の犯罪組織のアジトに乗り込むのは嫌がるし、タレコミがあっても見て見ぬふりをする場合が多い。刑事だって人の子だ。銃や刃物で襲いかかってくる奴らがうようよしてるアジトに乗り込んで殺されたくはねえよ。だが、ラーテルは違った。映画みてえにチャカ握り締めてアジトに踏み込んで、そこにいた六人を制圧したって話だ」
室橋が信じられないといった顔で、小さく首を横に振った。
「ラーテルに、俺らもマークされてるってことですか?」
長岡が掠れた声で訊ねた。
「俺らっていうより、ウチのボスは完全にマークされてると考えたほうがいいだろうな。なんつっても、関東最大のトクリュウ組織だからな」
「ど、どうするんですか? 俺、子供が生まれたばかりなんですよ。警察に捕まるわけにはいきませんよ」
長岡が蒼褪めた顔で言った。
「俺だって、ブタ箱に入るわけにはいかねえよ。これまで、実行役に何人の命を奪わせたと思ってんだ。強盗殺人は罪が重いからよ。直接手を下したわけじゃねえが、最低でも二十年は食らい込んじまう……出てきたときには五十過ぎてんじゃねえか!? 冗談じゃねえぞ」
室橋の顔からも血の気が引いた。
「お前、さっきから黙ってるけど、不安じゃないの?」
長岡が若宮に訝しげな顔を向けた。
「不安ですよ」
若宮は表情を変えずに言った。
「だったら、なんでそんなに落ち着いてるんだよ?」
「騒いでも、捕まるときは捕まるでしょう」
若宮が淡々とした口調で言うと、長岡が呆れたように肩を竦めた。
強がっているわけではなかった。
もちろん、逮捕されるのは嫌だった。
自分が逮捕されれば、母に仕送りができなくなる。だが、心のどこかでそれを待っている自分もいた。
しっかりしろ! お前が捕まったら、残された母親はどうなる?
このまま、なにごともなかったように生きろというのか? 間接的とはいえ、老婆と娘を殺した。あの二人にも、哀しむ家族はいる。
いまさら、なにを言ってるんだ? そんなこと、初めからわかっていたことだろう?
わかってなんかないさ……。わけがわからないうちに、人が死んでいた。わけがわからないまま、人を殺せと指示するようになっていた。
すべて、自分が選択したことだろう?
そう、始めたのは自分だ。そして、終わらせることができるのも自分だけだ。
お前、正気か? 強盗殺人は無期懲役、へたすれば死刑もありうるんだぞ!?
ああ、正気だ。人の命を奪ったんだから、奪われるのも当然だ。
「余計なことを考えずに作業に戻れ」
別室から現れたレイが、冷え冷えとした声で命じた。
「あ、ちょうどよかった。あんたに訊きたいことが……」
「ラーテルのことは気にするな」
レイが室橋の言葉を遮った。
監視モニターで、二人の会話をチェックしていたのだろう。
「気にするなって、そんなの無理だって! ウチの系列、三ヶ月で三件もやられてるじゃねえか!」
室橋が血相を変えてレイに食ってかかった。
「そうですよ! ここにも、刑事が踏み込んでくるんじゃないんですか!?」
長岡も理性を失いつつあった。
ほかの四人の指示役も、作業の手を止めレイと室橋達のやり取りを見ていた。
「それは、お前達が気にすることじゃない。作業に戻れ」
レイが相変わらず冷え冷えとした口調で命じた。
「捜査の手がどこまで伸びてるか聞かねえことには、作業なんてできるか! 包み隠さず、状況を教えろや!」
室橋が席を立ち、レイに詰め寄った。
「作業に戻れ」
レイが氷の瞳で室橋を見据えた。
「ふざけんな! 幹部だかなんだか知らねえが、ガキのくせしやがってえらそうに指図するんじゃねえ! 俺らが危ねえ橋を渡っているから、てめえら幹部が儲けてるんだろうが!」
室橋がレイに人差し指を突きつけた。
「何度も言わせるな。作業に戻れ」
レイが同じ言葉を繰り返した。
嫌な予感がした。
「室橋さん、もうこのへんで」
若宮は室橋の腕を引き、デスクチェアに座らせようとした。
「誰かが言わねえと、こいつらはわからねえんだよ!」
室橋が若宮の腕を振り払い、レイを睨みつけた。
「最終警告だ。作業に戻れ」
レイが表情一つ変えずに言った。
「てめえら幹部は、俺らを使い捨ての駒みてえに……」
レイが素早く室橋の首を掴むと引き寄せ、羽交い絞めにすると頭を鷲掴みにして顔を真後ろに捻った。
ゴキッという音が室内に響き、不自然に顔が横を向いたままの室橋が床に崩れ落ちた。
指示役達が息を呑み、表情を失った。
あっという間の出来事だった。
若宮は震える膝を手で押さえ込んだ。
「みな、作業に戻れ。こいつみたいになりたくなければ、余計なことを考えるな」
レイは無表情に指示役達を見渡し淡々と言い残すと、室橋の足首を片手で握り引き摺りながら別室へと消えた。
足の震えが止まらなかった。
ほかの指示役達も、凍てついた顔で固まっていた。
若宮は膝を押さえたまま、感情のスイッチをオフにした。
☆
(七十代の夫婦が二人。庭に中型犬が一頭。隣家まで二百メートル。箪笥預金五百万)
若宮はテレグラムで実行役の井川に指示メッセージを送った。
井川のチームは清瀬市の現場付近に待機していた。
《ほかに誰もいないんですか?》
すぐに返信があった。
(老夫婦だけです。もし誰かいたら、面倒なことになるので戦意を喪失させてください)
《どのくらい痛めつけるんですか?》
(抵抗できないようにナイフでアキレス腱を切ってください)
《アキレス腱を切るんですか?》
(それでも抵抗するなら殺してください)
《殺すんですか?》
(捕まりたくなければそうしてください。指示に従わなければ、あなたの大切な人達に危害が及びます。では、健闘を祈ります)
若宮は井川とのやり取りを終えると、別のスマートフォンを手に取った。
(いま、どんな感じですか?)
若宮は八王子市内の金券ショップを襲撃するチームの見張り役の伊吹に、テレグラムでメッセージを送った。
《五分前に、戻ってきました。いま、移動中です》
(相楽さんに電話をかけると伝えてください)
若宮は八王子チームのリーダー……相楽の携帯番号をタップした。
『相楽です』
「いくらですか?」
『まだちゃんと数えていませんが……百万から百五十万の間だと思います』
相楽が息を切らしつつ言った。
「おかしいですね。金券ショップには、買い取り資金として一千万はあったはずです」
すかさず若宮は言った。
『店主に訊いたら、大口の買い取りがあった直後だと言ってました。レンチで腕の骨を折っても同じことを言ってたので、嘘は吐いてないと思います』
「店主は死んだんですか?」
『いえ、嘘を吐いていなかったので途中でやめました』
「本当のことを吐かせるために、殺すまでやるべきでしたね」
若宮はさらりと言った。
恐らく相楽が嘘を吐いていないだろうことはわかっていた。
そこまで相楽を詰めるのは、組織の指令だからだ。
十日前、レイに詰め寄った室橋は頸椎を折られて死んだ。
逆らった者は見せしめのために処分するのが、組織のやりかたなのだ。
あのとき、若宮の感情のスイッチは完全に切れた。
指示役になったときからスイッチは切っていたが、完全ではなかった。
たとえるなら、今度はブレーカーが落ちたような感じだ。
すべてが、無駄だと悟った。
この組織にいるかぎり、殺されたターゲットに懺悔しても、殺すように命じた実行役に罪の意識を覚えても無駄だということを……組織のロボットにならなければ殺されてしまうということを。
捕まるか死ぬかしないかぎり、この無間地獄から逃れる方法はないのだ。
覚悟を決めたわけではない。
もう、どうでもよかった。
闇の世界に足を踏み入れた時点で、若宮の人生は終わったのだ。
『あまり時間をかけると、警察がくる可能性があったので……』
相楽の声で、若宮は我に返った。
「ターゲットだけではなく、あなたが嘘を吐いている可能性もあります」
若宮は抑揚のない口調で言った。
『俺は、嘘なんて吐いてません!』
すかさず、相楽が強い口調で否定してきた。
やはり、嘘を吐いているとは思えなかったが、若宮の主観は意味がない。
「まずは、テレグラムで送る銀行口座に全額振り込んでください。振込確認後、こちらが指定する場所にきてください。そのとき、配当を渡します」
『え……配当を差し引いて振り込むんじゃないんですか?』
相楽が強張った声で訊ねてきた。
「今回は奪った金額が確定していないので、あなた達から事情を聞いて確定したら手渡しになります」
若宮の脳内に、初めての現場で百万円しか奪えなかったときにコングから呼び出しを食らったときの恐怖が蘇った。
あのときの若宮のように、相楽は恐怖心に支配されているだろう。
『信じてください! 嘘は吐いていません! ごまかしてなんかいませんから!』
相楽が必死に訴えた。
無理もない。
行けば命を奪われるかもしれないのだから。
「後ほど場所を指定します。わかっていると思いますが、逃げようなんて……」
「おい、電話を切れ!」
長岡が切迫した顔で若宮に命じてきた。
「いま、実行役と電話中です」
若宮は相楽との電話を保留にして言った。
「馬鹿っ、ラーテルがここを特定したって氷花さんから連絡が入ったんだ! 備品を処理して撤収するぞ!」
長岡は捲し立てるように言うと、指示用のスマートフォンを次々と電子レンジに放り込んだ。
スマートフォンの爆発音が室内に鳴り響き、焦げ臭い匂いが鼻孔に忍び込んだ。
「お待たせしました。もし逃げたら、相楽さんのご両親の安全は保証できないので変な気を起こさないでください」
若宮は保留を解除し、相楽に釘を刺した。
「おいっ、お前、なにやってるんだよ! 早く撤収しろ!」
長岡はデスクの上の水溶紙のメモを足元のバケツに入った水に放り込みながら、怒声を浴びせてきた。
「電話が終ったらやりますから、構わずにどうぞ」
若宮は昼休憩を勧めるかのように、淡々とした口調で長岡に言った。
「お前……なに言ってるんだ!? 捕まってもいいのか!?」
長岡が宇宙人を見るような顔で若宮をみつめた。
「わかりましたか?」
若宮は長岡の問いかけを無視し、相楽に念を押した。
「知らないぞ……勝手にしろ!」
長岡は吐き捨て、寝室に走った。
指示役達の生活必需品は、非常時のときのために常にリュックの中にまとめて寝室のドア口に置いていた。
三十台を超えるスマートフォンの爆発音で、相楽の声は聞き取れなかった。
寝室から戻ってきた長岡は、もう若宮に構うことをせずにほかの指示役達を促してアジトを飛び出した。
爆発したスマートフォンの黒煙が漂う焦げ臭い部屋に、若宮は一人取り残された……いや、自ら残った。
『なにか、あったんですか?』
強張った声で、相楽が訊ねてきた。
「こちらのことはいいので、自分の心配をしてください」
若宮は、なにごともなかったかのように相楽に釘を刺した。
なぜ逃げない?
声がした。
無視した。
まさか、捕まる気か?
また、声がした。
無視した。
なぜだ?
みたび、声がした。
「人間であるため……」
若宮は、無意識に呟いた。
『え? なんですか?』
怪訝そうな相楽の声が受話口から流れてきた。
「いえ、なんでもありません。では、後ほど連絡します」
一方的に言い残し、若宮は電話を切った。
もう二度と、相楽に連絡することはないだろうとわかっていた。
眼を閉じ、デスクチェアの背凭れに背を預けた。
この決断が、命を奪われた者達への
ただ、止めることはできる。
本物の悪魔になることを……。
ドアが勢いよく開く音がした。
ラーテルがきたらしい。
足音は複数ではなかった。
噂通り、単独で乗り込んできたのか?
外に援軍を待たせているのか?
どちらでもいい。
自分を止めてくれるなら……。
腕を掴まれた。
若宮はおもむろに眼を開けた。
「えっ、どうして……」
予想外の人物に、若宮は思わず声を上げた。
「行くぞ」
片桐が若宮の手首を掴みデスクチェアから立ち上がらせると、有無を言わせずに玄関へと引っ張った。
連載一覧ページはこちら
連載小説『ダークジョブ』は毎月末日の正午に配信予定です。更新をお楽しみに!
https://kadobun.jp/serialstory/darkjob/