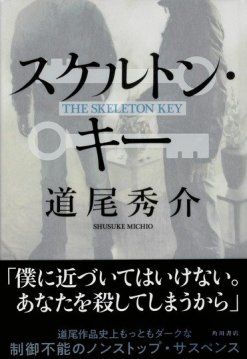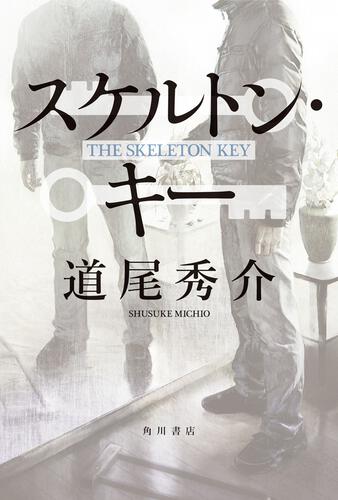直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
>>前話を読む
同じ児童養護施設で育った仲間、うどんに呼び出された僕は大宮へ向かう中、園での生活を思い出していた。
◆ ◆ ◆
夕食後、先生も子供たちもみんな園庭に集まった。
用意されていた花火セットは六袋だった。みんながバケツに水を汲みに行ったり、蚊取り線香に火をつけているとき、僕は花火セットを一袋、Tシャツの腹に入れ、トイレに行くと言ってその場を離れた。誰もいない園舎の中で袋を取り出してみると、入っていたのは手持ち花火が三十本くらいと、打ち上げ花火が三本だった。僕はトイレの中で便座の蓋にトイレットペーパーを敷き、花火の紙をむいて火薬を取り出した。ぜんぶの花火から火薬を取り出し終え、トイレットペーパーで包んで丸めたら、ゴルフボールよりも大きくなった。
火薬団子を手に、僕は職員室へ移動してキリカワ先生の鞄を探った。車のキーを見つけ、窓から駐車場に出て車のドアを開け、灰皿を引き出して火薬団子を奥に詰め込んだ。そして鞄にキーを戻し、園庭でみんなといっしょに夏の花火を楽しんだ。花火セットが一つ足りないことに、誰か気づくかと思ったが、意外にも気づかれなかった。
小学生未満の子供たちの消灯時間は八時だった。
二段ベッドの上の段で目をつぶり、暇つぶしに瞼の内側で目玉をぐりぐり動かしていると、遠くで叫び声が聞こえた。声はこもっていて、タッパーの中で小人が叫んだみたいだった。僕は身を起こし、腕を伸ばしてカーテンをちょっと開けてみた。三角形の夜の中で、駐車場に停められた車の運転席が明るく光り、中からキリカワ先生が飛び出してきた。着ているTシャツが豪快に燃え上がっていた。そのときキリカワ先生はすでに全身が真っ黒こげになっているように見えたけれど、死にはしなかったことが翌朝わかったので、あれはたぶん、火の中のシルエットがそんなふうに見えただけだったのだろう。
朝一番、僕たちは講堂に集められた。講堂といっても十畳間くらいで、いつもぎゅうぎゅう詰めだった。部屋は暑く、僕は普段あまり汗をかかない体質だったので、そうして夏場に講堂に集められると必ず背中がかゆくなった。
目の下に隈をつくった園長先生が前に立ち、声というよりも、咽喉が低く鳴っているような印象の音で説明したところによると、キリカワ先生は救急車で病院へ運ばれ、そのまま入院し、いつ戻ってくるかはわからないとのことだった。
──犯人捜しはしたくない。でも、自分が関係しているという自覚がある人は、いまここで手を挙げてほしい。
もちろん当時は矛盾なんて言葉は知らなかったけれど、園長先生はひどく矛盾したことを言い、僕が手を挙げると、眼鏡の向こうで目玉を二倍くらいにふくらませた。
突然、園の中で小さな毒虫が発見された。でもそれを殺すことも追い出すこともできない。だからみんなで慎重に観察するしかない。きっとそんな結論だったのだろう。その日から先生たちは、僕から目を離さなくなった。勉強の時間も食事どきも、自由時間も自習時間も、僕は自分がいつも大人たちの視界の中にいるのがわかった。キリカワ先生はけっきょく青光園には戻ってこず、別の施設で働くことになったらしいが、本当に移ったのかどうかは知らない。
いっぽう、子供たちのあいだで僕はヒーローになった。同年代の子供たちはいつも僕のまわりに集まり、年上の子供たちは僕を可愛がった。そうすることで、たぶんみんな、毒虫と仲良しであることを自慢に思ったり、それをペットにしている危険な自分みたいなものを楽しんでいた。僕は気持ちがよかったので、先生たちの視線をすり抜けて、さらにいろいろやってみた。雪が積もったときには、園庭の隅に生えていた桜の木に長いビニール紐を結び、反対側の端を回転式の草刈り機の刃にくくりつけ、ソリに乗り込み、両手で抱えた草刈り機のエンジンをかけた。草刈り機に猛烈な速さでビニール紐を巻き込ませながら、一直線に雪の上を走っていく僕を見て、みんな甲高い声を上げて喜んだ。園長先生の軽自動車を見よう見まねで運転したこともあった。座席に座ってしまうと前が見えなかったので、立ったまま上手くアクセルを踏まなければならなかったけれど、戸越先生が前に立ちはだかって決死の覚悟で車を止めるまでに、園庭の中で綺麗な円を描けるまで運転が上達した。でも、そんなふうに悪さばかりしていたわけじゃない。遊具倉庫の屋根の隙間で、スズメバチが巨大な巣をつくっているのが見つかったときは、雨樋をよじ登ってそこまで行き、両手で巣を摑んだまま飛び降りた。それを道路に向かって放り投げると、巣は園庭のフェンスを越えて路面に転がり、まじり合ったお経みたいな羽音が一気にあたりに広がった。先生たちはすぐさま子供たちを園舎に引っ張り込み、急いでどこかへ連絡した。三十分くらいすると、業者の人たちが集団で巣を片付けに来た。その人たちの装備が大仰だったおかげで、年下の子供も年上の子供も、いっそう僕に賞賛の目を向けた。
──こわくないの?
そう訊いたのは、ひかりさんだった。
怖いというのがどういうことか、僕にはわからなかった。その感情は、ただ知識として知っているだけで、身をもって体験したことが一度もなかったし、いまもない。首を横に振る僕を、三歳年上のひかりさんは、眼鏡の向こうから不思議そうに見た。知らない生き物を眺めるような目だった。
六歳の春が来ると、青光園から小学校に通うようになった。僕は自分が、勉強がよくできることに気づいた。青光園では同級生が僕のところへ宿題の答えを訊きに来た。
僕は園内での自分の位置づけに充分な満足をおぼえていたので、学校では敢えて何もせず、休み時間になるといつも机に顔をふせて、木のにおいをかぎながら頭と身体を休めていた。親がいないことをからかわれたりもしたし、何をどう勘違いしたのか「山の子」と呼ばれたり、ちょっとものを知っているクラスメイトに「ゼーキンで暮らしてる」と言われもしたけれど、特別であると感じることはむしろ僕の気分をよくさせたので、言うがままにさせておいた。そんなふうに過ごしていたせいか、三年生の秋頃から誰にも話しかけられなくなり、やがてそれは意図的な無視に変わった。相手にしないことと相手にされないことはずいぶん違い、僕は身体中が不快感でいっぱいになり、無視をした相手の持ち物を壊すことにした。目の前で鉛筆をぜんぶ折られたり、教科書を二つに裂かれたり、Tシャツの胸を大きく破かれたクラスメイトたちは、いちいちそれを担任に報告し、担任はそれを青光園に報告した。そのたび園長先生や戸越先生が職員室に来て謝り、僕はもうしませんと約束し、やがてそれも流れ作業みたいになってきて、面白くなくなってしまったので、また何もしなくなった。けっきょく卒業まで、僕は静かに授業を受け、いつも自分の席についたまま休み時間を過ごしていた。
(六)
大宮駅のロータリーが見えてきた。
駅前にバイクを停め、近くにあったBEAMSでダウンジャケットを買った。袖を破いてしまったやつをとても気に入っていたので、できるだけ似たやつを選んだ。セール品だったので、税込で一万三千八百二十四円。レジの店員にダウンジャケットの値札を取ってもらい、その場で着替えて、古いほうはショルダーバッグに詰め込んだ。
大宮駅の東口改札に着いたのは五時四十八分だった。
まだ待ち合わせまで時間があったので、僕は駅のトイレに入り、水道水でトリプタノールを三錠服んだ。手の甲で口を拭いながら顔を上げると、会社員の帰宅時間らしく、鏡越しの背後にはスーツ姿の男の人がたくさんいた。僕のすぐ後ろに、なんとなく会社の中では偉いのだろうとわかる、五十代半ばくらいの男の人が立ち、水道を使う順番を待っていた。僕がトリプタノールの箱をバッグに戻していると、わざと聞こえるような舌打ちをされたので、すみませんと謝ってトイレを出た。
迫間順平が入園してきたのは、僕が中学一年生のときだった。
僕よりも一つ年上で、いったい何を食べたらそうなるのかと不思議に思うほど筋肉質で、怒り肩で、でかい頭は胴体から直接はえてきたように見えたし、背は僕の倍くらいあるのではないかと思えた。肩幅は三倍くらいあった。
園で暮らす中学生の中に、迫間順平のことをもともと知っている女の子がいた。彼女によると、彼にはたくさんの武勇伝があった。これまでケンカで負けたことがなく、一度など、自分の友達を殴った高校生の家まで行き、相手を叩きのめしたこともあるのだという。しかし、そんなエピソードからはとても想像できないくらい、迫間順平の性格は温厚で、年上には気を遣うし、年下の面倒見もよかった。僕がまだ経験していなかった変声期の真っ最中で、声は電波の悪いラジオのようにときどきかすれて消えた。その独特な感じがまた、人の耳を引きつけた。彼はたちまち園の人気者になった。自分への崇拝がだんだんとしぼみ、迫間順平のほうに吸い取られていくのが目に見えるようで、僕は嫌だった。
冬の夕暮れ前、園庭で焼き芋パーティがひらかれた。僕はホイルに包まれた芋を火ばさみで挟み、炭火の中に突っ込んでタイミングを待った。しばらくすると、園長先生が、内容は忘れてしまったけれど何か冗談をやってみせた。その場にいた全員の視線がそこに集まった。僕は火ばさみで挟んだ焼き芋を火の中から取り出し、迫間順平の顔に押しつけた。彼は驚いてそれを腕で弾き飛ばし、焼き芋は地面に転がった。みんなが一斉にこっちを見た。僕は信じられないほど不当なことをされたという顔をしてみせたあと、迫間順平に向かっていった。彼はさすがに応戦した。
ケンカは力と力の勝負だと思い込んでいる人が多いけど、間違っている。実際の勝敗は、ためらいなく相手を傷つけられるかどうかの一点にかかっている。先生たちが止めに入るまでのあいだに、僕は地面の砂を握って迫間順平の目に突っ込み、右手に持ったままの火ばさみを、彼の側頭部に振り抜いた。頭を弾き飛ばされながらも、彼は僕のほうに腕を伸ばしてきた。僕はそれを抱え込み、人差し指と中指をまとめて摑んで反対側に折ろうとしたが、そのとき先生たちが何人かで僕の全身を押さえつけた。
僕が焼き芋を顔に押しつけたことを、迫間順平は先生に喋らなかった。何でだったのかはわからない。とにかく焼き芋パーティでの一件は、僕が先生たちに説明したとおり、彼が急にちょっかいを出してきたので僕が怒り、ケンカになったということで落ち着いた。
その出来事が、みんなの崇拝をまた自分に引き戻してくれると、僕は確信していた。一番強いと思われていた迫間順平に、一瞬で勝利したのだから、当然そうなるはずだった。でも、みんなの反応はずいぶん予想と違っていた。
誰も僕に近づかなくなった。
それまでずっと、年下や同学年の子供たちは、僕という毒虫に憧れをおぼえていた。年上の子供たちは、毒虫を可愛がっている危険な自分みたいなものを楽しんできた。でもあるとき、その毒虫が、新しくみんなで飼いはじめた、人なつっこい哺乳類を刺した。──いつのまにか毒虫が育ちすぎて手に負えなくなっていたことに、みんなは気づいた。だから、そのへんにほっぽらかすことにした。そんなものは最初から知らないという態度をとることにした。ためしに僕が自分から近づいてみると、みんな、どうでもいい相手の名前を呼びながら顔をそむけ、そそくさと離れていくのだった。
そんな中、唯一、僕に近づいてきたのは、意外なことに迫間順平だった。
理由は訊かなかったから知らない。初めてケンカでやられて、僕をすごいと思ったのかもしれないし、誰も近づかなくなった僕を可哀想に思ったのかもしれない。べつにどんな理由であっても、退屈しないですむのだから、損はなかった。
それから、僕たちはいつもいっしょにいるようになった。僕がいつか免許を取ってバイクを買いたいと言うと、彼は車のほうが好きだと言い、そのあとバイクのいいところ、車のいいところを競争みたいに言い合ったりして、なかなか楽しかった。
──お前、どうしてここ来たんだ?
迫間順平は僕に訊いた。
──わかんない。
何も教えられておらず、知っているのは坂木逸美という母親の名前くらいだと、僕は説明した。迫間順平は鼻の下を伸ばし、曖昧に首を揺らした。
──そっちは何で?
訊くと、彼はしばらく同じ顔つきのままぼんやりしていた。聞こえなかったのかと思い、もう一度言い直そうとしたら、やっと言葉が返ってきた。
──お父さんが、ずっと前に悪いことして捕まってな。
──そうなんだ。
──何したのか知らないし、俺、お父さんに会ったこともなくて。捕まったの、俺が一歳のときだったから。それで二年前にお母さんが自殺したんだ。俺、お父さんが捕まってからお母さんと二人で暮らしてたんだけど。
迫間順平はあまり頭がよくなかったので、言葉や話がいつも前後した。
──それで、お母さんのほうのお祖父ちゃんが俺のこと引き取って、二人で暮らしてた。だから、俺をここに預けたのはお祖父ちゃん。お祖父ちゃん、病気になって、逆に世話が必要になって、それで俺、ここに来たんだ。
お祖父さんに育てられているとき、家にはお金がなく、夜になると近くのうどん屋の裏口へ行き、廃棄された麵を盗んでは家に持ち帰り、ゆでて食べていたのだという。僕はそのエピソードが気に入ったので、彼をうどんと呼ぶことにした。
園を出たらまたお祖父さんと暮らすつもりだと、そのときうどんは言っていた。自分が働きながら看病をするのだと。でもそのお祖父さんは、うどんが高校三年生のとき、彼が園を出る直前に死んでしまった。
「……錠也」
声に振り返ると、うどんが立っていた。
〈第5回へつづく〉
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/