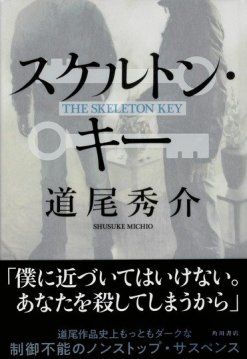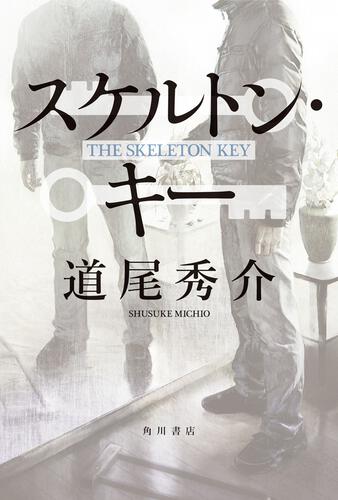直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
>>前話を読む
喧嘩から始まったうどんこと迫間順平との出会いは意外な方向に向かって――。
◆ ◆ ◆
(七)
ギアをトップに入れたまま、アクセルをいっぱいまでふかしてスピードを上げつづけた。車を追い抜いているのではなく、走ってくる車たちを左右にかわしていると錯覚できるほどのスピードだった。でもまだ駄目だ。まだ足りない。僕が上げようとしているのはスピードそのものではなく心拍数だった。
去年の春、磯垣園長が青光園の駐輪場で母の話を聞かせたとき、いったい何を隠していたのか。
うどんと二人で入ったファミリーレストランで、たったいま僕はそれを知った。
──お父さんといっしょに暮らすようになってから、初めて聞いたんだ。
うどんはテーブルの向こうで唐突に打ち明けた。
──どうして長いこと、刑務所に入ってたのか。
赤信号で停まった車が二車線を埋めている。僕はその真ん中を突き抜ける。視界の左右でテールライトとヘッドライトが混じり合い、橙色の直線に変わる。行く手では横方向に車が行き交っている。僕はアクセルをいっぱいにしたままそこへ飛び込む。
──俺が生まれたばっかりの頃、強盗に入った飲食店で、女の人を撃ったらしい。
うどんがそう言ったとき、まだ僕には見当がついていなかった。いや、母のことが頭に浮かびはしたけれど、ただそれだけのことだった。園長先生から聞いた母の過去は、半透明のフィルムのように目の前に浮かび、静止したそのフィルムの向こう側で、うどんが喋っていた。
──そのとき、お父さんとお母さんと、赤ん坊の俺、埼玉県に住んでた。このへんじゃない、もっと田舎のほうだけど。そこに、お父さんの親といっしょに住んでた。
うどんが聞かせる話が、しだいにもう一枚のフィルムになってそばに浮かびはじめた。
──その町にあった小さいパブに、お父さんは強盗に入って、女の人を撃ったらしい。
そして、つぎの言葉を聞いた瞬間、二枚のフィルムが目の前で重なった。どちらも曖昧な白黒の線の集合だったのに、ぴたりと重なり合うことで、急に明確な色を持つ一枚の写真になった。
──その人の名前を聞かされたんだけど──。
白バイのサイレンが聞こえる。
──坂木逸美だった。
スピーカーごしのひび割れた声が追いかけてくる。でも白バイに僕を捕まえることはできない。どれだけ高い運転技術を身につけていても、恐怖を感じない人間に追いつくことなんてできない。
──青光園にいた頃、俺たち、親の話をしたことあるだろ。俺が、お父さんのこと話して、錠也がお母さんの名前を教えてくれて。俺、イツミって苗字みたいだなと思って、そのときの名前をよく憶えてたから、驚いたんだ。錠也のお母さんの名前を、憶えてたから。それで、そのあと、これを……。
使い古されたスポーツバッグから取り出されたのは、『自動車整備ハンドブック』という、表紙のすれた茶色い本だった。ページのあいだに雑誌の切り抜きが挟まっていた。二つ折りにされた切り抜きが、うどんの手ですっかりひらかれる前に、その大きさと形状から、僕はそれが何であるのかに気づいた。見たことがあった。いや、いまも僕の部屋にある。
──お父さんが刑務所にいるあいだに、お父さんの仲間が切り抜いて、取っといたらしいんだけど……。
間戸村さんに頼んで取り寄せてもらったのとまったく同じ、十九年前の記事だった。埼玉県の片田舎で、開店前のパブ「フランチェスカ」に押し入った強盗が、そこに居合わせた坂木逸美という女性を散弾銃で撃ったという記事。
──ここには書かれてないんだけど、女の人はあとで死んだんだって、お父さんが言ってた。それで、その女の人は妊娠中で、死ぬ前に子供を産んだんだって。
単語の一つ一つを思い出すようにして話しながら、うどんの顔はだんだんと僕のほうへ近づいてきた。
──俺、お前に会って、確認しなきゃと思った。たまたま同じ名前だっただけならいいんだ。それがいちばんいい。人が殺されて、いいとか悪いとかないけど、俺のお父さんが殺したのが、もしお前のお母さんだったら、どうしようって。
どうするというのか。
僕は田子庸平を恨んでいる。それは母親のための恨みじゃない。顔も知らない母親に対して僕は何の感情も抱かない。僕の恨みは、僕自身のためのものだ。田子庸平という男は、この僕から、あったかもしれないもう一つの人生を奪った。でも田子庸平がいまどこで何をしているのか、僕はこれまで知らなかったし、そうであってよかったと思っていた。知ってしまったら、何もせずにいる自信がなかったから。
──何で、田子なの?
僕がやっと声を返すと、うどんは大きな顔を傾けて眉を上げた。その表情に、ほんの少しだけ嬉しさのようなものがにじんでいたのは、僕が本題と離れた質問をしたからだろう。心配していたことが見当違いだったと思ったのだろう。でも僕はただ意識をそらせたいだけだった。自分を抑えたいだけだった。
──何でうどんが迫間順平で、父親が田子庸平なの?
もっとも答えには見当がついていた。うどんが一歳のときに父親が捕まり、うどんは母親と暮らしはじめた。その母親が自殺したあと、母方のお祖父さんに引き取られ、そのお祖父さんが病気になったことで、うどんは青光園にやってきた。うどんの苗字は、もともと田子だったのだろう。しかし、父親がパブで散弾銃をぶっ放してから、母親が自殺するまでのあいだに、おそらく二人のあいだに離婚が成立し、子供は母方の苗字になっていたのだ。
うどんの説明も、まさにそのとおりだった。
──だから俺、お父さんから聞いて、初めて知ったんだ。自分が最初は、生まれたときは、田子っていう苗字だったこと。お母さんもお祖父ちゃんも、俺に教えなかったから。
うどんは分厚い唇を閉じて僕の言葉を待った。遠くで誰かが椅子を引く音がした。僕が何も言わずにいると、うどんの顔に浮かんでいた微かな嬉しさのようなものが、だんだんと薄らいで消えていった。でも僕はもう声が出なかった。言葉のかたまりが、無理に折られた木材みたいに、ギザギザの断面を上にして咽喉に詰まっていた。僕が立ち上がると、うどんの視線が僕の顔を追った。
──帰るよ。
うどんは尻を浮かせて呻くような声を洩らした。
──なあ、やっぱり俺のお父さんが撃ったのって……。
──違う。
僕はテーブルを離れた。
──違うから。
店を出たときのことは思い出せない。
気がついたときにはバイクに乗り、スロットルを限界まで開けていた。
もうどのくらい走ったのかわからない。白バイのサイレンは遠ざかり、とっくに聞こえなくなっている。大通りから大通りへと走りつづけ、大きなコの字を描くようにして、僕はいつのまにか足立区にある自宅アパートの近くまでやってきていた。車体を倒して暗い路地に飛び込む。ヘッドライトが投げる光を前輪で追いかけながら、そのまま走りつづける。しかし、路地を進んでいくにつれ、だんだんとバイクが重たくなっていくように、スピードが落ちていった。アクセルを握る手から勝手に力が抜けていく。右手の指が前輪ブレーキにかかり、右足が後輪ブレーキを踏み込む。スピードメーターの赤い針が、ゼロに向かってゆっくりと倒れていく。僕にはそれが自分の心拍数を示すゲージのように思えた。やがて赤い針の先がゼロを指した。左右のブーツが地面に触れた。ヘルメットのシールドの向こう側で、暗い景色が動きを止め、その瞬間に僕は、自分が人間ではなく、人間のかたちをしたプラスチックのような、脈も体温もない物体に変わってしまった気がした。でもその物体の中に、確かに何かが息づいているのだった。
そこは、アパートのすぐそばにある、小さな児童公園の脇だった。
エンジンを切り、ヘルメットを片手にぶら下げて公園に入る。湿った土と木のにおい。青光園の窓際で、夜になると吹き込んできた風のにおいに似ている。ベンチに誰かが座ってこちらを見ている。そのそばを、僕はブーツを引きずりながら横切る。からかうようなことでも言われたらどうしよう。僕は右手のヘルメットで相手の顔をつぶすかもしれない。倒れた相手の腹を、ブーツの裏に地面の感触が伝わるほど踏みつけるかもしれない。そちらを見ないようにしながら、ぽつんと明かりの灯った公衆トイレのほうへ向かう。
うどんと二人で、公園のトイレで大声を上げて笑い合ったのを憶えている。青光園から歩いて二十分ほどの場所にある、もっと大きな公園だった。僕が中学二年生、うどんが三年生のとき。人と身体をくっつけるというのはどんな気分なんだろうと、園での夕食後、うどんが僕に訊いたのがきっかけだった。親にくっついた記憶がないので、まったく想像もつかないとうどんは言い、でも僕のほうにもそんな経験はなかった。だから、ためしに二人で夜の遊具倉庫に入り、抱き合ってみた。冗談半分だったのに、思いのほか気持ちがよかった。うどんの体温のほうが高いように思ったので、そう言うと、うどんは逆のことを言った。声は耳よりも胸を通して聞こえてきた。息を吸うと汗のにおいがした。すぐに僕たちは、男同士でそんなことをしているのは変だと思ったけれど、それでもまだ少し物足りなかった。動物でやったらどうだろうと、うどんが言った。お祖父さんに連れられて、初めて青光園に来た日、近くにあった大きな公園を二人で抜けてきて、そのとき「動物ふれあいコーナー」と書かれた看板を見たのだという。僕はその公園の存在は知っていたけれど、入ったことがなかった。
──ふれあいコーナーだから、ふれあえるだろ?
うどんはそう言った。
夜中になるのを待ち、僕たちは二人で園を抜け出した。公園に向かい、「動物ふれあいコーナー」のゲートを壊して中に入ると、そこにいたのはウサギとモルモットとヤギだった。小さなやつよりも大きなやつのほうがいいだろうということで、僕たちは真っ暗なその広場で、逃げ回るヤギに飛びかかって抱きついた。暴れる相手を地面に押しつけ、蹴られないようにしながら、毛の中に顔を埋めた。毛は見た目よりも硬かったけれど、その奥にある肌はあたたかくて気持ちがよかった。僕たちはしばらくのあいだ、夢中になってヤギを押し倒して抱きついた。逃げられたら、また別のやつに飛びかかって同じことをした。ヤギたちはそのたび叫び声を上げた。同じやつにもう一度抱きついても、それが初めてのように叫ぶのだった。近くで見ると、ヤギはみんな顔が違っていて、人間の女の人のようなやつも、おじさんのようなやつもいた。そうしているうちに僕はふと、最初よりもヤギが少なくなっていることに気がついた。うどんも抱きついていたヤギを離して周囲を見回した。少なくなっているどころか、ぜんぜんいなかった。僕たちの視線は同じ場所で止まった。入るときに壊したゲートが開けっ放しになっていた。そうしているあいだにも、たったいま僕たちが抱きついていたヤギたちが、相ついでゲートの隙間を抜けていった。暗がりの中で、白いぼんやりとしたものが二つ、ジグザグに動きながら曖昧になって消えた。それが最後の二匹だった。
まずいな、とうどんが言った。
まずいね、と僕も言った。
どちらからともなく、二人でゲートを出た。公園の小径を歩くあいだ、どうしてか無言だった。両手をかいでみたら、くさかった。うどんも隣で自分の手をかぎ、まるでにおいが目にしみたように瞬きをした。僕たちは「トイレ」の看板が示す矢印のほうへ小径を折れた。水道で二人して手を洗い、においをたしかめては、また洗った。そのあいだ僕たちは、相変わらず無言だったけれど、やがてうどんが、まるで限界まで押し込まれた空気ポンプの口が壊れたみたいに、猛烈にふき出した。その大音量に僕は振り向き、でもつぎの瞬間、同じようにふき出していた。それから僕たちは大声を上げて笑った。息が苦しくて、空気が足りなくて、最後には、どちらも一人で立っていられなくなるくらい笑って、笑って、気がつけばお互いの身体を支え合いながら、息も絶え絶えになっていた。そうしながら僕は、うどんの体温をまた感じていて、最後のほうは、それをできるだけ長く感じていたくて、無理に笑っていた。
公衆トイレの入り口が四角く光っている。顎を上げると、トイレの向こう側にある木の枝のシルエットごしに、アパートが見える。二階にある僕の部屋の窓は真っ暗だ。すぐにはあそこに戻りたくない。誰も来ない場所で、誰からも見えない場所で、一人になりたくない。一人になったその瞬間、僕のかたちをしたプラスチックの中から何かが飛び出してきて、僕を部屋に置いたまま、どこかへ出かけていく。
トイレに入ると、蛍光灯の白い光に目がくらんだ。
ショルダーバッグを探る。トリプタノールの箱からシートを出し、そのシートから錠剤を一つ一つ押し出して手洗い場のふちに置いていく。ぜんぶ置き終わると、つぎのシートから出してまた置く。そうして三十錠ほどの錠剤を並べてから、僕はそれを手のひらに集めて口に押し込んだ。バルブをひねり、蛇口に直接口をあてて水を飲む。大量の錠剤は、一つの硬い石みたいで、なかなか咽喉から奥に入っていかなかったけれど、構わずごくごくやっているうちに、少しずつそこを通過していった。身体に浸み込んでいく水の冷たさを感じながら、僕はうどんの身体のあたたかさを思い出していた。僕が気持ちいいと思ったあの体温は、半分は田子庸平のものだった。トイレでいっしょに笑い合ったあの声も、半分は田子庸平の声だった。その田子庸平がいまうどんといっしょに暮らしている。うどんの住所は、電話で本人に訊けばすぐにわかる。
身を起こし、流しっぱなしにした水を見下ろす。水は天井の蛍光灯に照らされて、白く光を跳ね返す。その光が目の奥に突き刺さってくるようで、それがとても不快で、僕は目を上げた。鏡があった。鏡は垢と埃と、誰かの手の跡で汚れていた。
動けなくなった。
大宮駅で同じように鏡を覗いたとき、そこには見慣れた僕自身の顔があった。その後ろには、仕事を終えたスーツ姿の男の人たちがいた。ところが、いま目の前の鏡に映っているのは、僕でもなく、背景でもなく、二つの目だった。それ以外のものはすべて白く搔き消えて、両目だけが真っ直ぐに僕を見つめていた。これまで鏡の中で、数え切れないほど見てきた僕の目と、よく似ているけれども、明らかに違う目。誰の顔にも見たことがない目。凍りついたような目。僕は相手と視線を合わせた。両足を切り取られたような、身体の隅々まで流れていた血が一瞬で冷水に変わったような、生まれてからこれまで一度も感じたことのない何かに囚われていた。
たぶん、それは恐怖だった。
〈第6回へつづく〉
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/