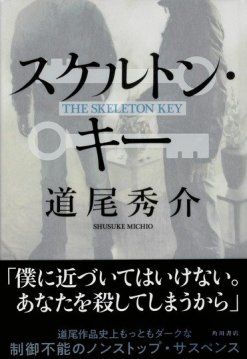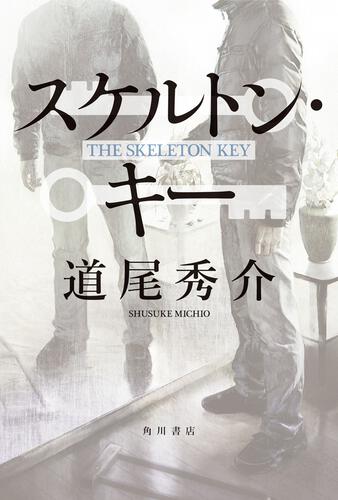直木賞作家・道尾秀介、衝撃のアーティスト・デビュー!
これを記念して、デビュー曲『HIDE AND SECRET』の原案となった『スケルトン・キー』の試し読みを連続公開します!
>>前話を読む
僕を呼び出したうどんの告白。それは僕の人生を揺るがす衝撃的なものだった。
◆ ◆ ◆
青光園のフェンス沿いに歩いていくと、若い女の人が行く手の歩道で立ち止まっていた。
「戸越先生ー」
両手に赤い灯油のポリタンクを持ち、フェンスの内側へ向かって声を飛ばしている。
「灯油って、こないだ教えてもらったお店で入れてくればいいんですよねー?」
園庭に目をやる。戸越先生が、指で輪っかをつくって頷いている。その目がいまにも僕のほうを向きそうだったので、顔を伏せた。ポリタンクを持った若い女の人は、こちらに向かって歩きはじめる。しかし僕の様子に何かを感じたのか、ふと歩調を緩めた。
「……あの」
声をかけられた。
「園に、何か御用でしょうか?」
短く迷ってから、僕は顔を上げた。
「卒園生です」
あっと彼女は口をあけ、ポリタンクを両脇に置く。
「ごめんなさい、わたしまだ配属されたばっかりで」
「だと思いました」
「誰か、先生呼んできますか? どなたが来たって言えば──」
「平気です。ちょっと、驚かしてやりたいし」
はあ、と彼女は微笑んだまま頷く。
「僕、坂木錠也といいます」
名前を言ってみた。
「去年の春、ここを出ました」
「あ、そうなんですね。じゃあ、ちょうどわたしと入れ替わりです」
「入れ替わりじゃないですよね」
訊ね返すように、彼女は眉を上げる。
「入れ替わってないでしょ。あなたは職員なんだから」
僕が笑いかけると、まるでそこに笑顔が二つあってはいけないというように、彼女の顔から微笑みが消え去った。
「べつに深い意味はないから大丈夫ですよ」
「あの──」
「灯油を買いに行くんですよね?」
「あ、はい」
最後にもう一度、僕は笑いかけた。そうしながら、ダウンジャケットのポケットの中で、母が僕に託した古い銅製のキーを、なんとなくつまんだり離したりしていた。
「お気をつけて」
僕の言葉に、彼女は上唇の両端を無理にめくり上げ、ぎこちなく頷いた。ピンク色の歯ぐきが唾液で濡れていた。そのまま視線を合わせていると、両目が顔から逃げ出そうとしているみたいに、上下左右に細かく揺れはじめた。やがて彼女は急に、歩道に置いた二つのポリタンクを持ち上げ、何か聞き取れないことを短く呟いたあと、うつむいたまま僕の横を過ぎていった。
振り返って彼女の背中を見る。彼女は園の駐車場で、白い軽自動車にタンクを積み込み、運転席に乗り込んで走り去る。
夜の公衆トイレで、あの凍りついた両目を見てから一週間。
最初はひどく驚いたけれど、いまはもう違う。僕は、眼球のかたちをしたその氷を、握って溶かして一つにして、ちょうどこのキーみたいに、ポケットの中に持ち歩いている気さえした。
「……錠也くん?」
フェンスの向こう側から戸越先生が近づいてくる。
「あやっぱり錠也くん。少し瘦せたのねえ。え何、また遊びに来てくれたの?」
園庭のフェンス越しに微笑みかけながらも、戸越先生の顔が少し強張っているのがわかった。たったいま、新人の先生が浮かべたのとはまた違う、明確な不安がそこにはあった。その表情を見て僕は、書類はこの人に見せてもらおうと決めた。
「遊びに来たというか、ちょっと、知りたいことがあって」
「うん、なあに?」
半分白くなった髪の毛が後ろで束ねられ、乾いた癖っ毛が左右の耳の上に飛び出している。冷たい風が吹き、その毛を震わせる。彼女の背後の園庭で、黄ばんだ砂ぼこりが舞う。
「いま、そっち行きますね」
青光園の見た目は、小ぶりの学校みたいだが、入り口に門はない。まだ記憶に新しいその入り口を、僕は抜け、園庭に立つ戸越先生のほうへ近づいていった。ひどく静かなのは、平日の昼間なので、小学生や中学生、高校生たちが学校へ行っているからだろう。園庭の隅、水道が並んだあたりに、小さな子供たちが何人かしゃがみ込んで遊んでいる。一人が僕に気づいて顔を上げると、ほかのみんなもこちらを見た。いちばん年下らしい男の子だけが、興味深げに顔を向けたままでいたが、ほかの子供はみんな視線を下げた。僕が軽く手を振ってやると、こちらを見ていた男の子は恥ずかしそうに手を持ち上げ、中途半端に振り返した。
僕は戸越先生のすぐそばまで近づいてから切り出した。
「うどんの住所を教えてもらえればと思いまして」
昨日、本人に電話をかけて訊こうとしたのだが、教えてくれなかったのだ。
──錠也?
「うどん」のメモリーを呼び出して電話をかけると、相手は即座に応答した。まるで待っていたかのような早さだった。いや、実際に待っていたのかもしれない。
──このあいだのことは、俺、すごく迷ったんだ。黙ってたほうがいいとも思った。でも、どうしても確かめておきたくて。なあ錠也、ほんとはどうだったんだ? お前こないだ、いきなり帰っちゃったけど、俺のお父さんが──。
そこで、ふと言葉が途切れた。愛想よく喋る男の人の声が後ろで聞こえていた。中古車販売の店で営業をやっていると聞いていたから、たぶん事務所の中だったのだろう。
──ただの同姓同名だよ。
僕が先に言葉をつづけた。
──うどんのお父さんが撃ったのが、たまたま僕のお母さんと同じ名前の人だったってだけ。僕のお母さんはちゃんと生きてる。最近になってわかったんだ。まだ会ってはいないんだけど。
用意していた噓を並べた。
──こないだは、ちゃんと言えなくてごめん。いろいろあって、いまちょっと母親の話とか、したくなかったもんだから。
──そっかあ、よかった。
相手はあっけなく信じた。
「うどんって……順平くんのこと?」
戸越先生が訊く。
「そう、迫間順平。あいつの住所を教えてください。園を出たあと住んでる場所。そういうの書いてある、書類みたいなのがありますよね?」
戸越先生はしばらく黙ってから訊き返した。
「……どうして?」
昨日、電話で本人に住所を訊いたときも、まったく同じ言葉が返ってきた。
──どうして?
──今度、遊びに行こうと思ってさ。
──でも、うちはお父さんがいるし……お父さん、いま仕事を探している最中だから、ほとんど家にいて。
──いいから教えてよ。
長い沈黙のあと、迫間順平はやっと声を返した。
──ごめん、ちょっと、教えたくない。
その様子からして、これ以上頑張っても無駄だなと思ったので、僕はそのまま電話を切った。だから今日、こうして青光園までわざわざ電車を乗り継いでやってきたのだ。何としても迫間順平の住所を訊き出して帰らなければいけない。
「うどんの家に、遊びに行こうと思って」
「順平くんに確認してからでもいいかしら?」
それでは同じことになってしまう。いや、青光園に行ってまで住所を調べたと知ったら、ますます怪しまれ、絶対に教えないでくれと彼は言うだろう。
「確認なんて、しないでいいですよ」
「そういうわけにはいかないわよぉ」
「平気です」
「平気じゃないわ」
「戸越先生の住所、僕、知ってますよ」
知らないけど言ってみた。
「ここからどうやって、どの道を通って家に帰るかも知ってます」
弱い電流でも流れたように、戸越先生の頰がぴくっと動いた。そのあと顔全体が固まって、でも唇だけがまた笑った。
「どうして……そんなこと言うのかしら?」
どうして。どうして。どうして。僕が理由を教えたくないのに、みんなそれを知りたがる。僕はいっそ理由をはっきり話してしまおうかと思った。迫間順平の家に行き、父親の田子庸平を殺すのだと。でもやっぱりやめた。そのかわり、ただ相手の顔を見た。目と目が真っ直ぐにぶつかった。戸越先生は相変わらず唇の両端だけを持ち上げたまま動かずにいる。しかし、僕がその目を見つめつづけていると、全身がほんの少しずつ、ゆっくりと前後に揺れはじめた。本人は気づいていないようだった。僕が片手を上げて先生の肩を摑むと、その動きはぴたっと止まった。
「メモしてきてくれるだけでもいいんです」
指先に、少し力を込めてみる。
「僕、ここで待ってますから」
やがて戸越先生の咽喉の上のほうから、嬉しくてたまらないという声が飛び出した。
「遊びに行ってあげるなんて、友達思いなのねぇ」
そして急に身体ごと横を向いた。
「じゃ、ちょっとメモしてくるわ」
そのまま園舎の中へよちよち歩き去り、しばらくすると正方形の黄色い付箋を手のひらに隠すようにして、必要以上の自然さで歩きながら僕のところへ戻ってきた。かかった時間から考えて、誰とも余計な話はしていないようだ。付箋には、さいたま市ではじまり202で終わる住所が走り書きされていた。
「僕が来たこと、誰にも言わないでくださいね」
「どうして?」
「どうして?」
「うん……どうしてかしら……と思って」
「どうしてもです」
付箋を手に、僕は青光園をあとにした。
メモされていた住所までは、けっこうな時間がかかった。でも、電車に乗っているあいだも、歩いているあいだも、田子庸平を殺す方法について思いをめぐらせていたので、退屈はしなかった。夕暮れ前にたどり着いたアパートはぼろぼろだった。外階段の下に並んだ錆だらけの郵便受けには、みんな自分の名前を書いておらず、202号室も同じだった。開けて中を探ってみたが、チラシしか入っていない。
ひび割れた外階段を上って部屋の前に立った。「202」というプレートの下に、別のプレートが貼られ、何か書いてある。太陽にさらされて、かなりわかりにくくなっていたけれど、どうやら「迫間」と読めた。下手くそな字で、とくに二文字目は、「門」と「日」のバランスが無茶苦茶だ。
「軍手、軍手、と」
ポケットに用意してきた軍手を装着し、呼び鈴を押す。返事はない。しかしドアに耳をくっつけると、物音が聞こえた。そうして耳をつけたまま、もう一度呼び鈴を押してみた。
「田子さーん」
室内の物音がぴたっと止まった。
「田子庸平さんにお届け物でーす」
しめったような足音が奥のほうから近づいてくる。
鍵が回され、ドアが内側からひらかれる。
初めて目にする田子庸平の顔は、思っていたほど凶悪そうではなかった。妊婦をショットガンで撃つような人間には見えない。ただ、身体が縦にも横にも大きく、もし暴れ出されたりしたら、すごく手こずりそうだ。
「田子庸平さんですか?」
念のために訊いてみると、相手はどろんとした目で頷き、僕の顔を見て、破れたダウンジャケットの袖を見て、また顔を見た。仕事を探していると言っていたけれど、田子庸平の顔面は無精ヒゲに覆われ、とてもそんなふうには見えない。迫間順平は電話で僕に噓をついたのだろうか。それとも父親のほうが息子に噓をついているのだろうか。
「……ものは?」
「はい?」
「届け物って言ったろうが」
そうだった。
「大きなマッサージチェアなんです。迫間順平っていう方からのご依頼でお届けに来ました」
どろんとしていた目に、ふっと芯が入る。
「商品、いま下にあるんですけど、運んでくる前に設置場所の確認をさせていただかないといけないので、ちょっと、いいですか?」
僕が中を指さすと、田子庸平は急に「おうおう」と嬉しそうな声を出して脇へよける。僕は「失礼しまーす」と言って三和土に入った。後ろでドアが閉まる音を聞きながら、スニーカーを脱いで家に上がる。短い廊下の右側に、生ゴミと汚れた食器で埋まったシンクがある。廊下の奥にある部屋は、六畳くらいだろうか。布団が二組、大きなロールケーキのように丸められて、腰窓の下に寄せられていた。
「なにお兄ちゃん、あいつが注文してたの? 驚かせようと思って? いやごめん、そんなのわかんねえか、ごめんごめん。あいつぜんぜんそんなこと言ってなかったからさ。なんだよマッサージチェアかよ、まいっちゃうね。でかいんだろうけど、端っこに置けるんじゃねえかな。奥のほら、右のほうとか」
意外と饒舌な田子庸平の声を聞きながら、流し台の下の戸を開けてみた。包丁ラックに月並みな包丁が一本挿さっている。それを抜き取り、先っぽがちゃんと尖っているかどうかを確かめた。
「お兄ちゃん、何してんの?」
僕は振り返りざま田子庸平の胸を包丁で突き上げた。濁点そのもののような短い息が口から飛び出し、顔に唾がかかった。腹を蹴って向こうへ追いやると、田子庸平は両手を左右に広げ、大きな身体で狭い廊下をいっぱいにしながら後ろ向きに飛び、玄関のドアに後頭部を激突させて沈み込んだ。両足はこちらに投げ出され、三和土がちょうど浅い風呂のようで、部屋着のままそこに浸かっているみたいだった。
「自分のせいなんだから、しょうがないよ」
近づいていく。田子庸平は根元まで胸に刺さった包丁を、まるで僕がいまから盗んでいこうとしているように、両手でしっかりと握っている。目だけが僕の顔を追ってくる。黒目がぶるぶる震えている。上唇と下唇が、互いにつぶし合うようにきつく結ばれ、鼻の穴が信じられないほど広がって、出入りする空気が甲高くかすれた音を立てる。僕は相手の脇に移動してしゃがみ込んだ。ふくらんだ両目が、やはり顔を追ってくる。包丁の柄を握る田子庸平の手を、外から包み込むようにして摑み、上下左右に動かしてみた。大きくなった鼻の穴から、ひどくこもった、はるか遠くから聞こえてくるような声が洩れた。しかしそれも、しばらく柄をぐりぐりやっているうちに小さくなっていき、やがて消えた。
無精ヒゲの生えた田子庸平の顎に手を添え、ぐっと下へ力を加えてみる。口が箱みたいにぱかっとあいた。意外にも田子庸平はきれいな歯並びをしていた。父子で顔のつくりは似ていないけれど、ここは遺伝していたのだろうか。
「死んでる?」
返事はなかった。
アパートに戻ると、ちょうど注文していたものが宅配便で届いた。
(この続きは本書でお楽しみください)
▼道尾秀介『スケルトン・キー』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321801000184/