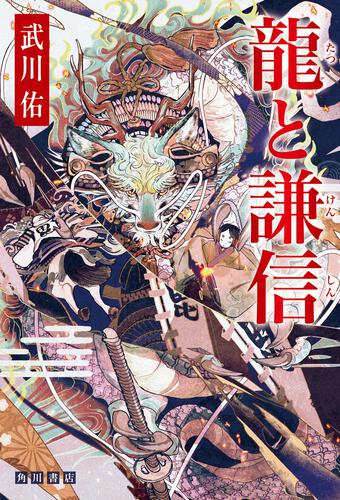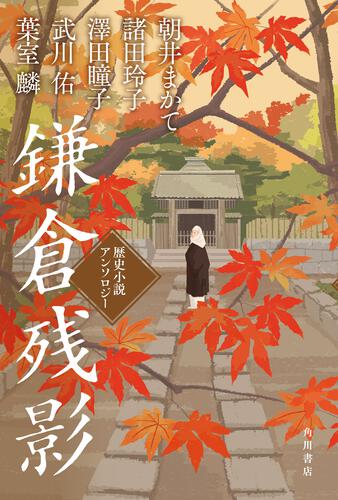戦国大名・
決して交わらぬはずの運命だった二人が、愛憎を超えて結んだ絆とはなんだったのか。
そしてなぜ、彼女は後世、いないことにされてしまったのか――。
史実を忠実に読み解き、最新資料を踏まえて描かれた物語の幕開けを、どうぞお楽しみください。
武川佑『龍と謙信』試し読み
「
まあ、
ああ、あなたのほうがそのへん御詳しいでしたわ。義の武将などとおもしょいことを
あ、いや、御気を悪くなさいますな。
あなたはあれでよかったと思いますか。なぜそんなことを聞くのかと。
あなたは、
御新造? はあ耳慣れない言葉でしたか。奥方の
そうですなあ、おもしょい御二人でしたなあ。みなの思うような
「ではこれからも、上杉をよろしゅう御頼み申す」
第一章
他人のものを盗んではいけない。仏教五戒の一。
〇長尾景虎書状
対晴景、黒田和泉守年来慮外之刷連続之間、去秋此口へ打越、可加成敗分候之処、其身以異像之体、可遁他国之由、累歎之候間、任其旨、旧冬当地へ相移候処、無幾程逆心之企現形之条、即以御屋形様御意、黒田一類悉愈為生害候、依之、本庄方へ被成御書候、爰元之儀、定可為御満足、恐々謹言、
二月廿八日 長尾平三景虎(花押影)
小河右衛門佐殿
(上越市史 別編1 P4―五)
一
――「わたし」が語る。
雪囲いをした屋敷にも、
童は舞い終えると深く平伏し、退出した。
舞を見物していたあなたは、ほっと息を吐く。
鼓を袋にしまった晴景が、娘のあなたに笑みを向けた。
「
「なんでございましょう」
やや
母が玉手箱のような真新しい
「於龍や、これは我が
箱から取り出されたのは、大人の片手に納まるほどの大きさの、
母は
「男雛は我が上杉家、女雛は長尾家に代々伝わったもので、私が長尾に嫁したことでもともと一対の物とわかり、そなたに授けようと晴景さまと話したのですよ。
母は生まれたばかりのあなたの弟、
「くたびれてはいるけれど、そなたが継ぐべきものです。私の幼いころも、この人形が友だったのですよ」
於龍と名づけられたあなたは、上杉と長尾、両方の嫡流の血を引く位の高い娘だ。
まだ九つのあなたの小さな手では、人形は片方しか手に取れない。どちらを手にするかあなたは迷った。ほんとうは袍に烏帽子、立派な太刀を
あなたは長尾家に伝来した女雛を取り、
「
母は鼻を鳴らし、我が子へ唇だけの笑みを送った。
「あなたは綺麗な衣も貝あわせも興味を持たぬから、心配していたのですよ。十二単の衣が古びて汚いわね。いい裂を探して新調しましょう」
父はあからさまに喜んだ。
「於龍は無口だからのう。いずれ好きなものもわかろうて」
主君を討つ下克上をなし、近隣に恐れられ、隠居してなお国主然としていた為景は、七年前に逝った。晴景が跡を継ぎ、ようやく越後に平穏が訪れるかに思われた。
障子の外で
「すこし外す。於龍、母さまと遊んでおれ」
晴景が出ていくときに吹きこんだ風で室内は底冷えし、外の音がよく聞こえた。あなたは耳を澄ました。馬の鼻息、雪を踏みしめる
四半
女雛を抱いたまま、あなたは立つ。母も静かに障子に手をかけた。なにかただならぬことが起きている。母子二人は身を寄せ、足音を忍ばせて屋敷の表に回った。
凍て風が鋭く鳴り、粉雪が踊る。
あなたの目に飛びこんできたのは、馬場に
肩や頭に雪が積もり、長いあいだ雪中を歩いてきたのだと知れた。最前列にまだ少年とも言える小柄な子がいて、あなたの目は吸い寄せられる。
少年は、黒い羽織の下に黒い腹巻を着こんだ具足姿だった。横には青ざめた男の首が置かれていた。
雪に、点々と血が
黒々とした少年の切れ長の目が、あなたを見る。よく通る甲高い声で言った。
「
あなたはなにが起きているかわからず、名を繰り返した。
「平三景虎――」
家臣に「御城」と呼ばれる晴景の、腹違いの弟。於龍にとって叔父にあたる少年は頷いた。
「
父の晴景が、強張った顔で振り返る。父の脇に控えていた童が首を隠すようにさっと動き、あなたと母に
「
さきほど舞を舞った童だ。
蛟に手を取られ、母子は屋敷の奥へ戻された。母がどっと膝を突く。
「なにが起きている。晴景さまの進退を諮るとは、謀反じゃ」
注意深く表を窺い、蛟という童が戸を閉める。
「謀反といえど家中ほとんどの臣は景虎さまについたかと。重臣の直江さま、
「
蛟が沈痛な顔で首を振った。
「風聞にございますが、守護の上杉定実さまも、景虎さまを支持しておられるとのこと」
けたたましく具足が鳴り、屋敷に人が踏み入ってくる。晴景が当主の座から「降りた」、つまり景虎たちの要求を
「父上までも! 私を見捨て申したか」
金切り声をあげ、母はあなたの手を
目を血走らせた「女」が白い手を伸ばす。
「
「黙れ
一喝された蛟が平伏する。助けはないのだとあなたは悟った。荒々しく衣を脱がされ、髪を摑まれた。手に
「お主は今日から男、晴景の嫡男になれ。平三景虎など認めぬ。平三景虎を討て」
「ははうえ、痛い」
「長尾など格下に嫁ぎとうなかった。長尾なぞ、長尾なぞただの
摑まれた髪はいくらか根元から抜け落ちた。あなたの悲鳴に耳も貸さず、母はざくざくと髪をそぎ落とす。涙でにじむ目で見あげると、薄笑みを浮かべた女の顔があった。
「安心せよ、猿千代が元服するまでの
「私は、人形」
あなたの頬を髪に
「よいか、男など柔順なふりをして
髪を切られ、
ほかにどんな道があった?
五年が経った。
於龍は十四歳、平三景虎は二十四歳になった。
病がちだった父の晴景が肺病で死んだ。それから六日経った
「龍姫さま。
於龍の前に、見あげるような大男が立ちふさがる。頬骨から耳にかけて五寸(約十五センチ)あまりの刀傷がはしり、鼻の右半分は
於龍の声はいつも、よく通った。
「愚か者ッ、太刀を抜く相手が違うぞ! 私を誰と思うておる。越後守護上杉家の血を引く、長尾の嫡流ぞ。
於龍は「平三景虎」ではなく、幼名の
考えてきた文言以外は口下手らしい大男は、うう、と口をもごもご動かした。
「い、いまの
「お主は山賊まがいのことをしていたときに、虎千に取り立てられたそうだな。
「う、うるさい、女子が偉そうに! おれは御実城の恩に報いるんだっ」
長尾の家督を父から奪った景虎は、自身を「御実城」と呼ばせている。
長尾為景の次男に生まれた景虎は、七つのときに
国府から離れた
あとは於龍が九つのときに見たとおりだ。晴景の腹心であった黒田和泉守および一族を家中専横の咎で皆殺しにし、晴景にその首を突きつけて進退を迫り、家督を奪った。
それから五年。母によって男と
だが、事前に決起は漏れた。
「一番の不義者は、虎千ではないか。兄から家督を奪うなど
「う、ううるさい、御実城は
「木島どの、口じゃ
於龍の一つ年上である旅芸人の少年。寒さで肌の白さが際だち、頬は上気していた。栗色の髪を結いあげ、紅梅と
思わず於龍は目を見開いた。
「蛟、お前――」
「龍姫さまごめんなさいねえ」紅を差した唇を、蛟はほころばせた。「あたしは芸人だけど、
「裏切ったのか」
「主は長尾家ですもの。もとからあなた一人についたつもりはございません。ねえ龍姫さま。女のくせに男の
「…………」
蛟の笑みが
「弟の猿千代さまも、ぽっくり死んじゃいましたしねえ。諦めて姫に戻り、どこぞに嫁に行けばよかったのに」
景虎を追い払ったのち、正嫡として
母は息子の死から目を背け、計画は変わらなかった。於龍は、母を
「龍姫さまの
言うと、蛟は引きずってきた女を放りだした。殴打され顔を
「母上。ひどい、こんなことが許されると思うな」
駆け寄り母を助け起こそうとすると、手を払われた。母は
「謀反は……於龍の
くすくすと蛟が笑う。
「だそうですよ、龍姫さま」
於龍の体はすっと冷えた。五年間すべて母の言うとおりにした。病で弱った父には会う必要がないと言われたからそうした。優しい父に会えないのは悲しかったが、家のためだと言われれば反論のしようがない。女言葉を
母が機嫌よくいてくれたら、それでよかった。
「そう、ですか。母上は無関係ですよね。謀反は私一人の企て」
太刀に手を伸ばす。どかと胡坐をかき、左手で着物の
「責を負い自害する」
そのとき、男が怒鳴りこんできた。みな、ぎょっとその男を見た。
「だちかん! だすけ殺しちゃならんと言ったがね!」
地言葉丸出しの甲高い声。五尺一寸(約一五五センチメートル)の中背に、紺の
これがいまの平三景虎だ。父の臨終の場で久しぶりに会ったが、家督を退くよう雪中押しかけたときの鋭さはまったくなく、「これがら長尾とわしはどしょば、
「於龍よ。そんな形をさせて、すまぬ」
「いえ……」
「景虎を、憎まないでやってくれ」
それが父の最期の言葉となった。
「なにしちょるが! みな出ろ、出ろ!」
景虎の声で於龍は我に返る。戸惑う木島という大男、蛟や母を追いだし、景虎は戸をぴしゃりと閉めた。於龍の薄い腹を凝視し、太い眉を
「腹の
「…………」
「
数度深く息を吸い、於龍は
「お前に言うことはない」
細い吊り目を見開き、景虎のこめかみに青筋が浮く。
「お主は殺さぬ」
「女だからと手心を加えられたくない」
「違う!」怒鳴り声を発し、恥じたように景虎は
於龍は小刻みに震えはじめ、手元の太刀が鳴る。それを見た景虎は、穏やかに言った。
「もうええじゃ。
「
不思議と悔しい気持ちはなく、胸がすっとした。於龍がさっと太刀を抜き
「お前、潔くて
袱紗に血の染みが広がるのを、於龍は凝視した。
「お前、指が」
「だーすけ、だめらて。まったくいちがいこきは誰に似たんら」
於龍の力が緩んだ隙に、景虎はさっと太刀を取りあげた。早業だった。太刀を背に隠し、引きつった笑みを浮かべる。
「於龍、秋にわしと
「……は?」
「行こ!
なにを言っているのか理解できず、於龍は目を白黒させた。
いつのまにか母は幾人かの侍女とともに屋敷から姿を消し、屋敷には於龍一人になった。寝所の外には武装した兵が数人詰めて、出ることもできない。
夜、つめたい床のなかで於龍は「
薄汚れても微笑みつづける少納言の君の顔を、於龍はそっと撫でる。母が衣を裂で新調しましょうね、と言った約束は果たされぬまま、金糸の
「聞いて少納言、父上も母上もいなくなった。これから私はどうなってしまうの。でも、なぜか――怖くはないの」
二
謀反の発覚と、父・晴景の死から
於龍は京へ向かう船に乗りこもうとしている。
思えば越後の国を出るのも、それ以前に国府一里(約四キロ)四方から離れるのも初めてだ。だのに、心は凍てついてなにも感じない。
上洛の目的は、将軍・
国府とほぼ隣接した
留守居役を務める白髪まじりの臣が於龍にちかづいてくる。雪中景虎とともに晴景に引退を迫った重臣「直江、本庄、大熊」の一人、栃尾城主・本庄
いつもの
「半年も御屋敷に
謀反の責を負う「
於龍のもとを、晴景の同腹の妹にあたる
「景虎は見てのとおり思慮が足りぬのです。
細面で神経質そうな叔父の政景が「お前、いくらなんでもそれは」と言い
「お主は、私たちがかならず助けます。お主は長尾に必要じゃ」
政景は「私たちとは、わしも勘定に入っておるのか」と不安げにしていた。
厚情に感謝しつつ、於龍は叔母夫婦の好意の源がわからず、
本庄実乃はそれらのどれとも違い、於龍に深く頭をさげた。
「もう、龍姫さまの好きな衣を召されてよいのですよ。京で上等な反物を求めるのもようございましょう。於桃さまからは新たな打掛と小袖を贈られたそうで」
「…………」
無言で睨み返すと、実乃は額を
「差し出がましいことを申しました。御無礼を」
二人の横を、景虎の
長尾は「守護同格」だと将軍の公認を得たことになる。
於龍は馬と傘をじっと見据え、ようやく口を開いた。
「御免状と官位を頂戴するのに、どれだけ
実乃は額を打った。
「またまた御無礼を。母君に担がれた哀れな姫君と、
早口で言って、実乃は軽く肩を
「年寄りは口ばかり回って。御許しくだされ。出立前にひとつ御耳に入れたく」
軍神と
「申せ」
「『某ども』は御謀反発覚のおり、龍姫さまを片づけるべき、と申しました」
「ほう。つづけよ」
実乃の
「龍姫さまが
「某ども、とは誰か。お主、大熊
実乃は背を伸ばし、声を
「いやはや、恐れ入り申す。みな、国がふたたび乱るるを恐れておるゆえ」
「
実乃は素直に認めた。
「さようにございますなあ……」
祖父の長尾弾正
「某を恨む気持ちはそのままで結構、なれど、どうか景虎さまを御恨みくださいますな」
「みなそう言う」
父もおなじことを言っていた。みななぜ景虎を
「黒田を族滅せよと決したのは、あなたさまの父上、晴景さまにございますぞ」
於龍は足を止めた。
荷を狙う海鳥たちの鳴き声と羽音。
「黒田和泉守の
於龍の両腕はだらりと垂れた。
――ああ、父上が「景虎を憎まないでくれ」と仰ったのは、こういうことだったのか。
於龍は唇をきつく
なんのために手の皮が裂けても木刀を振り、月経を止める薬を飲み、耐えつづけたのだろう。
「左様か」
「御実城
「景虎は、命に従っただけと申すか」
「道中見聞を広めてくだされ。さすれば、景虎さまの
家臣団の列に戻ってゆく実乃の背中に、於龍は
「道中すこしでも景虎が隙を見せれば、寝首を掻いてやろうぞ」
腰に
凍りついた心がわずかでも動くのは、景虎への害意を募らせるときだけだ。於龍は己に言い聞かせる。
長尾の嫡男の長子で、上役の上杉の血を引くのは誰だ。そうとも自分だ。私は長尾家中もっとも格が高い。妾腹の末弟ごときをのさばらせるわけにはいかない。
心のなかで繰り返し呟く。
直江津を出た二
二艘立てのうち、さきを行く大きな一艘には、領国内の通行許可を示す朝倉家の
「物見遊山気取りか」
船の
首からさげた御守りを、於龍は無意識に摑んだ。母が手ずから縫った
景虎は義姉にあたる於龍の母をほんとうに尼寺に入れ、不自由ない暮らしをさせているらしい。この御守りも長々とした文とともに届けられた。謀反露見のときに「自分は無関係だ」としらを切ったことは都合よく忘れたようで、長尾に対する恨みつらみが長々と書かれていた。於龍は途中で読むのをやめ、
のんびりとした声が
「
振り返ると、蛟が帆柱に摑まっていた。京に行くと張り切って
「この蛟が憎らしいでしょう。でも謝りませんからね。あたしは御家の命に従っただけ」
於龍が黙っていると、蛟は整えた眉を
「ねえ、その
男形は母に
それをうまく他人に説明し、理解してもらえるとは思えなかった。
蛟に強引に手を引かれ、艫屋形に入る。後方に積まれた荷から行李を降ろして、蛟は喜色満面で蓋を開いた。
「わあっ。金糸の刺繍ですよ。手がこんでますねえ、いいなあ」
打掛は薄桃色の唐草文様の地紋が織り出された
「龍姫さま?」
「これは、嫁入り用の衣だ」
上洛は、京へ於龍を嫁に出すことが目的の一つなのだ、とようやく気づいた。出航前、本庄実乃が「京で健やかに」とまるで越後に帰国しないかのような口ぶりだったのも、納得がいく。家中みな承知だったのだ。
藍の小袖の
「やだ、御顔が真っ青ですよ。酔いましたか」
「これが……いいんだ。これじゃなきゃ嫌だ」
腹がちくちくと痛んできた。母に飲まされた怪しい薬を飲まなくなって半年、月経が戻ってきたらしい。蛟の溜息が聞こえる。
「真に龍姫さまがそう思ってるなら、蛟はもう言いません。けどね。『角のない牛』と言われ朝から晩まで働き、子を産んで
百姓の女には百姓の女の
「畜生」
嫁ぐなど絶対に
女ゆえに元服もできない。於龍はもはや子供でもなく、かといって大人でもなかった。
――波に
揺れる艫屋形で体を抱きしめ、於龍は一人
一日、三国湊で嵐をやり過ごし、出航。敦賀湊へ入船後、すぐに陸路の峠越えとなった。
古くは
抜けるような秋晴れ、栃や
二十間(約三十六メートル)ほどさき、長尾の行列の先頭で、房飾りのついた白い傘袋が揺れている。あのもとに景虎がいるが、上り坂でも白い行者
「長尾弾正少弼どのの御成である、道を開けよ」
先触れの声に、白い真新しい
修験者さいごの一人は十七、八の青年だった。朱漆塗の
蛟が小走りでやってきて、馬上の於龍へ伸びあがる。ほかに見知った年ごろの者もおらず退屈なのか、裏切りなど気にとめていないのか、しょっちゅう話しかけてくるのが
「ねえ龍姫さま、さっきの美男見ました? いい身分の武家さまが変装していたりして」
青年の修験者のことだろう。美男かどうかは見る人によると思うが、たしかに山野を修行場とする
「
「んもう、張りあいがない」
そのとき、後方で「無礼者」と怒声があがった。振り返れば、さきほどの修験者を追い越そうとした魚売りの女の一人が木の根に足を取られて転び、背負った桐箱を道にぶちまけていた。銀色、桜色さまざまな魚が転がり、潮の濃い匂いがたつ。桐箱の一つが例の青年修験者にぶつかりでもしたのだろう、ほかの男たちが転んだ女を
知らずのうちに、於龍は腹を押さえていた。懐には袋に入れた女雛「少納言の君」をひっそりと隠し持っている。
それに気づかず、蛟が眉を
「蛟はうすのろが嫌いです、いい気味だ」
魚売りの親方がすっ飛んできて、転んだ女に
「売り物を駄目にしたうえに、人様に迷惑かけやがってこのっ」
於龍の口が動いた。
「やめよ」
(気になる続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:龍と謙信
著 者:武川 佑
発売日:2025年07月02日
大藪春彦賞受賞後第一作、謙信の妻を描く、初の歴史小説!
上杉謙信と、その妻・於龍
「奇妙(クィア)」なふたりは
憎悪も、愛情も、超えてゆく!
「抗え、戦え、歩みを止めるな。
かつても今も在り続ける魂の叫びに寄り添う物語」
澤田瞳子、推薦
父から越後守護代を奪った長尾景虎(後の上杉謙信)への復讐のため、母から“女”を捨てさせられた於龍。彼女は景虎を激しく憎むが、当人はどこ吹く風で、於龍のことを「面白(おもしょ)い奴」と気に入ってしまう。長尾の重臣たちが二人の婚姻を越後支配のために利用する一方で、甲斐の武田晴信(後の信玄)は隣国侵攻の調略を始めようとしていた――。史料を丹念に読み解き最新研究を踏まえ、生涯独身と言われてきた上杉謙信と、その妻の半生を鮮やかに描く。
謙信の妻・於龍は、どんな女性だったのか?
そしてなぜ、歴史の陰に消えたのか?
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000975/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら