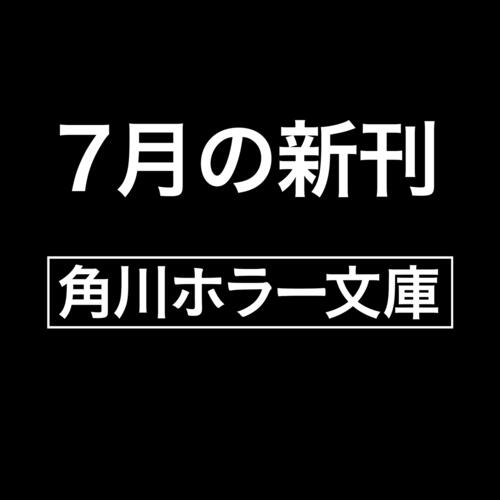「この本ができあがるまでに、編集者が二人消えています」
不穏なキャッチコピーで飾られた黒い文庫が、カドブン編集部に届きました。
タイトルは『身から出た闇』。
2025年10月3日(金)に映画公開を控える『火喰鳥を、喰う』の著者・原 浩さんによる新刊です。
添えられたメモ用紙には「試し読み掲載希望、68ページまで」と記されています。
どうやら編集者からの依頼のようですね。
それでは、さっそく――
本記事では『身から出た闇』の刊行を記念して、収録短編「トゥルージー」がまるごと読める大ボリューム試し読みを特別公開!
序章・幕間として掲載された「編集者との打ち合わせ」の様子も一部ご覧いただけます。
それにしても、角川ホラー文庫の真実とは?
読み進めれば、何かがわかるかもしれません。
どうぞお楽しみください。
原 浩『身から出た闇』試し読み
序章 角川ホラー文庫
最初の打ち合わせが行われたのは五月中旬のことだった。
場所は
ラウンジに向かうと
三人とも私とは年齢の離れた若い女性である。今井は私のデビュー当初からの担当で、この中では編集者としてのキャリアが最も長い。数年前に単行本から文庫本の部署に異動し、現在では拙作の文庫刊行を担当してくれている。和田は以前ライトノベルの編集を担当していたそうだが、今井の部署異動を引き継ぐかたちで私の単行本の担当編集者となった。
今回ほぼ初対面の菰田は、新卒入社からまだ数年というところだが、今後今井に代わり私の文庫本担当になるとのことで、徐々に今井の業務を引き継いでいくそうだ。彼女はこの打ち合わせには顔合わせを兼ねて参加してくれていた。今井によると、「菰田は誰よりもホラー文庫に向いているって編集長も太鼓判なんです」とのことだ。角川ホラー文庫にして期待の新人ということらしい。
新宿の眺望と
今井がいつものように
「
当時私は単行本三冊を
「原さんの良さを
今井の言葉に和田が
「以前プロットを頂いた『
「ああ、あれは主人公が作家だったっけ。そうね、それよりは一般的なキャラにしたほうが読者には受け入れやすそうかな。……原さんはどう思われます?」
「キャラ設定を変えるのは全然。ただ、因習村とか、もうお腹いっぱいな気もします」
「あはは。確かに」
私はふたりの話に時折合いの手を挟みながらも、自分自身が強く書きたいものが無いことに気づいていた。ただ執筆意欲はあり、どのジャンルでもある程度対応できるだろうという根拠の薄い自信もある。だが、このホラーをどうしても書きたい、という欲求に乏しいのだ。これは作家としてあまり良い在り方ではないだろう。
やがて議論は散漫になり、テーブルからケーキ皿が片付けられ、残った紅茶がすっかり冷めても結論には至らなかった。その時、不意に菰田が口を開いた。
「短編集とかどうでしょうか」
菰田はそれまであまり議論に参加していなかった。三人の編集者の中で最もキャリアが浅いということもあるだろうし、初参加の遠慮もあっただろう。だが今井は菰田の言葉に救われたように、文字通り
「ああ、短編かあ。それは考えてなかったけどアリだね。どうでしょう原さん、短編集とかは」
「ええと、書き下ろしでホラーの短編ですか……」
考えを巡らせるふりをするが特にアイディアはない。長編についてはあれこれと検討していたが、正直ホラー短編については何も考えていなかったのだ。幾つも別個のネタが必要になり検討の手間はかかりそうだと思った。だが執筆自体は楽しそうだ。私は短編集という方向性に同意した。
となると短編集としてのテーマは何が望ましいのか、という議論に結局は戻ってしまう。話が進みそうで進まなかった。長丁場になりそうだと私が感じ始めたところ、
「怖ければ何でも良いのでは」
という、菰田の一言で場が落ち着いた。
怖ければ何でも良い。確かにその通りではある。こうして文字に起こしてみると、どうにも素朴というか投げやりにさえ聞こえる意見表明ではあった。しかし、その時はどういうわけか不思議と説得力が感じられたのだ。今井も和田も私と同様に感じたのか、まあそうだねと、ぽつりぽつりと同意した。
私は三人に今後の進め方を話した。
「短編なので、ひとつひとつにそれほど時間はかからないと思います。プロットをいくつか考えつつ、それと同時並行でとりあえず一本書いてみます。駄目だったら、それ、没でも構いませんし」
私の言葉に今井が首肯しつつもこう提案した。
「でしたら、最初の一本はこれまでにない何か新しいネタがいいですね」
「新しい?」
「せっかく原さんに書いて頂けるのですし、他でやりつくされたようなものではなく、読者にとって日常にありつつも、何か目新しいネタが良いなと思うんです」
彼女の言わんとしていることはわかる。けれど日常にあり、なおかつ新しいといってもなかなかに難しい。近頃何か目新しい体験を得られなかっただろうか。その時、目の前の席に座る菰田が、ふとテーブルに置かれた自分のスマホに目を落とした。それを見た瞬間、私は自分の頭に浮かんだことを話した。
「SNSとかどうですかね」今井がふと微妙な表情をしたが、彼女が所感を漏らす前に私は言葉を足した。「もちろんSNSをテーマにしたホラー作品など今では珍しくはないと思います。けど、ああいうサービスってどんどん新しいものが出てくるじゃないですか。私の世代では理解不能なものもあって、それを取り上げたら新鮮な切り口になるんじゃないかと」
SNSはその内容によって利用する年齢層の差が大きい。中には大半の利用者が十代で占められているようなサービスもある。そうした世代間の
こうした経緯でホラー短編集の企画が立ち上がったのだった。
今にして思うのは、この時、私が短編集の企画を受けさえしなければ、現在の状況はまた違ったものになっていたのではないかということだ。
補足する。
本来短編集を編むには、読者により劇的な読書体験を提供できるよう掲載順も慎重に吟味されるべき要素である。だが、本書については私が書き上げた順番に掲載する形式を採っている。
また、言うまでもなく、これらの短編は全て創作である。
トゥルージー
「――だから節度だよ節度。お前には節度ってものが欠けているんだ。今回に限らず、いつもそうだぞ。集合時間とか、提出期限とか、そういうものを遵守しようとする意識も薄い。根本的な意識の問題なんだぞ。約束事を守らない人間は信頼もされなくなる。結局は自分が損をすることになるんだ。うちの高校はスマホ持ち込みOKにはしているけどさ。授業中の使用は厳禁だって知ってるよな? それを分かっていて、どうして使ったんだよ。どうして決まり事を破るんだ。
「はい。反省しています」
私の隣で身を縮こめていた亜美は小さく答えると、しおらしく頭を下げた。彼女らしくもなく、さっきからさも落ち込んだように
「いいか。次にまたこういうことがあったら、スマホの持ち込みは全面禁止にするからな。そもそも生活に
そう言うと原田先生は机の上にある亜美のスマホを指で突いた。それを横目に亜美はこくりと頷く。
「はい。そうですね」
反論もせずに殊勝な態度を続ける亜美だけど、もちろん本心で言っているわけではないだろう。三十代も半ばを過ぎたおじさんと高二女子の私たちとでは時代が違いすぎる。スマホが無い高校生活なんて想像もできない。今では必須以外の何ものでもないのだ。無くなったら不都合なんてもんじゃない。生死に関わる。そもそも原田先生たちの時代は、どうやって友達と
心の声が届いたのか、原田先生の目がいきなり私に向けられ、ギクリとした。
「
原田先生の説教口調に、「はい」と答えながらも、何で私まで怒られなきゃならないのかと、納得いかない気持ちになる。授業中にスマホを使っているのがバレて没収されたのは亜美なのに。私はその亜美に頼まれて職員室に付き添ってきただけだ。
「とにかくこれは返すけど、次から気をつけろよ。二度はないぞ」
そう言って、原田先生は亜美のスマホを差し出した。亜美は頭を下げたまま両手を伸ばし、恭しくそれを受け取った。
「ありがと先生。大好き」
原田先生は
亜美は受け取るなり、先生の目の前でスマホの画面に触れると「うわ、通知
ため息をついた原田先生と目が合ってしまった私は愛想笑いで取り繕う。
原田先生は苦い顔をして、スマホに目を落としたままの亜美に言った。
「お前さあ。何も授業中にまでインスタやんなくていいだろう。終わってからゆっくりやれよ」
「インスタじゃないですよ」と、顔も上げずに亜美が答える。
「え、だって写真撮ってなかったか?」
「トゥルージーです」
「なにそれ」
亜美はぱっと顔を上げると、信じられないという顔を先生に向けた。「噓。知らないんですか? 先生だって名前くらい聞いたことあるでしょ」
「いや無いが」
「やば。だって普通に生きていたら自然と耳に入るでしょ」
「入らねえよ」
原田先生はますます苦り切った顔になる。私は慌てて隣から補足した。
「今
「写真共有。インスタと同じじゃないか」
「ぜんっぜん違いますよ!」と、亜美が不満そうに声を上げた。
「インスタと違って一日に一度ランダムな時間に一斉通知が来るんです」私はさらに補足する。「通知が来たら二分以内に写真を投稿しなきゃならなくて。まあ、二分以内じゃなくてもいいんですけど、それだと写真は一枚しか投稿できないんです。通知が来て二分以内に投稿できたら、その日は無制限に写真をアップできるっていう特典があって」
「なんだその面倒なアプリ」
「別に面倒じゃないですよ。ぱぱっと写真撮るだけだし」と、亜美がスマホをかざして見せる。
「ぱぱっと撮れるかあ?」原田先生が首を傾げる。「だってお前たち、盛ったり、
原田先生に目を向けられたので私が答えた。
「トゥルージーは『真実を映す』っていうのがコンセプトらしいです。写真に加工とかも出来ないようになっていて、撮り直しも制限があるんです。なので基本、撮ったらそのままアップします」
「それじゃ、盛れないじゃん」
「はい。そういうものなんですよ」
「よくわからんな」言葉通り、先生は心底わけがわからないという顔をした。「今の子たちは盛るのがデフォなんじゃないのか? プリクラの写真だって原形無いくらい加工かけてるじゃん。目とか異常にでかいし」
「もうダメだ。先生おじいちゃん過ぎるわー」
亜美が呆れたように手をひらひらと振る。
「なんでやねん」と、インチキ関西弁で応じた原田先生は、すっかりいつもの調子に戻った亜美に
「しますよ。もちろん」
「それならどうしてそのトゥルージーは盛れなくていいわけ?」
「それはそれ。これはこれってこと。ってか、映えるとかはどうでもいいんですよ。トゥルージーはリアルタイムにみんなが何しているのか共有できるっていうのが良いんじゃん」
「どうしてそんなにプライベートを共有したいんだよ」
「先生だって奥さんと常に繫がっていたいでしょ。そういうことですよ」
「いや別に繫がりたくないが」原田先生はブルブルと左右に首を振る。
「あ。最低。愛がないですねえ」
「……ま、もういいや」
原田先生は自分の生徒への理解を完全に
「ごめんね佳代子。スマホ奪還に付き合わせちゃって。佳代子、先生のウケがいいからさあ。隣にいてもらうだけで助かるんだよね」
奪還したスマホを手で
「別にいいよ」と、隣を歩く亜美に答える。「でも授業中にトゥルージーはやめなよ。次は没収どころかマジでスマホ全面禁止になるよ」
「そだね。原田、口調マジっぽかったもんね。次からバレないようにやんないと」
「おい」
「あは。冗談だって」
本当に冗談なのか怪しいものだ。亜美とは小学校から一緒だけど、いつもこんな感じだった。いい加減というか楽天的というか。
うちのクラスにスマホを持っていない生徒は、おそらくひとりもいないだろう。だけど、みんな一応は真面目に決まりを守り、授業中はマナーモードにしているし机に取り出したりはしない。けれど亜美はトゥルージーが大好きだった。インストールしてから一年以上、毎日欠かさずに写真アップを続けているのが自慢だ。クラスではトゥルージーをやっている生徒も多いけれど、さすがに授業中に投稿を指示する通知が来ても応じる者はいない。――まあ自習などでたまたま先生がいなければ、取り出して撮影する人もいないわけじゃないけど――ところが、亜美は授業中であれ先生の目を盗んでトゥルージーをする常習犯だった。いつもは
「でもどうして授業中にトゥルージーするのよ。通知逃したってしょうがなくない?」
私の言葉に亜美はあっけらかんと答える。
「だって制限かかるの嫌だもん。いっぱいアップしたいじゃん」
「いやでも授業中はやばいでしょ」
「私この前、
「……そうだった」
亜美は映画上映中にトゥルージーの通知が来たために、客席でスマホを取り出したのだ。一緒だった玲奈にたしなめられたみたいだけど、亜美は止める間もなく撮影したらしい。トゥルージーでの撮影はアウトカメラとインカメラが同時に起動する仕組みになっている。撮影者自身と周囲の状況が二枚の写真として加工されることなく写し出され、日常そのままが共有されるのだ。この時亜美がアップした写真は、さすがに上映中のスクリーンに向けられてはおらず、暗い客席の背もたれと亜美の顔アップが写っているだけの画像だった。こんな写真を無理してまで撮る必要があったのか、めちゃくちゃ疑問だ。隣の席のおじさんに舌打ちされたって話だけど、確かに周りのお客さんにしてみればいい迷惑だ。
「映画始まったら通知切りなさいよ。迷惑」
「それ玲奈にも怒られたんだよね。でもついついユーワクに
「もうさ、病気だよそれ」
「でもそのお陰でまだ今日のぶん撮れるんだよ。ほら、トゥルージー撮ろう。スマホ取り戻し記念」
「もう」
亜美は私にぴったりとくっつくとスマホをかざした。私は片手で口元を隠すポーズでレンズに目を向ける。同じポーズをした亜美と一緒の写真と、無人の廊下を写した写真がトゥルージーにアップされた。
トゥルージーで写真を共有する相手は自分で選ぶことができる。不特定多数に公開するグローバル設定にもできるが、それをしている人は少ない。たぶん連絡先に入っている知り合いだけを共有相手にしているユーザーがほとんどだろう。それも相互に許可しないとトゥルージーの友達登録できない仕組みなので、見知らぬ他人に写真が共有されることはない。私たちの場合はもっぱらトゥルーグループというグループ設定を使っている。それは招待制になっていて特別に指定したメンバーだけに共有される、最もプライベートな共有設定だった。
トゥルーグループのメンバーは私と亜美、それから
こういう具合に信頼できる相手とプライバシーを交換するような仕組みになっていて、それがインスタなんかの他のSNSアプリと大きく違う点だった。通知がきたらすぐに写真を撮らなければならないというのがゲームみたいで楽しいし、『映え』を意識せず、自然体の写真ですむ手軽さも
私たちは毎日トゥルージーに写真をアップしていた。そもそも学校では一緒に過ごすことが多いので、お互いが何をしているか大体は知っているけれど、学校を離れた時間にもリアルタイムで近況を知ることができる。私はこのアプリが流行っていると聞いたから、なんとなく入れてみただけだけど、新鮮な体験で思ったよりずっと楽しかった。今ではトゥルージーは日常の一部になっていた。
チリリーン、という鈴のような着信音がトゥルージーの通知音だ。
「あ、トゥルージー来たみたい」玲奈がのんびりと言った。
「待って髪やばい」と、夏希がスマホケース背面のミラーで前髪を直す。
遥はじゅるる、と音を立ててパインフラペチーノの底をストローで探る。
この日の放課後、私たちは四人でスタバに来ていた。今日から夏限定のフラペチーノが発売になるというので、学校が終わると直行したのだ。亜美は部活が抜けられず、ダイエット中につき我慢するというので不参加だ。
「通知もっと早かったら良かったのに。タイミングわるっ」
夏希がピンクのネイルシールをした指で自分のグラスを持ち上げて見せる。ちびちびとフラペチーノを楽しんでいた夏希だったが、すでにグラスの三分の一くらいまで飲んでいて、写真
隣の玲奈のグラスにはまだ半分以上残っている。パインの鮮やかな黄色はまだ保たれていて、それを手に持つ玲奈の白い肌とのコントラストは、なかなかに『映える』絵だ。
「遥なんてもう飲み終わってるし。早くない?」
おっとりとした口ぶりで玲奈が示す遥のグラスは、ちょうど飲み終えたところだ。遥は
「だってこれ
「いや味わえよ」と、夏希が笑う。
私はスマホを手に取る。画面にはトゥルージーからの通知メッセージが表示されていた。
『トゥルージーの時間だよ 二分以内にトゥルージーを投稿しないと友達の投稿が見れないよ!』
私はトゥルージーを開き、撮影モードに切り替える。
「じゃ、撮るよー」と、スマホのアウトカメラを正面に並んだ夏希と遥に向けた。反対のインカメの画面には私と隣に座っている玲奈が同時に映っている。ほとんど飲み干したパインフラペチーノのグラスを持ち上げて口元を隠す、みんな同じポーズの写真を撮った。
「あたしも撮る」「次、私ね」
夏希と玲奈も順番にトゥルージーを撮った。同じような写真になってしまうのは、この際仕方がないだろう。
「あれ、遥は撮らんの?」
夏希が不思議そうに隣の遥に
「ああ、私はいいや」
「なんで?」
「だって、みんな同じとこにいるんだしさ。いいでしょ、もう」
「ふうん」と、夏希は納得したような、しないような顔をした。
遥は言葉を足した。「それに、なんか最近めんどくなってきちゃってさ、トゥルージー」
「そんな面倒かあ?」夏希が首を傾げる。
確かに最近では遥のトゥルージーの投稿タイミングは遅くなりがちだ。二分に間に合わないことがほとんどだし、終日アップされないこともちょくちょくあった。
「それちょっとわかるかも」と、玲奈が口を挟んだ。「私は別に面倒じゃないんだけど、最初の頃の楽しさは少し薄れてきたかもしれないかなあ。……佳代子は?」
隣の玲奈から急に振られて、私も少し考えた。
「私はまだ楽しいけど。でも惰性になっているところはあるかもね」
互いの近況を共有するトゥルージーには中毒性みたいなものがある。まだ飽きてはいないし、日常のルーチンに溶け込んでいるから、遥みたいに煩わしさは感じてはいない。だけどアプリに指示されるままに写真をアップしていると、何のためにこれをやっているんだっけ、という気持ちになることもあるのは事実だ。
私の言葉に
「そう、だから私、そろそろトゥルージーやめようかなって思って」
「え待って。マジ?」夏希が驚いた声を上げた。
「続けてもいいんだけどさ。気の向いた時だけにしようかなって。毎日アップしないかもしれない」
「まあ、いいんじゃないかなあ」玲奈が穏やかに応じる。「自分のペースでやるのが一番だよ。重荷みたいになっちゃうとねえ」
遥は少し申し訳なさそうな顔をした。遥が以前ほどトゥルージーに熱意を持てなくなっているのは知っていたが、やめる宣言するほどとは思わなかった。遥はさばさばした性格で、興味が無いことは無いとすぐに口にできる。それが遥の良さでもあった。
私も玲奈に同意して頷く。
「そだね。トゥルージーやめたからって友達やめるなんて言わないし」
遥はほっとしたような顔をした。
「よかった。アプリやめてハブられたら、どうしようかって」
「なわけないでしょ」
「うわやば!」突然、夏希が声を上げた。手にしたスマホの画面を見て
夏希はスマホの液晶画面をみんなに見せた。トゥルージーのグループ画面に、さっき投稿した私たちの写真が並んでいる。そして、その一番下に新たな画像が追加されていた。それは学校のグラウンドの写真だった。トラックにはハードルが並んでいて短パンの陸上部員の背中が何人か写っている。そしてインカメで撮られた写真には笑顔の亜美が写っていた。どうやら亜美は部活中にトゥルージーを撮ったらしい。
「えぐいわ。部活の練習にもスマホ持っていくとか」と、夏希が笑う。「亜美、どんだけトゥルージー好きなんだよ」
通知を逃さないためにグラウンドにスマホを持っていってこっそり撮ったのだろう。三年に見つかったら怒られるだろうに。亜美のトゥルージーへの熱意は衰える気配がないどころか、エスカレートしているみたいだ。
隣の玲奈が
「遥がトゥルージーやめるって言ったら、亜美どんな反応するかな」
確かに亜美なら引き止めそうにも思える。でも、本人がやめろと言われているわけでもないし、そこまで強い反応はしないのではないだろうか。
という、私の予想は大ハズレだった。
後日、学校の昼休み。私たちはいつもの五人で教室隅の私の席の周りに集まり、お
「えー! どうして!」
「どうしてって言われても」と、遥が苦笑しながら亜美に答える。「なんとなくだよ。スマホをずっと持ってるのもめんどいし」
「別にずっと持ってる必要なくない? 何も二分以内に投稿しなくてもいいんだし」
「まあそうなんだけど」
「トゥルージーするの楽しいじゃん」
「楽しいけどさ。通知が来ると、早く写真撮らなきゃって、ずっと頭の隅にあるのがなんか嫌なんだよね」
「そんな負担じゃないでしょ。だって写真いっこ撮るだけだよ」
亜美は大きな目を見開いて不満げな声を上げた。
「でも、人それぞれじゃない?」と、私がフォローする。「私はまだ飽きていないけど、義務感みたいなのを感じるようになったら楽しくないだろうし」
玲奈もこくこくと頷いた。
「そうだね。気が向いた時だけトゥルージー撮るみたいなスタイルでやってもいいと思うよ」
それでも亜美は
「えー。みんなとリアタイ共有するのが楽しいんじゃん」
「でもうちら結局いつも一緒じゃん」と、夏希がとりなすように明るい声で言う。「トゥルージーやってもやんなくても、別に同じじゃね?」
確かにそうだよね、と、私もみんなも口々に同意の言葉を漏らす。でも亜美だけは不満げな表情を崩さずに、ぶつくさと言葉を続けた。
「そういう問題じゃないじゃん。学校ない日でもみんなと
空気がぴりりと緊張した。玲奈と夏希の表情も、瞬間、
「ちょっと、いい加減にしてよ」遥は険しい目を亜美に向けた。「わがままはあんたのほうじゃん」
まずい。そう思ったが遅かった。亜美の顔色もさっと変わり、一際高い声で遥に言い返す。
「だってトゥルージーなんてたいした手間じゃないじゃん。それすら面倒って言うのは、なんか違くない? それって、みんなと絡むのが面倒ってことでしょ?」
「誰もそんなこと言ってないでしょ!」
遥の声も大きくなった。彼女が本気で怒ることは珍しい。私たちは口を挟むことも出来ずに
「だってそうじゃん」と、亜美が
「はあ?」
「だって帰宅部なんだし」
「そういう問題じゃないでしょ」亜美の言葉を遮るように遥が言い返す。「授業中や部活の最中までトゥルージーやってる亜美のほうがおかしいんだよ」
「そんな言い方ないじゃん」
「事実でしょ」
「でもおかしいとか、人を異常者みたいに」
「いや異常だよ。アプリの奴隷みたいにさ」
「なにそれ」
慌てて私と玲奈が割って入る。夏希も空気を和らげようと軽口を
ひりついた空気の中で、チリリーン、とトゥルージーの通知音が鳴った。しかしこの時ばかりは誰もスマホを開こうとしなかった。
翌日は土曜日だった。夕方、母に付き添って夕食の食材を買いに車でスーパーを訪れた。私たちが野菜売り場の前を歩いていると、トゥルージーの通知音が鳴った。昨日あんなことがあったばかりだ。私はトゥルージーを開くのが少し
みんな私と同じ考えだったのか、亜美だけではなく、すでに玲奈も夏希も写真をアップしていた。みんな自宅にいるらしく、どれも家の天井や壁が写っているだけのつまらない画像で、インカメで撮った写真には顔は写っていない。髪がぼさぼさだったり、すっぴんで口元を隠すだけではカバーできないくらいのビジュの時は、みんなこういう写真で逃げるのだ。とりあえず、全部の写真にいいねマークをつける。まだ遥の写真はアップされていなかった。遥はこのまま本当にトゥルージーをやめてしまうのだろうか。
その時、チリリーンと音が鳴った。トゥルーグループの投稿欄に新たな写真がアップされたのだ。
遥が更新してくれた、と
「アイアム……ヒン、ギス?」
アカウント名に意味はなさそうだ。それにユーザーアイコンにも顔写真がなく真っ黒に塗りつぶされている。その上、このアカウントからアップされたインカメラ、アウトカメラの二枚の写真とも、真っ暗闇の中で撮影されたかのような黒い画像だった。
トゥルーグループはメンバーの誰かが招待しないと入ることは出来ない。このアカウントを誰が招待したのだろう。私はグループのメッセージログを読むが、どこにもこのユーザーを招待した履歴は残っていなかった。グループ設定を確認すると、参加メンバー数には5と表示されており、グループメンバーのリストにも私たち五人のアカウント名だけで、このアカウントは含まれてはいなかった。
LINEに通知があった。アプリを切り替えると、私たち五人のグループLINEに、夏希からのメッセージが表示されている。
――トゥルージーに変なのが混じってる 見えるのうちだけ?
私はすぐに返信した。
――こっちも見えてる 真っ黒な画像 なにこれ
間を置かずに既読数が3になった。今度は玲奈からのメッセージが表示される。
――誰も招待許可してないよね
すぐに亜美から返信があった。
――してないよ
遥はまだLINEを見ていないみたいだが、遥が招待したとも思えないし、そもそも招待記録が残っていないのも変だ。
私がグループのメンバーリストにそのアカウントが表示されないことを告げると、アプリの不具合ではないだろうか、と玲奈が言った。いわゆるバグというやつだ。画像も真っ黒だし、言われてみればその可能性が高いように思える。
――私サポートセンターに問い合わせてみるよ
と、玲奈が言ってくれたので、その場はそれで収まった。
週明け、登校した私が教室に入ると、玲奈の席に夏希と珍しく早く登校したらしい亜美が集まっていた。遥はまだ学校に来ていないらしい。早速、トゥルージーの黒画像アカウントの話をしているようだ。
玲奈が私を手招きして言った。
「サポートから返信あったよ」
「マジで。結局なんだったの」
「ご迷惑おかけしてすみません。不具合だと思われます、だって」
「あのアカウント、人じゃないってこと?」
「みたいだよ。誤った表示だって。定型文みたいな返信だったから詳しいこと書いていなかったけど」
黒画像アカウントからのトゥルージーは日曜日にも投稿されていた。前日と違うのは時間制限ぎりぎりの二分ちょうどにアップされていたことくらいで、あとは前日と同じく、何も写されていない黒い画像だった。
椅子にあぐらをかいた夏希がいたずらっぽく笑う。
「焦ったよ。誰こいつって。変なやつが勝手にグループに入ってきたのかと思った」
「そんなこと出来ないはずだよ」と、亜美が言う。
「こういう不具合ってよくあるの?」
私は亜美に尋ねた。トゥルージーについては誰よりも亜美が一番詳しい。
亜美は「聞いたことない」と、答えた。「こういうことが他にもあるのかと思ってXとかも検索したけど、出てこなかった」
亜美が何も知らず、他に例もないということは、よほど珍しい現象なのだろう。
「で、結局サポートが対応してくれたんだよね。あのアカウントはもう表示されなくなったってことでしょ?」
夏希が尋ねると玲奈がかぶりを振った。
「こっちでやらないとダメみたい。
「え、めんどくさー」夏希が顔をしかめる。
「実害もないんだし。このままでも良いんじゃない?」と、亜美。
確かに見ず知らずの他人にトゥルージーが共有されているのであれば問題だが、ただの不具合による見かけ上の表示であれば、私たちが気にしなければいいだけの話かもしれない。
それにしても亜美はいつもより幾分か元気がないように見える。常にはしゃいでいるような明るさが亜美の魅力だと思うけれど、今の亜美は妙に落ち着いている。遥との
遥は結局、土日ともにトゥルージーに投稿していない。LINEは既読になっていたから状況は把握しているみたいだけど、例の黒画像アカウントを実際に目にしていないはずだ。
「お、遥来た」夏希がおはよー、と教室の入口に手を上げる。
教室に入ってきた遥も
「トゥルージー、何かあったんだって?」
遥は手にした
「そうなの。見てよこれ」と、玲奈が自分のスマホ画面を遥に見せる。
遥は表示されたユーザー名を見て
「え、ヒンギス? なにこいつ」
アプリの不具合らしいという玲奈の説明を聞きながら、遥は気味が悪いものでも見るような顔で液晶画面に目を落としている。
ここまで遥と亜美は一度も目を合わせていない。ふたりとも強情なところがあるし、たまに
遥は顔を上げると肩をすくめた。
「なんか終わってるね。トゥルージー」
「再インストールしたら直るらしいよ」と、玲奈が応じる。
「でも管理がずさんなSNSって怖くない?」
遥は苦いものでも
私はちらりと玲奈と目を合わせた。また嫌な空気にならないだろうか。
「……こういうの、私、聞いたかも」
ぼそりと
「聞いたって何を?」
亜美に問い返す遥の声はどこか
「不具合とか、バグ? とかって話は知らないけど。ひなぎさんの話」
「ひなぎさん?」
私が聞き返すと、亜美は小さく
「これ、トゥルージーじゃなくてLINEの話なんだけど……」と、前置きして亜美は言葉を続けた。「ひなぎさんっていう名前の中学生の女の子がいたの。同じクラスでLINEグループをつくっていて、ひなぎさんもそこに入っていたんだけど、何かのきっかけでクラスのみんなにいじめられるようになったんだ。仲間はずれにされたひなぎさんはLINEグループからも追い出された。それで、結局ひなぎさんは自殺しちゃった」
「ちょっと何の話してんの?」と、遥が遮る。「それ実話じゃないでしょ」
亜美はかぶりを振る。
「わかんない。けど、ずっと前に友達から聞いた話。……ひなぎさんが死んでしばらくしてから、そのクラスのグループLINEに誰だか分からないメンバーが入ってきたんだって。でも何も話さないし、他のクラスの子かもって、誰も気にしていなかったらしいんだけど」
亜美の話を聞いていて、ふと記憶が
「クラス替えとか、卒業とか、だんだんと関係が薄くなるとグループLINEを抜けたりするでしょ? 最初に誰かがグループを抜けた時、その誰だかわからない謎のメンバーが初めてクラスLINEにメッセージしたの。『誰々さんがいなくなった』って。しばらくして、そのグループを抜けた人は急に死んじゃって、本当にこの世からいなくなった。グループを抜ける人が出るたびに、こういうことが起こった。そのクラスの子たちは、その謎のメンバーが死んだひなぎさんだと思ったんだって。グループを抜けたらひなぎさんに連れていかれる。だから、今でもそのクラスのグループLINEから誰も抜けることが出来ない」
遥が悲鳴みたいな声を上げた。
「ちょっと待ってよ! 今つくったでしょ、それ」
「つくってないよ」と、亜美が首を振る。
私も亜美の否定に付け足して言った。
「私も聞いたことあるかも。細かいことは覚えていないけど、ひなぎさん? だったかな……。とにかくグループLINEを抜けたひとが死んじゃう話」
遥は
「だからって今そんな怖い話を持ち出して。それ絶対トゥルージーやめたいって言った、私への当てつけじゃん」
そういえば、遥はこれ系の話は超苦手だった。亜美もそれを知っていて、わざわざ怖い話を持ち出したのか。だとしたら、遥への仕返しということだろうか。
「違うよ」と、亜美はゆるゆると左右に首を振る。「だって、このアカウントの名前って、なんか……」
スマホを見つめていた玲奈が、ああ、と小さく声を上げた。私も亜美の言いたいことを理解した。アイアムヒンギス。ヒンギスの『hingis』という
ぞわりと悪寒がした。単なる不具合で表示されたアカウント名。それとひなぎさんの話に、何か関連があるのか。玲奈と夏希の顔からも表情が消え、液晶に映る正体不明のアカウントを凍ったように見つめている。
「こわっ」沈黙を打ち消すように、遥が明るい声を上げた。「やめてよね、朝からこんなしょうもない話。もう原田が来ちゃう」
遥はぎこちない笑顔を私たちに向けると、鞄を
事件が起きたのはその翌日のことだった。突然、遥が入院したのだ。
遥は放課後、校舎四階と三階の間の踊り場から階段を転落して鎖骨を骨折してしまった。その時、周囲には誰もいなかったが、たまたま廊下を通りがかった原田先生に発見され、すぐに救急車で病院に運ばれたらしい。命に別状はなかったが、手術の必要があるということで数日間入院することになったのだ。詳しい状況は分からないけれど、誰もいない階段で足をすべらせて転落するなんて、遥らしくもない事故に思えた。
私たちは四人とも口にこそ出さなかったが、やはり考えてしまうのはひなぎさんの話だった。遥はあれから一度もトゥルージーに投稿していない。だけど黒画像のアカウントからは相変わらず連日投稿があった。アップされるのは常に真っ黒の画像だけで、あの話にあったように『遥さんがいなくなった』などとコメントされることはない。ただのアプリの不具合だと自分に言い聞かせてはいたけれど、このタイミングで遥が大怪我したという事実が重なると、どうしても気持ちが悪く感じてしまう。
私たちの中でも特に亜美は沈んでいた。遥の入院について、ひどく落ち込んでいるように見えた。それも当然かもしれない。ただの怪談話とはいえ、自分の話したことが現実になってしまったようなものだ。でも遥は死んでしまったわけではないし、亜美が気に病むようなことでもない。そんな言い方で私は亜美をなぐさめたけれど、彼女の反応は薄かった。
私はひなぎさんの話がずっと引っかかっていた。この話を知ったのは、随分と前、たぶん小学生の頃だったようにも思う。でも、どこでこれを聞いたのかどうしても思い出せない。ネットで検索をかけてもみたけれど、それらしい怪談も小話も全く見つからなかった。それなら一体私はどこでこの怪談を耳にしたのだろう。本で読んだとかネット怪談とかではなく、直接誰かから聞いたのだろうか。
遥が手術をした翌日、状況は急転した。今度は亜美が急に学校を休んだのだ。原田先生は諸事情により亜美がしばらく休むことになったとしか言わず、詳しい事情を説明しなかったし、亜美に直接LINEしても返信がなかったので、最初は不登校の理由がわからなかった。だけど、その日の午後には、私たちはそれを知ることができた。夏希が亜美の所属する陸上部の一年から事情を聞いてきたのだ。その話は私たちをひどく驚かせた。
遥を階段から突き落としたのは亜美だったのだ。
遥が転落した南校舎の階段の踊り場には窓があって、向かいの北校舎四階の廊下から見下ろすと、ちょうど踊り場の様子が見える。事件当時、北校舎を歩いていた一年生が、たまたま階段から転げ落ちる遥の姿を目撃したのだ。そして真っ青な顔でそこから立ち去る亜美の姿も。一年生は陸上部で亜美の後輩だったので、一時は先生への報告を
夕方、入院中の遥から久しぶりにトゥルージーへの投稿があった。それは病院食を撮った写真だった。インカメに遥の顔は見えなかったが、病院着の上から左肩部分を固定する器具をつけた上半身が写っていた。
少し迷ったが、私は直接LINEで体調を尋ねるメッセージを遥に送ってみた。するとすぐに返信があった。
――大丈夫だー けど暇だー
自由にならないのは左手だけで利き腕は無事らしい。訊くと、どうやら亜美が登校停止になっているのはすでに遥も知っているようだった。遥は突き落とされたことを先生にも黙っていた。自分を突き落とした亜美を
――だって私も悪かったからさ
――階段ですれ違ったときに嫌味を言っちゃったんだよね
――まだトゥルージーなんてやってんの しょーもな、とか
――あんな怖い話とかされてムカついてたし
――そしたらどんって押されて
――けど亜美も突き落とすつもりなかったと思う
――だから大ゴトにしたくなかったのに
遥はその言葉通り、亜美を責めることはしたくないみたいだ。私は少しほっとした。被害者の遥がそう考えていてくれるのなら、亜美も大きな罰を受けることはないのではないだろうか。
遥から続けてメッセージが来た。
――トゥルージーだるいと思ってたけど、こうなってみると悪くないね
――病室にいてみんなの様子がわかるのって、なんか安心する
――亜美の家庭環境複雑だし こういう感じ求めてたのかも
メッセージの最後には、うさぎのキャラが温泉に入ってくつろいでいるイラストのスタンプが押された。
遥はその二日後には退院し、その翌日には学校に来るようになった。でも亜美はまだ登校していなかった。自分にも非があり、亜美を責めることはしたくないという遥の訴えを学校側が考慮して、正式に停学処分ということにはならなかった。もちろん警察
チリリーンと通知音が鳴る。タイミングも良く、ランチの時間だった。私たち四人は教室の隅に集まってお弁当を広げているところだ。
「トゥルージー撮ろうか」
私はスマホを頭上に構えシャッターをきる。四人で机の上に並んだお弁当を囲んでいる写真がトゥルージーにアップされた。
あれから亜美はトゥルージーを更新していない。毎日投稿を続けていたのが自慢だったのに、さすがにこういう状況ではその気になれないのだろう。反対に遥は毎日トゥルージーに投稿している。しかもほとんど二分以内だ。遥なりの亜美へのメッセージかもしれないと思った。亜美自身がトゥルージーに投稿していないので、私たちの写真を亜美は見ることは出来ないが、私たちが投稿したことだけは通知される。早く戻ってきてくれると良いのだけど。
そのままトゥルージーのグループ画面を見つめていると、ちょうど二分ぴったり経過したところで、チリリーンと更新の通知音が鳴った。
「えっ」と、思わず声が出た。
亜美が投稿したのかと思ったが、違っていた。いつもの黒画像アカウントの更新だった。そのアカウントは毎日更新されていたが、これまでは常に何も写っていない黒い画像だった。それが今回は違っていた。それは道路の写真だった。降り注いだ夏の日差しが白いガードレールに反射して強く輝いている。ガードレールの反対側にはブロック塀があり、その向こう側には
私がスマホの画面を見せると玲奈は
「どうして写真が」
この黒画像のアカウントはただの不具合、エラーで表示されているだけで、実際にアカウントの主はいないと私たちは考えていた。それなのに、今こうして写真がアップされた。トゥルージーは事前に準備した画像はアップすることが出来ない。その時アプリで撮影した画像のみがアップできる仕様だ。だからこの道路の風景写真は、たった今撮影されたものということになる。
夏希が首を傾げた。
「どこかで見た気がする。この道」
遥も医療器具で固定された左肩を窮屈にひっこめながら、机に置いた私のスマホを見つめていたが、あっと声をあげた。
「これって亜美の家の近くじゃない?」
夏希も思い出したように言う。「あ、ほんとだ。この道を真っ直ぐ行くと亜美の家だよ」
遥と夏希は去年の夏祭りの時に、亜美を迎えに自宅の前まで行ったことがあったらしい。その時に通ったのがこの道だという。言われてみれば、私もこの景色に見覚えがある。亜美と知り合って長いけれど私が彼女の自宅を最後に訪れたのは随分と昔。小学校の時だった。
「でも誰がこんなところの写真を」
首を傾げる夏希に、遥が憤りの混じった声を上げた。
「待って、この写真撮ってるの亜美じゃないの?」
「まさか」玲奈が戸惑った顔を上げる。「このアカウント、不具合の表示だって……」
「じゃあ、どうして写真がアップされるのよ。しかも亜美の家の近くなんだよ」
いつの間にかグループメンバーに加わっていた正体不明の黒画像アカウント。これが亜美のものだということがあるのだろうか。亜美はトゥルージーについては誰よりも詳しい。招待せずにメンバー追加する裏技のようなものを知っていたということなのか。そしてアップされた写真が家の近所ともなれば、状況としては亜美の仕業にも見えてしまう。
とはいえ、これが亜美の投稿だとは私には思えなかった。
「でも亜美がこんなことする理由はないでしょ」
私が言うと、みんなは顔を見合わせた。そうだ。亜美がこんなことをするなんてわけがわからない。その理由もない。亜美は単純な性格だ。こんな持って回ったいたずらをするだろうか。
「……ひなぎさん、なのかな」夏希が
「やめてよ」遥が大声で打ち消す。「あんな話、本当なわけないでしょ」
「でも」と、夏希は私を見る。「佳代子だって聞いたことあるんだよね? だったら少なくとも亜美の作り話じゃないじゃん」
「うん、まあそうなんだけど」
私は
その、ひなぎさんのアカウントは翌日も更新された。トゥルージーの通知は二時間目の授業の最中だったが、投稿制限期限の二分ちょうどで新しい写真がアップされていたのだ。それは前日と同じように誰もいない道路を撮影した写真だった。さらにそこに写っている道路もまた、駅から亜美の自宅へと向かう道だったのだ。しかも前の写真よりも、より亜美の自宅へ近づいていた。
そしてその翌日もまた、ひなぎさんのアカウントから写真がアップされた。この日の投稿時間は学校も終わった午後六時過ぎだった。トゥルージーの通知からきっかり二分でアップされている。驚いたことに、写っていたのは亜美の自宅だった。それは手前を横切る道路の反対側から、建物を少し見上げるような角度で撮影されていた。二階に見える大きな窓ガラスに西日が白く反射している。亜美がいるとすれば、その窓の部屋だろうと夏希は言った。この写真の撮影者は数日をかけて、ゆっくりと亜美の自宅へと向かっていたようにも思える。私だけでなく、玲奈も夏希も同じことを考えた。もしこれが、本当にそのひなぎさんであれば、亜美の身に危険が迫っているのではないか、と。しかし、遥だけはそう考えなかった。
「こんな悪ふざけ。構ってちゃんなだけでしょ。放っておけばいいんだよ」
遥はこの写真は亜美が撮っているに違いないというのだ。ひなぎさんの話も信じてはいない。けれど遥の様子はいつもよりどこか落ち着かず、彼女自身強い不安を抱いているのが私にもわかった。
翌日、学校が終わると、私はひとりで亜美の自宅に向かった。
まだ日は高く、日暮れまでにはだいぶ時間がある。亜美の自宅へ向かう道すがら、ひなぎさんのアカウントが写した場所を通った。辺りの様子はまったくあの写真通りだった。左手はガードレールになっていて、その向こう側の
私は二階の窓を見上げる。昼間だというのに白いカーテンが引かれていて、部屋の中の様子は見えない。私は玄関先に入ると、入口のドアの横にあるインターフォンを押し込んだ。チャイムが響き、しばらくして、
「はい」と、応答があった。亜美の声だ。
「亜美、だよね? 私、佳代子だけど」
返事はない。けれど私は続けて話した。
「今、少し話せる?」
しばしの無言の後、ぷつりとスピーカーが途切れる音がした。ドアが開くのを待ったが、一向にその気配がない。
「久しぶりだね。体調はどう?」
「別に。普通」
私の問いかけにも、亜美の表情は硬いままだ。
「最近、トゥルージーやってないね」
私の言葉に亜美はぴくりと片眉を上げた。私自身、どうしていきなりこんな話題から入ったのかと思う。何から話すべきかわからず、
「……何の用?」
亜美は表情もなく問い返す。ドアをそれ以上開いてもくれなかった。どんよりと
「亜美がどうしているかと思って。トゥルージーやっていないと、ほら、わからないからさ。もちろん全然無理することはないんだけど、みんな学校で待ってるから」
「無理するって何?」亜美は皮肉めいた暗い笑みを浮かべた。「私はどこも怪我していないんだから無理も何もないよ。怪我しているのは遥でしょ。あんな大怪我させといて、私はその場から逃げただけだから。私はなんともないよ」
「でも、遥はもうすっかり元気だよ」私は取り繕うように言った。「大きなギプスみたいなの付けてるけど、体育以外は普通に授業受けているし。それに知ってるかもだけど、ここのところずっとトゥルージーやってるんだよ、遥。病院で暇だったから再開したんだけど、トゥルージー熱が再燃したみたい。結局あの子、毎日トゥルージーやっててさ。亜美も
「出来るわけないじゃん」低い声で亜美が遮った。「……出来るわけないでしょ。トゥルージーなんて」
「亜美」
亜美は震える声を絞り出すように唇を動かす。
「私、殺しちゃったかもしれないんだよ、遥を。あんな……、あんなことをして。まだ直接謝りにいく勇気も出ないのに、それなのに、
私はかぶりを振って、ドアのむこうの暗がりに話す。
「でもわざとやったんじゃないって、遥もわかってるよ。だからそんなに――」
「わざとやったんだよ!」亜美が叫んだ。
私は驚き息を
亜美は涙の混じるかすれ声を吐き出すようにして言葉を続けた。
「わざとやったの。あの時、本当に死んじゃえって思ったの。遥が死ねばいいって、そう思って私は押したんだよ。どうしてそんな風に思ったのか、今でも分からない。友達なのに。そんな、私みたいな、こんな化け物と、また友達になれるわけないじゃない。元通りになんてなれるわけがない。またトゥルージーなんて出来るわけ……」
言葉はそこで切れ、亜美はその場に泣き崩れた。
私はドアを開き、
「誰も亜美が化け物だなんて思っていないよ。亜美が化け物なら、私だって、みんなだって化け物だよ。誰だって、ほんの一瞬、本当の自分でなくなる時ってあると思うんだ。亜美のは、その一瞬が、すごく悪いタイミングで来ちゃっただけ」
それは私の本心だった。亜美は少し子どもっぽいところはあるけれど、決して悪い子ではない。本当に悪い人間は、こんなふうに良心の
私は呼吸も荒く泣き続ける背中に手を置いたまま、しばらく亜美が落ち着くのを待った。
「亜美、ひとつ
亜美はのろのろと顔を上げて泣き
「あれって『ひなぎ』じゃなくて、『ひなぎく』だよね」
私の問いかけに、亜美は手の甲で涙を
「……うん。思い出したんだね」
私は頷く。
「名前を少し変えていたからなかなか出てこなかったけどね。ここに来る途中に児童館の前を通ったよ。それで完全に思い出した。古かった建物、きれいになったんだね」
「何年か前に建て替えたんだ」と、亜美が頷く。「でも児童館の名前は変わっていないから」
「みたいだね。新しい看板があった。あの話って児童館の名前からとったんだよね。ひなぎく児童館」
亜美はこくりと頷く。
「そう。ひなぎくさん。私が考えた怪談」
ひなぎく児童館は私たちが通っていた小学校の学区内にある施設だ。低学年の頃、兄と一緒によく遊びに行き、亜美とはそこで顔見知りになった。当時、亜美はお母さんとふたり暮らしをしており、仕事が忙しい母親は自宅に不在がちだった。その為、亜美は小学校が終わるとほとんど毎日のように児童館で時間を
ひなぎく児童館では子ども向けの催しが定期的に行われていた。私たちが三年生の夏休み、『物語づくり』というイベントがあった。それぞれ原稿用紙数枚程度のお話をつくって、みんなの前で発表するのだ。私と亜美も参加した。私がどんな話を書いたのか覚えていないが、時期が時期だったので怖い話を考える子どもが多かった。亜美が書いたのも怪談で、それは児童館の名前をつけた怪異のお話だった。LINEの仲間から抜けた者を呪い殺す、いじめられた子どもの幽霊のお話。ひなぎくさんだ。このお話はとても怖いと、他の子どもたちにも評判がよく、亜美は児童館の先生にも褒められていた。
「どうしてあの時、遥にあんな話をしたの?」
私が訊くと亜美は目を伏せた。
「遥にトゥルージーを馬鹿にされたみたいで悔しかったから。だから」
「あのアカウントも亜美がつくったの?」
え、と亜美は顔を上げると
「まさか。私じゃないよ。あのアカウントの
亜美の言葉は本当だろう。遥を怖がらせるためにあのアカウントを作るなら、もっとわかりやすい名前にしたはずだ。亜美はあのアカウント名『hingis』のアルファベットの並びを見て『ひなぎくさん』ではなく『ひなぎさん』に変えて話したのだろう。結局のところ、確かにこのお話は亜美があの場でつくったものではなかった。それよりずっと昔に考えられたお話だったのだ。
「じゃあ、トゥルージーの写真も関係ないんだね」
私の言葉に亜美はきょとんとした。「写真って?」
やはり知らないらしい。私はひなぎさんのアカウントから昨夜トゥルージーにアップされた画像を亜美に見せた。スマホの画面に目を落とし、亜美は
「なにこれ。私の家……?」
「うん。
「えっ?」
私は連日トゥルージーにアップされた画像について亜美に説明した。トゥルージーの写真は丸一日経過すると自動的に消去されるので、一昨日以前の写真はすでに消えている。亜美は戸惑った顔を私に向けた。
「これ一体誰が撮ったの?」
「遥は亜美がやっているんだろうって」
「私、撮ってないよ」
「だよね。わかってる」
「じゃあ、誰が」
亜美はうめくような声で言った。私は少し迷ったけれど、ずっと考えていたことを亜美に尋ねた。
「ひなぎくさんのお話って、グループから抜けると何日で死んじゃうの?」
「えっ」亜美は驚いたように目を見開いた。「四日、だけど」
「四日?」私は息を吞む。「亜美の家に向かう写真がアップされ始めてから、今日が四日目……」
「待ってよ。ひなぎくさんは私の作り話なんだよ。四日だって『死』って言葉からとっただけで、深い意味なんてないし」
「元ネタとかはないの?」
「そんなの無いよ。あの場で考えただけだもん」
亜美の考えた全くの創作怪談。もちろんただの作り話で現実じゃないってことは分かってる。でも、それならあのアカウントは誰がつくって、誰があの写真をアップしているのだろう。私はひなぎさんのお話のことを考えずにはいられなかった。写真共有をやめてしまった亜美の自宅へと向かっているような連日の写真。それは亜美にトゥルージーの再開を迫っているんじゃないか、と。
「亜美、トゥルージー、今日は撮ったほうがいいんじゃないかな」
私が言うと、亜美は「どうして?」と困惑した表情を見せた。「まさか佳代子、本当にひなぎさんだと思ってるの? 私の作り話なんだよ、あれは。それにあのアカウント、ただのエラー表示だって玲奈も言っていたじゃん」
「そうなんだけど……」私は口ごもる。
うまく説明できないけれど、普通ではないことが起きているように思えて怖かったのだ。実際にこの場所の写真が撮影されている。それが誰かの悪質ないたずらならば別にいい。けれど、それが本当にひなぎさんだとしたら。でも、それを口にすることさえ怖かった。ただの作り話を本気にするなんて良くないことのように思えた。
トゥルージーから今日のぶんの撮影を指示する通知はまだ来ていない。きっと、そろそろ通知が来るはずだ。
亜美は黙って私の顔をじっと見つめていたけれど、私の考えていることが伝わったのか、やがて暗い顔で小さく頷いた。
「わかった。今日はトゥルージー、アップする」
私が自宅に戻ってもまだトゥルージーは鳴らなかった。通知時間はランダムとはいえ、設定されたタイムゾーンでの深夜時間帯は除外される。遅くても午後十一時前には通知が来るはずだ。私はお
チリリーンと、通知音が鳴ったのは午後十時を過ぎた頃だった。
『トゥルージーの時間だよ 二分以内にトゥルージーを投稿しないと友達の投稿が見れないよ!』
私はすぐにアプリを立ち上げ、写真撮影してトゥルージーにアップした。自分の部屋の姿見を撮り、自分の顔は手のひらで隠した。遅い時間だったけれど、みんなの反応は早かった。三十秒もしないうちに、夏希、玲奈、続いて遥の写真が投稿された。みんな飼い猫の写真だったり、バラエティ番組が映ったテレビの写真だったりで、自分の顔は写っていない。けれど、今みんながどう過ごしているのか想像のつく画像だった。でも亜美の写真はアップされていない。それにひなぎさんのアカウントからの投稿もない。
時間は過ぎていく。私は嫌な胸騒ぎがして、急いで亜美にLINEした。
――トゥルージーきたよ
すぐに亜美からの返信があった。
――ほんとだ 通知切ってたの忘れてた
トゥルージーの通知が来てからもう一分が経過している。
――撮るでしょ?
私がもう一度メッセージを送ると、間を空けずに亜美からの返答があった。
――今トイレ ちょっと待って
私はスマホの時計を見る。もうすぐ二分が経過してしまう。ひなぎさんのアカウントよりも早く亜美に投稿して欲しかった。次第に亜美の自宅に近づいていくひなぎさんの写真。昨日アップされたのは亜美の自宅の前だった。それなら今夜の写真には一体何が写るのか。それが投稿されるよりも先に、亜美が投稿すべきではないかと思ったのだ。じりじりと待つが、まだ亜美からのトゥルージーは来ない。
――早く!
と、LINEを送る。すぐに既読になった。
チリリーン、と音が鳴った。
私は急いでトゥルージーを開く。
「亜美……!」
そこに投稿されていたのは亜美の顔だった。亜美が更新してくれたのだ。そう考えたけれど、私はすぐに違和感に気づく。
亜美がいるのはうす暗い廊下だった。その画像に写る亜美の表情は普通ではなかった。彼女は何か信じられないものに出会ったように、
はっとして、私は投稿されたアカウント名を見る。それは亜美ではなく、ひなぎさん、『iamhingis8281』のものだったのだ。
私は急いで亜美にLINEする。何度もメッセージを送ったが、いつまで待ってもそれらは既読にならなかった。
亜美は自宅に近い農業用水路に浮かんでいたのを、犬の散歩で通りがかった通行人に発見された。これは後からわかったことだが、亜美はこの夜、自宅を抜け出して外に出かけたらしい。近くの民家の防犯カメラのいくつかに、ひとりで歩いている亜美の姿が映っていたという。時間的にはトゥルージーの写真がアップされた直後のことだ。どこへ向かっていたのかは分からないが、亜美は水路に架かっていた橋から身を乗り出し転落したらしい。誰かに呼び出された可能性を含め、事件性については警察も調べたようだが、結局は事故、あるいは自殺と結論付けられたということは、それを示す証拠は何もなかったということだろう。あのアカウントからアップされた亜美を撮影した画像は、亜美が亡くなったと思われる時刻には消されていた。
亜美の葬儀のあと、私たち四人は全員トゥルージーをやめた。アプリ自体をスマホから削除した。
亜美が亡くなった後も、亜美を撮影したアカウントは相変わらず私たちのグループに残っており、連日画像がアップされていたが、それらはまた何も写っていない黒画像に戻っていた。このアカウントを残してトゥルージーをやめることに少しの不安はあったけれど、亜美があんなことになったので、私たちはこれ以上続けることが恐ろしく感じられたのだ。
朝、チリリーンという通知音で私は目を覚ました。
ここのところ全然眠れなかったが、この夜はいつの間にかまどろんでいたみたいだ。何か夢を見た気がするが思い出せない。通知音は気のせいだろうと思った。トゥルージーはすでにスマホから削除しており、通知音が鳴るはずもないのだ。ぼんやりと意識が戻るにつれて、音は窓の外から聴こえたことに気が付いた。
私は寝そべったベッドから手を伸ばしてカーテンの端をつまみ、隙間から窓の外を見る。うちの狭い庭に母の乗用車が停まっているのが見えた。空には暗い雲が垂れ込めて小雨が降っており、車のボンネットには細かい水滴がたくさん付いている。
たった今、スマホを持った誰かが窓の外に立っていて、そこにトゥルージーの通知が届く。そんな情景を想像する。けれどうちの庭の前には誰の姿も見えない。私の体にぶるりと震えが来た。まさか。
私はベッドから体を起こし、一度は消去したトゥルージーをダウンロードする。ログイン画面に自分のアカウント名とパスワードを入力すると、いつものホーム画面が表示された。アプリは削除しても、アカウントは消していなかったので、設定はそのまま残されていたのだ。私たち五人のトゥルーグループもそのままだった。
震える指先でグループ画面を表示させる。
私が恐れ、予期していたものがそこに現れた。そしてそれは私の想像を超えるものだった。
一番上に表示された画像には、私の家が写っていた。小雨の降る暗い曇天の下、
そして画像は一枚ではなかった。アカウント名は全て同じなのに、なぜか別のユーザー扱いになっているアカウントが幾つも増えている。もはやひなぎさんはひとりではなかった。たくさんに増えていたのだ。そして、それらのアカウントには全て写真がアップされていた。玄関の前から撮影されたもの、窓のすぐ前から撮られたもの、地面すれすれから見上げるような画角のものなど、それらは全て屋外から私の部屋の窓を撮影した画像だった。
こうしている間にも次々と写真がアップされていく。写真は私の家のものだけではなかった。新築の一軒家は明らかに夏希の自宅だし、空中から撮影されたとしか思えないマンション四階の写真は玲奈の家だ。古い日本家屋は遥の自宅ではないだろうか。
私はそれらが発するメッセージが明確に理解できた。そいつらは求めているのだ。私たちがトゥルージーで共有することを。今、私たちがどうしているのか知りたがっている。それが知り得ないのであれば、その者のそばに行くしかない。
ひなぎさんは亜美が考えた作り話にすぎない。創作なのだ。でもそれは現れた。亜美自身が生み出してしまったものなのか、それとも、もともと存在していた何かが亜美の創作物によって目を覚ましてしまったのか。
確かなのは、それが間違いなく存在するということだ。
トゥルージーは私たちをリアルタイムに
私はすぐに自分の写真を撮影してトゥルージーにアップした。
三人にも連絡してトゥルージーのグループが今どうなっているのか教えた。三人ともアプリを削除してしまっているからだ。玲奈と夏希は私の勧めに従って、またトゥルージーにログインして写真をアップした。けれど、遥はそれを嫌がった。もう二度とトゥルージーはやりたくないという。
私は直接通話して遥を説得した。今や大勢のひなぎさんたちがトゥルージーで共有を望んでいるのだと。それに
翌日、トゥルージーから通知が来たのは亜美の時と同じように夜になってからだった。遥はやはりトゥルージーを更新することはなかった。その代わり、今や多数に増えていたひなぎさんたちのアカウントから遥の写真が数多く投稿された。それらの写真は全て遥の部屋で撮影されたものだった。
立ち上がった遥が何かから逃れるように両手を胸の前にかざしている。驚愕に見開いた目はカメラに向けられ、口はいびつに
遥はその夜を最後に行方がわからなくなった。この直後に自宅を出たらしいことはわかっていたが、どこに行ったのかはわからない。財布も着替えも何も持たずに
その日から、私たち三人は毎日必ずトゥルージーを更新して日常を共有するようになった。それも必ず二分以内に。
授業中だろうと、電車の中だろうと気にしてはいられない。私たちのトゥルージーのグループには、その後も例の黒画像のアカウントが増え続け、その数は百アカウントを超えていた。それだけ沢山のひなぎさんたちが私たちのグループに加わり、私たちの日常の共有を望んでいる。それを怠れば、向こうからやってきてしまう。ひなぎさんは私たちと繫がりたいのだ。繫がってしまったのだ。
毎日忘れずにトゥルージーを更新することは、負担ではないといえば噓になる。初めのうちは、ひなぎさんたちが迎えに来ることがただ恐ろしく、ずっと追われているような気持ちだった。けれども、最近では少し心境が変わった。ひなぎさんたちに連れ去られてしまうのも、それほど悪くないということがわかったのだ。
というのも、ひとつ気がついたことがあるからだ。
ひなぎさんたちがアップする黒い画像。それらは常に何の濃淡もない真っ黒なものなので、撮影された写真ではなく黒いピクセルの集まりだと思っていた。だが違っていた。これらも写真だったのだ。ひなぎさんも日常を写真共有してくれていたのだ。それに気付いたのは、夜、暗い部屋の中でひなぎさんのアップした画像をぼんやりと眺めていた時のことだ。この黒一色と思われた画像の中にうっすらとした陰影があることに気がついたのだ。私は画像編集機能を使って、この写真のコントラストの値を最大値まで上げてみた。するとそこにはっきりと見えたものがあった。
それは亜美と遥だった。ふたりは何もない空間に寄り添うようにして並んで立っていた。こちらを見る
私たち三人は毎日必ずトゥルージーを更新し日常を共有しなければならない。それも必ず二分以内に。
そのうち、私たち三人のうちの誰かが疲れ果て、トゥルージーをやめる日が来るかもしれない。それが夏希なのか、玲奈なのか、それとも私なのかはわからない。その時、きっとひなぎさんが現れる。でも怖くはない。行き先はわかっているからだ。亜美と遥にまた会えるのだ。
五人はまた一緒になれる。その日が本当に待ち遠しい。
あの闇の中に五人揃ってずっと一緒。そうしたらもうトゥルージーなんて必要もないのだから。
編集者との打ち合わせ(一)
一気に書き上げた「トゥルージー」をKADOKAWAに送信すると、その週のうちに今井から電話で連絡があった。
「和田と菰田も一緒に拝読しました。良かったですよ、トゥルージー」開口一番、今井はそう話した。「アップしなければ殺されるというドライブ感もあるし、SNSの危うさも描かれていて、はっとさせられる名作ではないかと!」
流石に褒めすぎだろうと思ったが、一定の評価を得られたのは確かなようだ。短編としてかたちにはなっているようで、とりあえずほっとする。私は電話口に話した。
「こんな感じで良かったですかね。でしたら、この調子で他の短編も書いてみようかと。いくつかプロットをお送りします」
「はい。お願いいたします」
「なんかこう、一貫したテーマがあったほうがいいですよね。せっかくの書き下ろしですし。そこのところ、前の打ち合わせでもふわっとしたままだったというか」
「ですね」と、今井は同意して言葉を継いだ。「トゥルージーは、やはり身近なスマホが怪異の
「はい。でも全てスマホ絡みの話にするというのも勇気がいりますし。前回の打ち合わせでは日常という話もありましたが、一貫して身の回りに潜む恐怖というのはどうかと」
今井は電話口でううんと悩むように
「テーマとしては広範ですね。もっと絞っても良いような気もしますが。原さんのほうで何か構想がお有りですか?」
「通勤や通学とか買い物とか、誰しも日々外出すると思うのですが、次のやつはそういった日常から広げてみようかと」
「外出、と、いいますと」
「例えば、道路とか橋とか。一歩外に出たらどこにでもある場所に潜む恐怖です」
すると電話口の今井は何故だか急に押し黙った。
「今井さん?」
「……ごめんなさい。聞いています」やや間があって液晶画面から今井の声がした。「それって、何か着想のきっかけがあったんですか?」
表情は見えないが、常に朗らかな今井の声色にどこか影が差したようにも感じた。何か懸念でもあるのだろうか。
「きっかけというものは特にありません。まあ、道を歩きながら考えていたら思いついたというか」
私はそう答えて、続けて構想を話すと、
「なるほどですね。怖くなりそうな気がします」と、今井はいつもと変わらぬ明るい声を返してくれた。
さっきの不穏にも思えた彼女の反応と気配は、こちらの考えすぎだったのだろうと思った。
だが、そうではなかったことに、ずっと後になってから私は気づくことになる。
(続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:身から出た闇
著 者:原 浩
発売日:2025年08月25日
この本ができあがるまでに、編集者が二人消えています。
これは私が、角川ホラー文庫編集部から依頼を受けた連作短編集です。駆け出しの私に依頼が来るだけありがたく、最初は喜んで引き受けた作品でした。しかし、短編を提出するごとに、担当編集の休職が発生している以上、これを刊行するという編集部の判断が、正しいのか分かりません。
※このあらすじは、原浩氏の強硬な主張により、挿入されたものです。編集部の意図とは相違があります。本作は、あなたが望んでいる作品です。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000625/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら