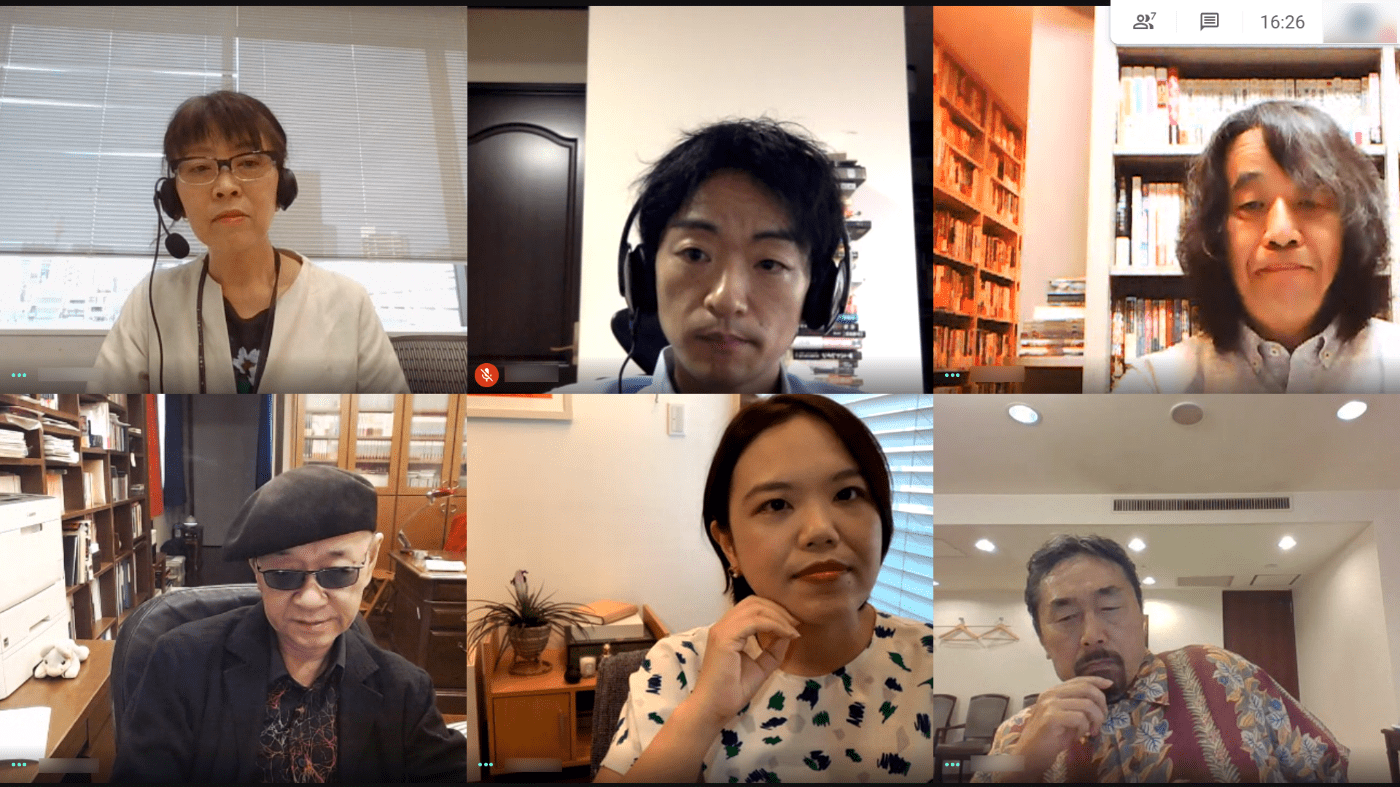KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み①
お前の死は私の生
まただ。またいつもの夢。
私は自分の身体が夢境の泥沼にあるのを認識している。夢から覚醒しようともがくが、下肢は粘液に囚われて思うようにならない。叫ぼうにも縫い付けられた唇は開かない。海底を這うようにもどかしく歩を進める。
逃れなくてはならない。
お前の死は私の生
再び、冷淡な声が告げる。
誰が何故そんなことを言うのだろうか?
私は自らを取り巻く暗黒に目を凝らす。声の主の姿はどこにも見えない。しかし私は確信していた。そいつは、とても近くにいる。そして同時に遠いのだ。
夢魔だ。
重なり合っていても、現実に邂逅することは無い。そいつは混濁し、たゆたう意識の内にのみ現れ、私の命を脅かそうとしている。
あなたは誰?
私は問いかける。が、やはり答えは無い。
取り巻く海底の漆黒はいよいよ圧力を増し、私の身体から蝶つがいが外れるような断裂音が響く。海面に這い上がろうにも、恐ろしい水圧が脳天から私を押さえつける。やがて二次元に投影された影のように、私の五体は海溝の底に潰され、張りつけになるのだろうか。
こうなれば、あと数秒で目が覚める。それは経験で知っていた。そして覚醒後、間もなく夢の内容は忘れてしまう。いつものように。
理不尽に自分の命を摘み取られるわけにはいかない。生きる為に戦わなければならないのだ。
覚醒前の一瞬、私は決意を新たにした。
始まる日
この信州中南部独自の民家形式は本棟造りという。開いた本を伏せたような緩やかな勾配の板葺き屋根が特徴で、建物の幅も広く堂々とした威風を帯びている。屋根の頂点には羽を広げた鳥のような棟飾りが据え付けられており、その形から「雀踊り」とも呼ばれる。昔からこの辺りの大きな農家や庄屋の家屋はこの形式で、戦前まで遡れば数多くあったらしい。しかし現在では希少になり、たまに物好きな見物人が写真撮影を請うこともあった。
南に向いた玄関口には夏日の陽光が照りつけ、木戸の曲がりくねった木目を輝かせている。常と変わらぬ久喜家の姿だ。私は生まれ育った我が家を仰ぎ見た。二週間離れていただけだが、この家に戻れば、やはりほっとする。
戦前に建てられたこの古民家の装いが、子供の頃は全く好きではなかった。しかし今や信州全域でも希少な歴史がここに在ると思えば、少しばかり誇らしくも感じるものだ。
玄関脇の古びた表札には「久喜保」と、祖父の姓名のみが掲げられている。私は埃のかぶった文字面を指で拭った。
盆を過ぎてもなお八月の日差しは厳しい。どうせ鍵などかかってはいないだろう。田舎では防犯意識も薄く、施錠などいい加減なものだ。しかし、玄関の木戸に手を伸ばして、私は固まった。
(嘘だろ)
かぶと虫の雄が木戸の持ち手にとまっている。
私は幼少期から虫が苦手だ。その性分は三十路を前にした今でも変わらない。中でもかぶと虫に類する甲虫は特に気味が悪い。小学生の時分は友人たちの多くがかぶと虫を飼っていたが、とても気が知れなかった。艶々とした背が粘液を塗したみたいで触る気になれないし、ツノの形もどこか猥雑で不気味だ。バナナが腐ったみたいな臭いも気に入らない。友達は臭いなど何も気にならないと言っていたが、私にとっては全くもって信じ難いことだった。
こいつに触れずに戸を開けられるだろうか。戸板は古いだけに建てつけも悪く、無理矢理に引くとごろごろと地面を擦こすり、やたらに重いことを知っている。
「……どれだけ田舎だよ。くそ」汗を拭って独り言ちていると、不意に声をかけられた。
「雄司さん、おかえりなさい」
躑躅の植え込みから歩み出てきたのは、妻の夕里子だった。裏の畑にでも行っていたのだろう。胡瓜を山と盛った銀色のボウルを抱えている。
「こりゃまた、胡瓜がよくお似合いですね、夕里子さん」
私がからかうと夕里子は片眉をぴくりと上げた。
「なあに? 田舎者臭いって言いたいの?」
「いやそんな。夏野菜が似合うなんて、褒め言葉だと受け取ってもらえないのかな」
私のおどけた笑顔に夕里子は無表情で返した。
「妻を揶揄しないでください。うちの旦那さまはさぞや都会人におなりでしょうね」
「一度出張に行ったくらいで洗練されないよ。新婚なんだから大都会への出張は当分勘弁して欲しいなあ」
「仕事ですよ。それに入籍から一年も経って新婚なんて言えるのかしら」
夕里子は口をへの字に曲げたままだが、機嫌が悪くないことはわかる。
「……で、その胡瓜、精霊馬にするの?」
夕里子はきょとんとした顔で「ショーリョーマ?」とおうむ返しした。
「ほら、野菜で作った馬とか牛を飾るじゃないか。お盆は」
夕里子は呆れ顔で、
「今頃何言っているの。お盆は終わってます。それにこんなに沢山。これは浅漬け」と答えた。
「そか。いや、でも漬物にしても多くない?」
「あなた好きでしょ?」
「何が?」
「胡瓜の浅漬け」
「好き」
「じゃ、良かったですね。お腹いっぱい食べてください。駅からはタクシーで?」
「そう」
「電話してくれたら迎えに行ったのに」
かける言葉とは裏腹に淡々とした無表情は変わらない。夕里子は色白と切れ長の目つきが相まって普段から能面みたいに冷たい容貌だが、私にとっては昔から、それこそ妻となるずっと前から心の許せる女性だった。二週間ぶりに対面した夕里子はちょっとだけ肥えたようにも見えるが、彼女の纏う凜とした空気はいつもと同じだ。
夕里子に初めて出会ったのは高校の頃だった。
入学してすぐ、気まぐれに入部した天文気象部に夕里子は一学年上の先輩部員として在籍していた。当初は彼女の愛想の無い瓜実顔に、どうにも好感が持てなかった。気難しくて付き合いづらいタイプに思えたからだ。
初めて言葉を交わしたのは、たちの悪い先輩に百葉箱の壊れたよろい戸の修理を命じられた時だ。不注意でよろい戸を壊したのは、当の先輩だったが、顧問の教師に気づかれる前に修理するようにと隠蔽工作を私に命じたのだ。
人の好い私は誰にも相談できずに途方に暮れていたが、それまで全く話したことのなかった夕里子が突然近づいてきて、無表情な顔で私に告げた。
「工具は用務員さんに借りられます。白ペンキは美術部の部室に置いてあるものを勝手に使えばいい。バレません」
「百葉箱のこと、知っているんですか?」
私が驚いて訊くと、夕里子は領いた。
「今夜の天体観測の前に作業を済ませましょう」
夕里子は私が何に困っているのか、何故だか正確に把握していた。私の様子から察してくれたらしい。実際に修理をした際も、夕里子は当然のことのように手を貸してくれた。そのお陰で、私は誰にも気づかれることなく隠蔽工作を終えられた。
後日、修理を命じた先輩は、理不尽な要請を神妙な面持ちで私に詫びた。それも、夕里子がそれとなく上級生に訴えてくれたらしい。
それから、私は自然と夕里子が気になるようになった。彼女は口数も少なく、一見何を考えているのかわからなかったが、誰に対しても細やかな気配りがあった。表情が薄く、ろくに笑顔も見せない癖にお笑い番組を録画して繰り返し見ているという意外性も、どこか可愛らしく思えた。
私は意を決して彼女に好意を伝え、交際をするようになった。高校生らしくそれなりに青春した付き合いを続けたが、彼女が先に卒業し、遠くの大学に通うようになると徐々に疎遠になり、一度別れてしまった。よくあるパターンだ。その後、決して追いかけたわけではないが、一年後に私も彼女の近くの大学に通うようになると再会し、紆余曲折の末によりをもどした。長い付き合いを経て、昨年ようやく結婚して今に至る。
夕里子は童顔に加え背丈も小柄なせいか、実年齢より若く見え、高校生と言っても通じてしまいかねない。それでいて老成した落ち着きもあり年齢不詳な雰囲気があった。一つ歳上に過ぎないが、高校生からの上下関係の延長で、いまだに下級生みたいな扱いをされるのだった。
「暑いから入ってください」夕里子は抱えたボウルで両手がふさがっている。
「ああ、そうだね……」私は戸を見る。
(まだ、かぶとがいる……)
逡巡していると、夕里子が私の視線を追った。私の顔とかぶと虫を見比べてため息をつくと、抱えたボウルをこちらに押し付けてきた。
「これが怖いんですか?」
夕里子は左手でひょいとかぶと虫の背をつまむと、それをかざして見せた。
「あ、いや… …」言葉に詰まり、汗が出る。かぶと虫のぬらりと蠢く黒、夕里子の白い指、それを飾る結婚指輪のルビーの赤。全てのコントラストが何とも気味が悪い。
夕里子はかぶと虫を砂利の上に置いた。そいつはのろのろと羽を広げ、ぶんと音を立てて重そうな体躯をふらふら揺らして飛び去った。
「田舎者なのに、相変わらず昆虫が怖いのですね」無表情に言われると、余計に気恥ずかしい。
夕里子は他人の持ち物とか公共施設のものには、あまり触りたがらない。昔から潔癖症の傾向があるのに、虫だろうが蛙だろうが蛇だろうが、生き物には全然抵抗が無いらしい。長い付き合いの夫としても、理解しがたい彼女の一面だ。
「いや怖いわけじゃなくて……」
「あなたの髪の毛、汗だく。のびてきたし、そろそろ切ったら?」
夕里子は私を冷たく一瞥し、土間への木戸をからからと開くと、さっさと中に入っていった。
まだ日も高いのに気の早いヒグラシの声が喧しい。家の裏手北側には竹藪があり、その向こうには頂上に小さな社を祀まつった雑木林の丘陵がある。それは裏山と呼ばれている。自宅との位置関係を考えれば、裏山と呼称できるのは久喜家だけだが、周辺の家々でも何故か皆そう呼ぶ。
土間に入るとさすがに蝉の声は遠くなる。三和土の土間は、ひんやりと暗い。広い空間だが、隅には古い農作業用具だの竹箒だのが雑然と積まれていて、面積の割には窮屈に感じる。
「あのね、怖くはないけど触った感触が気持ち悪いんだよ」
「そう」夕里子は取り繕う私に目もくれずに答えた。
「あ、そうだそうだ。母さんに聞いたよ。墓のこと」
冷ややかな態度をかわすべく目先を変えた話題に、夕里子は振り返った。
「……はい。どう思いますか?」
「悪質だね。人の家の墓にいたずらをするなんて、罰当たりな奴がいるもんだ」
「いたずら、ですか」
言いながら夕里子の視線がくるりと天井を巡った。長年の付き合いで、これは夕里子の否定的な反応だと知っている。
「いたずらじゃないの?」
夕里子は小首を傾げ「……だといいんだけど」と、答えた。
妙な返しだ。
「ところで、さっき……」夕里子は向き直ると真っ直ぐに私を見る。「こいつ太ったなって思ったでしょ?」
黒目に吸い込まれそうで怖い。私は慌てて否定した。我が妻は勘が鋭いのだ。お盆に食べ過ぎたのだと弁解の言を呟きながら、夕里子は台所に引っ込んだ。
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/