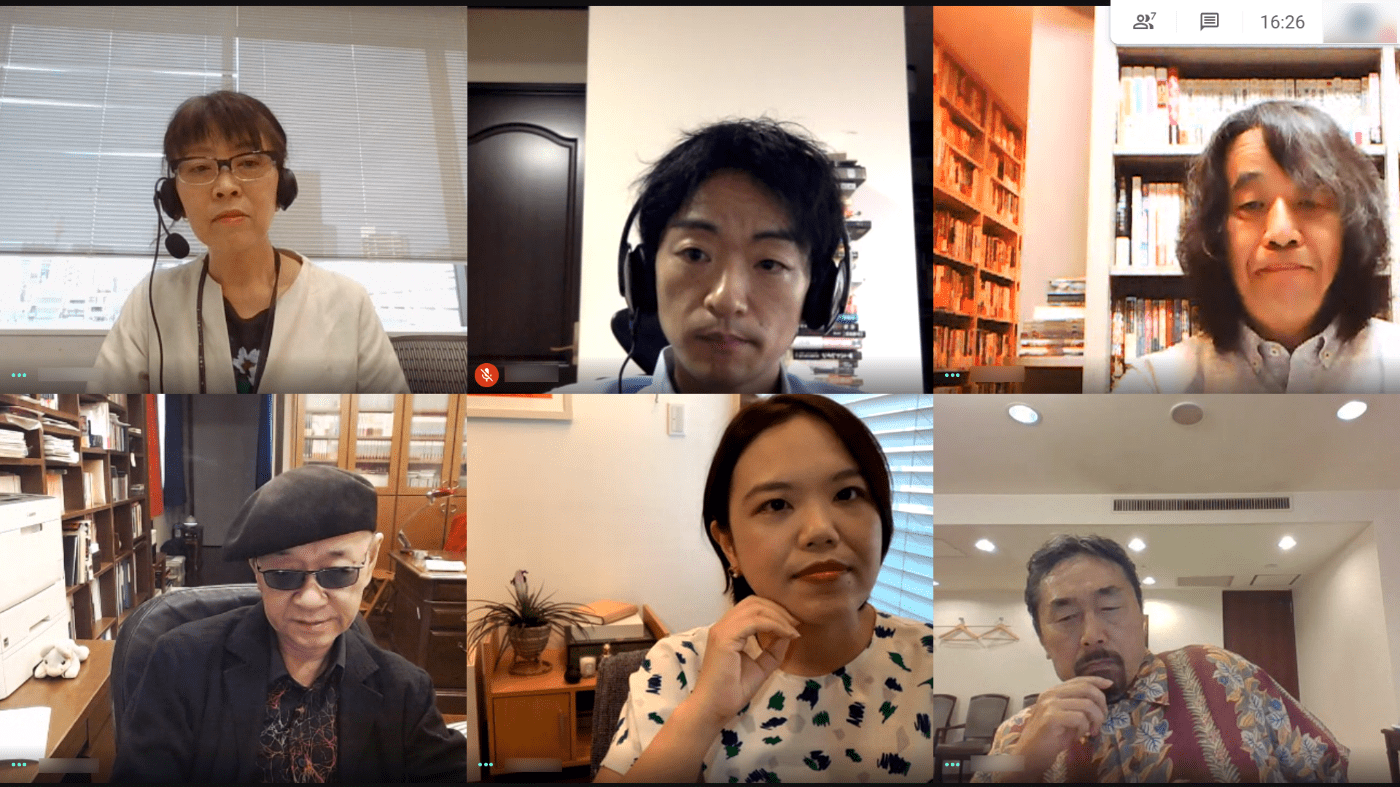KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
>>試し読み①へ
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み②
黒光りする板敷の廊下を通って奥座敷にある仏間に行くと、祖父、久喜保が座卓に背を向けて座っていた。私に気がつくと祖父は振り返って「おう、孫か。帰ったな」と言って再び背中を向けた。脳天はすっかり禿げ上がっているが、側頭部には侘しい白髪をふわふわとまとっている。どうやら足の爪を切っていたところらしい。
「仕事はどうだった?」広げた新聞紙に爪を飛ばしながら保が言った。
「ん。まあまあかな。帰省シーズンだし、どこもかしこも人がいなくてがらがら。ただ、こっちに比べると蒸し暑くてかなわなかったよ。この時期、暑いところは嫌だわ」
「ほうか。災難だったな」
祖父の保は八十三歳という老齢の割には、腰もさほど曲がらずに肌も艶やかで振る舞いも矍鑠としている。連れ合いが亡くなり、続いて十七年前に一子の雅史――私の父――までも若くして亡くした折には、気落ちゆえか一時期健忘症の気を発し、家族を心配させた。しかし次第に元気を取り戻し、庭いじりや畑仕事などを再開するに至ると意識も明瞭になった。それどころか今では、同年代の平均的な高齢者よりずっと健康で頭の回転もスムーズだ。
父の遺影に手を合わせていると、母の伸子が、おかえりと顔を出した。玄関先で夕里子に会ったことを伝えると、伸子は相変わらずの早口でまくしたてた。
「夕里子さんはできたお嫁さんよ、本当。つくづくそう思うもの。庭の植木、綺麗に剪定されていたでしょう? お盆なのでそろそろ手入れをしましょうって、夕里子さんが植木屋さんを全部手配してくれたんだから。あんたはそういうところ全然気が付かないじゃない? 無頓着というか鈍感というか。本当、男ってそういうものなのかねえ」
伸子は夕里子をいたく気に入っていて、何かにつけて褒めそやす。おしゃべりな姑と寡黙な嫁、気性の真逆な二人はかえって相性が良いのだろう。なんにせよ嫁姑問題が無いのは良いことだ。母の話が、ご近所の嫁姑間の諍い話に及びつつあったので私は無理に話をそらした。
「で、墓は今どうなってんの?」
伸子は「ああお墓ね」と、眉をひそめる。
「そのままよ」声を落として言った。
「まだ直してないの?」
「直すって、あんた、あんなの簡単に修理できないわよ。お金もかかるんだから。大体どうやって修理するのかねえ」
誰の仕業か心当たりが無いのかを問うと、伸子はかぶりを振った。
「犯人は見当つかないよ。気持ちが悪い。警察に届けようって夕里子さんとも話してたところ。うちが他人様に恨まれるような覚えもないけどね、本当。ね? おじいちゃん?」
聞こえなかったのか、保は背を丸めたまま答えない。足の爪をヤスリで削っている。
「壊されたのは大伯父の部分だけなの?」訊くと伸子は首肯した。
「そうよ。日記が今日届くことを考えると、妙な偶然よね」
「え? 今日なの?」
「そうよ、言わなかった? タイムスの記者さん、写真撮るみたい。いやだ、お化粧しなきゃ」
母がばたばたと引っ込むと、入れ替わりに珍しい顔がのそりと仏間に入ってきた。夕里子の弟、瀧田亮だ。亮は義兄さんお久しぶりです、と頭を下げた。
「来ていたんだ? 夕里子さん、何も言ってなかったから」
「一昨日からサークルの合宿で白樺湖の民宿に遊びに来てたんです。大学、夏休みですから」
「学生生活をエンジョイしてるね。羨ましい」
彼は夕里子の歳の離れた弟で、去年、東京の大学に進学した。昔から知ってはいるが、普段は顔を合わせることもない。会うのは我々の結婚式以来だ。ちょっと見ない間にいつの間にやら髪色も明るく垢抜けて、いかにも当代の大学生になったものだ。
「合宿は今朝までだったんだけど、俺だけ東京に戻らずに寄っちゃいました。姉さんに『日記』の話を聞いて面白そうだったので」「そりゃまた、お若いのにモノ好きな」
「姉さんに小遣いせびりに来たわけじゃないですよ」亮は笑って頭を掻いた。
「ああ、小遣い目当て?」
「あ、嘘嘘。本気にしないで下さい。いやでも、半分本当かな? 今月ピンチなんで、こちらで一晩ご厄介になればその分食費も浮くかな、なんて」
「相変わらずだね」
厚かましい軽口もどこか憎めない。義理の弟とはいえ、交流が深いわけではないのに十年の知己のように感じさせるのは彼のキャラクターだろう。そもそも、姉の嫁ぎ先に気軽に立ち寄ろうと思えるところが凄すごい。自分には一生辿り着けない境地だ。感心する他ない。
「でも日記に興味があるのも本当ですよ」と亮は続けた。「面白そうじゃないですか。死者の書いた日記なんて」
死者の日記。興味をひかれるのもわかるが、どうも不謹慎だ。
「期待に応えるものじゃないかもしれないよ。何しろ古い日記だし、ろくに判読できないかもしれない」
「まあ、それならそれで仕方ないですけどね」と亮は首を竦めた。「……ところで、ここって禁煙ですか?」
「亮くんタバコ吸うの? うちは喫煙者いないから灰皿も無いよ」
「嘘だあ」と、亮は箪笥の上を指差した。「あれ、灰皿ですよね? あのでかい奴」
よく目が利くものだ。確かに箪笥の上にガラス製の灰皿が埃をかぶっている。二時間サスペンスドラマならば、犯人が衝動的に被害者を撲殺する際の凶器に使えそうな重厚な代物だ。
思い出した。死んだ父が使っていた灰皿だ。遺品として大切にとっておいたのではなく、単に捨てるタイミングが無かったものだ。
「吸うなら使っていいよ」
「へいへい、ちょっくら拝借して、庭で吸ってきます」
「若いうちに悪癖は治すべきだぞ」
「自分でも禁煙したいと思ってるんですけどねえ」と、亮は眉を寄せて見せると、潰れたマールボロのケースと灰皿を手に座敷を出て行った。
禁煙も何も、よく考えたら彼はまだ二十歳になったばかりの筈だ。思わず苦笑した。
「……じいちゃんは親父が亡くなるまで吸ってたよね? よくその歳から禁煙できたよね」
昔の記憶では保はかなりのヘビースモーカーだった。しかし、息子の死をきっかけに悪癖から抜け出したのだ。保は爪切りを桐材の物入れに仕舞い込むと、背を向けたまま答えた。
「タバコも連れがいないと、美味くねえんだ」
「そのおかげで長生きできてるじゃん」
保は鼻先でふんと笑った。
「おれが入る前に墓が壊されなきゃあいいけえどな」
「出張中に話は聞いたよ。けど、どういう嫌がらせなんだろう。わけがわからないな」
墓石の損壊。何の意図があるにせよ、不愉快なことには違いない。
保は不快そうに薄い唇を曲げる。
「新聞社が来るまで、まだ時間があるら。夕里子さんと墓を見て来いやれ」
私の仕事は毎年この時期はどういうわけか多忙を極め、ここ数年は夏季休暇もままならない。今年もお盆時期に長期出張が重なり家をあけたが、その出張中に二つの出来事が起こった。
一つは、久喜貞市という人物の古い日記の発見。もう一つは久喜家代々の墓になされた奇妙な破壊行為だ。
久喜家の墓は家から徒歩で十分とかからない小さな墓地にある。植え込みと枯れかけた松の木に囲まれたその墓地は、遠くからは田園の海に浮かぶ離れ小島のように見えた。夜になると、すぐそばの農道に一本だけ立っている街灯の灯りが、イカ釣り漁船さながらに、この墓場を煌々と照らす。
「そっちじゃありませんよ」
後ろを歩く夕里子に叱られて、左に進みかけた歩みを慌てて反対に向けた。
「ご自分の家のお墓を忘れたのですか?」夕里子が呆れたように目を細めた。どうもいまだに部の先輩にたしなめられているような気分になってしまう。
盆の入りに墓参し、先祖の霊を迎える為に線香を手向け、家に戻って迎え火を焚く。仕事のせいでこの行事にしばらく参加していない。その為、この狭い墓地で自分の家の墓石の場所すらあやふやで満足に覚えていなかった。言い訳をするならばこの墓所にある墓は、ほとんどが久喜家と縁戚関係にある家のものだ。なにしろ、「久喜家」と刻まれた墓石だけで三基ある。既に関係の薄い分家などもあるが、多くの家と何らかの親族付き合いはあった。
「これか。これだった」
目の前に先祖代々の墓が現れた。棹石には久喜家という文字が刻まれ、花立には我が家の家紋である木瓜が彫り込まれている。一見したところは何の変哲も無いように思える。
「ここを」
夕里子が指差した棹石の側面を見ると、異常は明らかだった。
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/