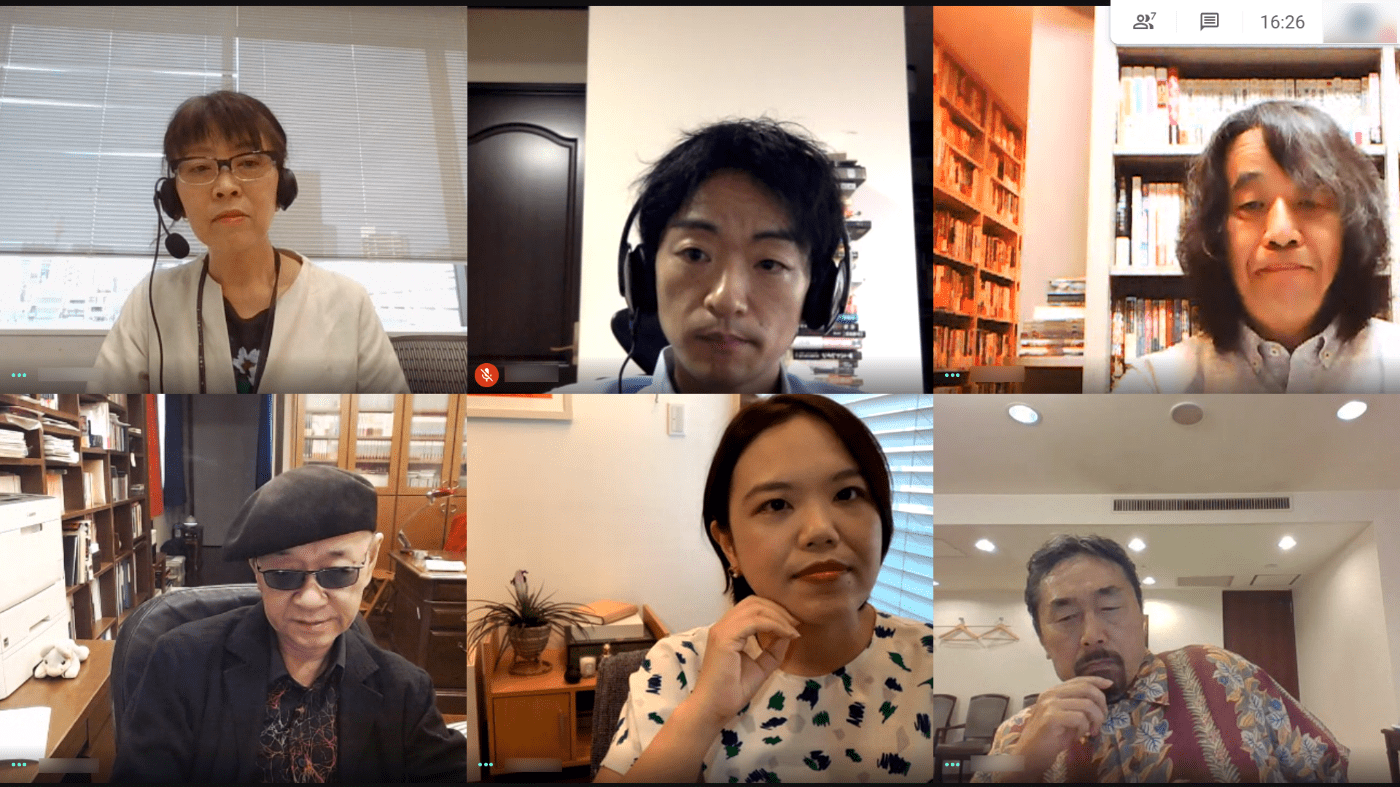KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
>>試し読み②へ
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み③
棹石には埋葬者の没年月日、戒名と共に俗名が刻まれている。
最も左には今から十七年前、四十四歳の若さで亡くなった私の父、雅史の名前がある。平成十四年十月二十日没。死因は自動車事故だった。渋滞中の高速道路で居眠り運転のトレーラーに追突されたのだ。玉突き事故だったが、死んだのは父だけだった。その時、助手席には祖父の保が、後部座席にはまだ中学生だった私も同乗していたが、幸いに二人とも軽い打撲で済んだ。事故の記憶は曖昧だが、車内から運び出される父のだらんと垂れた両腕だけが鮮明に記憶に残っている。
父の名前の右には祖父の亡き妻であり、私にとっての祖母の名前。
問題はその隣の行だ。その一行のみが荒々しく削り取られている。欠落した行の先には更に昔に亡くなった曾祖父、曾祖母の名が続いているが、それらの名前に欠損はない。
「なんだ、こりゃ……」
欠損部分には何か工具のようなもので砕かれた跡が見える。自然に朽ちたようには到底思えない。明らかにその箇所を狙って削り取っている。墓石の破片は周囲には落ちていないので、持ち去られたのかもしれない。
「これに気がついたのは四日前の朝です。私が掃除に来て、それで。迎え盆の時には異常は無かったので、いたずらをされたのはこの二週間の間です」
私は思わず欠損部分に手を伸ばす。石面はかなり深く削られていた。もともと彫り込まれた文字を完全に消すために余程深く削り取ったのだろう。やはり人為的なもののように思えた。
「お盆時期に、こんな悪さをしていたら誰かの目に留まりそうなものだけどね」
「まあ……、深夜ならば目立ちにくいとは思いますが」
確かに夜更けに人通りは無いだろうが、ここまで深く削るにはそれなりに準備が要りそうだ。子供のいたずらにしては、手間がかかり過ぎている。
「ここに記されていたのが、大伯父の名前ってこと?」
私の疑問に夕里子は頷いた。
「久喜貞市。昭和二十年六月九日。享年二十二歳。と、彫られていたそうです」
貞市は太平洋戦争で亡くなった、保の兄だ。
それにしても、誰が何のためにこんな悪さをしたんだろうか。うちの家に嫌がらせをするなら、正面側の久喜家の墓碑銘に傷をつければいい筈だ。
夕里子がひかえめに口を開いた。
「……雄司さんは、ただのいたずらだと思いますか?」
「いたずらにしては手がこんでいる気がするな。不可解だね」
「不可解なのです」
夕里子が続きをうながすように私をじっと見つめた。
「こういう時、ミステリー小説だと、犯人の動機から推理するね。墓石を傷つけて誰が得をするのか、とか」
「誰かの得になりますか?」
「そうだな……。例えばこれは何かの目くらましになっているというのはどうかな。目に留めて欲しくない真実から気をそらせようとしている、とか」
「ミステリー小説なんて全然読まないでしょ?」
「読まないね」
「…………」
夕里子は表情を変えない。決して大きな目ではないのに、彼女がじっと見つめるだけで無言の圧力がある。八月末の昼下がり。気温はそう高くはないが、風もなく、やけに蒸し暑い。私は苦し紛れに笑顔を浮かべた。
「ま、誰かの得にもなりそうにないし、どんな真実を隠そうとするのか、全く解らないけど」
夕里子は御影石の表面に手のひらを押しつけると、そっと滑らせた。
「ミステリーではないのかも」
「は?」
「サスペンスとか……。いえ、ホラー映画だとしたらどうでしょうか?」
「……怖いことを言わないでよ。大伯父のお化けがやったとでも?」
確かに名前を消された張本人の「日記」が同時期に戻ってくるというのは、奇妙な符合である。怪談話の種にはなりそうだ。私は茶化すように言ったが、夕里子は笑わなかった。
「いえ、ごめんなさい。そういうつもりではないのですが。最近、夢見が悪いせいかしら ……」夕里子は目を伏せて、取り繕うように言った。「何かが、おかしい気がして」
「へえ?」
「上手く言えませんが」
「夢見悪いって、どんな夢? 暑いし、疲れているんじゃない?」
「起きると忘れちゃうんだけど、どこか奈落に引きずり込まれるみたいな… …」そこで言葉を切り、「あ、お義母さん」と、夕里子は手にした携帯電話を耳に押しつけた。
何かがおかしい……?
夕里子がこういう類の物言いをすることが、これまで全くなかったわけではない。私には理解しがたい妻の一面がたまにこうして顔を覗のぞかせることがある。その度に、私にはごろごろと口内に残る異物のように感じられるのだった。
電話の様子からすると記者がうちに来たらしい。私は何も考えないようにして墓場に背を向けた。
帰宅すると、奥座敷には二人の記者が待ち構えていた。
ぽってりとした厚い唇がやけに目立つ、黒縁眼鏡の女性は与沢一香。顎鬚をたくわえ、ニューヨーク・ヤンキースのキャップを被った男性は玄田誠と名乗った。玄田は新聞記者というよりも山男といった風貌だ。与沢の方が明らかに若く、二十代後半といったところだが、どちらかと言えば彼女が取材の責任者であるらしい。玄田記者はカメラを肩に下げていることから撮影係なのだろう、説明や我々とのやりとりはもっぱら与沢記者に任せていた。
座敷では記者たちの他に、祖父の保と母の伸子、義弟の亮もすでに座卓を囲んでおり、私と夕里子もそれにならう。
与沢記者は一同の許可を得て、録音状態のボイスレコーダーを卓上に置き、黒縁眼鏡をくいと押さえると、その厚い唇を開く。
「私共信州タイムスでは、先ごろの終戦記念日に合わせ、太平洋戦争の特集記事を掲載致しました。こちら様でもご購読頂いていると伺っておりますので、お読み頂けたかと思います。その特集の中で、ニューギニア戦線にスポットをあてた記事がありました。今夏、東部ニューギニアにて催された海外戦没者慰霊祭を、私と玄田が取材したものです」
与沢が差し出した記事には私も覚えがあった。
太平洋戦争初期、日本はトラック諸島における海軍基地防衛、及び米豪の連携遮断を企図し、ニューギニア島をはじめとする南方の島々に進出した。しかし、連合軍により空路海路が封鎖されて補給路が断絶すると、戦局は惨憺たる経過を辿る。南方戦線での敵は、連合軍ではなく飢餓と疾病に変わったのだ。敵地で孤立した兵士の死因は、銃火による戦死よりも、病死や餓死が大半を占める状況であったという。
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/