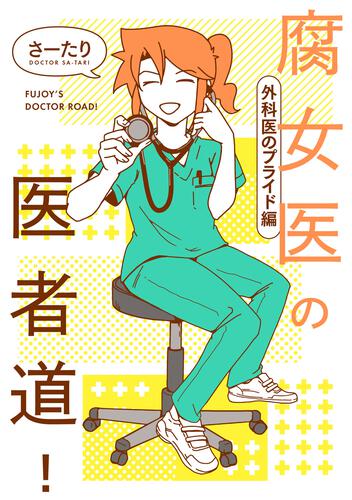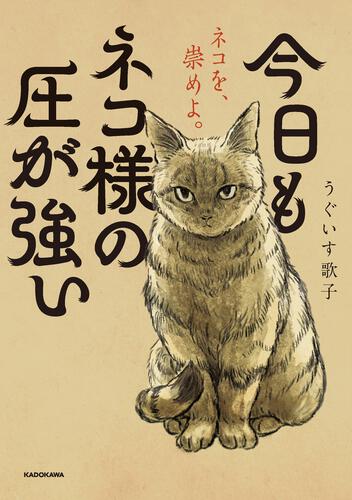これから“来る”のはこんな作品。
物語を愛するすべての読者へ
ブレイク必至の要チェック作をご紹介する、
熱烈応援レビュー!
(本記事は「小説 野性時代 2025年9月号」に掲載された内容を転載したものです)
書評連載「物語は。」第139回
笹原千波『風になるにはまだ』(東京創元社)
評者:吉田大助
今の自分から地続きで始まっていく未来に
素直な希望を抱くこと
一九九四年生まれの俊英・笹原千波のデビュー作『風になるにはまだ』は、第一三回創元SF短編賞受賞の表題作を出発点とする連作短編集だ。SFジャンルが長らく追求してきた「意識(精神)と肉体」の関係を筆頭に、人間にまつわるさまざまな問いを盛り込んだ詩的な物語となっている。
とにかく、全ての始まりとなった第一編「風になるにはまだ」が素晴らしい。大学三年生の「あたし」はこの日アルバイトで、肉体を捨て情報体となって仮想世界で生きている四二歳の女性・
報酬が高額とはいえ脳にナノボットを埋め込むなど、リスクを伴う仕事を「あたし」はなぜ引き受けたのか。〈むかしから、あたしらしさって呼べるのは背の低さくらいだった〉という「あたし」は、自分に自信がない人生を送ってきた。でも楢山さんにとって、身長と体重がぴったり同じで、肉体があった頃との違和感が少ない「あたし」の体は、最高に特別な存在だったのだ。一方で、楢山さんが一三年前に情報体になることを選んだ背景には、彼女のアイデンティティに関わる出来事があった。一人の体に共存する、二人の視点をスイッチしながら進む、という構成が効いている。
自分の体を自分よりもうまく乗りこなしてくれる──自分の個性にぴったり合う洋服を選べる──楢山さんは、「あたし」にかすかな劣等感を呼び起こす。しかしそれ以上に、「あたし」の体を愛おしく感じている楢山さんの思いを受け取ることで、「あたし」は自分の体への、自分の人生への肯定感を手に入れていく。他人の人生を生き、知り、追体験することは、憧れと同時に、自分は他の誰にもなれないという諦めもまた引き起こす。だが、それは絶望ではなく、希望になり得るのだ。
第二編「手のなかに花なんて」以降も、現実世界に生きる人と仮想世界に生きる人との交流が描かれ、この構造を採用したからこそ発見されることとなった特別な感情や関係性が探り当てられていく。仮想世界においても「散逸」――データの塵になる――という死の概念が、住人たちを脅かしているという設定は重要だ。住人たちは「散逸」を逃れるために、できるだけ現実世界と変わりない生活を送ることを余儀なくされた。死を恐れることと自由に生きることとのバランスを現実以上に問われる世界で、後者を重視するという態度は、死に自分から近づいていっているようにも見える。しかし、そこにもやはり、希望が宿るのだ。
本書を読み終えた時に心に浮かんできたのは、言葉の最良の意味での「若さ」だった。過去にこだわり甘やかに思い返したり、死という未来を極度に恐れるのではなく、今の自分から地続きで始まっていく未来に、素直な希望を抱くこと。ファッションで始まり建築で終わる(!)連作構成にも驚きがあり、納得感があった。若き作家はこれから多くの傑作をものすることになるだろうが、今後も「若さ」は一つの武器になるに違いない。
【あわせて読みたい】
『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』長谷敏司(ハヤカワ文庫JA)
2050年代の東京。27歳の気鋭のコンテンポラリーダンサー・