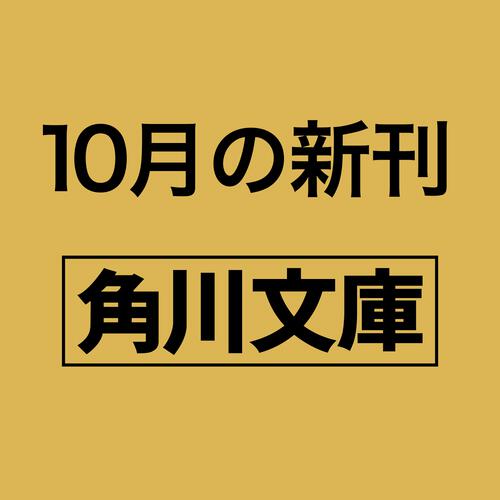文庫解説 恋の川、春の町 江戸戯作者事情より
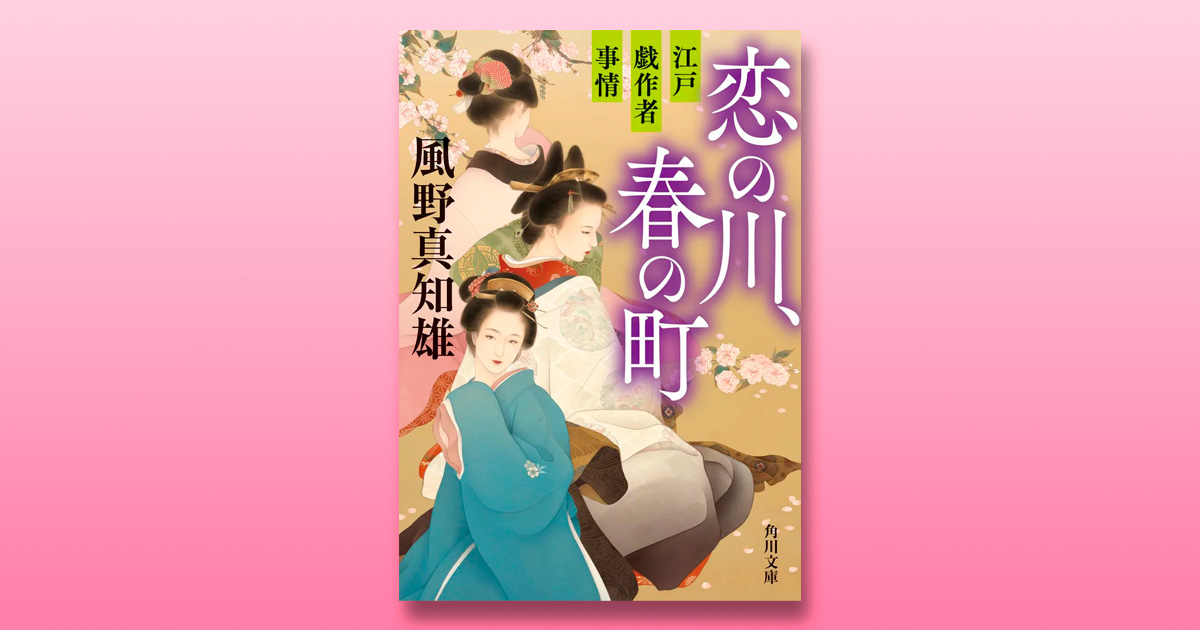
【解説】この作品はそのままに、風野真知雄という作家の心を写しているように思えた――『恋の川、春の町 江戸戯作者事情』風野真知雄【文庫巻末解説:永井紗耶子】
風野真知雄『恋の川、春の町 江戸戯作者事情』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!
風野真知雄『恋の川、春の町 江戸戯作者事情』文庫巻末解説
解説
虚しさもある終劇の後、本を閉じてしばらくしてから頭に浮かんだのは、春町が夢とも
やっぱり
以前、私が担当編集者と江戸時代について話をしていた時のこと。どんな作品が好きなのか、と問われて、
「風野真知雄さんの書く人物は、男も女も好きなんですよね」
と、答えた。
それが何故なのかが、この作品を読んでいて改めて分かった気がする。
私は江戸時代の作品を書く機会を頂くことが多い。しかし、元々、江戸時代が好きだったわけではない。昔ながらの時代小説の中には、「かっこいい武士」がよく出てくる。忠義のために刀を振るい、なよやかな女性から、「
最初に風野作品に会ったのは、「妻は、くノ一」である。「くノ一もの」というと、ちょっと色っぽい話なのかな……と、思いつつ、書店員さんの熱い応援ポップに
そして、ページを開いて読み始めて驚いた。
なんだろう、これ。ついつい引き込まれて読んでしまう。
数行読んで、先が気になった。何せ、文章のリズムがいい。さらりとしつつ、先へ先へと送られる。後々、風野さんが「ジャズが好き」というエピソードを読んだ時に、勝手に「だからか」と思ったことがある。スイングするように進んでいってしまうのだ。
やがて、くノ一、
これまで私が、はてな、と思った「時代小説」と何が違うんだろう……と、考えた。そして、気付いた。
「武士が、武士であることにちょっとだけ、斜に構えているからかもしれない」
江戸時代、身分制度の厳しい中、武士はその頂点に立っていた。武士であるということ、男であるということ、それこそが特権である。しかしそれは、自らの手で獲得してきたものではなく、生まれ落ちた家、性別だけで得られたものだ。それを
そして、『恋の川、春の町 江戸戯作者事情』の主人公である恋川春町、本名、
江戸時代も百年以上が過ぎ、戦乱は遠く、天下泰平の世である。老中
しかし、田沼の次に老中の座に就いた
定信が力を入れた一つが、倹約令。定信は物価高騰の原因が
そしてもう一つが文武奨励。作中でもしばしば取り上げられていたが、学問と武芸を奨励するという動きである。町中には突如として道場が出来たり、学問所が出来たりと、お上の顔色を
その様を見た戯作者たちは、付け焼き刃で文武に励む武士たちを
華やかな時代を
「そうだそうだ、笑ってやろう」
戯作によって笑われるお上の姿に、すっきりした人々は、武士も町人も、黄表紙に大いに沸いた。次から次へと刷られて売られていく。
やがてその存在は、定信も十分に知るところとなり、役人たちは定信の顔色を窺いながら動き始める。そして、書き手たちはじわりじわりとお上の圧を感じ始めていく。
今作のラストは、寛政元年の七月である。
その翌年、寛政二年五月の町触れには、こう書かれている。
「近年、子供持遊ひ草紙絵本等、古代之事によそへ、不束成儀作出候類相見候、以来無用に可致候」
つまり、子供のための草紙や絵本などに、昔のことのようなふりで不謹慎なことが書いてあるものがあるが、今後は無用、というのである。お上がこんな町触れを出したとあれば、これまで笑いながら手にしていた黄表紙が、途端に「禁書」になってしまう。そして、恋川春町らの黄表紙は絶版となっていく。
更に翌年の寛政三年には、黄表紙の版元であった
「言論の自由」などというものは、概念すらない時代。
お上がここまで本気で処罰に乗り出せば、書き手たちは縮み上がるしかなかったのは想像に難くない。
今作では、その言論統制のはじまりが描かれている。じわじわと掛かる圧力を感じた戯作者たちは、一人、また一人と、出版から手を引いていく。恋川春町は、去っていく同胞を口惜しく見て、「それでも引かない」と思い定めつつも、権力の持つ怖さも知っている。
物語のはじめのうちは、どこか
だが、定信と共に、江戸の著作に関わる者たちにとって、冒しがたい名がある。それが「
馬場文耕は、このときから三十年ほど前に、お上を批判する異説を記し、言い触らした罪で獄門に処された講釈師である。
だが、馬場文耕を軽 蔑 する戯作者はいないはずである。お上の圧力にまるで屈しなかった。その反骨の姿勢は驚嘆するほどである。
春町の中に宿る馬場文耕への密かな
しかし遂に、恋川春町に松平定信からの呼び出しの声がかかる。春町はこの呼び出しに参じることに
──権力はなんと重いのか。
と春町は思った。誰もそれとは戦えないのか。
いや、違う。戯作者は戦える。言葉という武器を駆使して、あの手この手でからかい、嘲笑い、あいつらの下 種 な心根や、頭の悪さ、おのれを守ろうとするいじましさ、そういった諸 々 を、あぶり出すことができるのだ。
自問自答の末に、戯作者としての気概を見せる春町。しかし同時に、定信に対する
読み進めていくうちに、春町の視界がぐにゃりと
そして、春町は「戯作者として死のう」と決めるのだ。
実際の恋川春町の最期については、史実の上では分かっていないとされる。病死であったと記されるが、自害であったとする説もある。
最期、夢とも現ともしれない春町は言う。
還ったらなにをしよう。もちろんまた書いてやる。やっぱり戯作から離れられない。
この作品はそのままに、風野真知雄という作家の心を写しているように思えた。ファンの一人として、その言葉が
作品紹介
書 名: 恋の川、春の町 江戸戯作者事情
著 者: 風野真知雄
発売日:2024年10月25日
筆一本で幕府と対峙した男がいた
駿河小島藩に仕える倉橋寿平には、もう一つの顔がある。「恋川春町」の名前で滑稽本を執筆する江戸で人気の戯作者だったのだ。浮世を楽しむため、さまざまな女性のもとを渡り歩く春町のもとに、突如として幕府の大物・松平定信から呼び出しの文が届く。倹約を旨とする幕府の方針に、春町の著作はそぐわないと判断されたのだ――。戯作者の矜持を胸に、命がけの洒落で権力に挑んだ粋人の生涯を描く軽妙洒脱な時代小説。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000637/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら