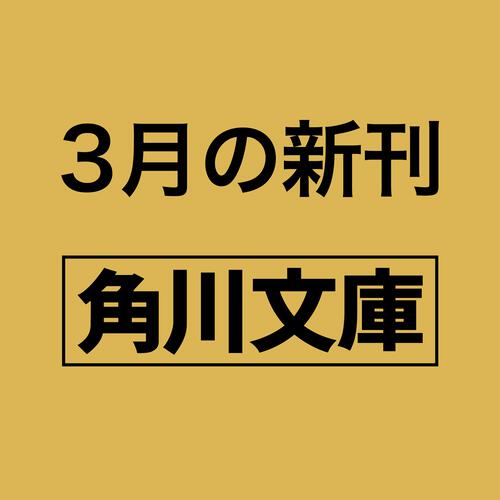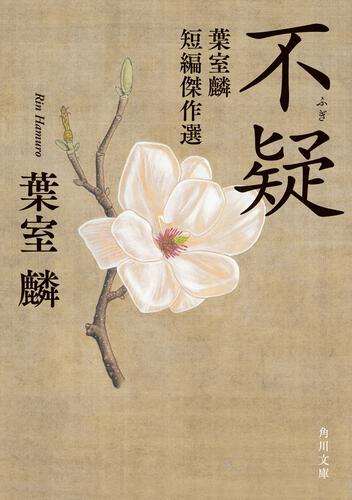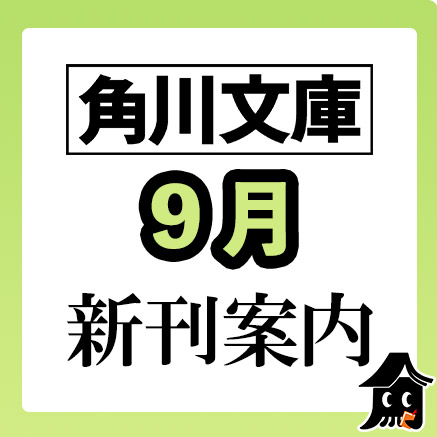葉室 麟『緋の天空』(角川文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!
葉室 麟『緋の天空』文庫巻末解説
解説
澤田 瞳子
現在の奈良市北部、奈良時代の古には平城京の北辺近くに相当していた場所に、法華寺という尼寺がある。藤原不比等の旧邸を娘である聖武天皇の皇后・藤原光明子が宮として用いていたものが、のちに寺に改められ、全国諸国の尼寺の束ねたる総国分尼寺の性格を有するに至った古刹である。
同寺の本尊たる国宝・十一面観音菩薩立像は、光明子の姿を写したものと伝えられており、肉感的な体軀と目鼻立ちのくっきりした顔立ちが印象的な御像。軽く踏み出した片脚の親指がわずかに反っていることから、今にも実際に歩き出しそうな躍動感すら放っている。
十一面観音は人々のあらゆる憂いと悩み、病苦障害や悪心を除くことを誓願した菩薩とされている。本作『緋の天空』において、葉室麟はしばしば主人公たる光明子を十一面観音に重ね合わせているが、それが法華寺の十一面観音像をイメージしてのことであるのはまず間違いあるまい。
幅広い時代・ジャンルの歴史時代小説を手掛けた葉室麟にとって、本作は唯一の奈良時代を舞台とした歴史小説。ただ葉室はこの物語において、主人公たる光明子を聖武天皇の皇后としてだけではなく、奈良時代、ひいては日本史全体を語る上で欠かせぬ女性として描いている。その点において、この物語は常に現代社会への問題意識を忘れず、歴史を通じて社会をそして人間を知ろうとした筆者の関心が強く打ち出された作品と言えるだろう。
歴史学的に説明すれば、藤原光明子は藤原不比等の娘。異母姉・藤原宮子が産んだ聖武天皇と結ばれて、のちに女帝・孝謙天皇(重祚して称徳天皇)となる阿倍皇女を産み、藤原氏初の皇后に立后される。厚く仏教に帰依し、盧舎那仏で知られる東大寺を創建した聖武天皇を支えた賢妻、悲田院・施薬院などの施設を作って人々を救済しようとした慈悲の人と捉えられることもある。
ただ本作の光明子はこういった歴史上の事跡を踏まえつつも、既存の人物像に甘んじはしない。もともと安宿媛と呼ばれていた彼女は、すべての闇を払い、自らが光たる存在になってほしいとの父・不比等の思いのもと、光明子との名を与えられる。それは藤原氏の繁栄を願ってのことではなく、法律によって治められるべき国家を見据えての計らいであった。
そんな光明子は、女帝としての即位を求められた氷高皇女(元正天皇)を間近にし、「帝のように生きたい」との望みを抱く。とはいえこれは断じて、権力者になりたいという野望の表れではない。気高く、困難にも怖じぬ生き方をする氷高を慕っての感慨。一方で氷高は父・不比等を失って悲嘆にくれる光明子を、藤原氏と天皇家の紐帯のあかしとも呼ぶべき黒作懸佩刀を持たせて勇気づける。かくして光明子は女性ではあるが、いや、女性だからこそ聖武天皇を守り、不比等の思いを受け継がねばと自らに誓うが、この思いは臣下たる藤原氏の出でありながら、国を平けく治めんとする過去の天皇たちと変わるものではない。光明子を聖武天皇とともに国家仏教を進めた夫唱婦随の女性ではなく、自ら国の安寧に関わろうとする強靱なる女性と描いた点こそ、本作の眼目と言えるだろう。
とはいえこの光明子像は決して、物語を面白くするためだけに葉室が設定したものではない。彼は本作の二年後に刊行された歴史対談集『日本人の肖像』において、奈良時代を「女帝の世紀」と位置付けている。女帝はただの中継ぎの天皇ではなく、「革命の起きない国」として日本を作り上げるために必要な政治的存在だったと考え、光明子を「それまでの女帝の流れを受け政治力を発揮」した女帝政治の後継者だと述べている。
実際、光明子が産んだ娘は、女性でありながら初めて皇太子となり、日本史上初の正統なる女帝として皇位を踏む。言うなれば臣下たる藤原氏の女性である光明子がいればこそ、「持統の帝から元明、元正と引き継がれてきた女帝の政」は無事に次なる女帝に引き継ぎ得たのだ。
ところで葉室は「女帝の世紀」について語る中で、
──歴史の転換点で妻が大きな役割を果たすのは、日本人の特徴的な資質、個性を表しているようにも思えますね。
と述べ、鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻・北条政子にも言及している。政子が生きた鎌倉時代には鎌倉にも大仏が造られており、奈良と鎌倉、二つの大仏には女性が政治の先頭に立った時代精神が象徴されているようだとの感慨も漏らしている。
葉室にはそんな北条政子を主人公とする短編「女人入眼」(『不疑 葉室麟短編傑作選』角川文庫集録)があるが、政子はこの物語では都に振り回される頼朝を冷ややかに眺め、夫亡き後は鎌倉を守るために奔走する苛烈な女性として描かれている。孫娘に当たる竹御所鞠子とともに源家を守るべく手をたずさえ、承久の乱の勝利を導く政子像は、『緋の天空』において国を守る志を共有する氷高皇女と光明子の姿とも重なり合う。
代表作『蜩ノ記』のヒロイン・戸田薫、『津軽双花』に描かれた徳川家康の姪・満天姫と石田三成の娘・辰姫、『蝶のゆくへ』の主人公・相馬黒光と彼女が出会う明治期の女性たちなど、その作品に意志的な女性が多く登場することは、葉室麟ファンにとってはもはや周知の事実だろう。ただ日本の政治体制の礎に深く関わる存在として描かれている点において、本作の光明子は他のヒロインたちとは大きく性質を異にする。日本の歴史をひもとくことで、現代社会と日本人そのものを解き明かそうとした葉室麟の問題意識が濃厚に投影されたのが、この『緋の天空』なのである。
ところで本作は二〇一二年十月に第一章「緑陰の章」に該当する部分がまず短編小説として雑誌掲載され、その一年半後に第二章以下がまったく別個の長編小説として連載スタートするという、珍しい形式で発表されている。
二〇一二年といえば年頭から民主党・野田佳彦内閣のもと、皇室典範の改正が検討され、いわゆる女性宮家の創設の審議が始まり、女性天皇・女系天皇のありかたについても議論が噴出した年である。その後、同年末に行われた総選挙で民主党政権が大敗したこともあり、結局、この改正案は先送りされたまま今日に至っている。ただいずれにしても女性皇族に関してさまざまな検討が行われた最中に、『緋の天空』が起筆されたことは、葉室麟の社会に向ける鋭い目を思えば、決して偶然ではないだろう。
──日本の成り立ちを振り返ると、男と女が協力しあい、うまくやる知恵を古代の人はもっていたと考えればいい。(『日本人の肖像』)
葉室麟はかつてを知ることで現代を、未来を知ることが出来ると堅く信じた。彼が残した作品から、我々はいま、なにを学び得るだろうか。本書を通じて、改めて考えねばならない。
作品紹介
書 名: 緋の天空
著 者:葉室 麟
発売日:2025年09月22日
古代日本の安寧は、ひとりの皇后に託された――
朝廷第一の実力者・藤原不比等の娘として生まれた安宿媛は、平城京を走りまわるお転婆な女の子だった。汝は、この世を照らす光明となれ――。長じて「光明子」の名を与えられると、この世を鎮め、平穏をもたらす決意をする。だが立太子の式が行われる日、皇子の寝所から呪詛のための蠱毒の壺が見つかり、平城宮は大混乱に陥る。そこには、権勢を求める貴族たちの陰謀が隠されていた。日本の黎明を描く、葉室麟渾身の歴史長編。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000592/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら