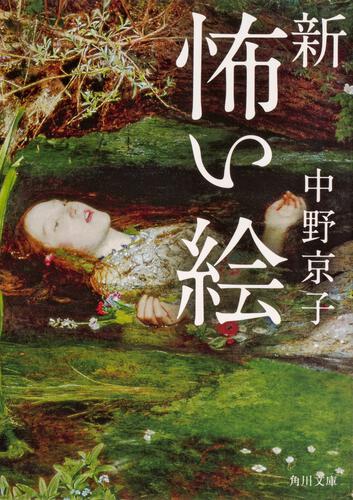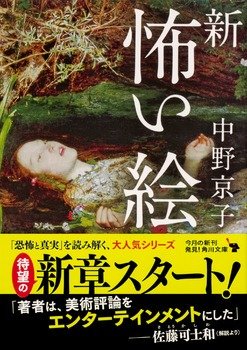名画の新しい楽しみ方を提案する中野京子さんの『怖い絵』シリーズから、選りすぐりの作品を特別試し読み! 平民出身でありながら王の絶大な信頼を受けたスペイン宮廷画家ベラスケスを紹介。
ベラスケス 『フェリペ・プロスペロ王子』
老人の顔の中に、ふと子どもがよぎる瞬間がある。その人の遠い過去の名残りなのか、それとも歳月を超えて生き延びた無垢が、何かのはずみで皺の奥から輝き出るのか。
逆に、子どもの顔の中に浮かびあがる老人もいる。不思議なほど達観した顔つきの子どもは、遠い未来を先取りしているのか、あるいは初めから老成した魂を持って生まれてきたのか、それとも……。
「童顔」と「枯れた表情」の取り合わせが極みに極まれば、岸田劉生『麗子像』(一九二一)のように、とてつもなく無気味に感じられる場合がある。
劉生は娘の麗子をいとおしみ、可愛い可愛いと、一筆一筆、丹念に執拗に色を塗り重ねていった結果、ついには麗子と一体化し、可愛がられる幼女の表情と可愛がる己の表情が絵の具を混ぜるように混じりあい、とうてい子どもの顔つきとも思えぬ顔が現出してしまった。
ベラスケス描く本作の幼児も──麗子が強烈に発している存在感とは少し違うが──、やはり子どもらしさを超越した独特の雰囲気を醸し、見る者に曰く言いがたい思いを抱かせる。
贅沢に金糸を織り込んだ薔薇色の少女服のこの子は、男児である。男児は女児より生存率が低かったから、邪気払いのためか、洋の東西を問わず二十世紀初頭に至るまで、幼年期の男の子の多くが女児服を着せられていた。ルイ十五世しかり、昭和天皇しかり。王侯貴族だけではない。十八世紀のホガース『グラハム家の子どもたち』(『怖い絵』参照)や、十六、十七世紀のオランダ絵画を見れば、階級に関係なく同じ風習にならっていたことがわかる。
この男児は王族だ。それもスペイン・ハプスブルク家──傾きかけているとはいえ、未だ強大国の──君主フェリペ四世の息子にして、王位継承筆頭者フェリペ・プロスペロ、二歳。
王子はしかし見るだに生命力乏しく、巣から落ちた丸裸のヒナみたいに頼りない。少女服のせいもあって性差定かでなく、表情だけだと年齢も曖昧で、さらに言えば、この世にいるやらあの世の者やらもはっきりしない。頰はさすがに幼くふっくらしているものの、血の気は薄く、健康な赤みはわずかだ。頭蓋にはりつくブロンドの髪の毛、大きな耳、蠟のように白い手。誰の目にも明々だが、この子は現世に、ほんの束の間立ち寄っただけ。
──名画とは、ある種の痛みを見る者に与えるのかもしれない。この作品をベラスケス肖像画中、屈指の一枚に数える美術史家もいるのは、そうした痛みが悲劇的といっていいほどに画面を覆っているからだろう。
フェリペ・プロスペロ王子はどこか遠くを見ている。椅子の上の、目ばかり大きな小型犬パピヨンが、まっすぐ無邪気にこちらを見つめてくるのと異なり、眼差しには、周囲への子どもらしい好奇心が全くうかがえない(心は早や、別の次元へ向かってでもいるように)。
ここにはまぎれもない美があるが、それは顔立ちからくるのではなく、静かな表情からきている。穏やかさや悟りというのとも微妙に違う、しんとした静けさ。ただもう静かなたたずまい。こんなたたずまいを、ふつう、幼児はしない。
わざわざ緋色のカーテンを開けて闇を招じ入れたかのごとき黒すぎる背景に、王子は今にもすうっと溶け込み、消えてゆきそうだ。重厚な家具や分厚い絨毯、薄手のエプロンや袖の折り返しにふんだんに使われたレースなどのリアルな実在感に比べ、か細いこの肉体はなんと抽象的で透明だろう。
血族結婚くり返しの弊害により、フェリペ四世の子どもたちは次々早世し、この時点で男児はフェリペ・プロスペロひとりしか残っていなかった。やはり生まれたときから病弱で、幾度も発作を起こしては死に瀕したので、そのたび宮廷中が一喜一憂した。跡継ぎがいなくなるのは、ヨーロッパの勢力地図を塗りかえるほどの大事であるから、なんとしても王子を生き延びさせねばと、国内外から名医が招聘された。医者ばかりではない、祈禱師やら占い師たちもおおぜい集められた。王子のウエストの赤い紐に、悪霊祓いの鈴や伝染病除けのハーブ入れなどがぶら下がっているのは、そういうわけなのだ。
ベラスケスは、フェリペ・プロスペロが決して年を取ることはないと感じていたのだろう。幼児の生き生きした愛くるしさを巧みに捉えることで知られた彼だが、この王子の肖像に限っては、命の輝きの代わりに死への親和性をほのめかしている。劉生が麗子と同化したように、ベラスケスも無意識のうちに王子に我が身を重ねたのかもしれない。これがほとんど最後の画業になると、予感していたがために……。
実際ベラスケスは翌年、過労が祟って六十一歳で死去。王子の死はさらにその一年後、四歳だった。子どもというものは──たとえどれほど小さな子であっても──、死が間近にきたことを感知すると言われる。王子もそうだったのではないか。少なくとも絵からはそう見える。描くほうも描かれるほうも、迫りくる漆黒の闇を背に負っていた。死を従容と受け入れようとするその静けさは、王子のものであると同時にベラスケスのものでもあったろう。
フェリペ・プロスペロの生まれ変わりのように、死の同年、奇蹟的に弟が誕生した。これが後のカルロス二世で、スペイン・ハプスブルク家は彼の代をもって断絶するわけだが、それについては『怖い絵 泣く女篇』でさんざん書いた。
今回は別の怖さ。
透かし細工のように脆くいたいけなフェリペ・プロスペロ王子は、先述のごとく女児服を着ている。女児服というのは即ち子ども服の一種だと、現代の我々は思う。ところが当時の子ども服は今と違い、大人服を単に小さく仕立てただけのものだった(あとは汚れないようにエプロンをする程度)。子どもには子どもにふさわしい、着用して楽な服がいいとの考え方は、十八世紀後半、ルソーの画期的教育論によって初めて出てくる。しかもルソー派改革者たちの奮闘にもかかわらず、実用的な子ども服が広く用いられるようになるのは、なんと二十世紀に入ってからだった。
いわゆる「子どもの発見」に至るまでの、長い長い間、子どもたちは「大人のできそこない」で動物に近いとの認識のもと、時代の流行に無理やり従わされ、ある時はハイヒールを履かされ、ある時はスズメバチさながらにウエストを絞られた。十六世紀から十七世紀のスペインでは、甲冑なみのコルセットだ。胸は薄ければ薄いほど美しいとされていたため、時に乳腺が萎縮するまで乳房の成長が抑えられた(『ラス・メニーナス』でマルガリータ王女が着ているのがこれである)。
大人の女性が自らの愚かしさゆえに選択したファッションに対しては、何も言うまい。けれどその馬鹿げた流行が、縮尺されて幼児にまで及んでいたのだから問題だ。フェリペ・プロスペロ王子も、ファージンゲイル(スカートを拡げるためのワイヤー入りの輪)こそしていないが、硬いコルセットはしっかり装着させられている。胸をきつく締めつけるこの拷問具は、子どもらしい活発な動きを制限したばかりでなく、十分な呼吸を不可能にし、内臓の健やかな発育まで阻害した。
世継ぎの王子の健康を祈って魔除けのお守りをたくさんスカートにぶら下げるくらいなら、なぜ肝心の衣服自体にもっと注意を向けなかったのだろう。王子はしょっちゅう発作で倒れていたというが、そのうちの何度かは、鞘のような不自由な衣装のせいだったのではないか。現代人ならそう周囲を咎めたくなるが、「子どもは未熟な大人」と見なされている限り受難は続くのだった。
実のところ、幼児になる前の段階はもっとひどい。コルセットよりさらに息苦しい拘束具の中に、赤ん坊は閉じ込められた。さまざまな絵画に描かれているので気づいた人は多いと思うが、例としてラ・トゥールの『聖母子像』を見てみよう。マリアに抱かれたイエスは、まるでミイラのようなぐるぐる巻きである。
これはスワドリング(swaddling)といって、赤子の両手両足をまっすぐ伸ばし、身動きできないよう幅広の長い布できつく巻いたもの。おむつも兼ねた。古代エジプト以来、十九世紀に至るまで、世界中のあらゆる地域あらゆる階層に見られた習俗で、ペルーや東南アジアの一部などでは今も行なわれているというし、日本の「おくるみ」もスワドリングの遠い親戚といっていい。まだ首のすわっていない新生児を抱くには都合がいいし、生後三カ月頃までの夜泣きする子には、母親の胎内と似た環境を作るという意味で、この布巻きが有効な場合もあるのだという。
しかしそれ以降は?
自然な動きを封じられるのだから、とうぜん赤ん坊には不快きわまりないだろう。だというのに、蓑虫状態にしておけば我慢強くなるし、ぐにゃぐにゃの体がまっすぐになり、大人から病気をうつされにくいし、魔物に変身することもない(!?)と、いくつも効能があげられ、新生児の時期を過ぎてなおスワドリングされ続ける子が多かった。
けっきょくのところこれは、世話する側に都合よい方法なのだ。泣いてもそのへんにころがしておけるし、堅いので壁の隅に立てかけて(?)おくこともできた。まだ衛生観念も発達していなかったから、排泄物もそのまま中に放置されたし、布自体の取り替えや洗濯もめったにしない。病気になりにくいどころか、汗、垢、排泄物のせいで感染症にもかかりやすかった。ルソーがこの育児法を激しく糾弾したのももっともである。
ただでさえ乳児死亡率の高い時代、無事に生まれても長すぎるスワドリング期間というハードルがあり、その後も体を締めつける衣服に苦しめられるなど、身分にかかわらず子どもはいくつもの受難に耐えねばならなかった。生来頑健でなければ、生き残りは難しかったのだ。
現代では幼児のサバイバルはかなり改善された。しかし受難という点ではどうだろう?
いっときアメリカの某医学博士が(自分では直接子育てもしていないのに)、甘やかしになるから赤子は泣いても決して抱くなと説き、日本の母親まで一斉にそれに従ったことがあった。目覚まし時計のように、どの子も同じ時刻に目を覚まし、同じ時刻に腹をすかせるのが正しい赤ん坊の道だと、集団で錯覚したのだから恐ろしい。ファッションにおいてもそうだ。コルセットこそしないまでも、着せ替え人形にされ、弱い皮膚に化粧され、やわらかな髪にパーマされ、染められ……。
ディエゴ・ベラスケス(一五九九~一六六〇)の晩年は、宮廷官吏としての仕事に忙殺され、絵筆を取る機会は激減していた。一六六〇年、フェリペ四世の娘マリア・テレサ(フェリペ・プロスペロ王子の腹違いの姉)とルイ十四世の結婚式において、城館の装飾責任者をまかされた彼は心身ともに重圧のもとにさらされた。結婚の儀を無事見届けたのが六月、病に倒れたのは七月、八月初めにはあっけなくこの世を去っている。
(中野京子『怖い絵 死と乙女篇』より)
ベラスケスの作品は、「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」でも見ることができます。同展で展示されるのは《マルタとマリアの家のキリスト》という作品です。
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展とは
ヨーロッパ絵画を網羅する質の高いコレクションで知られる「ロンドン・ナショナル・ギャラリー」が、200年の歴史で初めて開催する館外での大規模な所蔵作品展。ゴッホの《ひまわり》、フェルメール の《ヴァージナルの前に座る若い女性》、ゴヤの《ウェリントン公爵》など、今回は61作品、すべてが初来日という、開催前から注目を集めている美術展です。
https://artexhibition.jp/london2020/
会期:2020年6月18日(木)~10月18日(日)
※6月18日(木)~6月21日(日)は、「前売券・招待券限定入場期間」とし、前売券および招待券のをお持ちの方と無料鑑賞対象の方のみご入場いただけます。
会場:国立西洋美術館
開館時間:午前9時30分~午後5時30分 (金曜日、土曜日は午後9時まで) ※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜日、9月23日 ※ただし、7月13日、7月27日、8月10日、9月21日は開館
※日時指定制となります。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。
※国立西洋美術館では入場券の販売はございません。
中野京子が贈る名画の新しい楽しみ方 角川文庫「怖い絵」シリーズ
関連記事:注目の「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」を観るならこの2冊! 美術鑑賞がもっと楽しくなる文庫をご紹介