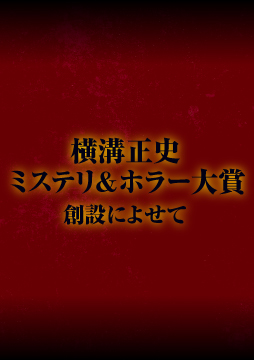消してしまいたい、どうしても忘れられない記憶を消してくれるという「記憶屋」。遼一は、都市伝説だと思っていたけれど――。
◆ ◆ ◆
Prologue
「記憶屋」という都市伝説を遼一が初めて聞いたのは、小学校にあがる前のことだ。
夕暮れ時、公園の緑色のベンチに座って待っていると、記憶屋が現れる。そして、消してしまいたい、どうしても忘れられない記憶を、消してくれる。
近所の老人たちの間では有名な話だった。
遼一の祖母なども、誰かがうっかり物忘れをすると、「記憶屋が出たかねえ」と言って笑ったものだ。
幼かった遼一は、それを物語として聞いた。三つ年下の幼なじみが怖がるのを、作り話だよ馬鹿だな、と笑ったこともある。
その時は、信じていなかった。
*
男と子どもが、向かい合って立っている。どちらも顔は見えない。
白い煙。黒い革靴。灰色の布。ひるがえる。遠くで何度かクラクションが鳴る。
伸ばされる腕を見る。
逃げろ。逃げろ。
誰に言っているのか、自分に言っているのか、わからないまま繰り返し、しかし足は凍ったように動かない。
そこでいつも夢は終わる。
ぴろりろりん、と間抜けな高い音が耳元で鳴ったのと、夢の終わりとがほぼ同時だった。一瞬で、遼一は目を覚ました。
もう夏も終わりだというのに、汗をかいている。久しぶりに見たその夢は、相変わらず意味不明だった。意味が分からないのに、何故かいつも、ひどく緊張して目が覚める。
頭を振って顔をあげると、オレンジ色のカバーをつけたスマートフォンが、目の前にあった。
取り上げようと手を伸ばしたが、スマートフォンはさっとそれを避けて、遼一の腕の届かない距離まで移動する。
「……マキ」
「遼ちゃんの寝顔撮っちゃったー」
「……最近の女子高生は。貸せ」
「やだ」
突っ伏して寝ていたせいで、背中や腕の付け根が軋む。机から身を起こして肩を回していると、後ろからMacのモニターを覗き込んだ真希が声をあげた。
「何これ、年表? うわーすごい、こんなのまで作ってるんだ」
寝起きの頭に、少女の高い声は響きすぎる。顔をしかめ、開きっぱなしだったファイルを閉じた。けちー、とぼやく真希を無視して、Macそのものもシャットダウンする。
消える寸前までモニターを見ていた真希は、色を抜いた髪の先をいじりながら口を尖らせた。
「1956……って書いてなかった今? 五十年も前からいるの記憶屋って?」
「噂が最初に流行ったのが五十年前ってだけだろ。都市伝説ってのはそういうもんなの」
立ち上がり、机の上に広げていたノートやメモの類をかき集める。まとめてクリアファイルにしまいこむと、真希が「秘密主義ー」と非難する口調で言った。
「その話、結構前から気にしてたよね? 遼ちゃんそういうのバカにしそうなのに、信じてるって超意外」
「別に信じてねえけど。俺は、噂って形で人から人へ伝達される情報、っていうコミュニケーションの形態に興味があんの」
噓だ。遼一は、記憶屋という都市伝説がでたらめだとは思っていない。しかし、この幼なじみの前で、それを口に出すのははばかられた。
「都市伝説ってのはつまり、出所がわからない噂なんだよ。友達の友達が実際に体験した、とかいう触れ込みで広がるけど、実際にはその『友達の友達』には絶対辿りつけない。だから確かめようもない。口裂け女とか人面犬とか、皆そうだろ」
「あー、うん」
「そういういかにも作り話っぽい噂が、何で広まるのかとか、広まる過程で、どう変化していくかとか。そういうのを調べてるだけ。大学の課題なんだから、邪魔すんなよ」
「はーい……あ、じゃあさークラスの子に聞いてみてあげようか? ほら、女子高生ってそういうの好きだし結構情報集まるかも」
「俺の課題気にしてる場合か。おまえ中間もうすぐなんじゃねえの?」
「あ、忘れてた。数学教えてもらおうと思って来たの!」
「俺は忙しいの」
「寝てたくせに」
遼一は、実際に記憶屋に記憶を消されたと思われる人間を、三人知っている。
そのうちの一人がこの、三つ年下の幼なじみ。河合真希だ。だからこそ、この件に彼女を関わらせるつもりはない。
遼一は随分と長い間、真希の記憶が欠落していることと、記憶屋の存在とを結びつけなかった。二つを結びつけて考えるようになったのは、一年前。「二人目」を知った後だ。
そして、遼一が、都市伝説にすぎないと思っていた記憶屋の存在を確信したのは、「三人目」の存在に気づいてからだった。
1st. Episode:ノーティス
大学に入学してすぐ、初めて参加した飲み会で、遼一は一学年先輩の澤田杏子と知り合った。
遼一が彼女の鞄に足をひっかけて、倒してしまったのがきっかけだった。
「あっ、すみません」
「ううん、こっちこそ通り道に荷物置いててごめん」
畳の上に膝をつき、鞄から飛び出した本を拾って手渡す。「催眠療法と脳科学」という、硬いタイトルが目に入った。
「心理学専攻ですか?」
「うん、ちょっと興味があって」
パステルカラーの布の鞄に、分厚いハードカバーの専門書。ギャップに、おっ、となった。顔が好みだったということもある。
そのまま、隣りに座って話をした。乾杯の前、全員で自己紹介をしたときに、彼氏がいないことは確認済だ。
話しているうちに、同じプロ野球チームのファンだということがわかって、さらに盛り上がった。
(あ、何か、いいかも)
話していて疲れない。
スポーツ観戦や好きな映画、いろいろと趣味が合って、純粋に楽しかった。
飲み会で可愛い先輩と出会って仲良くなる、なんて、思い描いていた大学生ライフそのものだ。
誘われて断りきれず参加したものの、先輩ばかりの飲み会など気を遣いそうで憂鬱だと思っていたのだが、来てよかった。誘ってくれた友人に、感謝の目配せを送る。
しかし、
「あ、ごめん。あたし帰らないと」
ちらちらと時計を気にしている様子だった彼女は、飲み会が始まってから一時間ちょっとで席を立った。
「ちょっと顔出しに来ただけなんだ。ごめん」
えー、とあがった声に、すまなそうに片手を立てて「ごめんねポーズ」を作る。
じゃああとちょっとだけ、と言ってくれることを期待したのだが、彼女は友人らしい女の子に千円札を渡すと、本当にそのまま帰ってしまった。
遼一は半ば呆然としながらそれを見送る。
おいおい門限があるにしても早すぎないか? まだ八時過ぎだぞ八時。
口には出さなかったが、顔にはしっかり出ていたらしい。
「別に吉森君が嫌われたわけじゃないよ。杏子はいつもそうなの」
他の先輩たちが教えてくれた。
「そもそも飲み会に参加することがあんまりないけど、参加してもすぐ帰っちゃうのよ。今日は長くいた方」
もう少し話したかったと思っているのを見抜かれたのか、残念だったねと慰められる。
別に、と笑って返したが、本当はちょっと残念だった。メールアドレスくらい交換しておけばよかった、と後悔する。
その後も何度か飲み会はあったが、杏子は来なかった。
飲み会には来なくても学部が同じなので、当然、構内で杏子を見かけることはある。
選択授業で一緒になって何度か話をして、三回目に、学食でのランチに誘ってみたら、意外にもあっさりとOKしてくれた。
その前に図書館に寄りたいというので、遼一もつきあって、彼女が「心理療法の基礎」という分厚い本を借り出す手続きを終えるのを待つ。
「難しそうですね」
「結構おもしろいよ。吉森は? どんな講義とってる?」
「えーと、コミュニケーション概論とか……噂の伝達過程とか、都市伝説の伝播についてとか、先生が話してくれて、おもしろかったっすね」
「何それ、あ、あれだ、口裂け女とか? 怖い話だ。私そういうの結構好き」
「ネットにまとめサイトとかもあって、色んな話がありましたよ」
「へー、見てみようかな」
初対面で抱いたイメージの通り、杏子は人当たりもノリも決して悪くない、むしろ、活発で社交的な性格のように思えた。少なくとも、人見知りをするタイプではない。飲み会にあまり参加しないのは、人づきあいが苦手だからというわけではなさそうだった。
学食の窓際の席で、それぞれAランチと肉うどんのトレイをテーブルの上に置き、向かいあって座る。
「澤田先輩の家って、門限とか厳しいんですか?」
「え?」
「いや、飲みとかカラオケとか、遅くまでいたことないって聞いたんで」
杏子自身が、皆で集まることを嫌っているのでなければ、家が厳しいという理由くらいしか思いつかない。
遼一が言うと、杏子は「そういうわけじゃないんだけど」と苦笑して口ごもった。
「あ、何か言いにくいこととかだったら、別に……」
「そんな大したことじゃないよ。逆に、わざわざ言うほどの理由がないっていうか……その、」
視線が泳ぐ。そうして、迷うように少しの間沈黙した後で、杏子は小声で言った。
「夜道が怖くて」
意外な答えに、割り箸を割ろうとしていた遼一は動きを止める。
杏子はその反応を見るなり声をワントーンあげた。
「自意識過剰だよね! わかってるんだけどさ」
「いや……別に、そんなことは……女の子は大体皆そうなんじゃないんですか? 変な事件とかも多いし」
「うん、……そう、なんだけど」
それでも、八時になったら即帰宅、という徹底ぶりは珍しい気がする。そう思いはしたが、口には出せなかった。何やら理由がありそうだということはわかった。
遼一が割り箸を割ると、杏子もフォークをとって食べ始める。しばらくの間、二人で黙って食事をした。
自分の丼の中の肉うどんが減っていくのを他人事のように眺めながら、思う。
(これ、食べ終わったら、「じゃあね」って流れだ)
このままでは、気まずいまま別れることになってしまう。答えにくい質問をして、彼女に居心地の悪い思いをさせて。せっかく、誘いに応じてくれたのに。
それに気づいて、それではだめだと気づいて、箸を止める。
「八時までなら、大丈夫なんですよね」
丼から顔をあげて言った。気が付いたら、口から出ていた。
その勢いに、杏子も驚いた様子でこちらを見る。
「こないだの飲み会で話してた映画。スペイン映画のハリウッドリメイク版、先輩観たいって言ってたでしょう」
前置きもなく、一方的にまくしたてる。
早口になっているのに気づいて、いったん口を閉じ、唾をのみこんだ。
「よ、……よかったら、この後観に行きませんか?」
杏子の目が、開いたまま固まる。
五秒ほど、見つめ合う形になった。それから、ゆっくり、杏子の睫毛が上下する。
杏子はフォークを皿の上に置いた。
「……ごめん、今日は用事があって」
「じゃあ、来週とか。俺、月曜は午後から講義なくて」
「月曜はダメなんだ。ごめんね」
重ねての謝絶。申し訳なさそうに、眉が下がる。
その顔を見て、ようやく力が抜けた。
「そう……ですか。すみません、いきなり」
我に返れば恥ずかしい。
何度か話したことがある、という程度の相手に対して、一気に距離を詰めようとして、空回った。もう少しスマートにできたはずだ。
そこまで深く考えていなかったが、今の自分は、どう見ても、勢い込んでデートに誘って、玉砕した男だった。これでは、さらに気まずくさせただけだ。
さすがに、これだけ断られれば、脈なしと諦めるべきところだ。
しかし、遼一が肩を落とす前に、杏子が言った。
「でも、ありがと。誘ってくれたのは嬉しいよ」
そして、少し困ったように、照れくさそうに、でも嬉しそうに、笑った。
笑った顔が、可愛かった。
たった今誘いを断られたばかりなのに、萎みかけた心がまた浮き上がる。
(そういうこと言われたら、期待するんだけど)
自分は、惚れっぽいタイプではないはずだ。
顔やスタイルが好みでも、趣味が合っても、それだけでは足りない。まだ、好きになるほど彼女を知らない。
今は、知りたいと思い始めていた。
▼織守きょうや『記憶屋』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321506000128/
関連記事
- 「辛い記憶も含めて自分の人生だから」 山田涼介インタビュー! 映画「記憶屋 あなたを忘れない」公開記念
- 人の記憶を消せる『記憶屋』っていう人がいるらしい――。怪人? 都市伝説? その謎に迫る! (『記憶屋』映画化記念特集)
- 【キャラホラ通信11月号】『記憶屋0』刊行記念 織守きょうやインタビュー「原作者から見た映画『記憶屋』」