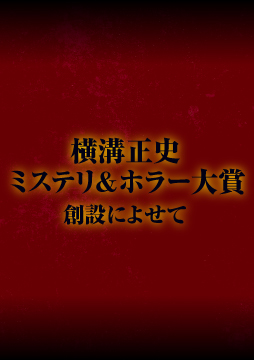【カドブンレビュー×カドフェス2017】
忘れてしまいたい辛い出来事や、悲しい記憶。自分ではどうしようもない、いっそ忘れてしまえたら、という苦しい想い。そんな記憶を消してくれるという「記憶屋」。
都市伝説として伝えられるその存在が、もしかしたら実在するのでは……。
子供のころに記憶の一部を失ったことのある幼馴染の真希。自分のことを忘れてしまった想い人の杏子。そして「記憶屋」に記憶を奪われたと思われる三人目の存在に気付いたとき、この物語の主人公である大学生、遼一は真実を知るために「記憶屋」を探し始める。
「記憶屋」に関わる3つのエピソードを通じて、その正体に迫る遼一。
トラウマを乗り越え、大切な人と向き合うために。
自分がいなくなった後、残されたものを守るために。
そして大好きな人を思いやり、いつまでも一緒にいるために。
「記憶屋」に記憶を消してもらおうと依頼をする理由はさまざまだが、どれも切なく胸が締め付けられる。これらのエピソードを通じて、遼一はたとえ辛い出来事でも、記憶を消してしまうことが本当に正しいことなのか、それしか方法はないのかと思い悩む。どんなに辛くても、悲しくてもそれはその人の一部であり、その人を形作っている歴史だ。欠けていいはずがない。揺らぎながらもそう信じ続ける遼一の前に、おぼろげながら輪郭をあらわしはじめた「記憶屋」は、人の記憶を喰らう悪魔なのか、それとも負の記憶に搦め取られた者に救いの手を差し伸べる神なのか。
遼一を通して読者に投げかけられるのは、「記憶を消すこと」の是非。
登場人物の一人が語るように、強姦事件の被害者を例に挙げ、ケースバイケースだと言われればその通りだと思う。また、忘れてしまう人よりも忘れられてしまった人の計り知れない喪失感を訴えられれば首肯するしかない。「時間が全てを癒してくれる。自然にまかせればいい」というのは所詮幸せな人間の綺麗事ではないのか。読者に委ねられたその問いに正解などないのかもしれない。
物語のラスト、「記憶屋」の正体にたどり着いた遼一の前に驚愕の真実が姿を現す。
押し寄せる疑念の数々。「まさか」と思いながらも、その想像は確信へと変化していく。
これまで腑に落ちなかった点が次々に解き明かされていくと同時に、切なさと恐怖が入り交じったえも言われぬ感情に支配される。
そして物語は幕を閉じる。
文字通り幕を閉じるのだ。
おそらくは何度でも。
最後の最後でその本性が露わとなり、それまでの切なさを恐怖が覆いつくす。
この物語は間違いなくホラーだ。